ファンの炭治郎×アーティストの善逸の現パロです。
炭治郎が善逸を推して生きてます。
約15000字/現パロ
終わった。俺の生きる糧がなくなってしまった。
俺はもうお終いだ・・・・・・。
俺は絶望に打ちひしがれながら、ふらふらとバイト帰りの夜道を歩いていた。向かう先は誰も待つ人のいない6畳一間のアパートだ。片手には遅い夕飯の材料がぶら下がっているが、これを使って料理をする気力は湧かない。なぜなら俺は人生で最大の生き甲斐を失ってしまったところだからだ。6人兄弟の長男だって生き甲斐を失ったら凹むんだ。この先どうやって生きていけばいいんだという気持ちにもなるんだよ。
俺は街頭の前で立ち止まると、もう一度だけと思いスマホを開く。そしてブックマークの一番上にあるアイコンをタップして、この6年間毎日欠かさず5回は読んでいるブログを開いた。
そしてその最新記事、それも今日の夕方にアップされた記事だ。それを開くと滲む視界で文字を読んだ。
活動休止のお知らせ。
ブログの記事タイトルにそう書かれている。
中身は形式張った文章で、活動休止を無期限ですること。
応援に今でもとても感謝していることが綴られていて、なぜ活動休止なのかも、今後いつか活動が再開されるのかも分からない。
「うううっ・・・・・・ゼンイツ・・・・・!!」
俺はとうとう悲しくて涙が出た。
『ゼンイツ』がメジャーデビューする前から応援して6年。
こんな日が来るなんて想像もしなかった。
『ゼンイツ』の曲に出会ったのは、俺の父さんが亡くなってすぐの頃だった。父と母のパン屋の新規オープンを控えた最中に父は病で亡くなった。若かった分、進行が早くて気がついた時には末期だったのだ。てんやわんやで碌に父さんと満足のいく別れもできなかった。
そのまま俺は高校へとすぐに進み、家のパン屋を支えながら父さんの死のことをなんとか忘れようと足掻いていた。なぜなら思い出せば、考えれば弟妹たちや母を心配させてしまうと分かっていたからだ。
寂しい、悲しいと泣けば下の子たちも悲しくなる。みんな泣いたら母の負担がとんでもなくなる。俺は泣けない。だから、父さんのことはなるたけ思い出さないように努めて忙しく過ごしていた。
そんな時、上級生との交流をはかるオリエンテーションで同じグループで仲良くなった村田さんに「すごいいい曲を見つけたから聞いてくれよ!」とイヤホンを差し出された。村田さんは軽音学部で、バンドを組んでいるらしい。あまりにもいい曲だったので、知り合いみんなに進めているというその曲は動画投稿サイトに投稿されていたものだった。
差し出されたイヤホンから流れてきた曲に、俺は昼休みの廊下なのにもかかわらずに豪快に泣いた。むせび泣いた。目の前の村田が焦っていて、気がつけば俺は保健室にいたけどひたすら曲を、歌を聴いて泣いた。父さんのことを思い出して泣いた。
その時の曲、歌が『ゼンイツ』のものだったのだ。
『ゼンイツ』は大切な人の死は当たり前に悲しくて、当たり前に辛くて、当たり前に泣くことを歌っていた。寂しいのも当然で、それを隠したいのも当然で、逃げたいのも当然で、でも最後には歩き出せればいいと歌っていた。弱くても、諦めなければいいと歌っていた。大切な人が死んでも世界は動いていて、変わらず食事も睡眠も笑うことができても薄情ではない。けれど突然に大切な人の死を思い出して寂しくなって泣きじゃくるのが生きているということだと歌っていた。
俺はそこでようやく理解した。時間がなくて、父さんと満足のいく別れができなかったと思っていたけれど、本当は違う。いくら時間があっても父さんがとても大切だっから満足のいく別れなんて到底できなかったのだ。
父さんがいなくても食事が喉を通るのも、変わらず眠れる自分も嫌だった。忘れようとする自分が嫌だった。
その日は保健室でかわらず泣いて、中等部にいる妹の禰豆子が俺を迎えに来て帰った。家に帰ったら俺は母さんにしがみついて泣いて、父さんが死んで寂しいと喚き、弟妹たちも母さんも泣いてその日はみんなで一緒に寝た。翌日、俺は父さんのことを思い出して生きられるようになった。
それから俺は村田さんに動画投稿サイトのURLを教えてもらって、母さんに頼み込んで格安スマホを契約してもらった。本体に関しては俺の貯めていたお年玉で買って、毎月の料金はお小遣いから出すつもりだったけど母さんが家計からだすからと笑って言ってくれた。
俺は動画投稿サイトで『ゼンイツ』の曲を聴いた。『ゼンイツ』は投稿し始めたばかりらしく、聴いた曲が最初の曲だった。2曲、3曲と投稿されて俺は必死にいいねを送った。
そしてブックマークや再生回数が増えると、『ゼンイツ』はブログをやり始めた。そこでは曲のダウンロード販売がされていて、俺は買った曲を繰り返し聞いた。もうイントロクイズで誰にも負けないくらい聴いてると思う。
ブログは事務的なことばかりで、『ゼンイツ』のことは何も分からなかった。たくさんある中のコメントに俺のものも混じり込んでいるけれど『ゼンイツ』は個別に返事をすることはなく、「全部読んでいます。ありがとう」という言葉が毎回ブログ記事に書かれていた。
『ゼンイツ』は顔も年齢も性別も分からない。でも若めの男性だというのは歌声でわかる。徹底して『ゼンイツ』は個人が分かるものを出さなかったが、『ゼンイツ』の人柄はよく分かった。それは歌によく出ているからだ。
優しさに溢れた歌詞、世の無常を受け入れながらも生きていかねばという意思が曲には出ていた。
俺は『ゼンイツ』の曲に出会ってから、正直いってずっと幸せだった。アイドルを追いかける人たちの気持ちが分かるようになったと思う。
俺のアイドルは『ゼンイツ』だ。アーティストだけど。
好きで好きでたまらない。
だから、『ゼンイツ』がメジャーレーベルでデビューしたのに歓喜した。けど相変わらず『ゼンイツ』はメディア露出が一切なく、PVだって本人映像はなかった。イメージクリップだった。
それでも俺は良かった。他のファンも別にそれで良かったと思ってる筈だ。
なぜなら『ゼンイツ』はブログにはっきりと書いていたからだ。
「人前に出るのも人前で歌うのも怖くて苦手」ですと。
だから『ゼンイツ』のコンサートツアーをやることが決定した時は驚きながらも生歌聴けると飛び上がって喜んだんだが、その決定から1週間経った今日、夕方に活動休止の報告に俺は天国から地獄へと叩きつけられたわけだ。
なぜコンサートが決定したのに活動休止なのか。
真の『ゼンイツ』ファンならすぐに理解できる。 間違いなく運営側と揉めたのだ。『ゼンイツ』はコンサートしたくないのに、運営側が強行したのだろう。『ゼンイツ』はメジャーデビューしてメディア露出がないのにオリコンチャートの上位に入る人気ぶりだからな。
理由は明かされてないが運営側に腹が立つ!!
こちとら『ゼンイツ』の歌が生き甲斐なのに!!
俺は遣る瀬無い気持ちになりながら、それでも慣れた動作でイヤホンを耳に入れると『ゼンイツ』のものしか入っていないミュージックアプリを起動する。
『ゼンイツ』に慰めてもらわねばやってられない。
俺はリストから曲を選んで流し始めるとまたトボトボと歩き始めた。
『ゼンイツ』の耳心地のいい歌声が俺の脳をゆっくりと揺さぶる。聞こえてくる歌詞に、俺は「そうだ!」と思いついた。
聴いている曲では「辛い時はブランコに乗ろう。楽しいあの時の思い出を取り戻すんだ」と歌っている。俺もそれに倣おう。ブランコに乗って、楽しいことを思い出そう!!
俺はほんの少し元気を出すと近くにある児童公園へと向かった。幸い夜だから子供は誰もいない。気兼ねなくブランコをこげる筈だ!!
そう思って児童公園に到着するとブランコに先客がいた。黄色い三角マークの柄のフードパーカーを着た・・・・・・おそらく男がブランコに座る。そして男はキイキイと小さくブランコを漕ぎはじめた。
俺と同類かな?辛いことがあったのか?
だがブランコは2つあるから、隣を使おうと近寄ると目的のブランコには使用禁止と札がついてテープが貼られている。俺は仕方なく、男が乗っているブランコ側の柵の外に立った。
男はしばらくキイキイとブランコを漕いでいたが、ゆっくり振り向くと俺の顔を見た。フードを被っていたから分からなかったが、男はは俺とそう年頃は変わらない青年だった。顔はわりと童顔で、榛色の丸い瞳と綺麗な金髪が印象的だった。けれど軽い印象を受けないのは立派な太眉のせいかもしれない。
「え?」
「ん?」
青年が呟きに俺は小首を傾げた。青年はゆっくり顔を正面にすると、またゆっくり振り向いて俺を見る。
「あの・・・・・・な、なんですか?」
青年は俺に向かってそう言うと怪訝そうな顔をした。
「順番を待っています!」
「じゅ、順番?」
「はい!俺もブランコに乗りたいので!」
「あ、そうなの・・・・・・?ごめんなさいね・・・・・・?」
青年はそう言うと立ち上がって、俺に「・・・・・・どうぞ」とブランコを譲ってくれた。なんて優しいんだ。だが譲るのは少し早くないか?
「いや!君も乗り始めたばかりだろう!俺はもっと待つことはできるので存分にブランコを楽しんでくれ!!」
俺はそう言って青年にブランコを進めたが、青年は首を振るとどうぞどうぞと俺に譲ってくる。しかし俺は本当に我慢できるのだ。けれどそれを伝えても青年は納得してくれない。
「わかった。ではこうしよう!俺が10回漕いだら、君と変わる。君が10回漕いだら、俺と変わる。これでいこう!!」
「え?え?本気で言ってる??」
俺は戸惑う青年をそのままに、ブランコを漕いだ。そして高らかに・・・・・・と言っても夜なので声を抑え気味にして1から数え始める。
「いーち!にー!君も俺が数を間違えていないか数えてくれ!」
「え?え?マジで?・・・・・・さーん、・・・・・・しー・・・・・・」
俺たちはそうしてお互いに10回ずつブランコを漕いでは交代してをしばらく繰り返した。
****
「お前・・・・・・本当になんなの?」
「ん?俺か?俺は竈門炭治郎だ!」
「そういうことじゃないんだよなぁ。まあ、いいや。俺は・・・・・・我妻だよ。下の名前は今とっても嫌いだから教えない。ごめんなさいね」
2人で公園の自販機で買ったお茶を飲みながらベンチに腰掛ける。ブランコを漕ぐ際に2人して数を声に出して数えていたから喉が渇いたのだ。
「いいよ。教えたくなったら教えてくれ。それにしても、我妻に会えて良かったよ。今の俺、すごい落ち込んでたからひとりだったらブランコを漕いでもダメだったかもしれない」
「え?何?炭治郎、落ち込んでたの?そんな風には見えないくらい強引だったんだけど??」
我妻の言葉に俺は恥ずかしながら落ち込んでいたと頭を掻きながら言った。我妻はへにょりとした笑みをこぼすと「お揃いだな」と言った。
「お揃い?」
「俺と落ち込んでたの。もうこれからどうやって生きていこうって思うくらいにね」
「我妻もそうなのか?俺もこれからどうやって生きていこうかと悩んでいたんだ。それで、ブランコ漕いで楽しいことでも思い出そうと思って・・・・・・」
俺の言葉に我妻はビックリしたような顔をした。
「へえ?炭治郎も落ち込んだ時はブランコ漕ぐんだ?俺も昔からそうなんだよね。ブランコ漕いで、子供の頃の楽しかったこと思い出すの。・・・・・・爺ちゃんが生きてて、笑ってブランコを押してくれたこと・・・・・・。それを思い出せば、いつもならまた頑張ろうって思えるんだけど・・・・・・今回はダメでさぁ。・・・・・・俺、自分のダメさに嫌気がさすよ」
我妻は泣きそうな顔をしてそう言った。詳しい事情は知らないが、本当に落ち込んでいることは分かるし、そんな姿に俺は不思議と苦しい気持ちになった。俺はどうしたら我妻が元気になるだろうかと考えて、そうだと思いつく。
「よし!!もう一度、ブランコに乗ろう!!」
「え?もう一回?」
「今度は俺が押してやる!楽しかった思い出に浸るんじゃなく、今を楽しくしよう!ひとりでは無理でも、今は俺たちは2人だ!2人で楽しく過ごそう!!」
俺はそう言って、我妻の手を引くと夜の公園へと駈けもどる。後ろから我妻が「えええええ?なにそれぇ?」というのが聞こえるが、声は笑っていた。
俺たちはそれから2人で夜の公園で童心に返って遊んだ。ブランコだけじゃなく久しぶりに滑り台を滑り、砂場で山を作ってトンネルを作ったりした。時間が午前に回ると、俺たちは汚れた格好のままコンビニに寄って今度は大人の楽しみとばかりに酒を買い、そのまま俺のアパートでテキトーな鍋を食べて飲んだ。俺が買ってきた夕飯の材料は見事に無駄にはならなかったということだ。
俺たち2人は馬鹿みたいに笑って過ごした。深夜のバラエティ番組を見て、なんだか分からない海外のB級映画を見て、朝方にようやく風呂に入って、そして狭いベッドで2人で寝た。
出会ったばかりなのに俺たちはまるで竹馬の友のようだった。会話も心地よいテンポで、面白いと思うタイミングも悲しいと思うタイミングもよく似ていた。それに我妻はすごく落ち着く声をしていて、とても俺の心に響くのだ。じんわりと暖かい気持ちになる。
なぜ我妻が落ち込んでいるのか、なぜ俺が落ち込んでいるかの話はしなかった。我妻は話したくないだろうし、そして俺はもう落ち込んでいなかったからだ。新たにできた友人の存在に救われたからだ。
「我妻に会えてよかった。俺、落ち込んでいたのが嘘のように元気になったよ。ありがとう」
「・・・・・・俺も、炭治郎に会えてよかった。俺、相変わらず自分が嫌いだけど、炭治郎が俺に会って元気がでたなら、俺もそう捨てたもんじゃないなって、ちょっと思ったよ。・・・・・・俺こそありがとう。俺、いろいろ難しいけど、もう少し頑張ってみるよ」
「ああ、俺も応援するし、大したことはできないかもしれないが協力もするよ」
「・・・・・・ありがとう、炭治郎」
眠りに落ちるほんの少し前、2人で布団に潜ってそう囁きあった。我妻が目を閉じたのに倣って俺も目を閉じる。
今日のこの出会いと安らぎも『ゼンイツ』のお陰だ。彼の歌が俺を導いて、我妻に出会わせてくれたのだ。
『ゼンイツ』、俺はあなたが活動を辞めてもずっとファンを続けるよ。君が歌ってなくてもいい。音楽の世界は俺が想像もできないほどのしがらみや圧力があるんだろう。逃げてもいいんだ。願わくば、あなたにも安らぎがあるといい。
あなたの歌に何度も救われた、俺からの祈りだ。
****
ピンポーンという音に目が覚めた。
なんだと思って顔をあげると、10時をしめす目覚まし時計が目に入る。しまった。大学の講義をすっぽかしたなと頭を掻くが、またピンポーンという音に意識がしっかりしてくる。
「んん・・・・・・。たんじろぉ?」
「まだ寝ててもいいぞ。はーい!今開けまーす!」
俺は前半の言葉は我妻に、後半は外の来客に向けた。しかしなんだろうか?家族が来るとは言ってなかったし、そもそも平日だし。宅配便とか頼んでいただろうかと、思いながらアパートの玄関を開けた。
すると銀色の長髪をした、すごく男前な男性が立っていた。上背がかなり大きくラフな格好をしている派手な男だった。なお全く知らない人だ。
「・・・・・・どちら様でしょうか?」
「宇髄というものだが、ここに我妻善逸という家出野郎はいないか?」
宇髄と名乗った男はちらりと玄関のタタキをみた。そこには俺の靴と、我妻の黄色いスニーカーが転がっている。宇髄さんは我妻のスニーカーを見ると目を細めた。
「います・・・・・・けど・・・・・・」
我妻は家出青年だったのか?あれ?それよりもなにか聞き捨てならない言葉があった気がするが・・・・・・。
俺の返事に宇髄さんは「悪いな」というと狭い玄関に入ってきた。俺は慌ててひとまず廊下に上がる。
「おいこら善逸!!テメェ連絡もなしに外泊してんじゃねえ!しかもよそ様の家にあがりこむったあどういうことだ!迷惑かけてんじゃねえ!!」
宇髄さんが大きな声でそう言うと、どさりという音がして慌てて我妻が廊下に出できた。
「宇髄さん!?なんでここにいんの!?なんで居場所わかるの!?」
「うるせえ。俺に分からないことらないんだよ!おらっ!さっさと支度してい会社行くぞ!今後のミーティングだ!!」
「うん、わかった」
宇髄さんは青筋立てながら、我妻・・・・・・善逸にそう言った。善逸は宇髄さんの言葉に頷くと自身のボディバッグを引っ掴むと俺が貸したスウェットのまま、靴を履く。
「ごめん炭治郎!服このまま借りるね!ちゃんと洗って返すから!」
「あ、ああ。それは構わない」
「外に車を回してあるから、先に乗ってろ」
善逸は宇髄さんの言葉に頷くと、俺に「またね」と言ってでて行った。突然の出来事に目を白黒させている俺だったが、宇髄さんはまだ玄関にいた。
「・・・・・・面倒をかけたな。だが助かった。あいつは昔から俺が面倒見てたんだが、今はちょっと色々あってな。励ましてくれたんだろ?」
「あ、いえ、励ませたのかは分かりませんが・・・・・・。え?善逸?名前が?」
俺は我妻が、大好きな『ゼンイツ』と同じ名前なのに驚いた。いや、しかし『ゼンイツ』は本名とは限らないし名前とも限らない。
「気づいてなかったのか・・・・・・。まあいい。お前、明日の午後は暇か?改めて派手に礼をしたい」
「えっと、明日なら講義は午前までなので・・・・・・16時までなら大丈夫です」
「じゃあ、ここに書いてある住所に来い。受付でこれ見せて、名前言えば俺のところまで案内する。じゃあ、善逸が世話になったな竈門炭治郎」
宇髄さんはそう言うと出て行った。俺の手には【ミュージックピラー・ジャパン】という会社名の名刺がある。そこには【代表取締役 宇髄天元】と書かれていて茫然とした。
俺は慌てて『ゼンイツ』の公式ホームページを開いた。そしてそこから所属レーベルを探して名刺と見比べる。間違いない。この名刺の会社は『ゼンイツ』が所属してるところのものだ。
俺はそのまま今度はミュージックアプリを起動した。そして震える手で目的の曲を再生すると、2:54のところまでタイムゲージを進める。目的のフレーズは間違いなくこの秒数だ。なんども聞いたから脳が覚えてる。
そうして流れてくる、語りかけるような囁く歌声に俺はがくりと膝をついた。
眠る前、布団の中で聞いた囁きと声が同じだった。
****
さて俺はそれからわりと茫然としたまま1日を過ごした。でも洗濯機に入っていた我妻善逸の着ていた服は風呂場で丁寧に手洗いした。推しの服を問答無用で洗濯機に掛けられるほど俺は豪胆じゃない。
そして戦々恐々としながら絶対に失敗できない心持ちでアイロンがけをし、折り目正しくたたみ、商店街よ梱包材屋で買いもとめたた販売用ビニールに洋服をいれ、これまた梱包材屋で買った綺麗な紙袋に洋服を入れた。
翌日の午前の講義はいるだけ無駄だった気がする。教授の話は何も入ってこなくて友達の玄弥には散々心配された。とりあえず今度ノート貸して欲しい。それだけでいい。
そうして俺は今、【ミュージックピラー・ジャパン】の社長室に隣接しているらしい、応接間にいる。ふわふわした頭のままで受付に名乗ると受付の女性は「竈門炭治郎様ですね。宇髄から承っております」と言ってどこかに電話を掛けると雛鶴という女性秘書が現れてこの応接間まで案内してくれた。
目の前には高そうな器で日本茶が置いてあるが飲めそうにない。しかし・・・・・・それにしても俺は名乗った覚えがないのに何故宇髄さんは俺の名前を知っていたのだろうか。アパートの表札には確かに『竈門』とは書いてあるが・・・・・・。
そんなことを考えていると、ノックとほぼ同時に宇髄さんが入ってきた。宇髄さんは相変わらずラフな姿だ。スーツとかではない、派手な色のパーカーを着ている。中のシャツも派手だ。
「よお!わざわざ来てもらってすまねぇな。ちょっと立て込んでて、そっちに行く暇は俺も善逸も取れねーんだわ」
宇髄さんはそう言うと、どさりと俺の目の前のソファに座った。
「いえ、大丈夫です。その・・・・・・『ゼンイツ』はいま大変でしょうから」
俺の言葉に宇髄さんは「本当になぁ」と笑った。
我妻善逸は『ゼンイツ』だった。その結論は俺の中に衝撃はあれどストンと納得できた。落ち込んだ善逸がブランコに乗っていた理由も、名前を今は嫌いだと言った理由も、初めてあった俺たちがしっくりと来た理由も。
何しろ俺は『ゼンイツ』の歌に強い共感を持っていた。それは彼の生き方に共感を持ったのと同じだ。だから俺たちは初めてあったのに、初めてとは思えないくらいしっくり来たんだ。烏滸がましいかもしれないが、感性が似ているのだろう。
「しかし、本当にこっちは助かったよ。もうやめるとか言って、勝手に活動休止をブログに宣言して逃げ出したあいつをどうやって説得しようかと悩んでたんだわ。けど善逸のスマホのGPSで辿ってお前ん家に迎えに行ったら復活してたからな」
「・・・・・・いや、特に何もしてないんですが・・・・・・」
俺がしたことと言えば、成人男性2人で夜の公園で遊んで鍋食って酒飲んでテレビ見て寝ただけだ。大したことはしてないし、俺がしたいことをしたに過ぎない。いま思い出すとそうとう強引だった気もするしとなんだか落ち込んできて、ついつい俯く。
「ふーん?だが善逸はお前のお陰で頑張る気になったって言ってたぞ?楽しかったから、その気持ちを歌にしたいって」
宇髄のその言葉に、俺は驚いて顔を上げた。『ゼンイツ』が歌にしたいって言ってくれたなんてファン冥利につきる。全ファンに殴られてもいいくらいだ。あまりのことに顔がカッカとしている気がする。
「おーおー。派手に嬉しそうな顔だな。まあ仕方ないか。ファン歴の長い『竈門炭治郎』くんだもんな」
にやにや笑って言う宇髄さんに俺は首を傾げる。なぜ俺が『ゼンイツ』のファン、しかもファン歴が長いことを知っているのだろうか。
「あの、なぜ俺が『ゼンイツ』のファンであることを知っているんですか?」
「なぜってお前、新曲が出るたびにド派手なファンレター送ってくるじゃねぇか。A4封筒に入ったなんのレポートだっていう分厚さのとんでもねえファンレター。あんなの送ってくんのはお前だけだぞ」
その言葉にそうなのかと驚愕した。曲がいかに素晴らしかったかの感想を思うままに書いていただけなんだがあれは量が多過ぎたのか。
「うちのスタッフの中じゃ、『竈門炭治郎』は有名だよ。善逸に届くファンレターは全部検閲が入るからな。お前のファンレターは毎回長い長いって話の種だ」
なんだか恥ずかしい。スタッフの人に苦労をかけていたのかと申し訳ない気持ちになるが、そもそも善逸にもその長いものを読ませてたのかと思うと悪いことをした気持ちになる。
「あの、検閲が入るってことですが・・・・・・善逸も俺のファンレターって読んでるんですか?その・・・・・・気持ち悪い奴って思われてないですか?」
だとしたら最初に名乗った時、熱烈なファンなのはバレていたのだろうか。
「いや、流石に長すぎるから抜粋して見せてるはずだ。それと悪いが善逸にはファンの名前は非公開にしてるから、お前の正体は気がついてないぞ」
宇髄さんは相変わらずニヤニヤ笑っている。この人は悪い人ではないようだが、ずいぶん人を食ったような雰囲気がある人だ。
「そうですか・・・・・・良かったです」
自分のファンレターが常軌を逸しているのを知ったら、流石に全容を読まれるのが憚られる。次からはちゃんと良識ある量にしよう。
「さて、とりあえず礼の件だが・・・・・・」
「あ!お礼はいいですよ!今日は服を渡しに来ただけなので」
お礼と言われても本当に大したことはしていない。なんでもないことなのだ。それに『ゼンイツ』がまた活動を再開してくれるというなら、それ以上に嬉しいことはない。
「俺は『ゼンイツ』がまた歌ってくれるだけで十分です。心のままに歌ってくれることだけが願いです」
俺のその言葉に、宇髄さんは「なるほど」と頷いた。そう『ゼンイツ』は活動休止宣言を撤回したのだ。人気アーティストのこの騒動に雑誌各社は賑わいをみせている。人前が苦手な『ゼンイツ』には辛いことだろうけれど、俺と過ごした時間を歌にしたいと言ってくれた『ゼンイツ』の強さを信じたい。
「あ!でももし、本当に何かお願いできるならひとつだけ・・・・・・」
「ん?なんだ?言ってみろ」
俺は叶えてもらえるか分からないけれど、けど宇髄さんは善逸を本当に心配していると信じて、お願いを口にした。
「善逸が活動しやすいように、環境をサポートしてほしいです。今回の活動を巡っての騒動の全容は俺には分かりません。けど善逸が活動休止をしようと、歌をやめようと思うまで追い詰められのは分かります。今後はそうならないように、そんな風に追い込まれることないようにフォローをしてほしいです」
俺がそう言うと宇髄さんはゆっくりと目を閉じて「耳が痛え話だな」と言った。
「お前の言う通り、今回の騒動は俺たち運営側が善逸を追い込み過ぎたのが原因だ。あいつは極端に自己肯定感が低いやつでな。長いファンなら分かるだろうが歌に自信はあっても自分という存在に自信が持てない。だから極端に自分が見えることを嫌がる。だがアイツは間違いなく今後の音楽業界でトップを走れるやつだ。だから運営側ではアイツをもっと全面に出して売り出したい奴らがいてな。・・・・・・コンサートツアーもそいつらが無理に通した結果、善逸がビビって逃げ出したんだ。善逸に全く準備ができてねぇのに、下からの報告に俺もとうとうやる気だしたかと思って本人に確認も取らずに承認しちまった。善逸は寝耳に水だったんだとよ。・・・・・・今回は本当に俺の落ち度だ。だからこそ、それをフォローしてくれたお前にとても感謝している」
宇髄さんの説明にそんなことがあったのかと納得した。しかしコンサートツアーはもう開催は取りやめられない段階まで来ているらしい。だから善逸が活動休止の撤回をしたということはコンサートツアーをやる覚悟を決めたと言うことだ。
「あの、コンサートツアーやって大丈夫ですか?ファンとしては嬉しいですが、アーティスト本人が潰れるのは本末転倒なので・・・・・・」
「ああ、それな。それは俺も心配してるからとりあえずはマネージャーを変更する予定だ。今のやつだと全く善逸の個性にあってない。才能を守りきれてねえ。もっと派手に相性がよくて、善逸のあの七面倒くさい性格のフォローができるやつにする」
「そうですか!良かったです!」
俺はその言葉を聞いてホッとした。
それなら善逸が周りに潰されてしまうのも防げるかもしれない。これでまた俺は善逸の新曲を楽しみに生きていける。
「さて、それを踏まえた上で竈門炭治郎。お前、まだ大学生3年で就活まだだよな?」
「はい。そうですけど・・・・・・」
「じゃあ、お前は来週から善逸のマネージャーな。学校はひとまず休学して、バイトとかの都合があるなら相談しろ。代わりの人間をこっちで手配するわ。学費に関してはこっちの都合で休学させるわけだから、大学4年分の学費はこっちで負担する。ああ、給料はもちろん普通に出るからな」
ポンポンと言われる言葉に俺は目を剥いた。この人は何を言ってるんだろうか。
「ひとまず来週から一通りのマネージャー業務とこの会社のレクチャーするから。スーツとか必要なもんはこっちで用意しとくから後で採寸するそま。あと善逸のマネージャー業で最も重要な仕事は善逸のメンタルケアだ。その都合で寝食は共にしてもらうから、善逸のマンションに引っ越ししろ。家に帰ったら引っ越しの準備始めてくれ。費用は全部経費で落ちるからうちの会社宛てに領収書切っとけよ。項目は善逸って書いとけばそれでいい。さて、ここまでで質問はあるか?」
「あ、ります・・・・・・え?お、俺が善逸のマネージャーするんですか?」
「そうだ」
「社員じゃないし、学生なんですが・・・・・・?」
「ああ、そうだったな。一番重要な雇用契約の説明忘れてたわ。これがお前の雇用契約書だ。ハンコないだろうから、家に帰って来週の出社の時でもいいし、家に誰か取りに行かせるでもいいぞ」
そう言って出てきた書類には俺の名前がきちんと書かれていた。手書きじゃなくキチンと印字されている名前に前もって用意されていたのが伺えて宇髄さんが本気なのが分かる。
「あの、なんで俺が?だって、そんな・・・・・重大な仕事でしょう!!」
俺の言葉に宇髄さんは笑っていなかった。真面目な表情に逃げるのかと言われてるように感じる。
「・・・・・・お前の願いは善逸が活動しやすいように環境を整えてほしいってことだったろ?なら簡単だ。お前がそれをやればいい」
「俺が・・・・・・」
「そうだ。お前の願いを俺が了承したとして、それが口約束だったらどうする?お前は善逸がキチンとケアされていることをどうやって知るんだ?新曲が出続ければそれでケアされていると安心できるのか?本当はアイツが、自分をすり減らして歌っていたとしてもお前はそれが知り得ない立場でいいのか?アイツの歌が、お前の生き甲斐じゃなかったのか?分厚いレポートにはそれがひしひしと感じられたぜ?『竈門炭治郎』くん?」
宇髄の言葉にどっと心臓が鳴った。たしかに善逸が安心して歌える環境かどうかなんてただのファンである俺には知りようがない。現に今回の騒動だって、ここまでなってから知ったのだ。むしろ知ってから俺はたまたまの幸運で関われたに過ぎない。
「自分の生き甲斐なら、自分で守れ。そのチャンスとお前の生き甲斐を一番側で見守る権利をお前への礼にしてやるよ」
じわじわと汗が出てくる。
だって確かにこれはチャンスだ。
善逸がどうしているか、健やかにしているかを誰よりも理解できる立場だ。そして『ゼンイツ』が歌っていくのを直接的に支えることができる。
しかしそれでも不安がある。だって俺は音楽業界のことも詳しくなくて、ただの普通の学生で、メンタルトレーナーでもなければマネジメントのプロでもない。善逸を守りたいとおもってもできるのだろうか。
「宇髄さーん。炭治郎来てるって本当?」
ノックなしで開いた扉に体がびくりと跳ねた。宇髄さんは「ノックしろよ」と呆れているが宇髄さんもノックと同時に開けてたから大差ない。
「へいへい。ごめんないさね!・・・・・・へへへ!炭治郎!また会えたな!」
ニコニコしながら近づいてくる善逸に、俺は生き甲斐が歩いてると感動する。それと同時にこの生き甲斐を生かすも殺すもできるチャンスが目の前にあるのだと自覚した。
この笑顔が曇れば、歌は生まれないのだ。
「宇髄さん!!俺!!やります!!」
「お、マジか。じゃあこれ忘れずに持って帰れよ」
「はい!頂きます!!」
「え?なになに?何の話?あ、炭治郎。洋服クリーニングしてもらったから返すね」
「ありがとう!!俺も洗ってアイロンかけてきたぞ!」
「ありがと・・・・・・ってなんで梱包してんの!?」
俺の持ってきた紙袋をみて善逸はびっくりしていたけど、ふっと笑った。可笑しそうにケタケタ笑う姿にじーんとする。推しが笑っている。
「善逸!!」
「ん?何?あ、名前名乗るの遅れてごめんね?」
「それはいいんだ!そんなことより、来週からよろしく頼む!俺がしっかり、お前を支えてみせるからな!!」
「え?うん?何の話?」
「宇髄さん!俺は学校への手続きやバイト先への連絡があるのでこれで失礼します!」
「え?炭治郎、俺の話聞いてる?」
「おう、またな。帰る前に採寸してけよ。お前を案内した秘書が廊下の受付にいるからそいつに言えばいいぞ」
「分かりました!それでは失礼します!善逸もまたな!」
「えええええ?何なのよ!帰るの早いよ?!!」
俺は善逸の声をBGMに応接間から出た。目の前がカッカッしている。熱に浮かされたように足元もフワフワと覚束ない。
けれどまさしく、俺の未来は開かれた。
俺は名実ともに自分の生き甲斐のために生きるのだ。
いくぞ竈門炭治郎。
自分の生き甲斐の生殺与奪は己自身で握るのだ。
****
【補足説明】
◯我妻善逸
『ゼンイツ』の名前で個人の時から活動してる。大学は行ってない。曲を始めて作ったのは身寄りのない善逸を引き取って育ててくれた、ただ1人の家族であった桑島慈吾朗が余命幾ばくもなく、善逸を案じてやまないために爺ちゃんがいなくなっても生きていけるという気持ちを歌にして慈吾朗に捧げたのがきっかけ。音楽に関して類い稀なる才能があるが本人は好きにやっている為、自分の技術の高さに無頓着。作曲、作詞、編曲も全部自分でやる。大体の楽器が演奏できるため、たぶんオーケストラの指揮者にも今からでもなれる。しかし捨て子であったために自己肯定感が極端に低い。なお動画投稿は宇髄がやった。現在はアーティストとして宇髄のレーベルに身を寄せているが、本物のプロになったことで個人で好きにやっていた時と金儲けしなければならないというプロのギャップに色々ダメージを食らっていたところモブのマネージャーにもっと売れるようにと顔出し必須なコンサートやイベントを知らぬうちに組まれてしまい逃げ出した。
寂しんぼな為に一人暮らしにも色々ダメージきてる。けど炭治郎がマネージャーになって、最初はすごいびっくりしたけどお母さんかなっていうくらいの衣食住のサポートに胃袋はもちろん、精神的にもがっちり掴まれてる。ちなみに炭治郎がマネージャーになってから楽曲が恋の歌の比率があがったのにファンは私生活が何か変わったのではと邪推している。
◯竈門炭治郎
アーティストの『ゼンイツ』の大ファン。思春期のデリケートな年頃のデリケートな時にドンピシャで心を打たれたのでもう一生ファンをやめられない。思いがけずに本人に出会って物理的に応援し、支える立場になる。
6人兄弟の長男だけあり、人との距離は近いし世話焼きたい願望もありで寂しんぼの善逸と相性ばっちり。ひとまず善逸を支えるにあたって出来ることから、体の健康からと手料理で食生活の改善をした。手製のお弁当まで持たせてる。美味しそうにご飯を食べる善逸に、自分が作った食事で推しの血肉が形成されるなんて幸せだなあと思ってる。
炭治郎はマネジメント能力はまだまだ未熟だが、その辺は宇髄の秘書3人に教えてもらいつつ向上中。けれどメンタルケアの方は対善逸に関しては天才かってくらい上手い。頑張れ!できるぞ!善逸なら大丈夫だ!!俺がここで見守っている!やれるぞ!!楽しんで歌えばいい!!!とツアーコンサートの間中、でかい声が響き渡っていて正直、前列のお客さんにも聴こえてた。けどコンサートは『ゼンイツ』ガチ勢が多い為、本当に人前が 苦手なんだなというのが伝わり、コンサート開始前は「ゼンイツ頑張ってーー!!」がお決まりのコールになった。
ちなみに炭治郎が宇髄にもらった雇用契約書の中の担当業務欄に『担当アーティストの恋愛のサポート』と記載があり、特記事項に『社内恋愛は自由とする』とあり、炭治郎は3ヶ月後にこの記載に感謝した。
◯宇髄天元。
ミュージックピラー・ジャパンのCEO。年齢はかなり若くアラサー。子供の頃から桑島家と親交があり、桑島慈吾朗に自分亡き後の善逸を託されていた。宇髄は善逸の音楽の腕を伸ばすためと自己肯定を促すために動画投稿をしていたが、いくら人気が出てても音楽に対する真摯さは成長しても音楽以外の自己肯定感は育たなかった。
仕方ないので親から引き継いだレーベル会社で善逸とその才能を保護しようと思ったが、思いのほか社長業が忙しくて善逸のケアが全然できず、活動休止騒動が引き起こってしまう。
いなくなった善逸にどこに行ったかと個人的に仕込んでいたGPSで住所確認したら社内で激重いファンで有名な竈門炭治郎のファンレターという名のレポートが入っている封筒に書かれている住所ですぐに迎えに行くのではなく昼前にした。
なお、宇髄は社内忘年会で酔った際に「派手に前世の記憶がある!!」と言っていたのを複数の社員が目撃している。
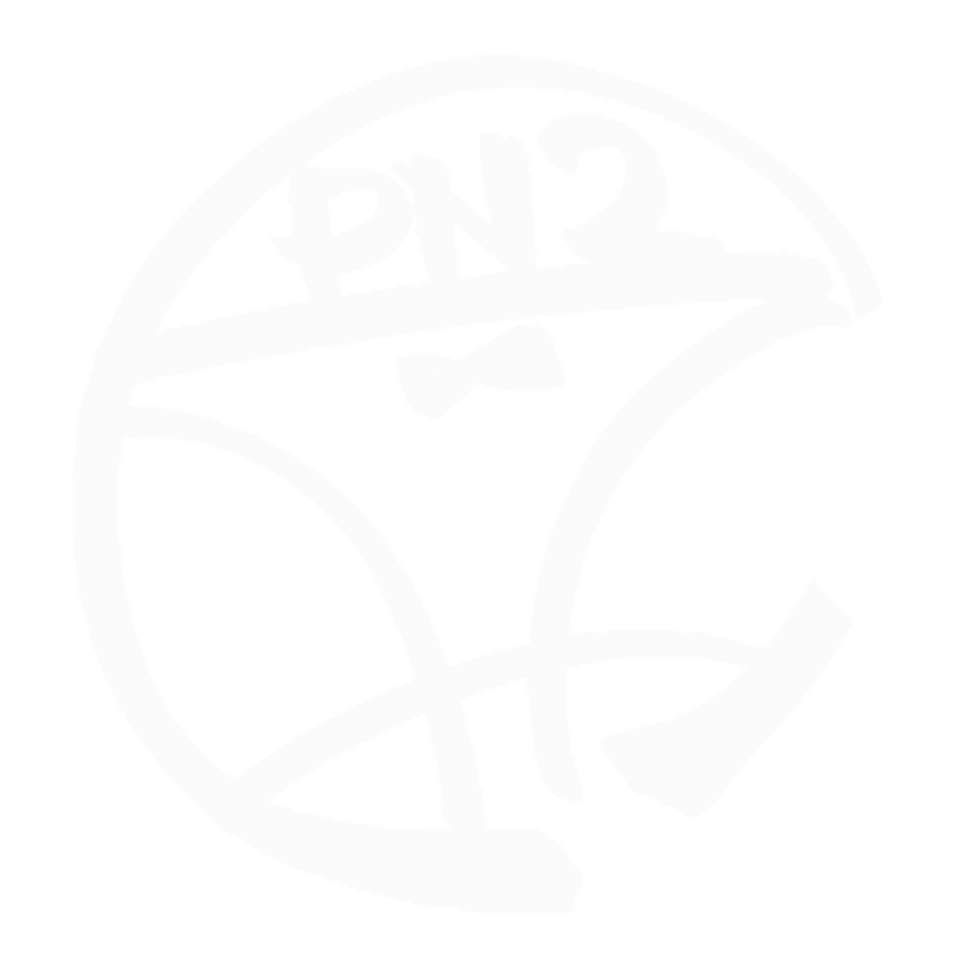


コメント