花吐き病パロです。無自覚な炭善の話です。
ぜんねずを匂わす描写がありますが、周りの勘違いです。
約19000字/原作軸
「善逸から花の匂いがする」
「花ぁ?」
炭治郎の言葉に善逸はきょろりと自分の周りを見渡した。そして腕を持ち上げてすんっと匂いを嗅ぐが分からない。花の匂いなどするだろうか?
「なにそれ?炭治郎お得意の匂いの比喩表現?」
「いや、違う。本当に匂いがするんだ。たぶん・・・たんぽぽか?」
「たんぽぽぉ!?全く季節じゃないじゃない!」
善逸が言うように今はたんぽぽの季節からは遠い冬に差し掛かったあたりだ。現に任務終わりの炭治郎と善逸の家路は木枯らしが吹いていて、善逸の髪色ににた銀杏の葉がひらひらと舞い踊っている。
「匂い袋とか持ってないか?」
「そんな洒落たもん持ってないし、そもそもたんぽぽの匂い袋って存在するの?」
善逸の言葉に炭治郎もうーんと首を傾げた。そして善逸の方へと顔を寄せるとまたスンスンと鼻を鳴らす。
「やっぱり・・・する・・・」
「いや知らんよ。そんなことより帰ろーよ。禰豆子ちゃん待ってるぞ。お兄ちゃんを心配してるだろうから早く安心させてあげなきゃ!」
そう言って善逸はひらりと炭治郎の隣から駆け出した。ほんの少し先に行き、振り返って手を振る善逸に炭治郎はふっと笑いが溢れる。善逸が自然に妹の禰豆子の心配をしてくれるのが擽ったくもあり、心地いい。自分の大切なものを息をするように大切にしてくれる善逸に、炭治郎は途方もなく救われている。
「ああ、そうだな。早く帰ろう」
炭治郎が笑ってそう言うと、善逸も嬉しそうに笑った。するとまた、たんぽぽの匂いが濃くなりーー。
「ケホッゲホッ・・・ゴホッゲヘェッ!」
「善逸!?」
えずく様に咳き込む善逸に炭治郎は慌てて駆け寄った。突然のえずきに何事かと思うが苦しそうに汚い声をあげる善逸を少しでも楽にしてやらねばと背中を撫でる。
「ウッ・・・・・・ウォエエエエエエエエエ!!」
「わあっ!!」
昼間の蕎麦をがっつり吐き戻した・・・・・・と思った炭治郎だが、善逸の口からボトボトと落ちてきたのは蕎麦ではなく、たんぽぽであった。
そう、たんぽぽであった。
「ぜ、善逸ーー!!たんぽぽをどこで拾い食いしたんだ!!たんぽぽは確かに食べられるが花が開ききったのは食用としては向かないぞ!!たんぽぽは花が咲く前の蕾がつくかつかないかくらいが一番いい時期だ!!」
「食っとらんわーーー!!」
炭治郎はひとまず落ちた花をかき集めるべきかとしゃがみ込んで手を伸ばそうとした瞬間、善逸に強かに蹴飛ばされて転んだ。
「おわっ!何をするんだ善逸!」
「馬鹿野郎!!迂闊に触るんじゃないよ!!これは花吐き病かもしんねぇだろ!!」
「花吐き病?」
呆気にとられる炭治郎を置き去りに、善逸は青い顔で花をかき集めると手拭いにでも全てを包み込む。そしてスッと立ち上がると炭治郎を見下ろして言った。
「俺、蝶屋敷行かなきゃ。アオイちゃんに診てもらうわ」
確かに花を吐いたなど異常な事態だ。血鬼術の可能性もあるし、そも善逸は花吐き病と言った。何か心当たりがあるのかもしれない。
「俺もいくぞ!」
「いや、お前は帰れよ。禰豆子ちゃん待ってるだろ」
「どうせ帰っても善逸が心配ですぐに蝶屋敷に行くことになる。無駄を省きたい。俺もついて行くぞ!!」
そう言う炭治郎に、善逸は困ったように笑うと懐からすやすやと眠っていた雀を取り出した。
「チュン太郎、お昼寝してるとこ悪いけどさぁ。禰豆子ちゃんに蝶屋敷に寄って行くって連絡してくれる?あ、怪我はないってちゃんと言ってね」
「チュン・・・・・・チュンチュン!」
寝惚け眼だったチュン太郎はパチパチと瞬くと、小さな羽を羽ばたかせて飛んで行った。これで禰豆子が炭治郎が帰らぬとヤキモキすることもないだろう。
「よし!じゃあ急いで行こう!・・・・・・善逸、走れるか?」
「大丈夫。ほら、行こう」
そう言って駆け出した2人は2刻もしない内に蝶屋敷に着いた。ここの主人であった胡蝶しのぶが亡き今は継子であった栗花落カナヲが屋敷を管理し、病院部分はしのぶから看護の手ほどきを受けていた神崎アオイが取り仕切っていた。
炭治郎と善逸はすぐにアオイに面会すると、診察台に拾い集めたたんぽの花を見せた。もちろんこの花が善逸の体から出てきたことも告げる。
「えーっと、これって花吐き病かなぁ?」
青い顔で震えながら言う善逸に、アオイもまた顔色を悪くしてたんぽぽの花を見つめている。口から出てきた、たんぽぽの花。アオイは額に手を当てるとゆっくりと頷いた。
「間違い無いと思います。これは通称『花吐き病』・・・正式には『嘔吐中枢花被性疾患』です。症状は明確で口から花を吐く。これだけです。そして吐き出された花に触れると感染します。炭治郎さんは触ってませんね?」
アオイの言葉に炭治郎は頷く。そして感染するという言葉にだから善逸は花に触れようとした自分を蹴飛ばしたのだと理解する。
「そ、そんな病があるのか・・・・・・。善逸は知っていたんだな」
「・・・・・・まあね。俺の育ちは牛込神楽坂だから・・・まあ、色々あんのよ。だから風の噂で花吐いて死んじまったってのはよく聞いたの」
なるほど。と、そう思った炭治郎だが善逸の言葉に聞き逃せないものがあった。思わず善逸の肩を掴んで揺さぶりをかける。
「善逸!!」
「おわっ!なんだよ!?」
「この病は死んでしまうのか!?」
炭治郎までもが真っ青になっている。善逸は炭治郎に何も返せずにアオイの方を見た。それに倣い、炭治郎もアオイの方を振り向く。2人に見つめられたアオイはもじもじと前掛けをいじると諦めたように言った。
「・・・・・・花を吐く頻度があがり、体力を消耗しすぎると衰弱で死ぬ場合があります。衰弱でなくとも、眠る時に花を吐き戻し喉に詰まらせて死亡という事例も多いです」
アオイの返答に炭治郎は言葉をなくす。善逸は震えてはいるが泣き喚くこともなく、じっとたんぽぽの花を見ている。いつもと違い静か過ぎるその様子に恐怖が積もる。炭治郎は何を考えているんだと思うように善逸の肩をさらに強く握った。
「おい!痛いって!」
「あ・・・ごめん」
善逸に涙目で訴えられて炭治郎はようやっと手を離した。何を言うべきか分からぬ炭治郎は行き場のない手を彷徨わせてゆっくりと下す。その様を見ていた善逸は諦めたのようなため息を吐くと自嘲気味に笑った。
「はあああああ。マジかよ。俺の人生こんなところで終わりかよ。鬼に殺されるよりはマシかも知んないけど、いや、むしろ死に方としては粋な方かなぁ?花吐き病で死ぬなんて浪漫溢れる死に方だよね」
「何を言ってるんだ!死ぬとは決まってないだろう!治療をちゃんとすれば治るはずだ!」
「・・・・・・いやいや、治らんよ」
呆れたように言う善逸に炭治郎は目の前がカッと赤くなる。善逸は逃げはしても諦めない男だ。そんな男が病に負けるなど到底認められない。
「だからーー!」
「炭治郎さん」
世捨て人のような物言いをするなと一喝しようとした炭治郎にアオイが待ったを掛けた。アオイは目を潤ませて泣かないようにしているようだった。その姿に、花吐き病をよくも知らない炭治郎は最悪の想像をする。
「花吐き病には根本を治療する方法が見つかってないんです。花の吐き戻しを抑える程度しか、できません。そしてその抑制もだんだんと効かなくなっていきます」
「嘘だろう・・・・・・?」
そうだと言うのなら、善逸はいつか花に殺されると言うことなのかと炭治郎は絶望的な気持ちになる。そんな筈はない。善逸は幸せになるべき男だ。こんなに頑張って恐怖を乗り越えて鬼を狩る、自分を捨ててまで庇う心優しき男が若い身で病で苦しんで死ぬなんてあんまりだ。
「本当に!本当に治す方法はないのか!?ひとつも!?そもそも、なんで・・・・・・善逸が・・・・・・?」
禰豆子によく花を贈る男だ。もしやその中に花吐き病に罹ったものの花が混ざっていたのか?いや、善逸は野に咲く花を摘んでくるのがもっぱらだ。そんなわけはないだろう。じゃないと花をもらった禰豆子も罹ってしまっているだろう。ぐるぐると考え込む炭治郎にアオイは言いづらそうに口を開く。
「花吐き病は片想いを拗らせると発症する病です。・・・・・・治療法はありませんが、片想いが叶い、両想いになると白銀の百合を吐き出して完治するそうです・・・・・・」
「片想い・・・・・・。両想いになると・・・・・・完治・・・・・・」
「なあ?俺には無理そうだろう?」
そう言って困ったように笑う善逸に炭治郎は涙を溢しそうになった。なぜなら、人に戻った禰豆子が善逸の求婚を断ったのはふた月ほど前のことであったからだ。
その時まで炭治郎は禰豆子は善逸と夫婦になるだろうと思っていたし、禰豆子を任せられるのは善逸以外にいないと思っていた。だって鬼となった禰豆子を何の迷いも葛藤もなく自然に女の子として愛でて慈しむ男は、今までもこれからも我妻善逸ただ1人と分かっていたからだ。
だから善逸が禰豆子に求婚すると炭治郎に言った時も炭治郎は「禰豆子が望むなら構わない」と返した。善逸と禰豆子が夫婦となれば、この一等大切な親友と家族になるのかと炭治郎は嬉しく思ったものだが、いくら経っても結果を報告しにこない2人に焦れて、任務先で会った善逸に事の次第を問うたのだ。
結果として、善逸は禰豆子に振られたらしい。
「善逸さんはとても大切な人だけど、絶対にあなたとだけは結婚できない。夫婦になれない。でも世界で2番目に好きですよ・・・・・・って言われた」
善逸は遠い目をしながらそう言った。炭治郎は「そうか・・・」と一言だけしかいえなかった。禰豆子に善逸への気がないのならば仕方がない。善逸もそのことをよく分かっているようで、以降も禰豆子に「可愛い!」とか「本当に天女みたい!」とか花やお菓子の贈り物をしても結婚してと言うことはなくなった。その手を引いて散歩に出かけることもなくなった。ただ、兄の友人として友人の妹を慈しむだけに留まっていた。
つまりは善逸はもう片想いに脈がないのだ。なぜなら既に振られてしまっているからだ。炭治郎はそのことに思い至ると今度こそボロリと泣いた。嘘だろうと叫びたいが、叫んで泣きたいのは善逸だろう。
しかしそれをしないのは善逸が禰豆子を慮って泣き言も縋り付くこともしないのだ。だって善逸だ。優しすぎる善逸だ。禰豆子への想いを拗らせて死にそうだと言うことを大きな騒ぎにしたがるわけがない。そんなことが禰豆子に知らられば、禰豆子は一生気に病むだろう。
炭治郎の考えはほんの少し間違いがあったが、善逸は禰豆子を慮っていたのは間違いなかった。ゆえにその日その時の蝶屋敷の診療室で、善逸は炭治郎とアオイに頭を下げた。
「どうか、誰にも知られないようにしてほしい」
頭を下げた善逸はもう震えていなかった。その姿が岩柱の柱稽古の時の善逸に似ていて、炭治郎は焦った。この後どこぞへと消えてしまうかもしれないという不安があった。ゆえに炭治郎は善逸に条件をつける。
必ず目の届く範囲、連絡の取れるようにすること。さもなくば知り合い全員に病の善逸が逃亡したと伝えて全力で探すと脅せばこれに善逸は心底迷惑そうな顔をしたが、しぶしぶ頷いてくれた。
「なんでそんな脅すのよ」
「すまん。善逸が信用ならなくて・・・・・・」
「信用ならなくて!?すみませんねぇ!!ロクでもない人間で!!」
「いや、違うぞ?そういう意味じゃなくて・・・・・・」
善逸はキイキイ言って騒いでいたが、その後に咽せこんでまたたんぽぽの花を吐いた。ポロポロと落ちる花に炭治郎はやはりこれは夢ではないのだと絶望的な気持ちになった。
****
善逸は毎日3回、朝昼晩に吐き気止めを飲むのが日課になった。そして通い寝床を蝶屋敷や竈門家ではなく元音柱の屋敷に変えた。さらに全集中・常中も気を遣って気を遣って、ようやっと吐き気を起こしにくい流れのものに変えられた。これもそれもあれも、善逸が片想いを拗らせて花吐き病を発症したせいだった。
善逸は単独任務の後に宇髄に借り受けているド派手な鎹鴉に報告を託した。病に侵されている善逸は鎹鴉を2羽使うように上から申し付けられている。ゆえに1羽はチュン太郎、もう1羽は宇髄のド派手鴉である。
善逸は宇髄のを借り受けていいのか甚だ疑問であったが、当の主人は引退した身だと使うことあんまりないからとのことだった。なんでも重要な連絡は基本、向こうから来るとかなんとか。何かあれば自分で走るとまで言われてしまえば善逸はもう文句は言えない。なぜなら宇髄からも善逸を心配する音が聞こえるからだった。
要するに善逸の病のことを知る人はこぞって善逸を心配していた。知っている人間は僅かで、炭治郎と伊之助とアオイ、そして宇髄と嫁御達、最後にお館様だ。
当然ながら禰豆子には知らせていない。そんなことになれば禰豆子は気を揉むことになると善逸はよく分かっていた。なんなら風評被害を被ることも分かっていた。そう、風評被害だ。
我妻善逸は竈門禰豆子に振られて死んだのだという風評被害だ。
これがなぜ風評被害かと言えば、そもそもとして善逸は禰豆子に片想いを拗らせていないからの一言に尽きる。
遡ることふた月半前、善逸は禰豆子に求婚をした。彼女と彼女の兄と家族になりたかったからだ。共にいる約束が欲しかったのだ。ここに帰ってきてもいいという保証が欲しかったのだ。
そんな善逸の欲を禰豆子には看破されたのだ。むしろ善逸すら把握しきれていなかった欲なのに禰豆子は見事に見抜いたのだ。善逸が、禰豆子を大切にしながらもそれは情欲を一切含まぬ愛であると見抜いたのだ。
指摘された善逸は驚いた。禰豆子に私を孕ませられぬだろうと言われて、それはその通りだと思ったのだ。無理を通せば抱けぬこともなかろうが、そも無理を通して抱く時点でお話にならない。
善逸にとって禰豆子は大切で綺麗で汚すものではなく慈しむものだった。言い方は悪いが、自らの欲望の捌け口となることはあり得なかったのだ。
禰豆子は世界で2番目に善逸が好きだと言った。1位は兄であり、ちなみに1位も2位も暫定らしい。恐らくこれから禰豆子が誰か特別な人に恋をすればその人が1位となり、暫定1位と2位は繰り下がるのだろう。その人との間に子でも設ければさらに順位は下がっていくのが伺える。
まあ、つまり善逸はこっ酷く振られたのだ。しかし納得のいく理由でもあり、そもそも求婚自体がお粗末だったともいえる。善逸は逆にすっきりとした心地で禰豆子と新たな関係を結ぶことができた。
要するに親友の妹と兄の親友という関係だ。それでも禰豆子は善逸にとって特別な女の子であった。何に変えても守ってあげたいと思う女の子だった。
だがこのやり取りを知っているのは善逸と禰豆子の2人だけである。しかし善逸が禰豆子に熱をあげていたのは周知の事実だった。その為、善逸が花吐き病で死んだとなれば禰豆子に振られたからだろうと皆が思ってしまうだろう。そうして人の口に戸はたてれないのだからその噂はいつか禰豆子を追い詰めるだろう。そんなことはあってはいけないのだ。善逸はそう思っている。
我妻善逸は竈門禰豆子に片想いを拗らせてはいない。つまりは他の人に恋をして片想いを拗らせているのだ。だがそれを周知することができない。なぜならーーー。
「もおおおおお!俺は一体!誰に片想いしてんだよおおおおお!!」
その通りだった。善逸はいま、いったい、誰に恋をしているのか皆目見当がついていないのだった。善逸は頭を抱えて地面を転がるが、カサカサと枯れ葉が踏まれる音が響き、そして己の血脈は愛も変わらず音が近過ぎで逆に聞こえない。そのため善逸は会う人会う人、誰に反応が一番出るかも自己分析できやしないのだ。
「誰に恋してるかも分からずに死ぬなんて最っ悪だわ!!こんなことってあるぅ!?嘘でしょ!?夢でしょ!?やだやだやだやだーーー!!助けてよ炭治郎おおおおおおお!!」
ゴロゴロと転がり5メートルほど移動して止まったのち、善逸は大きく溜息をついた。喉をこみ上げる嘔吐感に善逸は呼吸を巡らせて実に『上手く』吐き出した。コロリコロリと横たわったまま吐き出される花は相変わらずたんぽぽだ。
「なんでいつもたんぽぽなんだろ。俺の頭が黄色いから?・・・はーああ。どっこいしょ。さて、お腹空いたし帰るとしますか・・・」
木の上にいるチュン太郎を呼び寄せて懐にしまう。零れた花はむんずと掴んで花用に用意した巾着に粗雑に放り込む。あとで燃やしてしまわねば要らぬ被害が出てしまうかもしれない。
「しかしまあ、恋に死ぬなんて本当に浪漫ちっくですこと」
へっと吐き捨てるように言って善逸は歩き出した。誰とも知らぬ相手への恋で死ぬなんて間抜けだ。善逸は微塵も死にたくもないが、相手がわからねば両想いにもなれないし玉砕した後の恋を捨てるということもできない。しかし相手が分かっていないのに拗らせているとはこれいかに。もしや分かってないのが拗らせている証拠なのだろうか。善逸はけふけふと上手に花を出しながら仮初の家路に向かう。
このまま恋で死ねば、ついぞ本当の家路につくこともないのかと善逸は凹んだ。
善逸とて諦めたいわけではない。しかし方策がないのも確かだった。善逸にできるのは吐き気止めを飲むことと、喉につまらせぬように上手に花を吐くことだけだ。まだ衰弱もしていない。食べ物の摂取も睡眠も問題ない。むしろ生気を取られて動けなくならぬようにとより多い、滋養のつくものを摂取させてもらえている。
「恋で死んだなんて、爺ちゃんに呆れられちゃうよー」
鬼になって斬られて死ぬよりずっとマシであろうが、身を焦がしてもいない恋で死ぬのはお笑い種だ。草葉の陰で獪岳も大爆笑のことだろう。
鬼舞辻がいなくなり、残念ながら鬼は全て消えたわけではないが数は減った。少なくとも鬼舞辻のように新たな鬼を生み出す能力を持つ鬼がいないのだからこのまま鬼を発見次第、倒すのを繰り返していけばいずれいなくなるだろう。
柱も減ってしまったが強い人たちが残っているし、炭治郎や伊之助、カナヲちゃんいる。対して有力な強さを持つ鬼達は先の決戦にてほぼ倒されてしまっている。善逸がよく向かう単独任務でもそこまでの強さの鬼はいない。恐ろしいことには変わりはないが、善逸が意識を落とすことなく戦えているのがその証左だろう。
善逸は雷一門の汚名を濯ぐために鬼をより多く倒さなければならない。周りがどうのというよりも、善逸がそうするべきだと決めたからだ。
「ああ?・・・・・・禰豆子ちゃんや炭治郎に会いたいよ?」
よく通っていた竈門家には行けない。善逸は寂しいなぁと思いながらも宇髄の家に伊之助が来ていないかなと期待しながら走り出した。
****
「発症から半年、初月は1日に1回程度の吐き気がいまは4?5回ってところだな。回数は増えてきてやがるし、食事の量は減ってきた。確実に生気が失われていってるな」
「そうですか・・・・・・」
宇髄の屋敷にて、炭治郎は善逸の現状に憂いていた。花吐き病は早ければひと月で逝ってしまうものらしく、日がな花を吐き出すようになるらしい。それを思えば、善逸は吐き気止めと呼吸の併用で進行をだいぶ食い止めている。
しかしその吐き気止めも慣れというものがあり、アオイは手を替え品を替え新しいものを作り続けているが、同時に眠気や頭痛という副作用もでてきている。これ以上の投薬を続けてもいずれ打ち止めが来る。となると呼吸のみで堪えることになるが、そうなると雷の呼吸は下半身に重きを置いた呼吸だ。実戦の際に不都合が出るとのことで善逸は任務を減らさねばならない。だが善逸はそれを頑なに拒否しており、どうせいずれ死ぬのならばより多くの任務をこなすべきだと引かない。
「今のところは任務に支障があるほどの衰弱は見せてねぇな。けどもう薬が効かなくなってきて、そっから回数が増えてやがる。・・・・・・おそらく、これからどんどんと衰弱が進むだろう」
難しい顔をする宇髄に炭治郎は唇を噛んだ。アオイも宇髄も、ありがたいことにお館様も何か治癒させる方法はないかと探しているが、今のところ何もない。対処療法しかなく、それも延命に繋げるものでしかない。根治治療には程遠い。根治させるためには善逸の片想い・・・・・・つまり禰豆子と結ばれれば良いのだが人の心にを縛ることも強制させることもできないのだ。炭治郎は自らに出来ることがないと嘆いた。親友の窮地にもなんの手も伸ばせないのが口惜しい。このまま善逸を失うかもしれないと思うも恐ろしくて堪らない。
「・・・・・・つーかよ、お前も痩せてってねぇか?」
「え?ああ、その・・・ここ半年で2キロほど・・・・・・」
「何やってんだよ!お前まで参っちまってどうすんだ!」
「面目ありません・・・・・・」
宇髄の指摘のように、炭治郎はこの半年で自身の体重を2キロばかり減らしてしまった。間違いなく善逸への心配ゆえだ。剣士として身体を減らすのは良くないことだというのはよくよく分かっている。なぜなら技の威力に影響してくるからだ。けれど竈門家に善逸が来なくなり、笑い声を聞くこともなく、宇髄の家に顔を出すたびに少しずつやつれていく善逸を見て食欲など出るわけがない。
禰豆子は家にやって来なくなった善逸と、食欲があがらない炭治郎に疑念の目を向けている。禰豆子には善逸は長期任務に出ていてここには来られないのだと嘘が下手な炭治郎の代わりに伊之助が説明してくれた。だから禰豆子はそうだと信じている筈だった。少なくとも炭治郎の中ではそうなっている。
炭治郎とて善逸が禰豆子への恋を拗らせて死に向かっているなど言いたくもないのだ。心優しい禰豆子はきっと衝撃を受けるだろう。気落ちをし、自分のせいだと思うだろう。一生、引きずるかもしれない。兄としては妹の未来が暗く落ち込むことなど容認はできない。
しかしとなれば、善逸は禰豆子への恋を抱えてひとり死んでいくということになる。恋を向けた相手に死ぬほどの気持ちを抱えていることを知られることすらなく、死んでいくのだ。そんなのはやりきれない。切ない。悲しい。
恐らく善逸が花に埋もれて死んだなら、任務にて死亡とされるのだろう。鬼殺隊は死亡の理由など簡単に説明がつく生業なのだから。
炭治郎が不安とやり切れなさに胸を押さえていると、ふわりと花の香りが漂ってきた。匂いに顔を上げると縁側から草臥れた様子の善逸が現れた。
「はあー。ただいまーって炭治郎!また来てくれたんだ!」
善逸は炭治郎の姿を見るとパッと笑った。纏う匂いもあいまり、まるで善逸自身がたんぽぽの花のようだ。しかし善逸の?のコケ、濃くなった隈、青白い肌に病魔に蝕まれているのを感じる。しかし病人の匂いはしない。善逸からはただ、濃いたんぽぽの香りがするばかりだ。
「ああ。・・・・・・調子はどうだ?」
「調子?いいわけないだろ!?あーもう!任務を入れて欲しいって言ったのは俺だけどこんなに連続でいれる!?恐怖が断続的に続くのよ!!任務!1日休み!任務!1日休み!任務!!1日休みいいいいい!!はああああああ!?安心と恐怖が交互に襲いかかるのよ!!やってらんねーわ!!」
たんじろおおおお!と涙を零しながら抱きついてくる善逸を受け止めて慣れた手つきで頭を撫でる。反射のように行われる己の反応に、炭治郎はこれが後どれだけやれるのかと不安になる。
善逸からは恐怖というよりも心配と諦念の匂いが強い。こうして騒いで炭治郎に縋るのも善逸なりに『いつも通り』を行うためだろう。そうするのは必要以上に炭治郎が悲しまないようにする為だ。炭治郎の心配を和らげようとするためだ。
「はあ、まあ人手足りないんだからしょーがないけどさぁ。ほら、炭治郎。もうそろそろ暗くなるよ。お帰りよ。禰豆子ちゃんが待ってるぞ」
そう言って善逸は炭治郎を笑って追い出した。炭治郎としてはこのままもっと傍にいたかったが夜に屋敷に禰豆子を1人きりにするのも恐ろしいし、そんなことを善逸が許すはずがない。
炭治郎は結局、大した時間を善逸と過ごすこともできずに帰途へと着いた。後ろ髪はひかれっぱなしであった。
そしてその晩に善逸は大量に花を吐いて、とうとう床に伏せるようなる。
「禰豆子、一生のお願いだ。善逸と夫婦になってほしい」
深夜の竈門家で目の下に隈を作った炭治郎が妹である禰豆子の寝床に訪れていた。夜半の突然の兄の訪問に禰豆子は不思議に思いながらも招き入れる。炭治郎は禰豆子同様に寝巻き姿で、生気のない顔で畳の上に正座すると禰豆子が何を問いかける間もなく冒頭の台詞を言って頭を下げた。
予想だにしない兄の奇行に禰豆子は驚くばかりだ。この数ヶ月、兄である炭治郎の様子がおかしいのは気がついてはいた。それが善逸が絡んでいることも禰豆子は看破していた。なぜなら善逸が竈門家を訪れなくなって半年だ。兄と何かあったのかもしれないと思っていたが、禰豆子は2人を信じていたので介入はしてこなかった。
しかしながら目の前で頭を下げる炭治郎に、禰豆子はどうやらくるところまで来てしまったらしいと頭が痛い。何をとち狂って善逸と結婚しろというのか。
「・・・・・・お兄ちゃん。何があったのか知らないけど、私は善逸さんとは結婚しないわ。お兄ちゃんには言ってなかったけど、もう随分前に求婚を受けて断っているのよ。善逸さんも納得していたわ」
たがら顔をあげてと禰豆子が言うよりも前に炭治郎は顔を上げた。その顔は置いていかれた子供のようで、炭治郎がとても追い詰められているのが分かる。本当に善逸と何があったのかと禰豆子は不思議に思った。
喧嘩をしたとしてもすぐに仲直りできる2人だ。余程、面倒に拗れたのだろうか?しかし善逸が拗れたとしても炭治郎は押せ押せに善逸を捕まえに行くだろう。その炭治郎がこんなにも様子がおかしい。これは異常だろう。
「禰豆子に善逸が気持ちがないのは分かっている・・・・・・。だが、だが、本当にダメなのか!?善逸ほど禰豆子を想ってくれる男もいないんだぞ!?あれだけ優しい男もそうはいない!情けないところもあるが・・・・・・他人の為なら身を張れる男だ!逃げたとしても最後は諦めない男だ!やらねばならぬことは遠回りでも必ず成し遂げる男だ!!見た目だって泣き虫という点はあるが、平素は悪くない顔立ちだろう?大きな目だって愛らしいし、髪だって本人は悪目立ちすると卑下するが、陽や月光に当たれば煌めいていつまでだって見つめていられる。霹靂一閃を放った際など余韻で残る金糸の美しさは例えようがないほとだ!それに何より善逸からは馬鹿みたいに優しい匂いがする。出会って間もない俺の何気ない言葉を聞いて、身を挺してお前を守ってくれた何よりも優しい男なんだ!禰豆子、本当にダメなのか?善逸を特別に好いてはくれないのか?・・・・・・人の心は縛れないし強制もできないのは分かっている。だが、本当に万の一つも善逸に想いを寄せてやれないだろうか!?なあ、禰豆子!」
「・・・・・・できないわ」
禰豆子の言葉に炭治郎は絶望に暮れた顔をした。ごっそりと色をなくしたその顔は幽鬼のようでほんの少し恐ろしかった。しかしそんなことよりも禰豆子は炭治郎に指摘しなければならないことがある。言わなければならないことがある。禰豆子が善逸を一番にできない理由をだ。
「・・・・・・できないわよ、お兄ちゃん。私にはできない。お兄ちゃんが日本で一番好きで愛してる人のお嫁さんになるなんて、私にはできない。お兄ちゃんから善逸さんを取り上げるなんてできないのよ。・・・・・・善逸さんと結婚したいのは私じゃない。お兄ちゃんでしょ?」
禰豆子のその言葉に炭治郎は目から鱗が落ちた。
****
「ゲホッゲホッ、オエッ!・・・・・・ああ、しんどいわ・・・・・・」
「薬飲めよ」
「それが効かないのよ。はー・・・・・・潮時かねぇ」
「諦めてんじゃねえ!それでと俺様の子分か!?」
がなる伊之助に善逸は顔を顰めた。近距離での大声は勘弁してほしいと思うが、伊之助からは不安の音が大きくしているので文句は言わなかった。伊之助もまあ、皮膚から感じとっているのだろう。善逸の死期が近づいているという事実を。
善逸が床についてはや4日。花を吐く頻度、量は格段に上がり食事もままならなくなった。食べると花と一緒に吐いてしまうからだ。花と一緒に嘔吐物まで出てくるのは酷い絵面だった。仕方がなく桶を常備する羽目になった。しかもその片付けを誰かにやらせるのは憚られるのでまだ自分でやっているが、それも時間の問題かもしれない。今だって大量のたんぽぽが善逸の布団には散らばっていて、万が一にも触れぬようにと伊之助は遠ざけて座らせている。
「だってもーしょーがないじゃん。鬼も倒しきってないのに一抜けするのは悪いけどさぁ。ゴホッゴホッオエッ!・・・・・・ふー。オエッ!!・・・・・・はぁー。俺も死にたかないけどさぁ、もうこんなんなのよ」
疲れたように笑う善逸に伊之助は歯を食いしばった。善逸の言うように死にたくなどないのだろう。伊之助だってこの世にはどうにもならんことがあるくらい分かっている。鬼殺隊の人間が鬼と戦って必ず生き残るといえないように、どうにもならんことはならんのだ。それを伊之助はたくさん見て来た。
炭治郎と善逸が強いと知っているが、万が一もあると心の何処かではいつも思っている。しかし、しかし・・・・・・。
「病になんか負けてんじゃねえよ!馬鹿善逸!!」
涙が滲んだような伊之助の声に、善逸は困ったように笑った。そんな顔して笑わないで欲しいと伊之助は思う。どうせなら死にたくないと助けてとみっともなく泣き喚いて欲しい。けれど善逸はそれをしない。助けてくれと喚いて死んだら、伊之助たちに助けられなかったという事実を残すからだ。
伊之助は善逸を助けたい。だからどの道助けられなかったと思うに決まっているのに、善逸はよく分からない遠慮をするのだ。
死に向かっているのに、我慢などして欲しくはない。伊之助はそう思うが善逸のこの悪癖は一朝一夕では直らない。何しろいずれ死んでしまうと分かっているのに善逸が心配するのは残されたものたちのことばかりだ。特に禰豆子と、禰豆子の兄である炭治郎を気遣っている。
禰豆子は善逸が片恋の病で死に瀕しているなど知りはしない。死んでも任務で死んだと伝えられるから悲しみはしても己のせいと責めることはない。善逸が一番心配しているのは炭治郎だ。
己の妹への恋心が原因で親友が死ぬのだ。しかもその親友は善逸だ。伊之助は炭治郎が善逸を一等、特別な人間だと位置付けているのを知っていた。
鼓屋敷にて初めて禰豆子が入った箱を見て、鬼だ!殺さねばと構えたときに善逸が立ち塞がったのをよく覚えている。最初はなんだコイツはと思っていたが、炭治郎と禰豆子、そして善逸と仲を深めるにつれて善逸という存在が炭治郎にとってどれだけ得難くて大切で、救いを与えた存在かを理解していった。
善逸は馬鹿な程にお人好しで、価値観がぶっ壊れていて、それが正しく炭治郎を救ったのだ。だから伊之助は知っている。善逸が死ねば、炭治郎もいなくなるのだ。体と精神がそこに変わらずあったとしても、伊之助が可愛がっていた子分としての炭治郎は死ぬだろう。心を半分持ってかれてはさしもの炭治郎も壊れてしまう。炭治郎は生きながら死ぬのだ。そのことを善逸は分かっていない。
だが結局は伊之助には何もできない。現に目の前で花を吐きだす善逸を黙って見つめるしかできないのだ。
もうさほど長くはないだろう。炭治郎にも早く来るようにと鴉を飛ばした。こっから先は悪いが任務に出る気はない。もはや伊之助には泣き虫の子分が寂しがらないように死ぬまでの間、側にいるしかできないのだから。
「善逸、入るぞ」
聞こえた声に伊之助も善逸も振り返る。静かに部屋に入ってきた人物は炭治郎であり、それは掛けられた声から分かっていたがその表情を見て伊之助も善逸も固まった。
とんでもなく目が座っている。
「た、炭治郎?なんかもの凄い音がしてるんだけど・・・・・・?」
「伊之助、悪いが席を外してくれないか?」
「え?無視するの?」
「・・・・・・いいぜ。終わったら声かけろよ」
「え!?伊之助行っちゃうの!?ヤダヤダ!なんか炭治郎怖いんだけど!2人きりにしないでえええええ!!」
善逸の叫びも虚しく、伊之助は部屋を出て行った。炭治郎と2人きりにされた善逸はギギギという軋むかのような動きでゆっくりと炭治郎に顔を向けた。炭治郎は変わらずに目が座っており、ゆうるりと笑みを浮かべている。
「ええと?」
「座ってもいいか?」
「ど、どうぞ」
善逸が許可を出して布団の中で正座をし直すと、炭治郎は大股で善逸の前に進んで座った。その距離は膝と膝が触れ合うまで10センチというほどの距離だ。ひたすら近い。というか布団に乗り上げている。
「えっ?近くない?」
「善逸、俺はようやく気がついたんだ」
「無視ですか?」
「俺がどうしてもお前を死なせたくない理由にだ」
「聞いてないねぇー」
こちらを無視して話し始めた炭治郎はもう好きにさせる他ない。善逸は溜息をつきながら傾聴する構えに入った。
「お前に出会って2年余り、気がつくのが本当に遅かったと思う。分かればこんなにもすとんと心にはまることなのに俺は無知で頭が固かった。禰豆子と話し合わなければもっと気付くのに時間が掛かっていただろう。・・・恐ろしいがそのときにはお前がいなかったかもしれない。病のことは全くいいことだと思えないが、今回のことがなければ俺はずっと気がつかなかった可能性すらある」
うんうんと頷きながら言う炭治郎だが、善逸はさっぱり話の内容が分からない。何に気がついたというのか。核心をつく単語が何も出てこない。
「え?なんの話?禰豆子ちゃんと何の話したの?」
「ん?ああ、禰豆子に善逸と夫婦になって欲しいと頭を下げたんだ」
「はあ!?何言ってんの!?するわけないじゃん!」
「禰豆子にもそう言われて断られてしまった」
「振られるのは1回で十分なのに!なに2回もさせてんだよ!!」
うわんと泣く善逸に炭治郎が背中を撫でる。じんわりと温かい、人よりも高い体温に善逸の涙腺はさらに緩んだ。こうやって慰めてくれるのもあとどれだけなのかと不安が募る。覚悟はとうにしているが、それでも別離の恐怖はあるのだ。
「・・・死ぬのが怖いんだな、善逸」
「いや当たり前だろ」
「そうだよな。俺もお前が死ぬのは怖いよ。自分が死ぬよりも誰が死ぬよりも怖いよ」
どしんっと何か重たいものが落ちるような音に善逸は泣いていた顔を上げた。炭治郎はじっと善逸を見ていて、その目は善逸を見ているが見ていない。何かを待っている目だった。
「・・・・・・たんじろ、ウッ、ゲホッゲホッ!アッ・・・カハッ・・・んっ!」
こみ上げてきた嘔吐感に花を吐くと分かった。それも大量だ。善逸は呼吸を何とか使おうとするが、花の量が多くなってから巡らせるのが難しくなってきた。とにかく詰まらせずに吐き切らねばと喉を動かしているといつの間にか眼前に炭治郎の顔があった。
短い時の筈なのに、善逸には炭治郎が顔を寄せてくるのがことさらゆっくりに見える。炭治郎は鼻が触れ合うほど善逸に顔を寄せてるとそのまま善逸の唇に噛み付いた。善逸が口付けされたのだと気付いた時には炭治郎の舌が善逸の口内を侵し、上顎を刺激してくる。花が出る。
「んっ!んんっ!!」
花を吐くのにと一気に思考が戻った善逸が炭治郎を引き剥がそうとするがガッチリと抱きしめられていて叶わない。堪えようとした善逸であるが、そんなことは土台無理で、ごぼりと口内
に上がってきた花は善逸と繋がっている炭治郎の口いっぱいに吐き出されていく。それでも収まりきらない花はようやっと炭治郎が口を離してくれたことでボトボトと2人の間に落ちた。
炭治郎は口いっぱいのたんぽぽの花を嬉しそうな顔で噛み砕いて、咀嚼しようとしている。
「何やってんだお前!!馬鹿野郎!!吐き出せ!!」
善逸の怒号が屋敷中に響き渡った。善逸が炭治郎を引っ掴むが炭治郎はムンっとした顔で花を噛み砕くとごくんと大きく喉を動かして飲み込んだ。
「ああああああ!!お前!飲み込みやがった!!」
「そもそも触れた時点で感染するから、吐き出してても感染はもうしてると思うぞ」
「そりゃそうだけど!炭治郎、お前!本当になにしてんだお前えええ!!」
ガクガク揺さぶってくる善逸は怒りの顔からだんだんと泣きそうな顔になっていく。その顔に炭治郎は嬉しさを感じたのだから、そうとうに善逸にやられている。善逸が己の心配をして、死を感じて悲しんでくれるのが嬉しい。
「落ち着け善逸。これでいいんだ」
「よくねぇわ!どこがいいのよ!」
「いいんだよ。これで俺も恋で死ねる。それもお前からの貰った恋の病でだ」
炭治郎が笑ってそう言えば、善逸はあんぐりと口を開けた。その不細工な顔もいまの炭治郎には輝いて見える。炭治郎はふふっと笑うと善逸の額、頬、そして唇に降らせるように口付けをした。
「勘違いしないでくれ。俺は死ぬつもりはない。両想いになれば完治するんだろう?だから俺は自分の好いた人と心を通わせてみせるよ」
「えっ?あ?なに!?本当によく分かんないわ!!好きな人と両想いになるのにわざわざ花吐き病になる必要なくない!?なんでそんな叶うか叶わないかを生か死かにわざわざするのよ!?」
「叶わなかったら、好きな人と同じ病で死にたいからかな」
「はあ!?同じ病って・・・・・・え?」
善逸は花吐き病も知らなかった炭治郎に、花吐き病で苦しんでる知り合いがどれほどいるのかと思い至った。善逸は周りの状況など詳しくも知らないが、花吐き病か珍しい奇病だということは分かっている。そうホイホイとあるものではない。ならば、炭治郎がいう好きな人とは・・・・・・。
「お前が好きだよ善逸。だから俺と両想いになって欲しい」
「は、へ・・・・・・?」
「お前が禰豆子を好きなのは知っている。けど禰豆子への恋を忘れて、これから俺を好きになって欲しい。考えたんだ。両想いにならなければ花吐き病は死ぬ病なのだろう?ならばその恋を上回る恋をして、両想いになれば治るじゃないかって」
何それそんなので治るのと善逸は思ったが、炭治郎の顔は真剣だった。真っ直ぐに善逸を見て、音が、炭治郎の全身から善逸が愛しいとキラキラして音が鳴っている。その音に善逸はドキドキと胸が高鳴るのを感じた。
「・・・・・・だから善逸、俺を好きになってくれ。俺もお前に好いてもらえるように努力する。これから先も善逸と一緒に幸せになりたいから。禰豆子じゃなく、俺を選んでくれ」
そう言われて、善逸は炭治郎にぎゅうと抱きしめられた。
「オエッ」
「ケホッ」
コロリコロリ。
2つの白銀の百合がこぼれ落ちた。
****
「全く!人騒がせな話ですね!!」
「面目ありません」
プンプンと怒る禰豆子に善逸は土下座した。目の前には彼女の好物である金平糖の詰め合わせを用意してあり、禰豆子は怒りながらもウキウキとした様子で金平糖の袋の口を開けている。
炭治郎の告白を受けた善逸は、あっさりと白銀の百合を吐いた。もちろん善逸から病を貰っていた炭治郎も恋が叶ったので百合を吐いたが、初めて吐くのが百合とは凄いことだ。まあ、罹ってから迅速に完治したのでしょうがないのだが。
炭治郎は白銀の百合をあっさりと吐いた善逸に「チョロすぎやしないか善逸!?禰豆子への想いはそんな簡単に鞍替えできるものだったのか!?」と盛大に怒った。理不尽と思いながらも、善逸は諸々の事情を白状した。つまりは禰豆子への片想いはしておらず、善逸自身が誰を好きか把握していなかったことをだ。
最初、炭治郎は呆れたように聞いていたが自分も禰豆子に指摘されて気がついたのだから同じだと笑った。そして炭治郎の告白を受けて善逸が白銀の百合を吐いたということは善逸が好いていたのは己だったのだと飛び上がって喜んだ。善逸はというと怒涛の展開に思考がついていっていない。自分は炭治郎に片想いしていたのか!?というところからであった。
「私を除け者にするからですよ!善逸さんが病気になって死にそうだっていうのに、私に教えてくれないなんて酷いにも程があります!」
「すみません」
「私が知ってたらもっときっと早く解決してました!!お兄ちゃんがずーっと善逸さんを好きなのも、善逸さんが私じゃなくてお兄ちゃんのことを好きなのも、ちゃーんと私は分かってたんですからね!!」
「えっ!?そうなの!?炭治郎だけじゃなくて俺の気持ちも分かってたの!?俺も分かってなかったのに!?」
「分かってましたよ!私のこと女として見れないのに結婚したいなんて、お兄ちゃんと一緒にいたい、家族になりたいっていう以外に何があるんですか!!本当に失礼な話ですよ!!」
「本当に申し訳ありません!!!」
善逸は再び綺麗に土下座を決めた。禰豆子の言うように本当に失礼な話だ。求婚してきた相手は自分を見ておらず、兄をその目に映していてさらに無自覚ときた。それなのに優しく振ってくれるなんて女神に相違ない。
「・・・・・・でも善逸さんが恋とか愛とかに無理解なのは仕方ないです。道ゆく初対面の女性に求婚するくらいですから、全くこれっぽっちも自分の気持ちなんて分かってなかったんでしょうから。私のことを馬鹿にしたわけじゃないことはもちろん、私との結婚を真剣にちゃんと、考えてくれていたことも分かってます」
優しい声音に善逸はそろりと顔をあげた。禰豆子は困りものの弟を見るような目で善逸を見ていた。トクトクと聞こえる禰豆子の音は天上の音楽のように美しい。善逸は惚けた目で禰豆子を見つめた。
「もしお兄ちゃんが善逸さんをただの友達としか思っていなかったら、私はきっと善逸さんの求婚を受けてましたよ。そしてあなたの隣でずっとずーっと善逸さんが本当の気持ちに気づかないようにと願いながら、あなたに愛を教えるために、気持ちを注いだと思います。それくらい、あなたに恋はなくても愛はあるんですよ?・・・・・・でも、ふふふっ!」
可笑しそうに笑う禰豆子に善逸は首を傾げた。禰豆子はひとしきり笑うと、目尻に浮かんだ涙を脱ぐって善逸に微笑む。
「お兄ちゃんたらおかしいのよ。今にも死にそうな顔をして、善逸さんと結婚してくれなんて私に頭下げるんだもの。必死に善逸さんがどれだけ素敵な人か説明してくるんだけど、自分が善逸さんのどこを素敵に思ってどれだけ好きかを言ってるも同然で・・・・・・馬鹿よねぇ。妹の気持ちを無視してでも、善逸さんを助けたいなんてお兄ちゃんからしたら天と地がひっくり返るくらいのことなのよ?それなのに善逸さんのこと友人だなんて思ってるんだもの。本当にお兄ちゃんたら鈍かったわ!2人ともそっくりよ!」
禰豆子の言い分に善逸はもはや声も出ない。恥ずかしさここに極まれりだ。顔を赤らめてぐったりとする善逸を前に、禰豆子はコロコロ笑いながら金平糖を口に入れた。
「それにしても、善逸さんの口から出る花がたんぽぽなんて面白いですよね」
「あー・・・俺とたんぽぽが似てるから?」
禰豆子が鬼の時、善逸のことを珍妙なたんぽぽに見えていたという話は聞き及んでいる。まあ、髪の色似ているといえば似てるのでしょうがない。そんなことよりもたんぽぽが動き回って叫んでも不思議に思わない鬼の禰豆子が可愛いと善逸はにやけてしまう。
「違いますよ。知ってます?たんぽぽって江戸時代には鼓草(つづみぐさ)って呼ばれてたんですよ?お兄ちゃんと善逸さんの始まりを思い起こす名前ですよね」
善逸は恥ずかしさのあまりに蹲った。確かに善逸がより強く、明確に炭治郎を認識したのは鼓屋敷の任務の時だ。最終選別では炭治郎のことを覚えていたけれど、向こうはこっちを見ていなかったし、善逸も玄弥の骨を折った炭治郎にビビるばかりだった。そう思うと確かに己と炭治郎の始まりは鼓屋敷で間違いはない。
つまりは善逸は、本人は知らずとも誰が好きかを花は知っていたということだ。なんと恥ずかしいことか。
「お兄ちゃん、早く帰ってくるといいですね」
禰豆子の言葉に善逸は曖昧に微笑んだ。病に伏せっていたゆえに本調子ではない善逸の代わりに炭治郎は事の顛末をお館様に報告しに行ったのだ。善逸は自分が行くと言ったのだが、「これは善逸と俺の問題だったんだ!俺も当事者なんだ!」と言って聞かなかった。
あれから善逸は炭治郎に連れられてここ、竈門家にいる。結局は禰豆子にも心配と迷惑をかけてしまったので金平糖を手土産にしたわけなのだが、竈門家に来て見ればなぜか善逸に部屋が用意されていた。客間ではなく、善逸の部屋だ。それも炭治郎の部屋の隣に用意されていた時の心情を考えてみて欲しいと善逸は強く思う。
「善逸ー!禰豆子ー!」
その時玄関がガラリと開く音と共に声が響いた。特別な耳を持たない禰豆子にも聞こえるクソでかい声だ。その声は喜色に富んでいることもよく分かる。善逸も禰豆子は顔を見合わせて笑った。
「善逸さん。お兄ちゃんのこと宜しくお願いしますね?あの人、善逸さんがいなくちゃダメなんだから!」
「・・・・・・うん、俺も炭治郎がいないとダメなやつだからね。まあ、いてもダメな奴なのは変わらないんだけど」
「そんなことないですよ?でも、お兄ちゃんはお世話したがりだから善逸さんくらいが丁度いいですかね」
2人でうふふと笑いあっていると勢いよく襖が開いた。満面の笑みで入ってくる炭治郎に善逸はああ、愛しいなぁと思う。気持ちを理解したら、どうして今までわからなかったのかと思うくらいに炭治郎のことが好きだった。
妹を何より大事にしているところも、誰にでも優しいところも、強くそして努力家であるところも。そして何よりもーー。
「善逸!」
何よりも善逸と己の名前を嬉しそうに呼ぶそれが、善逸がここにいてもいいのだと教えてくれる。ああ、全く。
「好きだなぁ」
自然と溢れた善逸の本音に、向けられた当の本人はカアッと顔を赤らめた。そして善逸も禰豆子の前で何を口走っているのかとこれでもかと赤くなり絶叫する。
慌てふためく兄と義兄となる人に、すべてを見通していた禰豆子は金平糖を口に入れてほほほと笑った。
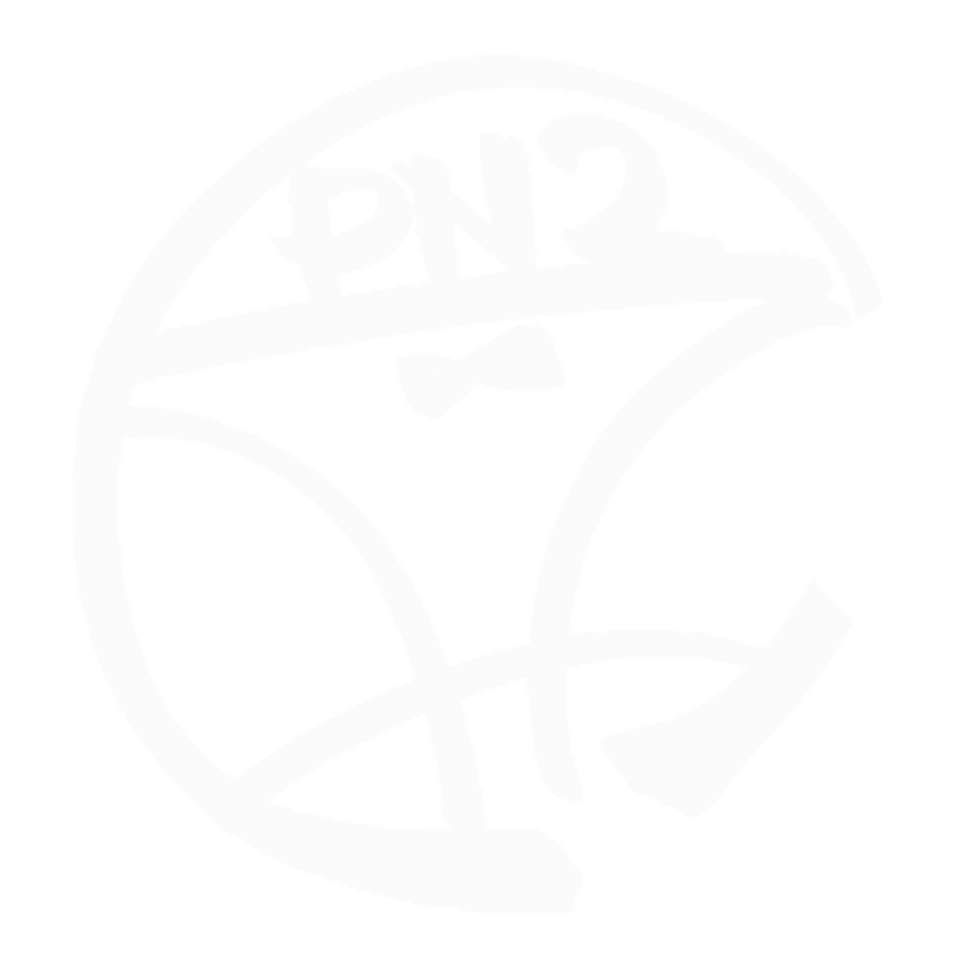



コメント