鬼化、年齢操作、概念にょた、概念カニバを含むメリバな炭善ですが、Twitterで公開してたときは「これはハピエン」と言われましたので、たぶんハピエン。最終回後の話です。
約26000字/原作軸/軽微なカニバ表現あり
まだ夜が明け切らぬ中、森の一軒家の周りは暗い。しかし二人の青年はそんなもの影響はなく、仄かな月明かりがあれば十分でお互いの顔もよく見えた。もっとも二人とも良く利く鼻と良く利く耳があるゆえにお互いの感情など筒抜けであった。
どちらもほんの少しだけ悲しくて、ほんの少しだけ寂しくて、そして大きな罪悪感の下に安堵があった。隣に共犯者とも言える連れが、心を許せる親友がいることに安堵していた。しかしそれはそれとして、お互いの気持ちは分かっていても確認してしまうのは止められない。
「炭治郎、本当にいいのか?」
「……ああ、大丈夫だ。善逸こそ付き合わせてしまって……良かったのか?」
「いやお前の状態知ってて付き合わない選択肢がないわ」
ケっと吐き捨てるように言い、顔を歪めた善逸に炭治郎は嬉しそうに笑った。そして善逸の手にある油を受け取ろうとして、身を逸らされて空振る。どうしたのかと思うと善逸は「させねぇよ。お前は火種のほうやれ」と言って、自分で八年間程を過ごした家の周りに油を撒き始めてしまう。それを炭治郎はじっと見つめ、罪を背負ってくれる親友の存在に心が震えた。彼の為にも心を強く持たねばと思う。
「ほい。完了。炭治郎、後は頼むわ」
「分かった。そら」
「ん?えっ!?あー!!馬鹿っ!!」
軽い様子で投げ出された火種が、善逸の巻いた油に引火する。すると木造の小さな家は轟々と燃え出した。赤く、赤く燃え上がる長年住んだ家に炭治郎が目を細めるよりも早く、首元に伸びてきた手に揺さぶられる。
「おいこら!何やってんだ!!」
「え?家に火をつけただけだ。そういう話だったろ?」
「そうだけど!!もう少しゆっくりやれ!!情緒を大事にしろ!情緒を!!懐かしむことすらないのかよ!!」
そう言って炭治郎から手を離した善逸は「あーあ」というように燃え上がる竈門家を見つめている。炭治郎は善逸が泣きそうになっているのに、目尻に涙がないことを確認してほっとした。善逸にはこうなっても、後悔の匂いはしない。木が燃える匂いが強いけれど、隣にいるから炭治郎には分かる。
「……大丈夫だ。思い出は胸にある。長年経って……崩れた有様を見るより、ずっといいんだ」
そう言った炭治郎は隣にいる善逸の手を取った。ギュッと繋ぎ合わせて、そういえば善逸と手を繋ぐのは久しぶりだなと思い出す。何しろお互いが二十四と二十五なので、いい歳した男同士が手を繋ぐことはおかしいかと自然と手を繋ぐことはしなくなった。十五と十六の頃はよく、その手を繋ぎあっていたのに。炭治郎が善逸の手を繋いで引いていたのに、今度は善逸が炭治郎の手を引いていくのだ。
「……そうか。炭治郎、まだ見る?」
「いや、もういい。家族にも挨拶を済ませた。禰豆子には手紙を送った。……俺は大丈夫だ。善逸がいるから」
「そうか」
善逸はそう言うと炭治郎の手を引いて歩き出し、炭治郎は引かれるままに善逸について行く。これから二人が行く先は何も決まっていない。ただ、この故郷から逃げ出すことだけが決まっていた。家族の墓を麓の寺に移し替え、家の荷物を整理して、そして禰豆子にだけ手紙を書いた。手紙は鎹鴉なんてものはもういないので、郵便で送った。届くのはいつだろうか。
「……ひと月前の禰豆子ちゃんの式、良い式だったな」
「そうだな。禰豆子は幸せになれる」
「あーあ。俺の奥さんが……」
「いや、善逸の奥さんじゃないだろう」
二人はそんなやり取りをしながら、燃える山を麓の町とは逆方向に歩いていく。きっと麓では赤々と燃える山に驚いているだろう。山火事にならないように家の周りの木を二人で全部切り落として、だいぶ禿山としてきたから大丈夫だと思う。今日は風もないし。そんなことを思いながら、炭治郎も善逸も散歩に行くような雰囲気で山道を歩く。走ることはしない。そこまで慌ただしい旅路ではない。それでも疲れ知らずの為、てくてくてくてくと休まず歩いて街道に出た頃には夜明けが迫っていた。舗装されていない街道の遠く先、山あいから登る朝日に炭治郎はほんの少しだけ目を細めた。
「お。朝が来たな」
そう言った善逸からは声とは別にほんの少しの期待と、ほんの少しの恐怖を感じた。彼は日の光で炭治郎が逝けるならばと期待をし、しかしそれが恐ろしいと思ったのか、繋ぐ手の力がぐっと強まる。炭治郎は眩しい太陽の光を見つめ、そして隣にいる親友を見た。朝日を浴びてキラキラと輝く金の髪。それはきっともう、炭治郎のものだ。この先善逸は、何があっても己の側から離れないのだろうなと炭治郎は申し訳なく思いながらも、嬉しさを感じていた。
親友が、心優しい親友が全てを投げうって自分の味方になってくれた。炭治郎はこの先にどんな辛さが待っていようとも、善逸がいれば大丈夫だと信じている。
「良い朝だ。旅立ちはやっぱり、天気がいいと気持ちがいいな」
「ええ?そんな清々しい旅じゃないだろ。……お前を治すか、殺す為の旅だぞ」
そう言って振り返った善逸は炭治郎の顔を見て溜息を吐く。炭治郎は善逸のその呆れた物言いにハハッと口を開けて笑った。その炭治郎の口からは鋭い牙が見え、さらには笑って細まった目の瞳孔は縦になっている。
「マジでお前、日の光大丈夫なのな」
「うん。そうだなぁ。どうやったら死ねるだろうか」
「いや、死ぬ前に戻る方法を探そうぜ?」
そう言って善逸は「はー、やれやれ」というように首を振って、炭治郎の手を引いて歩き出す。炭治郎は善逸に導かれるままニコニコと歩き、十年以上前に鬼になった妹の手を引いて旅立った時とはだいぶ違うなと思った。あの時は絶望が、悲しみが凄かったがいまの炭治郎は落ち着いていた。もしかしたら連れられていた禰豆子の方も思いの外、落ち着いていたのかもしれないと十年以上前の兄妹の旅立ちを思い返していた。
竈門炭治郎に鬼の兆候が見え始めたのは二十四になってすぐの頃だった。その時期から炭治郎はちょっとした怪我も治りがやたらに早く、そして何をしても疲労感から縁遠くなった。しかし炭治郎はこの時はまだ気のせいだろうと思っていたのだ。珠世としのぶの努力の結晶により、鬼から人間に戻っていたので彼女達の手腕を疑っていなかったということもある。
だから炭治郎は普通にそれからを過ごした。何よりも産屋敷家の伝手で見合いをし、いい人と巡り合った妹の祝言が来年の春に予定されていたのだ。何がなんでも妹の幸せを見届けねばならない。そう思って夏を超え、秋を超え、冬を過ごして春を迎える頃に炭治郎は善逸に言われた。
「炭治郎、お前、鬼になってるだろ」
炭治郎は親友の言葉に項垂れながら、疑っていた事実を認めた。認めればあっという間に炭治郎の瞳孔は縦になり、牙は生え、しわが寄って動かなかった左手が瑞々しい肌に変わる。その様子を善逸は驚きもせずに黙って見つめていた。しかし切なげに揺れる目は、きっとかつて兄弟子が鬼になったことを思い出しているのだろう。家族がまた鬼になったことに善逸は確実に心を痛めていた。
炭治郎は人間に戻ったはずなのに、なんの因果かまた鬼になってしまっていた。珠世としのぶの薬の効果はなんだったのか、一時的なものだったのか、結局炭治郎は鬼になってしまった。首を切っても死なず、日に当たっても死なぬ鬼になってしまったのだ。
「ごめん、善逸。ごめん……」
本当ならば鬼になり切る前に、人間の時に首を切り落とさねばならなかったのだ。しかし出来なかった。炭治郎は鬼狩りの人生から離れて八年だ。その志は曇り、禰豆子の晴れ姿をどうしても見たかったのだ。
「……いいよ。俺も気がついてたのに黙ってたからな」
善逸は「共犯だよ」と言って笑い、炭治郎の肩を叩いた。炭治郎が「共犯……」と呟けば、善逸は「うん。禰豆子ちゃんの祝言に、炭治郎がいないと始まらないだろって思ったから……お前が鬼になってくのをずーっと黙ってたんだよ。知らぬふりしてさ。伊之助いたら誤魔化し切るのは無理だったかもな」
ハハッと笑った善逸に炭治郎はギュッと唇を噛む。そしてボトボトと涙を流して、親友に許されていた事に申し訳なさと安堵を感じた。確かに善逸の言うように伊之助がいたら指摘されていたかもしれない。
「ああ、でも伊之助も見逃したかもな。あいつ、前に炭治郎が鬼のなった時も斬るの躊躇ってたし」
「……そうか……」
「子分に優しい親分だからな」
そう言って善逸は炭治郎を抱きしめて背を撫でてくれた。炭治郎は上背の伸びた身体で、自分より僅かに小さい善逸に縋る。そして鬼になっても変わらず優しい善逸に、やはり善逸は善逸なんだなと鬼の妹にも優しかったことを思い出していた。
「……炭治郎、禰豆子ちゃんの祝言が終わって落ち着いたらさぁ。治す方法、探しに行こうぜ」
「……治るかな」
「治るだろ。前は薬でなんとかなったんだし」
「……そうだな」
炭治郎はその方法を探しに行くのに、当然のように善逸はついて来てくれるのだなと思った。昨年の秋に禰豆子が見合いをした時は善逸は今後どうするのだろうかと、いつまで一緒に自分といてくれるのだろうかと考えては、炭治郎は寂しい気持ちになったものだが……。どうやら善逸は自分に寄り添って付いてくれるらしいと炭治郎は嬉しくなる。この状況で嬉しさを感じるのは申し訳ないが一人で秘密を抱えなくていいのだと思うと、安心が違うのだ。
「まあ、うん。今は禰豆子ちゃんの祝言のこと考えようぜ。……とりあえずお前が鬼になったこと知られないように祝言乗り切らないとな」
「そうだな」
鬼になりました。しかし意識はしっかりしています、人食いの衝動もありませんと伝えれば産屋敷家は様々な援助をしてくれる気がしたが、折角鬼がいなくなった世になったのだから、あの幼かった当主達にまた辛いことを思い出させるのは嫌だった。鬼の呪縛から解き放たれたのに、また鬼に関わらせるのが嫌だったのだ。
それから結局二人は黙ったまま禰豆子の祝言を見届け、宴席で仲間達と語らい、そしてひと月の身辺整理の後に旅立った。家に火をかけて行方をくらませた。理由は明確には書かなかった。ただ善逸の提案で「二人で一生を生きることを決めたから、迷惑が掛からぬように姿を眩ませる。同じ空の下で幸せを願っているから、どうかそっとしておいて欲しい。数少ない兄の我がままを聞いてくれ」と認めた。
文面から感じ取れるのは確実に兄とその親友の男色であったが、二人はそんな関係ではない。しかし確かに身を眩ませるには丁度いい言い訳であった。二人とも何故か色恋の話はなかったし、少し麓の町では噂されてもいたし。炭治郎はその文面に追加で家族の墓についてだけを書き足して禰豆子に送った。禰豆子は驚きつつも兄の我がままを聞くだろう。常日頃から「お兄ちゃんはもっと欲張りになったほうがいいわ。もっと我がまま言っていいの」と言ってくれていた妹だ。間違いなく、男二人で連れ合いになったとされる二人を探すことはしないだろう。これで禰豆子は憂いなく、兄と親友の幸せを願いながら自分の幸せを守っていける。
「なぁ、これからどこ行く?」
「ん?そういえば何も決めてないんだよな」
「そうなんだよ。どうするかな。昔の給金が銀行にたんまりあるから生活には困らないからなぁ」
「確かにな。まあ、何か働きつつ方法を探した方がいい気がするが」
炭治郎はそういえば愈史郎さんは今どこにいるのだろうと考えた。鬼についてなら愈史郎さんに相談するのが良さそうだなと炭治郎は思い、善逸に言おうかなと思ったところで善逸が「閃いた!」と言ってニシシッと笑いながら炭治郎を振り返る。
「まずは湯治を試そうぜ!全国の温泉や秘湯を巡ろう!病に効くっていうだろ?」
「……それ、善逸が温泉に入りたいんだろ?」
「いやいいだろ別に。それき湯治が効果ないかなんて分かんないだろ?鬼舞辻無惨は絶対、湯治なんで試してないぜ。断言できる。なんとなくだけど」
「いやまあ、確かに……湯治で鬼を治そうとはしてないだろうな」
あの苛烈で残酷な奴がのんびり温泉に浸かっている姿が想像できない。炭治郎はポリポリと頰を掻いて、くすっと笑う。愈史郎のことはまた今度にしよう。あと禰豆子が前に鬼の時に刀鍛冶の里で温泉に入ったけど効果なかったこともひとまずは黙っていよう。あそこの湯が効かなかっただけかもしれないから。
「じゃあまずは箱根だな!有名なところに行こうぜ!観光地は飯屋も美味いし!」
「いいな。海があるから魚介も食べれるな」
二人は手を繋ぎ、笑い合って街道を行く。煙が立ち上る雲取山はもう振り返らなかった。
****
「おとうさぁん」
小さな声に振り返り、炭治郎は笑った。そして一生懸命作ったのだろう。白詰草で出来た少し歪な花冠を掲げて走ってくる幼子を両手を広げて迎え入れた。
「見てぇ。善逸くんに教えてもらって僕が作ったよ!」
「そうかそうか。善逸に教えてもらったか。上手に出来てるぞ!」
炭治郎はニコニコしながら幼子の頭を撫でる。いがぐり頭はゾリゾリと手触りがいい。後頭部を撫でて耳の裏をくすぐると、幼子は「うひゃあ!くすぐったいよお父さん!」なんてキャッキャと笑い声を上げる。炭治郎は子供の屈託ない笑い声が好きなのでぎゅうとその子を抱きしめた。
「はー。花冠なんて久しぶりに作ったわ」
「善逸」
「善逸くん」
土手を上がってきた善逸を二人で振り返れば、善逸は少し泥に汚れた手を払ってから手拭いを取り出す。そしてそれを幼子の頰に当てて、ぐいっと汚れを拭った。幼子はむふふと笑いながら少し首を竦めて受け止めていた。その様子を見ながら、炭治郎は腕の中の子が安心して自分達を受け入れているのに、しみじみとした気持ちになる。
「さて。日も暮れるから帰ろうかね」
「そうだな」
そう言いながら幼子を抱きかかえたまま湯治用の宿へと向かう。空は少しずつ茜色に染まってきており、借りている宿に戻ったら善逸は三味線を持って温泉街の宿の座敷に向かわねばならない。夜は善逸にとったら稼ぎ時だ。そこまで贅沢をしていないこで、二人合わせれば貯金も十分にあるのだが、炭治郎も善逸も子供を育てる親であるので倹約したい。先立つものはたくさんあった方がいい。いつかこの腕の中の子に持たせる為に。
「ありゃ、寝ちゃった?」
「うん。駆け回って遊んでいたから疲れたんだろうな。帰り着くまでは寝かしておこう」
そう言って腕の中の幼子を愛しげに炭治郎は見やる。幼子はぷうぷうと寝息を立てながらしっかりと炭治郎の着物を握りしめていた。今度こそ、どこにも行かないよう。
「この子を育て始めて三年か。もう六歳だよ?凄いよなぁ」
「そうだなあ。子供がいると月日が経つのは早いな」
炭治郎はそう思いながら、腕の中の子と出会った日のことを思い出していた。三年前、雪解けの頃の山中を善逸と歩いていて炭治郎が血の匂いを嗅ぎつけた。慌てて走って山の中の小さな家に飛び込めば、木戸は倒れていて、若い夫婦が血を流して死んでいた。
人喰い鬼はこの世にはもういない。もう鬼は一人だけだが、なぜか食人衝動はない。炭治郎は大量の血を前にしても冷静に、しかし心をキリキリと痛める。どうみても、冬眠明けの熊に襲われた状態だった。食べ散らかされた跡がある。人の肉を覚えた熊は危険だ。麓に降りて人を襲う前に殺さなければならない。
乗り掛かった船だ。弔いをしてから熊を探そうと思っていた炭治郎の肩をちょんちょんと善逸がつつく。なんだと思うと善逸は押し入れを指差した。そちらに目をやれば、鼻に入ってきた人の匂いに炭治郎はハッとする。
「誰かいる。たぶん子供だ」
「うん」
炭治郎はそっと押し入れに近づくとそこをあけた。するとしまわれている薄っぺらい布団の合間で眠っている子供がいた。まだ幼子で恐らく、男の子だ。目尻には涙の跡があり、親指をちゅうちゅうと吸ってるのに炭治郎はどうしようもなく切なくなる。親を失ってしまったのだと、一人きりになってしまったのだと胸が痛む。
「寝てるな。起こさないで、先に両親のこと埋めてやろう。こんな小さな子が見たらダメだ」
「……ああ、そうだな」
善逸の言葉に頷くと、炭治郎は一度襖を閉めた。そしてすっと立ち上がると腕まくりをして事切れている大人たちを外へと運ぶ。炭治郎の怪力を持ってすれば簡単なことで、穴を掘るのもあっという間だ。中の血を始末するのを善逸に任せて炭治郎は僅かな間に若い夫婦を埋葬した。盛り上がった土を見て、手を合わせながら炭治郎はふっと息を吐く。ジャリジャリと土を踏みながら近づいてくる音に振り返れば、善逸が手抜いを炭治郎に差し出してきた。それを受け取って炭治郎は土に汚れた手を拭う。
「あの子、どうする?」
「麓の町に連れて行くか?誰かに預けて……」
「……いやあ、それはどうだろうな……」
善逸の言葉に炭治郎も肩を落とす。二人が通ってきた麓の町は今はあまり余裕がないようだった。麓の町は蚕の養殖を盛んにしている場所であったが、今年に入ってから輸出先の米国の経済状況から悪化しているらしいのでどの家も家計に喘いでいるのだ。我が子でもない幼子を一人増やすのは渋るだろう。
「預けたらどうなると思う?」
「間違いなく欠食児童だな。女の子じゃないから売られはしないだろうけど……あの歳でろくに飯も食えなくて、働かされて、殴られて……ロクなことはなさそうだ。多少の金を渡したとしても、俺達がここを離れれば子だけポイ捨ての可能性もあるな」
「そうか……」
親なしの子というのは肩身が狭いものだ。もっと麓の町に余裕がある頃であったなら対応も変わってくるだろうが、今は間が悪かった。多少の金を渡しても金だけ奪い取られて捨てられるなんて、あんな幼子では生きられない。どう見ても三つになるかならないかだ。
炭治郎はぐっと眉をしかめて目を瞑る。記憶の中で弟妹達のあの頃の姿が思い起こされる。とても可愛い盛りなのだ。悪戯をたくさんする頃で、無邪気笑いながら駆け回る姿は愛しい以外の言葉がでない。そんな頃合いなのに、ロクに飯も食えないなんてと炭治郎は苦しくなる。両親を失い、更にはひもじく生きるなんて生まれてきた意味を問いたくなるだろう。しかし幼すぎてそんな事を考えることもできやしない。
「……善逸……」
「ん。いいぜ」
「まだ何も言ってない」
「いやあ、言わんでも分かるって。けど子を抱えるなら、お前は見かけだけでも取り繕っていけよ。子供はぐんぐん大きくなるんだ。お前が『老けない』とかおかしいからな。顔の皺の一本でも増やせるようになっておけよ」
「分かった。こんな感じか?」
「……びっくりした……いや、いきなり老けすぎじゃない?今の顔、老人一歩手前だぞ。おかしすぎるわ」
「そうなのか?鏡がないからな。難しい……」
頰をさすりながら炭治郎は溜息をついた。顔の皺一本だけを制御するのはできるのだろうか。大雑把に大きい、小さいとかは出来るのだが、顔に老けを取り入れるというのは中々に難しいなと炭治郎は思う。
「まあ、まだ平気だろ。少しずつ練習しとけよ。さ、あの子を起こそう。両親に手を合わさせて……ここから離れようぜ」
「あ、待ってくれ。先に熊を片付けたい。麓に降りたら大変だ」
「ああ、そうか。人の味を覚えたからな。んじゃ俺はここで待ってるからさっさと行ってこいよ」
「分かった」
炭治郎はそう言って森へと駆け出した。匂いを辿ればすぐに分かる。獣くささと……そして恐らく口から漂う血の匂い。相手は自然の掟に従って、弱いものを喰ったのだろう。そこには生きる為以外の理由はない。決して、鬼のように「強くなる為に食う」なんて理由はない。けどダメだ。人を喰ったら、鬼じゃなくても熊でも殺す。炭治郎はとても普通の人では見えぬ速度で森を駆け抜け、熊の前へと躍り出た。
「なあ、来年どうする?」
「……ん?」
幼子と出会った頃を思い出していた炭治郎は、善逸の言葉に意識が引き戻された。振り返れば善逸が子を見つめて優しげに微笑んでいる。その表情なまた少し大人になったようで、そういえば善逸ももう、三十路を超えたのかと炭治郎はそちらの成長にもしみじみとなる。鬼である炭治郎は老いないが、善逸は少しずつ変化していくのだ。腕の中の子と同じように。
「どうするってなにがだ?」
「何がって来年はこの子、小学校の通う歳だろ。どうするんだ。俺たち、全国行脚してるから通うの難しいぜ?」
「ああー……」
炭治郎はそうかと夕焼け空を仰いだ。炭治郎と善逸、そして幼子は三人で全国の湯治場を行脚する旅をしている。その理由としてはどこか一か所に身を寄せると炭治郎の肉体の時が進まないのを気取られる可能性があるからだ。あと一応は炭治郎を戻す方法を探す旅でもある。どうしていいか分からずにひたすら温泉を堪能しているだけの感じになっていたが。
「……キチンと勉強させてあげたいな。いつかこの子は、そう遠くない頃には俺たちから巣立つんだから」
「まあ、そうだよなぁ」
育てるのは子供のうちだけと決めていた。鬼と人は深く交わるものではない。大人になっても炭治郎を父として慕い、顔を合わせるのは良くない。子が一人前になったのを見届けたら、姿を眩ませねばならない。だからせめて、金だけでなく知識という財産も与えたい。親がいなくなっても立派に生きていけるように、知恵を授けたいと炭治郎は思っていた。
「……どこかに一旦、腰を落ち着かせるか」
「いいぜ。まあ、お前の治すのも湯治じゃ無理っての分かってきましな。はー……しっかしお前の方のあてがないな。どうやって治すんだか。やっぱりしのぶさんみたいに薬の方面じゃないと無理なのかね」
ガリガリと頭を掻く善逸に、炭治郎はそういえばというようにある事を思い出して口にした。愈史郎のことを伝え忘れていた。
「愈史郎さんを探そうか」
「愈史郎さん?……あ。あの鬼の……?いたな!?そういえば!!えっ!?待って!?あの人生きてるの!?」
「分からない。珠世さんが居なくなって……どうしたんだろうか。生きていて欲しいと別れ際に伝えたんだが……」
珠世を失った彼は生きているのだろうか。珠世の猫、茶々丸も鬼になったと聞いているし、一人と一匹で生きていないだろうかと炭治郎は少しだけ俯く。彼らは日に当れば死ねるから、どちらかを残して死ぬことはないだろう。両方生きているか、死んでいるかだ。
「すっかり忘れてたわ……。湯治に勤しむより先に探した方が良かったんじゃない?」
「今更だなぁ。まあ、湯治場を巡る旅は楽しかった。この子にも出会えたし」
炭治郎はそう言って微笑んで、腕の中で眠る子を少しだけ力を込めて抱きしめる。安心しきっている重みは炭治郎を幸せにするばかりだ。子供はいい。
「それもそうか。まあ、急ぐ旅でもなかったしな。よしっ。それじゃあ都会に向かうか。東京に戻ろうぜ」
「ん?人が少ない場所の方が良くないか?」
あまり鬼である自分が人の多いところにいるのは良くないのではと炭治郎は思ったのだが、善逸はふるりと首を振る。
「いや、都会の方が人の出入りや入れ替わりが多いからな。周りなんてあんまり気にしちゃいないよ。田舎の方が人同士の結びつきが強いから、俺たち怪しまれちまう。腰据えるなら、根掘り葉掘り聞かれない都会がいい」
「なるほど」
炭治郎はひとつ頷く珠世と愈史郎も鬼であることを隠す為に移動を良くしていたらしいことを思い出す。確かに都会の方が、居た人が消えたり、居なかった人が増えたりは多いから気にならないのだろう。
「じゃあ、近いうちに東京に戻るか」
「震災から向こう、どうなったのかねぇ」
「禰豆子の様子を前に見に行ったきりだもんな」
「禰豆子ちゃんとこの子達も様子覗いて行こうぜ」
「いいな。そうしよう」
そんなことをつらつらと話しながら、仮宿へと向かう。今は仮宿への帰り道だが、これがほんの少し先には家路になるのだと思うと、炭治郎は少しだけ楽しみであった。
****
「俺は行かないよ。ここに友達もいるんだ。俺だけ徴兵から逃げるわけにはいかない。戦いたいわけじゃないけど……でも逃げたくもない。父さんと善逸さんだけで行ってくれ。二人が無事なら俺は平気だ」
その言葉を聞いた時、人間は脆くて弱いのにと初めて炭治郎は思った。子が国に取られていなくなり、日々の物資が不足していく中、少しずつ痩せていく善逸にも炭治郎はゾワゾワとしたものを感じる。住んでいる街だけでなく、どこへ行っても不安と悲しみと怒りと焦燥の匂いが満ちていた。
「ほい、飯できたぞ。少ないけど」
「……」
「なんだよその顔。少ないのは我慢しろよ。街行っても売ってないんだからしょうがないだろ。いただきまーす」
そう言った善逸に炭治郎はふるりと首を振った。そして用意されている二膳を睨んで、グイッと自分の分を善逸へと押しやる。
「善逸が食べろ。俺はいらない」
「はあ?」
「前から言ってるだろ。俺の分はいらない。俺は人の食事は必要ないんだ。眠れば回復できる。食べる必要はない。俺の分を用意して善逸の取り分を減らすのはやめてほしい」
そう言ってギュッと服の裾を握った炭治郎の姿は十三の子供であった。なぜそんな歳かと言われると、子がいなくなった後に壮年の男二人で暮らしているのを数奇な目で見られたからだ。ただでさえ世界大戦が幕開けし、異人にたいする目が厳しくなる中で善逸は金の髪をしているのだ。極力、目立つことはしたくなかった。
子がいなくなった中、炭治郎と善逸は再び全国行脚をする生活に戻るべきではと話し合いをしたが、結局は住処の場所を少し移動させただけで東京から離れることはなかった。単純に戦争が終わった時に帰ってきた子を迎えられないのが困るからだ。本当ならば炭治郎を人間に戻す方法を探すべきであったが、子を憂う親としてできなかった。
しかしそもそも現状としては人間に戻る方法の手がかり以前に、愈史郎も未だ見つかってない。探し始めてから十年以上経つが、愈史郎は血鬼術のこともあり、隠れるのが大変上手く一切の足取りを掴めていない。……子の成長を見守るのに夢中でかまけていたのも原因であるが。
というわけで子がいなくなり、子を待つ間にもっと真剣に愈史郎を探すかと二人の間で決まったわけなのだが、最近になって炭治郎は子を待ち、愈史郎を探すために東京にいるよりももっと田舎に移動した方がいいのではないかと思うようになってきた。
それは日々、戦争が激化の一途を辿っており、ついには日本本土にも敵国の攻撃が及ぶのではないかと言われているからだ。敵国の偵察機が夜に飛んでいるのを見たことがあると叫んでいる街人に、炭治郎は「ミサイルで俺は死ねるのだろうか」とチラリと思ったがどうやっても試せない。例え、本土に攻撃が始まった時に運良く当たれたとしても……その時は一緒にいる善逸も巻き込まれで死ぬだろう。善逸は間違いなく最後まで自分の隣にいることを炭治郎は自覚していた。
何しろ出会ってもうすぐ三十年になる。三十年近くも共に過ごし、共に歩み、見返りなんて何もないのに自分を支え続けてくれる善逸がここまで来て炭治郎を捨てて何処かへいくなどあり得なかったし、炭治郎も非常に勝手な言い分だがそんなことは許せなかった。
我妻善逸の全ては自分の為にある。きっと自分に寄り添い、支える為に生まれてきたのだとそんなことを思う傲慢さまで炭治郎の中にはあった。それを自覚したのは最近で、善逸が四十を超えてもう結婚はないなと思ってホッとしたのがきっかけである。
炭治郎は善逸が禰豆子に本気であったのを知っていた。本気で結婚したいと思っていたのを知っていた。しかし善逸は禰豆子に手を伸ばすのをいつの頃からか、止めてしまったのだ。口では「禰豆子ちゃんと結婚したいよぉ〜!」と言うことはあっても、いつからか禰豆子本人にそういうことを言うことがなくなった。そして禰豆子に見合い話が来たときも悔しがりながらも、自分が禰豆子を得るための行動などは起こさず、ほんの少しの切なさの匂いをさせながら禰豆子の行く末を見守っていた。
それが何故か炭治郎は分からなかった。いや、分からないふりをしていた。禰豆子の見合い話が起こった直後に炭治郎は自分の鬼化が進んでいることに気が付いたが……もしかしなくとも善逸は、炭治郎の変化にもっと早く気がついていたのかもしれない。
それがいつからかは分からない。炭治郎は自分の身体の変化に気がつかなかったが、もっとずっと前から兆候があったのかもしれない。炭治郎の変化に善逸が黙っていた理由も分からないが、炭治郎は痣の影響で二十五まで生きられるかどうかという話であった。善逸は炭治郎の変化を死の予兆と勘違いした可能性もある。どちらにしても善逸は黙っていた。そして炭治郎も黙っていた。善逸が禰豆子を諦めるのを隣で見つめながら、黙っていた。「禰豆子を諦めていいのか?」なんて親友と妹の恋を応援することはなかったのだ。
炭治郎は、善逸の恋を応援しなかった理由に今更ながら気がついてしまった。理由は単純だ。善逸を禰豆子にとられたくなかったのだ。善逸と禰豆子が結婚をすれば親族になり、なくならない確かな縁が結ばれるのに炭治郎はそれも嫌だった。善逸が自分以外の家族になるのが嫌だった。親族は親族だ。家族じゃない。
炭治郎は善逸が誰かに心を傾けて、善逸の中の存在として自分がどんどんと優先順位が下がることが嫌だった。善逸の真ん中に自分がどんと居座っていたかったのだ。
そしてそれは、炭治郎が鬼化をしたことで叶えられる。優しい善逸が親友を見捨てて所帯を持つことなんてできる筈もなく、まさしく善逸はその生涯を炭治郎に捧げてくれている。
しかし二人の間に情はない。友情しかない。独占欲ともいえる気持ちに気がついた炭治郎は、今からでも善逸をそういう目で見れるが、善逸はそうはいかないだろう。今まで炭治郎に特別な色を含む匂いなどを向けることはなかった。それが善逸の中に本当に友情しかないからか、はたまた善逸が四十を超えてしまっているからか、炭治郎には分からない。
しかし善逸が炭治郎をどう捉えていようと、炭治郎からすれば善逸は大切な人なのだ。自分が死ぬまで隣にいて欲しい人なのだ。しかし、自分はどうすれば死ぬのか分からない存在で、それに引き換え善逸は死んでしまう身体の持ち主であった。
炭治郎は善逸が四十を超え、世界が戦争へと向い、死を連想させる匂いが自分の周りをとりまいて初めて善逸が死ぬことを恐怖に感じた。そうだ。善逸は死ぬのだ。ミサイルに当たらなくとも、病気や、怪我や、飢餓や、はたまた何もなくても寿命がくれば死ぬ。それに炭治郎はゾッとする。
善逸に死んでほしくない。寿命を迎える前に外的要因で死ぬなんてあり得ない。だから戦争の足音が遠い場所に行きたい。死から遠ざかりたい。目の前にある自分には必要のない飯を食らい、少しでも血を肉を力をつけて生きて欲しい。
炭治郎はギュウッと服の裾を握りしめながら善逸を見つめた。善逸はそんな炭治郎を呆れたような顔で見つめ、手に持っていた箸を置いた。そして両手を膝の上に置くとスンッと澄ました顔をする。
「炭治郎が食わないなら、俺も食わない」
炭治郎は叱られた子のように下から善逸を見やった。そして善逸の匂いに一つの譲歩もないのを嗅ぎ取って仕方なく両手を合わせる。
「……いただきます」
「いただきまーす」
カチャカチャと小さな音が立つなか、炭治郎は沢庵を口に入れた。味がじわりと舌の上に広がる。普通に美味しい。炭治郎は人を喰ったことがないし、食べたいとも全く思わないし、むしろ死んでも食べたくない。しかし人の飯がいくら美味しくても炭治郎の力にはならない。しのぶの薬の効果なのか、それとも炭治郎が特別な鬼なのか、元々炭治郎は飢餓感とは無縁だ。大きな怪我をしたことないからかもしれないが、炭治郎は空腹感の辛さを知らない。食事はただの趣味のようなものなのだ。
「……俺は食べなくても死なないのに……」
「ぐちぐちと煩いぞ。いいから付き合えよ。飯は一人で食っても美味くないんだよ。……あと鬼だから必要ないとか言うな。飯はお前に必要だよ。たぶん」
「そうかなぁ」
そう言いながら炭治郎は少ない飯を食べ切った。善逸の取り分が減ってしまったと不安に思いながら手を合わせて挨拶をすれば、食事を用意してくれた善逸は目を細め、優しい顔で炭治郎を見つめている。その表情に炭治郎はホワッと心臓のあたりが温かくなるが、善逸の目尻に寄る皺に言いようもない不安がまた込み上げてきてしまう。死が、寿命の終わりが、ひたひたと善逸に迫っていると炭治郎は感じていた。
****
カラーテレビを電気屋で眺めながら、善逸はふむふむと頷く。全く文明とはどんどん発展していくものだなと終戦から十五年経ち、復興めざましい東京に善逸はすごいなぁと月並の感想を持った。そしてそういえば夕飯の買い出しの帰りだったと思い出し、五十を超えてから思うように動かなくなってきた足を引きずり家路につく。
空襲で焼け野原になった街はもうビルが立ち並び、東京タワーなんてどでかい塔が立ち、そして数年後にはこの東京でオリンピックがあるというのだからとんでもないことだ。あんなに戦争で全てがなくなったのではないかというくらいの状況に陥ったのに、人というものはこうも強いのか。年月を重ねることで木々が伸び、草花が芽吹くように元の生活へと、なくなったものを新たに作り上げていく。
死んだ人は決して戻ることはないけれど、生きている人達で悲しみを抱えながらも未来を紡いで行こうとする姿はとても美しい。この日本に住む人達が再び戦禍にか見舞われることがありませんようにと善逸はぼんやり、十五年前の空襲を思い出しながら歩く。
あの戦争で知り合い達と離れ離れになってしまった。風の噂で禰豆子の嫁いだ家は東海地方の親類を頼って疎開したと聞いたのできっと無事だろう。しかし伊之助の消息も、蝶屋敷の子達もどうなったかは分からない。けれど皆んなきっと無事に生きている。各々ができることをやって、幸せに過ごしているはずだと善逸は信じていた。だから自分も、できることをやっていこう。最近になって善逸は、よくそう思うようになった。
「ただいま〜」
「善逸っ!!」
古い家屋の玄関を開けると十五歳の姿の炭治郎が奥から飛び出してくる。目はギョロリと鬼の目になり、牙は大きくなり、そしてなによりも漏れている。善逸は「あーあ」と思いながら荷物を床に置いた。
「善逸!!出かける時は俺を起こせと言ってるだろう!!」
「ちょいと商店街まで行ってただけだよ」
「それでも起こしてくれ!車に轢かれたりしたらどうするんだ!」
「そんなこと起きないって。それより炭治郎、背中から『出てる』ぞ」
善逸が指摘をすれば、炭治郎はハッとした顔で自分の背中を見た。炭治郎の背中からはウゾウゾと触手が生えて蠢いている。炭治郎は顔を悔しそうに歪めると背中の触手をするするとしまった。
「……また服に穴を開けてしまった」
「直せばいいだろ。ほい、買ってきたもの冷蔵庫にいれてきてくれ」
「……うん……」
炭治郎はしょんぼりした様子で善逸から荷物を受け取った。そしてくるりと振り返ると炭治郎の着ていたシャツは見事に穴が開いている。それを見ながら善逸は溜息をつきそうになるのをなんとか堪えた。
炭治郎の鬼としての制御が年々、できなくなってきている。前から疑ってはいたが、それを間違いないと断定したのは善逸の足が悪くなってからだ。若い頃の無茶が祟ったのか歳を重ねた結果、善逸の右脚は動きが悪くなった。左脚も決していいとは言えない。ゆっくりとしか歩けなくなった善逸に炭治郎は狼狽し、グニャグニャと触手を出した。全く居たのが家の中で良かったものだ。
とにかくそれを機に炭治郎は触手がよく、漏れ出るようになった。となればあまり外に連れ出すわけにはいかない。往来で触手など出せば化け物騒ぎになってしまう。それに触手だけでなく、炭治郎はコロコロと年齢も変わってしまう。それは朝は青年だったのに、夜には子供というようにだ。しかし禰豆子のように意識をしてではなく、ぼーっとしている間に変わってしまう。
炭治郎がぼーっとし始めたのは十五年前に戦争が終わり、子が帰ってこず、そこから八年の後にあの子の友達が遺品を届けてくれたからであった。あの子の友達も何年もの療養の果てにようやく帰ってきたらしく、若いのによたつく身体で、あの子が立派であったことを涙ながらに教えてくれた。
それから炭治郎は少しずつ、少しずつおかしくなっていっている。善逸な炭治郎がおかしくなっているのに気がついている。人は喰わないが、身体が人に寄せられていない。異形そのものだ。善逸は炭治郎のシャツの穴を見つめながら、大変なことになってきたと眉をしかめる。
(……そろそろ潮時かなぁ……)
善逸はそう思いながら炭治郎の後を追って台所に入る。すると机の上には虫除けの網が掛けられたおにぎりが置いてある。昼に食べるようにと善逸が置いていったものだが、炭治郎は食べなかったらしい。これで炭治郎が食事をしなくなって五日だ。善逸はかごを除けて、おにぎりを掴み齧り付く。乾いて美味しくない。
(炭治郎のおにぎりが食べたいな)
しかし炭治郎は料理をしなくなってだいぶ経つ。少しずつ、少しずつ、炭治郎は人の道から外れていく。夜は眠れ、飯を食え。善逸は炭治郎を人と同じように過ごさせることで人としての意識を強く持たせてきた。その結果があったのかは知らないが、炭治郎は人を食う様子は一切ない。欲しもしない。人を喰いものにするのが鬼であるなら、炭治郎は鬼ではない。首を切っても死なぬ人間だ。善逸にとっては……だが。
(……たぶん、ダメだろうなぁ)
善逸は握り飯を腹に収め切ると縁側で夕陽に当たる炭治郎の横に腰掛けた。炭治郎は足の爪先に向けていた視線を、そろりと善逸に向けた。善逸は出会った頃の姿の炭治郎に、思わず懐かしさを感じて口元が緩む。一人だけ色んな炭治郎の姿をちょくちょく見れるのは贅沢だなと思ってしまう。
「炭治郎、出かけるぞ」
「え?今からか?」
「そう。ダラダラするのはお終いだ」
善逸の言葉に炭治郎は困惑した表情であった。しかし善逸が立ち上がり、足を引きずりながら歩き出せば炭治郎は必ずついてくる。善逸は簡単に財布とそれと居間に飾っている二本の日輪刀を手に取った。
「善逸、どこに行くんだ?」
「……俺たちが最初に会った場所」
そう言って二人が向かったのは、四十年近く前に訪れたきりの場所であった。一年中、藤の花が咲き狂う鬼を閉じ込める美しい檻。炭治郎は先導する善逸について行きながら、ぼんやりと藤の花を見つめた。
「藤襲山……」
「炭治郎、藤の花が大量にあるけど平気か?」
「平気だぞ」
ケロリとした様子の炭治郎に本当に強いものだと善逸は苦笑いする。ここにいた鬼達は出ることすら出来ずに中に篭っていたというのに。やはり太陽をすぐ様に克服したように、炭治郎は『鬼になる才能』というものに恵まれ過ぎていたらしい。しかしその才能も肉体だけの話で、精神に関しては全くダメそうだが。
善逸は藤襲山の中に踏み入り、山の中腹、少し広いところで立ち止まった。なぜなら脚がしんどいのでこれ以上は登りたくなかったからだ。呼吸を使ってもしんどいものはしんどい。善逸はヨタヨタと岩の上に腰掛けて一息ついてから炭治郎を見る。炭治郎は困惑した音をさせながら、二本の日輪刀を持っていた。善逸は前に手を差しだし、炭治郎は差し出された手に善逸の日輪刀を置いた。
「……首を斬るのか?」
「いや、しないよ。お前は首を斬っても死なないだろ。何回試したと思ってんだよ」
「…………」
「心臓だってさ、鬼舞辻無惨と同じようにいっぱいあるしさ。斬っても刃が抜けた次の瞬間にはくっついてるしさ。吹き飛ばすより早くくっつくのはズルイだろ」
「……ごめん」
「謝るなって。炭治郎のせいじゃないだろ」
「……うん……」
匂いで善逸が本当に炭治郎のせいじゃないと思っていることが分かっているのだろう。こくんと素直に頷いた炭治郎は日輪刀をギュッと握りしめる。けれどみしりと音がして慌てて手の力を緩めた。炭治郎の怪力では日輪刀など簡単に折ることができる。日輪刀を自ら折るなんて鬼殺隊士としてあり得ないことだ。炭治郎も善逸も鬼殺隊士を辞めてもう何十年も経つが、それでも体には、心には鬼狩りが染み付いている。
とはいえ、善逸は炭治郎ほどではないが。何しろ鬼狩りとして鬼を狩ったことなどないのだから。善逸は兄弟子の頸を落としたが、おれは雷一門として、桑島慈悟郎の名誉の為に近い。桑島慈悟郎の為に何かをしたいとそう思ったからこそできたのだ。
善逸は最終的に鬼舞辻無惨とも戦ったが、ついぞ憎いという感情はあの場では生まれなかった。多くの隊員、自分の知っている先輩達を喰い殺したのは知っていたが、それでも鬼舞辻無惨への憎悪よりもあの場にいた皆んなを生かしたいと思う気持ちの方が強かった。感情や気持ちを鬼舞辻無惨に向ける暇がなかったのだ。
そもそも善逸は鬼を殺したいと思ったことはない。鬼狩りをしていた時も気がつけば鬼が死んでいるばかりで、後に「あれは俺がやった」とその事実から目を逸らすのはやめたが、自分の意思で生き物の息の根を止めるのは勇気が必要だから善逸は苦手なのだ。躊躇って決断できない。自分の中で「やらねば」と納得がいかないと手が震えて動かない。
だから気を失って自分に危機が迫るまで動けないのだ。桑島慈悟郎を喰った兄弟子ですら「対話」をして納得せねば頸を斬れなかった。最初から問答無用の速さで行けば良かったのは分かっている。けど「対話」をして納得しなければその速さはでない。そして……今回もその時と同じように納得がいかないから動くことができなかった。
善逸はふーっと息を吐き、ドキドキ鳴る心臓に自然と奥歯に力が入る。鬼殺隊が解散したが一般の人と元鬼狩りではその役目はきっと違うだろう。元鬼狩りが鬼を前にして、知らんふりなどしてはいけない。だから善逸は、周りに全てを秘密にして連れて逃げたのだから責任を取らねばならない。じゃないと死んだ育手にも顔向けできない。
「炭治郎」
「……なんだ?」
匂いで不穏を感じ取ったのだろう、炭治郎は僅かに緊張をしているようだった。頸を斬っても死なない、日に当たっても死なない、最強の鬼が置いていかれる子供のように瞳を不安で揺らしている。それを見て、ますます善逸は「やらねば」と覚悟が決まった。
「俺を鬼にしろ」
善逸のその言葉に炭治郎は目を見開いて……そしてざっと青くなる。しかし一瞬、喜色の音がした……と思ったのは善逸の都合のいい聞き間違いかもしれない。炭治郎は青い顔のままふるりと首を振った。
「だ、ダメだ!善逸を鬼になんてできない!」
「でもこのままじゃ炭治郎は一人になっちまう」
「そんな……そんな理由で善逸を鬼できるか!俺の為だけに善逸がそんなことする必要はない!!」
「いやお前の為だけじゃないですけど?」
「え?……え?」
啖呵をきるように叫んだ炭治郎は善逸の否定を聞いて、途端に恥ずかしそうに顔を赤らめた。青から赤に。忙しないなと笑った善逸は立ち上がって目の前の炭治郎へと近づく。確かに炭治郎の為というのもあるが……理由はそれだけではない。
「炭治郎。俺はさ。鬼は人を喰わないなら、人に危害を加えないなら、悲しみを生まないなら、生きていていいと思うんだよ。実際に禰豆子ちゃんは全く断罪される謂れはなかったと思ってる」
「うん……」
「そもそも人間だって非常時になればきっと人間を喰うよ」
「えっ!?」
「……喰うよ。でも大半の人は他に食えるものがあるから、人を喰わないんだよ。あとは、まあ、倫理観の問題だけどさ。だから鬼も同じだ。喰ったか、喰ってないか。生かすか殺すかはそこだけだ」
炭治郎はパチパチと瞬いて善逸を見上げる。今の炭治郎は十五の頃合いなので善逸の方が少しだけ上背が高い。見下ろす形になりながら、善逸は何十年もかけてようやく「納得」した結果を炭治郎への披露を続ける。
「だからさ。俺は炭治郎は生きていていいと思ってる。無理に死ぬことはない。死ぬ方法も分からないしさ。お前が人を襲わない限り、人を食わない限り、この世界が、星が滅ぶまで生き続ければいいよ」
「…………でも……」
「分かってるよ。生き続ければいいって言ったけど、炭治郎には無理だよな。だってお前、普通だもん。普通の優しい心の人間だもん。鬼舞辻無惨みたいにさ、百年も千年も一人きりで生きられる才能は炭治郎にはない。お前は鬼になる才能は抜群だったけど、鬼として生き抜く才能はきっとゼロだ。炭治郎は孤独に耐えられない。出会った人が、仲間が、新たにできた家族に置いていかれるのに一人で耐えられる奴じゃない」
善逸の言葉に炭治郎は目線を下に向ける。心当たりはあるのだろう。仲間が死んだらしい、子が死んだ、善逸も禰豆子も死に向かっているとなれば炭治郎は心が荒れる。そうして心が荒れるから鬼としても姿が安定がしない。
「さっき俺を鬼にしろって言ったよな?」
「……うん」
「あれは確かに炭治郎を寂しくさせたくないって気持ちもあるけどさ、元鬼狩りとして鬼が人を喰うのを防ぐためでもあるんだぜ」
その言葉に炭治郎は善逸を悲しそうに、辛そうに見てくる。善逸はそんな炭治郎に言うのは辛いなと思ったが、鬼が人を喰うのを防ぐのが鬼殺隊士の仕事だ。周りは鬼を殺すのが仕事だと言っていたが、善逸はそうは思っていない。人を喰うのを防ぐために殺しているのであって、人を喰わないなら殺す必要はないはずなのだ。
「炭治郎、断言するぞ。俺が死んだら、お前は人を襲うよ」
「…………」
「お前の中にある人間の意識がきっと死ぬ。そしたら、鬼舞辻無惨が植えた鬼の芽が出る。分かるか炭治郎。何十年も経って、鬼舞辻無惨にぬか喜びさせられたことになるんだぜ。鬼が消えたなんて喜んで牙を抜いたら、忘れた頃に鬼が蘇るんだ。そんなことになっちゃいけない。あってはならないんだ」
炭治郎は善逸の言葉に目を伏せ、そして体の中の空気を吐ききるとゆっくり顔を上げて善逸を見た。しかしまだ覚悟が決まらないのか揺らめいている。覚悟を決めた竈門炭治郎の顔はこんなもんじゃないと、善逸はさらに言葉を重ねた。
「炭治郎、俺を鬼にしろ。そしてお前はここで、この藤襲山で鬼の俺を監視し続けろ。俺はお前みたいにすごい鬼になる才能はないだろうから、きっと藤の花を嫌う。それできっと、我を忘れて人を喰いたがるだろうな。だから炭治郎。俺をここに閉じ込めてどこにも行けないようにし続けるんだ」
「……善逸を鬼にして、生きるのか……?ヒトを食えなくて苦しむ善逸を見ながら、長い時を過ごすのか?」
「そうだよ。お前は苦しむ俺を見て苦しむ。俺は人を襲う食えなくて腹減って苦しむ。……まあ、お前由来の鬼になるから、もしかしたら俺も人を食わなくても平気かもしれないけど……期待しすぎはよくないな」
そもそも鬼になれるのかという問題もあるが、そこを考えるとどうにもできないので善逸は見ないフリをする。もはや最後に取れる手はこれしかない。きっともっと色んな方法があるのだろうが、善逸は自分は馬鹿だからと方法を探るのはやめたのだ。自分から炭治郎を取り上げないでくれ。自分の知らないところで炭治郎を始末するのをやめてくれ。
善逸の気持ちはきっと、ずっとこれだった。あの日、住みなれた家を燃やし、二人で逃げるように旅立ったのはそれが理由だ。炭治郎を誰かに、自分の納得いかない方法で殺されるのが嫌だったのだ。善逸はずーっとずーっと炭治郎への気持ちに名前がつけられない。
生きてきた中で、炭治郎にしか持ち得ない感情と気持ちだからこそ、名前がつけられないし、今も名前がつけられない。
「炭治郎」
「……善逸……」
「俺はお前を人喰い鬼にしたくない。友達としても、家族としても……爺ちゃんの教えを胸に抱える元鬼殺隊士としても。お前を俺の中に閉じ込めるよ。お前が人を喰わないよう、鬼になってもお前の側で生き続けるよ。だからお前も鬼殺隊士だったなら、鬼の俺が人を喰わないように防ぎ続けろ。自我を保て。人間の心を見失うな。……俺を人喰い鬼に絶対するな」
そう言って少年の身体の炭治郎を抱きしめた。炭治郎は善逸の腕の中でぶるりと震えて、そしてゆっくり腕を抱きしめ返してくる。そういえばこうして二人きりで、正面から抱きしめ合うのは初めてだなと善逸はぼんやりと思う。
(炭治郎、炭治郎)
善逸は泣いているのか少し震えている炭治郎を宥めるように背中を撫でてやる。ぎゅうっと抱きついてくる炭治郎を、この感触を忘れぬようにと善逸も少し抱きしめる力を強くした。
「……大丈夫だよ炭治郎。この戦いは終わりが見えてる」
「……終わり?」
「うん。人間が絶滅したら俺たちの勝ちだ。鬼が喰いたがる人間がいないんだからな」
「……持久戦だな」
「我慢比べは得意だろ?竈門家長男」
「……ふふっ。……勿論だ!!」
パッと顔を上げてそう言った炭治郎は笑っていた。それが心からの笑顔ではないのを善逸は分かっていたけど、指摘はしない。不安に苛まれた音の中でも、炭治郎の目には光がある。善逸が知っている覚悟を決めた竈門炭治郎だ。
「んじゃ、ぐずぐずすると良くないからパパッとやろうぜ。……痛いのかなぁ?」
「うーん。多分、触手でブスッとやってブシャーって感じだけど……」
「いやー!!音が怖いっ!!」
「大丈夫だ!優しくする!」
「ひいいいいん!本当だな炭治郎おおおおお!!嘘だったら許さないからな!!」
「分かってる分かってる。大丈夫だ。俺に任せておけ」
はははっと自分の口から自然に笑みが溢れたのに、炭治郎はびっくりしたような顔をする。そして切なげに目を細めて微笑むとゆっくりと善逸の手を取った。少しカサついた善逸の手は、少し皺が出てきている。その手を炭治郎は大切そうに撫でて、そして自分の額をあて、そっと柔らかい唇を手の甲に押し当てた。
善逸の耳に届く炭治郎の音。その気持ちに名前をつけることはできる。自分の気持ちにはできないのに。
(ああ、でも……俺も鬼になって、炭治郎と一緒に最後の戦いを勝ち抜いたら……そしたら分かるかな)
炭治郎は善逸の手の甲に恭しく口付け、そして手を離す。一歩、二歩と後ろに下がり善逸と少しだけ距離を取って笑った。
「善逸」
呼ばれた名前には、きっと、竈門炭治郎の全てが籠もっていた。
****
「あっっっつい」
「そうだなぁ。夏だしなぁ」
炭治郎は寝転がっていた布団から起き上がると、扇風機に手を伸ばした。大家さんから譲り受けた年季の入っている扇風機は羽が少しガタガタいっているがまだ動く。それを善逸の側に置いてやると、パンツ一枚の姿の善逸が布団の上で大の字になった。先ほどまでは横に同じくパンツ一枚の炭治郎が寝転がっていたので手足を開けなかったのだ。
全身で風を浴びる善逸を横目に、炭治郎は氷が溶けて温くなった麦茶を喉に通す。別に喉は乾いていないし、涼も取れないから意味がない麦茶だがそこにあれば手が伸びるのが人情だろう。先ほどまで夏の最中、締め切ったエアコンもない部屋で善逸と熱を交わし合っていたのだ。心理的には喉は渇いている。
「あ、いいなー。俺も飲みたい」
「温いから新しいの持ってくるよ。待ってろ」
「うーん」
善逸は気怠いような仕草を見せたが、実際には気怠さなんてあるわけがない。何しろ基本的には疲れ知らずの肉体だ。とはいえ、疲れはなくても眠気はくるのだが。炭治郎と善逸は食事からの栄養を必要としない代わり、睡眠によって生命を維持している。善逸はそれに加えてあるものを定期的に摂取する必要があるが。
炭治郎はこれまた貰い物の冷凍庫を開けてコップに氷を放り込む。そして今度は冷蔵庫を開けて麦茶の入ったポットを取り出した。そのついでに、朝に仕込んでおいたハンバーグのタネの様子をみる。豚と混ぜ合わせて作った『特製の合い挽き肉』はいい感じに油が出てきていた。少し早いが今晩は夜に出かける予定なので、夕飯の支度をそろそろ始めるかと炭治郎は入れたての冷たい麦茶を一口だけ飲んでから善逸の元へと戻る。
「善逸、新しい麦茶」
「うーん。ありがと」
「眠いか?夜に出かける予定だけど……ひと眠りするか?」
「そうしようかなぁ。急ぐわけでもないしね」
「まあ、明日の開演時間までに間に合えばいいわけだしな」
炭治郎は麦茶を飲んで動く善逸の喉仏をじっと見つめながら、手探りでTシャツを探した。正直言うと足りないなぁとか、もっとしたいなぁという気もあるが、部屋の長押(なげし)にハンガーと一緒に引っ掛けてあるワンピースをチラ見して溜息をつく。久しぶりに善逸が女物の服を出してきている。これが何を意味するかといえば、善逸が明日をとても楽しみにしているということだ。
(……善逸が女の子になるのって何年ぶりだ?前にネズミーランドに行った時以来か?)
炭治郎はワンピースを見ながら思い出す。あの時のレジャー……いやデートも楽しかったなと。そしてあの時も楽しかったのだから、今回もきっと楽しいと炭治郎はワンピースを見ながら「ふふふ」と笑った。
「なーにワンピース見てにやけてんだよ。この助平」
「す、助平!?違うぞ!善逸は明日このワンピースを着るのを楽しみにしてるんだなと思ってだなぁ!」
「いや別にワンピース着るのを楽しみにはしてないわ。普通にYKJ(ユニバーサル・キメツ・ジャパン)を楽しみにしてるだけよ。女になるのは、ほら、男同士でキャッキャウフフしてたら寒いだろ?可哀想な目で見てくるカップルとか、彼女連れてる男にマウント取られるの嫌だろ?」
「物凄い被害妄想だな。誰も俺たちのことなんて気にしてないと思うぞ?」
Tシャツを着て、ハーフパンツを履いた炭治郎が呆れたようにそう言えば、善逸はムッと唇を尖らせる。それにキスしたいなあと思うが、それをしたら最後、夜まで離してやれなくなるかもしれない。そうなると善逸はきっと眠ってしまうだろう。背負って移動してもいいけれど、そうなると翌日に自分が眠くなるかもしれないと炭治郎はやはり我慢することに決めた。善逸は明日を楽しみにして、節約の為に夏の暑い中でもエアコンをつけずに頑張っていたのだから、台無しにしてはいけない。
そんな炭治郎の覚悟なんてつゆ知らずなのか、善逸はペタペタと衣装ケースの前に移動すると引き出しを引いてゴソゴソと何かを探している。何をしているのだろうと思いながら、炭治郎は汚れたタオルや丸まって転がっているティッシュペーパーを片付け始めた。
「全くそうやって炭治郎は気取ってるけどさあ。俺は知ってるんだぜ?炭治郎が女の子になった俺にデレデレなこと。……じゃじゃーん!」
「え?な、なんだそれは!?」
「なにってマイクロビキニ」
「マイクロビキニ!?」
「うん。通販で買ってみたんだよ。布が少ないからか、めちゃくちゃ安かった」
善逸がそう言って見せてきたのは殆ど紐であり、到底水着には見えない代物だ。炭治郎は真っ赤になりながら、白いそのマイクロビキニをじっと見つめる。
「そ、そんなのどうするんだ?」
「向こうでホテルに泊まるだろ?その時に着ようかなあって」
「それでプールに行くのか!?」
「まさか!そんなの痴女じゃねぇかよ!普通にホテルの部屋で着るの!!……折角、久しぶりの旅行なんだし、盛り上がりそうだろ?」
そう言って二ヒヒと笑う善逸に炭治郎は脱力をする。本当に善逸はどうしようもないと思う。しかし楽しそうに肉体を変化させているのを悪いとは思わない。炭治郎は溜息を吐いて立ち上がると、のそのそとキッチンに向かう。そして冷蔵庫から野菜やハンバーグの種を取り出した。
「ん?そういえば今日の夕飯なに?」
「特製炭治郎ハンバーグだ」
「げっ」
「そろそろ摂取しないといけない時期だからな」
「げーー!!こっそり出してくれよ!!」
「こっそり出しても合い挽き肉のたびにどうせ確認してくるじゃないか」
「そりゃそうだろ!!後から知るのと覚悟して喰うのじゃ違うんだよ!!」
「だから教えてるんだろう?今日は『特製炭治郎ハンバーグ』だ」
「うあああああー!!正気度が減るっ!!」
ゴロゴロと騒ぐ善逸を無視して、炭治郎は簡単に付け合わせのサラダを作り、朝に大量に作った味噌汁を火にかけると、熱したフライパンに油をひいて、そこにそっとハンバーグを乗せた。ジュウウウと音を立てる『特製炭治郎ハンバーグ』になにも感じないのだから、自分はやはり鬼だなと炭治郎は思った。
大正から昭和、昭和から平成。そして平成から令和。炭治郎と善逸は人間からすれば短くない時を共に過ごしていた。各地を転々と流れたこともあるが、今はここ立川市の川沿いにある六畳一間のアパートで暮らしている。男同士の同居であるが、町内会のイベントやボランティア活動にも二人で参加しているのでご近所からは「若いのに偉いわぁ」と評判であった。そう。若いのに。
炭治郎と善逸は大正どころではなく、明治生まれだ。明治生まれが若いわけない。しかし二人はどう見ても二十代前半の青年である。時たま二十代前半の女の子も現れるが、基本的には青年二人だ。
どういうことかといえば、なんのことはない。炭治郎は善逸を鬼にし、善逸は問題なく鬼になったのだ。令和から遡ること何十年も前、藤襲山で二人は鬼として生き抜くことを決めた。炭治郎は善逸が鬼として飢餓と戦うのかと悲しみを感じつつも決断した。善逸を道連れ、いや、善逸と共に進むことを決断した。どんなに苦しくとも、自分からは決して投げ出さないと決めた。それが善逸への信頼と期待とそして全てを差し出してくれた気持ちへの答えになると思ったからだ。そして——。
炭治郎の血を取り込んだ善逸はあっという間に目を開けた。そしてその時には鬼になっていた。血肉を欲しがるなんて衝動もなく、炭治郎と同じぐ瞳孔が縦長になった瞳をパチリパチリとしながら「あれ?俺、鬼になった?」と言った。それが善逸の鬼としての第一声であった。
結果として善逸は炭治郎と同じく睡眠で体力を回復させる鬼になったし、自我もそのままだった。何故だろうか。あんなに盛り上がったのに恥ずかしい。炭治郎と善逸は真っ赤な顔をしながら、さっきまで吐いていた決め台詞の数々に地面に転がりのたうち回った。
しかし問題なく鬼になったのだ。万々歳だ。二人はそうして恥ずかしがった後に喜び合った。恐らくであるが、善逸が人の血肉を欲しがらず、自我もしっかりあるのは炭治郎がそう願ったからであろう。珠世由来の愈史郎が自我を保っているのも、血を必要としないのも珠世が鬼にする際に『そうした』からだ。しかし珠世は努力と科学によって鬼を作り出したので、愈史郎と茶々丸しか鬼にはできなかった。それに対して炭治郎は鬼舞辻無惨から能力を引き継いでいる。鬼を作り出す能力がある。そしてそれは本人が『どうするか』という意識が大きく影響を与えるのだ。
つまり炭治郎は善逸をなるべく人間の頃と同じく維持したかったのでそうなったのだ。なので二人はそのまま藤襲山を降りて家に帰った。冷蔵庫に食材もあるから、問題ないなら腐る前に使いたい。勿体ない。
けれどそこから暫く経って問題が起きた。善逸が日に当れなくなったのだ。突然、外に出るのを怖がるようになった善逸に炭治郎は驚いた。何しろ昨日まで普通に太陽の下を駆け回っていたのだから。しかし善逸の鬼としての本能に逆らうべきではないと、炭治郎は善逸を昼間に連れ出すのを一切やめた。そしてどうしたらいいのかと悩んでいるうちに、ここでまさかの再会が二人に起きる。
「たぶん、体内にあった太陽に対する免疫がなくなったんだ。補充すれば良い」
二人にそう言ったのは本当に何十年ぶりに再会した愈史郎であった。どこで再会したかといえば、深夜に二人で遊びに出かけていた時のガードレール下のおでんの屋台だった。鉢合わせた時にはびっくりしたが、今までの経緯を話し、呆れられ、叱られ、そして同情されて助言を貰った。
要するに善逸は鬼になった時に炭治郎の血から太陽に対する免疫力を貰ったが、善逸自体はその免疫を自分で生成できないので定期的に炭治郎から投与する必要があるとのことだった。
血か。血でいいのか。そう問う二人に愈史郎は少し首を捻った。なんでも始祖の血を投入しすぎると自己崩壊や肉体が崩壊しやすくなる可能性もあるらしい。試してみてもいいが、結果は保証できないと言われて炭治郎と善逸はやめておくことにした。無茶はよくない。善逸が死んだら大変なことになる。
「血を直接は強すぎるから、効果を落とす為に間接的に摂取するのはどうだ?」
「「間接的?」」
「加工して、食事で摂取しろ」
そこからは暫くの間は地獄の有様であった。善逸に自分の肉を食べさせようとする炭治郎。それを拒否する善逸。二人はドタバタと暴れまわって争った。無理やり指一本分を食わせたこともあるが、その後に善逸が泣きに泣き、「こんなの人間の食事じゃない!!」と叫んだので炭治郎も「確かにそうだな」と思った。そこから炭治郎は丁寧に肉を下ろし、丁寧に焼いたり刻んだり捏ねたり丸めたり小麦の皮で包んで蒸したりとか手を替え品を替えて『特製炭治郎料理』を二ヶ月に一度、善逸に振る舞っている。
善逸は相変わらず泣きながら食べるが、これにより日の下にまた出られる。炭治郎は満足げにそれを見つめて、そして二人で生きて、気がつけば令和の世になっていたというわけだ。
炭治郎は焼き上がったハンバーグを皿に乗せるとくるりと後ろを振り向く。善逸は不貞腐れたように布団に転がっていて、そっと覗き込めばスヤスヤと寝息を立てていた。炭治郎は起こすかどうか少しだけ迷いながら善逸をしげしげ眺めていると、枕元に先程のマイクロビキニなるものが転がっているのに気がついた。
「……マイクロビキニ……」
広げてみるがやはり紐すぎて、これを着用するとどうなるのか分からない。隠せるところなんてないのではないかと心配になる。いや、部屋で着ると言っていたし、盛り上がりそうだろと言っていたので、そういう用なのだろう。ならば隠せてなくても問題ないわけだなと炭治郎はひとまず納得した。
「女の子の善逸でマイクロビキニ……。男の姿でも見たいって言ったら引かれるだろうか?」
善逸は炭治郎が女の身体の善逸をより好んでいるのではないかと考えている節があるが、そんなことはない。炭治郎は善逸であれば男でも女でも構わない。もちろん、女の子になった善逸の柔らかい身体も好きだが、男のしなやかな筋肉も好きだ。どっちもいい。
「……善逸」
そっと呼んだ名前に善逸の口元がほんの少しだけ緩み、炭治郎はそれが嬉しくて、愛しくて善逸の金に輝く髪を撫でる。そして風でも入れるかと手を伸ばして、カラリと窓を開けた。
抜けるような青い空。今年もまた、何十回目の夏が来た。そしてこれからも夏は、二人に来続ける。
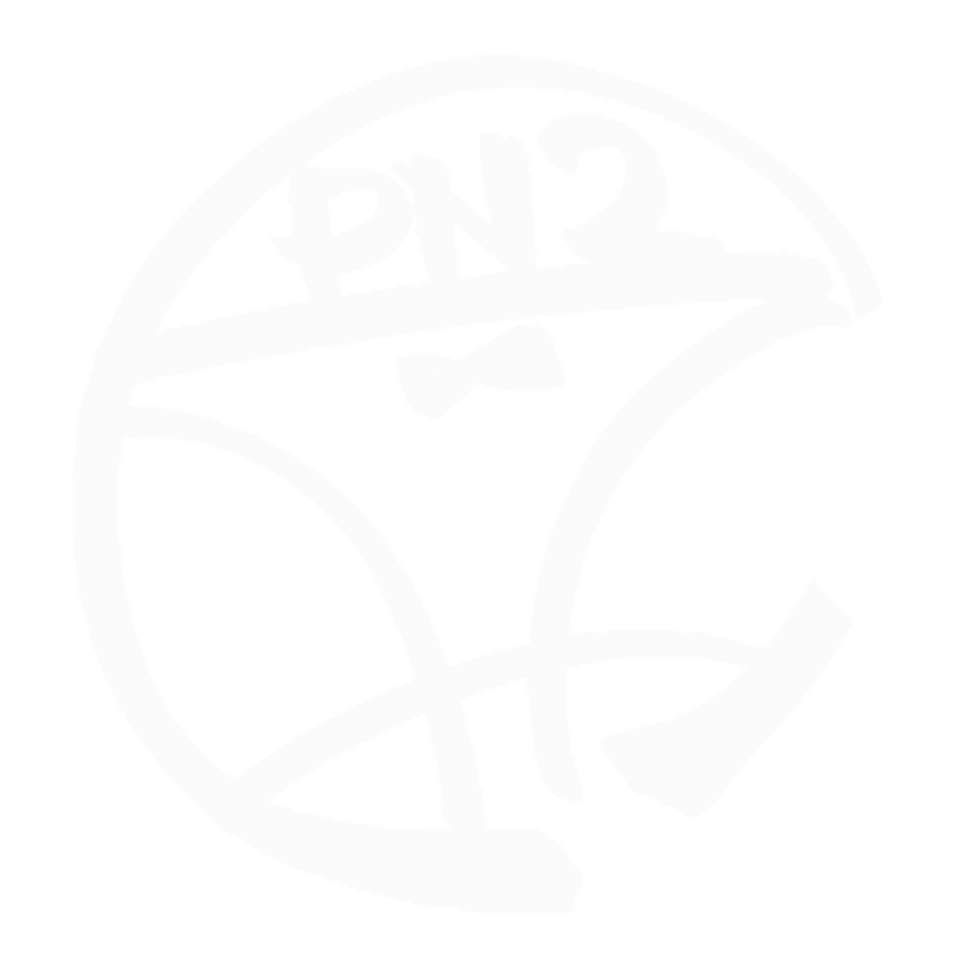



コメント