料理が上手い善逸くんと炭治郎とその他の人々。
約55000字/全年齢/原作軸・生存if
出汁巻き卵
単独任務を命からがら終わらせて、蝶屋敷に戻ってきて寝起きればものの見事に善逸は朝餉と昼餉を食いっぱぐれていた。もちろん、命をかけて鬼を狩って来た隊士が朝寝坊したからと食事を取り上げるような人達はこの蝶屋敷に居るはずがない。
現に主犯・・・・・・というか犯人の伊之助はアオイの怒りの剣幕に逃げおおせており、アオイたちは守りきれなかった食事の末路に善逸に頭を下げてくれた。しかもこれから何か拵えるなんてことまで言ってくれて、善逸は人の食事を盗み食いした伊之助に腹を立てても女の子たちには罪はない。しかも彼女たちは隊士の看護に回復訓練も行う忙しい人達だ。
善逸はひらりと手を振るといい顔をして自分でテキトーに拵えると言った。アオイたちは済まなそうにしながらも食材は好きに使っていいというので善逸は久しぶりに台所へと立つこととなった。
「あーくそ!伊之助のやつ!!俺の少ない楽しみを奪いやがって!!」
善逸は文句を言いながらも米を研ぎ、慣れた手つきで火を起こした。料理が好きか嫌いかと言われたら面倒なので嫌いと善逸は答える。しかし人は食わねば生きてはいけないし、孤児で奉公人として生きてきた善逸は上手い下手は別として最低限の衣食住のことはできる。要領が悪く、時間が掛かってもできることはできる。
それに育ての元にいた頃もある程度、修行が進んだ後の飯炊きは善逸の仕事だったのだ。隊士になってからは久しからずやっていなかったが、意外にも体は素直に動く。
じゃかじゃかと米がぶつかり合う音をぼんやり聴きながら米研ぎをして、土鍋に米をぶち込んでざっくりと水をいれる。善逸は人が作った飯が好きだ。愛を知らぬ孤児の善逸はこの美味しさは愛に似ているのかもしれないなどと他人の作った飯から考えてしまうクソ重たい人間でもあった。誰にも言ったことはないけど。それくらいしてないと愛情不足で人間不信になるからだ。
善逸はひとまず米はこれでよいと、卵を3つほど拝借して今度はだし巻き卵を作ろうと小鍋の前に立った。まずは出汁だ。善逸は沸騰したお湯にこれまた何となくの量で厚削りの鰹節を突っ込む。そして鰹節が揺らめき沈んでいくのを見ながら、ふつふつと鰹節が立てる音を聞いていた。ふつふつ、ぷつぷつ、くつくつ、ほんの僅かな差だが立てる音が変わっていく。湧いてくる灰汁をとりながら、善逸はある音になるのを待った。そして善逸は奉公先の料理人がいつも取り出していた時と同じ音になった瞬間、鰹出汁を布巾でこして取り出しだ。
「これでよし」
善逸は手早く卵を割ると出汁と混ぜ合わせ、熱せられた卵焼き鍋にジュウジュウと流し入れた。ふあーと薫るだし巻き卵の匂いに善逸はお腹空いたと思いながら音の時機を見計らって巻いていく。
そしてゆっくり色々とやっている間に米の音がいい感じになってきたと、善逸は火を止めて蒸らすことにした。この間に味噌汁作ろうと善逸が振り返ると、台所の入り口に中を伺う炭治郎の姿があって驚いた。
「うわっ、びっくりした。帰ってきたんだな炭治郎。怪我はないの?」
「ああ、怪我はないよ。今回は血鬼術もない鬼だったからな。・・・・・・善逸は今から昼餉か?」
「怪我ないなら良かった!・・・・・・そうなんだよ、伊之助に食われちまってさあ。あーあ、アオイちゃんの美味しいご飯食べたかったわ」
善逸がガンガンと大根とその葉をこれまたテキトーにしかし、火が早く通るように薄く切り、沸騰した出し汁に放りこんだ。背後には炭治郎がソワソワとしているのを感じて、善逸はどうしたのかと振り返る。すると炭治郎の腹からぐううううと情けない音がした。
「あれ?炭治郎も昼食べてないの?」
「じ、実はそうなんだ。早く皆んなに会いたいと思って特に何も食べずに帰途についてしまって・・・・・・」
腹がなったのを恥ずかしそうにする炭治郎に、善逸は後ろを振りかえった。味噌汁は十分にあるし、米はがっつり炊いてあるからおかずが少ないだけでまあいけるであろうと善逸は頷く。
「俺が作ったやつでいいなら食べる?オカズ少ないけど」
「いいのか!?」
「えっ。いいよ?いいから誘ってんだし」
「ありがとう善逸!!」
「はいはい。どーいたしまして。禰豆子ちゃんと刀、置いてきちゃいなよ」
「分かった」
いそいそと向かう炭治郎を見送り、善逸は出し汁に味噌を溶いた。そして蒸らし終わった米を簡単に塩握りにしていく。ひとつ、ふたつ、みっつ、よっつと握ったところで炭治郎が戻ってきた。ちょうど良いと、塩握りを乗せた盆を炭治郎に渡し、善逸はもう一つの盆に味噌汁とだし巻き卵、そして漬物を乗せた。
「んじゃ、部屋行こうぜ」
「ああ!」
ニコニコと笑い、楽しそうに嬉しそうな音を立てている。そんなに腹減ってたのかぁと善逸はなんだか申し訳ない気持ちになった。あまりにもテキトーに作りすぎたからだ。
「なんか・・・ごめんな炭治郎」
「ん?何がだ?」
「いや、期待しないでって意味」
「?」
炭治郎はよく分かってないようで、首を傾げている。善逸達に貸し出されている部屋はそう遠くもなかったので飯が冷める間もなく到着した。禰豆子は続き間に布団を敷いて寝かされているようで、善逸はそちらに耳を傾けながら禰豆子の眠りが安らかであることにホッとする。
「頂いてもいいだろうか?」
「ん?あ、どうぞどうぞ」
ソワソワとする炭治郎に善逸は手をひらりと揺らめかせて箸を勧めた。炭治郎はパンっと手を合わせると「頂きます!」と丁寧に挨拶をする。善逸もそれに倣い、手を合わせると「頂きまーす」と告げた。
(そういや、誰かに食べてもらうの久しぶりだわ)
育ての元で修行していた時はもちろん、師匠と兄弟子に振る舞っていた。師匠は厳しくも優しい人であったため、善逸の飯を褒めてくれていたが、兄弟子は文句は言わなかったが褒めたこともなかった。それゆえ善逸は自分の料理の腕前は良くもなければ悪くもない、と評価している。
対して炭治郎は炭焼きの家の息子ゆえに飯炊きは得意としていると自身で言っている。自分で誇るくらいになのだから、確かに炭治郎の料理の腕前は良かった。善逸は炭治郎の握り飯は今まで食べた握り飯の中で一等だと思っているし、ほかの料理も美味いと感じていた。
そんな料理が得意な炭治郎に、果たして自分の料理は口に合うのだろうかと善逸は心配になるが、炭治郎は正しくいい男なので人が作ったものに文句を言うことはないだろう。しかし善逸は人の感情を音で捉えてしまうゆえに炭治郎が文句を言わずともガッカリした音をさせたら嫌だなあと少しばかり怖い気持ちを抱えていた。
して、果たして。
炭治郎は善逸の作った卵焼きを箸で割るとひと口頬張った。その時の炭治郎の音と言ったら!朝にはお日様の光を浴びて花開く蕾のような音であった!
というか顔からもパアアアっと音がしているように見える。まさに顔を輝かせた炭治郎は善逸を真正面に捉えると大きな声で名前を呼んだ。それに握り飯を齧っていた善逸は喉に詰まりそうになる。
「善逸!!」
「ふぁい!」
「美味しいぞ!!すごい!美味しい!」
「あ、そーお?よ、良かったね・・・」
「ああ!良かった!嬉しいぞ!」
炭治郎はそう言うと目を輝かせて味噌汁を啜る。そして肩から力を抜きながら、思わずと言うように「美味しい・・・優しい味がする。匂いも美味しい・・・・・・」などと言っている。
その姿を見ながら、なんともまあ珍しいと善逸は思った。食事をしきりに美味しいなぁと言いながら食べるのは専ら善逸の役目だ。炭治郎は美味そうに食べる善逸や勢いよく食べる伊之助をニコニコと見ているばかりで飯の感想をあまり言う方ではない。もちろん善逸の「美味しいなあ」という言葉に「そうだな!」と同意を返すことはあるけれども。
「すごい、美味しい・・・・・・。久々に感動したかも・・・・・・」
なんてぶつぶつ言いながらもダラシない顔で食べる炭治郎に善逸は相当疲れてて腹減ってたんだなぁと思った。じゃなければテキトーに作った己の料理にこんなに感動するはずがないからだ。
「善逸は料理が上手かったんだなあ」
「いや、ふつー以下よ」
「そんなことないぞ!この出汁とかびっくりするくらい美味しいしいい匂いがする!蝶屋敷に帰ってきて、ついつい台所に引き寄せられてしまうくらいにいい匂いがしていたんだ!!」
「そんなに腹空くまで何も食べないのよくないぞ。今度からはちゃんと道中でなんか食いなね?」
呆れたようにいう善逸に炭治郎は困った顔をしたが料理が冷める前にと握り飯に齧り付いた。ふわっとした米粒にちょうど良い火加減で炊かれていることを炭焼きの家の息子である炭治郎はしっかりと感じ取った。間違いなく、善逸は料理が上手い。
「善逸の料理は毎日食べたいくらい美味しいぞ」
「そういうのは女の子に頼みなさいな」
善逸は無感動に食事を終えると手を合わせる。ごちそーさまでした」と雑に唱えられる挨拶に炭治郎は全くもって己の感動が善逸に伝わっていないなあと残念に思った。
カツ丼
「俺も紋逸の飯食いたい」
炭治郎と善逸と伊之助の3人で無事に合同任務を終えて、それじゃあちと早いけれど昼飯食べてから蝶屋敷に帰ろうということになったら、少し後ろにいた伊之助が冒頭の台詞を口にした。
善逸が「はあ?」と言えば、伊之助は表情がわからぬ筈の猪頭をかぶっているにも関わらず、ぶすくれたような、拗ねたような様子に見えた。そして「権八郎にだけ食わせたんだろ!!ずりーぞ!!」と騒ぎ出す。
なんの話だと思う善逸だが、炭治郎が「ほら、この前の卵焼きだ」と言うのに思い出した。あったなそんなこと。
「いやあれはお前が俺の昼餉を勝手に食ったからだろ!!」
「うるせえ!!親分の俺にも飯食わせろ!!作れ紋逸!!」
伊之助はそう言うと作るって言わなきゃ動かないぞというかのように往来に座り込んでしまう。駄々をこねる子供のようなその姿に善逸はげんなりして炭治郎が何とかしてくれないかと期待して振り返れば、当の炭治郎は善逸に期待する目を向けていた。
その目と炭治郎の期待をする心音に、つまりは炭治郎も善逸に飯を作れと言っているということだと善逸は理解した。
「そもそもなんで伊之助は飯のこと知ってんのさ?」
「・・・・・・あまりにも美味かったから、その、あちこちに自慢して回ってしまったんだ」
「はああああ!?厚焼き卵と握り飯と大根の味噌汁をお前は自慢してまわったのか!?馬鹿じゃないの!?そんな大層なもんでもないわ!」
「だ、だが本当に美味しかったんだ!確かにちょっと優越感はあったかもしれないが・・・・・・その、どうしても言って回りたくて」
「とんでもねぇ炭治郎だ!!やめて!?大した腕前じゃないんだから!!変に期待されても困る!!」
「何でもいいから俺にも食わせろ!!権八郎だけなんてズリィだろーが!!」
ざわざわと遠巻きに見られてる現状に善逸はハッと冷静になった。あまり煩くすると警らが来てしまうかもしれない。こちとら帯刀していて、かつ半裸の猪頭の男がいるのだ、めちゃくちゃ怪しい。
「分かった!分かったよ!作ればいいんだろ!ひとまずここから離れよう!材料買って、そんで蝶屋敷に行くぞ!!あ!材料費くらいはお前らがもてよ!!」
善逸の言葉に炭治郎と伊之助が商店街の方へと喜んで駆けていく。その2人を追いかけながら、なぜこんな面倒なことにと善逸はがっくりと肩を落とした。
「何を作るんだ?」
「んん・・・。ちょっと小耳に挟んだ料理かな」
蝶屋敷に戻り、手当てを受け、湯あみを済ませた3人は小さい台所を借りた。蝶屋敷には大きい台所と小さな台所があり、大きな方は昼餉の片付けに追われているために邪魔になる。アオイ達に断りを入れた3人は小さい台所に3人で詰まっていた。小さいと言っても一般家庭としては普通の大きさだ。3人がおっ詰まっていても自由に動ける。
善逸は買ってきた材料を台の上に並べた。三つ葉、玉ねぎ、卵、小麦粉に生パン粉、そして厚めの豚肉だ。
炭治郎は材料を見つめながら、何の料理を作るのか検討がつかないようでじっと善逸を伺っている。伊之助に関しては壁際に座り込んでまだかまだかと体を揺すらせるばかりだ。
善逸は材料を見つめながら、はてさてと聞き及んだレシピなるものを思い出す。細かいところは置いておいて、下味をつけた豚肉に天ぷらの要領で小麦粉とパン粉をつけて揚げる筈だ。
「まあ、まずは米と出汁かな」
善逸はそう言うと炭治郎に土鍋を差し出したが、炭治郎はそれを見つめ、善逸を見つめ、申し訳なさそうな顔をしてずりずりと後ろに下がっていき静かに伊之助の横に正座した。つまりは手伝う気がないということだ。
「おい長男」
「すまない。けど俺は善逸が作った料理が食べたい」
苦渋の決断のように言う炭治郎に善逸は諦めた。まあ、なんでも背負いがちの炭治郎が珍しく甘えているということだろう。押し問答していると腹を空かせた伊之助が暴れかねないのでさっさと済ませるのが吉だ。
善逸は手早く米を研いで火にかけると、そのままの流れで湯を沸かす。そして湯を沸かしている間に豚肉に下味をつけ、溶き卵を用意すると小麦粉を豚肉に振りかけまぶした。
「味噌汁いる?」
「腹が膨れるならどっちでもいいぜ」
「俺は欲しい」
炭治郎が欲しいというので味噌汁用の鍋も用意する。湯が沸いた時点で善逸は鰹節を入れるとじいっとまた耳を済ませる。その様子を炭治郎もまたじいっと見ていた。
頃合いだと音で判断した善逸は少々危ない手つきで出汁をこすと、一部を味噌汁に、そして一部を別の器に取り分けた。
「出汁、味噌汁以外に何に使うんだ?」
「えーとね、割下につかう」
善逸は出汁を一旦置くと、腰に手を当てて次にどうするか考えた。善逸はあまり要領が良くないし、そも料理も別に手慣れているわけではないのだ。
「次はえっと、肉かな?」
善逸は米の火加減を調節しつつ、油をたっぷりと鍋に注いで火にかける。そして今度は小麦粉をまぶした豚肉を溶き卵に潜らせるとパン粉をつけていく。炭治郎と伊之助はだまーって善逸が料理をしているのを見ていた。何しろ邪魔すんなよという真剣な様子が見て取れる。あと油を使っているから騒いだら大変なことになる。
「よし!これで揚げるだけだ!ひえええ、怖えええ・・・・・・」
「善逸、火傷に気を付けろよ?」
「分かってる!」
善逸は肉を菜箸で挟むと油の中に入れた。パチパチと揚がる音が聞こえてきて、善逸は思わずふふっと口元を緩める。この音はわりと楽しいのだ。
善逸は3人分の肉を音が軽くなったところで取り出した。綺麗にカラッと揚がっているその肉の姿に伊之助が出来上がったかと立ち上がるが、「まだだよー」と善逸に言われて渋々腰を下ろす。
「ポークカツレツか?」
「いんや?違う料理だよ」
ポークカツレツは前にしのぶが振る舞ってくれたことがあり、食べ盛りの3人には非常に評判が良かった料理だ。しかし炭治郎の問いに否を示した善逸は米の火を落とすと味噌汁にワカメを入れて仕上げる。さらに揚がったポークカツレツをいくつかに等分して切った。
そして粗方の準備が整ったところで今度は大きなフライパンを取り出すとそこに出汁を入れて醤油やみりん、砂糖、玉ねぎを放り込んでいく。
「割下作ってるのか?」
「そう。なんか専用鍋で作る方がいいらしいけど・・・・・・ないし、手間だからこれでいいだろ」
善逸は割下が沸騰し始めるとそこにカラッと上がったポークカツレツを放り込んだ。
「わあ!!」
「何してんだ紋逸!?」
せっかくのポークカツレツがと立ち上がる2人を無視して、善逸は手早く溶き卵を作るとフライパンに流し入れた。焦げつかぬように揺らしながら、ハッと気がついて振り返る。
「伊之助!丼だして!炭治郎!!丼に米よそってくれ!!」
「おう!」
「分かった!」
「んでこっち持ってきて!!」
慌ただしく伊之助と炭治郎が動くなか、善逸は卵が立てる音を聞きながら三つ葉を追加してから数秒後、このくらいかと火を消した。少し卵がゆるい気もするが余熱で固まるだろう。
「よそえたぞ」
「ありがとね」
善逸は用意された丼にしなびたポークカツレツと卵を乗せていく。綺麗には乗せられなかったので若干、見栄えが悪いが料理屋じゃないのでご愛嬌だ。
そして味噌汁も装い、丼と一緒に並べて・・・・・・。
「よっし、完成だー!!」
「美味そうだな!いい匂いがする!」
「なかなかやるじゃねーか紋逸!!」
3人はさて実食するかと作業台に椅子を持ち寄る。部屋に戻るのも面倒だ。どのみちこの台所に来るものはいないのだからと手を合わせようとした時、ひょいと入り口から顔がのぞいた。
「あらあら、いい匂いがしますね」
そう言ったのは少しくたびれた様子の胡蝶しのぶだった。どうやら任務帰りのようだ。
「あ!しのぶさん!お疲れ様です!」
「お帰りなさい、えと、怪我ないですか?」
「しのぶが怪我するわけねーだろ」
3人が口々に言うのにしのぶはふふふっと笑った。そして台所に入り、料理がされていた形跡と3人の目の前にある料理に首を傾げる。
「昼餉に間に合わなかったのですか?」
「あ、いや、善逸の作ったものが食べたいなと思って・・・」
「権八郎が紋逸の料理が美味いっていうから作らせた!」
「過剰評価やめて?俺の腕前は普通です」
ふむふむとしのぶは頷くと丼を見る。どうやらポークカツレツを卵とじにしたもののようだ。
「これは?ポークカツレツの卵とじ煮ですか?」
「あ、そんな感じです。前にちょっと行った洋食店で賄いで作ってるらしくて・・・・・・店員さんがめっちゃ美味いって話してるのをこう・・・・・・盗み聞きしたというかなんというか」
なるほどとしのぶは頷く。つまりはどこぞのお店で賄いとして食べられている料理の話をまさしく善逸は聞きつけたということだろう。運良くレシピまで聞き取れるとは素晴らしい耳だ。
しのぶは見たことのない料理とそして仕事をして帰ってきたばかりという空腹感から珍しく緩んで気持ちが漏れ出てしまう。
「美味しそうですねぇ」
その言葉に・・・・・・というよりも音と匂いにしのぶの空腹と疲れを感じ取った善逸と炭治郎は急いで追加の丼を用意した。お米を丼に小ぶりに装い、3人のまだ手付かずであった丼から肉と卵と野菜を取り分ける。伊之助は2人の様子を見て立ち上がると残っていた味噌汁を器に入れた。
「どうぞしのぶさん!!」
「どうぞどうぞ!!俺の料理で本当に申し訳ないですけど!!」
「あらあら」
目の前で展開された一幕に、しのぶは少し迷ったけれど用意されてしまったのだから断る方が失礼だろうと素直に椅子を引いて腰掛けた。狭い台所で4人で顔を突き合わせているのが少しだけ面白い。
「早く食おうぜ!!」
「はいはい。そうしましょうかね」
「なんだか悪いですねぇ」
「ご飯はみんなで食べた方が美味いんだぞ!!知らねーのかしのぶ!」
「知ってるに決まってるだろ!何言ってんだよ!」
「2人ともその辺にして頂こう。しのぶさんを待たせてしまう」
炭治郎の言葉に善逸と伊之助がしのぶをみる。しのぶが箸を取るのを待っているようで、これは待たせてはいけないとしのぶは素直に手を合わせた。
「それでは、頂きます」
「「「いただきます」」」
出汁茶漬け
静まりかえった蝶屋敷の廊下をアオイは疲れた顔で歩いていた。蝶屋敷は任務で傷ついた隊士達がよく運び込まれてくる場所であるが、この連日は凄かった。同じ任務についていた隊士たちが重症の状態で次々と運び込まれてくる。任務自体は柱が赴くことで筒がなく鬼は討伐されたようだが、鬼が消えても怪我は治らない。
蝶屋敷の看護師たちはそれこそ必死に手当てをした。容態が安定しない人もいて寝る間も食事も惜しんでの戦いだった。それが今日、ようやく落ち着いたのだ。なほ、すみ、きよや他の看護師達は早く上がらせて深夜の交代まではアオイがひとりで病室を見回った。そしてやっと交代の時間が来てたので休もうと、こうして病棟から住居棟への廊下を歩いているのだが・・・・・・。
(お腹空いた・・・・・・)
食事の時間をすっかりと逃してしまったアオイは空きっ腹で歩いていた。身体は簡単に拭いたのでこのまま眠ってもいいのだが、いかんせんお腹が過ぎていてだめだ。疲れているのに眠気がこない。連日の看護に興奮しているのかもしれない。それに指先も足先も冷たくて、この冷えのままでは眠れない。
(せめて温かいお茶でも飲んで寝よう・・・・・・)
食事を用意する元気などないし、もう食事の時間も逸脱しすぎている。身体を温かめてやれば眠れるかもしれないと住居棟の小さな台所へと足を向ける。するとふんわりと柔らかい出汁のいい匂いが漂ってきた。
(誰かいる・・・・・・?)
アオイがそっと台所を覗くと金髪を持つ男が釜の前に立っていた。漂ってくる出汁の匂いは彼のものかとアオイは納得する。金髪の男、我妻善逸は女好きでややふしだらで、薬が苦いと転がり周り、鬼が怖いと泣き喚きながら任務に赴きほぼ無傷で帰ってくる変な奴だった。
しかしそんな男も特技があるようで彼は存外料理上手であった。耳の良さからあちこちで秘伝のレシピやら秘密の賄いの作り方を聞き及んできて、そしてそれを再現できる程度の才があった。
料理中には音の変わる瞬間があるという。もちろん、それはアオイも分かってはいるが善逸のいう音の変わる瞬間とは常人では分からない領域であるのは確かだ。しかし彼はそれが明確にわかるため、料理人が時間を掛け研鑽した結果で到達できることを耳だけでやってのけてしまうのだ。
それの証左として善逸の取る鰹出汁はとんでもなく透き通った味がして美味しい。アオイは料亭の味など知らないがきっとこういったものなのだろう。
「あ!アオイちゃん!仕事終わったの?お疲れ様?!」
何を言わずとも振り返った善逸が、アオイを見てデレデレと様相を崩す。それを見てアオイが顔を歪めれば善逸は「ひえ、声かけただけで怒んないでよぉ!」と眉根を下げた。
確かにいくら善逸の日頃の行いが悪いとしても、仕事上がりの労りの言葉を掛けてくれた相手に今のは感じが悪いなとアオイは反省した。なので通り過ぎることはなく一歩、中へとはいる。
「夜食ですか?夕餉の量が足りませんでしたか?」
善逸は胡蝶しのぶ預かりとなっている竈門兄妹の友人隊士だ。しのぶの方針として我妻善逸と嘴平伊之助は竈門兄妹の精神上の安定の為にもまとめた方がいいだろうとして同じく蝶屋敷を間借りして活動している。
となれば蝶屋敷から食事は支給ということになるが、彼らは活動量が多くさらに育ち盛りだ。食事が足りずに筋肉を減らすなどもってのほか。量が足りないのならば必ず申告してもらわねばならない。そういったつもりでアオイが聞けば、善逸は「違う違う」と手を振った。
「炭治郎が任務から帰ってくるんだって。さっき鴉が来たんだよ。だからお腹空いてるかなって思って」
「炭治郎さんが・・・・・・。そうですか。それならいいんです」
炭治郎や伊之助が善逸に何某かの手料理を強請ることは最近の蝶屋敷ではよく知れていることだった。アオイは味噌汁に使う出汁くらいしか善逸の腕前を体験したことがないが、善逸の料理を食べたことがある胡蝶しのぶは「結構な腕前でした」と優しくにっこりと笑ったので仲の良い友人たる二人が手料理を強請るのは不思議なことではないだろう。
けれど善逸は「野郎共に振る舞う腕も暇もない」とにべもなく。あまり腕を振るう機会はないらしい。しかしもしかしたら、夜遅くに任務から戻ってくる友人達にはこうして腕を振る舞っているのかもしれないとアオイは思った。
「アオイちゃんはどうしたの?」
「え、あ!いえ、そのお茶を飲んで身体を温めてから寝ようかと・・・・・・」
「あ、そうなの?じゃあそこに座ってなよ。お茶くらい俺が淹れるよ!」
ほらほらと善逸に勧められて、アオイは戸惑いながらも作業台の横の椅子に腰かけた。押し問答するほどの余力はないし、善逸はまだ料理途中のようだから火の周りをウロウロするのも邪魔になるかもしれないと思ったからだ。
アオイが椅子に腰をかけると吸い付いてしまうように力が抜ける。まずい、立てないかもなんて思いながらぼんやりと作業台を見つめる。
今日は本当に疲れたのだ。けれどまだ眠気はこない。身体中が気怠い感覚はあるけれど、頭のどこかが爛々としており目を閉じても悲痛な声を上げている隊士達の姿が脳裏に浮かぶ。
傷だらけの隊士達を見るたびにアオイは己の情けなさを感じる。怖い、鬼が怖い、死にたくないとそればかりが体を支配して、最終選別に生き残ったのに剣士になれなかった自分が情けない。
鬼に強い恨みをもって、誰かの為に頑張る人達の方が情けない自分よりもどんどんと居なくなっていくのが申し訳ない。
ここにいる善逸も鬼が怖い、行きたくない、死んでしまうとみっともなく震えて泣いているのに叩き出されるようにしてでも最後は任務に行く。そして帰ってくる。
彼が強いことをアオイは知っている。最初の機能回復訓練で、訓練が辛いと逃げ出したのをなんだあいつはと思ったが、遠回りしても善逸は力を身につけた。しのぶの継子のカナヲと同じ高みにいるのだ。不真面目でも、怖いと泣いても彼は強い。そして何よりも彼は怖くても震えてもちゃんと足が前に進むのだ。己とは全然違う。
(・・・・・・本当は情けない奴だなんて言う資格、私にはない・・・・・・。格好つけるばかりの私より情けなく泣いても、ちゃんと鬼を倒してくる善逸さんの方がずっとずっと凄い人だもの・・・・・・)
アオイは正直言って善逸が苦手だ。女にデレデレする軟派なところが性に合わないのもあるが、我妻善逸はアオイの劣等感を刺激するのだ。鬼を倒したいと剣士を目指したのに蓋を開けたら恐怖で一歩も動けない自分に対して、善逸は鬼を倒すために剣士になったわけでもなく、アオイが恥ずかしくて口にできない怖いと言う言葉を照らいもなく口にする、大声で叫ぶ、しかし鬼は倒す。
(私、本当に情けない・・・・・・)
アオイは真面目な気質ゆえによく自己嫌悪に陥る。しかしそれは誰にも見せないで、主に1人きりの時にしていたが今日は疲れとそして劣等感を刺激する善逸が側にいるので珍しく漏れ出していた。
作業台に肘をついて手の甲に額を当てて俯いていると、ふわりと良い匂いがしてアオイの目の前にことりと小ぶりな丼が置かれた。
「はい、お待ちどうさま」
「・・・・・・え?」
アオイの目の前にあるのは出汁をたっぷりと淹れと『出汁茶漬け』であった。具材として解された鮭と塩昆布がのっている。そして少量振りかけられている胡麻の香りが食欲をそそる。
「お茶はお茶でもお茶漬け?なんてね!」
「駄洒落ですね」
「まあまあ、炭治郎の用意するついでだし、材料余ってたからさ。少しお腹に何か入れた方がきっとよく眠れるよ」
ニコニコと笑う善逸に見破られているとアオイは理解した。しかし目の前の出汁茶漬けは本当に美味しそうだし、今にもお腹が鳴りそうだ。それにせっかく作ってくれたのだからとアオイはそっと匙を取った。
「・・・・・・では、頂きます」
「どうぞどうぞ!」
善逸はそう言うと今度こそ薬缶を片手に火へと向かっていった。この女性には優しい男のことだ。お茶を淹れてくれるのだろう。
アオイは出汁茶漬けを掬うとふぅーっとひとつ吹き冷ましてから口に入れた。優しく繊細な出汁の味が鼻を抜け、少し塩気のある昆布と鮭の味が後からくる。
ほうっとひとつ息を吐いたアオイは手が勝手に進むのに任せて茶漬けを口に運んだ。減ってくる茶漬けに少し残念に思いながらも腹はくちてくる。ほんの少しだけ物足りないかもという具合なのはこれから眠るアオイを思って加減をしてくれているのだろう。
「はい、お茶もどうぞ」
「・・・ありがとうございます」
アオイが食べ終わった頃を見計らって差し出されたぬるめの玄米茶。普段からこれくらい気遣いができればいいのにと思いながらもアオイはグッと口の中の味を流した。
「・・・美味しかったです」
「そう?良かった?!よく眠れるといいね!」
善逸の言葉にアオイは自然に笑みが溢れた。食べ終わった丼と湯呑みを片付けなければと立ち上がれば、善逸がすっとそれらを引き受ける。ニコニコと笑う姿に参ったなぁと思いながらも厚意に甘えることにした。
「暖かくして眠ってね」
「はい。善逸さんもあまり夜更かししないでくださいね」
「うん。炭治郎に食べさせたら寝るから」
そう言ってアオイは善逸に見送られて台所を出た。胃の腑からほこほこと湯気が出ているみたく温かい。いつの間にか指先も暖かく、布団に入ればすぐに眠れそうだと今は思う。
廊下を出て、住居側の玄関に差し掛かるとガラス戸の向こうに人影があった。庭に隠している鍵を使って扉を開け入るのは今、先ほどアオイが別れてきた我妻善逸の待ち人だった。
「炭治郎さん、お帰りなさい。ご無事で何よりです」
「ああ、アオイさん。ただいま。今回も何とかなりました」
笑ってそう言った炭治郎は?や手首に傷があるようだったがどれも手当てがなされていた。恐らく現地で軽傷のために隠から手当てを受けたのだろう。
「この前の任務で怪我を負った隊士たちは・・・・・・」
「皆さん、容態が安定しました。もう大丈夫です」
「そうか、良かった」
心底安心したような顔で笑った炭治郎にアオイも微笑む。しかし炭治郎はすぐにすんっと鼻を動かすとハッとした顔をしてソワリソワリと身動ぎをした。その様子を見て、アオイは「ははあ、なるほど」と納得する。さしもの竈門炭治郎も食欲には勝てぬらしいとアオイはすいっと人差し指を己が今きた廊下の方に向けた。
「善逸さん、お待ちですよ」
「そ、そうか!ありがとう!」
炭治郎は急いで足の泥を落とすといそいそと善逸が待つ台所の方へと向かった。その背中ははっきりと喜びを表していて、そういえば彼のために料理を拵えていた善逸も嬉しそうにしていたなと気がついた。
彼らだって喜び勇んで楽しくて鬼を狩っているのではない。たぶん、嘴平伊之助以外は・・・・・・。
やれることをやるしかない。アオイは結局、いつもそこに考えが落ち着く。だってウジウジ悩んでも何も結果は出せない。それなら一つでも多く手を動かすべきだ。できることで。しかしその考えに至るまでの時間は確かに今日はいつもよりも短かった。
アオイは炭治郎が忘れた戸締りを代わりにするとひとつ伸びをする。
「さて、私は寝ますか」
そう一人呟くと宛てがわれている自室へと向かう。アオイの耳は善逸ほど良くないが、廊下の向こうから密やかに、しかし楽しげな話し声が聞こえたような気がした。
紅葉弁当
秋の葉が完全に色づいたこの頃合い。朝はもうすっかり冬なのではと思うほどに冷え込む。善逸は寒い寒いと溢しながらも療養着に羽織を重ねて蝶屋敷の廊下を進んだ。
まだ夜が明けたばかりの真白い朝日の中、善逸は最近すっかり馴染みができた台所に立つ。冷えた水で手を洗い、米を研いでいつものように火にかける。その間に慣れてしまった手つきで出汁を取って、善逸が作るのに何故か炭治郎自慢の出し巻き卵を巻いていく。
「後は魚と・・・・・・昆布巻き、金平ごぼうっと・・・・・・」
前日にある程度の仕込みをしていたのでさして時間も掛からない。善逸は炊き上がった米を飯台に広げると簡単に団扇で扇いで粗熱を取り、鮭の解し身やゆかり、あとは出汁を取った後に残る鰹節で作った炒りカツオをそれぞれ混ぜ込んでいく。
「あちち・・・・・・。まだちょい熱いわ」
善逸はそう言いながらもどんどんと一口より少し大きい程の俵握りを作っていく。その数は五十以上にのぼる。
「よっし、後は詰めるだけだな」
善逸はそう言ってお重と、そして3つの曲げわっぱを棚から出した。
時刻はそろそろ朝餉の頃だった。
********
「おっ、竈門は弁当持参か」
「はい!出掛けに渡されたので!」
炭治郎は村田の言葉に元気に答えた。今日は鬼がいたという噂がある街を夕方から警らする任務に村田と共に当たることになっている。しかし鬼の活動が始まるまで時間があり、先じて街に到着した二人は腹ごしらえと紅葉が綺麗に生える川縁に腰を下ろしていた。村田はどこぞの店で握り飯を買ってきて、炭治郎は蝶屋敷を出る際に手渡された風呂敷に弁当が入っている。
炭治郎はまるで雀からもらったつづらを開けるようなウキウキした気持ちで風呂敷に指を掛ける。出てきた曲げわっぱからはわっぱの匂いとそして色々ないい匂いが香ってくる。蓋を開ける前なのに炭治郎がすーっと匂いを吸い込むのに隣に座る村田が笑った。
炭治郎はようやく蓋に手を掛けると勿体ぶるかのような速度で蓋を開けていく。隣からは「早く開けろよ」と呆れた声がするが、炭治郎は余韻を楽しみたいのだ。
「わぁ!」
「うわっ!手が込んでるなー!」
隣からは覗き込む村田の言うようにその弁当はとても手が込んでいた。かなり小ぶりな俵握りが6つ、それも2つずつ混ぜ込まれているものが違う。大葉によって仕切られた隣には西京焼きが入れられていて味噌の甘い匂いが食欲をそそる。そしてすっかり炭治郎の好物になってしまった出し巻き卵に、味がよく染みている昆布巻きに金平ごぼうとふんだんにおかずが詰まっていた。
「蝶屋敷ってこんなこともしてくれんの?」
「いえ、これは善逸の手製ですよ」
「はあ!?我妻の!?あいつこんな特技があったのか!?」
村田の驚きに炭治郎はまるで自分のことのように嬉しくなる。善逸は凄いんだぞ!強いだけじゃないんだ!と自慢したいような誇らしい気持ちになる。が、あちらこちらに自慢するのを善逸はいい顔をしないので、炭治郎は余計なことを言うのをぐっと我慢した。
炭治郎はまずはとばかりに出し巻き卵を口に入れた。解けるような柔らかさと出汁の風味が炭治郎の舌も鼻もくすぐっていく。
「うん!美味しい!」
パァッとにこやかにそう言う炭治郎に村田はじぃっと弁当箱を見た。彩り鮮やかな弁当箱は野郎に持たせるには随分と可愛らしい。現に炭治郎の風呂敷には追加の握り飯も入れられていてなんだこれといったところだ。しかしそんなことよりも確かに美味そうな弁当に村田は善逸の腕前が気になってしまった。
「我妻って料理できんだな」
「はい!善逸は料理上手ですよ!本人に自覚が全くないですし、面倒くさがってあまり奮ってくれないのですが、本当に美味しいです!毎日食べたいくらいです!」
「へえ」
炭治郎は自慢してはいけないというのもすっかり忘れて村田に善逸の料理がいかに美味しかを力説していく。その説明の大半が擬音なので村田にはどう凄いかさっぱり分からないが、まあ弁当を見れば腕前はわかる。
そしてあまり奮ってくれないという言葉に、善逸の料理は希少性が高いのだろうということも理解した。
となれば次にいつ目の前にあるか分からぬ機会というわけだ。村田は好奇心から炭治郎に「一口くれよ」と強請ってみた。炭治郎が毎日食いたいという味を知りたくなったゆえだった。しかし・・・・・・。
「えっ」
炭治郎は見たことないくらいに嫌そうな顔で固まった。そして目をギュッと瞑り、上を向いて下を向いて、また上を向いてゆっくり目を開けると歯を食いしばりながら震える手で村田に弁当を差し出してくる。
「・・・・・・どうぞ・・・・・・」
「食いにくいわ!!嫌なら嫌って言えよ!!怒らないから!!」
心底嫌だけど、しかし我慢しなければというのがめちゃくちゃに透けて見えている。村田は「やっぱりやめとくわ」と弁当を押し返せば炭治郎はあからさまにホッとした表情をした。そしてまた嬉しそうに今度は西京焼きを頬張るのに村田はやはりいいなぁと思った。
流石に後輩の顔を曇らせる選択はできないけれども。
****
「おらよ!!頼まれた届けもんだぜ!!」
「おう。ご苦労だったな」
伊之助がそう言って差し出した紙袋を宇髄は片手で受け取った。縁側に腰掛ける宇髄はちょいと伊之助を手招きすると駄賃とばかりおかきを手にのせてやる。
伊之助はおかきを受け取ると猪頭を脱ぎ、特に了承を取ることもなく宇髄の横に一人分を空けて並んで座った。ボリボリと貪るようにおかきを齧っていると雛鶴が盆に湯呑みを乗せてやってきた。それを伊之助に差し出す。
「伊之助君、お昼食べていく?」
「おお!そうだな、食ってけよ!お前はあれか、天ぷらが好きなんだったよな?」
雛鶴と宇髄の誘いを横に伊之助はぐいっと湯呑みを煽ると「いらねぇ!!」とはっきりくっきり言った。
「飯ならある!!」
伊之助は腰に括り付けていた風呂敷を外すと自慢げに中を見せた。そしてまた了解も取らずにその場で「いただくぜ!!」と手を合わせると蓋を取る。
出てきたのは炭治郎と同じ内容の弁当だ。しかし、炭治郎よりも振り回されることを想定して中身が崩れないようにギッチギチに詰め込まれている。
「あら、美味しそうなお弁当」
「そうだなぁ」
「俺様の子分が作ったんだぜ!!」
伊之助はそう言うと握り飯を一口で口に入れた。物足りない大きさであるがこれは仕方がないのだ。善逸は伊之助に「皆んなで揃いだから」と言っていた。それに伊之助には足りなかろうと炭治郎と同じく追加の握り飯を別に持たされている。
「炭治郎が作ったのか?あいつ小器用だなぁ」
「権八郎も飯作るのうめぇけど、これは紋逸が作ったやつだ」
味わっているのかいないのか、なかなかの速さでムシャムシャと平らげていく伊之助に宇髄も雛鶴も感心した。もちろん、伊之助ではなく善逸に。
「へぇ、あいつこんなん作れるんだな」
「そうですね。とても綺麗なお弁当だもの」
感心する二人に伊之助はふふんと笑った。子分が褒められるのは中々に気分がいい。それに親分にと献上されたものを褒められたのだ。尚のこと気分がいい。
「なんか女共が紅葉狩りしたいとか言ってんの聞いて、紋逸が弁当作ったんだよ。だから今頃、女どもは庭で皆んなで食ってる筈だぜ」
「ははっ。なるほど、だから手が込んでんのか。お前はそのお溢れ預かったわけだ」
冷やかす宇髄の言葉に伊之助はムッと眉を顰める。弁当を作ろうと思ったのは確かに蝶屋敷の女性陣に対してだろうが、伊之助へ弁当を差し出したのは決してお溢れなどではない。追加の握り飯が付いているように、そこには善逸の親愛がある。
「ちげえよ。俺たちはそれぞれ別の任務だからって紋逸が3つ弁当を用意したんだ。それぞれ違う場所で紅葉見ても弁当は同じだってあいつ言ってたぜ。だから俺たちは皆んなで紅葉狩りっつーのをしてるんだ」
伊之助はそう言うと庭にある見事な紅葉に目をやった。キラキラと輝くような伊之助の瞳に宇髄は「なんだよ、あいつも粋なことすんなぁ」と笑う。
伊之助は善逸手製の紅葉弁当も追加の握り飯も食べきると少し足りないと思いながら腹をさする。けれど胸はホワホワでいっぱいで、なんともむず痒い気持ちになった。
「今度作った飯食いに行くって善逸に言っとけ」
「ぜってーやだ」
すぐに飛んできた宇髄の拳をギリギリで躱すと伊之助は風呂敷に包まれた空の弁当を引っ掴んでひらひら落ちる紅葉の最中を走り出した。
****
「へっくし!・・・・・・あー・・・風邪かなぁ。ねぇ、チュン太郎。風邪かもしれないからやっぱり任務は・・・・・・ってごめんごめん!ちゃんと行くから!突かないで!!」
善逸は相棒の雀に突かれるのは勘弁と、慌てて弁当の蓋を開けた。そして米粒を取り出すと雀に差し出してやる。チュン太郎はコロリと機嫌が直ったようにツンツンと善逸の手のひらを突く。それがこそばゆいなぁなんて思いながら、善逸は俵握りを口に放り込んだ。
街道に座り込んだ善逸の頭上には見事な紅葉が風に揺れていた。
サンドウィッチ
「こっち仕上げー!」
「牛ステーキ2、入りまーす」
「前菜、席に出してー」
くるくるくるくる。目まぐるしく人が回る厨房で善逸は奥のグリルなる場所に立ってひたすら肉を返していた。ジュウジュウジュウジュウ、ジューウ。あ出来た、とヒョイと肉を持ち上げて皿に乗せれば目ざとく誰かが持っていって野菜を乗せてソースを掛けていく。そうすれば看板メニューのひとつである牛ステーキのできあがりである。
善逸はひたすらに肉を焼きながらなぜこんなことにと絶叫したかった。潜入捜査中なのでしないけれども。
遡ること1週間前、胡蝶しのぶにより任務が下された。なんでも特殊な場所での任務になるということで索敵能力が高く、そして場に順応できる必要があるとのことで善逸に声が掛かった。
善逸は「無理無理無理!無理ですよ!!俺に出来るわけない!!」と騒ぎ立てたが胡蝶しのぶが聞いてくれる筈もない。
任務の内容は帝國ホテルの厨房でシェフとして入り込み、鬼を探すというものだった。善逸はどういうこと?と首を傾げるがしのぶの説明によると帝國ホテルではここ数年間、定期的に人がいなくなったり死んだりするらしい。しかしそんなことが天下の帝国ホテルで起こったら大変な騒ぎになりそうだが、その失踪や死亡というのは帝国ホテル内で起こるのではなく、帝國ホテルを直近で利用した人間に起こるらしい。しかも失踪や死亡は必ず夜に発生し、必ず1人で帝國ホテルに宿泊していて、ルームサービスではなく、必ずホテル内のレストランを使用していることが隠の調査で分かった。
帝國ホテルはこの国を訪れる外国の要人なども泊まることがある、外交上で重要な場所だ。そこに鬼がもしいるのならば大変なことだと、国の上の方からも産屋敷家に圧力が掛かったらしい。
そんなの柱を出すべきではと善逸は思ったが、まずは調査目的で先遣隊を出すことになったらしい。2人1組で1人がレストラン内で調査担当、もう1人が館内の巡回と発見した場合は柱を待って共に討伐を。もちろん柱が到着する前に接触した場合は被害を出さないために迅速に討伐を。「柱は私が行きますから。善逸君を頼りにしてます!一緒に頑張りましょうね!」と微笑むしのぶに善逸は「頑張ります!!」と身体をくねらせて答えた。
ちなみに胡蝶が抜擢されたのは柱の中で一番、帝國ホテルにいても違和感がないからだった。宿泊客に対して違和感なく溶け込めるのも重要だ。以前はそういう任務は宇髄がよく担当していたが彼は遊郭の件で柱を退いているため、しのぶ以外には目立たぬことも複芸も難しかったのだ。
そういうわけで善逸は帝國ホテルの厨房に立っている。配膳係でもやるのかなと思っていたのにまさかの厨房。なぜなんだと善逸は真顔で考えるが分からない。厨房内で善逸の正体を知っているのは総料理長だけで、見習いとして入るのかと思っていたのに何故か潜入1週間で肉を焼いている。おかしい。初日は皿洗いだったのに、その後は野菜を切る、スープの灰汁取り、そして肉焼きとだんだんと仕事が難しくなっているのだ。
そして周りで働く人達の音が怖い。明らかに善逸よりも年嵩でシェフとして長くやってきているのに未だに灰汁取りしてる人とかいますけどなんなの?と考えそうになるが考えるのはよそうと善逸はひたすら肉を焼く。
そして夕方のクソ忙しい時間、総料理長により「『休憩』はいれー」と普通に考えてありえない時間に厨房の外に出される。これは初日からずっと同じでなぜなら善逸の本当の仕事は肉を焼くことではないからだ。
善逸は厨房の隅に移動すると卵を3つほど手に取った。そしてそのままボウルに割ると手早く塩胡椒をしてフライパンに流し込む。厚焼き卵ではなく薄い真四角になる様に火を通すとフライ返しでクルリとひっくり返した。最初は菜箸じゃないのか・・・・・・と戸惑いはしたが使ってみれば薄いものをひっくり返すのには楽だと気がつく。
焼き上がったオムレットの粗熱をとっている合間に食パンを取り出すと1.5センチほどの厚めに切っていく。1、2、3、4と切ったところでそれぞれにバターを塗りつけていく。そしてその上にチーズ、ボイルハムと乗せたところでソースを少量塗り、少しばかりまだ熱い卵を乗せた。
そしてそれをパンで挟み込むと耳の部分を落としてから等分していく。切り口の断面をみると色鮮やかな切り口に善逸は「おおっ」と自分で作っておきながら驚く。そしてそれを何回か繰り返して量をこさえていく。
「こんなもんかな」
善逸はサンドウィッチを皿に乗せると布巾を掛けて、そっとバスケットに入れる。蓋を閉めてなるべく揺らさないようにと思いながら厨房を出ると従業員通路を通って階段へ行き、軽快に屋上まで上がっていく。
人がいない屋上の踊り場でそっと鉄の扉を押しあければ、夕陽の最中に鬼殺隊の隊服姿が見える。なんでも今回の隊服は帝國ホテルに合わせて背中の一文字は描かれていない。それだけで上等な服に見えるのだから凄いものだ。まあ竹刀袋に終われている刀がめちゃくちゃ目立つけど。今回は完全に洋装のほうがということで羽織は置いてきているけど、刀が目立つななと善逸が思っていると隊士が振り返った。
「善逸!」
「炭治郎」
善逸は軽く手をあげると炭治郎のそばへと近づいていく。炭治郎は屋上の壁際に腰を下ろすと手拭いを広げて善逸に差し出してくれた。まるで女性にする様な心遣いだが・・・・・・善逸はコックコートを汚すわけにはいかないのでありがたくそこに腰を下ろす。炭治郎も衛生面を考えてくれているのだなと善逸は一人で無理やり納得した。
「仕事はどうだ?大変だろう?」
「大っ変っだわ!なんで俺がシェフなん!?おかしいでしょ!年齢が釣り合ってない!!」
「まあ・・・・・・どうやってねじ込んだんだろうとは思うが、善逸は料理上手だ!そこらのシェフに負けてないぞ!!足りないのは知識と経験くらいだ!手際はまだ良くないがゆっくりやれば善逸はすごい腕前だ!!」
「褒めてんのか貶してんのかどっちだよ!!」
炭治郎の言葉に善逸は喚くがすぐに炭治郎にしぃーっと口元に指をやられたので黙り込んだ。しかし指は自分の口元に持っていくものではなかろうか。なぜ相手の口元に指を立てるのか。
善逸の口元に炭治郎の指があり、勢い余ってふにっと善逸の唇を押してしまったのでなんだか恥ずかしいと善逸が思っていると炭治郎もあからさまに顔が赤かった。
「なんでやったお前が赤いのよ・・・・・・」
「ああ、いや、なんでもない・・・・・・」
2人して赤くなって沈黙していると、その沈黙に耐えられず善逸は「そうだ!」とバスケットを差し出した。蓋を開けて皿を出し、布巾を取って見せると炭治郎は「わっ!」と顔を明るくする。
「材料使っていいっていうから、今日はサンドウィッチ作ってみた。炭治郎、食べていいよ」
「ええ!いいのか?サンドウィッチなんて食べるの初めてだ!」
「いいよ。今日はとうとう、しのぶさんと鬼を狩るんだろ?精をつけろよ」
善逸の言葉に炭治郎は真面目な顔になると「ああ」と大きく頷いた。
鬼は夜にレストランに必ず顔をだす。それが善逸がこの1週間で気がついたことだった。炭治郎は館内を回って確かに鬼の匂いは感じ取れたらしいが広いし入れない場所もありなかなかどこにいるかの特定が難しかった。
しかしレストランに鬼が必ずくる。そして何も食べずに一杯の珈琲のみで、それも飲まずに帰っていく。そんな客だった。そして毎回、顔が違う。
顔が違うからこそ従業員達は気がつかなかったのだ。同じ顔で毎日同じものを頼んで、しかも飲まないとあれば目立つが顔が物理的に違うのだ。耳のよい善逸か鼻の効く炭治郎でなければ気がつかない。よってしのぶを召集して今夜、討伐することになったのだ。ちなみに善逸はコックとして顔が従業員に知れてしまっているため、今回は余程のことがない限りは現地待機になっている。
「しのぶさんが一緒だから大丈夫だろうけど、気を付けろよ?」
「ああ、油断せずに行くよ」
炭治郎は善逸に差し出されたサンドウィッチをひとつ手に取ると興味津々に観察すると「頂きます」と言って口に入れた。パンを分厚めに切ったからなかなかに食べ応えがあるだろう。善逸もひとつ手に取ると囓る。
バターの風味とチーズの匂いが特に秀でてもない善逸の鼻でも感じられる。ハムを初めて食べたが、これは確かに美味しい。普通の肉とは違うと感じるが・・・・・・たぶん、伊之助は食べ応えがないと言いそうだなと善逸は思った。
「美味しいっ!」
一つを食べた炭治郎がキラキラとした目で善逸をみた。炭治郎は善逸の料理をなんでも褒めてくれるが、今回は相当にお気に召した様だ。善逸の耳にドッドッドッと高揚した音が響く。
「もっと食えよ」
「ああ!頂く!」
そう言うと炭治郎はニコニコしながらサンドウィッチを食べていく。ふにゃふにゃした顔は最初に出し巻き卵を作ってやった時と同じだった。善逸はもう一つのサンドウィッチを摘みながら炭治郎の珍しい表情をじいっと観察する。
嬉しそうに食べているが、特になにも善逸は変わったことをしていない。卵を焼いてソースを作ったくらいで、あとは具材を挟んだだけだ。とういうことでさすが帝國ホテル。賄いの材料も一流だということだろう。
「すごい美味しいぞ善逸!感動した!」
「素材がいいからなぁー」
「・・・・・・その辺はよく分からないが、禰豆子にも食べさせてやりたいなぁ。これがパンか。ふわふわしててすごい美味しい」
「本当に感動してる点が素材だったわ」
善逸はくふふっと笑いながら残りのサンドウィッチを炭治郎に差し出す。この後の善逸は戦闘はない。ならば炭治郎がたくさん食べて英気を養うべきだろうと皿ごと手渡した。
余程、サンドウィッチがお気に召したのか・・・・・・いや、パンかもしれないが。とにかく炭治郎は珍しく遠慮することなく皿を受け取った。しかしほんのり?を赤らめているのに、美味しいものをたくさん食べたいと思ってる己が恥ずかしいのかもしれない。
「俺、炭治郎が美味しそうに食べるの見るの、結構好きかも」
年相応で、なんだか安心する。その気持ちは声に出さなかったが、鼻の効く炭治郎には筒抜けかもしれない。炭治郎は善逸の言葉に視線をウロウロと彷徨わせると擽ったそうに笑った。
「・・・・・・俺、来世はパン屋になろうかな」
「なんで来世なのよ」
「今生は炭焼きしたいから」
「・・・・・・はぁ、なるほど?じゃあ早く鬼舞辻倒して、禰豆子ちゃんも人に戻さなきゃな」
「ああ、頑張るぞ!」
炭治郎はサンドウィッチを片手に持ちながら、むんっと意気込んだ。そしてそのままサンドウィッチをかじるとふにゃりと口元を緩めるのが善逸にはおかしくて、ふひひっと声を上げて笑った。
鮭の笹蒸し
「ほらよ。活きのいいやつ持ってきてやったぜ。これでなんか作れ」
そう言って宇髄が掲げるものに善逸はイッと歯を食いしばって嫌な顔をした。横にいる炭治郎は困ったような顔をしていて、その隣にいるしのぶはニコニコとしているが変わらずどこか怒ったような音をさせている。はしゃいでいるのは伊之助となほ達だ。4人は宇髄が持ってきたこれまた大きい、しかも生きた鮭を「うおおおあお!この鮭めちゃくちゃでけえ!!」とか「鮭だー!」「すごーい!」「ビチビチ動いてるー!」と言ってはしげしげみている。
「おらよ!」
「ぎゃあ!ヌルってしてる!!」
放り投げられた鮭を両手で受け取ると相当な重さがあるのに善逸はうぇっと顔を歪めた。受け取った衝撃で任務の際に折れた肋骨が痛んだからだ。ちなみに炭治郎は足が、伊之助は左手にヒビが入っている。三人で行った合同任務で思いのほか強い鬼に当たった結果だった。
「善逸君はまだ療養中なんですが?」
「ちんたら寝てるだけじゃつまらないだろ?気分転換だよ、気分転換。つーわけで俺、今日の夕飯はここで食ってくから。宜しくな」
微笑みながらもピクピクと口の端を動かすしのぶであったが、なほ達がキラキラとした目で鮭を見る姿にため息をつくとクルリと善逸を振り返る。
「善逸君。申し訳ないですが腕を奮っていただけますか?このはた迷惑で浮かれた人の横っ面をその鮭で殴ってください」
「比喩表現ですよね!?美味しい鮭料理つくれってことですよね!?」
「もちろんです」
この生きた鮭でぶん殴るんじゃなくて良かったと善逸はホッとするも、いや殴っても良かったかもと炭治郎と一緒にえいこらと鮭を台所へと運んだ。療養着が実に生臭い。炭治郎も少し困った顔しているのは魚の匂いがするからだろう。焼いたのはいいけど確かに生は匂いがきつい。
台所に入ると善逸はまずは着替えとばかりに一旦、自室に戻る。その間に鮭のウロコの処理は炭治郎がしておいてくれるというのでお任せすることにした。
道中、客間の前を通ると宇髄が善逸を見てニヤニヤと笑っている。宇髄と伊之助となほ達は双六をして遊ぶらしく準備しているようだった。
「お前の腕前、楽しみにしてるわ」
「うっさいわ!!」
善逸はドスドスと廊下を歩いて間借りしている部屋に入ると、ひとまず替えの療養着に着替える。そして押入れからとある箱を取り出すとそれを片手に台所へと戻った。引き返した時に通り過ぎた客間ではキャッキャと遊ぶ伊之助となほ達とついでの宇髄に善逸はハァと心の中で溜息をついた。
廊下に向いて座っていたすみが善逸に気が付き顔をあげる。それにひらりと手を振って笑えば、なほときよも善逸に手を振った。3人とも善逸をみてウキウキした音を立てるのに「期待しているなぁ」と善逸は少しばかり荷が重く感じるも、宇髄は置いておいて、なほ達が期待しているのだからきちんと美味しいものは食べさせてあげたい。
そうしてよしっ!と気合をいれて台所に戻ると鮭のウロコ取りが殆ど終わっていた。振り向いた炭治郎に「ありがとね」というと、善逸は腕を組んで鮭を見る。
「何を作るんだ?手伝うぞ」
「あ、本当?ありがとね。とりあえず主菜と副菜1品、汁物に白米と漬物でいいかな」
善逸はそう言うと土鍋を炭治郎に手渡す。炭治郎は心得たようにそれを受け取ると米櫃の方へと片足を引きずりながら歩いていく。その後ろ姿を振り返ると善逸は「ねぇ」と声をかけた。
「味噌汁と副菜ーー」
「俺は副菜の方を作るぞ」
「まだ何も言い切ってないんだけど」
「味噌汁は善逸が作るんだ。絶対にだ」
「全然聞いてないのね。まあいいけど。副菜何にする?」
「大根と人参があるからなますとかはどうだ?」
「いいんじゃない?味噌汁はどうしようかなー」
善逸はそう言いながらも下処理が終わっている鮭を包丁で下ろしていく。ところでかなり大きい。余った分はどうしようかと思うが、そのまま焼いて伊之助に渡せば綺麗に食べてくれるだろうが・・・・・・最近は寒くなってきたから、塩漬けにして外で乾燥させてもいいかもしれない。善逸は大きな鮭をどんどんと切り身にしていく。
炭治郎は米を吸水させているのか、大根と人参をもって善逸の横に戻ってきた。
「鮭はどうするんだ?鮭大根とか作るか?」
「いや、そんな手間かかることはしない。簡単に作る」
「えっ、なんでだ?」
炭治郎の純粋な疑問に善逸はぐるりと首を回して炭治郎を見やる。その目はギラギラと怒りに燃えていて、炭治郎は「わあ」と一歩引く。
「なんでってあいつ何様だよ!!家に帰れば可愛い嫁さん3人の手料理が待ってるんだぞ!?なのになに!?美味いもん作れだぁ!?愛妻料理より美味いもんなんかないだろ!!どこの高級ホテルでも高級料亭でも愛妻の作る料理よりも美味いもんなんかないだろうが!!くそったれ!!炭治郎だってそう思うだろ!?やっぱり好きな人が作ってくれる料理が1番美味しいに決まってるって思わない!?」
目を血走らせて叫ぶ善逸に炭治郎はなるほどと頷く。確かに自分を愛してくれる妻が作る料理が1番美味しいのは確かだろう。亡き父も亡き母が作った料理が1番美味しいっていつも言っていた。
それに善逸が言うように自分が好きな人が作ってくれる料理が1番美味しいのも・・・・・・炭治郎には実感がある。確かに1番美味しいに決まっている。
「そ、そうだな・・・・・・俺も善逸の言うように好きな人が作ってくれる料理が1番だと思うよ」
顔を赤らめながらそう言う炭治郎に善逸はひぐっと喉を引きつらせる。そして目をあちらこちらに彷徨わせると生臭い手の甲を口元に当ててそっぽを向いた。善逸の耳は炭治郎から見ても真っ赤であった。
「ごめん、炭治郎。変なこと言って・・・・・・」
「へ、変なことではないぞ!やはり好いた人が作ってくれた料理というのは味だけではなく、心も満足させてくれるというかだなあ!」
「もういいから黙って!!料理!料理をしよう!!」
お互いの効きすぎる耳と鼻に困りながらも2人は料理を再開した。善逸は魚の切り身に軽く塩を振った。次に手早く玉ねぎを細く、くし切りにすると広げた笹の葉の上に敷き詰める。そしてその上に鮭を置くとここで善逸は部屋から持ってきた箱を作業台に置いた。
「ぜ、善逸!それはまさか・・・・・・!!」
「そう!簡単には作りたいけど美味いもんは作りたい!!というわけでこいつを使う!!」
「本当にそれを使うのか!?夜食で俺たちだけしか食べてこなかったそれを!?伊之助が怒らないか!?」
「いいだろ!俺が任務のお礼に貰ってきたもんなんだし!」
善逸はそう言うと帝國ホテルの任務でお礼にと個人的に総料理長に頂いた箱の中身を取り出して鮭の上に置いた。そして調味料を垂らすと手早く笹の葉を巻いていく。
「後は蒸すだけだな?」
「うわあ?。もうすでにいい匂いがしている・・・・・・。それ絶対に美味いぞ」
善逸の鼻では感じ取れないが炭治郎の鼻ではもういい匂いらしい。しかしこれは完成した方がもっと美味いのだと善逸は確信して、ふふっと笑った。
*****
「お待たせしました?。出来上がりましたよ?」
そう言ってお膳を客間に運べば、上座に宇髄としのぶが、下座に伊之助が座っていた。なほ達はアオイとカナヲと食べるらしくお膳を別室へと運んでいる。炭治郎と善逸はお膳を置いていく。そしめ5人分揃ったところでようやく宇髄が口を開いた。
「さてさて?お手並を拝見と行きますかね。・・・・・・笹蒸しか?」
すんっと鼻を鳴らした宇髄は不思議そうな顔をした。笹の葉の匂いと共に食欲をそそるような芳しい匂いがする。顔を上げて善逸を見ると澄まして横を向いている。
「折角、善逸君が腕を奮ってくれたのです。冷めないうちに頂きましょう。宇髄さん、どうぞ」
しのぶに促され、宇髄は片手で笹の葉を開いた。瞬間、香りたつ匂いに目をほんの少し大きく開く。すると宇髄があけた笹によって広がった匂いにいち早く反応したのは伊之助であった。
「あああああーー!!こいつは『バター醤油』の匂いじゃねえか!!バターは貴重だって言ってたの紋逸じゃねえかよ!!」
立ち上がって抗議する伊之助に炭治郎が「まあまあ」と宥め、善逸は「いいだろ別に。俺のなんだからいつ使うかは俺が決めるよ」と言うのに伊之助はブルブル震えている。曰く「バター醤油ご飯が食べれる回数が減る!!」とのことであった。
宇髄は開かれた笹の葉に包まれていた鮭を見て、嗅いだことのない香りに洋風なのかと理解する。バターといえば高級食材だ。宇髄も食べたことがないわけではない。
「バター醤油・・・・・・ですか?バターに醤油を混ぜたものですかね?それでは頂きます」
しのぶはそう言うと箸を取って鮭を一口分に切った。宇髄もそれに倣い箸を取ると鮭を口に放り込む。するとふわっと濃厚なバターと香ばしい醤油の味が口に広がる。
正直言って、宇髄は期待していたわけではなかった。していないわけでもなかったが。ただこの小煩い我妻善逸という人間が、それなりに料理ができるというのが面白おかしくて。冷やかしてやろうという気持ちが多分にあって宇髄は来たのだ。
出されるものが鮭の塩焼きであっても宇髄は不満はなかった。「地味だなぁ。捻りがねぇ」と軽口を叩いたとしても、不味いとか期待外れとか言うつもりは毛頭なかった。
何しろ宇髄は育ちが忍びの里だ。訓練として相当酷いものを食べることもよくあった。家族で食事を取ることも育った家ではなく、場合によっては毒が混入されていることもあった。それは殺伐とした食事風景であったし、実際に家でだされた食事で死んだ兄弟だっていた。
そんな場所だから宇髄は嫁を連れて里を抜けた。嫁達を産屋敷家に預けている間に鬼狩りとしてやっていく為に訓練を重ね、最終選別を超えてようやく家族4人で食事を囲めた。
3人の妻が宇髄の為に作ってくれた食事に宇髄はようやく、肩肘から力を抜けて「美味い」と思ったのだ。思えることができるようになった。
それから宇髄の好物は何があっても『嫁達の手料理』につきる。だけど、そうだとしても善逸の料理も美味かった。そこでようやく、嫁たち以外で知り合いの作る料理を食べたことがなかったのだと気がついた。
確かに善逸の腕前は悪くない。
しかしやはりそれなりに目をかけてやってる後輩の作ったものというのも感慨深さが相まって味に良さが加わっているのかもしれないと宇髄は素直に思った。要するに・・・・・・可愛がってる後輩が作ったというものはいいものだということだ。勿論、文句なく味もいいけれど。
「美味い」
食べたことのない味に、宇髄は素直に称賛の言葉を口にした。隣ではしのぶが?を僅かに紅潮させながら、口元を抑えて咀嚼をしている。どうやら子供のように美味しさに喜ぶのは彼女の矜持にそぐわないらしい。
すんっとお澄まししているのが胡蝶しのぶではあるが、雰囲気が美味いと言っている。元忍びの目は誤魔化せないし、この場にいる残りの3人も鼻と耳と触覚に優れているのだ。しのぶの機敏などお見通しだというのに。
しのぶのその姿に宇髄はくっと喉の奥で笑うと彼女の代わりというように、満足げにもう一度言った。
「美味い!善逸、やるじゃねえか!」
宇髄の言葉に善逸は「お粗末様でーす」と言うとしてやったりというように、にっと笑った。
****
「つーわけで、まあ楽しい時間だったわ」
宇髄は手酌で酒を注ぐと、ぐいっと酒を煽った。酒の肴は「沢山できたから」と投げつけられて寄越された鮭とばだ。しかも切り身。硬くて噛み切れやしないと思いながらもガリガリと齧る。
宇髄は向かい合っている男にも切り身のままの鮭とばを差し出せば、男は素直に受け取ってガリッと見事に噛みちぎった。まったく色んなところが強靭な男だなと宇髄は呆れながらも感心する。
「興味あればお前も行ってみれば?」
宇髄がそう言うと硬い鮭とばをあっと言う間に食べ切った男がその山猫のような目をいつも通り大きく見開いたまま、にいっ口角をあげる。
「よもやよもやだ!我妻少年にそんな才能があったとはな!実に興味深い!!よし!俺もなにか手土産をもって行ってみるとしよう!」
笑う男に宇髄は「時間が合えば一緒に行くかな」などと善逸の被る苦労など慮ることもなく呑気に構えていた。
ローストビーフ
台所の作業台に鎮座する巨大な牛の塊肉、それも5つという数に炭治郎は素直に「うわあ」と声を漏らした。対する善逸は腕組みをして顔を青ざめさせている。
別に巨大な塊肉に怯えをなしているわけでも、驚いているわけでもない。何しろ以前の任務でかの帝國ホテルの厨房にて潜入任務をこなしていたのだ。あそこでも牛肉の塊を切っては焼いて、切っては焼いてをしていた。この大きさの肉はよく見た。よく見てはいたが・・・・・・。
「なんなの皆!!俺は料理人じゃあないんですけど!?」
「善逸落ち着け。今更過ぎるぞ」
慰めにもなっていない炭治郎の言葉に善逸は「キイイイイ」と床に手をつけて仰け反る。炭治郎はその奇行を止めはしないが「ちゃんと手を洗うんだぞ」と明後日なことを言った。
ことの始まりは一通の手紙だった。蝶屋敷の主たる胡蝶しのぶに呼び出された善逸は何だろう、もう任務かななんて戦々恐々しながら向かった。善逸はようやく肋がくっついてきた頃で、炭治郎も足が戻り2人して回復訓練に入ったところだった。
しのぶの部屋に到着した善逸は「何の用ですか?」とびくつきながら聞けばしのぶは手元に手紙らしきものを広げたまま、「牛肉を使った料理を作る場合、どんな食材や調味料があると良いでしょうか?」とわけの分からないことを聞いてきた。
なんの話だと言わんばかりに善逸が「はあ・・・・・・?牛肉、ですか??」と問えば、しのぶはくうるりと持っていた手紙を反対に返して善逸に見せてくれた。
何が書いてあるのかと首を突き出して善逸は内容に目を通す。
ーー
来ル、○月○日。十四時。
牛ノ肉を持ッテ蝶屋敷二赴く。
煉獄杏寿郎
ーー
書かれている簡潔な内容に目を通して、善逸は嫌な予感に目を瞑る。しかし現実は無情であり、しのぶは「恐らく、宇髄さんが漏らしましたね」と呟き善逸は頭を抱えて蹲った。
「煉獄さんはとても健啖家なんです。これは蝶屋敷としてもすこし備えねばなりません。善逸君は必要な材料を選定してください。取り急ぎ仕入れます。あ、費用は気にしなくて結構ですよ?全て煉獄さんにお支払い頂きますので!」
ニコニコと告げるしのぶに、善逸は「マジか」と震える。まあ要するにしのぶが言いたいことは「煉獄さん来るからお前、飯作れよ」ってことである。
善逸はしのぶの部屋を後にすると、泣く泣く台所に向かう。そして「牛肉ってなんだよー。どんなのくるんだよー」とグスグス鼻を鳴らしながら材料や調味料を選定していく。善逸はひとまず、薄い牛肉が来たら牛鍋、塊肉がきたら・・・・・・帝國ホテルで知った料理でも作ろうと決め、しのぶに伝えるために紙に書きつけていった。
帝國ホテルの料理は手が込んでて面倒だが、善逸は牛肉の料理などろくに知らない。しのぶ直々に頼まれてしまったからには中途半端な料理は出せない。だって女性陣の口にも入るわけだし。
これが炭治郎や伊之助だけなら塩振って肉焼いてお終いだが、何やらしのぶからも期待する音がしているのだ。あの帝國ホテルに潜入任務をこなしてから特に。
あの任務に他意があったとは善逸は思わない。確かに情報を集めるなら善逸の耳は持ってこいだ。炭治郎の鼻でも良かったかもしれないが、炭治郎は嘘が苦手なため潜入に向いていない。となるとやはり善逸になる。だがしかし、ならばなぜ・・・・・・厨房に潜入だったのかとは疑問がある。
まさか料理のレシピを盗み聞きしてこいということだったのだろうか?いや別に盗み聞きしたくても耳に入ってきてさえしまえば、善逸は内容も音も覚えてしまうのだから後で記憶から引っ張り出せる。それも盗み聞きなのだろうかと善逸は頭を抱えるが、すぐに覚えてるものは仕方ないと開き直る。
「俺は別に商売でやってんじゃないし。個人的なことだし」
善逸はウンウンと頷くと材料を書き付けた紙を手にしのぶの部屋へと戻っていった。
さて、そこから5日後。
牛肉が・・・・・・いや、煉獄杏寿郎がやってきた。両片手にで牛塊肉に2つずつ持ち、その後ろに両手で牛塊肉を抱え込んだ、煉獄の弟たる煉獄千寿郎が付き従ってくる。
無限列車の際に上弦の参と戦った煉獄は九死に一生を得た。その代わり片肺に大きく深い傷を負い、呼吸を使うことが出来なくなった。煉獄は長い治療と機能回復訓練を経て、最近ようやく遠出ができるようになったらしい。その話を善逸に教えてくれたのは煉獄と文通をする炭治郎で、炭治郎は元気そうに歩く煉獄に嬉しそうだ。もちろん、善逸だって嬉しい。
「こんにちは、煉獄さん。お加減はいかがですか?」
「うむ、久しいな胡蝶!身体の方はすっかりいいぞ!むしろする事がなくて退屈すぎるくらいだ!!」
「煉獄さんは育てに回るとお館様から伺ってますが、今は無理をせずにしっかり治療と回復訓練をしてください。間違っても型を使おうとはしないでくださいね」
しのぶさんの言葉を困ったような顔で聞いている千寿郎の音に、善逸は「これは相当、兄に困らせられてるな」と利発そうな少年に同情した。恐らく今日もついてきたのは兄が無茶をしないか心配だったのだろうなぁ、なんて考えながら煉獄としのぶのやり取りを眺めていたら、煉獄はぐるっと善逸の方を見た。
「おお!我妻少年!今日は宜しく頼む!」
「ああ、はい・・・・・・」
「宇髄が皆で食事をして楽しかったし美味かったと自慢していてな!俺も羨ましくなってしまった!今日は是非とも美味い飯を食わせてくれると嬉しいぞ!」
にっかーというような笑顔で言う煉獄からはワクワクしてますという音が大きく響いている。子供のような眩しい期待に善逸は「ひぇっ、期待が重い・・・・・・!」と思うが実はこの手の好意全面の期待に善逸は弱い。日頃近くにいる男が正しく煉獄と同じ傾向の期待をしてくるからだ。
この手の音をさせる奴は食べる前はもちろん、食べた後の感激も大きい傾向がある。その時の音は本当にこちらも楽しくなってしまい、嬉しさで身体中がむず痒くなるのだ。
そういえばこの前に強請られて作った夜食の時も・・・・・・と善逸が思い出していると、ぽんっと肘で軽く小突かれて振り返った。隣にいた炭治郎がほんの少しだけ、つまらなそうな顔をしてそして鼻をひくつかせるのに、そして炭治郎から聞こえてくる僅かなザラつく音に善逸はおやまあと目を丸くする。
「それでは肉を台所まで運ぶとしよう!どっちに行けばいいんだ!」
「あ、えっと、俺たちで運びますから大丈夫ですよ!」
善逸と炭治郎は煉獄達から肉を受け取ると庭を通って台所の勝手口へと向かった。2人で連れ立って歩くが、善逸の隣を歩く炭治郎からはジリジリと焦げるような音が聞こえており、それは何というか炭治郎から聞こえるには珍しい音であった。この音は街でよく聞こえた音で、花街であった為に大体は惚れた腫れたの時に聞こえる音だった。他にもあったが。
この音は欲張りの象徴でもあるわけだが、炭治郎の中にはジリジリと焦げる音と共にギシギシと自分を責める音も聞こえる。
煉獄と言葉を交わして小突かれた辺りから聞こえる音だが・・・・・・たぶんこう、何か勘違いしてるんだろうなぁと善逸は思っている。だからそんな音を炭治郎がさせる必要はないのだと、そんな悲しい気持ちになる音をさせないでくれと思って、恥ずかしながらも本当のところを口にした。
「何を勘違いしたのか知らんけど、俺が考えてたのはお前のことだからな。煉獄さんがお前に似た音させるから・・・・・・」
いつ、どの時になんて言わない。
そんなにはっきりと明確にできるほど善逸と炭治郎の気持ちははっきりともしておらず、整理させてもいない。今はまだふわふわとさせていたいとお互いで思っているのは、鼻と耳で分かり合っている。
「・・・・・・なんだ、そうか」
ふふっという笑い声と共にパチパチと火花が散るような楽しい音が戻ってきて、善逸もふっと口元を緩める。2人してふふふっと笑いながら勝手口に入ると、山のように積まれている材料に「おおう・・・・・・」と2人は現実に引き戻された。ロマンティック終了。
「というわけで俺と炭治郎の2人じゃ到底手が回らないのでアオイちゃんとなほちゃん、すみちゃん、きよちゃんにも手伝ってもらいます!4人とも本当にありがとう!!蝶屋敷は治療施設であって飯処じゃねえええんだよおおおお!」
「全くその通りです。しかし元柱の方のご希望としのぶ様のお願いならば聞き遂げねばなりません」
アオイの言葉になほ達も気合をいれて頷く姿と音に、屋敷の主人で自分たちの恩人にあたるしのぶに少しでも報いたいという気持ちを感じ、善逸は涙腺がホロリと緩む。しかし感動で泣いている場合ではない。時間は有限なのだ。早く始めねばこの量の食材で料理など拵えきれない。
「とにかく始めよう。善逸、俺たちはどうすればいい?」
「えーと、炭治郎はひとまず外にもかまどを組んでもらっていい?肉の量が多いわ。これじゃ全然かまどが足りない。ひとまずえーと、3つくらい組んで。あと火起こしもお願い!アオイちゃんはここにある玉ねぎとじゃがいもと人参の皮剥いて切っちゃって。玉ねぎはくし切り、じゃがいもと人参は一口大で。なほちゃん達3人は俺の手伝い。それじゃあ、皆さんよろしくお願いします!」
善逸が頭を下げるとみんな元気よく返事をした。そして炭治郎は勝手口から庭へと出て行き、アオイは材料のカゴを持つと作業台を善逸に明け渡すために広い台所の隅へと移動する。
善逸たち4人は肉を作業台の上にのせるとあまりに大きすぎるので塊肉を半分にきっていく、すると10個の塊肉になるわけだが・・・・・・。この量を本当に10人足らずで食い切れるのか善逸は不安になった。
何しろ今日は伊之助が不在なのだ。怪我の症状が比較的軽かった為に早々に完治させた伊之助は一昨日、任務にでてしまっていてる。場所が遠方であったのとまだ終わったと連絡は入っていない為、戻るのはまだ先だろう。
ひとまず大量の肉を全てを同じ料理にすると飽きるなと思った善逸は半分はやはりシチューにしようと決める。しかしその前にもう一品の下拵えだ。
「なほちゃん、すみちゃん、きよちゃん。ニンニクの皮剥いて叩き潰してもらってもいい?」
「はあい!」
「わかりました!」
「大丈夫ですー!」
トテトテとニンニクを取りに行く3人をチラっと見送ってから善逸は腕まくりをして肉の塊達に多めの塩を振りかけていく。しっかりとした重さで「重たいなぁ」なんて思いながらひっくり返して裏側にも振る。
そして振り終わった肉達を隅に寄せると、シチュー用の肉を包丁で適度な大きさに切り分けていく。
「善逸さん出来ました?」
「ありがと?、じゃあこっち持ってきて!」
善逸は3人がすりつぶしたニンニクを肉に軽く揉み込むとそれぞれの肉を紙で包んでいく。じわっと肉の脂が紙に染みをつくる。
「これで暫く放置かな」
「善逸、かまどの支度できだぞ」
「はやっ!待って待って!まだアオイちゃんの作業が終わってないわ!」
「じゃあ皆んなでやってしまおう!」
庭から戻ってきた炭治郎に、善逸は慌ててアオイの方へと駆け寄った。流石のアオイも大量の野菜の皮むきに難儀していた。それもそのはず、ジャガイモなんて剥きづらいし、あまり食卓には上らぬ食材だ。慣れぬ食材の皮むきにアオイは難しい顔をしながらもせっせと手を進めているが終わりは見えない。
「ごめんねアオイちゃん!皆んなでやろう?」
「すみません、助かります」
刃が滑ると危ないからとジャガイモを善逸と炭治郎が剥き、アオイが人参、なほ達が玉ねぎと分担して一気に片付けた。その結果、カゴに山盛りの野菜達が出来上がり達成感がすごい。
「よし!火にかけよう!」
全員で火がついたかまどへと行き、複数の鍋にバターを入れると一口大の肉から順に炒めていく。量が多いので大変だ。なほ達に焦げ付かないようにかき混ぜて、肉が色づいたら玉ねぎ、にんじんを投入して玉ねぎが透き通るまで炒めてくれと伝えてから善逸はアオイとニンニクを馴染ませていた肉が置いてある台の方へと向かう。ちなみに炭治郎は例の如く米焚きだ。コメを大量にといで炊く。しのぶさんにはまさかの20人前の米を用意しろと言われているので炭治郎が水場でガッシガッシと米をといでいる音が善逸の耳には届いでいた。
「ところで善逸さん。今日は何をつくるんですか?」
「えーとね、今日はローストビーフとビーフシチューだよ」
「・・・・・・シチューは聞いたことがありますが、ローストビーフとは?」
「牛の塊肉を蒸し焼きにして薄く切った料理・・・・・・かな?作り方は知ってるけど、どこの料理とかは知らないなぁ」
善逸が聞いて知っているのは美味いかどうか、そして作り方だけだ。善逸とアオイは肉からニンニクを取り除くとそれをフライパンに入れて炒めていく。
ニンニクの香りが立った頃、フライパンからニンニクを取り出してとうとう、塊肉を焼く時が来た。
「片面ずつ、順番に焼いていくよ。えーとね、目安は2分程度かな?音が変わったら声かけるね」
「分かりました」
「善逸さーん!焼けて来ました!」
「今いくー!アオイちゃん、ここよろしくね!」
「はい」
早く早くとなほ達にせっつかれて呼ばれた先では確かに玉ねぎが綺麗に透き通っている。善逸は水を適量入れ、しのぶにお願いして仕入れてもらった赤ワインなるものの蓋を開けた。
すると庭の方から「うわっ!なんの匂いだ!?」と炭治郎が顔を出す。びっくりした様子の炭治郎に善逸は「酒だよ酒!」笑うが、すぐにアオイを振り返ると声を掛けた。
「アオイちゃん!焼き面変えて!」
「はい!」
善逸は赤ワインを鍋に入れていくと物珍しいようになほ達が見ているが、善逸はいっぱいっぱいだ。同時にやる事が多い。
「アオイちゃん焼き面?!」
「はい!」
「こっちはこれで暫く煮込むよ。沸騰したら灰汁がでるから、それを綺麗に取って、灰汁が出なくなったら蓋をしてね」
「わかりました?!」
善逸は急いでアオイのところに戻ると自分もどんどんと肉を焼いていく。アオイの肉が全面焼き色がついた時点でフライパンに蓋をして火から下ろす。
「完成ですか?」
「まだだよ。これで余熱で火を通して、反対に返したらまた火にかけるの。他のもおんなじようにやっていこう」
2人でせっせと肉を焼いて、余熱で火を通してまた火にかけてとやって、ようやくそこまで手を入れた肉に善逸は耳を澄ます。ふつふつと肉が熱によって収縮する音にばっちり火が通ってるのを確信して満足げに息をはいた。
「よし!この肉は大丈夫だから、紙に巻こう!」
「紙にですか?」
「なんか知らんけど帝國ホテルでそうしてた!そんで30分以上放置する!」
善逸は手早く肉に粗く引いた胡椒をふると紙で肉を幾重にも巻いていく。アオイも善逸に出来上がりと言われた肉を取り出すと胡椒を振って同じように肉を巻いていく。そうしてようやくローストビーフの手が離れたので善逸とアオイは洋風な副菜をとキャベツを千切りにしてトマトを添えていく。
2人で黙々と作業しているとアオイが珍しく善逸に自分から話しかけた。
「・・・・・・帝国ホテル、どうでしたか?」
「え?ホテル?あーすっごい綺麗なところだったよ。びっくりした。綺麗な服着た人たちも沢山いたし、異人さんもよく見たし、上流階級ってのは凄いねぇ。住む世界が違うなーってしみじみ思ったよ」
「・・・・・・料理は」
「え?」
「料理はどうでした?今日のビーフシチューもローストビーフもその時見聞きして覚えてきたものなんでしょう?・・・・・・他にも沢山、覚えてきましたか?」
アオイの言葉にふっと帝國ホテルで見聞きした料理やレシピや食材の立てる音たちを思い出す。確かに善逸の脳内のあちこちに料理たちは住んでいる。思い出せばいくつか料理が作れるのは間違いない。
「えと・・・・・・覚えてるとは思うけど??なんで?」
「しのぶ様と恋柱の甘露寺様は仲が宜しいんですよ。そして甘露寺様も食べるのが大そうお好きな方です」
「・・・・・・そ、それで?」
嫌な予感に冷や汗が出る善逸に、アオイは盛り付けの為に下を向いていた顔を上げると珍しく口角をあげた。
「きっとまたありますよ。頑張ってください。ここはご飯処ではないのですが・・・・・・私たちも美味しいものを御相伴に預かれるのでたまにならば、そう悪い事ではないですね」
「そっ、そっかーーー!!俺、頑張るね!!」
珍しくアオイに褒められて善逸はデレデレと顔を緩めた。そのダラしない顔にアオイは露骨に嫌そうな顔をしたが・・・・・・善逸はパッと顔を戻すと「ここお願い」と言ってなほ達の方へと行ってしまった。そして蓋を開けて真剣な顔でかき混ぜているのを見るといつもあんな風にしていればいいのにと残念な気持ちになる。
「ああして普通にしていればもっと評価があがるのに・・・・・・」
「善逸の?」
「そう善逸さんの・・・・・・って炭治郎さん!」
「ああ、すまない。驚かせてしまったか。何か手伝えないかと思ってきたんだが・・・・・・」
炭治郎はどうやら米の蒸らし中らしく手持ち無沙汰らしい。アオイの盛り付けを見て、善逸を見て、アオイを見た。
「アオイさんは善逸がもっとしっかりして欲しいって思ってるのか?」
「はあ・・・・・・まあ。女性にだらしない顔をするのは改めて欲しいですね。後は甘味を盗むところとか、しのぶ様の部屋の金魚を持ち出す事とか、あげ出したらキリがありません」
「あはは・・・・・・すみません」
そう言って困ったような顔で炭治郎はアオイに謝る。なぜ炭治郎が謝るのかとアオイは思うが、炭治郎は鍋に調味料を入れている善逸の姿を眩しそうに目を細めて見つめているのを見て、口を閉じた。
「こっちはいいですから、あちらにいかれては?」
「えっ!?」
「こちらは盛り付けたら終わりなので。ほら、あちらへどうぞ」
アオイが炭治郎の背を押すと、炭治郎は戸惑いながらも足は前に進んでいく。心なしか嬉しそうに見えるのは己の勘違いではないのだろうなと、アオイは最後のトマトを皿に乗せた。
****
「完成した?!ひえええ、皆んなありがとう?!」
おいおいと泣く善逸だが、皆なんとか支度が済んだのにほっと息をつく。それにしても大変だった。慣れぬ献立だったため、段取りもなかなか上手くいかず、善逸は調整に走り回ってばかりだった。
しかしシチューもローストビーフも味見をさせてもらったが文句なく美味しかった。そこに達成感と早くしのぶや煉獄に食べてもらいたいという気持ちが蝶屋敷の娘達には大きくある。
「冷めないうちにお料理出しましょう!」
「そうしましょう!」
「早く早く!」
なほ達が言うのにそれもそうだと、そこからまたてんてこ舞いで配膳をしていく。シチューなどもはや面倒でそのまま鍋ごと運んでいく。だって煉獄は沢山食べるらしいし、そういえば無限列車でも大量の弁当を消費していたなと善逸と炭治郎は思い出した。
そうして完全に洋風だからと長机に並べられた料理の数々に煉獄はもちろん、千寿郎もしのぶも驚いていた。
「すごいな!本当に美味そうだ!いい匂いがする!」
「洋食ですね。僕、コロッケとかカレー以外の洋食を食べるの初めてだから楽しみです・・・・・・!」
「皆さん、ご苦労様です。素晴らしい料理の数々ですね。とても、美味しそうです」
キラキラとした顔で褒めてくれるのに、善逸は蕩けた顔で照れては「ウィヒヒッ」とぐねぐね動くのに炭治郎はまた「気持ち悪い声で笑ってるなぁ」と思いはしたものの、善逸は確かに頑張っていたので指摘はしなかった。けど千寿郎君そんな善逸に驚いている様子だったので、後でしっかり控えるように言わねばと思いながらも炭治郎は目の前にある料理に目を向ける。
テーブルに並べられた料理たちはまさしくご馳走と言っていい様相だった。洋風の皿はないから全て和食器に入れられているが、それも和洋が合わさっていて見目にも美しいと思える。
何しろローストビーフを乗せた大皿などはしのぶが出してきた蝶屋敷にある飾り皿たちだ。美しい模様と金箔が豪勢さを醸し出している。盛り付ける時など善逸は「これに乗せるのおおおおおお!?」と戦々恐々としていたが、炭治郎も怖かった。伊之助がいなくて良かったと思ったくらいだった。
「ふむっ。何という料理かな?」
「こっちの焼いてある肉がローストビーフで、こっちかビーフシチューです。蝶屋敷の女の子達と炭治郎に手伝ってもらって作りました」
煉獄の質問に善逸はすいっすいっと指を動かして本日の献立をいい、そして己1人の功ではないと自然に口にする。そんなところが善逸の良いところだと炭治郎はふふっと口元を緩めた。
「どんなお料理なんですか?」
「・・・・・・ええと、蒸し焼いた牛肉と煮込んだ牛肉かな?」
千寿郎の質問に善逸はううん、と頭を悩ませてかなりざっくりとした回答をした。何しろ善逸は作り方は知っていてもどんな料理であるか、どんな国の料理であるかなぞ知る由もないし興味もない。あるのは美味いか否かだけだ。
「さあさあ!冷めぬうちに!皆さん、頂きましょう!」
パンっと手を叩いたしのぶに煉獄は頷くとこれまたクソでかい声で「頂きます!!」と言って箸を取った。そして遠慮なくローストビーフを二枚同時に掴むと口に放り込む。
固さのある肉だが、醤油を混ぜ合わせた甘じょっぱいタレとよく絡んでいる。完全に焼き切っているない、食べたことのない食感に煉獄は「これは!」と思った。そして追加で米を口に入れると案の定、肉と米が合う。
頑強な歯をしている煉獄は硬めの肉でも難なく噛み切るとゴクリと飲み込んだ。そして自然と湧き出るまた食べたいという欲求に箸を伸ばすと今度は米の上に乗せ、箸を使って肉で米を巻く。
しばし夢中で肉と米で頬っぺたパンパンにしていた煉獄であったが、どこを見ているか分からぬ目を一度目を閉じるとゴクリと咀嚼した。そしてカッと目を見開き、今の己の気持ちを素直に口にした。
「うまい!!!」
部屋が振動するくらいのデカく響く声の称賛に、耳のいい善逸は驚いてびっくり返りそうになるが、炭治郎が慌てて支えたので事なきを得た。しかしあまりの声の衝撃が大きかったのか善逸は涙目になりながら片耳を押さえて炭治郎に縋りつく。
「び、びっくりした・・・・・・心臓が口からまろびでるかと思った・・・・・・」
「大丈夫か?」
そんな善逸のことなど知ってか知らずか、煉獄はすごい勢いでローストビーフを消費していく。千寿郎も兄に倣い、ビーフシチューを口にする。すると濃厚なバターの匂いと赤ワインの僅かな風味、そして牛肉がホロリと口の中で蕩けるのに驚いた。豚の角煮のように柔らかい。そして野菜までもが甘く、簡単に歯で崩せてしまう。
「すごい・・・・・・初めて食べる味です。濃い茶色ですが、醤油を使ってるんでしょうか?」
「あ、それはドミグラスソースっていう小麦とバターを炒めて茶色にしたものだよ。それに・・・・・・まあ、出汁とか野菜とか色々ぶち込んで煮詰めてます」
善逸は事前に牛塊肉が来るという前情報をしのぶより頂けたため、念のためにと朝方からドミグラスソースを作っていたのだ。非常に手間と時間が掛かるものだった。二度とやりたくない。大事なことなのでもう一度繰り返すが、二度とやりたくない。
しかし善逸からドミグラスソースなるものだと聞いても千寿郎は全くピンとこない。しかしほんの少し聞いた限りでも手間が掛かっているのだろうことはわかる。それだけでなくとも、調理にも時間も人の手も多分に掛かっている。しかも兄である杏寿郎のわがままでと思うと申し訳ないが、嬉しそうに「うまい!うまい!うまい!」と食べる兄の姿を見ると結局は来てよかったと千寿郎思ってしまうのだ。
鬼狩りの家に生まれ、長い時間それこそ人生の半分以上を訓練に注ぎ込み、鬼狩りとして柱へと登り詰めた杏寿郎は負傷により前線を退かねばならなかった。
確かに今後は育てになるとは決めている。しかしやはり目に見えて兄に活力がないと千寿郎は感じていた。治療と機能回復訓練とを毎日真面目にこなす兄ではあるが、今までと違い明確な目標がないからか少しばかり熱量が違うのだ。
鍛えても体を戻しても鬼と戦うことはない。そのことが兄から心の力を奪っているのかもしれない。しかし今はちょっと心が弱くなったとしても兄は立ち止まるような人間ではないことを千寿郎はよく知っている。そう遠くないうちに自分がするべきことを心の底から見定めて邁進するに決まっている。だからそれまで、その力を蓄えるためにも杏寿郎に沢山のいいことがあればいいと千寿郎は思うのだ。
「兄上!美味しいですね!」
「うむ!美味しいな千寿郎!」
嬉しそうに輝く顔で笑い合う煉獄兄弟に皆がほわほわと微笑んだ。それからなほ達が頑張ったビーフシチューを食べたしのぶが3人を労い、もちろんアオイも褒められて嬉しそうにしている。カナヲもしのぶの隣でほんの少しだけいつもより?を紅潮させながら料理をせっせと口に運んでいて・・・・・・善逸はホッと心が柔らかくなるのに気がついた。
善逸も皆んなが褒めるビーフシチューやローストビーフを口に入れる。すると「確かに美味しいなぁ」と小さく頷いた。
善逸は別に自分の料理が取り分け好きなわけではない。食わないば腹が減るからという理由で作って食べるだけだった。
しかし今回は多くの人の手を借りて、みんなで頑張って作ったのだ。協力してくれたみんなの優しさが料理に染み込んでいて、「これが愛情なのかなぁ」なんて思った。
料理は愛情というが、善逸は本当のところよく分からない。名も知らぬ人が作った料理をお金を払って食べて、美味しいと思って、これが愛情かもと思って生きてきた。正解は知らない。善逸には家族がいなかったので愛情が入っている料理を食べたことがないから分からない。
だから炭治郎が作ってくれるおにぎりに愛情が入っているのかも、自分が作る料理に愛情が入っているかも分からない。なにしろ入れ方も分からないのだから。
しかしこうして皆んなが嬉しそうに食べているのを見ると、炭治郎が煉獄がしのぶが料理を口に入れてコロコロと楽しげな音をさせるのを聴くと善逸は「愛情・・・・・・うまく入ってるといいなぁ」と願ってやまなかった。
卵の天ぷら
サクサクと枯れ葉を踏みながら歩く。もうすっかりと秋も暮れて冬が来たなぁと善逸は木枯らしの中でそう思う。
嫌で嫌で仕方がない単独任務が終わり、大した傷もなく蝶屋敷へと向かうべき道中で、善逸は少し遠回りと曲がるべき道を反対に進んだ。道の先の方からはコッコッコッとすっかり聴き慣れた養鶏の鳴き声が善逸の耳に届いていた。
「我妻善逸、無事、帰還しました?」
蝶屋敷の門扉をくぐり、今のところなんとか恒例となっている挨拶を口にすれば庭の方から見慣れた顔が覗いた。どうやらシーツを取り込んでいたらしく、両手いっぱいの籠を抱えた神崎アオイである。
「はい、ご無事で何よりです。お怪我はありませんか?」
「うん、ないよ。今回は大丈夫?。めっちゃくちゃ怖かったけどね!!」
善逸は真面目な顔でいるものの、音ではホッとした安堵をみせるアオイにヒヒヒッと笑った。アオイは引いた目をみせるものの、ほんの少しの間で怪我のない善逸に「良かったです」といって頷いてくれた。
善逸はアオイから籠を受け取ろうと思うも、自分が洗濯物を持つには少々薄汚れ過ぎているのに気がついて差し出しかけた手を宙に止めた。そして苦し紛れに「手伝うことある?」と聞けばアオイはううんと考えて「伊之助さんのご機嫌取り、早くしてください」とだけ言って病棟の方へと引き上げて行ってしまった。
「伊之助のご機嫌取りか?」
善逸はボリボリと頭を掻くとトロトロと間借りしている部屋の方へと向かった。アオイがご機嫌取りと言うことには屋敷には伊之助がいるのだろう。実は善逸はこのところ伊之助の顔を見ていないのだ。具体的にいうと3日間ほど。
煉獄兄弟がこの蝶屋敷にやってきて、ビーフシチューとローストビーフを綺麗に食べて帰った後、伊之助は戻ってきたのだ。
その日のうちに戻ってくることを知っていたならばローストビーフとシチューを取っておいたであろうが、伊之助の赴いていた任務地は遠くてまだ帰らないと思っていたのだ。
しかしながら伊之助は新しい料理を作ることを知っていた故に間に合うようにと急いで任務を終わらせて頑張って走って帰ってきたらしい。それこそ鎹鴉を飛ばすことも忘れて。
しかし料理は煉獄が綺麗に平らげてしまっていた。何一つ残っていなかった。食べ切れるのかというような量だったのに平らげられてしまい、善逸と炭治郎も驚いていたくらいだったのだ。
しかしこの事実を知った伊之助はご立腹だ。かつてないほどに荒れに荒れた。それはそうだ。任務をこなして到底帰って来れないと皆んなが思っていたほど遠方から頑張って帰ってきたのに楽しみにしていた料理がない。
伊之助は善逸の宥めも炭治郎の謝罪もしのぶの取りなしにも聞く耳なしでぶすくれて山へと駆けて行ってしまった。それが5日前のことだ。
伊之助は食事時には蝶屋敷に戻ってくるが善逸と炭治郎とは一切口を聞いてくれない。俺は不機嫌なんだと意地を張り、善逸と炭治郎がほらおかきだ。ほら大福だと食べ物を持って行ってもなしのつぶてであった。むっつりとして雰囲気でさっさと何処かへ行ってしまうのだ。
善逸は「もう気が済むまで放っておかない?」と言ってすでに3日前くらいから放置なのだが、炭治郎は「伊之助は除け者にされたのが悲しいんだ!放って置いたら可哀想だろ!!」と言ってあれやこれや手を尽くすが今のところは一切効果なしだ。
善逸はひと風呂浴びてさっぱりすると予備のシャツとズボンに袖を通す。隊服の上着は迷ったが羽織は洗濯に出してしまったので大人しく袖を通した。善逸はあまり寒さに強くはないのだ。
そして台所にひょいと顔を出すと夕餉の下ごしらえをしているなほ達に一声かけて食材を頂戴していく。南瓜にサツマイモ、海老にナス。人参に玉ねぎと拝借したところですっかり慣れ親しんでしまった小さな台所へと向かった。
「さて、と。本番といきますかー」
善逸はそう言って腕まくりをする。そして人参と玉ねぎも細切りにし、サツマイモや南瓜を食べやすい大きさと形に切っていく。もちろん米の仕込みも忘れずにした。
「えーと、味噌汁はワカメでいいかな」
何しろ本命はおかずなのだ。そこが良ければ後はなんでもいいだろうと善逸は気軽に作っていく。
「さて、衣を用意と・・・・・・」
そう言いながら善逸はたっぷりと油を注ぐと火をかけた。衣を作り終わるくらいには程よい温度になっているだろう。器に卵、そして冷水を注ぐと軽く混ぜあわせて少しずつ薄力粉を投入していく。菜箸でかしかしと混ぜ合わせ、ほんの少しダマになる程度で衣は準備完了だ。
善逸は食材に衣を絡ませるとカンカンに熱せられた油の中へと滑らせた。パチパチと聞こえる音に合わせて鼻歌を歌いながらドンドンと食材をあげていく。
台所の窓から見える空の色は茜に染まってきており本当に日が暮れるのが早くなったなぁと思っていると窓の縁にひょこひょこと獣の耳が見え隠れしているのに気がついた。
揚げ物の音に集中しすぎて気がつかなかった。善逸はパチリと瞬いてニヤリと笑う。窓を少し開けるとじいっとこちらを見る猪・・・・・・の頭をした人間が立っている。
「よお、お帰り」
「・・・・・・・・・・・・」
「そんなところにいないで入ってこ行って。面白いもん見せてやるからさ!」
善逸がニシシっと笑えば伊之助はふんっと鼻息を一つ鳴らして勝手口の方へと回った。流石に油を使ってるから窓から入るのは危ない。伊之助は勝手口から上がると手招きする善逸のそばへと恐る恐る寄ってきた。
「よーく見てろよ」
善逸は小さな器に天ぷら粉を入れるとその中に卵を割り入れる。近くの養鶏場で買ってきたばかりの産みたて卵は新鮮で張りがある。その上からさらに天ぷら粉を流し込み匙で掬ってそうっと油の中へと流し入れた。
パチパチと音を立てながら生卵に火が入っていく。善逸はこれでもかというくらいに耳を澄ませると、この3日間ほどでようやく見つけた最適な音の時に卵を油から取り上げた。
「よしっ!上手くいった!!どうよ伊之助!!」
「何がすげぇのか分からねぇ」
「はあああああ!?俺がこれ作れるようにどれだけ頑張ったと思ってんだよ!!普通は生卵なんて天ぷらにしねーーんだよ!!これ難しいんだからな!!」
善逸はぷりぷり文句を言うと丼にご飯を盛り、配置よくエビや野菜の天ぷらを乗せてさらに中央に生卵の天ぷらを乗せた。そしてつゆを掛け入れるとこれで生卵の天丼の完成だ。
「ちょっと夕餉には早いけど食っちゃおうぜ。なほちゃん達には俺たち夕餉いらないって言ってあるし」
善逸は作業台に天丼を二つ、味噌汁を二つ、そして漬物を置くと席についた。伊之助は少し迷ったような素振りを見せたが黙って善逸の斜め前に座る。
「あー腹減った。頂きまーす」
善逸は手を合わせると天丼に箸を入れる。海老を齧って白米を口入れると問題なく出来ているのに「ふむ」と一つ頷いた。続いて卵に箸を入れて二つに割ると中から黄身がトロリと流れ出てくる。
ちゃんと中がとろけているのにホッと息をつくとチラッと伊之助の方を見やった。
「食べないのか?冷めるぞ?」
「・・・・・・食う!!」
伊之助は被り物を取り払うとムンズと箸を取った。そして掻き込むように天丼を口にしていくのを善逸はニヤニヤしながら見るが、あまり見るとまた煩いかなと思い直して自分も天丼を食べ進める。
伊之助は海老を食べ、南瓜を食べ、白米を口入れて。そうしてようやく善逸が苦心して作り出した生卵の天ぷらに箸を入れた。善逸がしたように半分にするととろけた黄身が米に流れていく。
伊之助は黄色く染まった米と卵の天ぷらをいっぺんに口にいれた。するとトロトロにとけた濃厚な黄身の味とサクサクした衣の食感、そして白身の弾力のある歯応えに伊之助はパッと頬を紅潮させた。まさしく食べたことのない天ぷらだった。
「・・・・・・うめえ!」
「そりゃ良かった」
伊之助は掻き込むように天丼を食べ進めると善逸は食事の途中だと言うのに席を立って皿に取り分けていた追加の天ぷらを伊之助の丼に乗せてくれた。
「米も足りねえ!!」
「はいはい」
己の要求に唯々諾々と従う善逸に伊之助は気分が上がる。ふふんと鼻を鳴らすとドンドンと天ぷらと米を消費していく。善逸は夢中になって食べる伊之助に笑いが漏れてしまいそうだったがせっかく機嫌が直ってきたのだからと震えそうになりながらなんとか堪えた。
「おい!紋逸!卵ももっと食いてえ!」
「油に火を入れるからちょっと待って」
最後の方には天丼を作っていたはずなのに天ぷらの一品料理屋のような様相になっていた。伊之助が食べたい食材を善逸が用意して揚げて、揚げたてを伊之助が食べる。
タレや塩など好物の天ぷらを好きに食べられるのがお気に召したのか善逸に届く伊之助の音はもはや弾む太鼓のようなものだった。
「やるな紋逸!うめぇぞ!」
「お褒めいただき光栄だわ」
5日前に耳に届いた土砂崩れのような衝撃の音もなく、ジトジトとした雨のような恨みがましい音もなく、シクシクと腹が痛むような怒って意地を張った手前どう歩み寄ればいいのかわからずに戸惑う音もない。
カラリとした清々しい伊之助の音が戻ってきたのだった。
伊之助は鼻歌まじりに天ぷらを揚げる善逸の背中を、作業台にだらりと頬をつけながら眺めていた。
実のところ伊之助はここ3日くらい、善逸がこうして天ぷらを揚げていることを知っていた。窓の外や、入口の近くから中を窺うと善逸は真剣な顔で生卵を天ぷらにしようと苦心していた。
初めの頃は油が跳ねまくって少々火傷しては炭治郎に心配を掛けていたようだったが善逸は何度も養鶏場から卵を買ってきては試し料理を繰り返していた。
(生卵の天ぷらがどんだけ難しいかは俺は知らねえし、俺は普通の天ぷらだけでも好きだけどよ)
しかしながら卵の天ぷらに善逸が拘ったのは伊之助に何某かの特別を差し出したかったからだというのは分かっている。本当は鎹鴉を飛ばすのを忘れた己もマヌケだったのだと伊之助はちゃんとわかっている。その場にいなかったのだ。食事に間に合わなかったのだ。
山の中なら食べ物の取り合いは早い者勝ちで、間に合わなかったということは負けたというだけのことなのだ。それはわかっていたけど、伊之助はどうしても食べられなかったのが残念で、悔しくて、そして善逸と炭治郎が差し伸べる手を跳ね除けてしまったのだ。
「ほら。卵揚がったぞ」
そう言って差し出される卵の天ぷら。
これには親分のことだけを思って費やされた時間と努力が詰まっている。煉獄のために用意された料理よりももっと特別だ。
(仕方ねぇ!これで許してやるか!)
伊之助はニッと満足げに笑うと卵の天ぷらに齧り付いた。揚げたてのそれは熱々でとろりと溶けた黄身が伊之助の舌を襲う。
「あちっ!!」
「慌てて食べるなよー」
呆れながら笑う善逸に伊之助は「うるせぇ!」と一つ強がった。
チョコレートケーキ
腹部にできた傷口に顔を顰めながら、善逸はガラガラと小さな手押し車を押していた。任務で負った傷口は医者がしっかり縫合してくれているが、痛いものは痛い。なんでこんな痛い時に大量の荷物があるのかと泣き喚きたいが、この荷物は善逸が直々に受け取ったものなのでしょうがない。
遡ること二日前、善逸は単独で任務に出ていた。なんでも二十三歳の資産家の男が失踪するという事件が繁華街で起きているらしく、耳を頼りに二十三で金持ちの男を探した結果、実に偏執な鬼を見つけることに成功した。なんでも金持ちの二十三の男に嫌な記憶でもあるのか鬼は非常に恨み節であった。善逸も金持ちの男なんて嫌いなので鬼に共感する点もあったが任務は任務だ。・・・・・・まあ気がつけば鬼の首は切れていたのだが。ちなみに善逸は斬った記憶はない。
かくして善逸の任務は無事に終わった。腹に傷が出来ていて、善逸はすぐさま近くの藤の花の家紋の家に運ばれて治療を受けたわけなのだが、なんと驚くことにその家の娘が善逸にどうしてもお礼がしたいと言ってきたのだ。
これはもしや素敵な出会いか!?なんて期待した善逸であったが、実際のところ、その娘は善逸が先の任務の際に助けた二十三の資産家の男の婚約者であったのだ。さすが藤の花の家紋の家。嫁ぎ先も良いところだと善逸は泣きたくなる。
「我妻様、婚約者を助けていただき本当にありがとうございました」
そう言って嬉しそうにお礼を言う娘に善逸は心で泣きながらも「いいんですよー? 」と手をひらりと振った。そういえば今回の任務はこの藤の花の家紋の家から情報がもたらされたとのことだった。つまりは娘の婚約者が失踪者達と条件が同じだった為に鬼であったら大変だと慌てて鬼殺隊に連絡をしたのだろう。
「つきまして、我妻様に何かお礼をしたいのですが・・・・・・」
「ええ?でも俺は仕事でやってるですし、こうして宿を提供して貰ってるわけですし・・・・・・お礼は貰えたらそりゃあ嬉しいですけど?」
善逸は貰えるものは貰っとく主義だ。善逸の言葉に娘はにっこり笑うとお礼というものを手伝いの男に持って来させる。そして善逸の目の前に積まれたものは・・・・・・なんと製菓材料であった。
「こ、これは・・・・・・?」
「実は以前、竈門様という隊士様がいらっしゃいまして。同期の金髪の隊士様がたいそうお料理がお上手で、ご趣味にされていると伺ったものですから・・・・・・金髪の隊士様のお名前はお伺いしませんでしたが、金の髪の方などそうそうおられませんので我妻様のことであろうかと・・・・・・」
なんてこった!!炭治郎の野郎!!嘘八百並びたてやがって!!どんな伝え方したんだよ!とんでもない誤解が生まれてるじゃねーか!!
「なんでも我妻様はかの帝國ホテルの総料理長にも腕前を認められていると・・・・・・」
「ひえええ!違いますううう!そんな腕前ありませんんん!!」
藤の花の家紋の家でとんでもないことを吹聴されていると善逸は戦慄した。炭治郎が善逸の料理を自慢したいという欲求があるのを承知していたが、なんでこんなところで自慢するのかと今すぐ問いただしたい。
「またまたご謙遜を。竈門様がお持ちになっていらしたお弁当は見事な出来栄えでしたもの」
クスクスと笑う娘は本当に善逸が料理が上手いと信じ切っているようだった。善逸は弁当という言葉にいったいいつの弁当だと記憶を巡らせるが、炭治郎や伊之助に弁当を持たせるのはそこそこの回数があったのでもはや見当もつかない。
「実は我妻様の腕前の話を聞いた婚約者が、それならば是非とこうしてお礼の品を用意したのです。我妻様の腕前ならば扱える筈だと申しておりました」
「んん?婚約者の人が?」
「はい。実は婚約者は楓月堂の後継でして」
「楓月堂?え、あの洋菓子屋さんの!?」
「はい。その通りです」
善逸は娘の返答になるほどと頷く。そして目の前に積まれた製菓材料の数々に納得する。実に高級な品々が揃っているのは老舗菓子店の息子だからか。
「うわっ!これもしかしてチョコレイト!?」
善逸が目にしたのは黒い塊である。帝國ホテルでも扱いがあったそれは、菓子専門の料理人が扱っていたので善逸も近くで見るのは初めてだ。
「はい。楓月堂は日本初のチョコレイトを扱う店ですから。これは商品ではなく、製菓用に扱いやすいように作られたチョコレイトです。そのままでも勿論食べられますが・・・・・・こちらに彼が考案したお菓子帳の写しがありますので、良ければ是非、洋菓子を作ってみてあげてください」
「え?お菓子帳?それって人に渡してもいいものなの?」
「はい。これはまだ試作段階のものばかりなので大丈夫です」
ふうんと思いながら善逸は紙に包まれたチョコレイトを見る。そして手元にある紙を捲り、ざっくりと中を見て作りやすそうなものはないかと探した。
「あ、このビスコッティっていうのは作りやすそうかも」
「我妻様、差し出がましいことですがお勧めはこちらです」
「ん?」
娘さんは善逸の隣に来るとペラペラと帳面を捲り、一面にびっしりと文字が書かれている箇所を示した。そこにはチョコレイトケェキと書かれてもの凄い細かく色んなことが書いてある。
「え?これがお勧め?」
「はい」
「本当に?俺、お菓子なんて作ったことないんだけど?これ難しそうなんだけど?」
「大丈夫ですよ。我妻様なら」
にっこり笑う娘さんからはゴゴゴゴゴと音がしており、なんとしても善逸にこのチョコレイトケェキを作らせるという意思を感じさせた。善逸はごくりと喉を鳴らし、レシピと目の前の製菓材料を見る。驚くことにこのチョコレイトケェキを作る材料が全て揃っているではないか。
「ええと」
「もしお作りになられたら、是非出来栄えやお味などお教えくださいね」
「・・・・・・はい」
****
「ようするに実験台にされてんのよ」
「実験台?」
蝶屋敷の住居棟、借り受けている一室で善逸と炭治郎は向かい合って座っていた。お互いに負傷しており、善逸は腹。炭治郎は肩から背中に掛けて負傷している。
善逸が腕を組み難しい顔をしているのを見て、炭治郎は首を傾げた。そして目の前にある製菓材料を見てどうして実験台などと善逸が言うのか考えてみたがさっぱり分からない。
「なんでそう思うんだ?」
「いや普通に話してるの聞こえた。なんか後継の婚約者とやらはお父上に自分の腕前というか考案した菓子を認めて貰いたいらしいのよ。ほんで帝國ホテルの総料理長に腕を認められてる金髪の隊士に自分のレシピが評判良かったら大手を振って父親に見せられるってわけよ。いやーなんでその金髪の隊士は料理が上手いって話が藤の花の家紋の家にまで知れ渡ってんのかねえ?全くもって不思議じゃない?誰が吹聴してんだろうねぇ?」
善逸の言葉に炭治郎は申し訳なさそうにして俯いている。善逸の耳に届く炭治郎の音は落ち込むような音で後悔はない。善逸が料理の腕を誰かに広めるのにいい顔をしないことを分かっていたのについつい口を滑らせた己の不出来に落ち込んでいるのだ。
「まあ、お前のことだから持ってる弁当のことをなんか言われてついつい口を滑らしたんだろうけどさあ」
「そうなんだ!俺は善逸の弁当の出来を褒められて嬉しくなってしまって・・・・・・!だがちゃんと名前は伏せたんだ!同期の友人が作ってくれたと名前はちゃんと伏せたんだ!!」
「でもお前!俺の容姿も話しただろ!!鬼殺隊に金髪って俺しかいねーじゃん!伏せられてねーよ!!」
「うっ。ごめん・・・・・・!どんな人なのか聞かれて、ついつい髪が稲穂のように美しい金だと言ってしまって・・・・・・」
しゅんと身体を小さくする炭治郎に善逸は腕を組んだままチッと舌を打つ。その音に炭治郎はますます身体を小さくした。
「お前、罰として助手やれよ」
「え?助手?」
「チョコレイトケェキを作る助手!なんでも火加減が大事って書いてあるのよ。なんか長時間一定にしろって。炭治郎は火加減みるの得意だろ。だから手伝えよ。それでチャラな」
善逸の言葉にパッと炭治郎は顔色を明るくした。チャラというのもだが、火加減の腕前を期待されるのは炭焼き小屋の息子として嬉しいものがある。
「任せてくれ!火の扱いなら誰よりも自信があるっ!」
「おー任しますとも。何しろ今回は西洋かまどが相手だからな。期待してるわ」
善逸はそう言ってお菓子帳をパラパラと捲る。そして唇を尖らせて胡座に肩肘付きながらチョコレイトケェキの作り方を読み始めた。
「せ、西洋かまど?それって普通のかまどと違うのか?」
「違うよ。何かこう・・・・・・扉付きの箱でね、それを外から火で熱して箱の中のものを蒸し焼きにする調理用の道具だよ」
「え?箱って燃えないのか?」
「あー、大丈夫。燃えない素材だから」
そう言って黙々と紙面に目を落とす善逸を見ながら、炭治郎はソワソワと身体を動かす。何しろ初めて使う道具なのだ。善逸の期待に応えられるだろうかと僅かに不安になる。そもそも西洋かまどと聞いて造形すら想像できないのだ。手に余るものだったらどうするかと炭治郎は唸った。
「・・・・・・あれ?蝶屋敷にそんなものあったか?」
炭治郎はふと疑問に思った。よく調理場を借りるが、大きい台所も小さい台所もそんな不思議なものはなかった筈だ。
「んん?ああ、なんかチョコレイトケェキ作りたいから庭に石窯っぽいもの組んでいいかしのぶさんに聞いたら買ってくれるって」
「ええっ!?」
「しのぶさんに話したのついさっきよ?十四日の朝には届くってよ。凄くない?手配して二日で届くものなの?ははっ。柱の権力怖いわ」
乾いた笑いを零す善逸の顔色は悪い。炭治郎もまた、しのぶという名前により緊張感が増した。しのぶが機材まで用意してくれているのだ、失敗しましたは許されることじゃない。上手くできたら皆んなに振る舞えばいいという心持ちではダメなのだ。必ずや成功させなければならない。
「善逸!頑張ろう!俺も出来る限り、尽力するぞっ!」
「うん、まあ、頼むわ。ほんとおおおおに頼むわっ!!」
そう言った善逸からビャッと涙が飛び出した。善逸は「ひええええん!作ったことないもん作るの怖いよおおおお!」とベソベソ泣いている。炭治郎はその背を撫でながら「大丈夫だ!今までも何とかなってきただろう!善逸なら大丈夫だ!」と励ました。
****
来る二月十四日の朝。本当に蝶屋敷に西洋かまどが来た。炭治郎は朝からその西洋かまどの仕組みを理解するのに真剣で、蓋を開けたり閉めたりしている。その姿を横目で見ながら、善逸は台所の作業台に必要な材料を置いていった。
「炭治郎どーお?」
「・・・・・・うん。たぶんこっちの右側に調理する物を入れて、反対の左側には薪を入れて・・・・・・火を起こして温めるんだと思う。どれくらい熱せばいいのか・・・・・・ちょっと俺はこっちの様子確かめるのに専念してもいいだろうか?」
炭治郎は振り返って申し訳なさそうに言った。西洋かまどに専念ということは、下準備や調理が手伝えないということだからだ。善逸は元より手伝いは西洋かまどの火だけで良いと思ってたので気軽に頷いた。
「いいよいいよ。オーブンが要だしな。そいつ動かないと食えないし」
「オーブン?」
「海の外ではそう呼ぶんだよ」
なる程と善逸は物知りだなぁという顔で頷く炭治郎はどこか誇らしげだ。その反応に「善逸に聞いたんだが!!」とでかい声で善逸のことを強調しながら話を巻き散らしそうだなと善逸はゾッとする。しかし口止めしても炭治郎は「なんで言ったらダメなんだ?」とか本気で不思議という顔をするので善逸はもう何も言わないことにした。無駄なことはしない。口止めしてもどうせポロッと言ってしまうからだ。
「善逸は物知りだなぁ」
「はいはい」
「むっ!なんで呆れた匂いをさせるんだ!」
「ほらほら、早くやっちまおうよ!今日はしのぶさんに任務がない日なんだから、俺は今日中に作っちまいたいの!」
善逸の言葉に話を逸らされたと不満げにしながらも炭治郎は薪を取りに庭へ出て行った。その姿を見送って、善逸はふうと息を吐くと目の前の材料達を睨む。
卵に砂糖にチョコレート、薄力粉にバターに牛乳に。色々使う材料があり、善逸は貰ったお菓子帳に書かれてるものと相違ないか確認していく。そして材料のひとつ、瓶に入ったそれをふむっと見つめた。
「ラム酒・・・・・・ねえ?酒蒸し饅頭と似たようなもんか」
善逸はまずは湯が必要と鍋に水を入れて煮立てた。その間にバターをケェキの種を流し込む型にぬり、チョコレイトが湯煎でよく解けるように細かく切り刻む。
後ろではいつの間にか戻ってきている炭治郎がせっせと西洋かまどに薪をくべていた。その横顔は真剣そのもので、鬼と対峙してる時と同じような顔をしているのけど、相手は料理用の西洋かまどだ。しかし火の扱いに関しては炭焼き小屋の息子としての矜持があるのだろう。炭治郎から聞こえる音の真剣さに善逸は「これなら焼くのは心配ないな」と安心する。炭焼き小屋の息子は必ずやいい結果をもたらしてくれるだろう。
「えーと、湯煎の際にチョコレイトに水を入れてはいけない・・・・・・」
善逸はお菓子帳の注意文を読みながら作業を進めていく。チョコレイトに湯煎の湯が入るとダメらしいのは分かるが、なぜダメなのかは不明だ。はてと思いながらも湯が沸くまでの間で卵黄と砂糖を混ぜて行く。中々に力と根気がいる作業だし、なんで黄色かった卵黄が白くなっていくのかも不明だ。西洋菓子は不明なことが多い。
「えーとチョコレイト、バター・・・・・・っと」
「善逸!これってどれくらい温めればいいんだ?」
「・・・・・・適度って書いてあるわ」
「え?適度?適度ってどれくらいだ?」
炭治郎と善逸は二人で顔を見合わせて、焼ける匂いと焼ける音で判断しようと決めた。ひとまず炭治郎はどのくらいの火でどのくらいの火力になるのかを調べるらしい。そちらは完全に炭治郎にお任せだ。
善逸は湯煎の中で温めたチョコレイトとバターをかき混ぜて溶かし、そこにやや温めた牛乳を投入して混ぜていく。そこに何故か白くなった卵黄も入れ、最後にラム酒を入れようと瓶の蓋を開けた。
「えっ!?何の匂いだ!?」
「えっ?酒だけど?ラム酒っていうらしいよ」
炭治郎に瓶を掲げて見せると、炭治郎は困惑した顔をしていた。以前ビーフシチューを作った時もそうだったが、西洋酒の匂いにやたらに驚く。苦手なのだろうかと善逸はもう一つ小さなケーキ型を手に取った。それにバターを新たに塗る。
「ええと、ラム酒を入れて・・・・・・こんなもんかな」
少量のラム酒を入れた善逸はそこから必死にかき混ぜる。帳面にはひたすら混ぜるとあるのでひたすら混ぜた。途中、本当にこれでいいのかと思う場面があったが、ひたすら混ぜていたら滑らかな生地になっていく。
「えーと、次はっと・・・・・・」
善逸は卵白をかき混ぜながら俺は本当に何をしているのだろうかと考える。ひたすら混ぜる作業が多いため、頭は色々と考えてしまうのだ。何でこんなことにとか、けどせっかくの高級食材だしとか、ふつふつと考えが浮かんでは気泡のように消えていく。
「ん?」
ソワソワと聞こえる音に何かと顔を上げた。すると台所の入り口にすみ、きよ、なほが覗いており、さらに三人の後ろからカナヲまでもが覗いている。すみ達三人はワクワクした音をさせていて、善逸に気づかれているのを知らないのかコソコソと「楽しみー」「美味しそうな匂いする」と話して廊下を駆けていった。ちなみにカナヲだけは変わらず覗いているし、ワクワクした音は止まない。
声を掛けようか迷ったが、そろそろメレンゲなるものができてしまう。ここからは余りもたもたしてはいけないとお菓子帳にも書いてあるため、善逸は泣く泣く作業に集中することにした。
(くっそーーー!カナヲちゃんと楽しくお喋りできそうなのにーー!!)
チョコレイトケェキの素を西洋かまどに入れさえすれば手が空くのだと善逸は急いでかき混ぜて、チョコレイト生地とメレンゲを合わせていたが、肝心のカナヲは満足したのかトタトタと去っていってしまった。
「ああああああああーーー!!」
「うわっ!どうした善逸!?」
「なんでもありませんんん!!そろそろ焼いてもいいですかね!?」
善逸と炭治郎は型に流し込んだものを温められて西洋かまどの庫内に入れた。大きいものをひとつ、小さいものをひとつ。パタンと閉めて二人してじーっと西洋かまどの前に張り付く。何しろよくよく聞いて、嗅いでいないと温度調節が難しいからだ。
炭治郎は時折、隣の蓋を開けると火の調節をした。善逸はその様子とケェキの中からじゅわじゅわ聞こえる音に耳を傾けていた。炭治郎は余程、火加減に真剣なのか善逸がまじまじ見ているのに気づきもしていない。そういえばカナヲ達にも気がついていなかったなと善逸はぼんやり思った。覗いているのに気がついたら炭治郎な迷わず声を掛けるからだ。
(すけー真剣。心音も割と早いし、緊張してんのかな?あー・・・・・・顔赤いな。やっぱ火の番って暑いもんな)
善逸はお茶でもいれようかと立ち上がる。するとこそりとこちらを覗く陰にカナヲが戻ってきたのかなと思うと洗濯物を抱えたアオイがいた。
「アオイちゃん」
「・・・・・・どうも。とてもいい匂いがしたので・・・・・・その、つい」
恥ずかしそうに、プイっと顔を逸らすのに善逸はデレッとする。やはりアオイのようにきっちりかっちりした子でも甘いものには惹かれてしまうのだろう。
「えへへぇ。炭治郎に火加減見てもらってるし、たぶん上手くできると思うよ!完成したら皆んなでお茶にしようね!」
「・・・・・・楽しみにしてますね」
アオイはそう言って微かに笑うと早足で廊下を過ぎていった。善逸はデレついた顔を隠しもせず「やっぱり女の子は可愛いなあ? 」と思いながら振り返れば、炭治郎がじっと瞬きもせず真顔で善逸を見ていた。
「ひえっ!なによ!」
「・・・・・・・・・・・・」
炭治郎は無言のまま西洋かまどに視線を戻す。静かな様子に善逸は「ええ??」と言うが、炭治郎は無反応だった。
***
「おおー!やったー!できたー!」
「いい匂いだな!これは間違いなく中まで焼けてる匂いだ!」
バンザーイと二人で喜んで、善逸と炭治郎はチョコレイトケェキを西洋かまどの庫内から取り出した。それを作業台に乗せて、ケェキを型から取り出す。丸くできたチョコレイトケェキに二人は満足げに頷いた。
「冷めたら完成ー!温かくても美味しそうだけどねぇ?」
「でもそろそろ伊之助も戻ってくるだろ?先に食べたらうるさいぞ」
「それもそーね。伊之助が来る頃には冷めてるか」
一旦はお預けだなと善逸は薬缶に水を入れた。ひとまずチョコレイトケェキはなしでお茶にしよう。そう思っていたら善逸の肩にボスンっと炭治郎の顎が乗る。えっ、と思い目をやれば炭治郎はとろんとした目で善逸を見ていた。その目の色がなんか濁っている気がして善逸は冷や汗が流れる。
「た、たんじろーさん?」
「うー・・・・・・んんっ・・・・・・」
炭治郎は鼻先を善逸の首に埋め、すんすんグリグリとしてくる。善逸はひえっとなりながら身を竦めた。手にある薬缶が揺れて水が溢れる。
「善逸は・・・・・・いい匂いするなあ・・・・・・」
耳元で囁かれる炭治郎の熱っぽい声に善逸はゾワゾワっと背筋が震える。耳がいい善逸は当然の如く耳も弱い。吹き掛けられる吐息に歯を噛み閉めて変な声が出そうになるのを必死に耐えた。
「ちょ、お前、炭治郎!どうした!?」
「んん??」
「炭治郎さん!?ねえ!?もしもし!?」
ぎゅうぎゅうと抱きしめてくる力に善逸は混乱した。善逸から抱きつくことはあったとしても、炭治郎からなんて今まで皆無だ。それに善逸もこんな風に閉じ込めるような抱きつき方などしたことない。だいたいは恐怖からの縋りつきなのだから。
「炭治郎!?たんじろおおお!」
「あらあら、なんの騒ぎですか?」
「あっ!しのぶさんっ!!」
男が男に抱きしめられているという地獄に来たしのぶは仏になりうるのだろうか。しのぶさんに見られたのが既にしんどいと善逸は思いながらも、炭治郎を引き剥がして貰いたいので縋るようにしのぶを見た。しかししのぶは台所に入ってすぐ、美しい柳眉を寄せて首を傾げた。
「・・・・・・なんだかお酒くさいですねぇ。洋酒ですか?」
しのぶの言葉に善逸はすんっと鼻をならす。確かに酒の匂いがしているかもしれない。しかしケェキに使った量はそれ程の量ではないのにと、ふと作業台を見れば見事に蓋が閉められてないラム酒の瓶が見えた。そして次いで炭治郎の鼻の良さを思い出す。
「あーーー!!炭治郎!?お前まさかラム酒の匂いに酔っ払ってんのか!?」
「んん?・・・・・・善逸・・・・・・」
「あらあらまあまあ」
「おい!しっかりしろ!たんじろおおおおー!」
酔っ払ってるなら揺さぶることも出来ない。善逸は抱きしめてくる炭治郎が寝落ちするまでの間、ぎゅうぎゅうと抱きしめられて続ける羽目になった。
***
炭治郎が目を覚ますと布団に寝かされていた。むくりと起き上がり、何でだろうか首を捻る。記憶を辿ってみれば、善逸とチョコレイトケェキを作っていて、焼き上がって二人で喜んだところまでは覚えていた。しかしその後のことは霞が掛かっており曖昧だ。
炭治郎はぼんやりと窓の外の夕陽を見て、部屋の隅にある禰豆子が眠っている木箱を見て、そろそろ禰豆子も起きるかなあなんて考えていてハッと我に還る。夕陽が見える。もう夕方だと炭治郎はだらりと冷や汗を流した。部屋の中に伊之助の刀が二本、転がっている。つまりは伊之助が任務から帰ってきているということだ。
「しまった!!食いっぱぐれた!!」
なんで自分が眠っていたかは知らないが、この時間は確実にお茶の時間は過ぎ去っているだろう。伊之助も帰ってきているのだし、部屋に伊之助の匂いはほぼ残っていないから戻ってきたのは随分前だ。
しかし部屋にはチョコレイトケェキの匂いが強く残っている。これはきっと善逸と伊之助がここで食べたからに違いない。腹を空かせて戻ってきた伊之助が炭治郎が起きるのを待ってくれるかというのは・・・・・・少々、分の悪い賭けだ。
「ああー・・・・・・やってしまった」
炭治郎はがっくりと肩を落とす。炭治郎は長男ゆえに欲しがる誰かに自分の分を差し出すのにさして抵抗はないし、今までも気にしたことはないが・・・・・・善逸の料理に関しては別だ。炭治郎は善逸の作る料理が好きなのだ。勿論味が美味しいこともあるが、善逸の料理を食べると心の真ん中が温かくなって幸せな気持ちになる。それに病みつきになってしまっているのだ。
「ぐううううううう」
悔しさのあまり歯を食いしばって炭治郎が唸っていると、カラリと襖が開いた。そちらに目をやれば呆れた顔の善逸がいる。
「何を唸っているのよ」
「善逸・・・・・・」
「目ェ覚めた?具合はどうだ?気持ち悪くないか?」
ほんの少しだけ伺う目で見てくる善逸に炭治郎ははてと思う。なんでそんなに心配するのか不思議だ。
「いや、特に変わったところはないが・・・・・・そういえば俺はなんで眠っていたんだ?」
善逸は足が布団に入ったままの炭治郎の元へと来ると、「よっこいしょ」と言って正座をする。そしてチラと炭治郎の顔色を見て様子がおかしくないことを確認するとふむっと頷いた。
「なんでってお前、ラム酒の匂いに酔っ払って寝たんだよ」
「えっ!?」
「まさか匂いだけで酔っぱらうとは思わなかったわ・・・・・・。まあ原因は俺がラム酒の瓶の蓋を閉め忘れてたからなんだけどね?ごめんよ炭治郎・・・・・・」
申し訳なさそうに言う善逸に炭治郎は首を振った。まさか匂いだけで酔っぱらうとは善逸も想像していなかっただろう。何しろ本人である炭治郎も思っていなかったのだから。
「いや、気にするな。しかし酒の匂いだけで酔っぱらうとは・・・・・・。今までそんなことなかったんだがなあ」
炭治郎は腕を組んで昔を思い出すが、酒の匂いがすごく嫌だと思ったこともないし、苦手だったこともない。どういうことかと考えていると善逸が「んー」と唸った。
「もしかして洋酒だったからかな?前もお前、ビーフシチューを作った時も何の匂いだって驚いてたろ」
「そうだったか?」
「そうだったのよ」
こくりと頷いた善逸に炭治郎はそうだったのかと納得した。確かに日本の酒と違い、洋酒は独特な匂いがする。嗅ぎ慣れていないから深く考えなかったが、もしかしたら洋酒には弱いのかもしれないと炭治郎は思った。
「そうだ!お茶の時間はどうなった!?」
「お茶の時間?とうの昔に終わったよ?」
「やっぱりそうなのか!!ああ・・・・・・なんてことだ・・・・・・」
布団に蹲り、炭治郎は頭を抱えた。善逸の作った料理を食べたかったし、初めて使った西洋かまどで焼いたケェキの出来栄えも知りたかったのにと唸る。善逸との共同作業だったのに、結果だけを逃してしまったと炭治郎は心の中でさめざめ泣く。
そしてゆっくりと身体を起こすと炭治郎の様子がおかしいことに若干引き気味の善逸を見遣り、言った。
「善逸。タラの芽の天ぷらが食べたい」
「はいぃ?」
「食べたい!!俺は善逸の作ったタラの芽の天ぷらとタラの芽のお浸しとタラの芽の味噌和えが食べたい!!あと出し巻き卵も食べたい!!」
「増えてんじゃねえか!!どうしたんだよいったい!!」
驚いた顔をする善逸を炭治郎は恨みがましく見た。食べ物の恨みは怖いという言葉を炭治郎は知ってはいるものの、いまいち共感や実感したことがなかったのだが・・・・・・今、なるほどこれがと納得している。
「チョコレイトケェキを食べ損ねてしまった!埋め合わせを要求する!」
「えええええ?何よそれ。やだよ。必要ないし」
「なっ!!」
以前、伊之助がローストビーフを食べ損ねた時は怒って駄々を捏ねる伊之助に善逸はしょうがないとばかりに卵の天ぷらを作ってやっていたのにと炭治郎は悲しくなった。伊之助には練習までして作ってやっていたのにとさらに悲しくなる。
「・・・・・・伊之助ばかりずるいぞ。俺だって伊之助と同い年なのに」
そうは言っても今回は事情が違うのは炭治郎も分かっていた。前回、伊之助はローストビーフを楽しみに任務を終わらせて急いで帰ってきたのになかったのだ。しかし炭治郎は自分が酒に酔って倒れるという失態からの食べ損ねだ。伊之助の方が頑張っていたのは分かっている。しかし、それでも伊之助ばかりずるいと羨んでしまう。
「何だよ炭治郎お?お前、伊之助にヤキモチ妬いてんのかぁ?」
ウィヒヒっと笑い、ニヤつく善逸から炭治郎は顔を逸らした。今はまだ心がくさくさしているから、善逸の軽口の相手はできない。みっともない姿を晒してしまうだろうから。
そうやって炭治郎が善逸から顔を逸らしていると、善逸ははーっと大きな溜息をついて立ち上がった。畳が擦る音に炭治郎は慌てて振り返る。長男なのに子供っぽい態度を取ってしまい、呆れられて部屋を出て行くのだろうかと不安になった。
しかし善逸は窓の雨戸を閉め、ランプの灯りをつけてから部屋の隅にあった禰豆子の入っている背負い箱の前に腰を下ろした。そしてコンコンコンと木箱を軽く叩く。
「禰豆子ちゃん?お兄ちゃん起きたよ。預けてたもの渡してもらってもいい?」
善逸がそう言うと箱の扉が内側から開き、小さい姿の禰豆子が出てきた。片手に皿が持たれており、皿の上の物を落とさないように気を付けているのが這い出す動きで分かる。
「禰豆子ちゃん、預かってくれててありがとうね。お兄ちゃんに渡して来てくれるかな?」
「むー」
禰豆子は善逸の言葉にこくりと頷くとトテトテ歩きながら炭治郎の元にやって来る。そしてずいっと皿を差し出した。
「むっ!」
「禰豆子・・・・・・善逸・・・・・・これって・・・・・・」
炭治郎は禰豆子が差し出す皿を受け取ると、その上に乗っている物を見て、禰豆子を見て、そして善逸を見た。善逸は目を猫のように細めながら微笑んでいる。
「お前さんの分のチョコレイトケェキだよ。伊之助に食べられちゃわないように禰豆子ちゃんに預かって貰ってたんだよ」
「むーっ!」
禰豆子は頑張ったというように胸を張っている。そんな禰豆子を見ながら善逸はデレデレと様相を崩していたが、これは善逸の普段の行動なので今更だ。炭治郎は目の前にあるチョコレイトケェキに目を輝かせる。嬉しい。食べ損ねなかった。善逸はちゃんと自分のことを考えてくれていたと?を緩めた。
「ありがとう二人とも。すごく嬉しい」
炭治郎の心からのお礼に禰豆子は満面の笑みを見せて、善逸は照れたように?を掻いた。
「あ、いまお茶と突き匙を・・・・・・ってそのまま!?」
善逸が言い終わるよりも早く、炭治郎はチョコレイトケェキを掴んで口に入れた。ポロポロと溢れるものを慌てて皿で受け止めて、そういえば布団の中だったと咀嚼しながらも慌てて畳の上に移動する。
「むぐむぐ・・・・・・うんっ!美味しい!」
「そりゃ良かった。しかしお前さん、手がですねえ?汚れるんですけど・・・・・・」
「本当だ。チョコレイトがつくな」
炭治郎はそう言いながらペロリと指を舐める。口に広がる甘い味は和菓子とは随分違う。甘さが強くてしかし苦味もあり、匂いも嫌いじゃない。すんっとチョコレイトケェキの匂いを嗅いで・・・・・・そして炭治郎はおやっと思った。
「洋酒の匂いがしないな?飛んでしまったのか?」
スンスンと嗅ぐがやはり匂いがない。ビーフシチューには洋酒の匂いがしていたのにおかしいなと首を捻った。
「ああ。それにはラム酒入れなかったのよ。お前さん、洋酒に過敏に反応してたから苦手かと思ってさ。それは別に作った小さい方のケェキの方なの。ラム酒が入ってる方は食べるとしっかり酒の風味あったよ」
さらりと言った善逸に炭治郎はドッと心臓を握られたかと思った。あっけらかんと言っているが、このチョコレイトケェキは炭治郎の為だけに作られたということだ。その事実に炭治郎はドキドキとした。
「えと、そうだ!皆んなはなんて言っていた?評判はどうだった?」
ドキドキした気持ちが収まらず、しかし目の前には善逸だけでなく妹の禰豆子もいるからと炭治郎は自分の中で湧き上がる何かを抑え込んだ。湧き上がりかけた何かはなぜ禰豆子がいると発露できないから炭治郎にはいまいち分からなかったが、今はそうするべきだと本能的に判断したのだ。
「えへへへぇ!それがさあ!皆んな美味しい美味しいって食べてくれたのよ!しのぶさんにも『素晴らしく美味しいです』って褒められちゃったし?!いやあ?女性の方々のあの笑顔を見れるもんならまた作ってもいいかなーなんて思うよね!くふふっ? 」
デレデレと笑う善逸に炭治郎はちょいともやりとしたが、善逸は素直に褒められたことを噛み締めているようで、本当に嬉しそうに笑っている。善逸は少し卑屈なところがあるから、こうして賞賛を素直に受け取るのはいいことだ。善逸が幸せそうにしているなら、炭治郎は自分も嬉しいとモヤを飲み下した。
「良かったな。善逸」
「うん。炭治郎もありがとうね。炭治郎が手伝ってくれなきゃこんなに上手くいかなかったよ」
善逸の心からのお礼に炭治郎は口元が緩む。善逸は実は本当はなんでもできる男だから、自分がいなくても西洋かまどは何とかして使いこなしただろうと炭治郎は思っている。しかしそれでも、『炭治郎、助けておくれよお』というように善逸に頼られるのが炭治郎は堪らなく好きなのだ。
「どういたしまして。また何かあったら手伝うぞ」
炭治郎はそう言うとまた一口、チョコレイトケェキを口に入れた。甘苦い味が舌の上を滑る。この味は善逸が自分を思って作ってくれたものだと思うと、胸の真ん中辺りがポッと温かくなるのを感じる。
「善逸の料理は病みつきになるなあ」
「それは過言にも程があるわ」
続く??
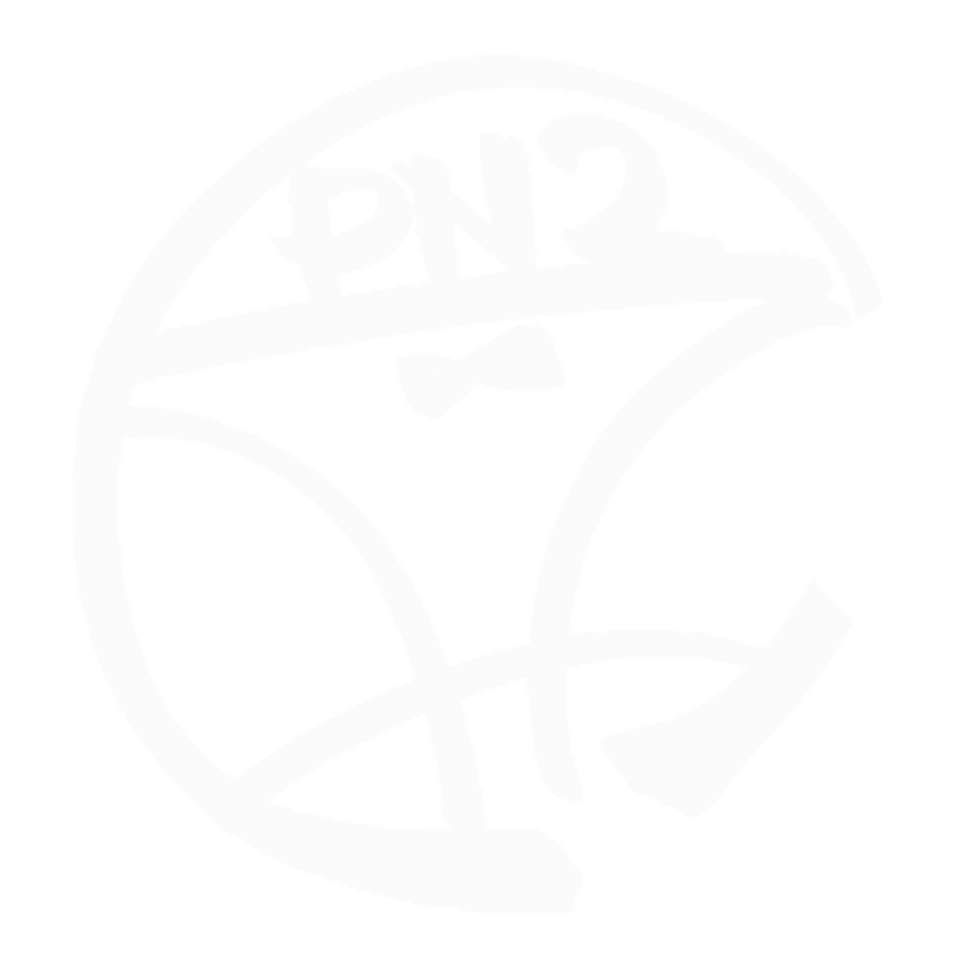


コメント