2020年11月に出した本の再録です。
高校生の炭と善が生まれ変わって出会う話。記憶なし×記憶あり。
約124000字/全年齢/現パロ/炭善
記憶のある男
「生まれ変わっても、一緒にいたい」
そう言って、旭柄の耳飾りを揺らしながら笑った男のことを、忘れられないし、好きだと思っている。
「またこの夢かよ……頻繁に見るなぁ」
木目がうねる天井を見つめ、善逸はその一部が顔に見えてきた段階で視線を逸らした。この家に施設から引き取られて早八年。天井のアイツとも長い付き合いだな、なんてくだらないことを考えてやり過ごそうとするが、善逸の頭の中はさっき見た男の夢でいっぱいだ。あの夢を見た日は、情緒の振り幅がいつも以上に大きく、煩いと言われる回数も多くなるので、善逸は朝から憂鬱だ。
(こういう日はきっと、行かない方がいいんだろうけど)
善逸はガバリと起きて部屋を出た。家の中はまだ寝静まっている……わけではなく、祖父は日課の朝の散歩に出かけていて、義兄は今年の春から大学の寮に入ってしまっている。
善逸は古い木造平家の桑島家の廊下をスウェットの裾から手を入れ、腹をボリボリ掻きながら歩く。冬の間は古い木造ということでやたらに寒かったが、桜も散った頃となれば過ごしやすいものだ。善逸は台所に入ると横着してそこで顔を洗った。何しろ水で簡単に顔を流しておしまいだ。
善逸はタオルで顔を拭きながら、朝ごはんと弁当を作ろうと水が張った鍋をコンロにかける。そして卵を幾つか取り出して厚焼き卵を作ろうとボウルにカンッと当てた。弁当の他のおかずは昨日の残りで良いので特に考えることもなく、ボーッとしていても慣れた手は勝手に動いていく。
交替制とはいえ、伊達に中一から料理をしているわけではない。母親が健在で時間にも余裕のあるご家庭のクラスメイトと比べれば、間違いなく料理はできると、四月にあった調理実習の様子を思い出して、善逸はふふっと笑った。
(あの時は、我妻君すごーいって女の子達が目を輝かせて褒めてくれたんだよなぁ)
善逸はニヤニヤとしながら、きゅうりを飾り切りする。もちろん、弁当に入れる為だ。とはいえ、だいたい外で一人で食べる為に誰に見られることもないのだが。善逸は飾り切りしたきゅうりを朝ごはん用にも量産しながら、あいつはこんなお洒落なことはしない奴だったなと、料理は上手いが飾り気のないものを作る男を思い出す。よくない。朝見た夢のせいで何でも思考が男に向かって行ってしまうと善逸は軽く頭を振った。
味噌汁がすっかり温まり、魚も焼けて簡単な付け合わせもできた頃、善逸の祖父である慈悟郎が戻ってきた。善逸はチラリと慈悟郎の足を見て、無事に二本あるのに毎朝なんだか安心する。完成した二つの弁当は蓋を閉めず空気に晒したまま、善逸は食卓に朝食を運んだ。義兄がいた頃の料理当番はフレキシブルなシフト制であったが、今はもっぱら朝昼は善逸の担当だ。夜は部活の都合で善逸は帰りが遅いので、慈悟郎がほとんど用意してくれている。
「ふむ、では頂くか」
「うん」
「頂きます」
「頂きまーす」
二人で向かい合って手を合わせる。今は一人足りないが、このやり取りを八年もしているのだと思うと善逸は不思議な気持ちになる。前はたった一年間で、三人だったのは半年程もなかった。そんな短い期間の縁なのに、こうして新しく生まれてみれば三人がまた集い、家族のように振る舞っているのだから相当に濃い縁だったのだろう。
(兄貴は可哀想だけど。いやでも、思い出さなきゃ平気なのかな)
夢を見たせいか今日は調子が悪い。どうしても昔に紐づけて考えてしまうのが善逸の悪い癖で、目の前にいる慈悟郎の箸の動きを見て、前とはどう違うかな、なんて間違い探しをしてしまう。そして違うことが少ないほど安心するが、しかし安心する自分を気味悪く思ったりする。
ああ、情緒が安定しない。本当なら叫んでしまえばいいのかもしれない。昔のように、大声で、怖い怖いと泣き喚いて誰かに取り縋れば良いのかもしれない。しかしそれをしたら、言っている内容を考慮すると病院のお世話になってしまう。そんなことになればここに居られなくなるかもと、善逸は結局、黙るのを選び続けている。
(ちゃんと自覚があるから、大丈夫だ)
自分で斬った自覚がない時は、目を覚ますと首が落ちていて怖かったが、自覚してしまえばだいたいは大丈夫になった。善逸は騒ぐか、黙るか、選べるようになった。そして今もきっちり自覚して覚えているので、善逸は黙ることができる。本当は泣き叫びたいけれど、それをしている場合じゃないと呼吸を紡ぐことができる。
「今日も美味いぞ」
「本当? ありがとう爺ちゃん」
泣くのを控えれば、義兄との仲も険悪まではいかない。恥を晒さなければ、善逸は歩くのが困難ではなかった。とてつもなく心は苦しいけれど、義兄である獪岳との関係を少し仲の宜しくない男兄弟、といった程度で維持できている。頸を斬って落としてやった昔を考えると、とても凄いことではないかと善逸は思うのだ。慈悟郎に笑いかけながら、善逸の脳裏では、ゴトンゴトンと繰り返し義兄の首が落ちる様が浮かんでは消える。食欲が減退するなあと思いながら、善逸は味噌汁を啜った。
「爺ちゃん、じゃあ俺、朝練だから」
「うむ。車に気をつけてな」
「うん。分かってる」
善逸が通学用の服に着替えて台所に戻ってくると、慈悟郎は後片付けを始めていた。それを流し見しつつ、善逸は弁当に蓋をして保冷バッグに水筒と一緒に入れる。もう一つのは慈悟郎の弁当だ。歳の割には大きいサイズで、毎度食べ切ってくれているのに密かに善逸は安心している。今回はもっともっと長生きしてほしい。
「じゃあ行ってきます」
善逸はそう言って家を出た。部活バッグである剣道の防具入れを背負い、走り出す。肝心の剣道の防具は学校の防具置き場にあるので鞄の中身は教科書と弁当だ。余白が大きいのでガチャガチャと中が揺れているが、幾つもカバンを持つのが面倒なので善逸はこれを使っている。帰りにスーパーで買い物をした時も全部入って楽なのだ。ちなみに匂いが染みつかないようにすごく気を付けている。でないと夢の男に顔を顰められ、もう出てきてくれなくなるかもしれないと思っているからだ。
善逸は住宅街を抜け、緩やかな坂を下っていく。そして十分程走った頃に商店街が見えてきた。この商店街は善逸が普段使っている家のそばのものではない。家と学校のだいたい中間くらいにある商店街なのだ。善逸は息切れひとつせずに商店街に差し掛かると、いい匂いがする店の辺りでゆっくり減速した。
ガラスのウィンドウから中を覗くと、パンはすっかり並べられている。善逸がスポーツタイプの腕時計を見れば、七時になる少し前だった。店の扉に目をやると『閉店中』の札が掛かっている。
(少し早く着いちゃったな)
いつもは七時過ぎに着くようにしているが、今日は朝に見た夢のせいもあって、速度が出ていたのかもしれないと善逸は反省する。夢を見た日は、どうにも呼吸の廻りが良くなってしまうのもまた、善逸の悪い癖だった。少し待つか、それとも諦めるか、店の前で待ち構えるのは恥ずかしいなあと善逸が迷いながら通り過ぎようとすると、カランカランとドアベルが鳴って店の扉が開いた。
「おはようございます! もう店開けるのでどうぞ!」
「……どうも」
中から出てきた店員がドアの前にあった札を『営業中』に変える。そしてどうぞというように扉を開けて待たれてしまえば、善逸は中に入らざるを得ない。善逸は店員にペコっと頭を下げて店の中に入った。すると外からでも十分いい匂いだったのに、それ以上の美味しそうな匂いが鼻を擽り、ホッと口元が緩む。
「今日は新作があるんです! もし良ければ試してみてください!」
「あ、そうなんだ。これかな?」
「はい! 生地を抹茶にしてみました!」
ハキハキとパンを紹介してくる店員に、善逸はふむっと頷いてそれをトレーに乗せた。これは朝練の後に食べようと決める。そして午後の練習前には何を食べるかと考えていると「これも新作です!」と自信満々に店員が指差すのに、善逸はへにょりと笑ってしまう。自分がいいと思うものを勧めてくるのは、昔と変わらない姿だ。
「じゃあ、それで」
善逸はそう言ってベーコンのパンを取った。するとパッと嬉しそうな顔をする店員に、善逸は今日も幸せそうだなと安心する。
「お兄ちゃんお店開ける時間……あ! ごめんなさい!」
奥から出てきた制服の上にエプロンという姿の少女に、善逸はヘラッと笑う。今日も特別に可愛らしい。ついつい緩む頰だが、流石に「禰豆子ちゃん可愛いよおおおおおお!!」と叫ぶことはしない。何故なら、善逸は彼女の名前を本当は知らないからだ。たぶん、九割九分『竈門禰豆子』であろう。しかし合っていた方がまずい。名前を伝えたことのない相手に名前を知られているなんて恐怖だろう。
善逸は余計なことは言わぬように口を閉ざすと、レジカウンターの方へ向かった。すると少女の方がレジに近いのにわざわざ店員……先ほど禰豆子にお兄ちゃんと呼ばれていた人物がレジに立った。
(真面目だなあ。禰豆子ちゃんでもよかろうに)
善逸はぼんやりとそう思いながら、花札の形で旭柄のピアスを見つめた。ゆらゆらと揺れるそれは善逸の記憶にこびりついているもので、なんなら今朝の夢にも出てきたものだ。真剣な顔でパンを袋に入れているお兄ちゃん店員……名前は九割九分『竈門炭治郎』を善逸はゆっくり瞬きをしながら見つめた。なんと善逸は、この男の前世を愛している。
どういうことかと言えば、信じられないことに我妻善逸には前世の記憶があるのだ。中二病かと言われても、善逸はもう高校二年生であるし、記憶自体はほぼ生まれた時からある。前世であった異常な程の耳の良さは失っていたが、記憶があることで善逸は見事に世間から浮いた。何しろ幼い頃は記憶の処理が追いつかず、危ない事ばかりを口にしていたからだ。
その結果、生来の孤児であった善逸は、桑島慈悟郎が引き取り手として現れるまでほぼ一人で過ごしていて、友達もろくにいなかった。そして前世の鍛錬漬けの日々の影響から、鍛錬をしないと安心できない難儀な状態となっていた為、実に子供らしからぬ肉体にもなっていた。
小学校低学年なのに腹筋割れているし、腕もモリモリ。あと、なんかその辺の棒で素振りしてますというのがあったが、幸いなことに遠巻きにされるばかりで虐められたりはしなかった。マッチョは凄いぞ。虐められたら皆んな! マッチョになろう! と、善逸はお勧めしたいくらいだ。
さて、前世では鍛錬漬けであったと言ったが、その理由は簡単だ。善逸は鬼殺隊という組織で、人を喰う鬼と戦う生業に従事していたからだ。切っ掛けは借金のかたであり、恐ろしすぎる日々であったが、その時も善逸を拾ってくれたのは慈悟郎だった。そして義兄はその時は兄弟子であった。つまりはなかった事にしたい過去ではない。むしろ過去のおかげから、家族三人が普通に食卓を囲んでいるだけで善逸は幸せを噛みしめられるのだからありがたいものだ。
なぜ幸せを噛みしめられるかと言えば、前世では兄弟子が鬼となり人を大量に喰い、その責任を取って慈悟郎は介錯なしに切腹、そして弟弟子の善逸は兄弟子であった獪岳の頸を斬って殺している。そんな前世のしがらみを持って今生で家族として暮らしているなんて、普通は発狂してしまいそうだが善逸は大丈夫だ。臆病な性質であるが、図太くあり、やるべき事、やらねばならぬ事の見極めは鋭く、己が決めた事への頑固さは筋金入りだ。要するに善逸は心も相当にマッチョであった。マッチョは凄い。
「290円です!」
「はいはい」
善逸は目の前の店員、竈門炭治郎の声に財布を開けた。そこから300円を取り出してトレーの上に置く。すると10円玉がレシートと共に返ってきて、善逸の掌の上に乗せられた。ほんの少しだけ触れ合う体温に、ズキリと善逸の胸が痛むが顔には出さず、お釣りを財布にしまう。そしてビニール袋に入れられたパンを受け取ったら後は店をすぐに出るだけだ。何しろ善逸には時間がない。
「いつもありがとうございます!」
「こちらこそどーも」
善逸は踵を返して店のドアを潜った。そして一歩出た瞬間に、呼吸を体に巡らせて一気に加速する。今は七時ぴったりだ。そして部活の朝練は七時半から。それまでに到着して、着替えをしなければならない。脇目も振らずに全力疾走できれば、ここから学校まであっという間であるが、そんな事をすれば善逸は世界新記録を叩き出し、オリンピック街道をひた走ることになる。それは御免であった。あと間違えて人とぶつかったら、ぶつかった相手が死ぬ。善逸は常識の範囲内で道を駆ける。幸いなことにまだ早朝なので人は少ない。ランニングの勢いで、しかしスピードも息も一定のまま学校まで駆け抜けた。
「お! おはよう我妻ー」
「おはようー村田さーん」
善逸は同じ学年の部員の名前を呼んだ。なぜに同学年なのにさん付けかというと、彼が単純に、前世で善逸の歳上であった人物で、その時に『村田さん』と呼んでいたからだ。高校の入学式で出会った時は、まさかの同学年と驚いたが、どうにも呼び捨てにしづらく、善逸は彼のことを『さん』付けで呼んでいる。結果、面白がったクラスメイトたちも彼を『村田さん』と呼ぶので、村田からは散々に「お前のせいだぞ!!」と善逸は言われたが聞き流すしかない。もうそれを一年も続ければ村田はとっくに諦めて、立派な『村田さん』だ。
「一年生みんな来てるかな?」
「先週の朝練の厳しさで減ってるかもな」
善逸と村田は剣道部員だ。善逸の通っている学校は私服の高校で、自由な校風と部活動で生徒がやりたい事を存分にできるように設備が整っていることがウリだ。その結果、あちこちの部活が常勝街道に乗っていて大会などの成績がいい。ちなみに剣道部は数ある部活動の中でも強豪である。昨年はインターハイを団体戦で準優勝しているし、今年も優勝候補の一角だ。それ故に練習は厳しく、沢山入る新入部員は一年経つ間に結構な数を減らす。去年の善逸達の代も二十人が入部して、夏を越えて残ったのは五人だけだ。
善逸と村田は部室に行くと、手早く用意をして剣道場に入った。朝練は自由参加の為、来なくても怒られることはない。強豪校であるが校風が自由な為、その辺は放任主義なのだ。強くなりたい奴だけが強くなる。
善逸はいつも使っている剣道場の隅に向かってだらだらと歩いていく。それを剣道場にいる人間全員が見つめているのだが、善逸は今日は夢見が良く、とても憂鬱な気分なので気にする余裕はない。いつもはビクビクと定位置につくが、この日はふてぶてしい態度で歩いて行くと、愛用の竹刀をピッと構えた。
この瞬間だけはスーッと心が落ち着く。善逸は竹刀を中段に構えると、前足を出して振り被り、速いスピードで真っ直ぐに面の高さまで下ろす。その速さに、そしてピタリと止める凄さに、部員達は皆んな息を呑むのだが、善逸は無心というように繰り返している。
たったこれだけの動作で、我妻善逸という男がどれだけ強いのか簡単に分かる。善逸と一年を共にした三年生と二年生は当たり前だが、入部してひと月くらいの新入生は溜息が出てしまう。あんなの化け物かと思えてしまう。
顔色を青くする新入生達に、村田など、剣道部に残ったメンタルの強い二年生達は、今年も練習の厳しさだけでなく、善逸の凄さに嫌気がさして辞める奴が多そうだと肩を落とした。村田達、メンタルが強い奴らは分かっている。善逸の強さは自分達と同じに考えたらダメなやつだ。
「はあ……。村田さん打ち合いしよー」
「いやだよっ!!」
「なんで!?」
「腕が午前中、使い物にならなくなるだろ!?」
「なんでよ!?」
善逸と打ち合いをするとそのしなりがある一撃のせいで腕の痺れがすごいのだ。防具をつけていても喰らいたくない。村田は泣きそうになりながら、二年生や三年生の部員を振り返るが皆んな「よっしゃ、俺たちも打ち合いしよーぜ!」とペアを組んで蜘蛛の子を散らすようにいってしまう。捨てられたと村田は本当に泣きたくなるが、後ろから「ねぇねぇ村田さーん」と引っ張ってくる男にがくりと肩を落とした。村田とて男の矜持がある。二回も誘われて断るのは剣道を嗜むものとして情けない。
「分かったよ!! 俺の腕がどうなっても知らないぞ!」
「え? うん? 分かった?」
****
「くそ痛い……やるんじゃなかった」
村田は汗だくの身体をタオルで拭きながら、早々に着替え終わり、クリームパンを齧っている善逸を睨みつけた。
善逸は何故かどれだけ動いてもあまり汗を掻かないので着替えが早いのだ。いまも美味しそうにニコニコしながらパンを齧っている。袋には『竈門ベーカリー』と書かれていて、この地域では美味しいと評判のパン屋だ。善逸の家から学校までのルートを考えると少し遠回りになるのだが、善逸はこのパン屋を気に入っているのか頻繁に買ってきている。たぶん、小遣いの大半をこのパン屋に捧げているだろう。
「我妻、そこのパン屋好きだな」
「ん? うん。美味しいからね」
幸せそうに笑って食べる善逸に、ふうんと思いながら村田はシャツの袖に腕を通した。するとビリビリと痺れが走り、さっき打たれた小手を思い出す。凄まじい一撃だった。さすが前回のインターハイ個人優勝者と村田は溜息を吐く。
「ん? どうしたの村田さん?」
「いや……今年の新入生にあいつがいないのが残念だなあと思ってさ」
「え? 誰?」
「誰ってあいつだよ! 去年のインターハイが終わった後に、お前に勝負しろって挑んできた奴!」
村田の言葉に善逸はひとつ瞬いて、口元についたクリームを舌で舐めとった。
「ああ。嘴平伊之助?」
さらりと出た名前に村田は驚く。向こうが名乗ったのは一回きりだ。それを覚えているとは、純粋に記憶力いいなと村田は感心する。
「去年の全中の優勝者だよな」
「えっ!? 知ってたのか!?」
「知ってるよ?」
村田は、自分が出ていない大会結果を善逸が把握していることに驚いていた。だって高校の大会ですらない。中学の大会だ。
全中とは『全国中学校剣道大会』の事だ。村田も出たことがあるし、あと村田が中学時代の頃の全中の優勝者は、全てこの目の前にいる男だ。村田は小学生から剣道をしていたが、目の前の男は確か中学からだ。それまでは祖父が指導する居合道をやっていたらしい。単純に居合道の部活がなかったから、消去法で剣道を選んだというとんでもない奴だ。
なぜとんでもないかと言えば、中学から始めたというのに、その年の全国大会であっさり優勝したからだ。高校で学校が同じになり、中学から始めたと聞いた時は、村田はたまげたものだ。中学から始めてあの腕前。さらに善逸は腕前の他にもすごいものがあった。何がといえば、まさかの上下共に白道着である点だ。
小学生ならまだしも、中学生になって上下白は珍しい。大半が藍染道着なので白道着は目立つのだ。その目立った出立ちは無意識でも注目を浴び、もしや強いのではと思われてしまう。その結果、負けると期待外れという風に見られるので、白道着を着るには勇気がいる。
なのに善逸は初めから白道着。幸いなことにめちゃくちゃ強いので、もはや今の時期に上下白道着なんて着たら「我妻善逸気取りか」と言われてしまうだろう。
ちなみにこれも何故なのか村田は聞いたことがあるのだが、善逸はあっさりと種明かしをした。曰く、「居合道をしてる時から上下白だからだよ。上下紺は兄貴なの」とのことだった。要するに一目で持ち主が分かるようにしているだけなのだ。
そんな中学時代から無敗を誇る我妻善逸は、割とあちこちに無頓着だ。自分の強さも分かっているのかいないのか。正直に言って、村田は善逸と打ち合うレベルの腕前はない。しかしそんなの気にせずに善逸は練習しようと誘ってくる。まあ、そもそも善逸についていける奴がこの部にいるのかと言われれば返事に困るのだが。
だからこそ、村田は例の『嘴平伊之助』がこの学校に入ってくれたらと思っていたのだが、現実はそう簡単ではない。噂によれば嘴平伊之助はこの高校の近くにある他校に行ったらしい。ここに来れば、善逸と練習し放題だというのに変なのと村田は首を傾げた。
嘴平伊之助は、去年のインターハイで善逸が優勝をし、勝利に湧いた会場通路に立ちはだかった男だ。そして「おい! 金キラ頭! 俺と勝負しろ!!」と言って竹刀を構えるその姿と気迫は、善逸に通じるものがあると、大した腕前はない村田でも思った。
結果として防具なし、しかも野良試合など出来るわけもなく「やだよやだやだ! こっちは試合後で疲れてんのよ! あと防具もなし、審判もなし、勝手にこんなところで試合できるか!! ここどこだか分かってる!? 建物のせっまい廊下よ!? この後も続々と人が通るのよ! 大迷惑でしょうが!! やらないやらない! やるわけがない! 来年の試合でやろうぜ!!」と善逸にいなされて終わった。
あんな風に強い人間と戦いたいと、まさかの廊下で挑んでくる奴だ。善逸の腕前に及ばなくても、喜んで毎日打ち合ってくれただろうにと、叶うことのない現実を想像して村田は溜息をついた。
残念ながら嘴平伊之助は同じ学校に来なかったのだから、善逸の相手は自分達が務めなければならない。そのお陰で昔より格段に腕前は上がっている自覚はあるが。
「ご馳走さま〜。美味しかった〜」
「そろそろ教室に行くか」
「うん。一限なんだっけ? 数学だったかな〜」
二人でダラダラと部室を出て昇降口に向かう。自分の下駄箱をそれぞれ開ければ、善逸はピタリと固まった。その様子に村田はおやっと思う。善逸は無表情のままにそーっとまるで恐ろしいものを手に取るかのように下駄箱からピンク色の便箋を取り出した。
「なに? ラブレター?」
「でへへへぇ♡ そうみたいっ♡」
ヘラっと相貌を崩した善逸に、村田は内心でケッと唾を吐き捨てる。流石に全中を全て優勝、インターハイも優勝となればおモテになられる。格好つけて謙遜するのも腹立つが、手放しに喜ばれるのもムカつくなあと、村田は善逸を睨みつけた。さっきの無表情は見なかったことにする。
「呼び出しか?」
「いや……ううん。返事はいらないって書いてあるよ。名前もないし」
あからさまにホッとした様子に、村田はますますイラッとくる。なぜなら善逸はいくら女の子に好意を向けられても応える気がないからだ。
我妻善逸は、女好きと言っていいほど、女子に優しくデレデレする男であるが、恋人はいらないらしい。剣の道が恋人なのかと思いきや、善逸は強いし剣に対して真面目であるが、好き好んでやっているわけではないらしい。それであれだけ強いのかとぶん殴りたいと村田は思う。
「お前、好きな人いるならさっさと告白すればいいのに」
「……放っておいてくださいよ〜」
唇を尖らせる善逸に、村田はやれやれと頭を振った。善逸は手紙をブレザーのポケットに入れると上履きを取り出す。丁寧にすのこの上に置かれてから履かれる、踵が踏まれた形跡のない上靴に、育ちいいなと村田はぼんやり思った。
そして視界に入る『竈門ベーカリー』のビニール袋に、善逸の片想い相手を想像する。村田は見たことがないが、あの店には看板娘がいるらしい。
村田は善逸の片思い相手はその子だなと睨んでいるが、幾ら聞いてもはぐらかされるばかりで回答はない。
水臭いなと村田は思うが、善逸はいつも少し距離がある。縋るようにくっついてくるのに、こちらが向き合おうとすれば、ひらりと何処かに行ってしまう。
気儘な猫といえば聞こえがいいが、たぶん、これはもっとタチが悪いものだと、村田のまだ少ない人生経験でもそれは分かっていた。深追いしたりすると痛い目を見るやつだ。それを善逸自身も分かっているから踏み込ませない。
(誰か踏み込んで、捕まえてくれりゃあいいのに)
本当はそれを嘴平伊之助に期待していた。我妻善逸はどこを見ているのか分からない男だ。普通にエロいし、食い意地も張っているが、底が見えない。そう、まるで底が見えない古い井戸を覗いているようなのだ。
あれを見つめ続けるのは村田にはできない。怖い。だから同じ剣の強さという視点で善逸と同じものを見られるかもしれない嘴平伊之助に村田は期待したが、残念ながら現れなかった。
きっと大会では再会するのだろうが、それでは足りない。我妻善逸を攻略するには、たぶん、しつこく粘り強く近い距離で時間をかけねばならない。
(なんでそんな風に思うんだろうなあ)
村田と善逸の付き合いは一年程だ。それでも部の誰よりも善逸の闇を知っているという自負が村田にはあった。他の部員はたぶん、善逸の闇なんて気が付いてもいない。
「村田さーん。予鈴鳴るよー!」
「あ! ヤバイヤバイ!」
村田は上靴を引っ掛けると、急いで昇降口から校内の階段へと走った。善逸はもうラブレターの事など気にしていないのか、大事そうに右手の全ての指でビニール袋の手提げを持ち、階段を駆け上って行った。
知らない男
一年程前から、たぶん、恋をしている。
朝の六時四十五分。炭治郎は焼き上がったパンを店の棚に並べながら、ちらちらと窓の外を見た。
店の開店時間は七時からだが、この辺の時間から気をつけていないといけない。今日は時間ぴったりだろうか、それとも少し早いだろうかと炭治郎がソワソワしていると、危うく新作のクリームパンを取りこぼしそうになった。
炭治郎は鍛えた体幹でバランスを取ってクリームパンの落下を防ぐと、ふうっと息を吐く。そして今日のこれは自信作なのだからと、丁寧にゆっくりとトングでパンの陳列棚に並べていった。何しろクリームパンなので、力を込めすぎると中身がででてしまう。
(このパンはきっと彼の好きな味だ! どうやら甘い味が好きみたいだし、四月限定の桜アンパンも毎日買ってくれていたし!)
炭治郎はせっせと並べながら、美味しそうに食べてくれる想像で心が弾む。残念ながらそれは本当に想像で、どんな顔で食べているかも、いつ食べているかも分からないのだが、想像するだけはタダだ。
炭治郎が音痴な鼻歌を歌い出しそうになった時、視界にチラリと金色が輝いたのにハッとして顔を上げた。窓の外を見れば、金髪の高校生が腕時計を見ている。炭治郎が慌てて時計に目を向けると時間は六時五十五分で、いつもより来るのが早いと、慌ててトレーをカウンターに置いた。そして店の扉を急いで開けると、通り過ぎようとした彼に声を掛ける。
「おはようございます! もう店開けるのでどうぞ!」
「……どうも」
金髪の少年がへにょりと眉を下げて笑うのに、炭治郎の胸がギュウッと締まる。しかし変な顔にならないようにと気をつけながら札を『閉店中』から『営業中』にする。そしてレディーファーストというわけではないが、店の扉を開けて待てば、金の髪の高校生は少し頭を下げて店の中に入って来た。
(……焼き魚の匂いがする。『我妻さん』、今日は朝ご飯が魚だったのかな? これはたぶん鮭の匂いだ)
炭治郎はすれ違い様に香った匂いを吸い込む。焼き魚の匂いに混じって、爽やかな柔軟剤の匂いと、おそらく本人の体臭が炭治郎の鼻腔を通る。ピリッとした匂いと、じわっと広がる甘苦いような匂い。不思議な匂いだなと思いながら、炭治郎は彼が背負うバッグの側面に刺繍されている『我妻』という文字を見つめた。
炭治郎が我妻という少年を知ったのはちょうど一年くらい前のことだ。去年の四月の中頃に、その少年は店に入ってきた。早朝の一人目のお客様で、カラカラとドアベルが鳴り、炭治郎が「いらっしゃいませ!」と声を掛けると、目を丸くして驚いた顔をしていたのを覚えている。その瞬間に香った匂いは嗅いだことのない、甘い花のような匂いで、炭治郎はくらりと目眩がしそうになったのを……覚えている。
固まった彼はすぐにトレーとトングを取ると幾つかのパンを買って、そして帰っていった。驚いた様子だったのは最初だけで、あれは多分、子供がパンを並べていたから驚いたのだろうと炭治郎は思っている。父親が亡くなり、何とか家族で仕事を回しているが、初来店の人から見れば驚く事だろう。炭治郎は甘い匂いがした金髪の少年のことが気になったけれど、また来るかも分からない人だからと、気にしないようにした。鮮明に記憶している段階で全く達成できていないが。
それから暫くして、また金髪の彼が店に来た。二回目の来店では、彼は驚いた様子もなく、炭治郎を気にすることなく、パンを選び始める。しかし炭治郎は花のような匂いがなくなり、湿った雨のような匂いに首を傾げた。どうやら彼は落ち込んでいるらしい。どうしたのだろうかと心配になるが、いきなり「落ち込んでるんですか?」などと話し掛けられたら驚くだろう。不躾にも程がある。
なので炭治郎は金髪の彼に「今日はこのパンがおすすめです!」とチョコレートパンを勧めた。落ち込んでいる時は美味しいものを食べるべきだ。その日の最高の出来栄えがチョコレートパンだったので、炭治郎はそれを勧めた。それくらいしか出来ることがなかった。
金髪の少年は炭治郎の言葉に対して、ふっと口元を緩めると「じゃあこれも」と言ってトングを使ってチョコレートパンをトレーに乗せた。ふわりと香る甘苦い匂いに、炭治郎の体がビリビリ震える。
それは不思議な心地であったが、少しは元気が出たかなと思いつつ、炭治郎はパンを袋に入れて少年に手渡す。そしてまた来てくれたら良いなと思いながら、金髪の彼を見送った。
それから彼は頻繁に店に来た。来るのはいつも開店直後で、甘いパンとしょっぱい惣菜パンを一つずつ買っていく。毎日というわけではないが、週二回から三回ほど来る彼は炭治郎が確認する限り、さっぱりプリン頭にならない人だった。
彼の頭はいつでも根元まで美しく金色で、炭治郎は半月ほど経ってから、地毛が金髪なのだと納得した。そしてほんの少しだけドキドキする。日本人顔なのに髪だけ金髪とは珍しい。しかし顔もよくよく見れば、眉毛も睫毛も金髪なのだ。
(綺麗だなあ)
そう思いながらも名前も知らぬ人に話しかけられず、炭治郎はパンを選ぶ姿をこっそり盗み見るしかできない。新作のパンや今日の自信作を伝える程度の会話は出来たが、それ以上のことは何も言えなかった。
そしてそんな炭治郎がとうとう彼の苗字を知ったのは、五月のゴールデンウィークが明けた後すぐだった。その日の彼は背中に大きな黒いバッグを背負っていて、炭治郎は何か部活をしているのだと判断した。そしてすれ違い様にチラッと見やれば、真新しいバッグに『我妻』という刺繍がされている。
(たぶん、高校生だ。一年生かな?)
ピカピカの部活バッグは届いたばかりなのだろう。背丈や体格を考えると中学生とは思えないので、高校生と考えるのが妥当だ。
今まで店に来たことがなかったのは、今年の四月から通学路の都合でこの辺りを通るのだろう。しかし着ている制服に見覚えがなく、この商店街を抜けた先の駅から電車か、バスに乗って学校に通っているのかもしれない。
(下の名前、なんだろう)
しかし我妻は急いでいるのか、基本的に買ったらすぐに店を出て走っていってしまう。のんびり向かう様子があれば炭治郎も話しかけやすいのだが、開店直後に店に入り、すぐに買ってすぐに出て行くとなれば、炭治郎も話しかけにくい。引き止めて遅刻なんてことになったら迷惑を掛けてしまう。だから結局は炭治郎は彼が店に入ってくるのをただ待って見ているしかなかった。
しかしある時、炭治郎は気がついた。彼は店に来ても中に入る時と入らない時があることに気がついた。
それは炭治郎が開店五分くらい前にパンを並べていた日のことで、視界に金色が掠めたのできっと我妻だと思い顔をあげれば、我妻は店の扉に掛かっている『 閉店中』の札を見て、そして時計を見て、そのまま走って行ってしまったのだ。
それを見た時の炭治郎の衝撃といったらなかった。だって慌てて外に出てみれば、我妻は竈門ベーカリーから十メートルほど先にあるコンビニに入っていったのだ。その事実に炭治郎は、ガーンという音を自分の内側から聞いた気がした。ショックだった。店が開いてないからとコンビニに行かれた。もしかしてコンビニのパンでも良いのかとショックでいっぱいで、その日の炭治郎は授業も耳に入らない有様だった。
しかし次の日、我妻は普通に店に入ってきた。炭治郎は彼を裏切り者めと思いながら盗み見る。すると炭治郎が前に勧めたチョコレートのパンを緩んだ顔でトレーに乗せるのを見てしまった。
それだけで炭治郎の中にあった、『裏切り者め』という気持ちはしおしおと萎んでいく。そして、きっと本当に急いでいるんだなぁと、その日も走って行く我妻を見送りながら、次は見かけたら少し早くても店を開けようと炭治郎は決めた。
それから約一年、炭治郎と我妻の間には何の関係性も育まれていない。ひたすらパン屋の店員と常連客でしかない。おすすめのパン以外の会話もなく、本人から名前を聞けてもいないし、向こうに自己紹介もできていない。
「あ、あの! 今日は新作があるんです! 良ければ試してみてください!」
「あ、そうなんだ。これかな?」
「はい! 生地を抹茶にしてみました!」
炭治郎の勧めに彼は唯々諾々とパンをトレーに乗せる。しかしその顔にほんの少しだけ笑顔があるから、炭治郎はホッとする。嫌がられていないと安心する。
本当はもう少し踏み込みたい。いや、嘘だ。深くまで踏み込みたい。炭治郎はこの一年、我妻にずっと絡みつく悲しみの匂いを気にしていた。
最初は分からなかったが、彼は落ち込んでいるのではない。たぶんずっと寂しくて悲しいのだ。何が我妻の身に起こっているのかは分からない。だが炭治郎が知る限り、彼が喜びでいっぱいというのを見たことがない。週の三日、憂鬱な日があるというのは正常としていいのか? 良いわけがない。
(俺がなんとかしてあげたい)
我妻を一年間見続けて、他の店に行かれる時のショックや悲しさを考えると、どうやら自分は彼のことを好きなのではないかと炭治郎は思い始めていた。
毎日毎日、来てくれないかなと窓や外を見る気持ちはなんだろうか。そんな事を思うのは我妻にだけで、そして炭治郎は『我妻さん』と心の中で呼ぶのも嫌いだ。何しろ名前を盗み見て知っているだけで、彼から与えられたものではない。だから絶対に炭治郎は彼を『我妻さん』と音には出さない。意地でもだ。この拘りはなんだ。なんて表せばいい。そう思った時に一番近いものが『恋』だった。けれどしっくりくるかと言えばそうでもない。
炭治郎は頭の中で悶々と考え事をしているが、もう一つのお勧めであるベーコンパンを我妻が取ってくれたので、自然と口元が笑ってしまう。お勧めのパンをなんの迷いもなく選び取ってくれるのが、まるで自分が肯定されているように感じてしまうのだ。そう思いながら炭治郎は名前、名前と心の中で呟く。我妻を知って既に一年経った。そろそろ名前くらいは聞きたいと、勇気を出して炭治郎が言葉を発しようとした瞬間——。
「お兄ちゃんお店開ける時間……あ! ごめんなさい!」
一つ下の妹である禰豆子の登場に、炭治郎は出鼻を挫かれた。禰豆子はまさにやってしまったという顔で、なぜなら彼女どころか家族全員、炭治郎が金髪の高校生と仲良くなりたがっているのを知っているからだ。その理由が恋かもしれないというのは、さすがに上の年齢の弟妹しか把握していないだろうが
我妻は禰豆子の登場に口元を緩めた。その表情の変化を炭治郎は見逃さない。これは仕方がない。なぜなら、禰豆子はご町内でも評判の美人だからだ。竈門ベーカリーの看板娘だからだ。
(でも、恋の匂いとかはしないんだよな……)
禰豆子は可愛らしいので、想いを募らせる男共も多い。炭治郎はそれを、「禰豆子にはまだ早い!」と、去年までは蹴散らしまくり、自分が中学を卒業していなくなっても、全部匂いで分かるんだからなと圧力を掛けているから知っている。
恋の匂いはこんなものじゃない。我妻から香るこれは何というか、孫を見るお爺ちゃんのような匂いだ。
(なんでそんな匂いさせるんだろうな?)
禰豆子に想いを寄せていないのは兄としても男としても嬉しいが、パン屋の常連がそこの看板娘に「いやあ、元気でいいことだあ」というような感情を滲ませているのはなんなのか。
しかしそんな答えは分かるわけもなく、我妻がさっさとレジに行こうとするので、炭治郎も急いでその後を追った。レジの近くには禰豆子もいるのだが、さささっと後ろに引っ込むのは、炭治郎のチャンスを潰さない為だろう。妹の気持ちはありがたいが、その不自然な行動に炭治郎は冷や汗がでる。しかしそれでも僅かな触れ合いを逃したくなくて、結局は炭治郎がレジについた。パンを袋に入れて、会計を済ませる。
「290円です!」
「はいはい」
財布から出された300円がトレーに置かれる。お釣りが出ない方が店としては嬉しいけれど、炭治郎個人としてはお釣りが出るほうが嬉しい。炭治郎はレジスターから10円玉を一枚取ると、差し出された手の上にレシートと共に乗せた。想像以上に硬く厚い掌に、何の部活をしているのだろうと思う。
「いつもありがとうございます!」
「こちらこそどーも」
あっという間に用件が済んで、我妻は振り返ることもなく店から出て行く。そして扉が閉まるとすぐに走り去っていき、炭治郎の視界から消えた。これでもう、我妻とは今日は会えることはない。時間にして僅か五分以下。それくらいしか会えない、一緒にいられないことに、炭治郎は大きな溜息をついた。
「……お兄ちゃん。お店番は私が替わるから、朝ごはん食べてきて」
少し炭治郎の顔色を伺うようにしながらやってきた禰豆子に、炭治郎は笑った。きっと邪魔をしてしまったのを悔いているんだろうが、禰豆子が来ていなくても、我妻に何か言えたとは思えない。何しろここ一年間、炭治郎は一歩も踏み出せていないのだから。
「じゃあ、禰豆子。店番頼むよ」
「うん、任せて」
炭治郎はコックコートを脱ぐと店の奥を通って家の中に入った。朝ご飯を食べて、炭治郎も制服に着替えて学校に行かねばならない。竈門ベーカリーの大黒柱は四月に入学したばかり、ピカピカの高校一年生なのだ。
****
「権八郎、なんかして遊ぶぞ!」
「ん? 伊之助、今日は剣道部ないのか? あと俺の名前は炭治郎だ」
放課後、クラスメイトの伊之助に声を掛けられて、炭治郎は少しだけ目を丸くした。目の前にいる男、嘴平伊之助は制服のシャツを全開に開き、見事に割れている腹筋を惜しげもなく晒している。その腹筋を見ながら炭治郎は「ますます育ったなあ」と感心した。ここのところの伊之助は剣道への情熱に目覚ましく、遊ぼうというより鍛錬してくると言っている方が多いのだ。
炭治郎と伊之助は出身小学校が同じだ。その時も家は近くなかったが、伊之助は少し特殊なタイプだったのでクラスに馴染むのが難しく、昼休みも放課後も一人で遊んでいることが多かった。伊之助はきっと気にならなかったのだろうが、炭治郎はそういうのを見ると放って置けないので、ついつい構いにいくというのが止められない。最初のうちは邪険にされていたが、しつこく伊之助に付いて回っていたら「お前を子分にしてやるよ!」と嬉しそうに言われたので、仲良くなれたと炭治郎は笑った。
しかし残念なことに、炭治郎と伊之助は学区の都合で中学校が別だった。休みの日は遊ぼうな、なんて二人で話していたけれど、炭治郎は父親の体調が悪化した都合で忙しく、また伊之助も中学校から始めた剣道の練習で休みなんてほぼなく、炭治郎と伊之助は中学生活をほぼ疎遠で過ごした。
お互いに電話をするなんて発想もなかったし、二人でいても会話を楽しむわけではなかったので、お互いの近況は殆ど知らなかった。ただ毎年の年賀状と残暑見舞いのハガキだけは出し合っていた。そのお陰か、まさか高校が同じだったとはと入学式での再会でも、自然と二人で連むようになるのだから、これが気が合うというやつなのだろうと炭治郎は思っている。
さて伊之助であるが、最初に炭治郎が言ったように高校でも剣道部に入っている。なんでも倒したい相手がいて、入学してからも練習に明けくれていた。だから遊ぼうと言ってくるとは思っておらず、炭治郎はきょとんと伊之助を自席から見上げる。
「今日はない! 何か知らねぇがなくなった!」
伊之助は部活が休みになった理由までは把握していないらしい。その言葉に炭治郎が二回ほど瞬きをしていると、斜め後ろくらいからクスッと笑い声がしたので振り返る。剣道部の女子部員だ。
「今日は剣道場の照明点検で部活ないんだよ」
「成る程」
炭治郎が頷けば、伊之助はそうだっけというように頭を掻いている。まあなぜ休みかは伊之助にとったら些細なことなのだろう。今日は練習があるかないか、するかしないかが重要なのだ。
「剣道場の点検かあ。それなら久しぶりに遊ぼうか」
炭治郎の言葉に伊之助はパッと顔を明るくした。小学生の時から変わらないなと思って微笑ましく思っていると、先程の女の子も帰るのか鞄を片手に立ち上がる。
「ところで嘴平君、今日は嘴平君が楽しみにしてた『日本剣道』の発売日だよ」
女子生徒の言葉に伊之助はグッと眉根を寄せ、次いでハッと表情を驚かせる。目にはキラキラと光が入り、そして次にはギラギラと熱が点る。その表情の変化に炭治郎は、いったいどうしたのかと首を傾げた。
「新妻紋逸!!」
「あはは。今回特集されてる筈だよ。じゃあねー」
女子生徒は教室の扉の前まで迎えに来ていた友達と一緒に帰って行った。炭治郎は何のことだろうかと思っているが、伊之助がソワソワし出し、慌てて荷物を鞄に詰めているので炭治郎もそれに倣って荷物をまとめる。たぶん、発売日と言っていたから買い物が最初だろう。
「おい! 本屋行くぞ!」
「あ、『日本剣道』って本なのか? 雑誌か何かか?」
「次の試合の特集だ!! 強い奴の話が載ってるぞ!」
伊之助は早く早くと足を踏み鳴らしている。伊之助の言葉から、つまり剣道の本の発売日で次の大会の特集か何かをしているのだろうと推察した。
「分かった。じゃあまずは駅前の本屋に行くか。その後はどうする?」
「読むっ!!」
「だよなあ。じゃあ、うちに行こう」
この勢いならそうだよなと、炭治郎は頷いた。それから二人で駆けるように本屋に向かった。そんなに早く読みたいのかと伊之助に聞けば、伊之助からは「売り切れてなくなるだろっ!」と言われた。そんなにすぐなくなるものなのかと、その辺の事情は知らないので炭治郎は素直に伊之助の後を付いていく。
そして自分のパン屋がある商店街に来ると、駅前にある三階建ての本屋に二人で入った。炭治郎も久しぶりにパン関連の本を買おうかな、なんて有名パン屋特集のものをパラパラと捲っていると、伊之助があっという間に紙袋を抱えて戻ってくる。
「早いな」
「他に用ないからな! お前んち行くぞ!」
嬉しそうにしている伊之助に、炭治郎は本を戻す。家から近いからまた来ればいい。結局二人は滞在時間五分程で本屋を出た。そしてそこから歩いて五分程の竈門ベーカリーに来ると、店とは別の住居用の玄関から中に入る。
「ちょっとここで待っててくれ」
「おう」
炭治郎はそう言うと廊下から事務所へと入り、そこを抜けて店舗に顔を出す。パートさんと働く母親に「友達が来ているから」と簡単に告げて、また玄関へと戻った。伊之助は待ち切れないのかソワソワとしている。その姿にふっと笑うと、炭治郎は伊之助を自分の部屋に連れて行った。
「お茶持ってくる。パン食べれるか?」
「幾つでも食える!」
「たくさん食べすぎると夕飯が入らなくなるぞ」
そう言ってみるものの、伊之助はたいへん健啖家なので大丈夫かもしれない。炭治郎はキッチンでパンを四つほど籠から取り出した。ソーセージパンとエピとブールとクリームパンだ。そして作り置きの麦茶を注ぐとお盆に乗せて部屋に戻る。扉は開けっ放しにしておいたから、開けてもらう必要はない。部屋に戻ってきた炭治郎からは伊之助の後ろ姿しか見えないが、真剣な様子で雑誌を読んでいるようだった。
「伊之助。お茶とパン持ってきたぞ」
そう言って折りたたみテーブルにお盆を置いてコップとパンの皿をテーブルに乗せていると、伊之助が「うん」と言って本を顔のところまで持ち上げた。それはたぶん、雑誌が小さいローテーブルに半分掛かっていたから、邪魔にならないようにという伊之助の配慮だったのだろう。しかし炭治郎は目の前に晒されたその本の表紙を見て、大きな声を上げた。
「あああああああー!!」
「うおっ!? なんだよいきなりっ!?」
「伊之助!! その、その表紙!! その人!!」
炭治郎の言葉に伊之助は「表紙ぃ? 『新妻紋逸』がどうした?」と不思議そうな顔をしている。炭治郎はその言葉にぶんぶんっと首を振る。下の名前はいざ知らず、苗字は間違いだ。その人の苗字は『我妻』だ。
そう。伊之助が読んでいる買ったばかりの雑誌の表紙には、炭治郎が一年間ずーっと名前やどんな人なのかを知りたいと思っている人物が写し出されていた。正面に竹刀を構えて立つその姿に、炭治郎は「剣道をやってたのか!」と変な感動をする。伊之助は炭治郎の様子が一変したのに困惑したのか、怪しんだ目をしていたが、パタンと雑誌を閉じると炭治郎に差し出してくれた。
「先に読んでもいいぜ」
「いいのか!?」
「おう」
「ありがとう!」
炭治郎は伊之助から雑誌を受け取ると、まずは表紙をじっくり見た。金の髪、蜂蜜色の瞳、そして剣道って男は皆んな藍染の道着じゃないんだなと、白い道着に白袴を着たその姿にドキドキと胸が大きく鳴る。
雑誌の表紙だからか我妻はカメラ目線で、まるで自分が見つめられているみたいだと炭治郎は緊張してくる。
「おい。早く読めよ」
「ごめん、そうだった」
伊之助も読み途中だったと、炭治郎は表紙を開いた。すると今度はピンナップとして練習風景が差し込まれている。金の髪を揺らしながら竹刀を振りかぶっている姿に炭治郎は床に倒れた。
「おい! どうした!」
「な、なんでもない……」
そう言いながらも心中では「カッコいい……!!」と叫びたくてしょうがない。金髪で白道着に白袴の威力が凄い。動きがつくと尚のこと凄いと、炭治郎は荒くなる息を整えながら起き上がり、次のページを開いた。
「うわあああああ!! 見開き二ページのインタビューがついてる!!」
「当たり前だろ。インターハイの特集で、そいつ前回の優勝者なんだから」
「えっ!? インターハイ優勝者!?」
さらっと言われた言葉に炭治郎は驚いて肩を揺らした。伊之助は一つ目のパンを食べ終わって、二つ目に手を伸ばしている。そして指先でちょんちょんと雑誌の一部を指し示した。そこには確かに『第◯◯回 インターハイ優勝者 我妻善逸』と書かれている。
「我妻……善逸……」
思わぬところで本名を丸ごと知ってしまったと、炭治郎は震えた。本人から聞きたかったが、インターハイ優勝者でこんな風に雑誌の表紙を飾ってしまう知名度なら知ってしまったのは仕方がないのではないかとひとまず納得する。というか、我妻善逸っていう字面が格好いい。
炭治郎は色々書かれているインタビューに目を通すが、大体は練習についての話だった。けれど雑記の記者が『全中と同じく三連覇を狙っているか』という質問をしていて、おやっと思う。
「伊之助、全中ってなんだ?」
「全国中学校剣道大会」
「三連覇って書いてある」
「そうだぜ。そいつ無敗だからな」
「えええええ!?」
想像以上に凄い人だった。炭治郎は何故か心にダメージを負う。こんなに凄い人なのに全然知らなかったのかとダメージが凄い。もしかしなくても有名人なのではと混乱してくる。少なくとも、一年前から顔と名字と好きなパンの傾向しか知らない自分よりも伊之助の方がこの我妻善逸をよく知っている気がする。
「なんか……息切れしてきた……」
「なんでお前、そんなに興奮してんだよ」
「いや、これには事情があって…って、伊之助!? 伊之助も載ってるぞ!?」
パラパラとページを捲って巻頭のページ以降にも我妻善逸の記事がないかなと探していたら伊之助が1ページ使って特集されていた。思わぬところで友人を見かけて炭治郎はさらにびっくりする。
「ん? ああ、四月の頭になんか撮られたやつだな」
「え!? ええ!? なんで……あっ! 待て待て! 伊之助も全中って大会で優勝してるって書いてあるぞ!?」
「去年のな。紋逸の野郎がいないから、簡単だったんだよ。くそっ! 今回のインターハイでは俺があいつを打ち負かしてやる!」
「…………はあ……」
伊之助の言葉に、炭治郎はようやく点と点が繋がった。伊之助が倒したいと言っていた相手は彼だったのだ。我妻善逸だったのだ。確かに彼がいた時は優勝できず、彼がいなくなったら優勝したとなれば勝った気持ちにはなれないだろう。
炭治郎は伊之助のインタビューを見ているが、集中できず、文章が頭に入ってこない。ちょっと色々刺激が強すぎたと、炭治郎はひとまず雑誌を閉じた。伊之助は四つ目のパンを食べ終わったところで、雑誌を返すにも丁度いい。
「返すよ。ありがとう」
「もういいのか?」
「うん。自分で買って読むよ」
そうだ、そうしようと炭治郎は頷く。そして、もしかしなくても全中優勝者の伊之助が載っているなら、去年のバックナンバーにも我妻善逸は載っているのではと考えていた。手に入るかは分からないが。すると麦茶を飲み干した伊之助が、雑誌を開きながら言った。
「これもう、あそこの本屋だと売ってないぞ」
「え?」
「俺が買ったこれが最後の一冊だったから」
炭治郎はその言葉にハーっと息を吐く。そしてスマホを取り出すと、近くの本屋をマップで調べ始めた。この辺は個人店舗の小さいものが多いから扱っているだろうか。
「この辺で買うの難しいぞ。紋逸の奴はそこの藤ノ花高校に通ってるから、この辺の剣道やってる奴はみんな意識して、この雑誌買うんだよ」
「藤ノ花高校!?」
「お、おう。書いてあっただろ?」
大きい声を出した炭治郎に、伊之助はびっくりした顔をした。炭治郎も思ったより大きい声を出したのに自分でびっくりしつつ、そういえば雑誌にあった名前の下に、学校名が書いてあったかもしれないと思い出す。だが色々と衝撃が強すぎて近くの学校と結びついていなかった。
藤ノ花高校は炭治郎の家から歩いて二十分くらいしたところにある高校だ。なるほど。となれば確かに朝練に向かうのなら店の開店時間が七時はギリギリなのだろう。
「……凄い人なんだなあ」
「俺の方が凄いぜ!」
「そうだなあ」
炭治郎の言葉は適当であったが、伊之助は怒らなかった。ふんっと鼻を鳴らすとまた雑誌を捲っていく。その目は真剣で、ミーハーで我妻善逸を見ているのではないことが伝わってくる。伊之助にとったら彼は好敵手なのだ。
「……なあ伊之助。インターハイを見に行ったら、彼の試合は観れるのか?」
「ん? 紋逸のか?」
「名前違うけど、うん。そうだな。その人だ」
炭治郎がこくりと頷けば、伊之助はパチリと目を瞬いて上を見た。なんだろうと炭治郎が思うと伊之助の視線が戻ってくる。
「紋逸が見てぇなら、今週の日曜日、うちの学校で練習試合あるぞ」
「えっ」
「インターハイ待たなくても観れるぞ」
「ええっ!?」
「俺の相手できる奴、部内にいないからな。向こうもそうだからって、インターハイ予選前に練習試合することになったんだとよ」
「えええ!?」
「確か今週がうちでやって、来週は向こうでやる」
「ええええええええ!?」
「見学に来るか?」
「行きたいっ!!」
炭治郎は食い気味にそう言った。一年間、全くなんの進展もなかったのに、僅か一時間程度でポンポンと新たな道が開いていく。そのスピード感についていけなくてクラクラするが、チャンスは逃せない。
「差し入れ持っていくぞ!」
「おう」
炭治郎は突如降って湧いたチャンスにふらつきそうだ。週末、今週の日曜日。今日は木曜日なのであと二日くらい。炭治郎はパチパチと瞬きながら、「何としても日曜日は時間を作るっ!」と仕込みのスケジュールを頭の中で立て始めた。
接触
お前を見つけた時、お前が俺を覚えていないと気がついた時、この恋とも愛ともつかない気持ちを終わらせる為に現れたんだって、本気で思ったんだ。
「お、おはようございますっ!」
「おはようございます……?」
土曜日の朝七時、いつも通りに店に行けば、推定『竈門炭治郎』はソワソワと落ち着かない様子でいた。
いつもと違い何だか所作がドタバタしているし、目線もキョロキョロしていてどこか上の空だ。今までの年齢の割に落ちついていた態度を考えると、これは間違いなくおかしい。私生活で何かあったのだろうか。
そこまで思って善逸は「ははーん? もしや彼女でもできたか?」と口元を緩めて微笑む……のではなく、引きつらせた。想像以上にショックが大きい。彼女が出来たと確定していないのに、ショックが大きいことにまた、善逸はショックを受けていた。
(お、おかしいな。なんでこんなにショックなんだ?)
善逸は自分が持つトングが震えているのに戸惑う。ブルブルと震えてしまい、上手くパンが掴めそうにない。これはまずいと、善逸は標的を柔らかいパンから硬いパンに変えた。明太フランスをなんとか掴み、トレーに乗せる。
ちらりと隣を見ると、竈門炭治郎がボーッと立っていて、心ここにあらずの様子に善逸はキリリと胸が痛む。
(……落ち着けよ! こいつは竈門炭治郎だとしても、俺の好きな炭治郎じゃないだろ!)
善逸はハッと息を小さく吐くと、痛みに理由をつけて納得した。この痛みは間違いなく、俺の竈門炭治郎を恋しく思う気持ちからだと結論づけた。
善逸は幼い頃から前世の記憶があり、そして……前世の恋人についてもよーく覚えている。それがこの目の前にいる男と瓜二つの男だ。前世の善逸は男で、恋人も男というのはこの際、目を瞑ろう。善逸はそれでも、今も昔も彼が好きだ。竈門炭治郎が好きだ。
今のではなくて、前世で孤児であった善逸を親友にしてくれて、信じてくれて、愛してくれた竈門炭治郎が好きなのだ。目の前の男が生まれ変わりであったとしても、本当は名前も知らない男に好意など抱く筈がない。
(……はあー。そもそも俺はこいつに恋人ができるのを見届けようと思って、ここに通っているんじゃないか。ならこいつに彼女ができたかもっていうのは良いことだろ)
善逸が竈門ベーカリーに頻繁に通っているのは、今生の竈門炭治郎(推定)の幸せを見届ける為だ。前世の竈門炭治郎はそれはもう、不幸な男だった。勿論、終始不幸だったなんてことは言わない。彼からはきちんと幸せの音が聞こえていた。優しくて、温かくて、少しだけ寂しさを底に敷いた音だ。
彼は十三歳で家族を鬼に殺され、妹を鬼にされている。復讐ではなく、鬼になった妹を人間に戻す為に彼は鬼殺の道に入り、そしてたまたま善逸と出会った。
善逸は炭治郎に会うまで、ずっと人間として不出来だった。耳ばかりが良くて、人とのやり取りの仕方もロクにできない、距離感も分からぬ子供であった。それがほんの少し、ほんの少しだけ良くなったのは炭治郎のおかげだ。
彼は善逸のひとつひとつに叱ったり、微笑んだり、泣いたりしてくれた。呆れられたことがないわけではないが、それでも善逸が出会ってきた多くの人達と違い、炭治郎は善逸と向き合ってくれた。
鬼殺の師である、桑島慈悟郎以外にもそんな人がいるなんてと善逸は思ったものだ。なにしろ善逸のそれまでの人生で、心の底が温まるなんてことは殆どなかった。だから鬼殺の道に入り、鬼は怖いが命を懸けることで、人の温かみを得られることだけは良かったなんて、善逸は笑ったものだ。
しかし次の瞬間に「そんなことあるか! 命を懸けてるから善逸と居るんじゃない! 俺が善逸と居たいから一緒に居るんだ! お前は優しい奴だ!」と説教のような愛の告白の始まりを炭治郎にかまされた。
なぜそれが愛の告白の始まりかといえば、そこを切っ掛けに二人の仲が転がるように進んだからだ。炭治郎と善逸は、お互いそれぞれ鼻が良く、耳が良かった。どれくらい良いかと言えば、お互いを見ると香り立ち、響き出す、匂いと音に感づいてしまう程だ。
炭治郎と善逸が普通に繋いでいた手に指を絡ませ合うようになるまで、時間はさほど掛からなかった。あれは多分、スピード感があったからだなと今の善逸は振り返る。
ちょうどお互いに負傷中で、任務ですれ違うこともなく、日がな一緒に訓練したり遊んだりしていたから良かった。またいつも一緒の伊之助は元気だったので三人でなく、二人だったのも要因だろう。
お互いの匂いと音で気持ちを察して頭がふわふわしている時に、お互いの手のひらの温もりを深く知り、じゃあ、もっと知ったらどうなるのだろうか。
そんな欲求に対して、籠もれば誰も訪れない部屋というのは便利すぎた。蝶屋敷で借り受けている一室、続き間にいる禰豆子は眠っていて夜まで起きてこない。
炭治郎と善逸は、さんさんと降り注ぐお天道様が空にいる時に、隠れるように部屋の影でお互いに触れた。手のひらを合わせ、首筋を晒して撫であい、そして唇を合わせた。そこで終わればまだ良かったのかもしれないが、残念ながら心と裏腹に身体は落ち着かない。
雰囲気に当てられたのか何なのか、二人はそこでシコシコと揃ってイッた。そこまでくればもう、友達だろうなんて言えない。シコシコだけならまだしも、擦り合わせながら舌も絡ませてしまったのだ。抱き合ってちゅぱちゅぱと吸いあったのだからどうしようもない。
きっとここで炭治郎に任務でも入り、善逸だけにされたならば「こ、こんなこともあるよな! うん! 友達だもん!」と片付けて拗れた可能性があるが、炭治郎は負傷していて機能回復訓練中だったので善逸の側にずっといた。がしりと善逸の腕を取り、逃してはくれなかった。責任を取られたし、責任を取らされた。
善逸はそこから死ぬまで、身も心も炭治郎のものだったし、考えようによっては今も炭治郎のものだ。目の前の推定竈門炭治郎ではなく、前世の竈門炭治郎の。
「……炭治郎……」
「はいっ!?」
「え?」
横から大きな声が上がったのに善逸は驚いた。二つ目のパンであったチョコレートマフィンがトングから滑って、慌ててトレーで受け止める。危なかった、びっくりしたと善逸が思っていると、真っ赤な顔をした推定竈門炭治郎が立っている。善逸はなんだなんだと思い、そういえば彼女が出来たかもしれないんだったと思い出す。
(彼女、彼女いいなあ。俺も欲しいや。今回は結構モテるのに〜! くそっ! 死んだ炭治郎がチラついて全然その気になれねぇし! だいたいあいつが、生まれ変わっても一緒にいたいとか言うから……!!)
善逸はバンッとトレーをカウンターに置いた。今はいない恋人に対する不満が凄い。しかも目の前には瓜二つの別人、だが多分生まれ変わりがいる。「テメーは代用だコラッ!」というように、善逸はほんの少しだけ彼を睨んだ。女の子にモテる男は敵である。
「あの、えと、270円です」
「はい」
たまたまぴったりお金があったので、善逸は100円玉二枚と50円玉一枚に10円玉二枚を出した。重ならないようにしたのでパッと見て分かるはずだが、推定竈門炭治郎はトレーをじーっと見つめている。
「ちゃんとあるよね?」
「あ! あります! 大丈夫です! 丁度いただきます!」
善逸はレシートを指先で受け取り、財布のポケットに入れた。そしてビニールを掴んでカウンターに背を向ける。
「ありがとうございました!」
「どうもー」
ついつい声がつっけんどんになってしまう。善逸は思ったよりダメージあるなあと思いながら、店を出て走り出した。ビュンビュンと景色が飛ぶ中、ズキズキ痛む胸に顔を歪める。
生まれ変わって十六年目。ようやく見つけた過去の恋人の生まれ変わりは、自分と違って全く何一つ覚えちゃいなかった。
その時の善逸の気持ちは複雑なもので、簡単な言葉では表現できない。しかしあえて表現するならば、家族が鬼に殺されたことも、鬼にされたことも覚えていなくて良かったという気持ちと、俺のこと忘れたのか。俺と生まれ変わっても一緒にいたいって言ったじゃんという気持ちが大きかった。
しかし善逸とて覚えていて良かったかどうかについて考えると、首を傾げてしまう。少なくとも義兄である獪岳とは前より上手くやれていると思うし、経験の分でアドバンテージがあるため、慈悟郎にもいいところを見せてやれているが。
慈悟郎が教える居合道に関しては、既にそこに獪岳がいるので善逸は小学生の時にやめた。中学で剣道部があったので、これ幸いとそっちに行ったのだ。慈悟郎と獪岳には「もっと激しく打ち合うのがやってみたい」と言えば納得された。
居合道は専ら、一人で型を演ずる稽古が主だ。打ち合いはないため、善逸の主張に特に二人とも反対はなかった。何しろ中学の部活だ。やりたい事をやりなさいという方針の慈悟郎と、善逸にさほど興味のない獪岳は反対することはなかった。
結果として善逸は、その年の全国中学校剣道大会で一年生ながらに全国優勝した。これには慈悟郎も獪岳も流石に驚いていた。恥ずかしいから来ないでと予選に来させなかった為、善逸の腕前は都大会まで知られなかったのだ。
実際に目にした善逸の腕前に、慈悟郎は唸り、獪岳は納得した。きっと似ていても居合道と剣道で分野が違うからだろう。全国優勝した善逸を、獪岳は本当に珍しく褒めてくれた。「よくやった」という上から目線かつ、全国優勝して五文字しかくれないのかという感じであったが、善逸は嬉しかった。
要するに善逸は、前世の記憶があることで、獪岳の地雷をほんの少し回避できている。獪岳と一緒に暮らしていく上で大事なのは、獪岳の立ち位置を奪わないことだ。慈悟郎の一番を奪わないことだ。
慈悟郎は獪岳と善逸を平等に扱うが、獪岳は慈悟郎の道場の後継者だ。それは揺るぎない。善逸は幼い頃から獪岳が跡を継ぐという未来について口にしてきたし、慈悟郎には跡を継ぐ気はないことをそれとなく口にしていた。
例えば「お菓子屋さんになって爺ちゃん達にケーキ作る」とか、「お花屋さんになって街中をお花でいっぱいにしたい」とかだ。それは口にしたのはわざとだが、思ったことは普通にある。
善逸にはやりたい事が沢山ある。前世を知っていると今の世の中は選択肢だらけだ。どれもこれも凄く魅力がある。前世を知っているが故に、善逸は自由でもあった。それは今生は幼い頃から慈悟郎に引き取られて、愛されて、自由な選択肢を与えられてきたからでもあった。
ここまでは前世を覚えていて良かったことだ。では悪いことは何かと言われれば、それはもうドシンと善逸の心の真ん中に座り込んでいる男の存在だ。それが前世の恋人である竈門炭治郎、その人だ。
前世の記憶がある故に、善逸は今生の初恋も考えようによっては竈門炭治郎であるし、初めての夢精の相手も竈門炭治郎であるし、オナニーの相手も竈門炭治郎だ。
今はオナニーの相手だけで済んでいるが、時が進めばアナニーの相手も竈門炭治郎になってしまうかもしれない。それは虚しいにも程がある。何しろ善逸の竈門炭治郎は、もうどこにもいないのだ。善逸の心の中、頭の中、記憶の中にしかいない。
この世に生きる、今の竈門炭治郎は推定でしかない。なぜなら名前も知らないからだ。聞いたこともない。パン屋の名前が竈門ベーカリーであり、禰豆子そっくりの妹がいるなら炭治郎であろうが、彼には記憶はない。
一年ほど前、入学したての高校に向かう最中。なんとなくいつもと違うルートで学校に行こうとした時に見つけたパン屋で、これまた見つかるとは思っていなかった人を見つけた。
あの時の善逸はこの世の幸運を全て使ったかというくらい喜びに満ちたけれど、自分を見ても表情になんの変化もなく「いらっしゃいませ!」と相手に言われたのに絶望した。たった十六年しか生きていないのに、こっから未亡人ルートかと善逸は絶望した。
自分のこと好きって言ってくれない竈門炭治郎は解釈違いです。別人です。そんな気持ちなのに善逸は、竈門ベーカリーに通っている。なぜなら、善逸の心の真ん中に居座る竈門炭治郎を殺せるのが、彼だけだと思ったからだ。
善逸の好きな竈門炭治郎はこの世にいないのに、我が物顔で善逸の心の真ん中にいる。お陰で善逸は女の子と付き合うこともできない。折角、今生ではモテ期が来ているのに全くもって遺憾であると善逸は思っている。
女の子に告白されても、ラブレターを貰っても、飛び上がって喜んだ先にあるのは「この子を一番にできるだろうか?」という事だった。
善逸は自分を好きになってくれる人が好きだ。自分がないと言われても構わない。真っ直ぐに自分を、最初に好きになってくれた人を大切にしたい。この広い世界で自分を見つけてくれた人を幸せにしてあげたいのだ。
そして前世では、それがたまたま竈門炭治郎だった。善逸にとっては凄いことであったが、炭治郎の立ち位置で見れば何故に自分を選んだのかついぞ善逸は分からなかった。
どうして自分が好きなのかという善逸の疑問と、炭治郎の回答によるその議論は永遠に平行線なのだ。何回も議論したが善逸には分からなかった。後半はもう面倒臭くて、善逸は理解するのを放棄した。自分には分からない感性と理由で炭治郎は自分が好きなのだと無理やり納得した。晩年の善逸は、もうあれは、あの時代の炭治郎の個性だと認識することにしたのだ。
とにかく善逸は今生、心の真ん中に居座っている炭治郎のせいで、未亡人ルートに入りかけている。物理的に恋人がいたことがないのに未亡人ルートである。酷すぎるであろう。
前世で善逸は童貞のまま死んだが、今世ではまさかの童貞と処女を極めてしまうかもしれない。悲しすぎる。前世でも童貞のまま死んだのは悲しい現実であったが、代わりに最高の快感は知っていた。それでペイできるかと言ったらちょっと違うが、好きな人に抱きしめられて朝を迎えられる幸福はあった。しかし今回はこのままいくとそれが期待できない。だって善逸の好きな人はどこにもいないのだから。
だからこそ善逸は、今生で見つけた推定竈門炭治郎に期待しているのだ。彼はきっと、間違えて覚えていた自分の恋心を殺す存在なのだと善逸は期待していた。でないと「なんでお前は記憶ないんだよお!!」と詰ってしまいそうだった。
(……彼女できたかもしれない。なら、もう通わなくてもいいかな? 決定的な瞬間とか見た方がいいかな? あいつが……思い出すかも、なんて期待しなくていいかな?)
善逸は炭治郎に前世の記憶を思い出して欲しいと思っていない。竈門炭治郎の前世にはあまりに辛い記憶が多すぎる。物心ついた頃から覚えていた善逸と違い、今の彼が思い出せば人格に相当な影響を受けるだろう。そうなれば、今の家族が竈門炭治郎としていた存在が歪むかもしれない。それはそれで悲しすぎることだ。
(それにきっと、あの子は思い出さない。そういうんじゃないんだ)
あの優しい笑顔は、愛される為に生まれてきたのだと善逸は心の底から思っている。前世の分まで、家族みんなで幸せになるために生まれてきたと本当に思っているのだ。家族を失った末に出会った恋人と再会する為ではない。善逸の存在はあまりに今世の竈門炭治郎には不吉だった。
だから深く関係したいと善逸は思わない。一切合切の関係を絶てれば良かったのだろうが、善逸には善逸の人生が下手したらあと六十年くらいある。その長さを一人寂しく生きるのは悲しい。前世は愛されていた事実があったからいいけれど、今生ではまさか一回前の人生で愛されてましたよ……だ。そんなの困ると善逸はしくしく胸が痛い。
(だから頼むよ。たぶんだけど竈門炭治郎。俺の幸せな人生は君に懸かってんだ)
善逸は学校の門を走り抜けて部室に向かった。いつもより早く走ったせいで村田にも会わなかったし、部室にはきっと一年生しかいないだろうと、走っていた足を徐々に緩めていく。あんなに走ったのに、生まれてからずーっとしていた呼吸法のお陰でちっとも苦しくない。幼児期から全集中・常中をしていたせいで、普通の呼吸が分からない。
(俺の今の人生、記憶のせいでぐちゃぐちゃだよ)
良いこともあった。しかし善逸は、中学で始めた剣道で周りの子達が全く強くないのに気がついてうんざりしていた。彼らにではない。まるでズルをしているかのような自分にうんざりしているのだ。
前世で死闘を繰り広げた剣士が、生まれついて使える呼吸を持って剣道で名を馳せるなんてズルだ。しかし今更、善逸は後戻りできない。戻れば居合道を邁進する獪岳の足場を揺らがせる。それにここまで剣道ができる自分がなんの理由があれば辞められるのか善逸には分からないのだ。
(竈門炭治郎、頼むよ。俺の心を殺してくれ。あいつを好き過ぎて身動きできないんだよ。俺のあいつへの気持ちを殺してくれ。君が誰かを好きになれば、君が誰かと幸せになれば、俺のこの行き場のない恋も死ぬ気がするんだ。そしたら俺はきっと、新しく始められる気がするんだ)
これが全くもって他人任せであることは、善逸も重々と承知している。しかし善逸には他に方法がない。心の中の炭治郎はどこにもいないから、「もう善逸はいらないよ」と言ってもらう事ができないのだ。
捨てられない限り、善逸は死ぬまで炭治郎のものだ。生まれ変わっても一緒にいたいと彼が言ったように、ずっと心の中に座らせ続けるに違いない。だからこそ、彼に、今生の竈門炭治郎に我妻善逸は殺されたいのだ。愛とも恋ともつかぬ、この胸に巣食う気持ちの息の根を止めて欲しかった。
****
中学の時から帰宅部だったから、日曜日の学校ってこんな感じで、さらには部活中ってこんな感じなのかと、炭治郎は新鮮な気持ちで剣道場にいた。目の前には道着を来た伊之助と先輩達がいる。炭治郎はこの日、制服姿のまま、見学という扱いで道場の隅にいた。
(凄いなあ! 伊之助、格好いいな!)
伊之助は藍染の道着の上に防具を着けており、ウォーミングアップなのか素振りをしている。他の一年生達は走り込みらしいが、流石に昨年の全中優勝者は扱いが違うんだなと炭治郎は頷いた。
そもそも三年生にも、伊之助より強い人はいないのかもしれない。鼻を動かせば匂いで強さが分かるかもしれないが、残念ながらここは剣道場。鼻を動かしすぎると汗臭さで曲がってしまうかもしれないと炭治郎は自分の鼻を撫でた。
「おはようございます!」
「おはようございまーす!!」
野太い男の声の重なりが響き、藤ノ花高校の剣道部員達が来たのが分かった。彼らは皆、すでに道着を着込んでいる。近距離にあり、徒歩で移動できることと、もしかしたら私服高であることを考慮しているのかもしれない。
藤ノ花高校はこの辺では珍しい私服の学校だ。自由な校風を謳っているからだろうが、そのお陰で炭治郎は我妻善逸がどこの学校の生徒なのかさっぱり見当がつかなかった。彼が着ているのはブレザー制服であるが、私服高校なのであれはなんちゃって制服なのだろう。学校が分かれば、だからブレザーを着ていたり、時にはセーターだけだったりしたのだと今なら納得できる。そういえばスラックスもまちまちだった。
(い、いた! 物凄く目立つ……!!)
剣道場にぞろぞろと入ってきた藤ノ花高校の剣道部員達は皆藍染の道着を着ているが、その中でただ一人、白道着に白袴の人物がいる。それだけでも目立つのに、髪も綺麗な金髪で物凄く浮いている。炭治郎は目当ての人物にハァーっと息を吐いて気分の高揚をなんとか落ち着けた。
(凄い……すでに格好いいな。強そうだ……)
ドキドキしながらその姿を見つめていると、我妻善逸がくるりと剣道場を見渡し、そして隅に座る炭治郎に気がついた。びっくりした顔をしたのに、炭治郎は照れてはにかむ。たぶん、よく行く店の店員がいたのにびっくりしたのだろう。パチパチと瞬く我妻善逸は炭治郎をまじまじ見ていて、こんな風に視線を貰うの初めてだなと緊張した。
「おいお前っ! 新妻紋逸!!」
「いやいやっ!? 誰だよっ!?」
剣道場に響いた声に、我妻善逸が反応した。炭治郎も視線を動かすと、剣道場の真ん中で素振りをしていた伊之助が、手にした竹刀をびしりと我妻善逸に向けている。名前が殆ど違うけれど、我妻善逸は自分が呼ばれているのだと分かったらしい。我妻善逸の周りにいた藤ノ花高校の剣道部員達は巻き込まれたくないというように離れていく。
「お前だよお前!! そこの金キラ頭!!」
「いやいや。名前違うわ! 我妻善逸だよ」
「んなもんどーでもいい! 俺と勝負しろっ!!」
吠える伊之助に剣道部員達は「あー……」という顔をしているし、藤ノ花高校の生徒達は「なんだこいつ」という顔をしている。物凄く空気が微妙だなと、炭治郎は止めに入るかどうか悩んだ。友人としては止めるべきだろうが、今の伊之助は剣道部員としてここにいる。となれば外野の炭治郎が割って入るのは早計だ。まずは同じ部員が止めるべきだろう。
「はいはい。練習試合だからね。ちゃんと勝負するよ」
「本当だな!? 今回は逃げるなよ!?」
「一回も逃げたことないわ。いつの話よ?」
「去年の全中に出なかっただろうが!!」
「あったり前だわ!! 俺はその時もう高校生だからな!?」
ポンポンと飛び交う会話に炭治郎は目が点である。まるで昔からの知り合いのように会話をしているが、伊之助の話ぶりでは面識はあまりなさそうだと思っていたのだが……と炭治郎の中にムクムクと黒いモヤのようなものが湧き出てくる。
結局、顧問達がやって来たのでその場は収まった。伊之助もこの後に試合できるのなら良いのだろう。ふんっふんっと鼻息荒く、頬を紅潮させている。
対して我妻善逸はどこか冷めたような目で、防具を身につけていた。しかしその手つきは丁寧で、所作ひとつひとつが美しい。炭治郎が無意識にじーっと、不躾なまでに視線を送っていると、我妻善逸は困った顔で炭治郎を振り返った。
(あ、気がつかれた……)
炭治郎は見すぎていたことが恥ずかしくなり視線を逸らすが、元から彼を見ることが目的なので、やはりついつい視線が向いてしまう。
剣道場の窓から差し込む光が、我妻善逸の金の髪に反射している。キラキラと輝くそれに炭治郎が目を細めていたら、我妻善逸は手拭いを取り出すと手際良く頭に巻いていく。そして顔を覆う面をつけた時に、炭治郎はハッとした。
一人を見つめ過ぎて気がつかなかったが、いつの間にか練習試合が始まろうとしていた。伊之助を押さえ込むのは諦めているのか、初っ端から伊之助と我妻善逸の試合のようで二人が向かい合っている。
(始まるのか……)
二人は竹刀を持ち、礼をすると三歩前に出る。そしてすっと竹刀を前に構えたまま腰を下ろした。しーんっとする中で皆んなの注目が集まっている。よく考えればインターハイの優勝者と全国中学校剣道大会の優勝者の試合だ。もしかしなくても、もはや次のインターハイの優勝者争いに近いのではと炭治郎は気がついた。こんな身近にそんな凄い人が二人もいるなんてと息を呑む。
「始めっ!」
顧問の声で二人が立ち上がった。その次の瞬間に伊之助は踏み出していて、我妻善逸の面に向かって剣先が飛ぶ。しかし剣先が善逸の竹刀でずらされ、軌道が変わる。二本の竹刀が交わって、肘と肘がぶつかるほど近づき合い、離れる瞬間に竹刀が振り下ろされた。
しかしどちらも当たることはなく、剣先がギリギリ合わさる距離で睨み合っている。炭治郎は一瞬で起きた一連の流れを息を止めて見つめていた。もはや瞬きをしている間に決着がつくものなのだと理解して、見逃さぬように目を見張る。
伊之助の竹刀は伺うように小刻みに揺れるが、我妻善逸の竹刀はピタリと止まったままだ。二人で弧を描くように足を動かし、お互いの様子を見ている。
再び動いたのは我妻善逸からで、気勢と同時に剣先が突き出され、伊之助はそれを竹刀の真ん中で跳ね上げると一気に踏み込んだ。気勢と共に上から打ち込まれる面に、炭治郎は「決まる」と思いきや、我妻の剣先が戻って来ており、伊之助の剣筋を竹刀の左側で擦り上げ逸らすと、そのまま竹刀を伸ばすようにして伊之助の面を打った。我妻の気勢の余韻が耳に残る。音を置き去りにするように素早く身構える姿に、炭治郎はぞわあと背筋が震えた。
「一本っ!」
顧問の手が赤の旗を立てる。それを見て、そういえば背中に赤タスキが結んであるなと、炭治郎は遅ればせながら気がついた。ちなみに伊之助は白だ。
我妻善逸と伊之助の二人は竹刀を構えたまま最初の位置に戻り、静かに腰を下ろした。そして竹刀の構えを解くと立ち上がって後ろに下がっていく。それから二人は礼をし、壁際にいる仲間達のところまで戻っていくと、ゆっくり面を取った。
炭治郎は我妻の横顔をぼんやり見ていたが、反対側から「落ち着け嘴平! 早まるな!」という声が聞こえて、ぐるりと顔をそちらに向ける。すると肩を怒らせて震えている伊之助を、先輩達が宥めているようだった。次の練習試合が始まろうとしているが、伊之助がめちゃくちゃ悔しそうに我妻善逸を睨んでいる。それをまるで目に入っていないというように、そ知らぬ顔をしている我妻善逸に、炭治郎は何故かハラハラとした。
(それにしても凄い試合だった……)
炭治郎は次に行われている試合を半分流し見しながら、先ほどの二人の試合を思い出す。比較してはなんだが、成る程これが全国優勝者同士の試合かというくらい、立ち姿、所作ともに美しく、他の追随を許さないというものなんだと素人の炭治郎でも分かった。
(カッコ良かった……伊之助が羨ましいなあ……)
きっとあの二人はインターハイで戦い合うのだろう。たぶん地区予選でも戦うだろうけれど、きっと全国でも戦う。大きな会場で、多くの観客の前で、二人で睨み合う様は、さながら一枚絵かな、なんて炭治郎がホワホワ考えていると気がつけばどんどんと練習試合が進んでいた。そしてまた我妻善逸の番となり、伊之助が「俺! 俺がやるっ!!」と騒いでいるが、総当たりで練習する手筈になっているのか三年生が恐る恐る前に歩いていく。
しかし伊之助は「うがああああ!」と両腕を抑えてくる先輩達を引きずって前に出ようとしていて、もはや藤ノ花高校の剣道部員達はドン引きだ。しかし我妻善逸だけが伊之助の様子に微笑んでいた。
「…………」
「おりゃあああああ! 勝負だああああ!!」
我妻善逸の表情に目が吸い寄せられてしまったが、伊之助の暴挙が酷い。剣道の礼節はどうしたと炭治郎は立ち上がると、伊之助の所まで走り寄った。そして——。
「いい加減にしろっ!!」
ガッツーンと伊之助に頭突きを喰らわせる。すると伊之助はぐるりと目を回すと後ろにひっくり返った。炭治郎は静かになったなと胸を張ったが、周りがシーンとしているのに気がついて辺りを見渡す。
そしてほぼ全員が真っ青であるのを確認して、意識がない伊之助を確認して、やってしまったと遅まきに理解した。
「は、嘴平ああああ!!」
剣道部の顧問の叫びが剣道場に響き渡った。
****
「頭痛え……」
「ごめん……」
炭治郎は剣道場の外の芝生で、寝転ぶ伊之助にアイスノンを当ててやっている。あの後はちょっとした騒動になり、ひとまず見学終了と炭治郎は伊之助と外に出された。
剣道場の中では試合形式を終えて、打ち合いの稽古をしているのか、竹刀がぶつかり合う音が聞こえてくる。炭治郎は我妻善逸が打ち合う姿が見たかったなと溜息を吐くが、元はと言えば小学校からのノリで伊之助に頭突きをかました自分が悪いことは分かっている。
伊之助は炭治郎の行動に理解があるが、他の先輩方や藤ノ花高校の剣道部員達、そして我妻善逸も炭治郎の行動は奇行に見えただろう。
(最悪だ。変な奴だって、危ない奴だって思われた)
炭治郎は伊之助の額に乗せたアイスノンがずり落ちないよう押さえながら、もう一度大きな溜息を吐いた。その音を拾ったのか、伊之助が「どうした?」と聞いてきたが、炭治郎は首を振り「なんでもない」と答える。だがやはり溜息は止まらなくて——もう一度大きなものを一つ零した。
「でっかい溜息だなあ」
聞こえて来た声に、炭治郎はパッと顔をあげる。剣道場周りは臭うので鼻を使っていないから全く気がつかなかった。ザリザリと砂利を踏みながらゆっくり歩いてきた人は我妻善逸で、日の光に当てられた金髪が輝いている。炭治郎は思わず鼻で息を吸い込んだが、彼からはあまり汗の匂いがせず、楽しげな匂いがしていた。
「あ、えっと……」
「ほら、水分補給しなよ。もう六月近いから油断すると熱中症になるぞ。これはうちの学校からの差し入れ」
「ありがとうございます」
差し出されたのは二本のスポーツ飲料のペットボトルで、炭治郎はお礼を言って受け取ると、一本を伊之助に持たせた。伊之助は受け取ると身体を起こして蓋を開け、それを呷る。炭治郎も伊之助に倣って蓋を開けた。
「頂きます」
「いーえ。こちらこそパンの差し入れどーも」
我妻善逸は炭治郎と伊之助の前に蹲み込むと、小袋に入ったあんパンを見せた。それは炭治郎が朝に大量に焼いてきたあんパンだ。運動して疲れたら甘いものかなと、粒あんパンを両校分に差し入れたのだが、喜んでもらえたなら良かった。
「あの、それ粒あんパンですけど大丈夫ですか?」
あんパンには粒餡とこし餡がある。その趣向の違いは山よりも高く、海よりも深い……場合がある。炭治郎は我妻善逸が粒あんパン嫌いだったらと焦ったが、我妻善逸はむしゃりとあんパンを齧って笑った。
「それ今更過ぎない? 俺はもう一年も君のとこのパン買ってるし、あんパンも散々買ってるけど? ちなみに俺はどっちも好きだよ」
そう言った我妻善逸に、炭治郎はカーッと赤くなった。確かに今更過ぎる質問だった。思い出せば彼は粒餡も、こし餡も、どちらも買っていた。特別の拘りがない第三勢力であった。ちなみに炭治郎も第三勢力側だ。そもそも特別にあんパンに好き嫌いを感じたことがないのだが。
「それに君のところのパンは美味しいからね。こし餡派もきっと文句ないよ」
「それは本当ですか!? うちのパンを美味しいと思いますか!?」
「うん? 美味しいよ?」
その言葉に炭治郎はパッと花咲くように笑った。頻繁に買いに来てくれるのだから、美味しいと思ってくれているのは分かっていた。けれど目の前で食べて、美味しいと評価してくれるのを耳にすると、やはり嬉しさが違う。
そうだ、目の前で食べている。ずっとどんな顔をしてくれているのかと思っていたが、美味しそうに目尻を垂らして頰を緩めてくれている姿に、炭治郎はじーんと感動した。
「良かった……!」
「やっぱり自分のとこのパン褒められると嬉しい?」
「勿論だ! 何しろ俺が作ってるんだからな!」
びっくりした顔の我妻善逸に、炭治郎はハッとする。一つ年上の常連さんにタメ口で話してしまった。
「ご、ごめんなさい。馴れ馴れしくタメ口を使ってしまった……」
「いやそれは全然いいけど……えっ? これ、君が作ったの? いや違うのか? え? 店のパンは君が作ってるの?」
「俺の名前は竈門炭治郎だ!!」
「いや何!? 突然どうした!? そんなの知ってるわ!!」
「やっぱり知っていたんだな!」
炭治郎は我妻善逸が炭治郎の名前を知っていたというのに喜んだ。どこで知られたかは分からないが、昨日の朝に彼は『炭治郎』と自分の名前を呼んでいた。いや、呼んでいたというより呟いたようで、反射で炭治郎は返事をしたが、彼は不思議そうな顔をしていたので、違ったかと、聞き間違いかと炭治郎は思っていたのだ。
だが我妻善逸はいま、炭治郎の名前を知っていると答えた。つまり昨日はちょっと理由は分からないが自分の名前を呼んでくれたのだろう。だったら昨日、名前を呼んでくれたのにもっと反応をすれば良かったと炭治郎は思う。しかし、いまこうして会話をしているのだから、ここから挽回すればいい。
「あ、いや、知ってたというか……」
「君の名前はなんだ? 是非、教えてくれ!!」
「いやもうすっごいタメ口だわ。どうした? いきなり過ぎない?」
「君がタメ口でいいって言ったんだぞ?」
「いや、いいとは言ってねーよ。……我妻善逸です。てゆーか、道場で名乗ってなかった?」
「直接、善逸の口から俺に対して自己紹介をして欲しかったんだ」
「下の名前呼びぃ……」
なんなのこいつと顔を両手で覆う善逸に、炭治郎はどうしたのかと覗き込む。善逸は両手の指の間からこちらをチラリと見てきていて、その目線に炭治郎はどきりとする。
「はー……まあいいや。なんだっけ? 何の話してた? ああ、そうだ。パンって君が作ってるんだっけ?」
「俺は炭治郎だ」
「……炭治郎が全部作ってるの?」
「そうだぞ!」
「ご両親は……?」
恐る恐る聞かれた言葉に、炭治郎はキョトンとする。そして確かに子供がパンを全部作っているのは不自然だよなと納得して正直に言った。そもそも隠していない。
「母親はいる。でも父親は病気で死んでしまった」
それを聞いた瞬間、善逸から悲しみの匂いが漂った。それは同情ではなく、本当に純然たる悲しみの匂いだった。まるで自分の親が死んでしまったというような程に親身なもので炭治郎は驚く。可哀想にと同情を差し向けられることはあっても、辛い、苦しいと悲しみを感じられたのは初めてだった。
「……ちなみに兄弟は?」
「え? ああ、うちは俺を入れて六人兄弟だな。俺が長男で、下に弟が三人に、妹が二人いる」
炭治郎の言葉に善逸はぐっと唇を引き結んだ。そして瞼を閉じると、噛み締めるようにして口元を緩めて、ゆっくりと目を開けて笑う。
「長男かあ。じゃあ大黒柱みたいなもんだな。弟と妹とお母さん守ってんだなあ。偉いなあ。凄いなあ」
ふんにゃりと笑った善逸に、炭治郎はドッと心臓が穿たれたように感じた。
これまでの人生で、お兄ちゃんしてて偉いねと、頑張ってて凄いと褒められた事は沢山ある。しかしこれ程までに尊いものを見るように褒められたのは初めてだ。
様々な初めてを与えてくる善逸に、炭治郎はカッカと身体が熱くなる。嬉しい、どうしよう、嬉しいと口元を片手で覆い、お礼を言わなければ。そう思った炭治郎だったが、すっと横に影が差し、何かと顔を上げる。それは今までずっと隣で二人のやり取りを見ていた伊之助だった。
「伊之助?」
「どうだ? もう頭平気か? 石頭のすげぇ頭突き食らってたからなあ」
善逸の言葉に炭治郎は恥ずかしくなる。石頭だと分かるくらい、凄い音がしていただろうか。引かれたかなとそう思いながらチラッと善逸を見ると、善逸は伊之助を心配そうな目で見ている。それに優しいと炭治郎は心がホワホワしてきた。
「新島半逸」
「苗字が一字もあってねえな。我妻善逸な?」
「おい善逸。お前、なんでそんなに強ぇんだ?」
伊之助は瞬きせずにじっと善逸を見つめていた。それに善逸はハッと息を吸い、伊之助を見上げる。炭治郎でもわかる。伊之助からはビリビリとした強い匂いが漏れている。
「なんでって、まあ、これでもインターハイ優勝してるしなあ。それなりに稽古してるよ?」
「違う。お前は根本的に他の奴らと違う。生き物として何かが違う。俺には分かるぞ。人間ではお前だけが、俺の肌をビリビリさせるんだ。これに似たのは山で熊や猪とかち合った時くらいだ」
善逸はびっくりした顔をして、マジマジと伊之助を見た。それはその筈だと炭治郎も思う。伊之助が山で遊んでいて猪とかち合ったのは聞いた事があったが、熊は初耳だ。山のことはよく駆け回っている伊之助の方が詳しいだろうけれど、怖いから気をつけて欲しい。熊除けとか持っていって欲しい。
「お前、熊はヤバイだろ! 猪もヤバイけど……熊除けとか持ってたか!?」
着眼点同じだなと炭治郎が思っていると、伊之助が「話を逸らすんじゃねぇ!!」と一喝した。それに善逸が困ったように笑うので、炭治郎は善逸は意図的に熊の話に着目したのだと分かった。二人が何を言っているのか分からないが、ひとまず伊之助は強くなる秘訣を善逸が持っていると思っているらしい。
「そんなこと言われてもさあ〜……」
「何かが他の奴とは違う。なんだ! 教えろ! それがお前の強さだろ!!」
「うーん? なんだと思う?」
「それが分からねえから聞いてるんだろ!!」
癇癪を起こした子供のように地団駄を踏んで、伊之助が声を上げた。善逸の他にも休憩となったのか、パンの袋を片手に剣道場から出てくる部員達が多い。彼らが伊之助の剣幕にチラチラとこちらを見てくる。
「伊之助、少し静かに……」
炭治郎がそう言って伊之助の興奮を諌めようとしたら、伊之助を見上げていた善逸がおかしそうに笑った。その笑みに炭治郎は、言いかけた言葉を飲み込む。
「伊之助なら、わざわざ聞かなくても気がつくだろ」
「……」
そう言った善逸に伊之助が沈黙した。そして言われた内容に納得がいったのか、にいっと笑う。
「アハハハハハ!! 当たり前だ!! 俺はすげーんだぞ!!」
握った両の拳を上下に振って伊之助が吠える。その声があまりにも大きくて、剣道場周りいる人達が皆んなこちらを見てきた。
炭治郎はちょっと静かにしなさいと、伊之助をオロオロしながら見る。こんなに騒がしくしたら、来週の藤ノ花高校に赴くという練習試合に影響がないだろうかと不安になってしまう。
「そうだな。伊之助はすごい奴だよ。じゃあ元気そうだし、俺はこれで」
善逸はどうやら伊之助を心配して様子を見に来てくれたらしい。炭治郎は再び、優しいなあと嬉しくなる。好きかもしれないと思って見つめていた人だったが話す機会はなく、どんな人となりなのかを炭治郎は知らなかった。
何回も何回も見つめ続けて恋なのではと気がついたが、正直、一目惚れに分類されると思っている。だからこうして優しいところを見ると、自分の鼻と目と直感は正しかったと嬉しくなる。
善逸はザリザリという足音をさせて去っていった。そして気がつけば、向こうのほうに部活バッグを持った藤ノ花高校の一団がいて、炭治郎も伊之助も首を傾げた。
善逸が部員の差し出すバッグを受け取ると、そのまま一団は剣道場を離れて、校門の方へと走っていってしまう。それをポカンと見守っていた炭治郎と伊之助だが、すっかり姿が見えなくなってから気がついた。今日の練習試合、終わったんだなと。
「はああああああ!? あいつ!! 勝ち逃げしやがった!!」
「落ち着け伊之助! 来週も練習試合あるんだろう?」
「俺はすぐに強くなりてぇんだよ! あいつの強さは技巧とかそんなもんじゃねえ! もっと根本的なものだ!」
伊之助はギリギリと奥歯を噛んでいる。炭治郎は伊之助が言わんとしていることを何となくだが、理解できた。善逸は剣の技巧はもちろん凄いが、それだけではない何かが、確かにありそうだった。
伊之助も強い人の匂いだが、善逸の強さの匂いは何か違う。きっと深みが違うと炭治郎の鼻も言っている。根本的な何かが違う。体質なんて言われたらどうしようもないが、善逸はわざわざ聞かなくても伊之助なら気がつくと言っていたのだから、何か秘訣があるのは間違いないだろう。
「……そうだ! おい権八郎!」
「炭治郎だ!」
「あいつ、お前んちのパン屋に来るのか!?」
「え。ああ、来るぞ。店の開店時にちょくちょく」
さっきの会話でパン屋の話が出ていたなと思い、伊之助の言葉に炭治郎は頷く。しかし善逸は、朝は急いでいるようだから長話をする余裕はなさそうだと、炭治郎は少し困った。引き止めて迷惑をかけるのは良くない。強さを調べて突き止める時間はなさそうだ。しかし伊之助は炭治郎の想像と全く違うことを言った。
「それならあいつの連絡先を聞いておけよ!」
「え?」
「お前が聞いておけば俺も分かるだろ!? あいつ呼び出して、観察して、強さの秘密を暴いてやるぜ!! グハハハハハ!!」
「えっ、ええ!?」
高笑いをする伊之助に、炭治郎はどうしようと思う。しかし友達が困っているからという理由は炭治郎の原動力になり得る。自分の為だけに善逸に接近するよりも、心が楽だ。
(……パンを渡す時に、メッセージアプリのIDと電話番号を書いた紙も一緒に渡せば良いかな? いやでも男らしくないな。ちゃんと直接聞こう)
炭治郎は棚からぼた餅のような展開に、情けなくもニヤニヤと口が緩んでしまった。
たぶん友人
「もし生まれ変われるなら、俺もまたお前に会いたいなあ。それで、仲良くなりたい」
俺がそう言った時、お前はどんな顔をしていたっけ。
「よおおおおし! 今日も逃げずに来たな! 勝負だ!」
「勝負はしねーよ!! 防具がねーって言ってるだろ!!」
善逸の放課後の日常は、部活をして、帰って、風呂に入って、慈悟郎の作ってくれた夕飯を食べて、学校の宿題をして、スマホゲームをして、そして眠るだけだったが、このスケジュールに最近新たに『部活後に公園に行く』が追加された。しかも無理やりだ。
そしてこの公園で何が起こるかと言えば、目の前にいる竹刀を持った伊之助の存在で分かるように、ここから更に練習である。いや、練習と言っても見取稽古のようなもので、善逸が竹刀を振るうのを伊之助が見続けるだけだ。
「はあ、それじゃあ、いつもの様にやって見せるから」
「おう」
善逸は竹刀を構えると腰を落として、居合道の型の動きをとる。竹刀だからとてもやりにくいけれど、居合道は型をやり続ける武道でもあるので、剣道よりもこちらの方が呼吸が分かりやすいだろうと思ったからだ。
伊之助は夕暮れ時の公園の、ベンチ側の街灯の下で竹刀を振るう善逸を真剣に見ている。瞬きせず、じっと見つめられる感覚に、善逸は竹刀を持つ手が震えそうだ。
伊之助は本気で自分から、強さの秘訣……呼吸を得ようとしているのだと、その事実に善逸は感動にも似た感覚を覚えていた。
善逸が伊之助の存在に気がついたのは、中学三年生の時だった。最近、頭角を現している存在として『嘴平伊之助』がいると三年に上がったばかりの春先に、顧問に教えて貰ったからだ。善逸は驚いて、喜んで、そして大会の予選で伊之助の試合を観に行った。そこで伊之助そっくりの女の人が「伊之助頑張ってー!」と一生懸命応援しているのに、直感的に善逸は「お母さんだ」と分かった。それに、「良かった! 伊之助は今回はお母さんと一緒なんだ! やったじゃん!」と手放しで喜び、そして伊之助の太刀筋を見て、伊之助には記憶がないことを知った。
前世の鋭さが全くない。いや、この年齢では強いのは間違いないし、お世辞抜きに日本の剣道界を背負って立つ男だろう。しかし善逸が期待していた程の強さを伊之助は身に付けられていない。呼吸が違う。呼吸が普通だ。
その時に善逸は改めて自分は寂しいのだなと理解した。伊之助の名前を聞いた時、期待したのだ。あの男は何かにつけて規格外であったから、もしや記憶があるのではと期待をしたのだ。
しかし結果としては『嘴平伊之助』という今を幸せに生きる少年でしかなかった。いや、幸せなのは良いことだ。伊之助が今の幸せを得るにはきっと記憶は邪魔だったのだ。そう思って善逸は納得した。
きっと皆んな覚えていないのだ。呼吸も本当なら、潰えるべきなのだ、そう思っていた善逸だったが、伊之助は記憶がなくともやはり規格外の男であった。善逸と竹刀を交えた僅かな時間だけで、善逸の強さには根本的に違う何かの技術があると見抜いたのだ。そして今はそれを、見出して会得せんが為に、じっと鋭い目で見つめてくる。
(前に霹靂一閃のコツを教えてやった時と似てるな)
善逸は伊之助の視線にぐっと奥歯を噛む。見取稽古で呼吸をどこまで会得できるかは分からない。しかし伊之助は元から育手を介さずに鬼殺隊に入隊している。だから野生に生きていた時より感度が劣るとしても、いずれ呼吸に気づくのではないか……なんて善逸は期待をしてしまう。
そう。期待だ。善逸は今になって色々と期待を掛けることになってしまった。少しずつ諦めて、自分しか記憶はないし、前世のように呼吸を使えるのも自分だけだと、善逸が少しずつ納得し掛けてきたところにこれだ。伊之助だ。伊之助なら、記憶は思い出さないとしても……呼吸は習得するのではないかと、善逸は期待をしてしまうのだ。
「……どう?」
「……うーん……すげえってことしか分からねぇ」
「そーお? じゃあ今日はここまで、また明日な」
善逸の言葉に伊之助は不満そうにしたが、時間も時間だ。帰らなくてはならない。伊之助にだって今は家族がいるのだから、心配を掛けたらダメなのだ。前のように蝶屋敷の裏山を駆け回って二日帰って来なくても「伊之助いまどこだろなー」なんて呑気にしているなんて許されない。
「俺も腹減ったし」
「そうだ! 権八郎! パン寄越せ!」
「ああ、二人ともお疲れ様」
伊之助の声に、ずっとベンチに座って見ていた炭治郎が立ち上がった。腕にぶら下げていたビニール袋からパンを取り出して伊之助に差し出す。伊之助には大きなパン。善逸には夕飯のことを考慮して小さなパンだ。
この見取稽古を始めた時から、炭治郎は終わった後にパンをくれるのだが、最初にがっつり重たいパンを差し出されて善逸は断ったのだ。
何しろ帰れば慈悟郎が夕飯を用意してくれている。直前に他のものを食べれば夕飯が美味しく頂けないかもしれない。だから申し訳ないなと思いつつ「あー、俺はいいや」と善逸が断れば、炭治郎は目を丸くして、もの凄く驚いた顔をした。そして大変ショックですという顔に見る見るうちに変わっていくので、善逸は慌てて「爺ちゃんが夕飯用意してんのよ! 帰ったらすぐなのよ! だから食べたいけど我慢するわ!」と訳を話せば、炭治郎はすぐに顔色を良くし、パーっと花が咲いたかのような笑顔を見せた。善逸はその笑顔に見覚えがありすぎて、ジクジクと胸を痛ませる。
それから炭治郎はこうして公園で集まる時、伊之助には大きなパンを。善逸にはそれの三分の一もない小さなパンをくれる。しかも毎回同じパンはなく、さらに明らかに規格外と思われるサイズだ。きっとパンを作るときにわざわざ小さいサイズで作っているのだろう。差し出されたミニサイズのクリームパンに、善逸は僅かに困ったように炭治郎に言った。
「ありがとう炭治郎。けどさあ、毎度毎度大変じゃない? こんな小さいの作るのさあ?」
「ん? いや? 大変じゃないぞ? ちょっと形を小さくするだけだし」
「いや、でも手間かけさせて悪いなあとも思うのよ。俺、繊細だからさあ」
そう言いながらも遠慮なく善逸はパンを受け取った。小さなクリームパンは放り込めば一口で食べられそうだが、善逸はなるべく味わいたくていつも三口で食べる。
「ん〜おいひい」
「あはは、良かった!」
カラリとした笑い声を上げながら屈託なく、嬉しそうにする炭治郎に、善逸はほんの少しだけ笑い方が違うかなと分析する。それはそうだろう。抱えている生い立ちが違うのだ。善逸が最初に出会った炭治郎も、鬼に家族が殺されなければ、長男としての責務はありながらも、屈託なく笑ったのかもしれない。
いや、あの時代の炭治郎だって年相応に笑っていた。ただ音が、いつもほんの少しの切なさを伴っていたから、善逸は炭治郎が大きな悲しみの上に立って笑っていることを知っていただけだ。
(まあ、俺は今は耳は良くないからなぁ。普通よりいいけど、絶対音感がある程度だし)
善逸が二口目を齧ろうとした時、一緒にパンを食べていた伊之助が手を払っていた。軽快になる音に善逸は「相変わらず食べるの早いな」なんて思いながら、もっと味わってやれよと半目で伊之助を見やる。しかし伊之助はあっという間に通学鞄のリュックを背負ってしまう。
「あれ? 伊之助もう帰るのか?」
「おう! 今日は母ちゃん早いからな」
炭治郎の言葉に伊之助はそう言って頷くと、「じゃあまた明日な!」と善逸と炭治郎の二人を残して公園から走って出て行ってしまった。
その速さに呆気に取られながらも、「また明日かぁ」と善逸は呟いた。善逸の言葉に、斜め前にいた炭治郎が「ごめん。いつも付き合ってもらって」とほんの少し申し訳なさそうに言う。
善逸は「いいよ、別に」と言って、口に残りのパンを入れた。クリームの甘味が口の中に残っているが、唇を舐めている間に、唾液でじんわり甘味が緩む。善逸はベンチに置いていたペットボトルを取ると水を一口だけ含んだ。
「御馳走様ー。今日も美味しかったよ」
「明日はもっと美味しいぞ!」
「ははっ、期待してる!」
善逸は通学鞄を手に取った。炭治郎は一度家に帰ってから公園に来ているので手ぶらだ。二人揃って公園を出る為にのんびり歩きだす。六月に入り、日もだいぶ伸びてきたので暗くはないが、次第に雲が厚くなってくる季節になるなあと善逸は空を見上げて思った。
「梅雨になったら、伊之助の奴はどうするつもりだろ?」
「ああ、考えないとな。屋根がある所をどこか借りられないだろうか?」
普通に続行するつもりの炭治郎に、善逸は乾いた笑いを向ける。いや、問題はないのだ。善逸も伊之助が呼吸を習得するかもしれないとなれば興味深い。自分から積極的に指導をするのは嫌だが、見取稽古で覚えたなら、それは伊之助の才能だ。伊之助の努力の結果だ。だからこうして集まるのは吝かではない。
(でもまさかこんなことになるなんて……)
事の始まりは間違いなく、五月下旬に行われた炭治郎と伊之助が通うキメツ高校との練習試合のせいだった。伊之助がいるのは元から知っていたが、まさか炭治郎もそこの生徒で、更には伊之助と面識が……というか友達だとは知らなかった。
二人の仲の良さそうな様子に「なにそれずるい」と羨ましくなり、伊之助が炭治郎の頭突きでぶっ倒れたのをいい事に、善逸はいそいそと二人に近づいたのだ。
ほんの少しだけ、三人で会話をしたい。それだけで後は我慢するからと、善逸は自分を甘やかしたわけなのだが、気がついたらこの事態だ。なぜか毎日のように伊之助に部活後に公園に呼び出されている。
どうやって呼び出されているのかと言えば、練習試合が終わり、次に竈門ベーカリーに訪れた際に炭治郎に捕まったのだ。「どうか連絡先を交換してくれないだろうか!? あ! これはお礼のパンだ!」と矢継ぎ早に迫られてパンを押し付けられた為に、あれよあれよという間に善逸は連絡先を炭治郎と交換した。そしてその日の夕方に炭治郎から「◯◯公園に来てもらえないだろうか?」と連絡が入っていて、何だろうと行ってみれば、仁王立ちの伊之助がいた訳だ。
それから何故か毎日のように三人で会っている。平日は部活が終わった夕方に、土日も善逸と伊之助の部活後に時間が合えば公園に集まっている。炭治郎は店の余裕がある時に抜け出して、善逸と伊之助にパンを持ってきてくれるのだ。
善逸は本当になんでこんな事にと思うけれど、これが結構楽しいのだ。今まで全く不幸だと思ったことはないし、慈悟郎と獪岳という家族の中で上手くやってきて楽しかった。
けれどずっと心のどこかで寂しさがあったのも事実だ。前世の恋人が恋しいというのも勿論あるだろう。しかし、それを抜きにしても、やっぱりこうして炭治郎と伊之助と過ごすのは善逸にとっては特別なことなのだ。
ここに禰豆子がいないのは少し残念だが、禰豆子を入れて四人と、禰豆子を抜いて三人ではやはり違いがある。女の子がいるとやはり男同士の馬鹿騒ぎはできないから。
だからこうして毎日、僅かな時間でも二人に会えることは善逸に取って、ウキウキしてしまう出来事であった。二人の記憶がなくても、それでも炭治郎も伊之助も気のいい奴だ。
(楽しいなあ。梅雨になって、雨が降っても会えるのかな? 俺も公園以外で練習できるところ探そうかなあ……あ。ていうか、俺ん家の稽古場で良くない? 毎日は無理でも、爺ちゃんに相談したら使わせてくれる筈!)
そこまで考えて、毎日という言葉に善逸はハッとした。そうだ。炭治郎は彼女が出来たのではなかったのか? そのくせなんだか毎回、伊之助との練習に顔を出すが、彼女との逢瀬はどうしているのだろうかと、善逸は冷や汗が流れる。
「……あのさあ。炭治郎」
「なんだ?」
二人で公園を出て、商店街の方へと向かう。距離としては、ゆっくり歩いて十分くらいか。本当なら善逸は炭治郎の家のある商店街を経由する必要なんてないのだが、この短い距離を一緒に過ごすのもやっぱり楽しいのだ。
最初は名前も知り合わずに遠くで見ているだけでいいなんて思っていたけれど、恋人になれなくても友人になれたらやっぱり嬉しい。炭治郎であっても、善逸が恋い慕う炭治郎ではないのだから、多少の心の痛みはあれど、仲良く友達になりたいと善逸は自分を甘やかした。
「お前、いっつもパン持って練習に付き合ってくれるけどさあ。大丈夫なのか?」
「うん? パン屋は大丈夫だぞ? そんなに長い時間でもないし、閉店作業にも影響ないし」
「いや、そうじゃなくて。彼女との時間はちゃんと取れてんのか? 女の子は繊細なんだから、ちゃーんと大切にしてあげなさいよ?」
「……彼女?」
ポカンとした表情をする炭治郎に、善逸はおやっと思った。そしてパチパチと瞬いて「彼女いるだろ?」と善逸が言うと、炭治郎はギョッとした顔をして、急いで首を左右に振った。それに善逸は再びおやっと思う。彼女が出来たのは気のせいだったのか。
「炭治郎、彼女いないの? 嘘でしょ?」
「嘘じゃない! 生まれてから一度も恋人なんていたことないっ!!」
「ええー? 本当に? だってお前モテるだろ?」
「いや? モテたことなんてないが……」
戸惑う炭治郎の声に、善逸は本当に不思議そうに首を傾げる。嘘をついてはいなさそうだが、これはモテているのに気がついていないのではないだろうか。
「気がついてないだけじゃないか? 絶対に炭治郎はモテるって」
「そんなことは……」
「だって顔は男前だし、声もいいし、優しいし、スタイルだって鍛えられてて格好いいし、加えてその年で大黒柱してんだろ? 家族想いじゃん。モテる要素しかなくないか?」
そう言って善逸は、指折り炭治郎の良いところをあげていく。やろうと思えばもっとあげられる気がしたが、下手をすると前世の炭治郎の良いところをあげてしまいそうだったので、善逸はそこで止めておいた。そうしてどうだと言うように炭治郎を振り返れば、炭治郎はそっぽを向いて手のひらで顔を覆っている。
「どうしたの炭治郎?」
「いや、その、そんなに褒められると流石に照れる……」
夕陽で気がつかなかったが、炭治郎の耳を見れば確かに赤らんでいる。善逸は、照れる炭治郎というのが少し珍しくて口元を緩めた。
「褒めてるかあ? 事実だろ〜?」
「か、揶揄わないでくれっ!」
そう言って慌てる炭治郎に、善逸はヒヒヒっと笑ってバシバシと炭治郎の背を叩いた。可愛らしい反応をする炭治郎に平和だなあ、なんて善逸は思う。
前世の炭治郎と善逸は、命のやり取りを常とする鬼殺隊に所属していた。となればゆっくりと愛を育むなんて余裕はあるわけがなく、お互いに心が向き合っていることを耳と鼻で感じ取った二人はあっという間に深い仲に転げ落ちていった。
厳しい任務の後には、多少の傷くらいものともせずにお互いの体温を求めたものだ。炭治郎はそこそこ深傷を負った善逸を優しく抱いたし、善逸は動けぬ炭治郎の代わりに自分で腰を振ることもよくあった。
そんな組んず解れつの関係であったので、恥じらいなんてものはよくよく考えればあまりなかったかもしれない。炭治郎も開き直っていたので、割と明け透けに自分を求めてきたな、なんて善逸がぼんやり昔の事を思い出していると、ぐいっと肩を掴まれて驚いた。
「善逸っ!!」
「えっ? な、なに!?」
「善逸には恋人はいるのか!?」
「は……? 恋人……?」
そんなものはいない。恋人は自分を置き去りにして生まれ変わり、新しい人生を歩んでいる。善逸はそのことにズキリと胸が痛んだが、誰を責められるものでもないので、それを無視してニィーっと笑った。
「いや〜今は恋人はいないけどさぁ〜。それなりにモテるからなぁ俺って! そう遠くない未来にはいるかもしれないなぁ! ウィッヒヒ!」
「つまり今はいないんだな? というか、その笑い方は随分と気持ちが悪いぞ? それはやめたほうがいい」
「酷っ! 笑い方にケチつけるなよ!」
「ごめん、そうなんだが、元は悪くないのに損をしているような気がして。折角可愛らしいんだから、もっと普通に笑ったほうが良くないか?」
「男に可愛いもクソもあるか」
ケッと吐き捨てた善逸は、賑やかな雰囲気に溢れた商店街に目をやった。歩いているうちにいつの間にか商店街まで来ていたらしい。善逸はここから商店街を左に行き、炭治郎は右に行く。つまりはそこの曲がり角で二人はお別れだった。ほんの少しだけ寂しいなと思った善逸だが、どうせまた明日の朝に会えるので、別れを惜しむよりさっぱり行こうと思って駆け出そうとしたその瞬間、炭治郎に「なあ善逸!」と声を掛けられてタタラを踏む。
「んあ? 何?」
鍛えられた体幹で危うげなく振り返ると、炭治郎は真っ赤な顔をしていた。その瞳の輝きに、善逸はそう言えばお互いの気持ちを確かめ合った時もこんな顔をしていたなと古い記憶が蘇った。しかし炭治郎は一生懸命なのか、少したじろいだ善逸に気がつかなかったようで言葉を続ける。
「さっき善逸は俺を男前だと、モテる要素しかないと言っただろう?」
「え? ああ、そうね?」
「……実は俺には好きな人がいるんだが……アプローチしたら上手くいくだろうか?」
真っ赤になって、見つめてくる炭治郎に、善逸はヒュッと息が詰まる。好きな人がいる。炭治郎に。俺以外の好きな人が。善逸はそう思って心の中で首を振った。
(落ち着け、こいつは俺の竈門炭治郎じゃないだろ。俺の竈門炭治郎は俺だけを愛して死んでったじゃねーか)
善逸はひとつ息を吐くと、平静を出来る限り装ってポンポンっと炭治郎の肩を叩いた。そしてぐっと親指を立てて、炭治郎を肯定してやる。
「安心しろって! 絶対に上手くいく! 先を越されるのはムカつくけどな!」
そう言った善逸に、炭治郎はホッとした顔をして笑った。その笑顔だけで、善逸はこれでいいのだと思える。炭治郎の恋が上手くいけば、友達としてその幸せを見届ければ、善逸も前世の竈門炭治郎への気持ちを昔の事だと区切りをつけられるかもしれない。そうして次の人を愛せるかもしれない。とりあえず、アナニーを始める前に決着をつけたい善逸は、炭治郎に「応援するぜ! なんかあったら頼れよな!」と言って手を振った。
「炭治郎またな〜!」
「うん。また明日……あ、いや、後でメッセージ送るぞ! じゃあな! 善逸! 気をつけて帰るんだぞ!」
そう言ってくる炭治郎に、善逸はへらりと笑って、いつもは左に曲がるところをまっすぐ走った。そして路地に向かい、左に曲がる。なんだか今日は走りたい気分だったのだ。走るのには商店街は人が多すぎる。
「……炭治郎に好きな人かぁ……すっげーいい子なんだろうなあー!」
善逸はずびっと鼻を啜る。なんだろうか、今日はとても星が輝いて見えるなーなんて、どうしてか溢れてくる涙を無視して、善逸は自宅への道を走って行った。
友人ではない
近づけば分かった。俺に向ける匂いは、悲しみと愛しさが混じり合ってる。だからずっと、俺といる時の彼からは甘苦い匂いがするんだ。
朝の六時三十分。炭治郎はパンを並べながら、ソワソワと外を見る。店の鍵はもう開けてあるので、店を開店中にせずとも、いつも通り入ってくる筈なのだが、炭治郎は未だこの時間に慣れないでいた。しかしそれもしょうがないことだ。何しろこれから来るのは友達であるが、ただの友達ではない。炭治郎の友達兼、好きな人なのだから。
カランカランというベルの音に、炭治郎はハッと顔を上げる。そして入り口を振り返れば、善逸がそろりと扉から顔を覗かせているところだった。
「善逸! おはよう!」
「おはよう、炭治郎。朝から精が出るね」
そう言って店内に入ってきた善逸は相変わらず汗を掻いていない。じめっとした天気の中を走って来ている筈なのにと思いながら、炭治郎はこっそりと鼻を動かして善逸の匂いを吸い込む。相変わらず、強さと優しさを感じる匂いだ。
善逸は働く炭治郎の横を通ると、いつものようにカウンターの近くにあるスツールに座った。それは炭治郎が事務所から毎日、善逸の為に持ってきてるものだ。炭治郎は善逸がそこに座るのに疑問を持たなくなったのが嬉しい。心がウキウキする。確実に仲良くなれていると実感ができる。
善逸が七時よりも早く竈門ベーカリーを訪れるようになってしばらく経つ。理由としては毎日のように伊之助の練習に付き合ってもらって悪いから、何かお返しをしたいと炭治郎が朝に買い物に来た善逸に、自分のおすすめパンを押し付けるようになったからだ。善逸は「ええ!? 遊んでるだけなのに、友達からパンを毎日もらうのは悪いって!」と遠慮したので、炭治郎は「それなら朝少し早く店に来て、俺の話し相手になってくれ!」とさらに強引に押し切った。
結果として善逸は平日はいつも六時半くらいには竈門ベーカリーを訪れる。そして七時くらいまでここで仕事をする炭治郎の話し相手をして、その礼を含めてパンを貰って学校に行くのだ。
これに炭治郎はニコニコなのだが、善逸は「ちょっと援交とかパパ活みたいだなあ」なんて冗談で言うので、確かに少し似てるかもなんて炭治郎は焦った。何しろこの時間は炭治郎に下心があるからこそ、用意したようなものだ。毎日、五分以下だった交流が朝に三十分、夕方に一時間となればとても凄いことではないだろうか。特に朝なんて二人きりだ。パン作りにも精が出る。
約束を取り付けた時は何を話せばいいだろうかと炭治郎は思ったが、正直言って想像以上に善逸とのやり取りは心地が良かった。打てば響くというような言葉のやり取りで、考え方や価値観が違っても嫌ではない。
炭治郎が大切にしているものを、大切なんだなと理解してくれる姿勢も好ましかった。善逸との何気ないやり取りでも炭治郎は実感する。何も知らずに好きになったようなものだったが、間違っていなかったと自分が誇らしくなる。
善逸を好きになって良かった。そして善逸からも好きって思って欲しい。友情だけでなく、もっと踏み込んだ特別な関係になりたい。炭治郎はそう考えつつ、昨日見たバラエティ番組の話をする善逸の声に耳を傾けていた。
「あーあ。なんかさあ。遊びたいよなあ」
「え? 遊びたい?」
「うーん」
善逸の言葉に炭治郎はキョトンとする。振り返ってみると、善逸はスツールに座りながらスマホを見つめていた。そのほんの少しだけつまらなそうな顔に、どうしたのかなと炭治郎は首を傾げる。
「遊びたいって、どうかしたのか?」
「んー? どうってこともないけど、部活三昧で遊んでないなーって思ってさあ。だって俺たち高校生だぜ!? 部活も青春かもしれないけどさぁ! 他にも青春っぽいことしたいじゃん!! ちょっとくらい遊びたいじゃん!」
そう言って溜息をつく善逸に、炭治郎はなるほどっと頷いた。そしてそういえば最近の善逸は、よく「数学の教師がやたらに小テストが好きなんだよっ! くそっ!」とテストについて文句を言っていたなぁと思い出す。
日々のテストに朝練に放課後練習、それに追加して伊之助の為の練習に時間を割いていたら、確かに気づまりしてしまいそうだ。そんなに頑張って生きているのだから、遊びたいと思っても不思議なことではないし、遊びたい気持ちが許されないなんて、あっていいわけがない。
炭治郎はよしっと頷くとパンを全て並べ終わって空になったトレーを小脇に抱え、善逸の正面に立った。
「善逸! 俺と遊ばないか!?」
「え? いいの?」
「いいぞ! 俺も善逸と遊びたい! 伊之助は……部活があるから合わせるのは難しいかもしれないが、俺は善逸の予定に合わせられるぞ!」
そう言った炭治郎に、善逸は少し考えてからふにゃっと笑った。その蜂蜜みたいな笑顔に炭治郎はどきりとする。しかし善逸は炭治郎の反応に気がついておらず「ええ〜いいの? じゃあ、いつにしようかなあ」なんて笑っている。
「都合いい時ある? 平日と休日ならどっちがいい?」
「俺は、善逸に合わせるぞ。そりゃあ、たくさん遊べる休日の方がいいけど……」
「じゃあ今度の日曜日は?」
「その日は部活の練習ないのか?」
善逸の学校は強豪校だろうと思い炭治郎が聞けば、善逸は「うん。平気だよ」とあっさり頷いた。
「俺の学校は自由が売りだから、部活に出る出ないも自由なの。結果主義なんだよねー」
「なるほど。結果主義」
そうであれば、善逸以上に結果を出している人間は日本にいない。何しろ昨年のインターハイ優勝者だ。善逸も少しは休まないと、他の部員も休みにくいかもしれないと炭治郎は納得して「じゃあ日曜日だな!」と笑った。
****
(これってデートだな……)
炭治郎は待ち合わせ場所の駅前で、ソワソワしながら善逸を待っていた。善逸はただ単に遊ぼうとしているのかもしれないが、善逸のことを好きな炭治郎からすればこれはデートだ。何かロマンティックなことがあるわけでもないだろうが、それでも少しだけ期待してしまうのが男心だろう。
とはいえ、部活上がりに伊之助も合流することになっている。伊之助は二時過ぎくらいに合流できると言っていたので、二人きりなのは実質四時間とちょっとくらいか。
炭治郎は腕時計の九時五十分を見つめ、遅刻のメッセージとか入ってないよなとスマホを取り出そうとした時、ふわりと心地の良い匂いが鼻に入り顔を上げた。
駅前に続く商店街から、善逸がゆっくりこちらに歩いて来ている。向こうも炭治郎に気がついたのか、手を振るとパタパタと走って来た。翻るTシャツの裾と揺れる金髪に炭治郎はポーッとしながら自分も手を振り返す。
「おはよう炭治郎! 早くない!? 待ち合わせ場所、家の側なんだからゆっくりで良くない!?」
「あ、いやそうなんだけど……」
家でソワソワしてたら邪魔と言われて追い出されたなんて炭治郎は言えない。善逸は特に言葉の続きを求めていないのか駅の改札へと向かい、スマホを取り出して改札機へと翳した。
「あ。スマホにICカード入ってるのか?」
「そうそう。楽だしね。徒歩通学だから持ち歩く習慣ないし、カードだといざって時にないっ! なんて困るじゃん?」
「へぇー。俺もそうしようかなあ」
「いやいや炭治郎! お前まさか切符なのかよ!?」
「俺も徒歩通学だし、そもそも電車を滅多に使わないからこれで十分なんだよ」
善逸が来る前に事前に買っていた切符を炭治郎は改札機に通す。笑っている善逸に「笑うな!」と言えば「ごめんごめん」と善逸は笑いながら謝ってくるので、炭治郎はすぐさまスマホで、ICカードのアプリをダウンロードする。
「炭治郎、電車来るぞ」
「あ、うん」
炭治郎がアプリに目を落としながらそう言うと、善逸が「ほら! ながらで歩くと危ないぞ!」と言って炭治郎の腕を引いた。自然に取られた腕にどきりとするも、善逸は気にした様子もないのか、ぐいぐいと炭治郎を引っ張っていく。炭治郎はスマホを下ろすと、逆らうことなく善逸にされるがままにホームに滑り込んでくる電車に乗った。
炭治郎はこうして誰かに主導されるのは珍しいことで、何となく面映い。何しろ炭治郎は長男であるという自負が大きいのだ。外でもその『竈門家の長男』という肩書は炭治郎の武器であり、防具でもある。もはやそれは標準装備で決して剥がれることがないものだと炭治郎は無意識に思っていたが、「なになに? アプリ入れたの?」と言って車両の隅に立ちながら炭治郎の手元を覗いてくる善逸に、素直に「うーん。それがよく分からない」と笑った。
普段の炭治郎であれば「家に帰ってからやる」とか「母さんに聞く」とか言って、一旦、外からの手助けはシャットアウトしただろう。勿論、家の中で解決できないなら外に助けを求めにいくが、炭治郎はまず家の中での解決を図るのが癖であった。情けない姿を母親以外に見られるのが嫌だという無意識の矜持のせいであるのだが……。
「ここ押して、ここ読んで、大丈夫ならこっちで支払いとユーザー登録できるぜ」
目を少し伏せながらそう言う善逸の金の睫毛を、炭治郎はじっと見つめた。スマホなんて小さい画面、しかも一つのものを二人で見つめるのだから当然顔が近くなる。
炭治郎が漏れ出そうになる溜息を堪えると、ついつい眉が寄って唇が引き結ばれた。窓ガラスに薄ーく映った自分は、明らかに少し変な顔をしている。
「炭治郎? 聞いて……る……」
パッと顔を上げた善逸に、炭治郎は「変な顔を見られてしまった!」と焦った。しかし善逸は炭治郎の顔を見た瞬間に、一気にボッと顔を赤らめる。その反応に炭治郎はびしりと固まった。何故なら本当に善逸は、林檎のように耳までもが赤いからだ。
「……善逸?」
「おっ、前っ!! マジマジ見てんなよ! めちゃくちゃ恥ずかしいじゃねぇか! そんなに見たら俺が減るだろ!!」
バシリと胸を叩かれて、炭治郎はうっと息が少し詰まる。善逸は口元を押さえつつ、サッと炭治郎から身を引いた。急に隣からなくなった体温、そして空いたスペースに入り込む空調の風が寒々しい。いや、六月も中頃で梅雨が遅れているとはいえ、湿気は増えてきている。寒いことなんかなく、暑いくらいだ。
しかし善逸から距離を置かれるのは寂しい。もっと隣にいてほしい。炭治郎は自然と手が伸びて、距離を取ろうとした善逸の腕を掴んで引き戻した。慌てた善逸に何かを言われるよりも前に指を動かすと、「次は? どうしたらいい?」とアプリの画面を見せる。
炭治郎が頼る姿勢を見せれば、「えーと、次は……」と言って善逸が再び顔を寄せてくる。その時にはもう表情は戻っていたけれど、善逸からは動揺の匂いがしていた。そして僅かな期待と甘い匂い。それに炭治郎はドッと大きく心臓を鳴らす。
(こ、この反応はなんだ。顔を赤らめて離れて、その後に平静を装っているが、心の中では動揺して期待して甘い匂いをさせてるって……も、もしかして脈があるんだろうか?)
炭治郎はドキドキしながらスマホの画面を見つめる。流石に炭治郎も好きだなぁと思いながら側にいても、関係性など発展しようがないと思っていた。
そりゃあ善逸と想いあって恋をしたいと願ってはいるし、好きな人にアプローチすると宣言したが、正直言ってどうしたら意識してもらえるか不明だった。男女であればもう少しハードルは低かっただろうが、炭治郎と善逸は同性なのだから近づいて距離を縮めても友情としか捉えられない可能性の方が高い。潜在的な意識というのはそれほど大きいことなのだ。炭治郎だって今まで同性が側に寄っても自分に好意があるのだろうかなんて思ったことはない。しかし——。
(ううっ……善逸っ! そんな反応は期待してしまうぞ! 今も、今も甘い匂いがする。ほんの少しだけ切なくて、苦くて、でも甘い、絡みつくような匂いがするっ!)
その病みつきになりそうな匂いに炭治郎は必死に耐えた。でなければ電車内で「好きだ善逸っ!!」と叫んで抱きしめてしまいそうだった。それくらいに、善逸は自分に対して筆舌しがたい感情を向けている。何故そんなものをと思うくらいに複雑な感情を自分に向けている。
ギリギリと理性の糸を張り詰める炭治郎だったが、幸いなことに目的地は二駅先だったのであっという間に到着した。開く扉に「ほら行こうぜ」と善逸に言われて、炭治郎は救われる。電車の中で醜態を晒して善逸に嫌われることはなかった。ひとまずは耐え切ったと炭治郎はホッとして電車を降りるのだった
****
(あれ? これって、ヤバくね?)
善逸は炭治郎と入ったゲームセンターの中で、ひたすらパンチングアクションゲームの敵を撲殺しながら、ぐるぐると考えていた。何をといえば、炭治郎のことであり、パンチングアクションゲームの展開ではない。パンチングアクションゲームでは見事な迄に全てヒットさせており、斜め後ろでは炭治郎が「凄いっ! 凄いぞ善逸!! 次がファイナルステージだ!!」とはしゃいでいる声が聞こえていた。
(……なんか、俺、ヤバいよな?)
そう思った理由は、善逸が炭治郎のスマホ画面を覗き込んでICカードのアプリの設定方法を説明していた時だった。反応のない炭治郎にどうしたのかと思い顔を上げれば、炭治郎は目の奥にぐらぐら湯だる熱を灯しながら、欲しいというのをひたすら我慢している表情をしていた時だった。
何故そうだと言えるのか。それは善逸が前世で、その表情の炭治郎をよく見たからだ。二人で街に降りて散策して遊んでいた時に、突然に炭治郎から欲の音が聞こえたと思えば先ほど見た炭治郎と同じ表情だったのだ。
その顔を見ると善逸はもうダメだ。炭治郎に求められる喜びに、しかし恥ずかしさに身が震えてしまう。
前世の時は二人で蕎麦屋の二階に駆け込むだけだったが、今はそんなことできるわけがない。炭治郎とはただの友達だし、そして善逸も今の炭治郎を恋しく想っているわけではない……筈だ。
善逸は無心になりたいと思いながらも、考えは頭の中をぐるぐるしている。行き場のない衝動を発散したくて、指だけで引き金を引くゾンビシューティングではなく、実際にパンチを敵にかますゲームを選んだ。炭治郎も隣で一緒にやっていたのだが、いつの間にかゲームオーバーしたらしく、今は善逸一人だ。
善逸はあちこちから現れる敵を片っ端からボカスカ殴る。腰を落として前後に軽く揺れながら、獪岳が見ている格闘技の番組のボクサーの動きを見よう見まねで再現し、ジャブとストレートを休みなく繰り返す。呼吸を使っているので疲れ知らずだ。息切れひとつせずにキレッキレの動きでハイスコアを叩き出すのを見て、とんでもないギャラリーが集まりつつあるのにも善逸は気づかず、ひたすらに敵を倒す。
(もしかして炭治郎、俺のこと好き? いやいやいや! 待て待て! あり得るわけねーだろそんなこと! こんな平和な世界で炭治郎が俺を選ぶわけないだろ! 選り取り見取りだろ!! さっきのはホラ! あれだよ! きっと日の光が眩しかったんだ! 今日は天気いいしね! 本当にいつになったら雨降るんだろーね!? とっくに梅雨なんだけどね!? 今年の夏は水不足とか大丈夫かしらね!?)
善逸は無理やりに考えを纏めると、ラスボスの巨躯に向かって連続パンチをぶちかます。このボスは体力が多く、さらには的確にマーキングに打ち込まなければヒット扱いにならず、加えて時間制限付きという無理ゲーじゃねぇかというキャラクターで有名なのだ。何しろそのボスに到達するまでに大半の人はクタクタだからだ。
しかし善逸は何も考えずにただマーキングを追った。素早く打ち込むパンチによってラスボスの体力はガンガンに削られ、最後は善逸の渾身の右ストレートによって倒れた。
流れ出すエンディングをボーッと見つめる善逸だったが、周囲からワアッと上がった大歓声に驚いて身体が跳ね上がる。何事かと振り返れば、真っ青になってしまうくらいに人垣ができていた。そしてそれは画面にランキング一位という表示がでて更に盛り上がる。
「善逸っ! 凄いぞ! ランキングで一位だ! 日本一だ!」
「あ、そう? そうなの? えっ!? 日本一!? 俺、日本一を取ったの!?」
わー! そんなの初めてー! なんて場の空気に当てられてポヤポヤする善逸だが、実際には日本一など剣道で取りまくりだ。しかしそんなの思い至らず、スタッフの人に促されるままに炭治郎とツーショットでランキング一位の画面と一緒に写真を撮る。店のチェキで一枚、炭治郎のスマホで一枚だ。
「いやなんで炭治郎のスマホで撮ったんだよ」
「ごめん。スマホをって言われたから咄嗟に俺のを出してしまった」
善逸と炭治郎はギャラリーの壁から手を取り合って抜け出すと、早々にゲーセンを出た。そしてどこか休める場所と思い、近くのショッピングモールの自販機エリアに来たのだ。汗はかいていないが、流石に動くと飲み物が欲しい。
善逸はスポーツドリンクを、炭治郎はお茶を買うとベンチに並んで座る。しかし炭治郎は買ったお茶を開けるでもなく、じーっと店でもらったチェキの写真を見ていた。善逸はそれの写真を横から覗く。写真は暗く、少しボケていて、明らかに二人とも顔色が悪かった。
「映り悪っ」
「まあ、暗い場所だしなあ。それにしても善逸、凄かったな! ドンドン倒してくのに興奮したっ!」
「あ、あらそーお? 炭治郎、放っておいてごめんな?」
「いやっ! そんなことない! 善逸の戦ってる動画も撮ったけど、ほら、凄い格好いいぞ!」
「ひえー! 撮ってんのかよ!?」
「撮った! 伊之助にも送った!!」
「やめて!? 伊之助が見たら、こんなの俺にも出来るって言ってクリアするまで齧り付くじゃん!?」
善逸の言葉に炭治郎はほんの少しだけ驚いた顔をした。それに善逸はどうしたのかと、口をつけようとしていたペットボトルの動きを止める。
「どうかしたの?」
「いや、確かに伊之助なら言いそうだなって思って」
「だよね? あいつなら絶対に言うよな?」
「言うな。間違いない」
神妙に頷く炭治郎に善逸はハハッと笑うと、今度こそスポーツドリンクを喉に流し込み、染み渡るその独特の甘みにハァーっと息を吐いた。
「あー! クレーンゲームもやりたかったのに!」
「人が凄かったからな。でも伊之助が来たらまたゲーセン行くからその時できるんじゃないか?」
「うーん。そうだけど……真っ先にパンチングゲームのところ行くだろ」
「確かにな」
そう言って同意した炭治郎を横目で見て、善逸はくるりと辺りを見渡した。そして「あっ」と言って立ち上がる。善逸の視線の先にあるのは自販機の並んだ少し先。小さなクレーンゲーム機だった。
「炭治郎、あれあれ」
「ん?」
二人でその小さなクレーンゲームの前に立つ。普通のクレーンゲーム機の三分の一サイズ。一回100円で、中に入っているのはよく分からない小さな人形に細い紐が付いているだけのものだ。たぶんこれは子供向けなのだろう。ちゃちな作りが面白い。
「これでいーや。やろうぜ」
「欲しいのか?」
「いいや? ただクレーンゲームがやりたいの」
善逸はそう言って100円を入れた。プラプラと細いアームが動いていくのだが、的である人形が小さ過ぎる。これはどれを狙っても同じ感じかなと、善逸はなんとなく縦横にアームを動かして、人形達の中に突っ込む。そして引き上がったアームは空を掴み、ゆっくりと元いた位置に戻ってきた。その空振りに人形など欲しくもなかったが、善逸は「あー!!」と声を上げてしまう。
「失敗だな」
「思ったより取れねぇ! 炭治郎やってみる?」
「じゃあやろうかな」
善逸に場所を譲られた炭治郎は、財布から100[円を取り出して、お金の投入口にカチャンと入れる。そしてほんの少しだけアームを動かし、取り出し口の穴の近くにあった少しだけ人形が積み重なった山の向こう側にアームを突っ込んだ。
「おっ! おお〜!」
「取れた」
アームによって山が崩れ、取り出し口の穴にコロリコロリと人形が落ちる。炭治郎は身体を屈めると取り出し口から人形を取り出した。炭治郎の手の中にすっぽりと二つ収まる、まあるい顔だけの人形だ。ウサギとブタ。善逸はちょいちょいと指でそれを突いて笑った。
「凄いなあ、二つも取れた!」
「弟や妹によく取ってたからな。この手のは得意なんだ」
「へぇー!」
「善逸、どっちがいい?」
「え?」
炭治郎の言葉に善逸は人形を見ていた顔をあげた。すると炭治郎は愛しいものを見るような目を善逸に向けていて、善逸の身体にじわっと熱と緊張が走る。
「どっちがいいって……」
「ひとつ、善逸に持ってて欲しい。今日の記念に」
そう言って柔らかく微笑まれるのに、善逸は恋人の炭治郎が記憶から引き摺り出される。柔らかい頬笑みが本当に瓜二つで、目の前の炭治郎が自分の炭治郎だと錯覚してしまいそうだ。
「あ、じゃあ……こっちで……」
善逸はそう言ってブタを取った。炭治郎は「じゃあ俺はこっちだな」と言って、ウサギをスマホのケースに取り付け始める。善逸は炭治郎を見て、俺もそうするべきだろうかとぼんやり思ってスマホを取り出した。そして炭治郎に倣い、ろくに考えもせずにブタをスマホのケースに取り付ける。
「お揃いだな」
そう言ってこつんとスマホを合わせてくる炭治郎に、善逸は何も言わずに頷く。どうしよう、めちゃくちゃ顔が熱い。突然に来た熱に善逸は焦るばかりだ。炭治郎はなんの意識もなく、出来たばかりの新しい友達との交流を楽しんでいるだけなのに、善逸はそこに穿った見方をしてしまう。
「善逸?」
「……なんでもない! 炭治郎、これ、ありがとうな」
そう言って無理くり笑顔を見せれば、炭治郎はグッと何かを耐えるような顔をした。それに善逸はごくりと喉を鳴らす。まただ。また炭治郎から欲を見出してしまう。善逸はこれは良くないと思うけれど、期待してしまうのだ。
そうだ。期待だ。自分は期待をしている。記憶がなくとも、この時代の炭治郎が自分を好きになってくれるのではないかと期待をしているのだ。
善逸が好きなのは前世の竈門炭治郎だ。けれどこうして目の前にそっくりな人がいると、ついつい目移りしてしまう。だって顔だけでなく、家族構成と性格まで似てるって中々ないだろう。だからつい、好きになって欲しいと思ってしまうのもおかしくないのではないか、なんて考えて気持ちを期待してしまう。
善逸はそんな浅ましい気持ちに苦しくなった。純粋な友人になりたくて距離を縮めたのにそんなと、Tシャツの裾をぐしゃりと掴んで助けてくれと願うように炭治郎を見た。
(助けて、助けてくれよ炭治郎。俺、苦しくて堪らないんだ。中途半端なのは嫌なんだ。炭治郎が手に入らないなら、こっぴどく俺なんかあり得ないって教えてくれよ)
****
炭治郎は善逸に気持ちを伝えるのは、今この時の他にないと思った。判断の遅い自分であるが、この時ばかりは「今しかないっ!!」とはっきりと判断した。炭治郎には告白に最適な場所とか、告白に最適なムードとかは分からない。経験もないし、そもそも善逸に今日告白しようなんて露とも思っていなかったし、自分の想いを伝えたいとはっきり意識したのもこの時だった。
だって男同士だ。そういう人達もいることは分かっているが、炭治郎は今まで男がいいと思ったことはないので、漠然といつか女性と結婚すると考えていた。けれど善逸と出会ってその考えが少しずつ変わった。今の炭治郎は善逸にしか目が行かない。他の人がいいと思えない。好きだなと思えない。
けれど炭治郎がそう思っていても善逸は違うかもしれないし、むしろ違う可能性の方が高い。男女だって縁が結ばれ、恋に落ちる確率はとても低い筈なのだ。それなのに自分達はさらに同性で、しかも仲良くなったばかりとなれば炭治郎の中に告白なんて選択肢はなかった。いずれは、ゆくゆくは、もしかしたら。アプローチはしていきたいけれど、告白はまだだと意識の外であった。
しかし今は違う。今の炭治郎は善逸に告白するという意思しかない。炭治郎はがしっと善逸の腕を掴んだ。なにを考えているかは分からないが、善逸からとても甘い匂いがする。炭治郎に縋り付くような、求めるような甘い匂いだ。それを嗅ぐと炭治郎はいてもたってもいられない。
「善逸っ!!」
「んおっ!?」
「好きだっ!!」
炭治郎は善逸の肩を掴んだまま、顔を近づけてそう言った。周りに居た家族連れがびっくりした様子で、そそくさと去っていくのが視界の端に映るがそれはいい。今はそれどころではない。善逸は炭治郎の言葉に驚いたのか、目を丸くして、そして直ぐにじわっと目を潤ませて顔を赤らめた。これに炭治郎は、正確に意味が伝わった、つまりは善逸にとって自分は、そういう意味で意識される範囲にいると確信した。友達に好きだと言われて、すぐに愛の告白だと思ってもらえるくらいには意識してもらえている。
「一年前に家のパン屋に通い始めた頃から好きだっ! 一目惚れなんだっ!」
「えっ!? 一目惚れ!? 俺に!?」
「そうだ!! ずっと好きで、話しかけたかった! でも勇気がでなくて……」
「こここここんな場所で告白してきて勇気がでないとか嘘すぎだろ!?」
「ごめん。でも今言いたくて。今しかないと思って……」
「うぐぐぐっ…! ひ、卑怯だぞその顔…!!」
善逸の呻きに炭治郎は首を傾げた。善逸は真っ赤になって顔を逸らしていて、炭治郎はこっちを見て欲しいなと思い、ひょいと顔を覗き込む。すると善逸は困った顔で目を潤ませていて、それが本当に『美味しそう』で炭治郎も困った。
「ちょ、ちょっとおおお! そういう顔やめろっ!!」
「えっ!? どういう顔だ!?」
「それだよそれ!! 俺のことめちゃくちゃ欲しいみたいな顔やめろっ!! 居た堪れない!!」
「そんな顔してるか……?」
「してるよっ! やめろっ! 本当に! やめろ!!」
「……嫌なのか……?」
自分が善逸を欲しがったから嫌なのだろうかと、炭治郎は胸がキリキリと痛む。すると善逸は、そんな炭治郎を見て「ううっ…」と唸る。善逸は困っているばかりで、嫌そうな匂いはしていない。それどころか強く香る、誘うような甘い匂いに炭治郎は背を押されて、善逸の肩から手を滑らせると、するりと自分の右手を善逸の左手に絡ませた。
「善逸、嫌か? その、俺は……付き合って欲しい……」
「はっ……」
「好きだから、付き合いたい」
そう言って炭治郎は善逸にさらに顔を寄せた。もう少し顔を寄せればキス出来そうだ。善逸は炭治郎が近づいた分だけ背を反らしたが、炭治郎が寄るので腹同士がピタリとくっつく。その温かな感触に炭治郎は、やはり善逸が欲しい欲しいと思ってしまう。
「善逸……!」
お願いだという意味を込めて名前を呼べば、善逸は一歩足を下げて、空いている右手でスマホを持ったまま顔を隠した。プラリと炭治郎がプレゼントした豚の人形が揺れる。
「わ、分かった。な、ならお試しで付き合おう」
「えっ」
「お互いにちょっと確認しようぜ? やっぱり違ったとかあるかもしれないじゃん? だから……お試しで」
「いいのか?」
「お試しだぞ!? 試してダメなら友達に戻るからなっ!?」
真っ赤な顔でびしりと指を突きつける善逸に、炭治郎はコクコクと頷いた。嬉しさで身体が震える。まさかお試しでもOKを貰えるとは。炭治郎は叫んで飛び上がって走り出したい。そして善逸を抱っこしてくるくると回りたい。喜びを大きく表現したい。
しかしそんなことをしたら大変だ。善逸に呆れられて、やっぱりなしと言われるかもしれない。だから炭治郎はぐっと堪えて一度善逸の手を強く握るのに留めた。
「痛いっ!!」
「ごめん!! 嬉しくて!!」
そう言ってニコニコする炭治郎に、善逸は結局呆れたような顔をした。そして大きく溜息をつく。それすらも可愛らしくて、炭治郎はソワソワとしてしまう。だってお試しとはいえ、付き合っているのだ。つまりここからは善逸と本当にデートだと思った炭治郎であったが——。
「あ、スマホ鳴ってるぞ」
「ん? あ、本当だ。俺だ」
ブーブーというバイブレーションの音に炭治郎は鞄からスマホを出した。そして画面をつけると通知欄に伊之助からメッセージが来ている。それを見て炭治郎はひくりと頰を痙攣らせた。
「……伊之助、もう着いたんだ。練習早く終わったのかな? 迎えに行こうぜ」
「……ああ」
伊之助からのメッセージは『駅着いた。どこだ? 』というものだった。これで善逸と二人きりは終了だ。お付き合いの了承を得てすぐにこれとは遣る瀬ない。炭治郎はしょんぼりしながら、『駅にいてくれ。迎えに行く』と打って伊之助に送る。
しかし炭治郎の手を離して先をいく善逸が、振り返ってほんの少し恥ずかしそうに「早く行こーぜ」というのにやっぱり嬉しくなった。
たぶん恋人
君の言葉ひとつ、動きひとつ、俺に向けてくれる眼差しひとつひとつが全部、特別なんだ。
「そういえば炭治郎ってチェッカー模様好きだよなあ」
「え? そうか?」
「そうだよ。今日もチェッカーのアクセント入ったTシャツじゃん」
善逸の指摘に炭治郎は服を見下ろした。着ているTシャツの袖の淵には確かに緑と黒のチェッカー模様が施されているのが目に入る。
「言われてみればチェッカーを選ぶことが多いかもな」
「緑と黒の組み合わせだよな。靴でも持ってなかった?」
「ある。そういえばペンケースもそうだ」
「なんだよめっちゃ好きじゃんか」
笑った善逸の口元には二人で分け合って食べられるアイスがぶら下がっていて、もう一つは炭治郎の手の中だ。
二人は商店街の外れにあるコンビニの前でほんの少しのデートをしている。伊之助との練習が終わって、二人で帰り道を歩いて、いつもなら商店街に着いたところでお別れなのだが、この日は善逸が「少しだけ寄り道したい」というので炭治郎は頷いたのだ。夕飯の時間にもまだ余裕があり、急げば家はすぐそこだ。善逸が大丈夫ならば炭治郎はできうる限り一緒にいたかった。何しろ付き合ってまだそんなに時間が経っていないのだから、お互いのことをもっと知っていきたい。例えお試しの交際であってもだ。
「……炭治郎って誕生日いつなの?」
「誕生日か? 七月十四日だな」
「へーえ? って近くない? もうあと少しじゃん!」
善逸が驚いたように言うのに、炭治郎は少し恥ずかしく、しかしほんの少し期待して頭を掻いた。誕生日を善逸に祝って欲しい。
「そうなんだ! 来月の十四日で俺は十六になるぞ!」
「知ってるよ。高一だもん。そりゃ十六になるだろ」
「善逸は? 善逸の誕生日はいつなんだ?」
「俺? 俺は……九月の三日だな」
「じゃあ一ヶ月半は同い年だな!」
思わぬ形で善逸の誕生日を知れて、炭治郎は上機嫌で笑った。そんな炭治郎に善逸はほんの少しだけ困った顔で笑ったが、炭治郎は見て見ぬふりをする。
いまは六月で、善逸の誕生日は二ヶ月以上も先だ。善逸はお試しの交際がいつまで続くかどうか考えているのかもしれないが、炭治郎としてはこの先、ずっと別れるつもりはない。別れるかも、なんて考えながら怯えて交際するのは嫌なので、炭治郎は二ヶ月後の善逸の誕生日をしっかり恋人として祝う気満々であった。
「九月三日にお祝いしよう! 善逸はケーキは好きか? 焼いてもいいだろうか?」
「えっ!? 炭治郎ってケーキも焼けるの!? すごいな……。甘いもの好きだからケーキは大好きだぜ」
すっかりと吸い取られてペシャンコになったアイスのボトルを善逸はゴミ箱に捨てた。炭治郎もそれに倣ってゴミ箱に放る。カンカンとゴミ箱の蓋が鳴り、気がつけば辺りはだいぶ暗くなってきていた。まだ夕陽は残っているが、空は群青に近づいている。
「なんのケーキを焼こうかなあ」
「いやその前に炭治郎の誕生日があるだろ?」
呆れたように言う善逸に、炭治郎はふふっと笑った。確かにその通りだ。毎年家族ができうる限りで盛大に祝ってくれるのだが……今年は場合によってはずらしてお祝いかもしれない。誕生日は今年は土曜日でお休みなので、できれば善逸と過ごしたい。
「なあ。なんか欲しいものとかあったりする? 金ないからそんな凄いもの用意できないけど」
「ううん……」
欲しいもの、と言われたら答えはひとつだ。善逸が欲しい。しかしこれを言ったら善逸は困るだろう。だから炭治郎はその言葉を飲み込んで、もう少し貰えそうなものを頼むことにした。
「ええと……その……誕生日にデートしてほしい」
「え? いいけど?」
「いいのか!?」
「いいよ? え? まさかそれが誕生日に欲しいもの!?」
驚いた善逸に炭治郎はコクコクと頷いた。善逸は「嘘だろー!?」と言って信じられないという顔で、しかし炭治郎からしたら今はこれ以上に欲しいものはない。善逸を一日中独占するように過ごせたら最高だ。
「物欲ないのかよ!? 他にほしいものは!? それじゃプレゼントにならんでしょーが!」
「いや十分だぞ?」
「はあー!? 何言ってんのお前!? 恋人の時間がプレゼントなら、炭治郎は俺の誕生日に作ったケーキだけ渡して帰るのか!? プレゼントは渡したからって、俺と一緒に過ごさないのか!?」
「そんなことしないぞ!! 善逸と一緒に過ごすに決まってるだろ!?」
「ほらみろ! 時間はプレゼントじゃないだろ!? 恋人同士なら誕生日は一緒に過ごして祝うもんだろ!? 好きな人の誕生日は一緒に過ごして祝いたいもんだろ!?」
その力説に、炭治郎はなるほどと頷いたが、善逸の言葉の中に『好きな人』というものがあってカッと頬が赤らむ。夕焼けに照らされているから分かりにくいが、炭治郎の顔は耳まで真っ赤だった。
「……どうした? 顔赤いぞ?」
「いや、だって……善逸が好きな人って言うから……」
「は? ……あっ……!」
炭治郎の指摘に善逸は愕然とした顔をし、そして一気に赤くなる。じわりと潤む瞳に夕日の色が移った気がした。
「違う!! いや、違わないけど!」
「え!?」
「違う違う!! 違うんだよ!! その、まだ友達以上恋人未満っていうかさあ!? お試しで恋人だけど、まだ本決まりじゃないじゃん!? でも……その、うおおお!! 炭治郎が変なこと言うから空気がおかしくなったじゃねえかあああ!!」
「痛い痛い! 頭を噛むな!」
二人でわあわあと騒いでいると、道ゆく人がなんの騒ぎだろうかと振り返って通り過ぎていく。それに気がついた二人は慌ててその場を離れた。打ち合わせたわけでもないのに、人混みになっている商店街を避けて住宅街に入り、遠まわりしてくれる善逸に炭治郎は嬉しくなって頬が緩む。
「はーあ。それで? プレゼントどうすんのよ?」
「ああ、うん。善逸から貰えるなら何でもいいかな」
「それ一番困るやつだぞ!! よく覚えとけ!!」
善逸は炭治郎にそう言いながらもスマホを取り出し『男子高校生 プレゼント』というキーワードで検索を始めた。真面目に考えてくれるんだなあ、なんて炭治郎はその様子を見ながら胸の真ん中あたりが温かくなる。
「何がいいかなあ。……あ! ところで誕生日の日は休みじゃん? どっか行くか?」
「いいな! ……そういえば善逸はインターハイの練習、大丈夫なのか?」
「平気」
「そ、そうなのか? 俺のせいで負けたりしたら……」
善逸は八月にインターハイの試合を控えている。そしてインターハイ二連覇が懸かっているのだ。恋人の誕生日だからって、練習時間を減らしてもいいのだろうかと炭治郎は考えてしまう。だが善逸は気にした風もなく「え? 平気だって。俺負けないよ」と呆気らかんとして言った。
その自信がある姿は人によっては驕りだと言うかもしれないが、炭治郎は実際に善逸の竹刀を振るう姿を毎日のように見ている。炭治郎は素人であるが、善逸の強さは本物だと確信していた。だから善逸が大丈夫というのなら大丈夫なのだろうと、素直に一緒に時間を過ごすことを受け入れる。
「それならいいんだが……。ああ、インターハイの決勝を応援しに行きたかった」
「仕方ないだろ。今回は開催地が県外で近隣じゃないし。それで誕生日はどこ行く? 行きたい場所とかある?」
「うーん……」
「折角なら少し遠出してみる? レジャー系もよくない? 雨が心配だけど……」
「なるほど! いいな! 遠出かあ!」
遠出なんて滅多にしない。というよりも、母方の実家に帰る時くらいしか遠出はない。何しろ竈門家は子供が多いのだ。全員で出掛けるだけで金が掛かる。だから炭治郎が最後に遠出をしたのは、お彼岸の墓参りに母の田舎に戻った時以来だ。それも遊びではないのだから、純粋に遊びとなると……ちょっと記憶にない。
「行きたい! どこにしようか?」
「炭治郎が決めていいぜ。雑誌に色々と紹介されてるよ」
「レジャー系の雑誌か? 探してみるよ」
炭治郎はふふふっと笑う。善逸からは穏やかな、柔らかい匂いがしていて、炭治郎は受け入れられていると漠然と思った。思わぬ告白であったし、まさかお試しといえど交際をしてもらえるとは思っていなかった。善逸も動転して、気の迷いで……なんてことだったのではと、デートから帰った日に炭治郎は浮かれていた気持ちが萎んで不安になったが、それから今までで、善逸から炭治郎を厭う匂いは全くなかった。男同士だからと嫌がられることもなく、善逸は自分とのことを前向きに考えてくれている。
(善逸は優しいなあ。好きだ。本当の恋人になりたい)
炭治郎は誰かをこんなに好きだと思うのは初めてだ。だから自分がどうしたいとか、善逸とどうなっていきたいとかはまだ曖昧で、今一番望むことは自分と善逸の双方がお互いを恋人と思い、気持ちを交わし合うことだった。そこが始まらなければ炭治郎は未来をうまく想像できない。
そりゃあずっと死ぬまで善逸と共に過ごしたいが、具体的な算段は何もない、子供っぽい理想だ。だから炭治郎はまずは善逸と好き合って、お互いに気持ちや考えをすり合わせながら隣を歩いていきたいと思っている。
(ああ、でも……手ぐらいは繋ぎたいかなあ)
そう思って炭治郎は、隣を歩く善逸のプラプラと揺れる手を見つめた。流石に商店街で手を繋いで歩くのは気恥ずかしいが、暗くなりつつある路地ならば人もいないしいいのではと思ってしまう。
(お試しといえど俺達は恋人だ! それに恋人らしいこともしないでいたら、やっぱり違うなんてことになりかねない! 善逸に友達のままでいいじゃないかとか言われたくない!)
炭治郎はそう決意すると、勇気を出して——善逸に許可を取ることにした。
「善逸!」
「んお!? なに!? 大声で呼ぶなよ! 隣にいるから普通の声で聞こえるわ! 心臓がまろびでるだろ!?」
「まろびでる?」
「……転がり出るの古い言い方だよ」
「そうなのか。知らなかった」
「……んで、何よ?」
古い言葉を知っている善逸に感心していた炭治郎だが、善逸に先を促されて当初の目的を思い出した。そうだったと立ち止まり、善逸に向き合う。しかし改まると恥ずかしいな、なんて炭治郎はほんの少しだけ俯いた。
「どした?」
「あ、いや、その……手を繋ぎたいなって……」
何とも男らしくない声量に炭治郎はますます恥ずかしくなった。しかし善逸の耳にはキチンと届いたのか、善逸は炭治郎の顔を見つめて口をもごりと動かすと、ゆっくり手を差し出してくる。
「ほ、ほらよ。……これでいいの……?」
「あ、ああ! ありがとう善逸!!」
炭治郎は善逸の手に触れようとして、ハッと気がついて手の平をズボンで拭う。それから善逸の手のひらを握り込み、手を繋ぐという願いを叶えた。善逸と繋がった自分の手のひらに、当たり前だが善逸の体温が伝わってくる。その体温は炭治郎よりも温かいかもしれないというくらいで、少し意外だった。
「善逸は体温が高いな」
「そーお?」
「ああ。俺とそう変わらないかもしれない」
「ふうん。……それにしても炭治郎」
「ん?」
「手を拭ってから繋いだのに、もう汗ばんでるのな」
「えっ!?」
善逸の指摘に、確かに炭治郎の手のひらは既に汗ばんでいた。元々体温が高く、代謝もいいので炭治郎は汗っかきである。善逸と繋いでいない反対の手が汗ばんでいるので、間違いなく自分の手汗だと炭治郎は慌てた。
「ご、ごめん! 気持ち悪いか?」
「いや別に? 面白かっただけだよ」
ハハっと笑った善逸は、ぶらんぶらんと繋がった腕を振る。ギュウッと握り込まれる強さに、炭治郎は心臓も握り込まれたと思った。心臓というか、心であるが。
「流石にそろそろ帰らないとなあ」
「……もう少しだけ歩きたい……」
「そーお? んじゃ、もう二つ向こうの角で曲がろうか」
「うん……」
炭治郎も善逸の手を握り返す。汗ばんだ自分の手のひらが恥ずかしいが、善逸が本当に嫌がっていないのは匂いで分かる。ほんのりと恥ずかしがるような、でも喜んでいる匂いがしていて、炭治郎も嬉しくなる。
(これ俺の匂いじゃないよな? 善逸からしてるよな?)
炭治郎はすっかり暗くなった夜道を善逸と共に歩いた。本当ならこのまま善逸の家まで送り届けたいけれど、腕っ節は善逸の方が確実に強いので意味がない。きっと逆に善逸に心配されてしまうだろう。だから炭治郎は素直に二つ向こうの角で曲がった。このまま先を歩いて、さらに角で曲がり、商店街のほうに続く道に戻るのだ。
「……善逸、後で眠る前に電話をしてもいいだろうか?」
「いいよ。でも炭治郎は明日も早いんだから、夜更かしはダメだからな」
「分かってる。少し声を聞けるだけでいいんだ」
「はいはい。じゃあ炭治郎の都合の良い時に掛けてこいよ。俺はいつでもいいからさあ」
善逸の寛容な言葉に炭治郎は心が弾む。許されることが嬉しい。もっともっと許してほしいと、そのまま全てを許してほしいと炭治郎はぼんやりとした善逸との未来を思い描いた。
手が早い男
結局俺は、現金なんだよ。
今生の炭治郎に好きと言われた時、俺は嬉しかっただろうか。善逸はそう思いながら家からの道を走り抜け、今日も竈門ベーカリーへと向かう。伊之助の練習に付き合うようになってから善逸は、平日の朝は六時半に竈門ベーカリーに行く。善逸に負担をかけて悪いからと、炭治郎は善逸にお礼と言ってパンをくれるのだ。
なぜ伊之助の練習に付き合うと炭治郎からお礼のパンが貰えるのか最初、善逸は不思議であった。今生でも世話焼きなのかなと思っていれば、何のことはない。あれは要するに炭治郎の下心だったのだ。
(炭治郎って胃袋から掴んでいくタイプだったんだな。そういや、俺も最終選別以来で炭治郎と再会した時におにぎり貰ったなあ。あれ、凄い美味しかったんだよなあ)
善逸は商店街に入ると腕時計を確認した。少し来るのが早かった。六時半に到着が常なのに、今日は五分ばかり早い。六時半でも早いんじゃないかと仕事をしている炭治郎を見て心配になるのに、更に早いのは迷惑じゃないかと善逸はほんの少し考える。
しかし脳裏にはいつもより早く現れた善逸にパッと嬉しそうにする炭治郎の表情が浮かんで、「まあいいか」と善逸は竈門ベーカリーのショーウィンドウを覗き込んだ。するとコックコートを着た炭治郎が緩く口元に笑みを浮かべながら、パンを並べている。その姿を見て善逸は、なんだか楽しい気持ちになった。
(炭治郎が仕事してる。いやいつも見てんだけどさあ、店の外から見るのもなんか雰囲気変わっていいなあ)
そんな風にニヤニヤしながら、せっせとパンを並べる炭治郎を善逸は見た。まだ高校生なのに、しかも一年生なのにこんな風に毎日働いていて偉いなあとか、凄いなあとか、さすが炭治郎だなあ、なんて善逸はニヤニヤしてしまう。仕方がないのだ。前世の記憶がないとしても、今の炭治郎だって善逸は好きなのだ。そもそも炭治郎というだけで善逸の中では好印象だ。
善逸が覗きのように炭治郎の仕事ぶりを外から見ていると、ショーウィンドウの前にある棚にパンを置く為か、振り返った炭治郎が善逸の存在に気がついた。炭治郎の口が「ぜんいつ」と動くのを見て、善逸は笑って店の扉に向かう。そして中に入れば、炭治郎はほんの少しばかり顔が赤かった。
「おはよー炭治郎」
「おはよう善逸……いつからそこに居たんだ?」
座りが悪そうに言う炭治郎に善逸はにやーっと笑ってしまう。「ウィッヒヒ」と口元を押さえて笑う善逸に炭治郎はすんっと真顔になった。
「もー! なんだよその顔ー!」
「ごめんごめん、善逸が笑うから、仕返ししてやろうと思って」
「ちょっと外から見てただけだろ。外も内もあんまり変わらないじゃん」
「善逸はそうでも、知らないで見られてるのはなんか恥ずかしいぞ」
ゴニョゴニョ言う炭治郎に善逸はそういうものかと首を傾げる。善逸からすれば、知らないうちに勝手に見られているほうが意識の外で気にならないと思うのだが。
「お邪魔しまーす」
「うん。座って待っててくれ!」
炭治郎はそう言うと、従業員用のアイスティーを出してくれた。最初に出された時、善逸はこんなの貰っていいのかなと思ったのだが、炭治郎は顔を赤らめながら「恋人だから」とはにかんで言った。
その笑顔に「嘘だろ炭治郎可愛くない?」と善逸はぶっ倒れかけた。いや、前世でも炭治郎は可愛い時もあったが、鬼の首魁を倒した男だ。色々と覚悟も鍛え方も違う。それに善逸にとっては炭治郎がニコニコしているのは普通だったのだ。たまーに炭治郎がお姉様方に「可愛い」と言われているのを聞くと「そんなものか」と思ったものだが、当の本人は「可愛い」と言われるのは、竈門家の長男として好きではなかったようなので善逸は特に意識もしなかった。むしろ炭治郎と二人きりになれば善逸の方が「可愛らしいなあ」と言われていたので、炭治郎が可愛いというのは善逸の中では薄い概念であったのだ。
しかし今は違う。はにかみながらも善逸を恋人だと言ってくる炭治郎に可愛らしさを感じてしまう。まさか自分が男相手に「か、可愛いっ!」と思う日が来ようとはと善逸自身も思うけれど、瞬間的に思ってしまうことに対してはコントロールができないし、そもそもする必要もない。
「……炭治郎は可愛いなあ」
「なっ! か、可愛くないっ!」
「いやいや、ムキになるところがまた可愛いよ」
善逸はありがたくアイスティーを飲みながら、ほら働けと言うように手を払って炭治郎を追いやる。炭治郎は不服そうにしながら、パンをまた棚に並べていく。善逸はそんな炭治郎を見ながら、本当に可愛いなぁということばかりが頭の中に巡っていた。
炭治郎に好きだと言われた時は、嬉しかったかよく分からない善逸だったが、二週間も経った今は慣れてしまい、さらにはだんだんと浮かれてきている。まさかまた炭治郎と恋仲になれるとは思わなかった。今は善逸が混乱して提案したお試しの交際期間であるが、それでも恋仲だ。
(炭治郎と恋仲……)
善逸はくるくると働く炭治郎を見て、幸せを感じる。善逸は炭治郎に記憶がない時にこれは未亡人ルートだと覚悟していたのだが、まさかまさかの炭治郎が善逸を好きだと言うのだ。炭治郎が好きだと言うのなら、嬉しそうに善逸が欲しいと笑うのなら、自分も炭治郎を貰ってもいいのではないだろうかと善逸は思ってしまう。
「……善逸、その、あんまりジロジロ見ないでくれ。緊張してトングが震える……」
「あ、ごめんな? 邪魔するつもりはなかったのよ」
仕事の邪魔になるなら、ジロジロ見るのは良くないかと善逸は残念な気持ちになったが、我慢しようと炭治郎から視線を逸らす。すると炭治郎は慌てたように振り返った。
「違う! 邪魔じゃない! ただその、恋人に見られてるのが……照れるというか……」
カチカチと行儀悪くトングを鳴らす炭治郎に、慌てているなと善逸は笑った。それにしても恋人が見ていると照れてしまうなんて、年相応で可愛らしい。善逸はすっかり可愛くなってしまった炭治郎に違和感はあれど、嫌な気持ちはしない。
そもそも仕方がないのだ。今世の炭治郎に前世の記憶はなく、善逸にはある。そうなれば人生の経験値で差が出てしまう。善逸はそう思いながら、可愛らしい、お試しの恋人をニコニコしながら眺めた。すると炭治郎はギッと照れたように善逸を睨んでくる。その様子すらも可愛いなあなんて善逸がデレデレしていたら、炭治郎は本当に困ったように言った。
「善逸! その匂いをどうにかしてくれ! 恥ずかしくて堪らなくなるっ!」
「えっ」
匂い? 匂いをどうにかしてくれってどういうことだ? 善逸は急に冷や水を浴びたように冷静になった。炭治郎から放たれた言葉に善逸はぶるりと震える。匂い、匂い、炭治郎は匂いと言ったのか。
「善逸……? あ! 違うぞ! 臭いとかそういうことじゃない! ごめん、言ってなかったから驚いたよな! 俺はその、すごく鼻が利くんだ」
(知ってるよ。そんなの知ってるよ。でも今のお前もそうだとは思わなかった)
「その……俺の鼻は物の匂いを辿れたり……それこそ人の感情の機微とかも何となく分かるんだ。他に嘘が分かったりとか……ええと、あまり人に言ってこなかったから、善逸に伝えるのを忘れてて……」
どんどん焦った様子になる炭治郎を見ながら、善逸はいま、自分はどんな感情なのだろうかと他人事のように思った。鼻がよく利く話になってから、炭治郎は見る見るうちに焦っていく。
それは自分から漏れ出る感情の匂いが酷いからではないかと善逸は思った。いや、実際に善逸の心の中は暴風雨の最中のように荒れていた。まさかの事実に自分でも想像できなかったくらいに心が散り散りになるように荒れていた。
「善逸、善逸、その……気持ち悪いか……?」
恐る恐るというように言った炭治郎に善逸は涙がでる。なんの涙だろうか。善逸にはよく分からなかった。ただ、前世であんなに耳が良くて気持ちが悪いと爪弾きにあっていた善逸が、炭治郎に「気持ちが悪いか?」なんて言わせてしまったというショックはあった。
「気持ち悪くないよ。大事な炭治郎の個性じゃないか」
善逸はするりと言葉を吐いたが、前半に嘘はないが後半には自信がなかった。大事な個性であるのは間違いないが、それを善逸が歓迎しているかと言われれれば話は別だ。善逸はずっと炭治郎も鼻の良さはないと勘違いしていた。自分も耳の良さを失っていたから、てっきり炭治郎もそうなのだと善逸は決め付けていたのだ。
「そうか……?」
そう言って少しホッとした様子を見せる炭治郎だったが、善逸はその表情の真偽を図りかねていた。今更ながら恐ろしい。なんてことだ。善逸は自分の耳の良さを失った為に炭治郎の機微が全く分からない。顔色や声の感じで伺うしかない。心音や筋肉の音で感じ取ることはできないのだ。しかし炭治郎は鼻が利くという。その鼻の力を以ってして、善逸の心情を詳らかにしてしまうというのだ。
(……ヤバイ。なんか、ヤバイ……かも……)
善逸は突然にゾッとした。足元から恐怖が這い上がってくる気がした。そして炭治郎の鼻が利くということを知って、追加で気がついたことがある。
(伊之助……あー……あいつも触覚が鋭敏なのか? ちゃんと服着てるから、てっきりないもんだと……いや、シャツの前全開だったわ。あーくそっ! だから俺が他と違うって分かったのか!)
善逸はアイスティーを飲み干しながらグルグルと考え込む。目の前で炭治郎が善逸を気にしているのだが、善逸はそれどころではなかった。何となく、今まで炭治郎と伊之助と共にいて、意識の外に追いやれていた前世の記憶という厄介さがまた忍び寄って来たのだ。
(待って? 待って!? 炭治郎の鼻がいいなら、もしかして初めて店に入った時からやべーこと考えてるの知られてたんじゃないか!? 炭治郎、一目惚れって言ってたじゃねーか!! なんか、俺、知らず知らずのうちに炭治郎に影響与えてたんじゃないか!?)
善逸はひとつだけ自信を持っていることがある。それは自分の身体から発せられる匂いが、どうやら炭治郎にとっては大変好みであるという点だ。
前世では、恋仲になる前から何かにつけてひっついて来ていた炭治郎だ。特に鬼の悪臭が酷かった任務の後は、ヨロヨロと善逸の元に来ては首元に鼻を突っ込んでいた。善逸も炭治郎の音が大変好きだったので、そういう事もあるよなあと、誰か女の子の匂いがドンピシャの好みであれば……と考えては、女の子の首元に鼻を突っ込む炭治郎は事案過ぎる。俺が男で良かった等と頷いたものだった。
正直言って、前世の善逸と炭治郎もお互いの鼻と耳ありきで好きあったところがあったのではと善逸は思っている。意外なことに善逸よりも炭治郎の方がロマンチストであったので「そんなことはない! 鼻がなくても俺は善逸を好きになった!!」と言いそうであったが、そもそもその仮定では炭治郎は善逸に会う前にどっかでおっ死んでいる可能性が高いので意味がないものだ。
とにかく前世ではその鼻と耳で二人は結ばれたも同然だった。しかしこれも善逸はしょうがないことだと思っている。他の人から見れば「鼻と耳のおかげでしょ」と優れた部分を羨むように笑われたかもしれないが、本当にしょうがないのだ。
だって生まれた時から鼻の良さと耳の良さがあって、切っても切り離せない。炭治郎と善逸はこれを前提に生きて来ているのだ。ならばそれに引っ張られて人を好んでも仕方がないだろうと善逸は割り切っていた。それくらい炭治郎の音は優しく素晴らしいのだ。炭治郎や禰豆子に聞かせてやれないのが寂しいくらいだった。
つまり善逸がそうなのだから、きっと炭治郎もそうだった。炭治郎も善逸の匂いがもの凄く自分好みでなければ、善逸に気持ちなど向けなかったかもしれない。言えば否定されるから口にはしなくなったが、善逸は生まれ変わった今でも思っているし、しかし愛された自覚はたんまりとあるので、炭治郎が好む匂いを発する自分で良かったと思っている。しかし、それは全て前世の話だ。今世もそれを持ち越しているとは善逸は思っていなかった。
(嘘だろ。嘘だろ。もしかしてあれか? 俺って今も炭治郎にとってはいい匂いなのか? やべえだろ。俺、もしかして間違えたのか?)
善逸は炭治郎を見つけて前世の記憶がないと分かった時、思い出す必要はないと思っていた。前世で恋人同士であったからといって、今世もそうあるべき筈はない。何しろ前世では炭治郎は鬼によって家族を失い、妹を鬼にされるという悲しみの末に善逸と出会ったのだ。何もなく、真っ当に暮らしていれば炭治郎は善逸になんて出会わなかった。
あの時代に運命の赤い糸なんて言葉はそれほど浸透してはいなかったが、今思い返してみても、炭治郎と自分は運命の恋人ではないのは確かだと善逸は思っている。炭治郎の家族が死んだ末に成立する運命なんて善逸は嫌だ。吐き気さえする。
前世での炭治郎と善逸はしょうがなく纏まった。お互いに欲しがって気持ちと身体を重ねたが、鬼殺隊という余裕がない場所だったからだ。平和な場所で、命の保証があったなら、あんな関係になっていないと善逸は思っている。炭治郎の隣には可愛らしい女の子が似合う。しかし女の子と真剣に向き合う時間は鬼殺隊にはなく、いつ死ぬかも分からない。おいそれと女の子に手を出すものではなかった。
ならば鬼の首魁を倒した後、平和になってからすればいいなんて話もまた夢物語だ。炭治郎は鬼舞辻無惨との決戦で片手と片目の機能を失い、さらには寿命までも大きく縮めた。善逸も右足は少し不具合が残った。要するにいくら鬼を倒した英雄とて、誰か素敵な人と未来を歩むには満身創痍過ぎたのだ。誰が十年後に死ぬような人と結婚するのか。いや、探せば居たのかもしれないが、炭治郎は愛した人を、そんな早々に未亡人にするくらいなら未婚でいいと言うだろう。
結局、炭治郎は善逸を選んだ。「死ぬまで隣にいてくれ」と言って、善逸の手を引いて雲取山に禰豆子と伊之助と四人で帰った。善逸もまた炭治郎の短い時を得る為に文句なんて何もなかった。自分の心の真ん中に座り込んだのだから、その十年。一生を懸けて償って欲しいと善逸は思っていた。その十年の時間を心に抱いて、残りの三十年、四十年を生きるからと思っていた。
さてそんな覚悟を前世ではしたのだが、今世はやっぱり別なのだ。何しろ炭治郎には家族がいて、痣はなく、寿命はたっぷりだ。だったら今度こそ運命という人と出会い、恋をして、結婚して、子供を作って欲しい。今度こそ禰豆子の系譜の竈門家でなく、竈門家の長男である炭治郎系譜の子孫を残してほしい……と出会った当初は思っていた善逸だが、炭治郎が改めて最初から自分がいいと言うのなら、しょうがないかなあと善逸は思っていたのだ。今世は同性愛も、昔よりは多少は寛容だ。そう思って炭治郎の気持ちに向き合いつつあったのに——。
(話が違う! 話が違う! 鼻が利くなら話が違うっ!! 匂いなんてなしで俺を好きになったなら自由恋愛のご時世だ。しょうがねぇって思うけど、鼻がいいならダメじゃねぇか!! 俺は炭治郎の好きな匂いなんだぞ!?)
今も昔も善逸には自分の匂いは分からない。しかし炭治郎の鼻が利いて、さらには一目惚れということは、もはやそれは匂いに釣られたのだと善逸は確信した。
(やっぱり炭治郎に記憶がないって分かった時点で距離を置くべきだったんだ。そうしたら炭治郎は、俺の匂いに血迷うことなんてなかったのに。何を常連になってんだよ!! そもそも俺は自分の恋心をなくして欲しくて、炭治郎に彼女できるのを見たくて通ってたのに、何で俺が彼氏してんだよ!! おかしいだろ!! 本末転倒だわ!! 炭治郎と伊之助と仲良くなれたからって浮かれ過ぎだろ!? 本来の目的をすっかり忘れてんじゃねえか!!)
善逸はスツールに座りながら、店のカウンターに突っ伏した。善逸は快楽に弱い自分を恨む。ついつい楽な方に流されてしまうのは本当に悪い癖だ。炭治郎が彼女を作るのを見て、やっぱり自分の気持ちは持っててもダメなのだと一方的に振ってもらう作戦だったのに、見事に炭治郎を射止めてしまっている。
(炭治郎の人生をねじ曲げちまった!! 俺が! 俺が炭治郎に近づいたばっかりに! 俺の匂いが炭治郎のドンピシャ好みなばっかりに!!)
今の炭治郎に確認したわけではないが、善逸は自信満々だった。何しろ前世であんなに嗅ぎ回られたのだ。恋仲になった後などは鍛錬後に「ちょっと水浴びする前に嗅ぎたい」とか真顔で言われ、木陰に連れて行かれたと思えば、それこそ犬のように嗅ぎ回られた記憶が善逸にはしっかりある。
いい匂いだと蕩けた顔で言ってくる炭治郎に善逸は恥ずかしかったけれど、満更でもなかった。本当に炭治郎の音には嘘はなく、むしろ汗臭いはずの自分の匂いに欲情すら覚えているのに、善逸は興奮してしまったのだから。
(あっ! やべっ! エロいこと思い出しちゃった……)
善逸がカウンターに突っ伏していた顔をそろりと上げると、炭治郎は変わらずに困った顔をしていた。その様子に善逸は「あれ?」っと思う。前世の炭治郎は善逸が少しでもエッチなことを考えたり思い出したりすると、「昼間からそういうのはやめろ!」と叱ってくるか、時間があれば人目を憚って二人であちこち触り合ったものなのだが——。
「善逸? 大丈夫か?」
「大丈夫」
善逸はすんっと冷静になった。そして炭治郎が心配そうな表情で見つめてくるのに、申し訳ない気持ちになる。そしてとうとう、居た堪れなくて善逸は立ち上がった。
「善逸? どうした?」
「宿題のプリント、学校に忘れてたの思い出した。ちょっと今日はもう行くわ」
さらりと口に出した言葉に炭治郎は「そうか」と頷いた。それに善逸は嘘だと指摘しないのかとぼんやり思う。宿題のプリントなんてない。鼻が利くなら善逸の嘘を見抜いただろうに。なぜ嘘をつくと指摘をしてこない炭治郎に、善逸は勝手にショックを受けた。
「じゃあ炭治郎、また放課後にな」
「ああ、うん」
善逸はそう言って炭治郎の顔をロクに見ずに店を出た。早朝で人が少ないのをいいことに、結構なスピードで学校への道のりを走っていく。善逸はぐらぐらと揺れる頭で炭治郎の事を考えた。しかし考えれば考えるほど分からない。
(俺いま…どっちの炭治郎のこと頭に浮かべてる?)
善逸は脳裏に浮かぶ炭治郎がぐちゃりと混ざっているのに気がついた。あの優しい笑顔は浮かぶのに、服装が分からない。痣の濃さが分からない。前世の炭治郎は痣が濃く広がっていたが、今世の炭治郎は痣が薄い。やっぱり火傷の痕らしいが、思い浮かべている炭治郎は笑顔だけがはっきりしていて痣の辺りはぼんやりだ。
(やばい。前世の炭治郎がうまく思い出せない。今世と混ざってきてる)
善逸はそれにゾッとする。しかし何故ゾッとするのかと言われたらはっきり言えない。はっきりさせると今世の炭治郎が可哀想だ。しかしそう思うこと自体が、善逸の心がどちらにあるのかを証明してしまっているようで申し訳ない。だけれど善逸には前世の記憶があるのだ。前世の炭治郎に愛された記憶が。それはどう頑張っても善逸は消せない。自分では消すことができない。
(どうしよう。どうしよう。どうしよう)
善逸の目にじわりと涙が浮かんでくる。そして炭治郎の優しい音が聞きたいと強く思ったが、残念ながらそんな素晴らしい耳は今世の善逸には備わっていない。そんなことはよく知っていた筈なのに、なくてよかったと思っていたのに、炭治郎の鼻が利くと知れたら耳がよくないのが善逸は悔しくなった。
(俺はもう、一生炭治郎のあの音が聞けないのか……)
側にいるのになんて辛いんだと、善逸は走っていた足を止めて俯いた。ポツリと涙が溢れて地面に染みを作る。そしてそれを追うようにポツポツと降り始めた明けきらない梅雨の雨が善逸の身体を濡らしていった。
****
(善逸の様子が変だ)
炭治郎はそう考えながら、友達に借りた近郊のレジャー特集が載った雑誌を捲っていた。雑誌には『夏にぴったりのおすすめアクティビティ! 家族や恋人と思いっきり楽しもう!』と銘打たれたページがあり、炭治郎はそれをぼんやり眺める。なぜ見ているのかといえば、善逸とのデートの為だ。
もう七月に入って期末テストも終わり、もう直ぐ炭治郎の誕生日だ。善逸と少し遠出して遊びに行こうと言っていたのでこうして目星い場所を探しているのだが、高校生の日帰りデートとしては遠すぎるかもしれないと、炭治郎は少し目を通した程度で次に行く。川下りやバンジージャンプなんて、できる場所まで行くだけで時間を使ってしまう。
(プールもまだ始まってないしなあ。どうするかな)
善逸に行きたいところを考えておいてくれとテスト前に言われたのだが、実のところ炭治郎は本当に行けるのかと少し不安な気持ちがあった。その理由は、日に日に善逸の様子がおかしくなるからだ。それがいつからかと言えば、炭治郎が自分の鼻のことを善逸に話してからである。
善逸は炭治郎の鼻の良さを聞いて動揺していた。それに炭治郎は思ったよりショックを受けた。なんとなく、善逸なら軽く受け入れてくれると思っていたからだ。そういう深い優しさがある匂いがしていたから。
(やっぱり、考えてる事が分かってしまうって、気持ち悪いのか?)
炭治郎は自分の鼻を便利だし、嫌ったことはないが、人によっては考えを看破されるのを嫌がるだろう。だから炭治郎もあまり人の考えを言い当てるようなことは小学生くらいからするのを止めた。小学生になって一年目で、人の考えていることにとやかく口を挟むと、だいたい良い結果にならないと炭治郎は学んだからだ。どうやら人は、自分を守る為に取り繕うという行動をするのだと、一学期のうちに数え切れないくらいの学級会や先生に呼び出されることで炭治郎は理解した。誰かが不利益を被りそうだったり、他者を貶めようとする以外は口出ししない。口出ししても、それとなくに留めて上手くやる。
それは炭治郎にとっては大変なことで、若干のストレスが掛かることだが、長年すれば慣れるものだ。善逸にも正直に言うか悩んでいたが、あまりに善逸から自分に向けられる甘やかな匂いに我慢ならなくて口を滑らせてしまったのが運の尽き……かもしれないと炭治郎は雑誌を閉じて溜息を吐いた。
(善逸に嫌われたかもしれない……!)
炭治郎はがくりと机の上に寝そべった。テストが明けた放課後の教室は人が少ない。皆んなさっさと帰って遊びに行ってしまったし、炭治郎もこれから遊ぶ予定がある。もちろん相手は善逸だ。善逸もまたテスト明けで、テスト後くらい部活はしたくないと言っていたのでなら遊ぼうという話になったのだ。
炭治郎は相変わらず毎日のように善逸と朝の時間を過ごしていたが、流石にテスト前であったので夕方の練習はこのところなくなっていた。練習中は伊之助も一緒であるから、何か恋人らしいことが起こるわけでもない。だけれど善逸の美しい居合の型を見て、終わってから三人で少し話をして、そして僅かな時間でも善逸と一緒に家路に着くのは炭治郎にとっては掛け替えの無い時間なのだ。最近、ようやく手を繋げるようになってきて、炭治郎は非常に満足していた。
だって一年間、じっと見つめるだけだった人に近づけて、お試しとはいえ恋人になれて、そして恋人として手を繋げているなんて凄いことではないか。炭治郎はゆっくり、じっくり善逸との仲を深めていきたい。
何しろ炭治郎は本気なのだ。本気で善逸とずっと一緒に居たいと思っている。高校生の身空であるが、将来的に善逸に対して責任を負いたいと思っているし、善逸にも責任を負ってもらいたい。自分の一生を背負って欲しい。流石にそれをいま、善逸に面と向かってお願いすることはできないが、いつかお願いできるようにじっくりと善逸とは仲を深めたいのだ。
(やっぱり言うのが早かったか? でもうっかり口を滑らせてしまったからなぁ……)
炭治郎は鼻の良さを善逸に伝えてしまったのを後悔していた。あれから善逸はなるべく平静を装っているようだが、前よりも感情の振れ幅が大きい。仲良くなり、話をしてみれば、善逸は喜怒楽をよく表すが、哀に関してはあまり露わにしなかった。しかし匂いでは哀しみを抱えている時があるのだ。
(いや……違う。善逸の底には悲しみがある。出会った頃から気になってた甘苦い匂いは、悲しみの上に感情が乗っているからだ。善逸はずっと何かに悲しんでいる。……仲良くなってから、楽しそうな匂いが強くなったのに、最近はずっと甘苦い……いや、もっと複雑な匂いだ。俺が嗅いだことない匂い。分からない。善逸は何を考えてるんだろうか?)
炭治郎はブブブと鳴ったタイマーに身体を起こした。そろそろ行かないと善逸との待ち合わせに遅れてしまう。窓の外を見れば、梅雨があけきらぬ空は雲が厚い。そのどんよりとした灰色の雲に炭治郎は鬱々な溜息をついた。
「そろそろ行くか」
そう思って立ち上がった炭治郎が鞄に荷物を詰めたところで、またスマホのバイブレーションが動いたのでおやっと思った。タイマーをスヌーズにしてしまったかと思って消そうと画面を見れば『善逸』という表示がある。それに炭治郎はびっくりするも、すぐに画面をタップして耳にスマホをあてた。
「もしもし!?」
『あ、炭治郎? まだ学校いる?』
「教室にいるぞ。これから行こうと思ってた。善逸も学校を出るところか?」
『いや? 学校に着いたところ』
「学校に着いたところ?」
着いたところとはどういうことか。忘れ物でもして戻ったのかと思った炭治郎だったが、善逸に「窓から校門を見てみろよ」と言われたので通話状態で窓から校門を見た。
「あっ!」
『へへっ。迎えに来ちゃった♡』
炭治郎の視線の先、校門のところには善逸がいた。炭治郎のことは見えていないのか、こちらを向いていないが電話をしているようなポーズをしている。
あの金の髪は善逸しかいないと炭治郎は慌てて鞄を掴むと教室を飛び出した。廊下を走るのは良くないが誰もいないからと飛ぶように駆けて、階段を三段ずつ飛び降り、昇降口の下駄箱に雑に上履きを放り込むと、ローファーに足を突っ込んだ。そして息切れしながら校門の方へさらに急ぐ。
「善逸っ!」
「あ、炭治郎ー。お前、電話切れよ。途中からガサガサ雑音がしてたぞ」
ケタケタと笑う善逸に、炭治郎はそういえばとポケットに手を入れて、構わず放り込んだスマホを取り出す。スマホ画面を見れば通話中で、炭治郎はちょっと急ぎ過ぎたなと通話をオフにした。
「善逸が切ってくれたら良かったのに……」
「いやなんか面白くてさあ」
ニシシっと笑った善逸に、炭治郎は先ほどまで暗かった心が一気に晴れやかになる。わざわざ学校まで来てくれたのが嬉しくて、炭治郎の心はウキウキし始めた。
「来てくれてありがとう。HRが早く終わったのか?」
「そうそう。炭治郎はまだ学校にいるかもなーって思ってさ。待ち合わせ場所よりお前の学校の方が近いし、寄ってみよーと思って」
「……走ってきたのか?」
「んん? まあ、そうね?」
「善逸は本当に汗を掻かないなあ。俺は体温が高いから、結構もう汗だくなのに」
そう言って炭治郎がスンッと鼻を動かしたのに、善逸はスススと後ろに下がった。それに炭治郎はハッとするも、善逸は顔を赤らめて苦い顔をしている。薫ってくる匂いは分かりやすい。これは『恥ずかしい』だと炭治郎は理解し、善逸に『不快感』は微塵もないのにホッとする。
「ごめん」
「いや、いーけど……全く汗かいてないわけじゃないぜ? 流石に臭いだろ?」
「え? 物凄くいい匂いだぞ? 善逸はいい匂いがするんだよなあ。柔軟剤か? 桃の匂いみたいな……丸のままの匂いだけでも甘いのに、齧ると一気に甘さが大きく広がるような感じの……」
すんすんっと鼻を動かしていると、善逸がびくりと身体を揺らした。炭治郎が「またやってしまった!」と慌てて離れれば、善逸は先ほどよりも真っ赤になっていた。涙目で恥ずかしそうに口元を手の甲で隠し、そっぽを向いている。
(え?)
ぶわりと香る匂いの甘さに、炭治郎は目眩を起こしそうになった。ふらりと足を半歩下げて、ごくりと唾液を飲み込む。今の善逸を目の前にしていると炭治郎はとんでもなく喉が乾く。身体中に飢えがある。目の前に大好物のタラの芽を出されて、料理することもなくただ、萎れていくのを見ていろと言われたような耐えがたい辛さがあった。
そっぽを向いていた善逸がちらりと炭治郎を見る。その目はねっとりとした重さがあり、炭治郎は一瞬、心臓が止まったかと思った。どうしたのかと炭治郎が問うよりも早く、善逸は炭治郎の手首を掴む。
「……来て、炭治郎」
「え? あ、善逸っ!」
善逸に手首をぐいっと引っ張られて炭治郎は駆け出した。出したことがないスピードではないが、かなりの速さでドンドンと走っていく。全力でマラソンをしているような状況に炭治郎は目を白黒させたが、前をゆく善逸は一つも汗を掻かずに息も乱れていないようだった。自分はこんなにも息が上がっているのに、インターハイで優勝する人はやっぱり違うなんて思いながら、炭治郎は善逸に腕を引かれるままにひた走った。本当は制止したかったが、前から漂う真剣な匂いが炭治郎の足を突き動かしている。善逸にがっかりされたくないと、食らいつくように走って行った。
****
「着いたよ。俺の部屋に行ってて。水を持ってくる」
「……はあ、はあ、はあ、はあ、わ、わかった……」
先に家に上がり、中に消えていく善逸を見ることもなく炭治郎は言った。単純に全力疾走に疲れていてそれどころではなかったのだ。炭治郎はダラダラと掻く汗を手で拭う。ハンカチを出そうと思うけど、手が震えてうまく出来ない。そう思って先に息を落ち着かせようと玄関先で靴を脱ぎもせずに肩を上下させてると、息の乱れが本当に一つもない善逸が炭治郎の元に戻ってきた。
「炭治郎、水」
「うん……」
渡された水を一気に飲む。乾いた喉が潤い、少し身体が冷えたような気がする。空になったコップを善逸に差し出せば、今度は氷の入った水のコップをかわりに渡された。炭治郎はそれを今度はほんの少しだけゆっくりと、けど休むことなくゴクゴクと飲む。氷の冷たさがありがたい。
「……ゴクッ……っはあ……! ありがとう善逸」
「部屋行ってて」
「あ、うん」
炭治郎は息も落ち着いてきたので、ローファーを脱いだ。外でご飯を食べてから繁華街に行こうという話をしていたのに家で遊ぶのかなと炭治郎はさして気にせず、善逸の部屋へと向かう。
梅雨が近づき、雨が降るようになってから、伊之助との練習で善逸の家の道場を使わせてもらうことが何回かあった。その際、炭治郎は善逸の部屋にも上がらせてもらっていたので、部屋がどこにあるかは分かっている。家の中に善逸のお爺さんである慈悟郎はいないのか、静かなものだ。もしかしたら敷地内の道場の方にいるのかもしれない。
善逸の家は中々の旧家だ。立派な庭もあり、土地を幾つも所有しているらしい。古い家特有の畳の匂いはするが、キチンと定期的に管理されているのか使い古されたというより、まだ新しめの匂いだった。しかし柱は年季が入っている。自分の家とは違う作りに、炭治郎はいつもドキドキしてしまう。この家の中にいる善逸は、何だか浮世離れして見えるのだ。剣道を嗜むゆえの独特な姿勢と歩き方、なのに金髪金目の姿に神秘性を感じてしまう。
(……善逸って不思議なんだよな。喋ると煩かったりとか、年相応な感じなのに……黙ってる時とかは達観してるように見える)
そりゃあ剣道で全国で一番、それも中学合わせると全国大会を四連覇している人間だ。よくある普通とは違うのかもしれないと炭治郎だって分かっている。全国優勝経験がある伊之助だって風変わりだ。しかし善逸は、それ以上に何かが違うのだと炭治郎の鼻が感じ取っていた。
炭治郎は廊下を進み、善逸の部屋の木戸を開いた。そこの部屋は板間でベッドが置いてある。日本家屋だから一部屋はそこまで広くなく、六畳間あるかないかくらいだ。空間を有効活用する為なのか、押し入れの襖は取り払われ、中が剥き出しになっていて、左側の上スペースに洋服が、左側下にチェスト。右側上下はデスクスペースになっている。
最初にこの部屋に来たとき、炭治郎は「えーなんだこれ! いいな!」と思ったものだ。収納兼デスクスペースはペンキでちゃんとお洒落に塗られていて、以前にホームセンターで見たDIYのサンプルみたいだと、炭治郎はワクワクしたのだ。ちゃんと服とデスクスペースを視覚的に分けるために柱も増設されていて、スッキリして見える。
なんでこんなこと出来るんだと興奮気味に善逸に聞けば、善逸は「……まあ、昔取った杵柄だなあ。何でも自分でやるのが普通だったから」と年寄りみたいなことを言っていた。知り合いから廃材を貰って何かを作ることが多いからと、今度何かを作る時は手伝わせて貰う約束を炭治郎は善逸としている。
炭治郎はジメッとした空気に窓を少し開けて、そして足元にある扇風機のスイッチを押した。これで少しは涼しいなと思いながらシャツの前を開いて、手のひらでパタパタと仰いでいると、ガラリと木戸が開く。
「タオル持ってきた」
「ああ、ありがと……」
ぴたりとタオルを額に当てられて、炭治郎はほんの少しだけ驚いた。善逸は何を考えてるのか表情が殆どない。どこか遠くを見ながら、炭治郎の額をタオルで拭いていく。
「じ、自分でやるぞ?」
「……俺がやりたい」
そう言った善逸からまた、甘い桃のような匂いが広がった。それに炭治郎は身体の奥に燃えたような熱さを感じる。まただ、またこの匂いだとくらりくらりとする間に、善逸は額を拭っていた手をするりと首元に移動させた。開かれていたシャツの合間から善逸の持つタオルが入り、炭治郎の汗を拭っていく。炭治郎が押されて倒れないようになのか、タオルを持っていない善逸の左手は炭治郎の右肩に添えられていた。そこが燃えるように熱い。
「……ぜ、んいつ……も、ういいよ……汗ひいたから」
鎖骨を撫でるタオルの動きが、炭治郎をソワつかせる。気がつけば善逸は程近くにいて、こんなにぴたりと寄り添うようにしていたら動きにくくないかな。なんて炭治郎は明後日の方向に頑張って思考を飛ばした。でないと空気に飲まれそうだったのだ。どんな空気だと言われれば……たぶん、きっと、付き合いたての自分達にはまだ早い空気だと炭治郎は分かっていた。
「たんじろう」
しかし善逸は引かなかった。炭治郎を本当に軽く押した。それだけで不思議なくらい簡単に、炭治郎は後ろにあったベッドの上に尻餅をつく。そして炭治郎が何が起こったのか把握する前に、すかさず善逸が覆い被さるように乗り上げてきた。暗くなる視界に炭治郎は慌ててしまう。これはきっと、いやらしい雰囲気でやっぱり間違いないと慌ててしまう。
(こ、これは……! も、もしかして何かエッチなことでもするつもりなのか!? さ、流石にまだ何にも考えてなかった!)
炭治郎は善逸とのことはゆっくりとしていくつもりだった。手を繋いで、キスをして、長男としては漠然とリードしたいなとは考えていたが、よく考えれば善逸の方が歳上だ。体格はほぼ変わらないし、むしろ炭治郎より細身に見えるが、実際の筋肉量は善逸の方が凄いだろう。考えようによっては善逸の方が男らしい。
(も、もしかして善逸は俺のこと抱きたいとか思ってるんだろうか……!?)
炭治郎から好きになったが、炭治郎は善逸に抱かれたいなとは微塵も考えていなかった。いつもキスしたいとか抱きしめたいとかばかりで、キスされたいとも抱きしめられたいとも考えたことがないので、きっとセックスについて考えてみても炭治郎は『抱きたい』だろうと瞬時に分析する。しかし善逸も同じタイプだとすれば相談は必要だ。場合によっては炭治郎も抱かれる選択肢を視野にいれねばならない。
「善逸、あの……!」
「たんじろ……」
「わあ……!」
炭治郎は目の前で小首を傾げ、トロリと蕩けた目でワイシャツのボタンを外し始めた善逸に真っ赤になった。善逸の目は炭治郎を乞う目だ。間違いない。善逸は抱かれる側だと未経験の炭治郎でもすぐに分かった。それくらいに善逸は誘惑するエッチなお兄さん感が凄かった。
「ぜ、ぜんいつ……!」
「触ってよ、炭治郎……」
ワイシャツも中のTシャツも脱ぎ去った、善逸の均整のとれた上半身が晒され、それに炭治郎はごくりと喉を鳴らしてしまう。善逸は炭治郎の手のひらを掴むと、ゆっくりと自分の胸の辺りに触れさせた。
「触って、炭治郎。なあ、俺を抱いてくれよ」
(わあああああああ!!)
覆いかぶさっていた善逸が、炭治郎の首に腕を絡ませて抱きついてきた。それに炭治郎は目の前が真っ赤に、そして真っ白になる。もう何が起こっているのか分からない。善逸はどうしてしまったのかとパニックだ。善逸の首筋からは酩酊してしまうのではというくらいの甘い匂いが漂っている。しかし酩酊までいってしまうと炭治郎には毒だ。心地良かった筈の甘い匂いが一気に不快になる。善逸なのに、善逸が自分を抱いて欲しいと強請ってきているのに、炭治郎はとてつもなく拒否感が出た。それが自分でも信じられなかった。
(な、なんだ? 何なんだ!? 善逸が、俺に抱きついてくれているのに、何でこんなに嫌なんだ!?)
炭治郎は直ぐにでも引き剥がしたいが、それは善逸を傷つけやしないかと躊躇っていた。いや、順序というものがあるとは分かっている。それとなく嗜めて止めさせればいいのだろうが、その冷静さが自分にあるかどうか炭治郎は分からなかった。
とにかく炭治郎は何かが我慢ならない。善逸に失望したとかそういう事ではなく、善逸の匂いが不快だった。自分に情を向けられているはずなのに、それはどこか遠くに投げかけられているような、自分ではない誰かに縋っているような気持ち悪い違和感があった。
「炭治郎。口吸って」
善逸のその一言に炭治郎はとうとう、手が出た。善逸の口を覆い、言葉を塞ぎ、一気に後ろに追いやる。
(誰だ『炭治郎』って。今の名前は俺じゃなかった!)
そう思って善逸を見つめた炭治郎は善逸の目が急速に暗くなっていくのに気がつく。匂いも桃の酒のようなくらいに濃かったものが薄まっていき、とうとう土砂降りの雨のような、泥水のようなそんな匂いに変わった。
これが一体どんな気持ちなのか炭治郎には分からない。後悔や辛さや悲しみを混ぜこぜにしてようやく出る匂いかもしれないし、違うかもしれない。炭治郎の短い人生経験では判別がつかなかった。
「……ごめん。炭治郎」
(……今のは俺の名前だ……)
炭治郎は返事が出来なかった。善逸は落ちていたTシャツを着るともう一度、「ごめん」と言った。その目は炭治郎に向けられる事がなく、じっと床を見つめている。
炭治郎はそんな善逸が見ていられなくて、善逸の横を通り過ぎると鞄を持って部屋を出た。階段を降りて、玄関に行き、揃えられたローファーを履いて……後ろを振り返る。
(……来てくれない……)
炭治郎は呼び止めにも来ない善逸に腹が立った。同じ名前なのに別人を呼んだ善逸に腹が立った。
(同じ名前の別人って誰なんだっ……!)
炭治郎は泣きたかった。善逸が抱いて欲しかったのは俺じゃないんだと悲しみを抱えながら、ガラス戸の玄関を出て走り出す。明けきらぬ梅雨の灰色の雲。遠雷が聞こえた気がした。
勘づく男
今と昔がぐちゃぐちゃになっている。自分がどこに立っていて、自分が誰かも分からなくなりそうだ。
「権八郎となんかあったのか?」
伊之助のその言葉に、善逸は打ち合っていた竹刀の切っ先を下にずらした。その隙を見逃さず面を狙ってくる伊之助の竹刀を頭部の位置をずらして躱し、強かに小手を打つ。パアアアンと響いた一本を知らしめる音に、伊之助は「あー!! くそっ!!」と言って竹刀を下ろすと面を結ぶ紐を乱暴に取った。
「おい、礼節!」
「分かってる! 試合ではちゃんとするぞっ!」
「練習からキチンとしてないと本番でミスするぞ!」
善逸の指摘に伊之助はべえっと舌を出した。そんな伊之助の様子に善逸は大丈夫かと心配になる。善逸と伊之助は六月に剣道のインターハイの予選に出ており、そこで善逸は団体と個人、伊之助は個人で全国への切符を勝ち取っている。
伊之助は昨年の全中の大会で優勝しているのだから、剣道の礼節だって分かっているのは知っているが、予選決勝で伊之助と当たった際に、相当に興奮していて善逸は冷や冷やとしたのだ。結果としては東京都一位代表が善逸、伊之助が二位となり、伊之助はとてつもなく悔しそうだった。大会中に審判の前で竹刀とか投げないでくれよと善逸は必死に祈ったものだ。
「伊之助、ちゃんとしろよ! 礼節がなってないといくら強くても失格になるんだからな! 聞いたらお前、中学の一、二年生の時は礼節欠いて失格になってたんだろ!?」
「なんで知ってんだテメー!!」
「お前のとこの顧問が、俺のとこの顧問経由で教えてくれたのっ! 大会に無事に出したいからよく言って聞かせてくれって! 俺はお前の保護者じゃねえってのに!!」
全くもって遺憾だ。いつの間にか伊之助と善逸が一緒に練習しているのが知れ渡り、全国大会が近づいてきたら「部活いいから、二人で切磋琢磨しろ!」と善逸と伊之助は部活動から出されてしまった。
なのでテスト明けからこうして毎日のように善逸の家の剣道場で二人で稽古をしている。打ち合いをしながらも伊之助は、善逸の強さの秘密を探っているのか、面越しに見える目は真剣だった。
「ちゃんとやるからギャアギャア言うな!!」
「本当かよお!? 俺だって決勝で戦うなら伊之助がいいんだからな!? 途中で失格になるなよ!?」
「……おう。ならねぇ」
「本当だな!? お前が実力で負けるとは微塵も心配してねぇけど、礼節だけは本当に心配なのっ!! しっかりしてくれよ!?」
「まかせろ!! 優勝するのは俺だーっ!」
両手を突き上げる伊之助に善逸も肩を下ろした。分かってくれているならいいのだ。伊之助がルール違反で失格など悲しいにも程がある。ショボくれる伊之助なんて見たくはない。
「……っておい! 俺の話! 無視するな!」
「えっ? 話?」
「健太郎と何かあったんだろ! あいつ、練習にさっぱり顔出さねーし、学校でもショボくれてんぞ!」
伊之助の言葉に善逸はぐっと息が詰まる。伊之助に倣って面を取るも、息はまるで楽にならない。善逸はドクドクと鳴る血流の感覚に、それでも音は遠いなと何となく思った。生まれ変わって、耳の良さを失って随分と慣れた筈なのに炭治郎や伊之助といると違和感の方が大きい気がするのだ。
「……炭治郎、元気ない?」
「ない。昼間の朝顔みたいになってやがる」
「萎れてんのね。……うーん……そっかあ……」
「……喧嘩したのか?」
心配そうに聞いてくる伊之助に、善逸はパチリと瞬いた。そしてそうだ、伊之助には今はお母さんがいるんだと思い出す。誰かを心配するのは当然だと、炭治郎や善逸が教えなくとも、伊之助はもう知っているのだ。そしてまた、心配の仕方も以前と違う。
前世の伊之助ならば炭治郎と善逸がぎこちない時は、最初は笑い飛ばし、喝を入れ、そして放っておく。二人ならば大丈夫だと信頼の元に放っておいた。しかし今の伊之助には前世ほどの信頼が炭治郎と善逸にない。当たり前だ。前世では命を預けあって戦った経験があるのだから。今世では死ぬまでにその信頼を得られるか分からない。
(……伊之助に心配されちゃった。嬉しい筈なのに、嬉しくないなんてなぁ……)
善逸はそう思う自分にひくりと口元を痙攣らせた。最近、ダメなのだ。仲良くなった当初は気にならなかった前世と今世の違いが、だんだんと違和感に変わってきている。しかし違和感と言っても、そもそも前世の記憶も大筋のことしか覚えていない。だから何となく違和感があるとしか言えない。
(やばい、今と昔が混ざってきてる…のかも……。昔の記憶が薄れてるような感じがする。今の二人が当たり前なものになればなる程、俺の家族がいなくなる気がする……)
前世で善逸は、全てが終わった後は炭治郎と伊之助、そして禰豆子と共に竈門家の生家に身を寄せた。炭治郎は寿命が二十五くらいだからと沢山一緒に居たくて、恋仲であったこともあり、伊之助と共に竈門家で暮らした。
そこから禰豆子を嫁に出し、炭治郎を看取り、善逸は戦争の際に禰豆子と子供達を保護した。実家に身を寄せていた禰豆子たちは結局、嫁ぎ先が焼け落ちて、禰豆子の夫は……どうなっただろうか。その辺りから善逸の記憶は殆どない。もしかしたら自分はその辺で死んだのかもしれないと善逸は思っている。
善逸は自分の死因を覚えていない。炭治郎が死んだあたりから記憶は朧気で、以降の出来事は教科書の年表のように概要しか覚えていない。本当にあったという自覚もない。だがその感覚がどんどん広がってきている。確かな実感があった過去の日常が、今の日常に上塗りされているかのようなのだ。
「……喧嘩、喧嘩なのかな。ただ俺が悪いのは確かだ」
「……何したんだ?」
「何……何かあ。何だろう……たぶん、最初からダメだったんだ」
「おいお前、分かるように話せよ。気取ったどっかの俳優みてぇなこと言うな」
「もおおおおお!! 人がしんみりしてるのにさああああ!! もういいよ! 水分補給したら早く続きするぞ!!」
善逸は道場の壁際に置いていたペットボトルを二本手に取った。その一本を伊之助に放り投げると、伊之助は危なげなく受け取る。そして善逸がその温いペットボトルを呷ろうとしたら、伊之助が「そういえば分かったぞ」と言ったので口をつけたまま振り返った。
「何が?」
「お前の強さの秘訣」
「え」
今日は爆弾発言が多いな、なんて頭の片隅に浮かんだ善逸だが、伊之助の言葉にドクドクと脈が高鳴る。期待が止まらない。
「何十回も打ち合ってようやく分かった。呼吸だ。呼吸が違う。俺とお前だと普段してる呼吸からして違うんだ」
これが答えだというような伊之助の真っ直ぐな視線に、善逸は全身から力と息を抜いてへたり込んだ。まさか本当にそこに気がついて答えに辿り着くとはと、善逸は茫然とする。
しかしすぐに遅れて、じわじわと興奮が湧いてきた。さすが伊之助だ。親分だ。記憶があるからできる俺とは違うと善逸は顔を覆って笑う。涙が出そうだ。呼吸を知る者が、体感する者が、自分以外にもいるという事実に善逸は涙が出そうだった。
「すげー……流石だわお前。あってるよ」
「そうだろ! そうだろ! 俺はすげーんだ!!」
「すごいすごい。本気で感動したよ。よく気がついたな」
「紋逸をよーく観察したからなっ! これで肌がビリビリする感覚にも合点がいった!! お前の呼吸の振動にビリビリしてたんだ!! お前は竹刀を振る時に深い呼吸をする! 深呼吸なんてもんじゃねぇ! もっと、もっと深い呼吸だ! 全身の血に空気を取り込んでる! すると次の瞬間に身体中の筋肉が熱くなるんだ!! なんだテメェ! そんなすげーのどこで覚えたんだ!!」
興奮して話す伊之助に、善逸は呆気に取られた。すごい、そこまで明確に感じ取れるのかと驚く。前世の善逸も耳の良さで全集中の呼吸が発揮される際の血と心臓と筋肉の状態を把握していたが、まさか今の伊之助でもそんなに感じ取れるのかと凄さを感じた。
「……俺は生まれつきに近いよ。物心ついた時には全集中の呼吸ができてたから」
「ぜんしゅうちゅうの呼吸?」
「うん。これはそういう名前の技術なんだよ。もう失われてるのかもしれないけど……昔はそう呼んでたんだ」
「失われてるかもしれねぇのに、お前はなんで知ってんだ?」
伊之助のその素朴な疑問に善逸は半目で笑った。伊之助はその笑みにムッとしたようだが、これ以上は善逸には伝えられるようなことがない。前世の話などしたら、頭のおかしい奴だ。
「さて、名前のことよりどうすんだ伊之助? 俺に呼吸のやり方を教えてほしいか?」
「……やり方ってあるのか?」
「……お前の言った通り、全集中の呼吸は酸素を血液に多く取り込み、心臓を早く動かし、体温を上げる。そうすると凄い力が引き出せるようになるんだ。じゃあ、どうやれば酸素を血液に多く取り込むことができるか。これは簡単だよ。とにかく肺を大きくする。めちゃくちゃに鍛える。そうすると一瞬で血の中に沢山の酸素が入れられるようになるんだよ。これができれば、血が沸き立つのに釣られるように、骨と筋肉が熱くなるんだ」
「どうやったら肺はデカくなる?」
「死ぬほど鍛える。これ以外にない。死ぬほどだ。死にそうだ、なんて頭が思わないくらいに鍛えろよ。そしたら伊之助ならきっとできる」
善逸はそう言うと、竹刀を拾って伊之助に放り投げた。それを受け取った伊之助が不思議そうな顔をする。そんな気の抜けている伊之助に、善逸はビッと竹刀を横なぎにして首筋の寸前で止めた。完全に意識の外からの攻撃だったのか、伊之助はピクリとも反応しなかった。しかし次の瞬間にはその目に闘志が宿り、燃え上がる。
「……防具なしか?」
「伊之助はつけてもいいよ?」
「いらねぇ!!」
伊之助はそう言って善逸の竹刀をはじき返すと竹刀を振るってくる。善逸はスッと後ろに下がり、伊之助の竹刀を避けた。そして振り降りた竹刀を上から抑えると、一歩を踏み込んで伊之助の腕を掴んで中空に放り投げる。伊之助はまさか竹刀以外で来るとは思っていなかったのか、びっくりした顔をしていた。それを見た善逸は、やっぱり今は野生児じゃないんだなとほんの少しガッカリする。しかし投げられた伊之助は持ち前の運動神経で体を捻り、着地すると、すぐさま竹刀を振りかぶって善逸に打ち込んできた。
「おい紋逸!! 礼節どうしたあ!!」
「剣道の大会じゃねぇじゃん」
そのまま善逸と伊之助は汗でぐちゃぐちゃになるくらいに稽古をした。ぐちゃぐちゃと言ってもなったのは伊之助で、善逸はほんの少し汗を掻いた程度だ。善逸はぶっ倒れた伊之助に、前世と逆だなとほんの少しだけ優越を感じるも、そもそも別人だったと思い直す。善逸は剣道場に寝転び肺を大きく上下させている伊之助をじっと見た。こんな伊之助はよく見た筈なのに、今世では初めて見る光景なんだなと善逸は寂しくなる。
目の前に伊之助がいるのに、全集中の呼吸を会得しようとしてくれているのに、伊之助は伊之助ではないのだ。善逸のよく知っている伊之助ではない。炭治郎と同じように今世に生きる、善逸の知る伊之助とは別の人間だ。
(……俺、何してんだろ)
善逸は伊之助が全集中の呼吸に気がついたのに興奮してしまい、ついつい要らぬお節介をしてしまったと、先ほどまでの自分の行動を今更後悔していた。どれくらい鍛えるのが『死ぬほど鍛える』なのかを、伊之助に散々体感させてしまったと善逸は頭を抱えたくなる。
そんな善逸を気にすることも出来ないのか、伊之助はヒューヒューと大きく息をしていた。そしてようやっと何とか這えるくらいまでに回復すると、仰向けだった身体をゴロリと転がした。
「……おい…もんいつ……あ、あしたもこれやるぞ……」
「……やらない。もうしない」
「は、はあ!? お前っ! 稽古に付き合えよ!!」
否定した善逸を、伊之助は信じられないという顔で見てくる。善逸は「そういえば猪頭ないんだよな」と伊之助のくるくる回る表情を見て、ぼんやり思った。久しぶりに本気になったから張り切りすぎて空回りし、頭に酸素が回っていないのだろうかとまで善逸は考えたが、目の前の伊之助の顔は鮮明に見えた。前世の伊之助とはなんら変わりない、美しく愛らしい、まさに美少女と言ったような顔だ。
しかしその下の肉体はやはり薄い。前よりも伊之助にムキムキが足りなくて違和感がある。この顔に過剰なムキムキは不気味だというのに、善逸はそれが不足していると切なくなった。美少女顔にムキムキが足りないとはとんでもない冒涜な気がするが、ムキムキは伊之助を伊之助として成立させる為に必要なのだと善逸は今度こそ頭を抱え、そして蹲る。
(……んなわけあるか。こいつも伊之助で俺の友達だろ)
善逸は自分はおかしいのだと、前々から知っていた。しかし知っていると理解しているは違うのだ。善逸はようやく今、自分がこの世界で異端なのだと理解した。
普通は前世の記憶なんてないし、いらない。あるべきではないのだ。そんなもの抱えて何になる。現にいま、善逸はあって良かったと思えなくなってきている。目の前の伊之助はもちろん、炭治郎でさえ違和感がある。あんなにも手が早く、全てを奪っていった炭治郎が自分を欲しがらないなんてと悲しくなる。
(当たり前だ。あれは俺の炭治郎じゃない。昔の炭治郎じゃない。普通の十五歳の子供だ。けど炭治郎は……俺を好きだって……)
記憶なんてなければ良かったと叫びたい。しかし記憶がなければ、炭治郎とは出会っても仲良くなれなかったのではないだろうかと善逸は思い至る。炭治郎は鼻が利く。きっと店に通い始めた自分の匂いに気を引かれて好きになったのだ。それはつまり、自分が炭治郎に意識を向けていたからで、記憶がなければ店をリピートしていたかも分からないと善逸はぐ頭をぐしゃぐしゃと掻く。
そして記憶がなければ炭治郎だけでなく、伊之助さえも知り合うことがなかったかもしれない。善逸は記憶がなければ、きっと居合道を続けていた。爺ちゃんに喜んで欲しいと期待に応えたいと空気も読まずに、獪岳への配慮などなく続けていた。そうなればまあ、獪岳の不興を買うのは間違いない。今のように悪態をつきあいながらも同じ空間で会話をするということもなかっただろう。
(……あった方が良かったのか……なかった方が良かったのか……分からなくなってきた)
そう思いながら善逸が髪をかき混ぜていた手をとめると、伊之助が目の前で善逸を見下ろしていた。それをチラッとだけ見つめて、善逸は俯く。そしてズビッと溢れそうだった涙を、鼻を啜ることで何とか堪えた。
「何泣いてんだよ」
「泣いてねーよ」
「泣いてんぞ。空気が震えてる」
そう言った伊之助に、善逸は今度は「伊之助らしいな」と思う。思考はぐちゃぐちゃだ。もはや伊之助とは何なのかと哲学すべきかもしれないと善逸は喉の奥で笑った。話してしまいたい。自分の抱えている、誰にも話したことのない秘密を、全部ぶち撒けてしまいたい。善逸自身も把握しきれない混乱を、ぐちゃぐちゃに絡まりあった前世と今世の記憶を、誰かに紐解き、善逸というものを掬い上げてほしい。
「伊之助、なあ、聞いてくれる?」
「何をだ?」
「俺の秘密。誰にも言ったことない、言えなかった秘密」
善逸が期待するように伊之助を見れば、伊之助はグッと眉間に皺を寄せた。そしてゆっくり目を瞑り、しかし目蓋を閉じていたのはほんの僅かで、伊之助は目を開くと善逸を真っ直ぐに見て言った。
「その秘密は、炭治郎より俺が先に聞いていいのか?」
射抜く視線と胸を抉る言葉に、善逸は何も言えなかった。伊之助はどこまで知っているのかと思うが、もしかしたら炭治郎が自分達の関係を言っていたのかもしれないと善逸は聞き返すことはしなかった。そして伊之助の言うように、もし秘密を話すなら炭治郎であるべきだと善逸は息を吐く。だってお試しと言えども善逸と炭治郎は恋人同士なのだ。そして善逸は、炭治郎が道を踏み外しかけている責任を取らねばならない。
「……ごめん。先に炭治郎に言うわ」
「おう。仲直りしろよ」
それはどうだろうかと濁した笑いを向けた善逸だが、伊之助は善逸など殆ど見ずに既に踵を返していた。善逸はしゃがんだままそれを見ていたが、伊之助は結局、帰る支度が終わるまで善逸を振り返らなかった。そして荷物片手にようやく善逸を見た伊之助は、さっぱりとした顔で言う。
「次に会うのは大会の決勝だ」
その言葉に善逸はおやっと思った。先ほどまで稽古を一緒にしろと言っていたのにと首を傾げる。
「稽古いいの?」
「お前、稽古つけれる状態なのか? 自分と権八郎のことなんとかしろよ。俺は自力でその、全集中の呼吸っつーのを習得する。お前にできて俺にできないわけあるかよ! 見てろ! 決勝で勝つのは俺だ!」
伊之助はそう言うとバタバタと走ろうとして、足が縺れて転んだ。それはそうだ。かなり扱いたからなと善逸は転んだ伊之助のもとに駆け寄る。
「伊之助ー。走り込みと筋トレしろよー」
「うるせぇ!!」
伊之助はよろけながら立ち上がると、今度は走らずに歩いて道場を出て行った。善逸はそれを見送ると、一人きりになった道場で竹刀を取る。そしてゆっくりと構えて振り下ろした。この四年で馴染んだ動き、剣道の動きだ。
善逸は振り下ろした竹刀を今度は鞘に納めたような形で握り持ち、左足を下げ、右足に体重をかけて前傾姿勢を取る。前世ではこれしかできなかった。『雷の呼吸 壱ノ型 霹靂一閃』だ。善逸はシィィィィと息をすると脚に呼吸を巡らせる。そして前世の感覚をトレースするように一気に踏み込もうとして——やめた。
「……はあ」
善逸はパチリパチリと瞬きをし、頭を振った。そして緩慢な動きで稽古の後片付けを始める。竹刀をしまい、面を拭いて乾かす為に外に置き、そして道場を雑巾掛けしなければと思ったところで、善逸は伊之助に逃げられたことに気がついた。
「あー!! 伊之助の奴うう!! 掃除してけよなっ!!」
秘密と好機
俺の向こうに、俺じゃない誰かを見てる。俺の名前なのに俺の名前じゃない。それに気がついた時、心臓が引き千切れるんじゃないかってくらいに悲しくなった。
『生まれ変わっても君が好きだ……!』
『私も…! 次こそは私をお嫁さんにしてね…!』
俺はなんでこれを観ているんだと思いながら、炭治郎はダイニングの椅子に座ってぼんやりテレビを眺めた。
テレビの前では壮絶なジャンケン大会の末にチャンネル変更の権利を勝ち取った花子が正座してドラマを観ている。ジャンケン大会にて敗北した茂と六太は早々に部屋に引きあげていて、竹雄も交えてトランプでもしてるんだろうと炭治郎は当たりをつけていた。
善逸が以前、炭治郎の家に寄って行った時に教えてくれた大富豪に、茂も六太もハマってしまっていて、炭治郎や竹雄、禰豆子が頭数として引き摺り込まれることは多い。大富豪は大人数の方が楽しいからな、なんて思いながら炭治郎は、花子が観ている恋愛ドラマを眺めていた。
ドラマの内容は、なんでも家の事情で結婚できない二人が来世の約束をするシーンのようだが、炭治郎はそれを見ながら「いま頑張れ!!」という気になって仕方ない。最近人気のドラマらしいが、炭治郎は今初めて観たので雑な感想を口にすれば「最初から見てないのにそんなこと言わないで!!」と花子に怒られるのは必至なので黙っている。
しかし来世に丸投げとはやはり努力が足りないだろうと炭治郎は思ってしまう。だいたい来世で覚えていなければ他人なのではないか? 覚えていてもそれは本当に前世と同一人物だと言っていいのかと首を傾げる。あまり細かいところを考えたらダメなのだろうが、ついつい突っ込んでしまいたくなる。花子に怒られるので炭治郎はしないけど。
『何度生まれ変わっても君を手にしたい……! 』
(それは理解出来るな。俺も何回死んだって、来世があるなら……ずっと好きな人と出会い直したい)
炭治郎はテーブルに肘をつき、顎を手のひらで支えながらそう思った。ドラマらしい台詞だが、これには非常に共感ができる。炭治郎は好きな人の今も未来も欲しい。この未来には欲を言えば来世も含まれる。生まれ変わりというものが存在するのなら、その来世も来来世も来来来世も全てほしい。魂が尽きてなくなるまで、好きな人とは出会い直して一緒に居たい。
(……俺も生まれ変わってるなら、前の俺も願ったかな。生まれ変わっても好きな人と一緒に居たいって。……その相手は善逸なんだろうか)
炭治郎は初めて好きになった人を思い描く。そして前世があるなら、前世の恋人も善逸がいいと思うけれど、ムッとする気持ちがあるのも確かだった。何にムッとするかといえば、それは勿論、前世の自分にだ。まるで自分の手柄ですというように、運命を作りましたというように、善逸の中に居座られても困る。
前世の記憶なんてものはないが、炭治郎は前世うんぬんでなく善逸が好きなのだ。前世に前ならえで善逸を好きになったのではない。運命なんて、そんな他に責任を持たせるような言葉で善逸に手を伸ばしたくない。自分が好きだから手を伸ばしたし、自分が好きだから来世も善逸と一緒に居たいと思うのだ。要するに今の自分の気持ちが一番大きい。今の自分が前世よりも来世よりも善逸が好きなのだとよく分からない独占欲を発揮してしまう。
(……俺はこんなに善逸が好きなのに……善逸は誰を見てるんだ?)
先日、善逸に抱いてほしいと言われた時、炭治郎の鋭敏な鼻が感じ取ったのは善逸が自分を見ていないということだった。なぜそう思ったのかは分からない。酩酊するほどの甘い匂い。あれを醸し出すには相当に気持ちを発酵させねばならない筈だ。
だが善逸と炭治郎は出会って一年、仲良くなって二か月くらいだ。あんな匂いを恋人とはいえ、自分に向けて醸し出すのは違和感が大きすぎる。絶対に自分に向けられていないと炭治郎は理解していた。
(俺の名前を呼ぶのに、俺の名前じゃなかった……)
じゃあ誰を呼んだのだと言われたら分からない。このドラマのようにまさか前世の自分なんてことがあるわけもない。そうなると善逸は自分を誰かの代わりに見ているということなのだろうかと想像して炭治郎は震える。そんなの嫌だ。
(……相手が死んでて、俺に似ているとか?)
相手が生きているというのは想像したくない。相手が生きていたら、善逸がそちらに行ってしまうかもしれない。炭治郎はあんなに別人に重ねられて迫られたというのに、善逸を諦める気はさらさらなかった。だってあんな事をされても、腹が立っても、善逸が好きでしょうがないのだ。
もし善逸が自分を誰かに重ねているというのなら、炭治郎は少しだけ分かる点がある。それは善逸が店に通ってる時に醸し出す甘苦い匂いだ。あれは自分を見て誰かを思い出して辛かったからかもしれないと、炭治郎は合点がいった気がした。
あの癖になるような甘苦い匂い。思わず抱きしめて「大丈夫だぞ」と言ってあげたくなるような匂いは、確かに炭治郎の意識を善逸に向けさせたものだ。もしかしたらその重ねられている『誰か』がいなければ炭治郎は善逸を見逃してしまっていたかもしれないし、善逸も店に通うことがなかったかもしれない。
(なんとか、なんとか善逸に好きになってもらう方法を考えないと。俺を見てもらう方法を思いつかないと、善逸に捨てられるかもしれない……!)
炭治郎はそう思って、しかし策がなくてテーブルに突っ伏した。先日、走って善逸の家から帰ってしまってから実は善逸とは没交渉なのだ。善逸からメッセージも電話もないし、炭治郎も善逸から何もないのが怖くて何のアクションも取れていない。善逸と稽古をしている伊之助に善逸の様子を聞いて「普通。剣の腕も特に鈍りがない」と言われると勝手にショックを受けてしまうのだ。自分はこんなに寂しくて不安なのにと、炭治郎は思ってしまう。
炭治郎はやはり、変わらず善逸が好きだ。優しいところも、想像より騒がしいところも、少し影があって寂しそうにしているところも、全部が炭治郎を惹きつけてやまない。善逸から香る匂いが、炭治郎を包み込んで逃してくれない。
きっと善逸以上の人にはもう会えないだろうと炭治郎は確信している。このまま善逸に振られれば、いくら他の人と付き合っても炭治郎は、心の奥底に善逸という存在を持ち続けることになる。そんなのは相手に不誠実だ。そして炭治郎には自覚がある。自分は一度好きになったら並大抵のことでは忘れられないし、昇華できないタイプだと自覚があった。
(善逸に……連絡を取ろう。逃げてても意味がない。話し合って、自分が思っている事を告げて、それで……それでも善逸が好きだと告白しよう! もし別れて欲しいと言われたら、また付き合って貰えるまで口説くしかない!!)
炭治郎はそう決めると早速善逸に連絡をとスマホを取りだした。その瞬間、ピコンと鳴った通知にびっくりする。なぜならそれは善逸からのメッセージだったからだ。炭治郎は通知画面に表示される、『今から会える? 』という文字列を見て、急いでロック画面を解除した。そしてすぐさま返事を打って送ると、間をおかずに既読になり、メッセージが返ってくる。
「花子! 兄ちゃんちょっと出掛けてくるな!」
「え? こんな時間に?」
「ちょっとそこの公園までだから!」
炭治郎はそう言ってリビングを出て玄関に向かった。風呂に入る前で良かったなんて思いながらサンダルを履こうとして、走るからと素足であるにもかかわらずスニーカーに足を通す。鍵を靴箱の上から取り上げると、玄関扉をしっかり施錠して、炭治郎は夜闇を駆けた。こんな時間に出掛けるのは滅多にないことだ。誰かが風邪をひいたりして、どうしてもゼリーを食べたいとかアイスが欲しいとかそういう時に買いに走る時くらいだ。
炭治郎はそんな事を考えながら、じっとりと暑い中を走った。雨が上がったばかりの地面は濡れていて、走ると小さく水音がする。炭治郎は緊張しつつも逃げていてはダメだと己を奮い立たせ、善逸が指定した炭治郎の家の近くの公園……伊之助を含めた三人で放課後を過ごしていたあの公園に向かった。
「善逸!」
「炭治郎。ごめん、遅くに呼び出してさあ」
「いや、いいんだ……」
善逸は公園の入り口で待っていた。いつもと変わらぬ様子の声音だが、善逸から漂う匂いは罪悪感でいっぱいだった。それが余りにも辛い匂いで、炭治郎は思わず善逸に手を伸ばす。
「善逸」
そう言って掴んだ腕を引くと、善逸はあっさりと炭治郎の腕の中に収まる。そういえば初めて抱きしめるなと思いながら、しっくりとくる感覚に炭治郎は腕に力を込めた。ギュッと抱きしめると、善逸は炭治郎の肩にぽすりと頭を乗せるが抱きしめ返してはくれない。それに何故かゾッとして炭治郎はさらに抱きしめる力を強くした。どうか抱きしめ返してくれと願って、善逸を掻き抱いた。しかし——。
「俺はどんな匂いがする? 今の俺は耳が良くなくてさあ。炭治郎が何考えてるのかさっぱり分からないんだよ」
「え?」
そう言った善逸に、炭治郎は腕を緩めた。そして顔が見たいと善逸の肩を掴んで離れれば、善逸は凪いだ顔をしていて、十六歳である筈なのに酸いも甘いも知り尽くした老人のようで、炭治郎はギクリとする。
「こっち。話があるんだ」
「…………」
何も返事がないのも気にせず、善逸は炭治郎の腕を引いた。公園の奥の方、ベンチ側の街灯の下。炭治郎は蚊除けスプレー忘れたな、なんて思いながら善逸に引きずられるままそこに立った。
善逸は立ち止まり、くるりと振り返ると「何から話すかな」と言って、困ったように炭治郎を見る。炭治郎は嫌な予感がするなと思いながらも、善逸の話から逃げるつもりはなかった。善逸から香る匂いが炭治郎の逃げの一手を封じているからだ。たぶんきっと、ここで逃げれば一生善逸に踏み込めないと、炭治郎は感じ取っていた。
「とりあえず、この前はごめん。ちょっと急に事を進めすぎたわ。怖かっただろ?」
「……怖くはない。ただ、その、うまく言えないが、善逸が俺に抱かれたいと本当に思っていたわけじゃないのが分かって、ちょっとだけ腹が立ったんだ。あの時の善逸はその……俺じゃない奴を見ていなかったか?」
炭治郎は自分の発言に対してど直球だなと思った。他の奴のことを考えていただろなんて、そんな事を言ったら大変なことになりそうだが、炭治郎には感じたままを口にするしか手段がなかった。恋の駆け引きなんてこれが初恋なのだから出来るわけがない。
善逸は炭治郎の言葉に驚くかと思いきや、大して様子は変わらなかった。むしろ「そっかあ。炭治郎がそう言うなら、間違いないんだろうな」なんて言って諦めたように笑っている。
「何がおかしいんだ。俺は、俺は悲しかった! 俺は善逸が好きなんだ! 本気だぞ! なのに、好きな人に自分ごしに他の奴を見られた! こんな悲しいことがあるか!!」
「うん。ごめん」
「……否定しないんだな。……本当に俺の向こうに誰かを見ていたのか?」
炭治郎は善逸が自分ではない誰かを見ていると思っていたが、本当にそうだったなんて衝撃を受ける。自分でそうではないかと考えているのと、本当に肯定されるのとではショックが違うのだ。
「見てた……かも。うん、見てたんだろうな。どっちも炭治郎であることには変わりないけど」
「……その人も名前が『炭治郎』なのか?」
「うん。そいつも『竈門炭治郎』だよ。額に火傷の痕があって、六人兄弟の長男で、代々家に伝わる旭の描かれた耳飾りをしてる」
「え?」
「責任感が強くて、泣きたくなるような優しい音をしていて、弱虫で、泣き虫で、ちっとも強くない俺を『善逸は強いぞ!』ってよく励ましてくれてたんだあ」
善逸はそう言って笑った。同姓同名で六人兄弟の長男でって、それは俺じゃないのかと一瞬思った炭治郎だが、善逸からは深い深い望郷の匂いがした。決して戻れない場所を求めるような、迷子と似ているが、愛が大きい匂いだった。
「会ったのは二回目だっていうのに、炭治郎は『お前みたいな奴は知人に存在しない!』とか言うんだぜ? でも任務が嫌だって泣く俺に一個しかないおにぎりくれてさぁ。お前、どんだけ優しいんだよって思うよな。まあ、その後無理やり任務に連れていかれたけど……。鬼が怖いから屋敷に入りたくないって言う俺に対しての顔が怖かったんだよ…マジで……」
「……善逸、その、何の話をしてるんだ?」
任務とか、鬼とか、何の話なのか炭治郎には分からない。それに話せば話すほど、善逸の匂いがブレる。色んな感情がぐちゃぐちゃでドロドロで、善逸が失われると錯覚してしまう。炭治郎が不安になるような匂いだ。そう思って一旦、声を掛けたのだが、善逸は黄色いビー玉のような眼を炭治郎に向けて言った。
「前世の俺と炭治郎の話だよ」
そう言った善逸からは嘘の匂いはしなかった。しかし目がおかしい。どこを見ているのか分からない目に、炭治郎はどっと汗が噴き出る。喉が渇き、ゴクリと唾液を飲み込んだ。
「前世?」
「嘘じゃないぜ。実は俺、前世の記憶があるんだ」
そう言って笑った善逸は、炭治郎に丁寧に教えてくれた。人々が大正ロマンを謳う頃、善逸は人を喰う鬼を倒す『鬼殺隊』という組織にいて、そしてそこで禰豆子を除く家族全てを鬼に殺された炭治郎と出会った。炭治郎は鬼にされた禰豆子を人に戻す為の手段を探して鬼殺隊に入り、善逸とは同期で鼓屋敷の鬼を倒す為に合同で任務についた時に仲良くなったのだと、初めての友達になってくれたのだと善逸は嬉しそうに笑った。炭治郎は泣きたくなるくらい優しい音をさせる少年で、善逸はその音が世界で一番好きだったと言う。そこから色々と割愛はあったものの、最終的に炭治郎は鬼の首魁を倒し、禰豆子を人に戻し、善逸と伊之助も連れて生家に戻ったのだとうっとりした顔で善逸は話しをした。
その瞳と匂いが甘く切ないものなので、炭治郎はなるほどと、理解が及ばない話ながらにも理解する。
「……前世の俺と善逸は恋人だったんだな?」
「……そうだよ。今と同じ男同士だったけど、俺たちは恋仲だったよ」
善逸の古めかしい言い方に炭治郎は額に手の甲を当てた。ちょっと頭痛がしそうだが、善逸からは一切の嘘の匂いがない。だが一般的に考えれば善逸の話は荒唐無稽過ぎて、本人が嘘ではないと言い切るなら、精神科をお勧めするような案件だろう。しかし炭治郎は善逸を信じる他なかった。それは信じたいというのもあるが、やはり嘘の匂いがないのと、話を聞いてみて、だからかと納得できる点が幾つかあったからだ。
(善逸が禰豆子を見て、慈愛の匂いをさせるのは前世の禰豆子を知っているからか。それに伊之助が言っていた他とは違う強さの秘訣……話の中に出てきた『全集中の呼吸』というもので間違いないだろう……)
ちょっと信じられないような話だが、信じるしかない。つまり善逸は、炭治郎を通して前世の炭治郎を見ているということだ。
「……一年前に、店に初めて来た時に驚いた顔をしたのって……」
「たまたま入った店にまさか炭治郎がいるとは思わなかったんだ」
「……あの後、店に来ては甘苦い匂いをさせてたのは、俺に記憶がないからか?」
「え? そんな匂いしてたの?」
「……してた」
「あー…そっか。うん。炭治郎は覚えてないんだよなあって、つい思っちゃうんだよ。前世のお前、生まれ変わっても一緒にいたいとか俺に言ってたのに、まるで俺のこと覚えてないからさあ」
「……ごめん」
「いいんだよ。普通は覚えてないもんなんだぜ。……俺が要領悪くて、忘れられなかったってだけなんだよ」
そう言った善逸は今にも泣きそうだった。いや、泣いている。目から涙は出ていないが、むせ返りそうなくらいの悲しみの匂いがしている。炭治郎は何故自分に前世の記憶がないのだと苦しくなって胸のあたりの服を掴む。善逸はきちんと覚えて生まれてきてくれたのに、生まれ変わっても一緒にいたいと口にした方がすっかり忘れているなんて酷いではないか。
「……善逸が店に通ってくれたのは、俺が思い出すんじゃないかって思ったからか?」
俺に会いたくて来たんだろうかと、俺のことを好きだから店に来てくれてたのかと炭治郎が思って尋ねると、善逸はふるりと首を振った。
「いや違う。本当はね、今の炭治郎に彼女が出来るのを見たくて通ってたんだ」
「……は? な、なんで?」
「……もうこの世にいない炭治郎を、未練たらしく好きなままの俺に止めを刺して欲しかった。炭治郎が欲しくて堪らない俺の気持ちを……殺して欲しかったんだよ。もう、俺の炭治郎はどこにもいないから。だから、今の炭治郎に好きな人が出来たら、俺の入る余地なんてないんだって、もう、俺は炭治郎の恋人にはなれないんだって諦めがつくかと思ったんだ」
そう言って善逸はとうとう涙を溢した。そして炭治郎は自分は本当に見てもらえていなかったのだと気がつく。善逸が好きなのは前世の自分だ。本当に前世の自分かは分かりようがないが、少なくとも善逸の中ではそうなっている。前世の炭治郎を想って泣く善逸からは、狂おしい程の甘い匂いがする。悲しいくらい寂しい匂いがする。それが今の炭治郎には耐えられない。自分の中にさっぱりない記憶が恨めしい。
「……なんで、諦めようとしたんだ? 俺がいつか思い出すかもしれないだろ?」
「ええ? ないない。ないよ。お前は思い出さないよ」
泣きながらおかしそうに言う善逸に、炭治郎はカッとなる。記憶を取り戻して前世の炭治郎にいつかなるかもしれないのに、そんな風に期待もされないなんて酷いと思ってしまう。
「分からないだろう! 俺が思い出したら…! 前世の炭治郎が戻ってくるんだぞ!?」
「……そしたら今の炭治郎が消えちゃうじゃん」
さらりとそう言った善逸は、今度は今の炭治郎を見つめていた。さっきまでは前世の炭治郎ばかり見ていたのに、今は善逸は目の前の自分を見ているとはっきりと炭治郎には分かった。その切り替えの速さに炭治郎は感情の置き場がない。情緒が振り乱される。
「……俺、今の炭治郎も好きだよ。仲良くなって、前とは違うなってところあるけどさあ、それでも今の炭治郎も好きだ。また俺のこと、好きって言ってくれた時はびっくりしたし、困ったけど……やっぱり嬉しかったかも」
そう言う善逸に炭治郎は戸惑った。先程までは酩酊するくらい濃い甘い匂いがしていたが、今は甘酸っぱいような爽やかな匂いがしている。発酵などまだまだ程遠いが、その兆しを感じるような匂い。それに炭治郎は期待をしてしまう。
「……善逸は今の俺も好きか?」
「好きだよ」
「前世の俺と……」
「…………」
「いや、比較はやめよう。想った時間が違うから俺が負けるのは当たり前だ」
「ごめん」
「肯定されると流石に悲しいぞ」
そうは言ってみたが、思ったより事態は良かったと炭治郎は息を一つついた。正直、別れ話に発展するかもと冷や冷やしていたが、善逸はちゃんと今の自分も好きでいてくれているらしい。前世に負けているのは悔しいが、これはおいおい、いつかひっくり返せばいい。前世の自分に時間はないが、今の自分には時間があると炭治郎はひとまず納得することにした。
「分かった。善逸が俺を通して、前世の俺を見てしまうというのは分かった。納得した。俺はそれでも構わない。変わらずに善逸が好きだ」
そう言った炭治郎に、善逸は困った顔をする。それを見た炭治郎は、再びゾッと背筋を凍らせた。まずい、やはり雲行きが怪しいのかもしれないと心中で慌てた。
「……実は炭治郎、こっからが本題なんだけど……」
「嫌だ!! 聞きたくないっ!!」
「……俺と別れてくれよ」
「ぬああああああー!!」
「お試しの恋人関係を解消したいんだ。友達に戻りたいけど……炭治郎が嫌なら、もう会わないようにするからさ」
「聞きたくないって言ったのに!! 酷いぞ善逸!!」
「ごめん。でも聞き分けてほしいんだよぉ。俺、もう駄目なんだ……」
そう言って善逸はホトホトと涙を零す。それに炭治郎は耳を塞いでいた手を離して善逸を見た。何がダメなのだろうか。今の自分を通して、前世の恋人を見てしまう罪悪感が苦しいのだろうかと、炭治郎は項垂れる。
「なにがダメなんだ? 今の俺のことも好きでいてくれてるんだろ? 俺はそれでもいいんだ。善逸が傍に居てくれるなら俺が一番じゃなくてもいい。それでもいい」
「……俺はやだ。炭治郎にはお前だけを一等愛してくれる人と結ばれて、世界一幸せになって欲しいんだ。前世で早死にした分、それを取り戻すくらい幸せになって欲しい」
「俺、早死にだったのか?」
「二十五で死んだ」
「早いな!? ……善逸は幾つまで生きたんだ?」
「詳しく覚えてないけど、五十くらいかなあ?」
「前世の俺! 善逸を一人にしすぎだろう!?」
「鬼の首魁と戦った時の後遺症で寿命が短くなってたんだ。責めないでやってくれよ」
拗ねるように言う善逸に、炭治郎は前世の自分にムッとする。聞くところによれば十六の時に会っているのだから出会って十年しか一緒に居られていない。愛の深さに時間は関係ないと思うが、それにしても十年で来世まで善逸の気持ちを掻っ攫うなんて、前世の自分は欲張り過ぎではないだろうかと炭治郎は奥歯を噛んだ。
「ずるい! ずるいぞ! そんなに善逸に想われている前世の俺がずるい!! なんで俺は覚えてないんだ!!」
そう言った炭治郎に、善逸は困った子供を見るような目を向けてくる。そんな大人ぶった顔はしないでほしい。いくら前世の記憶があっても、善逸は今世では十六歳なのだから。
「……炭治郎も伊之助も禰豆子ちゃんも……覚えてないのはきっと、今を幸せに生きる為なんじゃないかなぁ」
「え?」
「前世と同じ親から生まれて、前世と同じ家族を作る。きっとそれと引き換えに記憶を使ったんだ。俺は前も今も生来の孤児だし、きっとあれだな。前世で手に入れた家族を死んでも手放したくなかったんだ。未来に期待しなかったから、過去に縋ったんだ。だから俺だけ取り残されちまったんだよ」
そう言って笑った善逸に、炭治郎は言い難い感情が湧き上がる。何と声を掛けたらいいか分からない。炭治郎には前世の記憶がない。だから前世の記憶を持って生まれ、それと寄り添って生きる他なかった善逸の気持ちが分からない。前世の恋人が、来世も一緒に居たいと言ったのに、覚えていなかった時の善逸の悲しみが測れない。
きっと善逸は期待していた筈だ。自分に前世の記憶があるのだから、炭治郎にも同じくあると期待していた筈なのだ。しかしそれは裏切られて、善逸は一人ぼっちだ。昔の記憶を泣きながら抱きしめて立っている。好きだ好きだと、善逸を置いて逝った酷い男の思い出を大事に抱きしめている。そしてその気持ちを自分では捨てられないから、今の炭治郎に殺して欲しかったのだと言うのだ。
「……俺が新しい家族になるよ」
「落ち着けよ。ちゃんと爺ちゃんと兄貴がいるからさ」
「そうだった。でも俺もいつか善逸と家族になりたい」
「……あー……ごめん」
「そこで断るな! 善逸は俺に幸せになってほしいって言ってたじゃないか!! 俺は善逸じゃないと幸せになんてなれないぞ!! 善逸じゃないと嫌だ!!」
そう叫ぶように言った炭治郎に、善逸はもう一度「ごめん」と言った。炭治郎はそれに焦るばかりだ。善逸が頑なに拒否を示すのに、やっぱり今の俺は嫌いなのかと不安が生まれてくる。
「……炭治郎はさあ。俺が前世を覚えていたから、俺を好きになったんだよ」
「……どういうことだ?」
「いやあ、だって炭治郎は俺に一目惚れだったんだろ。それ、一目っていうか鼻だろ? 匂いで好きになったんじゃないか? どうやら俺はさあ、炭治郎にとってはいい匂いするらしいんだよね。前のお前も俺の匂いが好きだって言ってよく嗅いでた。前世のお前も鼻が利くんだ。……だからきっと炭治郎は不可抗力で俺を好きになったんだ。俺が前世を覚えてるばっかりにさあ。きっと覚えてなかったら、匂いは違ってて……お前の好きな匂いじゃなかったよ」
炭治郎はその言葉に何も言えなかった。炭治郎は善逸に一目惚れをした。しかし外見よりも確かに匂いに惹きつけられたかもしれない自覚がある。それくらい、善逸の匂いは特別だった。それはそうだ。前世の恋人を前にして切なく甘く香る匂いなんて、とんでもなく特別だろう。気になってしまうのは避けられない。
「炭治郎は道を踏み間違えたんだ。俺の耳が前世と違ってよくなかったからさあ。炭治郎も同じように鼻が利かないだろうって思ったのがよくなかった」
「踏み間違えてない……」
「そうだとしても、俺が未練たらしく覚えてたりするから、前世なんてもんに振り回させたのは間違いない。炭治郎、あのな。みんな前世を覚えてないのはな、きっとそんなの抱えてると前に進めないからだ。昔を思い出しちまう。俺はそうだよ。前のお前と今のお前を重ねてみて……ぐちゃぐちゃになって訳が分からなくなっちまった。自分が何者なのかも……最近、よく分からない」
炭治郎は恐る恐る顔をあげた。善逸は寂しそうな顔をして笑っている。善逸から香る匂いは切なさや悲しみや愛しさが混ざり合っていて、こんな匂いをさせる人を炭治郎は初めて見た。
「俺は前世の『我妻善逸』の続きなのかな? それとも記憶だけある別人の『我妻善逸』なのかな? 前までは前世の続きだと思ってた。けど、今の炭治郎や伊之助と仲良くなって、楽しくて……最近は少しずつだけど前世のお前らがどうだったか分かんなくなってきてるんだ。あまりにも似てるから混同し始めてる。新しいお前らに、どんどん上書きされていってる気がする」
「嫌なのか?」
「それが分からないのよ。だって今の炭治郎も伊之助も好きだ。伊之助は友達だけど、炭治郎は……きっとずっと一緒にいたらもっと好きになる。ずっと一緒にいたくて、いつか家族になりたくなる。けどその時には前世のお前はすっかり俺の中にいないのかもな。薄情だよな」
「忘れてる俺の方が薄情だ」
「それが普通なんだって」
ハハッと笑う善逸に、炭治郎は眉間に皺を寄せた。善逸からは諦めの匂いがし始めている。炭治郎を諦めようとしているのだ。どちらのをと言われれば、きっと両方だ。善逸は『竈門炭治郎』から解放されたがっているのだ。自分を縛り付ける『竈門炭治郎』という存在から脱却したがっている。
「……死んで生まれ直したい」
「善逸」
「他にスッキリする方法が分からないんだよ。記憶なんて持ち越すもんじゃないな。前世の記憶が薄れていくと俺は誰になるんだろうな? 新しい『我妻善逸』になるのか? でも忘れたなっていうことだけは覚えてるんだぜ。最悪だろ? ……こんな気持ちになるなら、死んで生まれ直して、またゼロからスタートして……お前に会いたい。なあ、炭治郎。俺とお前が死んで、それで生まれ直したら……またそっから始めようぜ」
そう言った善逸はもう決めているようだった。今の善逸はもう自分と結ばれる気がないのだと、炭治郎は理解した。悲しい。辛い。けれど善逸の抱えている辛さが記憶をもたない炭治郎には理解できない。善逸からは本当に張り詰めた糸のような緊張を感じた。楽にしてあげなければ、善逸の糸が切れてしまうだろう。切れてしまえば、善逸がどうなるか分からない。そして糸が切れた善逸を、自分が支えることはできないと炭治郎は分かっていた。きっと追い討ちをかけるだけだ。しかし善逸を諦めきれない。このまま善逸を寂しいままにはさせられない。とにかく今は、その張り詰めた糸をなんとか緩めてやらねばと炭治郎は思った。
(ここが正念場だ。思い出せ炭治郎。俺はずっと善逸の奥深くに踏み込みたいって思っていただろう。見つめるだけだった一年間、善逸に絡みつく寂しさと悲しみの匂いをなんとかしたいって思っていただろう。今がチャンスだ。俺はようやく、善逸に踏み込むチャンスを手に入れたんだ。善逸が俺に前世の話を打ち明けたのは、自分の心を開いて見せてくれたからだ!!)
炭治郎は一つ息を吐くと、善逸を真っ直ぐに見つめた。きっと顔つきが変わったからだろう。善逸は少しびっくりした顔をした。もしかしたら前世の自分が気合を入れた時の顔に似ているのかもしれないが、そんなのはどうでもいい。今、善逸の前にいるのは自分だけだ。前世の竈門炭治郎は善逸に何もしてやれない。
「善逸の気持ちは分かった。ちょっと考えさせてくれ。流石に色々あり過ぎて、直ぐには答えが出ない」
「……ああ、うん?」
「また連絡する。今日はもう帰ろう。すっかり遅くなってしまった」
「そうね。お前、明日も早いしね」
「送ろうか?」
「いらんよ。俺、今の世なら凄い強いから」
「そうか。でも気をつけて帰れよ」
「うん……」
善逸はそう言って、後ろ髪を引かれるような様子で公園を出て行った。炭治郎は善逸が帰っていくのを見つめながら、心に点いた火をメラメラと燃やしていく。負けられない。前世の自分になぞ負けてたまるかと心を燃やす。
(善逸は俺のものだ。前世の俺になんてくれてやるか)
炭治郎は全身を熱くするが、ひとまず帰ろうと自分も歩き出す。頭の中はチカチカとしていて真っ赤だ。興奮している。善逸を救いたい。いや、善逸の奥深くに踏み込んで居座りたいと炭治郎は興奮している。前世の竈門炭治郎を追い出してやると、炭治郎は息巻いた。
(好きだ、好きだ善逸! お前は匂いのせいだと言ったけどそれがなんだ!! 俺がいま善逸を好きなのが全てだ!!)
炭治郎は奥歯を噛み、拳を握る。何がなんでも善逸と一緒に今を生きる。その為なら死んでも構わない。必ずや善逸の心を手に入れると、炭治郎は己の命に懸けて誓った。
今生転生
全てに区切りをつけて、新しく生きたい。
気勢が飛び交う体育館の中、善逸は手元の手拭いを見つめていた。なぜタオルではないのかとよく聞かれるが、善逸は剣道をする時はタオルよりも手拭いのほうがしっくりくるのだ。呼吸の制御で汗もあまりかかないので手拭いでも事足りる。
手の中にある市松模様の手拭いは、去年の春先に買ったものだ。たまたま見かけたもので、迷わず購入してしまった。黄緑と白の市松模様はカラーリングが違えども善逸が恋しい相手が連想できた。好きな人を思い出すものを持ち歩きたいと買ってしまったのだが、これは今となっては乙女思考の自分を感じる黒歴史な一品になってしまった。
恋しい相手の生まれ変わりと一方的とはいえ、再会してしまった今となっては恥ずかしいばっかりだ。しばらくは封印というように仕舞い込んでいたのだが、最近はなんだか心が寂しくて。善逸は今日この日のためにお守りがわりに持ってきたのだが、やはり市松模様が目について、違いがあっても好きな人を連想してしまう自分を感じて恥ずかしい。一応、好きな人を感じることには成功しているが、恥ずかしさまで連れてこなくていいと善逸は手拭いをぐしゃりと握りしめた。
善逸が今いるのは、自分が住んでいる場所から幾つか県を挟んだ先にある場所だ。何故そこにいるのかと説明するならば、今年のインターハイの会場がこの場所なのだと言うしかない。剣道のインターハイは毎年会場が違うのだ。
それゆえ善逸が所属する藤ノ花高校の剣道部は皆んな揃って遠征しているし、なんなら昨日で団体戦の優勝を決めている。圧倒的に強くて敵がいない善逸がいる為、藤ノ花高校剣道部はそれに食らいついていく日々で部員達も強くなっているのだ。去年はなし得なかった団体優勝に湧く皆んなを、善逸は仲間として嬉しいが、若人が努力で腕を磨いて手に入れた感心さがあって、どこ目線だというような感情に複雑であった。
優勝は嬉しい。三年生が喜んでいる。良かったなあ、みんな頑張ったなあ、なんて少し他人事のように感じてしまうのが善逸にとってはストレスだ。もし前世の記憶がなければ皆んなと純粋に喜べただろうかと考えてしまうのだ。
(いやでも、この大会は勝ち抜き戦じゃないし。俺は大将にいた。ちゃんと皆んなが頑張って繋いでくれたから勝てたんだ。いいことじゃん)
そう思っても大将戦になると、もうチームメンバーは「ああ良かった」という風になってしまうのだ。何なら相手すらも消化試合だが胸を借りて頑張るぞという雰囲気で善逸は寂しい。去年はなにも感じなかったので、ズルで申し訳ないけれど持って生まれた能力のようなものだと割り切りができていたのに、今はそれが難しい。善逸は今年の春過ぎに仲良くなった二人のお陰で、自分はこの世界の何かを歪めているような感覚にすっかりなってしまったのだ。自分がいるから勝てない子がいると、より強く思えてきてしまったのだ。
(……はあ。俺の出番、あとどれくらいだろ。もう帰りたいけど……伊之助と決勝で会う約束してるからな)
善逸は体育館の廊下のベンチでぬるい空調を感じながらぼんやりと座っていた。大半の人が体育館の中で観戦しているのだが、善逸は伊之助の指示によって外に出ている。
全集中の呼吸に気がついた伊之助とは、道場でめちゃくちゃに稽古をして以来、本当に会っていない。しかし昨日の晩に伊之助からメッセージが入り、明日の個人戦は伊之助の試合を見るなという命令が書かれていた。善逸はそんな無茶なこと言うなと思ったが、こうして律儀に守っている。自分の勝負が終わればさっさとその場を抜け出して、招集に関しては優しい村田に丸投げしてある。もちろん伊之助からの指示だと伝えてあり、最初はなんだそれと呆れていた村田であったが、伊之助の試合を見たらしく「あれは確かに決勝で戦うときに見せたいわ」と言ってきたのでどうやら何か本当にあるらしい。
(伊之助、マジで全集中の呼吸を会得したのかな? 常中は無理でも伊之助のセンスなら全集中の呼吸なら習得できるか?)
伊之助を見るのだけがこの大会での楽しみだ。正直言って、伊之助に負けると善逸は全く思っていない。善逸はそう思ってしまう自分に何様だと思う。いつの間にこんな性格が悪くなったのだろうかと考えてしまう。いや、元から性格が悪いのは知っているが、こんな人を下に見る性格ではなかった。いつだって羨んで上を見ていた気がする。あれはあれで、妬ましいといつも他人を羨んでいたけれど、今みたいに心がうまく動かない感覚はなかった。感動が薄いのだ。喜び満ちて、手放しで跳ね上がることをしなくなったのはいつからだったか。
「……」
善逸は市松模様の手拭いを見つめ黙り込んだ。調子が出ない理由は分かっている。善逸はいま、炭治郎と疎遠になってしまっているのだ。炭治郎を呼び出したあの夜。善逸が打ち明けた秘密を無理やり受け取る羽目になった炭治郎とは「ちょっと考えたい」と言われてそれきりに近い。向こうから何の音沙汰もないし、善逸が朝に竈門ベーカリーに行くことをやめ、伊之助との練習もなくなったので会う機会は一切なかった。
しかし時間は経つので、そうこうしているうちに炭治郎の誕生日は来てしまった。善逸は迷った末に「誕生日おめでとう」と素っ気ない文章だけを送った。返事はすぐに来て、「ありがとう。嬉しい」と飾りも何もない言葉一つがあった。遊びに行くのをどうするかとか、プレゼントはどうするのとか、言いたい言葉が善逸にはあったが結局は何も言えなかった。そしてそのままだ。もはやこれは自然消滅ではと善逸は考えている。
(いやでもそれがいいだろ。炭治郎だって前世が〜なんて言う奴、気味が悪いに決まってる)
別れるのを渋って見せた炭治郎だが、冷静になって善逸が気味悪くなったのかもしれない。関わるのも嫌で、連絡を絶って自然消滅なんていうことを考えるのは……炭治郎らしくないなと思って、善逸は溜息をつく。
しかし善逸は分からない。この炭治郎らしさというのは、いったいどちらの炭治郎を基準に考えているのだ。大正の時代の炭治郎か。はたまた令和の炭治郎か。もはや二人が混ざり過ぎていて分からない。これが善逸を追い詰める。二人が混ざれば、自分の記憶の正否が分からない。自分は大正の善逸なのか。それとも令和の善逸なのか分からない。大正の記憶があったから大正の善逸の続きのつもりでいたが、実際には前世の自分という、所詮他人でしかない人物の記憶を有している令和の善逸なのだろうか。
(もし俺が……本当は大正の俺じゃないなら……炭治郎に愛されてたっていうのは勘違いなんだよな)
大正の炭治郎の愛は、大正の善逸にのみ注がれている。善逸が今でも思い出す、嬉しい愛しい言葉の数々は本当は自分のものではないのかもしれない。自分が言われていたと錯覚しただけで、本当はずっと自分は一人ぼっちだったのかもしれない。今の自分は、大正の炭治郎に愛されていなかったのかもしれない。
ならば令和の炭治郎はどうであろうか。令和の炭治郎は確かに今の善逸を見てくれていた。しかし切っ掛けは善逸が令和の炭治郎に大正の炭治郎を重ね見て、気を引く匂いをさせたからだ。善逸に記憶がなければ、令和の炭治郎が善逸を好きになるなんてことはなかったに違いない。
(俺の前世の記憶、ロクなことにならねえな)
多くの子供達が善逸を見て才能の違いに失望して竹刀を置き、そして一人の少年が、前世とかほざく電波野郎に恋をするという黒歴史までも作ってしまった。善逸は申し訳ない気持ちでいっぱいだ。しかしどうにもできない。死んで生まれ変われるならそうしたい。しかしそんなことできない。怖い。死ぬのはそれはそれで怖い。ひとりぼっちで死にたくない。けれど今のままだと記憶に振りまわされて、生き地獄なのも確かだった。
(もう考えるのやめよう)
考えても辛いだけだと善逸は思考を放棄しようとしたが、そのタイミングで電話が鳴る。村田からだろうかと、善逸はぼんやりしたまま通知相手も見ずに、スマホのサイドボタンを押して応答した。
「もしもし?」
『ああ、善逸。今大丈夫か?』
聞こえてきた声に善逸は息が止まる。その声は善逸が今も昔も一番優しいと思っている男の声だった。
「たんじろう……? なんで……」
『伊之助から、善逸は今は試合がない筈だと教えてもらったんだ。俺は直接応援には行けないから、せめて電話で応援をしたいなと思って。善逸は強いからきっと決勝に行くだろう。頑張ってくれ。伊之助のことも応援しているが、善逸のことも応援している。伊之助の優勝も見たいけど、俺は二連覇する善逸も見たい。どちらが優勝しても悔い無いように全力で頑張れ!』
「そっか……ありがと……」
突然の炭治郎という供給に善逸はパニックになった。こんなことがあって良いのだろうかと思いながらも、久しぶりに聞く炭治郎の声に善逸は喜びが浮かんでくる。そして喜んでしまう自分に困惑するのだ。大正の時代の炭治郎が好きだった筈なのに、令和の炭治郎に喜んでしまう自分に戸惑うのだ。炭治郎なら何でもいいのかと、この節操なしと自分をぶん殴りたくもなる。
『ところで善逸、今ここで言うのは悪いんだが……』
「え」
不穏な気配に善逸は身体を硬直させた。まさかここで別れ話かと、別れようと言ったのは自分からなのに焦りが出る。優勝できるように頑張れと言った舌の根が乾かぬうちにメンタルを揺さぶってくるんじゃないと、戦々恐々しながら次の言葉を待っていると、炭治郎は言った。
『俺の誕生日の件なんだが、祝ってもらうタイミングを逃してしまったので埋め合わせをしてほしい』
「え? 誕生日?」
『そうだ。遠出するって約束だっただろう?』
「そうね……そうだったね」
『行きたい場所ができたんだ。それとプレゼントはもう用意してしまっただろうか?』
「いや、まだかな。決められなくて……」
『そうか! なら欲しいものがあるんだ! それをお願いしたい!』
明るい声の炭治郎に、今まで何の反応もなかったのは何だったのだと善逸は思う。しかし突然の炭治郎に思うように思考が動かない。ただ、誕生日を祝って欲しいと思ってくれていることに、隠しきれない嬉しさが善逸の中には生まれてきている。
「欲しいもの? 俺が用意できるものならいいよ?」
『そうか! 実は善逸にしか用意できないものなんだ!』
「俺にしか用意できないもの?」
まさか炭治郎は我妻善逸をくれと言ってくるのではと善逸は少し焦った。言いかねない。少なくとも大正時代の炭治郎ならば言い出しかねないものだった。しかし——。
『俺と心中してほしいんだ。善逸の命が欲しい』
「へ」
『善逸は俺に言っただろう。死んで生まれ直したいって。だからしよう。俺も善逸と一緒に死んで生まれ直したい。生まれ直して、それから善逸と新しく恋をしたい』
「た、炭治郎さん? 何を言ってるの?」
善逸はダラダラと冷や汗を流した。まさか炭治郎が心中しようなんて言い出すとは思わなかった。確かに死にたいと、生まれ直したいと善逸は思っているけれど、炭治郎を巻き込みたいとは思っていない。だいたい家族はどうするのだ。せっかく平和な世で一緒に幸せに暮らす家族がいるのに、それはどうするのだと叫びたいが、善逸の喉は声を忘れたように固まってしまっていた。
『善逸は今日の夜に帰ってくるんだろう? 急で悪いが明日行こう。善は急げだ! 母さんにも、善逸のお爺さんにも事前に許可は取ってあるから大丈夫だぞ! 』
「いや待って!? 何の許可!? 遠出の許可でしょそれ!!」
『もう切るな! 試合頑張ってくれ! 応援している!』
「待って待って炭治郎! 切らないで!」
そう言って思わず立ち上がった善逸だが、遠くから「我妻ー!! 決勝の招集だぞ!」と言って駆けてくる村田の姿があった。善逸はそれに目を白黒させると炭治郎を止めねばと電話に再度耳をあてた。しかし無情にも通話は切れている。慌ててかけ直そうとするも、村田にぐいっと手を引かれてしまった。
「我妻! 電話しても通話中で焦ったわ! 行くぞ!」
「いやでも、電話が……!」
「後にしろ!」
そう言って村田に引きずられて善逸は、体育館の試合会場に足を踏み入れた。頭の中はぐるぐるしていて、しかし染み付いた習慣で面を装着する準備をしていく。手拭いを頭に巻きながら、善逸はひとまず落ち着けと己に言い聞かせた。
(炭治郎は明日来るって言ってた。炭治郎がしたいのは心中だ。一人で死ぬってことはないだろう。死ぬ前に確実に顔は合わせるんだから大丈夫。考え直せというチャンスはある。遠出で行きたいところがあるって言ってたから、出会い頭に刺されるとかもないだろう。というか心中したいってなに!? どういうことなの!?)
混乱しつつも善逸は準備を完了させた。竹刀を片手に持つと、名前を呼ばれたので立ち上がる。ひとまず今は目の前の試合をこなそう。それで、終わったら一回炭治郎に電話だと考えていた善逸の耳に、対戦者の名前が入ってくる。アナウンスに呼ばれた名前は、ひと月前に決勝で会おうと約束した『嘴平伊之助』だった。そこでようやく善逸はこれが決勝戦なのだと頭の中で繋がる。
(伊之助、決勝まで勝ちあがってっておおおおおお!?)
善逸はふっと視線を伊之助に向けた瞬間、目が飛び出るかと思うくらいに驚いた。面をかぶっているせいで表情がわからない伊之助を善逸は固まって見た。
なぜなら伊之助は竹刀を二本持っているからだ。剣道の二刀流ゆえに、左手に持っているのは短い竹刀の小太刀であるが、二本の竹刀を持つ伊之助の姿に善逸は、前世の伊之助を重ね見た。まさか二刀流に行き着くとは本当に凄い男だと善逸は感心する。剣道の世界で二刀流を扱う剣士は少ない。世界大会まで行くと見受けられるが、二刀流は指導者が少なく、志すのが難しいのだ。なのに伊之助は二刀流。間違いなく我流だと思いながらも、その類稀なるセンスで構えをとる伊之助に善逸は息を呑み、自身も構えをとる。
「始めっ!!」
審判の声を耳にしながら、善逸は伊之助をじっと見つめていた。伊之助から伝わってくる気迫から、期待をしてしまう。自分から攻め込むのは勿体無い。伊之助のひと月の成果をこの目でしっかり見たいと善逸は動かなかった。
伊之助は当たり前のように、善逸に臆することもなく斬りかかってくる。誰もが善逸に攻め込むのを躊躇うのに、伊之助はそんな躊躇いは無駄だというように、むしろワクワクすると踊るように斬り掛かってきた。
(うそお! 本当に全集中の呼吸を習得したのか……!!)
斬り掛かってくるスピードが以前と段違いだ。しかし善逸は難なくそれを受け止めて退ける。そして自身も伊之助に斬り掛かれば、小太刀に防がれ、右の太刀でその隙を狙われた。だが当たるよりも早く、後ろに下がり空を斬らせる。そして空ぶった伊之助の喉元を狙い突きを繰り出せば、伊之助は寸前で首を逸らして躱し切った。本気の速さでやれば殺してしまう可能性があるので、確かに速さは緩めていた。しかしそれでも見切って避けた伊之助に善逸は高揚してくる。昔、伊之助に追い回されて嫌々やった鍛錬を思い出す。伊之助の容赦ない打ち込みにヒイヒイ言っていたことを思い出す。
(このっ……!)
善逸と伊之助は一進一退というような攻防を続けていた。どちらも決定打にならないが、尋常ではない攻めの応酬だ。審判はちょっと目が追い付かないというような感じで紅白の旗を上げかけては下げるというのを繰り返している。観客も皆、今までと違う試合展開に固唾を飲んで見守っていた。お互いが持っている竹刀はまるで真剣だと言わんばかりに完全に避けるのだ。一撃でも食らえば死ぬというかのようなやり取りに皆の意識が二人に注がれる。
当の二人はといえば、ただただ楽しんでいた。伊之助は強者との戦いに、善逸は伊之助の成長と懐かしさを同時に喰らって心がふわふわとしていた。
楽しい。もっともっとと言うように二人はどんどんと集中していく。感覚が研ぎ澄まされていく。伊之助が善逸の攻撃を躱せているのは触覚の鋭敏さがあり、善逸の聴覚が普通であるからだった。そのアドバンテージがこの試合展開を許していた。しかしそれも長くは続かない。全集中・常中を会得している善逸と、全集中の呼吸を会得したばかりの伊之助では、天と地ほど経験が違うのだ。だんだんと呼吸が続かなくなるのを伊之助は感じ取っていた。このままでは負ける。そう思い、楽しい時間を終わらせて決めなければならないと伊之助は大きく打って出た。
(弍ノ牙! 切り裂き…!!)
正確に言うと形は違った。しかし二本で面を狙ってくる伊之助の動きに、善逸は脅威を感じた。そしてシィィィィと息を吸い込み、瞬時に中段構えを腰元まで引き、踏み込み、振り下ろされる竹刀が自分に届くよりも速く、伊之助の胴に当てて——そのまま伊之助を場外へと吹き飛ばした。
****
「おはよう善逸! 優勝おめでとう! 二連覇なんて本当に凄いな!」
八月九日の夏日が眩しい朝、善逸の家を訪れ、部屋まで自分を起こしにきた炭治郎にそう言われて、善逸はヨヨヨと泣いた。それに炭治郎が「大丈夫か!?」と心配して背中を撫でてくれる。
「死にたい……」
「どうしたんだ?」
「伊之助があああ」
「伊之助なら大丈夫だ。骨折した肋も新学期までには完治するそうだから」
炭治郎のその言葉にますます善逸は泣いた。伊之助に申し訳ない。そんな気持ちが込み上げて、善逸の心をぺしゃんこにするのだ。ひぐひぐと泣く善逸にひたすら炭治郎は「大丈夫だ。伊之助は怒ってないよ」と慰めてくれる。
昨日のインターハイ個人の決勝戦。善逸は伊之助に勝利した。伊之助の面が入るより早く竹刀を振った善逸は伊之助の胴に強かに打ち込み、そして伊之助を吹き飛ばした。まともに胴を喰らったのは誰の目にも明らかであったが、吹き飛んだのに動転し、さらには打ち込まれた側の防具が損傷していて、伊之助は肋を痛めるという事態になった。
その後のことを善逸はあまり覚えていない。伊之助がヨロヨロしながら蹲踞をしに戻って来て、お互いに礼をしたのは覚えているが、以降のことはほとんど記憶がない。誰かに手を引かれながら体育館を出て、しかし優勝した証のトロフィーは持って帰って来て家にある。自分は表彰台に上がったのだろうか? それとも顧問が貰ってきてくれたのか分からない。だが帰りの新幹線に乗る前に、伊之助の剣道部の顧問から、善逸の剣道部の顧問に連絡が入り、『嘴平伊之助は肋を二本骨折した』というのを聞いた。変に折れていることもなく、臓器を損傷してもいないという報告だった。
そこから、善逸はあまり寝れなかった。夏の最中の大会で、すべてが終わってそれなりに疲れている筈なのに新幹線の中で一睡もできなかった。隣に座る村田が「ちょっと寝たら?」と明らかに心配した声を掛けてくれたが、なんて返事をしたかも善逸は覚えていない。ただ頭の中で吹き飛ぶ伊之助がスローモーションで繰り返されていた。そして周りの驚く目。いや、驚く目は善逸の妄想だ。善逸は崩れ落ちる伊之助しか見ていなかった。しかし周りの目はきっと自分を恐ろしいものとして見ただろうと漠然と善逸は思うのだ。
「……死にたい。もう嫌だ……」
「善逸……」
善逸は炭治郎に縋り付いた。昨夜、日が沈み切ってから自宅に帰って来た善逸を迎えたのは慈悟郎だった。善逸から優勝したとも、負けたとも連絡がなくどうしたのかと思っていたが、顧問が善逸を連れて帰って来たので、その場で顧問から事情を聞き、慈悟郎は善逸に炭治郎と同じように「大丈夫だ。嘴平君は強い男だからそんなにしょげ返るな。落ち着いたら見舞いに行こう」と言って頭を撫でてくれた。
その晩、善逸は伊之助への申し訳なさと、世界の誰かへの申し訳なさでいっぱいだった。だから炭治郎に電話をすることも忘れて、言われるがまま風呂に入り、味のしないご飯を食べ、早々にベッドに入った。ぶるぶる震えていたらいつの間にか眠りに落ち、そして翌朝の六時という早い時間に炭治郎がやって来たのである。
善逸が冷静であれば「ちょっと早すぎない?」と言えたであろうが、今はとことん参っていた。だから慈悟郎に家に上げてもらい、部屋まで来て善逸を眠りから起こした炭治郎に、善逸は縋り付いてしまうのだ。
「お、俺なんか生きてたってしょうがないんだ……」
「……そんなことないぞ?」
「いや違う。記憶なんてあるからダメなんだ。俺がいなけりゃ、伊之助は怪我しなかったし、あいつが優勝してた。俺はずるい奴だ。みんな頑張ってるのに、俺だけズルしてるんだ……死にたい。いなくなりたい……」
「そうか。じゃあ今日は本当に丁度いいな。ほら善逸、着替えて行こう」
善逸は炭治郎に促されるままに着替えをして、鞄に財布とハンカチとスマホをいれた。そして「暑いから帽子を忘れるなよ」と炭治郎が言うのでキャップ帽を被り、家の外へ出る。
「それじゃあ、善逸をお預かりします」
「うむ。二人とも気をつけてな」
「……」
善逸は炭治郎に手を引かれて歩き出した。朝日が眩しくてクラクラしそうだなと思っていると、炭治郎が「朝ご飯がまだだろう」と言って握り飯を出してくる。それを見て、こうして炭治郎と連れ立って歩くのに善逸はデジャビュを感じた。
「……炭治郎が握ったの? お前のは?」
「いや、母さんが用意してくれた。俺のもある」
そう言ってまた出てきたお握りに、善逸のデジャビュは消える。気のせいだった。この男は竈門炭治郎であるが、『竈門炭治郎』ではないのだ。善逸がずっと好きだと想い続けている前世の男ではない。もしかしなくても、今の時代なら米を炊くのは炊飯器かもしれない。
「炭治郎って炊飯器以外で米炊ける?」
「土鍋ご飯ってことか? 炊けないなあ。というか、俺はパンしか作れないな。カレーくらいは作れるが……善逸は料理できるんだよな?」
「人並み程度な」
二人で炭治郎の母親が作ったお握りを食べながら、けれど手は繋いだままで駅までの道を歩いた。どこに行くかは知らないが、炭治郎に連れられるままに電車に乗る。炭治郎もとっくにモバイルのICカードを使用しているので、行先の見当すらつかない。善逸はただ導かれるままに炭治郎の後をついていく。
「どこ行くの」
「まだ内緒だ」
二人は並んで電車に座ると、炭治郎は優しく善逸の手の甲を撫でてくれる。そしていつもは善逸がテレビのことや雑誌のことを話すのに、この日は炭治郎がたくさんの話をしてくれた。だいたいは家族のことで、最近あった面白かったことや、茂の少年野球のこと、禰豆子が久しぶりに卵焼きを焦がしたとか色んな話があった。
それを善逸は思考停止したまま「うん、うん」と聞いている。炭治郎の肩に頭を寄せ、暑いのにぴったりとくっつき、手を撫でられながら聞いた。
善逸にとってはこの体勢は馴染み深いものなのだ。何しろ前世では鬼との戦いが全て終わった後、よくこうして縁側で二人で並び座り、手を繋いで寄り添いあっていた。あの時は炭治郎は左手の機能を失っていたから善逸は右側に座っていた。今は炭治郎は左手が元気なので善逸は左側に座っている。
炭治郎が五体満足だ。その事実に善逸はとても救われた気持ちになる。しかし救われているのは勘違いなのだ。何しろ右目と左手を失った炭治郎は、その機能を取り戻すことなく死んでいるのだから。生まれ直したらもう、前世の竈門炭治郎ではない。新しく、一人の人間として確立されている竈門炭治郎なのだ。重ね見ることすら本当は失礼だ。
「善逸?」
「うん……」
「もう少しで降りるからな」
「うん……」
善逸は車窓から見える海の反射に目を細めながらも、炭治郎の左手を見つめていた。自分の右手の甲を撫でてくる炭治郎の左手と左腕を善逸はなんとはなしに触れて撫でる。皺皺ではない、きちんと動くその腕に善逸は胸の奥が痛む。懐かしむ気持ちと、切ない気持ちと、良かったという気持ちと、申し訳なさでぐちゃぐちゃになり痛むのだ。
「善逸、大丈夫だ。今日できっと全部が終わる。俺たちは死んで生まれ直すんだ」
善逸の感情を嗅ぎ取っているのか、炭治郎はそう言って善逸の肩を抱きしめた。炭治郎の左手と善逸の右手は繋がっているので、炭治郎は向かい合うように右手で抱きしめてくる。途中で電車を乗り換えて、ボックス席に座っていなければ奇異な目で見られただろう。だがここにはまるで善逸と炭治郎しかいないように感じてしまう、区切られた場所だ。善逸は炭治郎に抱き寄せられるまま身を預けた。
(もうどうでもいい。何も考えたくない)
善逸はそう思って目を閉じた。浮かび上がるのは吹き飛ぶ伊之助と責める周りの人間たちだ。伊之助以外はただの被害妄想だが、善逸はそれが真実だと思い込んでいる。ずっとずっと心の奥にあった罪悪感だ。記憶があるから、ほかの同世代よりも抜きん出てしまう罪悪感だ。褒められるたびに善逸は言い訳したかった。けれどできない。前世の記憶があるからなんて言えるわけがない。
(俺は今日、炭治郎と死ぬんだ……。生まれ変わって今度こそ……炭治郎と何もなく出会い直したい……)
****
「とか言ってる場合じゃねえええええ!」
「なんだ? ようやく目が覚めたのか?」
「覚めた覚めた! 炭治郎、お前! 昨日の電話で何を言ってくれてんの!?」
到着したのは海辺の街だった。しかし奥に行けば渓谷があるらしく、滝も見られるらしい。そんな観光地に来た善逸と炭治郎の二人はまずは腹拵えと地元の海鮮丼を食堂で食べた。
お握り一個しか食べていなかったので、満腹になり頭に十分なエネルギーが回ってきた段階で、善逸の思考はようやく回り始める。そういえば昨日の夕飯も殆ど食べなかったのだったと思い出した。
「何ってなんだ?」
「心中! 心中しようとか言ってただろ!?」
きょとんとする炭治郎に、善逸が噛み付くように言えば、炭治郎はにんまりと笑う。その笑顔が初めて見るもので、過去の記憶にもないもので、善逸はドキリとしてしまう。
「言ったぞ。でも善逸が言ったんだろ。死にたいって。生まれ直したいって」
「言ったけど……それがなんで心中になるんだよ。炭治郎は死んだらダメだろ!」
腹ごなしというように、二人で誰もいない砂浜を散歩がてら歩きながら話をする。今の今まで善逸は正気を失っていたので流されるままであったが、死んでいいわけがない。特に炭治郎はダメだろう。百歩譲って善逸が自殺を図ったとしても、それに炭治郎を巻き込むわけにはいかない。炭治郎は父親を失った竈門家の大黒柱であり、そうでなくとも幸せに生きるべき存在だ。死ぬなんて許されないし、許したくもないと善逸は憤った。
「俺はダメだって言うけど、じゃあ善逸は一人で死ぬのか? 善逸が死んだ後の世界で俺に一人で生きろって言うのか?」
「いや一人じゃないだろ。お前家族いるじゃん」
「もちろん家族はいるぞ? けどその家族だって、人と人が出会って、お互いを唯一にするって気持ちで作り上げていったものだろう? 父さんと母さんはそうだった。俺は父さんと母さんがそうしたから生まれて竈門家の家族の一人なんだ。だったら俺が同じように、唯一の人を見つけて生きようとしてもおかしいことじゃないだろう」
「ええと……つまり……?」
「俺はいつか善逸と新しい家族になりたい。父さんと母さんみたいに、俺と善逸でお互いを唯一の相手にしたい」
「え……それ、本当にマジで言ってるのか? 前も家族になりたいって言ってたけど……本気で?」
「そうだ! だから善逸だけ死なれると困る! 俺はもう、お前しか見ないぞ! 断言する! 善逸に置いて逝かれたら俺は一生、生きる屍だ!!」
人の少ない海でそんなことを叫ぶので、親子連れで砂場遊びをしている人達がぎょっとした顔で二人を見るが、善逸も炭治郎も二人の世界なので全く気がついていなかった。善逸は炭治郎のまさかの覚悟に絶句だ。
(令和の世になってもそんな一途な考え方をしているのかこいつは……。マジか……)
善逸はそう思いながら、これはマズいと冷や汗を流す。まさか本当に炭治郎は死ぬ気ではないだろうかと不安になってくる。この竈門家の長男としての自負が強い男が心中なんてするわけないと思っていたのだが、見誤っていたのだろうかと善逸は怖くなってきた。
よくよく考えれば、善逸と炭治郎が仲良くなったのは最近なのだ。ここ数ヶ月の話だ。けれど善逸は前世の炭治郎を知っているから、今世の炭治郎もよく知っている気になってしまっていた。だがそれは勘違いだ。前世と今世ではやはり違って当たり前なのだ。炭治郎がパン以外を作れないように、炊飯器でしか米が炊けないように、違って当たり前なのだと善逸は今ようやく本当に理解をした。今までは違って当たり前だなんて気取って理解している風を装っていたに過ぎなかったのだ。
「た、炭治郎。まずは落ちつこうぜ。やっぱり、心中はよくない」
「ん? 怖くなったか?」
「うん。怖くなった。やめようやめよう。俺もなんか寝て、飯食って腹膨れたら元気になってきたし! いやーやっぱ腹が減ってると気が滅入るよな!」
そう言って別の所に行こうと歩き出した善逸を、炭治郎が腕を掴んで引き止めてきた。それに善逸は固まって炭治郎の方をゆっくりと振り返る。
「炭治郎?」
「善逸。誕生日プレゼントだ」
「は?」
「俺は誕生日プレゼントとして、善逸の命をくれって言っただろう? 心中をするぞ」
「えええええええ!?」
そうだった。誕生日プレゼントとして要求されているのだったと善逸は思い出す。そしてなぜ炭治郎はそんなに心中をしたいのか善逸には分からない。死にたがっていたのは自分であって、炭治郎ではない。ならなぜ炭治郎は善逸がやめようと言っても心中したがるのか。
「え!? なに? 炭治郎って実は自殺願望があったの!? やめとけやめとけ! あんな素敵な家族がいるんだぞ!? 馬鹿なことは考えなさんな!」
「いや、自殺願望なんてこれっぽっちもない」
「じゃあなんでよ!? なんで死にたがるのよ!!」
詰め寄った善逸に、炭治郎は真顔であった。いつも穏やかな表情を浮かべる人間の感情を削ぎ落としたような真顔は辛い。善逸はヒッと喉を痙攣らせるが、炭治郎は遠慮なく距離を縮めて、善逸の蜂蜜色の目を覗き込んできた。
「な、なに……?」
「……今の善逸は誰を見ている?」
「この距離でなにを言ってんのよ。炭治郎しか見えてないわ。物理的にそうだろ」
「本当か? 俺の向こうに前世の『竈門炭治郎』を見てないか?」
炭治郎にそう言われて、善逸は息を止めた。初めて炭治郎に責められた気分になる。そして耳の良さを失った善逸でも、今の炭治郎の感情は理解できた。その目が、奥底に炎を燃やす炭治郎の目が教えてくれる。炭治郎は前世の自分……いや、大正時代の『竈門炭治郎』に嫉妬しているのだ。
「……善逸は昔の竈門炭治郎と今の俺を混同し始めてるって言ってたな。昔の記憶がどんどんと上書きされていくみたいだって」
「うん……? 言ったかな……?」
「正直言って、俺としてはそのままどんどん上書きしていって昔の男のことなんて忘れ去ってほしい」
「おお……」
「善逸の中の竈門炭治郎は俺だけで十分だ」
「ひえっ……」
「でも完全に忘れるのは難しいだろう? 善逸は忘れるのに困惑しているし、自分が何者かも分からないって悩んでいるんだ。俺だけが嬉しくても、善逸が苦しいならそれは良くないことだ。俺は二人揃って幸せな気持ちになりたい。だから死んでやり直そう。生まれ変わって、お互いに真っさらになって出会い直そう」
炭治郎は覗き込んでいたのを止めると、一歩離れた。しかし腕は掴まれたままだ。そしてその腕を引かれて、善逸は再び連れられるままに歩き出す。前をゆく炭治郎は歩みを緩めることもなく前を見てどんどんと進んでいく。その迷いのない足取りに善逸は焦った。どこに行く気だろうかと汗が噴き出す。
「待て! 待て待て! 早まるなよ!」
「早まってない。よく考えたんだ。善逸と会わない間、ずーっと考えていた。どうするのが一番いいのか、考えに考え抜いた末の結論だ」
「ひええええええ! 考えてこれかよ!! ダメだって! 禰豆子ちゃんも、葵枝さんも、炭治郎の家族全員が泣くぞ!! 俺だって爺ちゃんに何も言えてない!」
「大丈夫だ。母さんに同意はもらってるし、禰豆子たちも楽しんでこいって送り出してくれたから」
「えっ!? 電話でも言ってたけど許可もらってるって心中の許可なの!?」
「善逸のお爺さんにも説明済みだ。ちゃんと同意は貰っているぞ!」
「うっそでしょ!? 爺ちゃん許可したの!? 心中の!? どういうこと!? 何を言ってんのよ炭治郎!! やだやだ! 海で心中なんていやああああ! ぶっくぶくに膨れ上がるし苦しいじゃん! 死ぬならひと思いで逝けるのがいい!」
「落ち着け善逸。ここが目的地じゃない。バスに乗って山の方まで行くぞ」
「あ、そうなの? 入水自殺じゃないんだ……」
「海は洒落にならないからな」
「は? 洒落にならないって……」
「あ! バスが来てるぞ! あれだ! 走るぞ善逸!!」
そう言った炭治郎に腕を引かれて善逸は走った。バスの行き先は分からないが、車中には若いグループが多い。その中に混じりながら二人は出発間際のバスに乗り込んだ。善逸はどうしようと思うけれど、炭治郎は動揺も恐怖もないのか黙って善逸の腕を掴んで吊り革に掴まっている。
「十五分くらいらしいぞ」
「そうなの……?」
俺たちの命って下手したら三十分未満でなくなるの? なんて不安になる善逸だったが、バスが進むにつれて少しずつ少しずつ周りが見えてきた。バスの中に、とある広告がぶら下がっている。そしてそこに書かれたカップルという文字列と周りにいる男女の組み合わせ。車中にいる人が話している「怖ーい! 大丈夫かなぁ……すっごく高いんでしょ?」という言葉。そして炭治郎がさっき言った『海は洒落にならない』という台詞と双方の家族から同意をもらっているという発言。
(……あれ? これってもしかして……)
まさかまさかと思いながらバスから降りた善逸は、炭治郎に連れられるままに五分ほど歩いた。他のバスにいた人達も同様の方向に歩いていて、そして渓谷の橋の辺りに差し掛かった頃、善逸の普通の耳は「きゃああああああ!」という叫び声を捉える。視線の先には渓谷に架かる大きな橋があり、その橋の上にはなんらかの施設があるのか、不自然に人の列ができていた。そこから悲鳴が聞こえているようで、善逸はまじまじと見る。
(あれバンジージャンプじゃん!)
善逸はバンジージャンプ台を初めて見た。テレビのバラエティなどで見かけることはあれど、実物を拝むのはこれが初だ。並んでいる人たちに近づいて行くのに、これはもしやという感情が善逸の中で生まれる。
しかし炭治郎はそちらを見ることなく、足取りを一切緩めず列を無視して前に進んでいく。それに善逸は「違うのか!?」と焦った。目の前にバンジージャンプが現れたので、心中というのは炭治郎のジョークであって、バンジージャンプをするのではないだろうかと淡い期待を善逸はしたのだが、本当に期待で終わってしまった。善逸は「怖えー! マジで怖えー!」とキャッキャしている列に並んでいる若いグループの人達に殺意が湧く。
(お前らはいいだろ!! 安全装置付きなんだから! こちとらマジで投身自殺の可能性あるんだぞっ!?)
善逸は炭治郎がどうやって心中するつもりなのか分からず戦々恐々だ。痛いのは嫌だ。怖いのも嫌だ。そもそも炭治郎を死なせるのも嫌だ。善逸はいつの間にか繋がっていた手のひらを握りしめると、やめようという気持ちを込めて炭治郎の腕を軽く引く。優秀な鼻があるというなら、気持ちが分かるだろうと鼻に情を訴え掛けた。だがそれも無視して炭治郎は進んでいく。なんでこんなに人気なんだというくらい、バンジージャンプは盛況だ。外国人もいるようだと善逸が流し見ていると、炭治郎は施設の受付近くに来て急にカクンと方向を変えた。
「えっ」
炭治郎はズンズンと進んでいき、バンジージャンプの列の真横にある『WEB予約』と札に書いてある場所で立ち止まった。
「WEBからの御予約の方ですか?」
「はいっ! 竈門と我妻です!」
「高校生の方ですね。保護者の同意書お持ちですか?」
「あります」
そう言って炭治郎は善逸の手を離すと、ボディバッグから紙を二枚取り出した。それには『ラブ♡バンジー 同意書』と書かれていて、それぞれ保護者同意のサイン欄に『竈門葵枝』、『桑島慈悟郎』の名前がある。それに善逸は真っ青になった。大変だ。結局はバンジージャンプを飛ぶらしいと血の気が引く。
「ではどうぞ〜」
同意書を受け取った受付のお姉さんはすかさずそう言った。炭治郎が善逸の腕を取り、列を無視してバンジージャンプの施設に進む。もう目の前にバンジージャンプの飛び降りる場所があり、なぜか当然のように炭治郎と善逸が迎えられる。
「いや待って!? なんでこんな早いの!? 人いっぱい並んでるじゃん!?」
「あちらは予約なしのスタンバイ列です〜」
「俺たちはWEB予約してあるから、すぐに飛べるんだ! 凄いよな!」
爽やかに笑う受付のお姉さんと炭治郎に善逸はもうパニックだ。心中するぞと言われて連れて来られたのに、気がついたらバンジーを飛ぶことになっている。これはなんなのだろうか、バンジーは最後のレジャーで飛ぶのか? これをした後に心中をするのか? それとも、心中はジョークなのか? しかし炭治郎はそんなジョークは言わないだろう。さっきの海岸の炭治郎は本気の目だった。
善逸が混乱している間にも準備はどんどん進んでいく。ハーネスを取り付けられ、お姉さんがバンジージャンプの諸注意をしていく。善逸はそれを右から左に聞き流しながら、ちらりとバンジー台の下を見た。高い。物凄い高さだ。
(え? 飛ぶの? これ飛ぶの!? 本気で飛ぶのか!? 炭治郎もお姉さんも当たり前みたいな顔してるけど飛ぶの!? 本気で!? というかこれは何なの!? 最後の晩餐ならぬ最後のバンジーなの!? これを飛んだ後に心中するの!? いるこれ!? 心中前の度胸試しいる!? もしかして勢いつける練習なの!? 心中って投身自殺なの!? 投身自殺する前にバンジーで予行練習しようってか!?)
善逸はゼエハアと息が荒くなる。久しぶりにくる極度の緊張と恐怖に膝が震えている。大変だ。どうしよう。助けて炭治郎というように隣に座る炭治郎に縋りつけば、炭治郎は宥めるように善逸の肩を抱いただけだった。
「説明は以上です。ご不明な点はありませんか?」
「大丈夫です!」
「いやいやいや! 何一つも大丈夫じゃねーわ!! なんだこれ!? なんでバンジー!? 心中するってのどこいった!?」
我慢ならず善逸が立ち上がって叫べば、その声は渓谷に大きく響いた。受付のお姉さんも並んでいる人たちも、心中という不穏なワードに驚いた顔をしている。しかし炭治郎はなんの変化もなく、きょとんとした顔で善逸を見上げて、そして言った。
「どこいったって……ここで心中するぞ? 今からバンジージャンプして、俺たちは死んで生まれ直すんだ」
「バンジージャンプは安全設計されてるから人は死なねーんだよ!!」
「そうだな。だからこれを選んだんだ。擬似的に死を体感するのに一番安全なのはバンジージャンプだからな」
……。
…………。
………………。
「擬似的に…死ぬの?」
ポカンとした表情をする善逸に、炭治郎は笑った。その表情に、善逸は本当に死を予感していたのだろうと炭治郎はひとまずここまでは成功だと頷く。まさか本当に二人で心中するなんてできない。死んですぐにその場で蘇る手段があるなら少し考えてもいいが、そんなゲームみたいなことは起きない。死ねば全てがおしまいだ。色んな人を悲しませる結果になるし、そもそも炭治郎は来世の善逸と幸せになりたいのではない。来世も一緒になれるならそれは万々歳だが、今世を棒に振るのは嫌だ。今世は今世で善逸と幸せになりたい。
「な、なんだよおおお! 脅かすなよ炭治郎! 心中するって言うから……俺本当にどうしようかと思ったのにぃ!!」
善逸はそう言って脱力し、蹲み込んだ。その目は潤んでおり、善逸のことだから残される人をどうするかとか、どうやって説得して止めさせるかとか色々考えていたのだろうなと、炭治郎には手に取るように分かる。
「ごめん。先に説明したら、遊びの気分になってしまうかと思って」
「……遊びの気分?」
「そうだ。善逸、確かにこれは本当には死なないが、俺としては死んだと思って飛ぶつもりだ」
真剣な顔でそう言った炭治郎に、蹲み込んで頭を抱えていた善逸が不思議そうに顔をあげた。
「んん? どういうこと?」
善逸は分かりませんというように、炭治郎を見上げている。その表情の幼さに炭治郎はじんわりと胸が熱くなってきた。可愛らしいと言って腕の中に閉じ込めてしまいたい。自分だけのものだと、隠してしまいたいがまだそれをする権利が炭治郎にはない。まず先にするべきことがある。
「冗談でなく、一回死んだ気になりたい。俺たちはここで宙に舞って落ちて、死んで生まれ直すんだ。区切りをつけよう」
炭治郎の説明に善逸はパチリと瞬いた。二人の周囲にいるスタッフや他のお客さん達は、男子高校生達の心中やら、死ぬやら、生まれ直すやらという単語にザワザワしている。本来なら飛ぶのに時間がかかるなら、覚悟ができるまで他所に移動してほしいところだが、真剣な様子の二人に誰も声が掛けられない。しかしそんな周りの状況は炭治郎も善逸も全く目に入っていなかった。
「区切り?」
善逸の疑問に炭治郎は力強く頷く。そうだ。区切りだ。ここで二人でバンジージャンプをして、生まれ直すのだと炭治郎は強く思った。
「そうだぞ! 善逸の中にいる過去の善逸には、ここで死んでもらう! そうしてお前は、今を生きる『我妻善逸』になるんだ。善逸の過去と今をここで切り離すんだ!! すみません! 飛ぶ準備お願いします!」
「あっ! はい!」
炭治郎の言葉にスタッフのお姉さんが慌てて追加の道具を持ってくる。善逸はいまいち理解が及んでいないのか、目を白黒させて炭治郎を見ていた。炭治郎は蹲み込んでいる善逸の腕を引き上げるとぎゅうっと強く抱きしめる。それによって思考が戻ってきたのか、善逸が「ちょっと待てええええ!!」と近距離で叫び声をあげた。
「待て待て待て!! 何となく言いたいことは分かった! 死んで生まれ変わったつもりで最初からやり直すってことだな!?」
「そんな感じだ」
「だよね!? でもそれでなんで心中ごっこになるのよ! 炭治郎は飛ぶ必要なくない!? いや、俺一人飛ぶのとかクッソ嫌だから道連れにはしたいけどね!?」
善逸の指摘に炭治郎は笑った。確かに一人飛ばせるのは酷だろうというのもあるが、炭治郎が飛びたいのだ。善逸と一緒に。それにはちゃんとした訳がある。炭治郎は善逸をもう一度強く抱きしめて、そして少しだけ腕を緩め、半歩分距離を開けた。そして善逸の蜂蜜色の目を見て大きな声で、渓谷中に響かせるように叫ぶ。
「善逸!! 俺はお前を愛している!!」
「ひぃ!! 声がでけえっ!!」
「俺はずっと善逸のことが好きだ! お前がうちのパン屋に初めて来た時から、ずっと俺は善逸を見ていた! 善逸は自分に前世の記憶があるから、前世の恋人だった俺を見て思うところがあり、特別な匂いが……俺の気を惹くような匂いが出ていたんだと言ったな!」
炭治郎の言葉に、その場にいる全員が「どういうことなの!?」と騒然とした。善逸はここでそんなことを叫ぶのかという気持ちで、他の人達は男子高校生が愛の告白をかまし、さらには前世とか言い始めたので騒然だった。興味が加速するばかりだ。しかし炭治郎は気にしない。いま善逸に伝えるべきことを伝えるだけだ。
「確かに俺は、善逸の匂いに惹かれたと言っても過言じゃない! だってしょうがないだろ! 店に来て俺を見た瞬間に甘い匂いをさせたんだぞ!? 凄くいい匂いだった! なのに次に来た時には悲しそうな、寂しそうな匂いをさせてるんだ! それは気になるだろう!? 俺だって匂いが切っ掛けじゃないと言いたいが、それはできない。俺は確かに、善逸に匂いで惹かれたんだ! だけどその後は違う! 善逸と仲良くなって、友達になって、善逸の内面を知っても、善逸が抱える辛さを知っても、俺はずっと善逸が好きなままだった! むしろどんどん好きになった! だから切っ掛けはなんでもいいんだ! 今の俺が善逸を好きで、愛してることを分かってほしい! その愛を証明する為に、俺は善逸と一緒に飛ぶ! 俺も善逸と一緒に死んで生まれ変わるぞ!! 俺はお前を一人で逝かせはしない!!」
炭治郎の愛の叫びに場はしーんとなった。周りはもう固唾を飲んで見守っている。スタッフの女性も追加の器具を両手に持ちながら二人の前に立って、これをいつ装着すればいいのかと機会を窺っていた。愛を叫んだ側は真剣な目で相手を見ていて、愛を叫ばれた側は呆然とした顔をしていて……ポツリと涙とともに言葉をこぼした。
「……炭治郎、お前……馬鹿じゃないのか? ここで飛んだって、本当に生まれ変わるんじゃないんだぜ? 俺の中にある前世の記憶だってなくならないだろ……」
そう言いながらも、善逸はぺたりと炭治郎に自分から抱きついた。それを炭治郎は大丈夫だというように抱きしめる。背中を撫で、頭を撫で、自分の肩口で泣く善逸にキチンと言葉にもして伝えた。
「大丈夫だ、善逸」
「……何がよ」
「飛んでみて、それでも前世の竈門炭治郎が忘れられないなら、俺がそいつよりもいい男になって善逸に好きになって貰えばいいだけだ。だから大丈夫だ。善逸はずっとここに居てくれ」
炭治郎は絶対に手放さないと善逸を抱きしめた。善逸がいる場所は自分の腕の中だ。一人で過去の男を追いかけるのは止めてほしい。忘れられなくてもいい。しょうがないのだ。前世の記憶があるのが、今世の善逸であって、自分が好きになった善逸なのだと炭治郎はちゃんと受け止めている。そりゃあ昔の男を見るのは腹立たしい心地もあるが、その記憶がなければ自分たちはこうしてここに立っていなかったかもしれない。ただの常連客とパン屋の店員で終わっていたかもしれない。いや、そもそも善逸は常連客になっていなかったかもしれないのだ。だから炭治郎は善逸の前世の記憶が嫌だなんて思わない。出会ってくれたことに感謝をするだけだ。導いてくれた記憶に感謝をするだけだ。
「……善逸、いいか?」
「……いいよ。お前も道連れなら」
顔を隠したまま言う善逸に、炭治郎は笑った。そしてスタッフに目をやると、顔が真っ赤になっているのでどうしたのかと思いながら「お願いします」と声をかけた。スタッフのお姉さんはハッとして抱き合っている二人に、丁度いいとばかりに「そのままの体勢でお願いします」と言って、追加の器具を装着していく。抱き合っている二人のベルトをしっかり繋げる器具だ。二人をガッチリと固定して、二人一緒に飛べるようにするもので、これがここの目玉である『カップル専用ラブバンジー』だ。
「これで準備できました! えと、もう飛ばれますか?」
「飛びます!」
「え!? 嘘でしょもう!?」
「後ろが詰まってる! 早く飛ばないと迷惑だぞ?」
めちゃくちゃ時間を掛けといて今更だなと、スタッフも並んでいるお客さんも思ったが、いい感じでまとまっているのでチャチャは入れない。みんな何しろ大学生以上の人達だけだ。男子高校生カップルのやり取りを微笑ましく見守っていた。
「ええええ!? うそうそ! 怖い怖い! 高いじゃん!!」
「大丈夫だ。俺も一緒だから。そうだ善逸。ちゃんと目を開けて飛ぶんだぞ。そっちの方が死ぬ感覚がリアルに感じられると思う」
「ふざけんな! 目なんて開けてられるかよ!! たんじろおおおおお! 俺を守れよおおおおおお!?」
「安全性は保証されてるから守る必要ないだろ?」
「俺の心を守れって言ってんのよ!! 怖い怖い怖い!! いやいやいやあああ!! 引きずって進まないで!! 落ちる! 落ちる! 落ちるからっ!!」
「そ、それでは行きますよー? 宜しいですかー?」
「はいっ!」
「よくねえええええ!!」
「3、2、1……ラブバンジー!」
「善逸うううう! 好きだぞおおお!! 死んで生まれ直して一番最初に善逸に会うのは俺だああああああああああ!」
「ぎゃああああああああああ!! 助けてええええええ!!」
八月九日
天と地が引っくり返る。痛いくらい股に食い込むハーネスと空気を破る感覚に、落ちているのが分かる。見開いた眼球からは確かに涙が出ているのに、乾いていく感覚ばかりだ。けれど股の痛みや眼球の乾きではなく、抱きしめてくる温度と、合わさった胸から感じる心臓のリズムが、俺の感覚を一番奪っていた。
「善逸、まだ歩けないか?」
「歩けない……歩けねーよ!! 歩ける訳ないだろ!!」
善逸はそう言って、しっかりと炭治郎に抱きついていた。二人はバンジージャンプの施設横にあるベンチに座っていて、善逸は炭治郎の膝の上に向かい合って座り子供のようにしがみついている。炭治郎はそんな善逸の頭をひたすら撫でている感じだ。そして二人の横には缶ジュースが四本、お菓子がたくさん積み上がっていた。
それは二人がバンジーを飛び、死んで生まれ直し、上からウインチで引き上げられた後、こうしてベンチで善逸の回復を待っていたら後に続くお客さん達が帰る前に二人にと置いていくのだ。皆一様に笑っていて、「頑張れよ!」とか「おめでとう!」と言っていく。炭治郎はとりあえず祝福されていると理解して、律儀に「ありがとうございます!」と返しているが、善逸は死にたい気分だ。腰が抜けてさえいなければこの場から走って逃げ出したい。けれど高いところから落ちた恐怖で全然足腰が立たないのだ。
「ううっ……もう二度としねーわ……」
「そうか」
「だいたい何だよこれ。本当に死んだわ! 死んだ死んだ! ねえねえ炭治郎!! 俺の足ちゃんとついてる!? 本当は死んで俺たち幽霊になってたりしない!?」
「ちゃんと善逸の足はついているぞ! 大丈夫だ! 俺たちは生きてる!」
「本当に!? ちゃんと生きてる!? めっちゃ俺たち川に向かって落ちてたよ!?」
「生きてるぞ! 正直俺も飛んでみたら思ったよりも怖くて、これは死んだと思ったがちゃんと生きてるぞ!」
「本当!? 良かったよ炭治郎おおおお!! 俺たち生きてるよおおおおお! 死にたくないよおおおおお! 俺もう死にたいとか言わないよおおおお!」
「そうだな。生きてて良かったな」
炭治郎はデレデレとしながら善逸を膝の上に乗せている。善逸はというと恐怖で涙まみれで、鼻水も止まらないのだが。しかし生きているという、生の実感に思った以上に感動もしていた。恐怖は大きいが感動もキチンとあった。
善逸は生まれてこの方、『死んでしまう!! 』という思いを感じたことがなかったのだ。前世の大正の世ではそれこそ奉公先の旦那にぶん殴られたり、折檻されたり、働き口のない冬なんていつも死んでしまうと善逸は思っていた。鬼殺隊に入ってからそれは加速して、任務だけではなく、鍛錬中だって死にそうだった。善逸はいつだって死にそうになりながらも、生き残る快感と喜びと次の任務で起こりうる死への恐怖で感情を揺れ動かしていた。
(はあー……。今の世の中ってまじで平和なんだな……)
しかし生まれ変わって令和の世。善逸の人生は実に平穏なものだった。孤児として生まれてもしっかりと育ててくれる施設に恵まれ、育ての親にも恵まれ、寒さや飢えで死ぬこともなければ、病気も心配ない。疫病を防ぐ予防接種をし、勉強もする機会を与えられていて、善逸はとっても平和ボケしていた。だからこそ、今回こうしてバンジージャンプをしたのは『死んでしまう』という恐怖を感じるいい機会ではあった。善逸は確かに怖かったけれど、空中に炭治郎に連れ出されてみて、真っ逆さまになって分かったことがある。
「炭治郎……」
「ん? なんだ?」
「好きだよ。俺、炭治郎のこと好きだわ。前世じゃなくて、今の炭治郎な」
善逸がそう言えば、炭治郎は呆けた顔をした。そして数秒を待ってから、がしりと善逸の腕を掴んでくる。その強い力に善逸は「こいつ実は全集中の呼吸使ってない?」と思うが何も言わなかった。キラキラと輝く炭治郎の目に意識が吸い寄せられたからだ。
「それは……本当か?」
「うん。本当だよ」
「やっぱり勘違いだったとか言われても取り消さないぞ!? いいんだな! 本当に俺のこと好きなんだな!? お試し交際とかもうなしにするぞ!? キチンとした交際だって思うからな!?」
「うん。いいよ。お前のことが好きだよ。……責任とってずっと一緒にいてくれよ炭治郎」
「……っ!!」
言葉にならず抱きしめられたのに善逸は笑った。よく利く耳があれば炭治郎の喜びの具合を感じられたのかもしれないが、自分は耳が良くないのが当然なのだ。仮定の話をしてもしょうがない。ありもしないことを願ってもしょうがないのだ。
(俺は結局、俺にしかなれない。今いる俺であることしか証明できないんだ)
善逸は宙に飛び出し、『死んでしまう』と初めて感じた。久しぶりの感覚ではないそれに、善逸は自分を見つけた。前世の『我妻善逸』であれば、この感覚を『久しぶり』と感じるだろう。しかし善逸は初めての感覚として受け取った。結局、善逸は前世の『我妻善逸』を記憶という知識でだけ理解していたということだ。
確かに鬼との戦いのことを思い出しても、そこまでリアルな恐怖は湧いてこない。確かに前世の記憶は善逸に影響を与えたが、本人だと、あの人生の続きだと言い張るには感覚が足りない。伊之助とインターハイの決勝で前世の鍛錬のような感覚に陥ったが、あれも勘違いだ。前世の伊之助は間違いなくもっと強い。善逸を追い詰めてやり負かす強さがあったではないか。
(そもそも俺が『我妻善逸』より断然弱いからなぁ)
善逸は炭治郎に抱きしめられながら、記憶の中の『我妻善逸』に想いを馳せる。彼はとても強かった。本人は自分は弱いと言っていたがそんなことはない。『雷の呼吸 壱ノ型 霹靂一閃』を使えるだけで今の自分とは大違いだと善逸は思う。だって自分は霹靂一閃が使えないのだからと、諦めにもにた気持ちで息を吐いた。
善逸の髪の色は生まれつきの金髪だ。前世のように雷に打たれて変色したのではない。それが原因かは知らないが、善逸はいくら全集中の呼吸が使えても、全集中・常中が使えたとしても霹靂一閃は打てない。雷の呼吸の型が使えない。
(雷の呼吸が使えないなら、俺は前世の『我妻善逸』なんて名乗れないよなあ。記憶がある別人だ。生まれ変わりかもしれないけど、大正の俺は終わってる。混同して生きるべきじゃない)
善逸は、心臓を大きく鳴らす炭治郎に抱きしめられ、嬉しさと愛おしさを感じる。好きだ、諦めきれないと必死に手を伸ばしてくれる炭治郎が善逸も好きだ。その目が他を向くのが嫌だ。空中に投げ出された時も、ずっとずっと離さず抱きしめていて欲しい、抱きついていたいと善逸は思ったのだ。大正の炭治郎はどこにもいない。善逸が目に映せるのは今の炭治郎で、今の炭治郎だけが善逸を受け止めてくれる。
(……今すぐ記憶に振り回されないっていうのは無理だけど、でも、俺は今の炭治郎だけを見つめていきたい……)
善逸は力を抜いて全身で炭治郎に寄りかかる。肩口に顔を寄せて、炭治郎の顔を見れば、炭治郎は真っ赤な顔で善逸を見ていた。その目の奥には確かな欲の炎が見えて、けれど躊躇うような表情は年相応だろう。善逸は大正の頃はどうだったかなと思い出そうとして、やめた。思い出すより、今の炭治郎を記憶に刻み付ける方がよほど大事なことだ。善逸は目を細めると、ゆっくり瞳を閉じた。顔に近づく息遣いに、初めての感触をよーく覚えておくぞと思った瞬間、善逸のスマートフォンから音が鳴った。
「えっ! あ! 電話!? あ、メッセージか……」
慌てて身体を起こす。善逸は鞄からスマートフォンを取り出すとメッセージの通知を確認した。相手は伊之助でアプリを開くと『次は絶対に勝つ!! 』と書かれている。それを見た善逸は、なんだ元気だなと安心して笑った。
「伊之助からだった。次は絶対勝つってさ」
「……そうか……」
「俺もう歩けそうだわ。そろそろ行こうぜ」
「……そうか……」
機会を逃して気落ちしている炭治郎に善逸は笑うしかない。しかしよく考えてみれば、ここはバンジージャンプの施設横のベンチだ。人が行き交っているから、いちゃつくなんて以ての外だった。善逸は炭治郎の膝から降りると周囲に対して恥ずかしい気持ちになりながらも、消えた体温に寂しくなってしまう。
「炭治郎、ほら立てよ!」
「うん……」
「この辺て何か他にあるのかなあ? どっか見たいわ」
「……この先に滝と、後はカフェが幾つかあるらしいぞ」
「カフェ! いいなぁ! 行ってみようぜ!」
そう言って善逸は捧げ物を鞄に突っ込み、炭治郎の手を握って歩き出した。炭治郎は最初は引きずられていたが、折れかけた心が立ち直ってきたのか次第に歩調を早めて善逸の横に並んだ。炎天下……と言っても山間なので多少は涼しい道を二人で歩く。善逸は今はもう、自分達は本当の恋人なのかと思うとじわりと心に熱と喜びが込み上がってきた。
「ウィッヒヒ……」
「またその笑い方か」
「いいだろ別に。慣れろよ。笑い方を矯正するより、お前が慣れた方が楽だぜ」
「それもそうだな。その笑い方だと、モテなさそうだし」
「酷っ!」
善逸は「これでも俺はモテるんだぜ!」と言おうとしたが、炭治郎が嬉しそうにニコニコしているのを見て言葉を飲み込んだ。確かにモテる意味はもうない。炭治郎がいるのだからそれでいい筈だ。
(あー……でも、普通に女の子にはキャーキャー言われたいけど……こいつは怒るだろうなあ)
剣道の実力ゆえに去年もそれなりにバレンタインチョコは貰ったのだが、今年は二連覇なのでさらに貰えるかもしれない。どうするかななんて善逸が考えていると、炭治郎が「そう言えば……」と切り出した。
「善逸。ケーキが食べたい」
「んん? ケーキ? この先のカフェにあるかな? 炭治郎ってケーキ好きなの?」
「いやほら、俺たちは今日が誕生日だろう?」
炭治郎のその言葉に善逸はパチリと瞬く。そして死んで生まれ変わったのだと思い至り、なるほどそれでと頷いた。確かに誕生日と称しても的外れではない。自分達の記念日としてお祝いして、ケーキを食べても不思議ではない。善逸はフヒヒッと楽しくなって笑った。
「あー…死んで生まれ変わったから誕生日? なるほどね。じゃあこれからは八月九日は俺たち二人の誕生日ってわけか。いいな! ケーキ食おうぜ! これからこの日は毎年お祝いだな!」
「そうだな! 真ん中バースデーだしな!」
炭治郎の思いがけない言葉に善逸は瞬時に頭の中でカレンダーを思い描いたが、分からない。しかし炭治郎がこんなことで嘘を言うはずもないのは、耳の良さがなくても分かっている。真ん中誕生日なら、ハッピーバースデーを歌わねばと善逸は笑う。炭治郎の歌が楽しみだ。
おしまい。
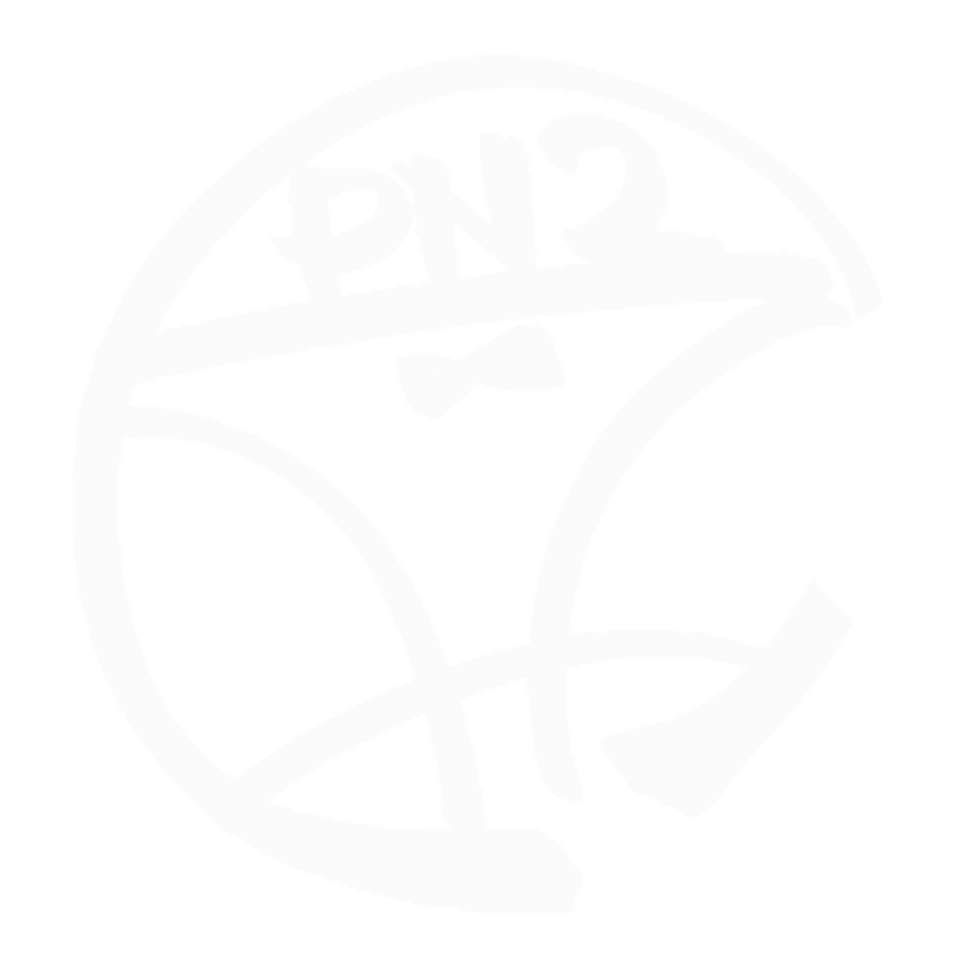



コメント
大好きです素敵な作品をありがとうございます!
もともと片方だけ覚えてる設定いいなあと思ってたんですが
それに伴う哀しみ苦しみをここまで掘り下げながら
そして思い出す訳でもなく
令和の炭善としてこんなに素敵なHappyENDを迎えるなんて…!
文字数めちゃくちゃ多いのに全く気にならない面白さドキドキそして感動でした!!
感想ありがとうございます!
片方だけ覚えてて―っていうのは、転生系のだいご味の一つですよね!
めちゃくちゃ頭ぐるぐるしながら書いた記憶があり、思い入れがある話ですー!
読んでくださってありがとございます!