原作軸のどっかの話。ふわっと媚薬ネタです。なのに全年齢。
約6000字/炭治郎×善逸
「それでは、お世話になりました」
しゃきしゃきと挨拶する炭治郎の後ろで、善逸はペコリと頭を下げた。相手は一晩の宿を提供してくれた藤の花の家紋の家の方だ。主人と奥方揃って見送ってくれるのに、善逸はなんだか座りが悪い気持ちになる。何しろ善逸は感謝されたりするほどの仕事をしていないのだから。
鬼の討伐に向かっても、その恐ろしさに膝が笑いだし、何とか逃げずに前に進んでも、鬼と対面すればあっという間に気を失う。そして気がつけば心優しき誰かが鬼を倒してくれているという結末だ。ことの真相はさておき、善逸にとってはそれが真実。何も覚えていないのだから、たいそうなもてなしは若干の罪悪感を植え付ける。もっとも、孤児に生まれたゆえに、かけてもらえる情けは余すことなく啜るけれども。
「よし、行こうか善逸」
「ああ」
これから向かうは蝶屋敷だ。二人は別の任務にでていたが、近くにあったこの家に寄った際に一緒になったに過ぎない。折角だからと一晩の宿をもらったのだ。本当は蝶屋敷に帰ることもできたが、疲れている時に無理をすることはないとの判断だった。一夜、ゆっくり過ごしてから帰還しても誰も叱るものはいない。
炭治郎と善逸は肩を並べて歩き出そうとしたが、それに「お待ちください」と声をかけたのは屋敷の主人であった。主人は炭治郎の元に静かに寄ると、そっと袖から包みを出して渡した。
「これは?」
「いえ、その……もし、宜しければと思いまして……。不要であれば、余計な世話としてお捨てください」
「はあ……?ありがとうございます」
炭治郎は主人に礼を言い、今度こそ二人は歩き出した。てくてくと歩いて、屋敷が見えなくなった頃合いの峠道で善逸は炭治郎の腕をつつく。
「なあ、なに貰ったの?」
「んん?なんだろうな」
「お菓子とか?」
「いや……そんな匂いはしないけど。どっちかというとクスリみたいなそんな匂いがするな」
炭治郎はそう言って羽織の袖から包みを出して、器用に包みを解いて見せた。包みの中にはさらに、紙の包みが幾つか入っている。そして、細く切られた紐のような……馴染みがあるものも。
「「!?!?!?」」
それは炭治郎と善逸がよくお世話になっているものだった。言ってしまえば昨晩も世話になったものだ。単純にどんなものか説明をすれば、男同士で抱き合う際に必要な滑り薬であった。善逸はそんなものが包みの中にある事態にくらりと眩暈がしてしまう。
これを藤の花の家紋の家の主人がこっそりと渡してきたということは、つまりはそういうことだろう。昨夜の炭治郎と善逸のあれやこれはくんずほぐれつといった事態はばっちり把握されていたということだろう。
「ああああーーー!!ばかっ!ばかっばかっ!このおばかっ!!」
「痛い!いたたっ!善逸、急に叩かないでくれ!」
「これが叩かずにいられるかーー!!しっかり家の人にバレてんじゃねーか!!なにが皆んな眠ってるよだよ!!この馬鹿!!」
「仕方ないだろう!善逸の喘ぎ声は大きいから!」
「人のせいにするんじゃないよ!!だいたい炭治郎がめちゃくちゃ気持ちいいことしてくるのが悪いんでしょうが!!あんな気持ちよくて声が我慢できるわけないんだよっ!!」
「そうか!そんなに気持ちよかったのか!」
「良い笑顔するんじゃない!!褒めてないだよっ!!」
二人はぎゃあぎゃあと騒ぎながら山の中を歩いた。恥も外聞もない内容だったけれど、幸いなことに山の中には八人くらいしかいなかったので、八人くらいに話を聞かれ、変な顔をされただけで済んだ。二人はそのまま歩き続け、峠を超えた辺りでようやく善逸が落ち着きを取り戻したので、包みの中にあった、もう一つのものに話題が及んだ。
「それで、もう一つの包みはなに?」
「なんだろう?文字が書いてあるけど……これの名称かな?」
「どれどれ……ふむっ……ってこれ!!あれじゃん!」
「なんだ善逸は知ってるのか?」
炭治郎の透き通った眼が迷わずに善逸を見た。その清廉潔白といった表情に、善逸はその物がなんであるかを言い当てるのに躊躇ってしまう。しかしこの清廉潔白といった様子の男は昨晩、自分を随分と揺さぶって泣かしてくれた奴だ。実は清廉潔白などではない。欲をしっかり腹の中に隠し持つ雄である。
「えっと……」
「うん」
「……それ……巷で有名な、媚薬だよ」
「えっ」
善逸はこそりと炭治郎に耳打ちをした。その瞬間、至近距離でドッと心臓が大きく鳴った。その音に善逸は自分の奥もキュンっと鳴った気がしたが、奥はそんな音は立やしない。全くの気のせいである。そして炭治郎は奥が疼いた善逸にはまるで気がついておらず、顔を真っ赤にして包みを見ている。ゴクンっと喉仏が動くその様子に、その媚薬を使ったら、この男がどうなるのかと善逸は興味が湧いた。
「……今度、使ってみる?」
「えっ!?媚薬をか!?」
「うん。ちなみにそれ、男が使うやつ。竿に塗りつけて……そうすると、すっごく気持ちいいんだって。炭治郎、使ってみろよ」
炭治郎の竿はただでさえ暴れん坊だが、媚薬を使うといったいいかほどになってしまうのか。もはや暴れん坊で聞かん坊かもしれないと善逸はゾクゾクしてしまう。いつも以上に、理性が溶けた長男らしからぬ姿が見れるかもしれないと、善逸は目を爛々とさせながら炭治郎を下から覗き込んだ。しかし——。
「いや……使わない。こっちの媚薬は捨てる」
「えっ!?捨てんの!?」
「捨てる。俺たちには必要ない」
炭治郎はそう言って滑り薬だけを残し、ほかの包みはくしゃりと握って草むらに放り投げてしまった。
「あーーもったいない!!」
「使わないから、もったいないも何もないだろう」
「あれ高いんだぞ!?」
「不要であれば捨てていいと言われた!!」
真っ赤な顔で、目を固く瞑ってそう言う炭治郎はなんとも意固地な子供のようであった。善逸はどこに落ちたか分からない包みに溜息をつき、肩を落とす。炭治郎はちっとも歩を緩めてはくれず、置き去りにするよう先に進んでいくではないか。
「はぁぁぁ……」
「善逸、置いていくぞ?」
先の道で振り返って呼びかける炭治郎を、善逸は睨みつけながら近寄っていく。不満ですというのをガニ股歩きと、足音で表現しているが、炭治郎は気づかぬふりのようだ。なので、正々堂々と善逸は炭治郎に言ってやった。
「俺は使ってみたかったのに」
「……使わなくても気持ちいいだろう?……まさか気持ちよくないのか?」
「悲壮な音を急に立てるなよ。ちゃんと気持ちいいって。……そんなの、匂いで確認するまでもなく、見りゃわかってんだろ」
炭治郎に抱かれてしまえば、善逸はもう前後不覚といったようにふにゃふにゃになってしまう。音も炭治郎のものしか追えず、声だってみっともなく口から垂れ流れる程だ。炭治郎は恐らく、執拗に匂いを嗅いできているのだろうから、自分の状態なんて手に取るように分かっているだろうと善逸は照れを含んで唇を尖らせる。
炭治郎はちゃんと気持ちいいという事実にホッと肩を下ろし、そして不思議そうに首を傾げた。
「じゃあ、やっぱり使わなくてもいいじゃないか。それに今まで以上に気持ちよくなったら……その、善逸はきっと物凄く大変なことになるぞ?」
「いや、俺が使うんじゃないのよ。俺は媚薬を使った炭治郎が見たいの」
「えっ!?なんで!?」
「なんでって……そりゃあ、今まで以上にクラクラしたお前が……見たいからに決まってるじゃん」
炭治郎とて、もっと気持ちよくなってくれと自分の理性を奪ってくるのだ。ならばこっちも同じように、理性をなくした恋人を見たいと思うのはおかしなことだろうかと、善逸はもじもじとしながら言葉にした。炭治郎は善逸の小さな告白に、ポッと頰を赤らめたが、それからしばらく沈黙して、ブンブンと頭を振る。
「善逸の気持ちは分かるけど……ごめん、俺は媚薬とかそんな変なものは使いたくない」
「……まあ、確かに怪しいもんもあるけどさぁ。さっきのは結構有名なやつだし……」
「違う。なにから出来てるとかそう言う話じゃなくて、理性をわざと失ったり、無理やり気持ちよくなるようなものを使いたくないんだ!俺は!俺の意思で!善逸を気持ちよくさせたい!!」
「おっ、おお……そ、そっか……分かったよ」
肩で息をするほど力のこもった言葉に、善逸は炭治郎の本気具合をみた。そしてこれは軽い気持ちで突いたらダメなやつと、その本気具合を右から左に流して、二度と触れないようにすることにした。変に突くと良くない。不穏なものには近寄らない。特段、普段の抱き合いに不満はないのだからこれで良いと、善逸はゆっくり息を吐いて空を見上げた。
(ああ、烏と雀が大空を羽ばたいている。今日も平和だ)
善逸はどんどんと近づいてくる烏と雀に嫌な予感がしたけれど、きっと気のせいだと、太陽の眩しさに目を閉じた。
****
汗を拭い、乱れた呼吸を整えながら善逸は廃寺に続く階段を登っていた。鬼殺隊士として呼吸を乱すのは良くないことだが、短い間にこの廃寺から蝶屋敷へと走り、そして休む暇なくまた戻ってきたのだから、多少の疲労と汗と呼吸の乱れは見逃して欲しい。
善逸は一つ大きく息を吸うと、細く吐き出して一気に階段を登った。陽が落ちて五時間、そして陽が昇るのも五時間。月は空の鉄板辺りにいる。善逸はまだまだ長く続く夜にぶるりと寒気がしたが、怯んではいられない。登り切った階段の上にある廃寺に迷うことなく突き進んだ。
あちこちと隙間のあいた寺の中では、息が荒い生き物が蠢いている音がする。善逸はその辛そうな音に心臓がぎゅうと握られたような心地になった。
本当なら側を離れたくはなかった。しかしどうしてもやらねばならない事があった。だから善逸はそれを急いでこなして、休むことなく走り続けて戻ってきたのだ。やるべき事はやった。あとは望むままに、そばに居られる。
「炭治郎っ!!」
善逸はそう言って廃寺の中に踏み込んだ。暗がりの中、丸まるように人が床に落ちている。近くには市松模様の羽織と、弱いものであれば、鬼の爪も通さない鬼殺隊の隊服が落ちている。丸まる背中は白く、恐らく体が火照ってしまい、熱くて敵わなかったのだろう。善逸は持ってきた水筒を片手に、急いで駆け寄ろうとすれば、背中越しに苦しげな声がした。
「近寄らないでくれ……」
「なに言ってんだよ。苦しいだろ炭治郎」
「……なんで戻ってきたんだ……」
そう言ってますます体を丸めて小さくなる炭治郎に、善逸は手を伸ばすかどうか悩んで……そっと触れた。その途端にびくんっと炭治郎は大きく反応した。そして反応した自分を許せないとばかりにきつく握られる拳に、善逸は慌てて己の手を重ねた。
「ダメだ、炭治郎。そんなに強く握ったら怪我するぞ」
「…………」
「ほら、水飲んで……。喉乾いただろ?」
「……なぁ、なぁ……たんじろぉ……」
炭治郎が弱っているのだから、自分が心を強く持たねばと思っていた善逸であったが、結局は怖くなって声が震えた。その途端に視界が反転し、背中が痛む。どうやらひっくり返され、押し倒されたのだと善逸が認識した時には、炭治郎はもう善逸の上には居なかった。部屋の隅で、今度は脚を抱えて座り込んでいる。しかし身体は小刻みに震え、呼吸も荒い。
その姿に善逸は炭治郎が可哀想だと思った。そして昼間に話していた、自分の意思というものを奪われるのが、炭治郎にとってはとんでもなく恐ろしい事なのだと善逸は認識した。
炭治郎はいま、鬼の毒にやられている。幸い、死に至るようなものではなく、どうやら人を強制的に発情させる毒のようだった。鎹鴉達が任務を持ってきた際に伝え聞いてはいたが、運悪く炭治郎がその毒を食らってしまったのだ。
となればそのまま蝶屋敷に連れ帰るわけにもいかない。あそこには年端も行かぬ娘達がいるのだ。毒は一過性のもので、身動きを取れなくする為に用いられていただけのようで、恐らく一晩もすれば抜け切るものだとされていた。日光さえ浴びれば、もっと早く解毒される可能性もあった。
だから炭治郎は毒を食らった己を置いて、善逸を蝶屋敷に帰したのだ。自分の命よりも大切な妹を託して。
善逸がここを発った時は、まだ炭治郎には余裕があった。本当は善逸は炭治郎と一緒に居たかったが、みっともない姿を妹には見せたくないという、炭治郎の兄心を汲んで一度は蝶屋敷に戻ったのだ。そして禰󠄀豆子をアオイ達に任せ、そして再びここに戻ってきた。
善逸は別に楽観視はしていなかった。徐々に血流が早くなる炭治郎の音を聞いたのだから、戻ってくるころにはすっかり毒は回っていると思っていた。そんな中に戻って、熱を持て余し苦しむ炭治郎に、負けるな頑張れ、耐えてみせろなど、言う気なんて毛頭なかった。
つまるところ、善逸は抱かれに戻ってきたのだ。熱に浮かされ、苦しむ恋人を楽にする為に戻ってきたのだ。どんなことになっても、どんなことをされてもいい覚悟だった。鬼と戦う覚悟はできやしないが、恋人を助ける為なら自分の体がどう扱われようと良かった。
善逸は隅で蹲る炭治郎に近寄ると、背後からそっと両腕を伸ばして抱きしめる。炭治郎が歯の隙間から息を吐いて震えたが、善逸は構わなかった。それどころかするりと太ももを撫でる。その途端に炭治郎が腕を振って善逸を引き剥がした。頑なに拒否されることに、ほんの少しだけ胸が痛むが、今の炭治郎は正常な状態ではないのだから、胸を痛ませるだけ無駄である。
善逸はスンッと鼻を鳴らして息を吐くと、炭治郎の真横に膝をついてだらりと体から力を抜き、炭治郎の顔を覗き込んだ。
「なあ、もう俺のこと抱いちゃえよ。そっちの方が絶対楽になるって」
「…………」
「明日の朝までそうしてんの?我慢するの苦しいだろ?というか、我慢しすぎで血管切れそうじゃない?もう、素直に出しちゃえよ」
擦るくらいはしているのかと思ったが、下袴には乱れがない。炭治郎の精神は鋼なのかと恐ろしささえ覚えた善逸あったが、溜息のような呟きが聞こえて、恐怖なんてどこかへ吹き飛ぶ。
「……いやだ……。善逸を……傷つけたくない……」
「傷つかないって」
否定をすれば、炭治郎もまた、善逸の言葉を否定するように首を振った。そしてまた、か細い小さな声で言った。
「きっと、酷い抱き方をする……。いまの……俺は……きっと猿に……なってしまう……」
悔しそうに、涙を浮かべる炭治郎に善逸もなんだか泣きたくなった。涙の理由は分からない。炭治郎が苦しそうなことも、炭治郎が辛そうなことも、自分を差し出したのに受け取ってもらえなかったことも、どれも理由になりそうであったし、どれも違うような気もした。だって、いま善逸は少し腹が立ってもいるからだ。
その怒りは炭治郎に何もしてやれない不甲斐ない己でもあるし、変に意固地な炭治郎にも感じていた。
善逸はぐすっと鼻を啜ると正面に腰を下ろし、炭治郎の肩をべちりと叩いた。本当は刺激を与えな方がいいのかもしれないが、善逸の目的は抱かれることなので、この刺激で炭治郎の理性が失われても別に構いやしなかった。
「ばか、ばか、炭治郎のばかやろう」
だから、二度、三度と肩をべちべち叩く。
「猿になるのがなんだよ。じゃあ炭治郎は、もし毒を食らったのがお前じゃなくて、俺だったら……禰󠄀豆子ちゃん連れて帰って、戻ってきてくれないっていうのかよ」
「…………」
「俺が苦しんでるのに、猿になるからって、なんもしないで放っておくのかよ……」
ずびっと鼻を啜って、善逸はそのまま炭治郎の肩に顔を埋めた。想像するだけで切ない。恋人に猿になるからと放っておかれるなんて、悲しくて仕方がない。そんなことを炭治郎は、自分にさせようとしているのだ。なんて酷い奴だと、善逸は顔を埋めながら、もう一度ひっ叩いてやろうと思った。しかしそれはかなわず、ぱしりと手首が掴まれる。そして顔を上げれば、グラグラと煮えた目が善逸をひたりと見つめている。
「たんじろぉ」
「……ごめん、善逸……!ごめんっ……!」
善逸は再びひっくり返る視界に、今度こそこのままでと体から力を抜いた。背中には腕が回っている。恐らくなけなしの理性が振り絞られ、背中は打ち付けられることなく横たわるだろうことを、善逸は分かっていたからだ。
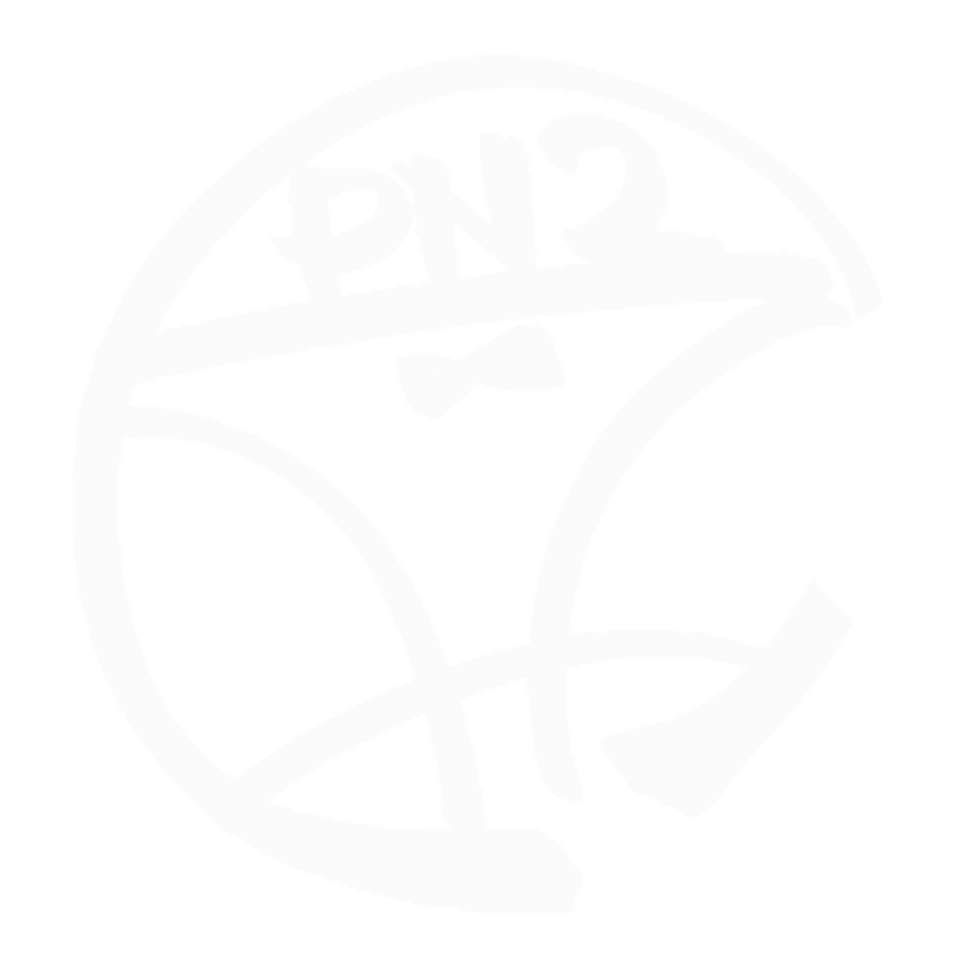



コメント