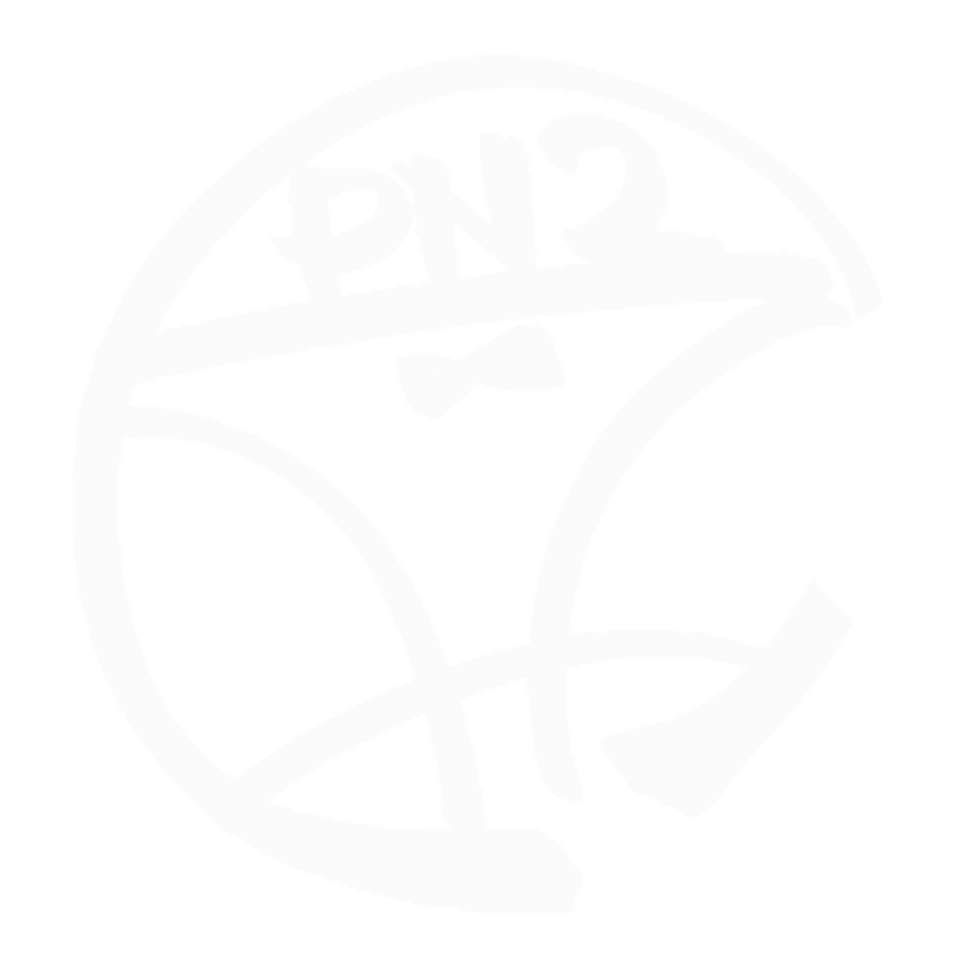約70000字/原作軸/炭善のつもり
さくさくさく。
枯葉を踏みしめる音がよく聞こえる。
背中には命よりも重いものを背負い、冬の最中を歩く。
「大丈夫だよ」
そう唱えるとカリカリと木を引っ掻くような返事がくる。その優しさに涙が溢れそうになるが、いまは泣くまいとむりくり上を向いた。いま泣いていいのは自分ではないからと少年は冬の中を歩き続けた。
****
「おはようございます。体調はどうでしょうか?」
「はい!だいぶいいです!」
「そうですか。散歩の方はどれくらいできるようになりました?」
「えーと、一時間山歩きしても息は上がりません!」
「なるほど。それでしたら本格的な機能回復訓練に入れそうですね」
胡蝶しのぶの言葉に療養中の隊士は嬉しそうに頷いた。前の任務で強い鬼と当たり、大怪我をして蝶屋敷に担ぎ込まれ、早一ヶ月。同期の友人はその間に何回も任務こなしているらしい。遅れをとっているなと思うし、早く家族の仇を討ちたいと焦る気持ちもある。隊士はシーツの裾をぐっと握ると僅かに肩を揺らした。
「それではこちらで予定を組んでおきますね。基本的には好きに過ごして大丈夫です」
「あの……俺の刀って……」
「折れてしまった君の刀は、いま打ち直している最中です。まだ掛かります」
「そうですか……」
しょんぼりとする隊士に胡蝶しのぶは焦るなと言わんばかりに肩を叩いた。隊士は彼女が何を考えているのか分からない。笑顔の下には鬼に対しての消えない怒りがあるのは分かるが、今は何を考えているのだろうか。
「大丈夫です!ちゃんと刀は打ってくれてますから!」
「はい」
隊士は確かにこればかりは焦っても仕方がないと頷いた。それに刀があっても体が戻っていなければ戦えない。万全に己を動かせねば、この前のように鬼にやられてしまうだろう。いまは生きていることを喜び、焦りは封じなければ。
「それでは今までどおり好きに過ごされて平気ですからね。外に出る際は外出届を出してください。日が落ちる前までには帰るように」
「はい。わかりました」
去っていく胡蝶しのぶを見送り、隊士は散歩にでも行くかとベッドから降りた。歩くのはすっかり前と同じくできるので、散歩がてらの日光浴だ。隊士は神崎アオイに外出届を出すと、療養着に羽織という姿で玄関から出ようとした。するとちょうどよく、知り合いの隊士とかち合う。
「村田さん」
「よう。元気してるか?」
「お陰様で。だいぶいいです」
出会ったのは先輩隊士の村田だ。那田蜘蛛山の任務で知り合い、お互いなんとか生き残ったのでそれからも見かければ会話を必ず交わす。今日はどうしたのかと隊士が首を傾げる。特に怪我はしていないように感じられた。
「今日はどうしたですか?」
「いや、お前の見舞いに来たんだよ。……その、どうしてるかなーって」
「え?俺のですか?」
「なんだよ。そんなに不思議か?お前、血だらけで、大怪我しまくって、生きてるの奇跡なくらいだったんだぞ?」
顔を歪めてそう言う村田に、それは確かにそうだったと隊士は頷く。隊士は向かった先で『人の大事なものを食う鬼』とやらと遭遇した。この鬼は上弦の鬼に匹敵するのではないかというくらい、長い間、生き続けている鬼だ。隠れて逃れるのが上手く、なかなか見つけられない鬼。何人もの隊士を使い物にできなくしてきた……らしい。
そんな鬼と対峙した隊士であるが、残念ながら討伐は叶わず、瀕死にまで追いやられた。手足も何も失わしなかったが怪我のせいで時間は失った。家族を鬼舞辻無惨に殺され、仇を討つことを何よりも大事に思っている隊士からすれば、停滞は手痛いものだ。しかし全集中の呼吸を会得しているゆえ、回復は早い。一ヶ月で起き上がり、歩き回れるようになったのだから順調である。
けれど目の前の村田はしきりに隊士を心配しているようだった。そう感じ取れる。隊士はいったいなぜと首を傾げた。
「村田さん、そう言って三日前も来ましたよ?」
「うっ。いや、別にいいだろ!後輩の様子を心配してもさぁ!」
ムキになるような村田に隊士は笑った。そんなに心配しなくても、順調な経過なのにと可笑しくなる。しかし確かに鬼殺隊士はいつ死ぬかわからないものだ。会える時に会っておかないと、気がつけば二度と会えぬなんてことはよくある。悲しいけれども。
「少し散歩をしようと思うんですが、村田さんも一緒にどうですか?」
「そうか。なら付き合おうかな」
村田はそう言って隊士と並んで歩き出した。ピュウと吹く風に羽織の前をしめる。不用意に体を冷やして風邪はひきたくない。体が弱ったいまは気をつけねばと隊士はイチョウの落ち葉を踏んで歩いた。すっかりと紅葉も終わり、冬が来ている。もう年も越す頃だと吐く息も白い。
蝶屋敷の周りに民家はなく、道には人通りは少なかった。裏には山があるが、表側は植え込みと雑木林になっていて、その間を縫うように拓かれた道を行けば町に着く。とりあえず人の多い方に向かうかとだらだら二人は歩き始めた。
「町に行くのか?」
「はい。皆んなに土産を買おうと思って。みたらし団子と大福、どっちがいいですかね?昨日は焼き餅にしたんですが……」
「……もしかし毎日、土産買いに行ってんのか?」
「はい」
頷く隊士に村田は頭を掻いている。あまり良くない反応に、隊士はまずかったかと小首を傾げた。
「毎日買うのは良くないですか?」
「いや……金をどう使うかはお前の自由だけどさ。貯金とかいいのか?」
「貯金……ですか」
村田にそう言われ、隊士はうーんと唸る。貯金なんて考えてもいなかった。家族皆、もう黄泉を渡ってしまった。小さな弟と妹を大きく育てるのことが、父を亡くして跡を継いだ長男としての誇りであり、夢であったのに……隊士の家族は誰もいない。
自暴自棄になっているわけではない。ただ、いまこの時を大事にしたいのだ。同期の親友や、世話になっている蝶屋敷の皆、そして先輩である村田。隊士はいまの自分を支えてくれ、力になっている人たちに出来る限りのことをしたいのだ。未来を語ってもどうなるかは分からない。だからこそ、今できる全力を皆に注ぎたい。
「いまはいいです。金のことは、鬼を全部倒してからまた考えればいいですよ」
「……そっか。まあ、俺も人のこと言えるほど、貯金なんてしてないからな」
二人はそれから談笑しながら町へ降りた。人混みの中、どの店の甘味を買うかと見回していると、隊士がひたと視線を止める。
「どうした?」
「いえ、見慣れない隊士がいて……」
「見慣れない隊士?」
そう言って隊士が村田に指し示したのは、木箱を背負った少年であった。少年は隊服の上に羽織を着て、長方形の大きな木箱を背負っている。同じくらいの年頃であるが、見たことがない。隊士は村田からまた木箱を背負った少年に視線をやる。少年は露天商が扱う女物のこまものを見ているようだった。
その横顔はあまりにも穏やかで、愛しいものを見るようで、誰か良い人にでも贈り物をするのかと、少年のことを良く知らぬ隊士にも簡単に思えるような様子であった。
「あ、あー……あいつか。あいつね。はいはい」
「知り合いですか?」
「まあな。……お前はあんまり近寄らない方がいいぞ」
「なぜですか?」
村田が隊士の肩を引いてその場から離れようとするので、踏ん張って逆らう。同じ年頃ならば、俄然、少年に興味がある。自分の親友も同じ年頃だから三人で仲良くなれるかもしれない。そう思って村田になぜ近寄らない方がいいのかと隊士は不満げな視線を向けた。
「あいつが背負ってる箱には、鬼がいるぞ」
その言葉に隊士は目を丸めた。鬼殺隊士が鬼を箱に入れて運んでいるというのか。なぜ。なぜそんなことをするとゾッとしてしまう。
「な、なんでそんなことが許されているんですか!?」
「……箱の中にいる鬼は、人を喰わない珍しい鬼なんだよ」
「えっ」
「あと、鬼舞辻無惨とちょっと因縁があるらしい。だから殺されず生かされてる。お館様も、柱もお認めになってるんだよ」
「そうなんですか……」
確かに人を喰っていない鬼ならば、少し話は別かもしれない。しかし鬼を憎む隊士としては、いまは喰っていないとしてもいつか喰うのではと心配になってしまう。人を喰ってからでは、何もかもが遅い。
「……それに、あいつが馴れ合わないよ」
「あいつ?」
「鬼を背負ってる奴だよ。あいつは、箱の中にいる鬼が命よりも大切なんだ。そうそう近寄れやしないぜ」
村田はしきりに少年に近づかないよう誘導しているようだった。隊士は人の機微がよく分かるのだ。何をそんなに焦っているのかと村田を見つめるが、聞かねば分からないだろう。しかし村田は嘘は言っていないようだった。少年が人を近寄らせないようにしているのは本当なのだろう。
隊士は村田を問い詰めるのはやめ、再び少年の方を向いた。すると少年が隊士の方を真っ直ぐに見ている。かなり距離があるのに、ひたと見つめられているのが分かる。見定めるようなその眼差しに、息が詰まり、胸がグッと痛んだ。
「あっ……」
少年が身を翻し、雑踏の向こうへと消えていった。隊士はその後ろ姿に残念な気持ちになってしまう。初めて会う、いや、ただ見かけたに過ぎない人に対して珍しい気持ちだと胸に手を当てた。
「行っちまったな。俺たちも行こうぜ」
「……村田さん、彼の名前はなんて言うんですか?」
少年とは反対方向へと進む村田を追いかけながら、隊士は問いかけた。先行く村田は少し沈黙してから、なんともないことのように言う。
「あいつは我妻善逸だよ」
「我妻、善逸」
口にしてみれば、これ以上ないほどの名前に思えた。隊士はいま一度振り返るが、少年の姿はもうどこにも無い。珍しい金の髪も、その色に似合いの蒲公英のような色の羽織ももう見えない。
「おーい、竈門。早く行こうぜ」
「あ!はい!」
村田の呼びかけに竈門炭治郎は小走りで駆け出した。後ろ髪を引かれる思いを振り切って、次に我妻善逸を見かけた時には必ず声をかけようとそう決めて、駆け出した。
****
「伊之助は我妻君を知っているか?」
「ああん?」
見目麗しい少年が露骨に嫌な顔をしたのに、竈門炭治郎はびっくりとした。そんなに変なことを聞いただろうかと考えるが、なんてことはない話題だった筈だと思い、意味が伝わらなかったのかなと前向きに捉えてもう一度言うことにした。
「我妻善逸君だよ。金色の髪をしていて、黄色の鱗柄の羽織を着ていて、その……背中に——」
「うるせぇ!俺はそいつのことよーく知ってんだよ!わざわざ細かく説明すんなっ!荒島紋逸だろ!?」
「我妻善逸だよ、伊之助」
お握りを片手に立ち上がった伊之助に、竈門炭治郎はそう言った。伊之助は「だから分かってる!」と地団駄を踏みならしてから、丸椅子に座り直す。そんなに鍛錬後で腹が減り、気が立っているのだろうかと、竈門炭治郎は伊之助の態度を訝しんだ。しかし伊之助はその空腹を満たす為にアオイに握り飯を作ってもらっている。右手にあるものがその証拠だ。
伊之助は大きめに握られたそれをぺろりと平らげると、竈門炭治郎の座っているベッドの横に備え付けられている水差しを掴む。そしてそれを綺麗に飲み干して、竈門炭治郎を睨みつけた。
「で?」
「……で?」
「てめぇがアイツのこと言い始めたんだろうが!そいつがどうしたってんだよ!!」
「ああ、我妻君のことか。いや、この前見かけたんだ。そこの町で。綺麗な髪の色をしていて気になったから……伊之助は知ってるかなと思って」
竈門炭治郎はあの日、町で見かけた金糸のような髪を思い描いた。
冬のせいか今は寒々しい印象を受けたが、春になれば色とりどりの草花の中で美しく輝くような気がする。蒲公英色の羽織といい、どうにも花冠が似合いそうだと考え、竈門炭治郎は少し笑った。我妻善逸は男だ。なぜ花冠が似合うなんて思うのだろうか。本人も迷惑だろう。
「……名前、あいつから聞いたのか?」
「いや、遠くから見かけただけなんだ。俺は村田さんと一緒で、村田さんに彼の名前を聞いたんだよ」
本人とは一言も会話をしていないことを遠回しに説明すると、伊之助は露骨にホッとしたような気配をさせた。香りたつ安堵の匂いと不快さを感じてるらしい匂い。竈門炭治郎は伊之助の様子に、どうしたのかと不思議な気持ちになる。もしかしなくとも、伊之助は我妻善逸を好んでいないのだろうか。しかし先程は『よく知っている』と言っていた。
「伊之助は我妻君をよく知っているって言っていたけど……任務で一緒になったのか?」
竈門炭治郎は我妻善逸を見たことがない。あんな派手な出立ちだ。見たら絶対に忘れない。しかしこの蝶屋敷では見かけた事がないから、伊之助が知り合うなら自分とは別だった任務先でのことだろうと思ったのだ。
「……任務、何回か一緒にやった事あるぜ」
「へえ!彼は何の呼吸を使うんだ?」
「……雷の呼吸だよ。つってもひとつしか技が使えねぇけどな」
「えっ!?我妻君は一つの技だけで鬼と戦ってるのか!?勝てるのか!?」
「勝てる。ひとつの技って言っても、そいつを何回も連続で繰り出したり……元から速ぇ技なのに、さらに超すげぇ速さで技使ったりとかするからな」
「へええええ!」
竈門炭治郎はまるで想像もつかない戦い方に興奮してきた。水の呼吸と日の呼吸を使う自分はかなり多彩な型を使い分けて鬼と戦っている。それでも四苦八苦しているというのに、一つの型、そしてそれの応用だけで鬼と戦うなんて凄いと竈門炭治郎は目を輝かせた。
「凄いなぁ……!雷の呼吸、どんなだろう?俺はその呼吸を使っている人を見た事ないからなぁ。想像ができない」
炎の呼吸、音の呼吸、霞の呼吸、恋の呼吸と柱の使う独自の呼吸も幾つか見ているし、風や土は他の隊士が使っているのを見た事がある。しかし雷の呼吸は一度もない。竈門炭治郎は雷の呼吸を想像してみて、どんなだろうかと胸を弾ませた。もしや、夜闇を切り裂く雷光のような速さの技だろうか。
「どんな技なんだ?我妻君は強いんだろう?」
「……まあな。けど俺様の方が強い!!アイツは弱味噌だからな!」
伊之助はそう言って胸を張ると水差しを元の位置に戻した。すっかり空になったそれに、取り替えてこなければと竈門炭治郎は思った。しかしそんなことは後である。今は我妻善逸だ。いったいどんな人なのか、知りたくて知りたくて仕方がない。彼を知る伊之助からまだ話を聞きたいと、好奇心に輝く目を竈門炭治郎は伊之助に向けた。
「そういえば……我妻君は背中に」
「あーーーっ!!さっきから聞いてばっかでうるせぇな!!俺様はもう行く!!腹がいっぱいになったら鍛錬だ!!」
伊之助は竈門炭治郎の言葉を遮り、猪頭を被った。突然のことにびっくりした竈門炭治郎だが、伊之助は声をかけ普通に前に部屋の中から走り去ってしまう。入院室にポツンと残された竈門炭治郎は伊之助に逃げられてしまったと頭を掻いた。
「そんなにしつこく聞いてたかな?」
もっと我妻善逸について知りたかったのだが、伊之助のあの様子では質問攻めされるのが嫌なのだろう。確かに自分としては珍しく色んなことを聞いてしまったかなと水差しを変えようと竈門炭治郎は立ち上がった。すると丁度よく、伊之助が出て行って開きっぱなしであった扉からしのぶか顔を覗かせた。
「こんにちはー。お加減はどうですか?」
「お陰様で、かなりいいです!」
「そうですか」
にっこり微笑み、しのぶは部屋に入ってきた。立ち上がっていた竈門炭治郎はどうしようかと思い、しのぶが問診票を持っているらしい様子を見て、もう一度ベッドに腰をかける。するとしのぶは先程まで伊之助が座っていた椅子に腰を下ろした。
「そういえば伊之助君が部屋から飛び出していくのを見ました」
「お握りを食べて、腹が膨れたので鍛錬をするそうです」
「なるほど、伊之助君は鍛錬に熱心で感心しますね」
そう言ったしのぶの言葉はごく自然なものであったが、竈門炭治郎はふと引っかかってしまった。自分も真面目に鍛錬に取り組む方であるが、しのぶは誰を思ったのだろうか。『伊之助君は鍛錬に熱心で』なんて、誰か鍛錬が嫌いな人間がいるかのようだ。この鬼殺隊で、そんな人がいるのだろうかと不思議に思う。
「鍛錬が嫌いな隊士がいるんですか?」
竈門炭治郎が何気なくしのぶに問いかけると、しのぶはピリッとした匂いをさせた。しかしそれはすぐに融解し、「いますよー。まあ、なんだかんだ言っても鍛錬しているんですけどね」と微笑むのに、竈門炭治郎は「へえ」と頷く。そしてそうだと、あることに思い至る。
(しのぶさんは柱だ。我妻君を絶対知ってる)
鬼を背負っている隊士。我妻善逸。経緯は知らないが、鬼を連れているのはお館様と柱が認めていると村田が話していた。ということは蟲柱たる胡蝶しのぶは我妻善逸を間違いなく、認知している筈である。
「炭治郎君、最近、気になることとか、聞きたいこととかありますか?」
しのぶの問診が始まった。間違いなく体についてのことを訊ねられているのだろうが、竈門炭治郎は待ってましたとばかりに顔をあげ、いま一番気になっていることを聞いた。
「あります!あの、しのぶさんは我妻善逸君を知ってますよね?」
「……はい。知っていますよ?」
「この前見かけたんです。金色の髪をしていて、黄色い羽織を着ていました!」
「そうですねー。いつもの善逸君ですね」
しのぶが『善逸君』と言ったのに、炭治郎は少し驚いた。しのぶが下の名前で呼ぶ隊士は数が少ない。蝶屋敷で暮らしている女の子達以外では、自分と伊之助くらいなものと思っていた。けれと『善逸君』と呼んだのだから、想像以上にしのぶは我妻善逸をよく知っているのかもしれない。しかし、蝶屋敷で彼を見かけたことはない。
「……しのぶさんは彼をよく知っているんですか?」
「はい、知ってますよ」
「そうなんですね……。あの、どんな人なのか聞いてもいいですか?」
「あまり彼の個人的なことはお話できませんが、まあ、よく知られている程度のことまででしたらいいですよ?何が知りたいですか?」
そこそこいい返事が貰えたので、竈門炭治郎は居住まいを正した。聞きたいことは沢山あるが、柱である彼女に聞くならこれだろうと前のめりにしのぶに問いかける。
「あの、我妻君は鬼を連れているそうですが……なぜ、鬼を連れているんですか?なぜ鬼を連れて鬼殺隊に?」
人を喰っていないとはいえ、鬼を連れているのは中々に危険だ。どうして危険があっても連れ歩くのかと純粋に疑問に思う。しかも連れ歩く鬼を守りたいのならば、なぜ鬼殺隊に入ったのか。
「鬼を連れている理由……ですか。うーん……彼が連れている鬼は人を喰わない鬼……というのはご存知ですか?」
「はい」
「なるほど。鬼を連れて鬼殺隊にいる理由は一つです。鬼を人間に戻す方法を探しているからです」
しのぶの言葉に竈門炭治郎は目を丸くする。鬼を人間に戻すなんてこと可能なのだろうかと、思いつきもしなかったと、胸の辺りの布地を掴む。ぎゅうと胸が痛くなったからだ。
「鬼を……人間に……」
「はい。様々な鬼に出会い、その方法を探しているようですね」
「そんな……」
途方もないことだ。そんな事は夢物語ではと思うけれど、鬼が入っているという箱を背負った我妻善逸の姿は竈門炭治郎の脳裏に焼き付いている。あの不思議な眼差しは覚悟を決めていた者の目だったのかと納得がいく。
「……背負ってる鬼は、我妻君の家族なんですか?」
「いいえ。彼は身寄りがないので違います」
さらりと答えたしのぶに、その内容は個人的なことに該当しないのかとびっくりする。けれど身寄りがないのに、鬼を人間に戻そうなんてことをするということは、相当近い関係の相手なのではと竈門炭治郎は思った。
「あ!もしかして、鬼は我妻君の良い人……?」
「違いますね」
ばっさりと否定されて竈門炭治郎はますます混乱した。どういった関係性ならそんなことになり得るのかと気になって仕方がない。そこまで気にすることでもないのかもしれないが、何故か我妻善逸に関してのことは些細なことでも知りたい気持ちが出てくるのだ。竈門炭治郎が難しい顔をして唸っていると、しのぶがくすりと笑う。
「そもそも最初に鬼を連れていたのは善逸君じゃありませんよ」
「え?」
「箱の中にいるのは、善逸君の親友の妹です。善逸君の親友が、鬼になった妹を連れて鬼殺隊士になったのですよ。彼はそれを引き継いでいるに過ぎません」
しのぶはそう言って、困ったような、呆れたような、悲しいような匂いをさせている。どういう感情なのか分からないが、それより元から背負っていたのが我妻善逸ではないなら、なぜいま彼が背負っているのかの方が気になる。
「なぜ、我妻君が引き継いだんですか?」
「善逸君の親友であり、鬼の少女の兄である人が……背負えなくなってしまったからです」
断定した言い方を避けたが、そういうことだろう。鬼殺隊はあっという間に隊士が死んでいく。竈門炭治郎は鬼になった妹を残して死んでいった隊士を想い、悲しい気持ちになった。さぞ無念だっただろう。悔しくて、辛くて堪らなかっただろう。自分がその立場なら無念の果てに幽鬼になるかもと竈門炭治郎はゆっくり息を吐いた。
「我妻君は優しい人なんですね」
「そうですね。とてもとても、優しい子ですよ」
しのぶはそう言って丸椅子から立ち上がった。問診は終わりの時間らしい。竈門炭治郎は自然と立ち上がったしのぶに視線をやった。
「機能回復訓練は来週から始めましょう。それまでは楽に過ごしてください」
しのぶはそう言って音も立てずに入院室から出て行った。しーんと静かになり、竈門炭治郎はふうと溜息を吐く。個人部屋を割り当てられているので、どうにも静かで仕方がない。胸が掻き乱されるような話を聞いた後に何の音もない場所にいると、心がどうにも落ち着かないと胸に手を当てた。ドキドキとしているのは、驚くような話を沢山聞いたからかもしれない。
「我妻善逸……」
炭治郎はここに居ない人の名前を呼んでみた。声すら知らない相手からは想像上でも返事はない。死んだ親友の代わりに、親友の妹、それも鬼になった妹を背負う。そんなのはどんな覚悟があれば出来るのだろうか。どれだけ優しさがあれば出来るのだろうか。そんな人はどんな匂いをさせるのかと気になって気になってしょうがないと、竈門炭治郎はジタバタしたい衝動に駆られて、布団にだらしなく横たわった。
「入るぞ」
「えっ!?あっ!義勇さん!」
布団に横たわった瞬間に入ってきた相手にびっくりして竈門炭治郎は起き上がった。まさかの人物の来訪に驚く。義勇は部屋の中をキョロリと見てから、真顔のまま竈門炭治郎の方に近づいてきた。
「土産だ」
「わあ!ありがとうございます!」
そう言って開けたのはおかきだった。たまたまだろうが、伊之助の好きな店のおかきで余計に嬉しくなる。
「……それで、どうだ?」
「(具合のことかな?)だいぶいいです!来週から機能回復訓練に入ります!」
「そうか」
「はい!」
竈門炭治郎はニコニコと話した。正直、待ち望んでいた機能回復訓練だ。怪我はとっくに良くなっているのに、何かに慎重になっているのか、しのぶがなかなか機能回復訓練に入るのを許可してくれなかったのだ。しかし来週からようやく始まる。すぐに良くなる自信が竈門炭治郎にはあったので、刀さえできあがればすぐにまた任務に入る事ができるだろう。苦しむ人が一人でも少なくなるように、早く自分も戦いたいと竈門炭治郎は拳を握った。
(ん……?この匂い……)
竈門炭治郎はすんっと鼻を動かす。義勇から鬼の匂いが漂ってくる。しかしその鬼の匂いは鼻が曲がるような嫌なものではなく、どことなく花の匂いがするような変わったもので、不思議な気持ちになる。人を喰った鬼は独特な嫌な匂いがするからだ。
「義勇さん、任務終わりですか?」
「……違う」
「そうですか。……昨日、風呂入りました?」
竈門炭治郎の言葉に義勇はびっくりしたのか、ゆっくりと袖口を持ち上げて匂いを嗅いでいる。暗に臭いと言われたと勘違いさせたかと、慌てて違うのだと説明しようと思ったがある事に思い至り、竈門炭治郎は止まった。
(……もしかして、義勇さんは我妻君と一緒にいたのか?)
この変わった鬼の匂い、嗅いだ事のない、清涼な鬼の匂い。それは人を喰っていないからではと竈門炭治郎は閃いた。人を喰っていない鬼ならば、我妻善逸が背負っている鬼であろう。竈門炭治郎は義勇にも我妻善逸のことを聞こうと顔をあげると、そこにはもう誰もいなかった。
****
「見て禰󠄀豆子ちゃん、オシロイバナだよ」
夕日が沈みゆくの土手の中を歩きながら、見つけた黄色い花を指差して善逸はそう言った。手を繋いでいた禰󠄀豆子はパッと表情を輝かせると、善逸の腕を引いて花へ駆け寄っていく。
「お、お、オシロバナ」
「うん、そう」
禰󠄀豆子の言葉は少し抜けていたが、一文字くらい些細な事だ。土手に駆け寄り、花をキョロキョロと見回す禰󠄀豆子をにっこりと見守る。禰󠄀豆子は夕方に咲く花に興味津々のようで、まだ爪が濃い桃色で人よりもだいぶ尖っているその指を上手に使い、柔らかい花弁を撫で回していた。
「こんなところにポツンと咲いてるけど……誰かが種でもこほしたのかね?」
オシロイバナは非常に繁殖力の強い植物だ。家の庭などで見かける事が多く、土手で咲いているのは珍しい。なんにせよ禰󠄀豆子が喜んでいるから良かったと善逸は空を見上げた。赤く染まった空はどんどんと夜を連れてきている。あまり悠長にはしていられないだろう。今夜は一匹、あの山で鬼を探して斬らねばならない。
「やだなぁ……」
ポツリと呟いた善逸だが、いまの善逸には泣いている暇も縋れる相手もいない。一人きりでも禰󠄀豆子を守ってみせると決めて飛び出したのだ。やるべきことから逃げるわけにはいかない。
「禰󠄀豆子ちゃん、ごめね。そろそろ行こう」
善逸がそう言って背中に背負っていた木箱を下ろすと、禰󠄀豆子は少し渋った顔をする。それは退屈とか不満とかではなく、心配の音を響かせるのに善逸は困ったように笑った。
「大丈夫だよ。一撃で仕留めてみせるから」
「う、う……うん」
禰󠄀豆子はそう言って頷くと、シュルシュルと身を縮めた。そして箱の中に収まると、大人しく善逸に背負われる。禰󠄀豆子は太陽を克服した鬼だ。もしかしなくとも鬼の首魁に狙われるかもしれない。だから鬼を狩る時は木箱の中に身を隠し、極力姿を見せないほうがいい。禰󠄀豆子は優しいから、一緒にいるのに善逸だけが戦うのが心配なようだが、禰󠄀豆子が傷つく方が善逸には負担が大きいのだ。
(もう太陽も克服してるんだから、本当ならどこか安全なところで好きなようにさせてあげたいけど……)
けれどそうすると、禰󠄀豆子は幼い気持ちのまま、帰りたいところに行ってしまうかもしれない。善逸は禰󠄀豆子をしっかり背負うと夜が来るので走り出した。向かうは村の奥に聳える山だ。あの山に入ると熊に食われたのか、人が消えるらしい。しかし隠れて逃げおおせた人がいて、その人が「鬼を見た」と証言した結果、隠の情報網にこの山の話が引っかかったのだ。
善逸は恐ろしく思いながらも耳を澄ませて山に入った。ここからは何がなんでも、向こうに見つかる前に、鬼の所在を探さねばならない。善逸は禰󠄀豆子を背負っていくことを決めた時に腹を括ったのだ。もう寝ている場合ではない。禰󠄀豆子の安全に無事に元いた場所に戻す為には、気づかれる前に鬼を斬るのが一番だ。
(や、やるぞ……!やる!やる!!)
善逸はごくんっと唾液を飲み込むとザリザリと聞こえる鬼の音を頼りに距離を詰める。向こうはまだ気が付いていない。音と気配を消しながら、山の斜面を駆け、そして一定の距離に来たところで善逸は構えを取った。右手を柄にかけ、左足を大きく下げる。
(霹靂一閃……八連!!)
善逸は地面を踏み抜くとその音が轟く前に木々を七回踏み倒し、そして遠くにいた筈の鬼の首を飛ばした。八回の踏み込みの音が一つの雷鳴のように重なり、山の間に響く。
一撃で首が切り捨てられた鬼はどれほどの強さだったのかはわからない。血鬼術を持っていたのかどうかさえも、善逸の一撃の前では闇の中だ。分かるのは『鬼は上弦には及ばない』この一つだけ。
消えゆく鬼の体の前に、素早く善逸は物陰に降りてその場を去った。禰󠄀豆子に万の一つも危険がないようにだ。鬼の首魁はなにやら鬼の目を通して物を見ることができるそうなので、消えゆく鬼の視界でも、禰󠄀豆子の入っている木箱を見られたくない。
(……一体だけだったのかな?)
善逸は山を駆け回りながら、もう不吉な音がしないことにホッと胸を撫で下ろした。今回の任務も無事にやり過ごせたようだ。一人で起きて戦わねばならない状況は恐怖ばかりであるが、気がついた事がある。知覚される前に鬼の首を落とせば良いのだ。幸い、善逸の技は間合いが長く、そして速い。上弦は無理でもそれ以外の鬼ならばもう十分な程に通用する。
(俺、少しは強くなったかな……?)
善逸は己を強いと励ましてくれていた親友を思い浮かべた。彼ならば『少しどころじゃないぞ!すごく強くなった!』と笑ってくれることであろう。善逸は想像上の相手の反応にくすりと笑い、早く山を降りて下宿先に戻ろうと足を早める。するとコンコンと木箱の扉を内から叩かれたので、しゃがんで木箱を地面に下ろした。
「禰󠄀豆子ちゃん?」
かぱりと木箱を開けると禰󠄀豆子が出てくる。そしてみるみるうちに大きくなると、善逸を見渡し始めた。どうやら怪我はないかを確認しているようだ。禰󠄀豆子の優しさに善逸はデレりと頰を緩めると、「怪我はないよぉ〜♡ 禰󠄀豆子ちゃん心配してくれてありがとぉ♡」と禰󠄀豆子に手を差し出す。
「折角だから、お散歩しながら帰ろうか。眠くなったら、背負ってあげるから」
「うん!」
善逸は禰󠄀豆子の手を引きながら歩き出した。片手が埋まっているので、木箱を片側の肩に引っ掛ける形となったが、禰󠄀豆子の手を離す気はない。禰󠄀豆子がどこかに行ったら心配でどうにかなってしまう。善逸は何がなんでも春までの間、禰󠄀豆子を無事に過ごさせねばならないのだ。
(まあ、春になっても何も改善してない可能性もあるけど……)
善逸は荒ぶる気持ちで、禰󠄀豆子の手を握り締めないように気をつけた。善逸はあることを考えると、どうにも心がささくれて叫び出したくて堪らなくなるのだ。暴れ回って、どうしてだと神仏を罵りたくもなる。しかしそんな事を禰󠄀豆子の前ではできない。禰󠄀豆子の前では落ち着いて、安心させて、大丈夫だと言わねばならない。そうしなければならない決まりはないが、善逸はそうすべきだと思っている。禰󠄀豆子に余計な心配も悲しみも味合わせたくはないのだ。けれどそれも、春になったら全てが終わる。
春になったら、何も改善されていなくとも、善逸は駄々を捏ねるのをやめて禰󠄀豆子を返してやらねばならない。
****
「炭治郎君は血鬼術を受けた可能性があります」
「へ……?」
任務を終えて、蝶屋敷に戻ってきた善逸がしのぶから聞いたのはまずその言葉だった。炭治郎は鬼の討伐任務に禰󠄀豆子と共に赴き、そして重傷の様子で隠達に運び込まれた。任務の様子を見ていた隠によると、炭治郎の動きが途中で突然悪くなり、しかし朝が来たから鬼は逃げていったとの事だった。要するに思いのほか強かった炭治郎から逃げるため、鬼は炭治郎に術をかけてその隙に逃げたと考えられる。
「あの、炭治郎と禰󠄀豆子ちゃんは……」
「禰󠄀豆子さんは消耗したのか、眠っています。炭治郎君は治療を施して、今は休んでいますが……怪我の具合からしてひと月は休息が必要でしょう」
「命に別状はないんですね?」
「はい」
「良かった……」
善逸はひとまず親友である炭治郎と可愛い禰󠄀豆子が無事であるのにホッとする。なによりも生きていてもらわねば、その後の心配もできやしないからだ。善逸は二人の無事に多少は心を落ち着けると、しのぶの顔色を伺った。
「えっと、それで……炭治郎が血鬼術を受けたかもしれないって……」
「はい。例の鬼の血鬼術は、『大事なものを奪う』ことです」
「……大事なものを奪う?」
「そうです」
しのぶが説明するに、炭治郎が立ち向かった鬼は長くその存在を鬼殺隊に知らしめている鬼らしい。隠れるのが上手く、なかなか見つける事ができない鬼で、今回はその所在を掴めたので、もしまた見失っても追跡しやすいようにと炭治郎が抜擢されたらしい。確かに炭治郎はその鼻を使っての追跡を得意とするところだ。
「その鬼の血鬼術ですが、術をかけた対象者が大事に思っていること自体を奪うようです」
「よくわからないんですが……大事な物を奪うとか、壊すとかってことですか?」
血鬼術でそんな事ができるのかと善逸は不思議に思う。もし大事なものが近くになく、極端な話、海の向こうなんて場合はどうするのだと首を傾げると、しのぶは首を振った。
「違います。鬼の血鬼術は本人の中から『大事なもの』の記憶をなくすのです。最初からそれがなかったように」
「えっ!?」
「この鬼の血鬼術の能力は分かりづらい。記憶を失っていても、全てではなく、また抜け落ちた部分はいいように本人の中で補完されるのです。術を掛けられたものは術を掛けられた事を認識できず、ただ大事なものの記憶を人知れず失います」
ゾッとする話だと善逸は身ぶるいした。人が大事にしている記憶や思い出をまるでなかったようにするなんて悪質にも程がある。
「命に別状がない血鬼術ではありますが、鬼殺隊では致命的な結果を引き起こしかねません」
「え?なんでですか?」
「憎しみを忘れてしまうからです」
その言葉に善逸は正しくこの血鬼術の恐ろしさを理解した。大事な物を忘れる。それは鬼殺隊士の中では要するに、仇をとってやりたい人のことを忘れるということだ。自分が鬼殺隊になると決めた覚悟自体を失うに近い。命を懸けても鬼を斬ると決めた原動力たるものを失えば、そりゃあ剣も鈍るだろう。鈍れば、鬼にやられてしまう。
「えっ!?待って!?炭治郎はその血鬼術受けたんですよね!?」
「はい」
「そ、そ、そ、それってつまり!!炭治郎は……」
「……大事なものを忘れてしまっていると思います。その存在自体を覚えていない。最初からなかったものと捉えているでしょう」
善逸はそれを聞いて、素早く立ち上がった。頭の中は大混乱していたが、もたもたしてはいられないとしのぶの執務室を後にしようと踵を返す。
「善逸君?どこ行くんですか?」
「禰󠄀豆子ちゃんを連れてここを出ます」
善逸は迷わずそう言った。炭治郎が大事なものを忘れたというのならば、それは間違いなく禰󠄀豆子であろう。炭治郎は禰󠄀豆子をなによりも大事にしていて、彼女を人に戻すことを目指しているのだ。
「……確かに炭治郎君は禰󠄀豆子さんを忘れている可能性が高いですが、勝手に連れ出すのは……」
「でもこのままじゃ、禰󠄀豆子ちゃんは大好きなお兄ちゃんに『知らない』って言われちゃうんですよ!?そんなのってないじゃないですか!!」
善逸は振り返ってしのぶにそう叫んだ。しかしすぐさま声が大きかったと口を塞ぐ。入院室から執務室は多少離れているので、二人には気が付かれてはいない筈。善逸はそろりと手を下ろすと、爪が皮膚に食い込むほどに握りしめた。
「……炭治郎だって、悲しみますよ……。忘れちゃったかもしれないのは、血鬼術に掛かってるからしょうがないけど……禰󠄀豆子ちゃんを『知らない』なんて……言わせないでやりたいんです……」
「いつ炭治郎君が元に戻るとも分からないのに?」
「うっ……そうですけど……でも……」
根本的な解決ではないのは分かっている。炭治郎から禰󠄀豆子の存在を隠せば、『知らない』と言わせることは防げる筈だ。離れ離れにさせるのは苦しいけれど、善逸は辛いのは嫌いなのだ。禰󠄀豆子が辛い目に遭うのを少しでも遠く遅くしたい。血鬼術だから、日光にあたるので治せないのだろうか。そう思うも、しのぶの音と様子からこの血鬼術は例の鬼を倒さねばならないのだろうことが予想できる。
「……俺がその鬼を探して倒します!!」
「…………わかりました。ひとまず、炭治郎君の様子をみたいのは確かなので、善逸君は禰󠄀豆子さんを連れてひとまず水柱の屋敷に行ってください」
しのぶはそう言うと手紙を書くのか、用紙と筆を取り出した。机に向かい、書きつけている姿を見ながら善逸は「えっ?いいの?」ともじもじする。
「ひとまず、春まで様子を見ましょう。その間に鬼を見つける必要がありますね。近い将来、鬼舞辻無惨との決戦が予想される中、実力のある隊士が本来の力を失うのは痛手ですから。善逸君はひとまず、炭治郎君の兄弟子である水柱の冨岡さんのところに禰󠄀豆子さんを連れて身を寄せてください。冨岡さんには私の方から連絡をしておきます」
しのぶはそう言うと手紙を鎹鴉に持たせて飛ばせた。あっという間に飛んでいく鴉に善逸はぽかんとしたが、椅子がキィと回転する音に視線をしのぶに戻した。
「春まで、時間をあげますね」
「……はい」
善逸はこくんと頷くと執務室を後にした。しのぶには見抜かれているのだろう。炭治郎と禰󠄀豆子の為と言いながらも、これは善逸の我儘であることを。
(……でも、だって……だってさぁ!)
善逸はボダボタと涙を溢しながら廊下を歩く。善逸は炭治郎が禰󠄀豆子を愛しそうに見て名前を呼ぶのが好きなのだ。優しくて、幸せな気持ちになれる。自分にはひとつも関係がないものだけど、側から見ているだけでお溢れもらって幸せな気持ちになれるのだ。それなのに、炭治郎が禰󠄀豆子を忘れてしまったなんて。
(禰󠄀豆子ちゃんを大事にしない炭治郎なんて……)
善逸はそっと炭治郎が眠っている部屋に滑り込んだ。ヒューヒューと苦しい寝息に怪我が酷いのだと胸が痛い。炭治郎が何をしたと言うのだと喚いて転がりたい。けれどそれをして起こすわけにはいかないので、炭治郎が何も知らず、意識を失っている今が好機だ。
(炭治郎……禰󠄀豆子ちゃん……ごめんっ!!)
善逸は眠っている禰󠄀豆子が収まっている木箱を拾い上げると、炭治郎を振り返らずに駆け出した。朝日が登ったばかりの早朝の蝶屋敷。その廊下を踏み鳴らし、玄関を飛び出し、誰にも見られず禰󠄀豆子を攫う。
(ごめんっ!ごめんっ!ごめんっっ!!)
善逸は仕切りに謝りながら日の下を駆けた。心中はぐちゃぐちゃで、仲の良い兄妹を自らの手で引き離してしまったと罪悪感でいっぱいだったが、これしか道はないと走り続けた。本音では、罪をお天道様に焼けだして欲しかったが、善逸は鬼ではないので日に溶けることはなかった。
****
(あれからもうひと月経ってんだよなぁ)
善逸は帰途の中で眠ってしまった禰󠄀豆子を背負って歩きながら、ひと月前のことを思い出す。しのぶから定期的に手紙が届き、炭治郎の様子は把握している。思った通り、意識を取り戻した炭治郎は禰󠄀豆子のことを忘れていたらしい。忘れているかを確認してはいないが、禰󠄀豆子を探すこともしなければ、鬼殺隊に入った経緯を聞けば、『親と弟妹の敵討ち』と答えたのを以ってして、炭治郎は血鬼術に掛かっていると認められることになった。
(……しかし、なんかアイツ、俺のことも忘れてるみたいたけど……なんでなんだろ?)
炭治郎は禰󠄀豆子を忘れていたが、同様に善逸のことも忘れていた。伊之助や義勇のことは覚えていたが、善逸は忘れられていた。ちっとも会話に出てこない善逸の存在に訝しんだしのぶがあれこれ、『我妻善逸』という名を引き出そうと試みたが、一向に出てこないので『忘れている』と判断したのだ。
しかし謎である。炭治郎が禰󠄀豆子を忘れるのは分かるが、なぜ自分も忘れられてしまったのか。まあ、善逸はどこだと探されたりすると面倒なことになるので今は便利であるとしか言えない。禰󠄀豆子が忘れられているのだ。自分が忘れられて悲しいなんて善逸は口が裂けても言えない。
(……俺、普段から禰󠄀豆子ちゃん、禰󠄀豆子ちゃんってよく言ってたもんな。多分、引きずられて忘れられたんだ)
失った記憶の隙間はいいように補完されるとのことだが、善逸の日常には禰󠄀豆子が溢れていた。おそらく禰󠄀豆子を忘れる際に、善逸のことも忘れたほうが記憶の補完がしやすかったに違いない。
善逸はそう納得しながらも、早く例の鬼を見つけなければとテクテク歩く。探すにしても善逸はその鬼の音を知らない。結局は回ってくる任務をこなす他はなく、義勇やしのぶも隠も探してはくれているようだが隠れるのが上手い鬼は見つかりはしなかった。
(早く鬼を倒して、禰󠄀豆子ちゃんを炭治郎に会わせてやりたい)
了解も取らずに連れ出した禰󠄀豆子は、兄がいないのに何も言わなかった。最初に「お兄ちゃんは今ちょっと大変だから、俺と一緒に待ってようね」と伝えはしたが、てっきり帰りたがると思っていたのに反し、禰󠄀豆子は大人しく待つ様子を見せたのだ。
禰󠄀豆子が善逸の言葉をどう解釈したかは分からない。日々、楽しそうに水柱の屋敷の中で過ごし、時たま善逸と夜を駆けるが、禰󠄀豆子の本当の心は善逸の耳でも読めなかった。
(早く、早く迎えに来いよ炭治郎!!自力で思い出したっていいんだぞ!!)
そう思いながら、石を蹴り、善逸はようやく見えた水柱の屋敷の塀の横を歩いた。一人きりで暮らしているのに柱ということで家が広い。玄関まで行くのにも一苦労だと塀を曲がると、遠くに人影が見えた。
療養服に草履姿で門扉に佇む姿。善逸は聞こえてくる泣きたくなるような優しい音に、別の意味で泣きたくなる。
「あっ」
その空気の振動が聞こえた瞬間、善逸は素早く踏み込み門扉の前にいる相手の口を手のひらでバシリと塞ぐ。相手は突然のことに赤銅の色をした瞳を大きく見開かせ驚いている様子だったが、善逸にはどうでもいいことだ。そんな事よりも善逸には守らねばならないものが背中にあるのだから。
「騒ぐな。一言も声を出すな。眠ってる子がいるんだよ」
こくこくと頷く相手に善逸は本当にわかっているのかと睨みつけて凄む。音がどきどきと煩いのに、無性に殴りたい気持ちになったが、そんな騒ぎを起こせば禰󠄀豆子が目を覚ます。
「ちょっとそこで待ってろ。寝かせてくるから」
善逸はそう言って、門扉の前になぜかいた竈門炭治郎を捨て置くと、禰󠄀豆子を奥の座敷に寝かせようと水柱邸に入っていくのだった。
****
ちよちよと鳥が鳴くのをぼんやり聞きながら、竈門炭治郎は先程の一瞬を思い返していた。本当に、一瞬。瞬いたと思ったその後には目の前にいた。さらりと口元を押さえつけられ、文字通り一言も出せない状態に目を剥くよりも早く彼は言った。
「騒ぐな。一言も声を出すな。眠ってる子がいるんだよ」
それはとても切実な匂いがして、竈門炭治郎は神妙に頷いた。我妻善逸の背中には木箱があり、確かに鬼の匂いがするので眠っているというのはその鬼であろう。
竈門炭治郎は待っていろと言われるがまま、門扉の側で待つことにした。外で待っていてもよかったが、中に入っていいというように開けたままにしてくれたので、そろりと庭の中に入る。久しぶりに来た水柱である義勇の屋敷の様子にそういえばと我妻の言葉を思い返す。
(……寝かせてくるって言っていたけど、ここに住んでいるのか?)
前に冨岡の家に来た時は、一人きりだと話していた。ということは我妻達は今は義勇の元で厄介になっているのだろうかと竈門炭治郎はくびを捻る。
(義勇さんが継子をもつなんて、あまり想像できないな)
義勇は性格のこともあり、あまり継子をもつ印象はない。そして一言二言しか会話をしていないが我妻善逸もまた誰かに師事するというようにも見てなかった。そもそも水の呼吸と雷の呼吸であるし、確かに呼吸が違っても継子にはなれるが、どうにもしっくりこない。
(うーん?じゃあ、間借りしてるのかな?)
自分も蝶屋敷で伊之助と一緒に部屋を借りているし……と思って、竈門炭治郎は眉を顰めた。そもそもなぜ自分は蝶屋敷の部屋を間借りをしているのだろう。蝶屋敷に初めて踏み入った切っ掛けは入院であったが、その後は退院している。そして無限列車の任務後に再び蝶屋敷で世話になっているが、なぜ女性ばかりの屋敷で部屋を間借りしているのか。
(…………?なんでだっけ?流れでそうなったんだったかな?)
竈門炭治郎が経緯を思い出そうと頭の中を探っていると、警戒した匂いと共にざりざりと地面の砂を蹴る音が聞こえて意識を目の前に戻した。向かってきているのはもちろん我妻善逸で、竈門炭治郎はなぜか待ち遠しかった対面に口元をにこーっと釣り上げる。しかしそれを見た我妻は訝しむ様子を見せた。
「なんだよその笑顔。……で、なんの御用ですか?水柱ならいないぜ?」
じろりと睨まれるのに、竈門炭治郎は怯まず元気よく挨拶しようと息を吸った。しかしすぐに「小声で話せよ?」と出鼻をくじかれ、ポソポソと声を出す。
「俺の名前は竈門炭治郎です」
「俺は我妻善逸だよ」
「えっと……」
「だから、冨岡さんはいないんだって。用があるなら静かに庭で待てよ。中には寝てる子いるから。驚かせたくないんだ」
我妻は言いたいことを言ってしまったのか、ぐるりと向きを変えると家の裏手の方に行ってしまう。あっという間に置き去りにされたのに、竈門炭治郎はぽかんとしてしまうが、庭には居ていいという話なので我妻の後をついていく。
我妻は家の裏手にある風呂焚き口の側にくると、刀を抜いて壁に立てかけた。そして斧を手に取る。近くに丸太が転がっているのを見るに、風呂を焚く為に薪を割ろうとしているのだろう。我妻が慣れた手つきでやり始めたのを、竈門炭治郎はなんとなくじっと見てしまう。
カン、コン、パキンッ。
カン、コン、パキンッ。
次々と作られる薪。我妻は近くにいる竈門炭治郎のことなんて何も気にせず、我関せずで薪を作っていく。しかし我妻から漂うのは緊張と警戒の匂いだ。竈門炭治郎は我妻善逸が自分を怪しんでいるのにどうしたものかと迷った。
(会話の糸口を見つけたいけど……きっと我妻君は静かにして欲しいんだよな。鬼の子は寝ているみたいだし、起こさないでそっとしてあげたいんだ)
我妻が『親友の妹である鬼の子』が大事にしていることに、竈門炭治郎は「優しいな」と胸の中が温かくなり、あと何故か嬉しい気持ちになる。人が誰かに優しくしている姿は、確かに心温まるし、嬉しくなるものだが、それが我妻であると思うと沸き立つような心地がある。
(鬼の子を連れているのは、ちょっと危ないんじゃないかって思った筈なのに……)
なのに出会い頭に『喋ったら殺す』と言わんばかりの視線と勢いに『危ないのでは……?』なんて中途半端な気持ちは吹き飛んでしまった。我妻は竈門炭治郎が想像できないほどの覚悟で、鬼の子を背負っている。絶対に何が起きても、世界中が鬼の子の死を望んだとしても、我妻はそれに当たり前のように抗うのではないかと思うほど。
(……俺には……真似できない)
竈門炭治郎はどうしてかそう思った。
「……え?おまえ、そこで何してんの?」
「え?」
「冨岡さんに会いたいなら、家の表にいた方がいいんじゃないか?」
ふいに我妻に話しかけられて炭治郎は驚いた。我妻は薪を作り終わったらしく、それを拾い上げ風呂焚き口に詰めていく。どうやら今から風呂を沸かすらしい。炭治郎はそれをぼんやり眺めていたが、質問をされていたのだと思い出して何となく手を揉む。
どうすべきか。ここに来たのは冨岡に会うためなのは確かだが、冨岡に会いたかったのは我妻について何か知らないかと問うためだ。けれど予想に反して目的たる本人がその場にいた。
(我妻君に興味があってって……言ったら怪しまれるかな?)
竈門炭治郎は、なぜこんなに我妻のことをもっと知りたい欲求が自分にあるか分からない。確かに玄弥と居合わせた時も、せっかく同期だし、仲良くなりたいなと色々と押しかけていったが、居合わせたからというところが大きい。現に再会するまでは「玄弥はどこだろう?」なんて探し回ることもしなかったし、本人の知らぬところで勝手に探ることもしなかった。
(はっ!そうだ!俺……我妻君に関しては随分と人に聞き回ってしまった!!)
どんな人なのか知りたくて、竈門炭治郎は冨岡の屋敷に来る前にも、蝶屋敷で散々色んな人に聞いてしまっていた。アオイ、カナヲ、すみきよなほ、あと村田。「女好きな一面がある」とか「今は違うが、前は鍛錬から逃げていた」とか、「任務が怖いとよく喚く」とか色々なことを言っていたが、最後には「優しい」という評価に落ち着く。それが嬉しくて次から次へと色んな人に我妻の人となりを聞いて回っていたが、考えようによっては嗅ぎ回っていたとも取れるものだ。
竈門炭治郎は焦った。どうしたら変な勘違いをさせないかと言葉を考え、ぐるぐる思考を回していると、杉の葉や薪を風呂焚き口に入れ終わった我妻がゆらりと立ち上がる。
「おい……お前、まさか……」
「うっ!?」
「あの子のことを怖がってるとかないだろうなぁ!?」
「……あの子?」
猫背になった我妻がやや下かは睨みつけてくる。おどろおどろしいとも言えるほどのその睨みに、竈門炭治郎は一歩下がった。すると我妻は追いかけるように一歩を踏み出す。
「あの子は優しいし、可愛いし、絶対に人は食わない。お前がもし何か悪い話聞いてたとしてもそれは真っ赤な嘘だからな!?お前は、髪の毛一本分でも怖がるんじゃねぇぞ!?」
「あ、ああ……いや、怖がってはないよ。大丈夫だ」
「本当か?嘘だったら承知しねぇからな。俺に嘘は通じないぜ?」
我妻はギリギリと歯を鳴らし、風呂焚き口の前にしゃがむと杉の葉に火をつけ、ふいごで風を送り出す。竈門炭治郎は慣れた手つきで風呂を沸かす我妻に、扉を閉める為の棒を渡してやった。我妻はそれを受け取ると、火がついた風呂焚き口の扉を閉める。
「ありがと」
「いや、随分早く風呂を沸かすんだな」
「俺、任務終わりなの。風呂に入ってなくて汚れてるからな」
「あ!そうか!任務終わりだったのか!!」
竈門炭治郎はハッと気がついた。確かに我妻は隊服を着て、朝に帰って来ている。もしかしなくても休みたかったのに、邪魔をしたのではないかと申し訳ない気持ちになってくる。
「ごめん、休むところだっただろう?」
「いやいいよ。どうせ風呂は沸かさないとだし。……冨岡さんはだいたい昼前に戻ってくるんだよ。そんで帰ってきてすぐに風呂入るんだわ。ちょっと前までは入らないでも寝てたんだけど……ここのところやたらに風呂入るんだよなぁ。まあ、汚れてない方がいいに決まってるんだけど」
「へえ、そうなのか」
突然、風呂好きになったのだろうか、なんて竈門炭治郎はのほほんと考えた。とりあえず風呂焚きを始めてしまったということは、一時間半くらいは我妻はここにいるということだろう。しかし任務を終わらせてきて、風呂焚きをしないといけないなんて大変だ。蝶屋敷では行けば風呂が沸いているし、藤の花の家紋の屋敷でも家の人が沸かしてくれる。
「……なあ、沸かすの代わろうか?」
「へ?」
「我妻君、疲れているだろ?俺は療養中で任務はないし」
「……いいの?」
「もちろん!」
「やった!ならお願いするわ〜」
我妻はそう言って立ち上がると伸びをした。コキコキと首を動かすのに、やはり疲れているのだろうと竈門炭治郎はなんとも言えない気持ちになる。疲れるのは大変だが、人を喰った鬼は狩らねばならない。だから無理せずなんてことは言えないが、終わった後は労ってやりたい。
「任務、お疲れ様。ちっとも汚れてないから、気がつかなかった」
そう。我妻は泥汚れが殆どなく、またいやな鬼の匂いも染み付いていない。任務に行けば身が汚れるものと思っていたが、我妻は随分と綺麗なものだった。
「まあ、俺は基本的に一撃だからな」
「えっ!?」
「技が一つしかないのよ。一つの技を応用したりはするけどさぁ。まあ、素早く近づいて首を落とすだけなの。居合いの型だし。それが一番怖くないし」
やれやれと言うように我妻は木屑を払うと、平たい丸太の上に腰をかけた。竈門炭治郎は我妻の一撃という話を聞いて、出会い頭に素早く間合いを詰められたことを思い出す。あれよりも早い速度で、そして居合抜きでとなれば、それは凄いことだろう。
「凄いなあ。一つの技を極め抜くのって、格好いいよな」
竈門炭治郎は自分の技の多彩さに助かってはいるが、どれもこれも習熟するのは難しい。なんとか形になっているに近く、正直、刀鍛冶の里で絡繰り人形との鍛錬がなければ今も上手く扱えない技が多かっただろう。だからこそ、一つの技に全てを注ぐその姿が眩しく見えるのだ。
(……ん?)
竈門炭治郎は自然に脳裏に走った雷光に首を傾げた。我妻の技は見たことはない。しかしなぜ、雷光のような印象持ったのだろうか。話に聞いているせいだろうか。
「俺はたくさんの技を使えるのを尊敬するよ」
ポツリと溢された言葉に、竈門炭治郎は振り返った。羨ましいという匂いも表情を隠しもしない我妻にきょとんとしてしまう。我妻は頰を膨らませると、下からむすりと睨みつけてきた。ふくふくの頬っぺたはとても柔らかそうだ。
「……えい」
「ぶっ」
膨らんだ頰を指先で突けば空気が唇から抜けた。竈門炭治郎は驚いた顔をしている我妻に笑うと、薪が燃えた匂いを感じて風呂焚き口の扉を開けた。そしてそこに新しい薪を追加して閉める。
「なにすんだよぉ!」
「いや、面白いくらいに頬が膨らんでいたから」
「はあ〜?」
ぷんすかというように怒る我妻に竈門炭治郎は楽しくなってきた。初対面だというのに、こんなに楽しいなんてと伊之助と鼓屋敷で出会った時のことを思い出す。あの時は双方の意見の違いでやり合いをしたが、その後は親友になれたのだ。
(我妻君とも友達に……伊之助みたいな……)
そう思ってピタリと固まる。我妻善逸は死んだ親友の代わりに鬼を背負っているのだ。そのことを思い出したら、なぜだか心が萎んでしまった。彼にはもう、かけがえのない親友がいるのだ。この世にはいなくても。
(……親友は一人だけと決まってるわけじゃないけど……)
けれどきっと自分は我妻の親友には勝てないだろうと竈門炭治郎は思った。死んだ人間にはどうやっても勝てない。友情に勝ち負けはない。けれど、特別さはやはりあるだろう。
(俺はなれても二番手の友達かな……)
そう思うと急にしょんぼりしてしまう。一番がいいなんて子供みたいだし、言うべきことではないが、竈門炭治郎はしょんぼりしてしまったのだ。それが全てだ。自分が死んでも、願いを親友が引き継いでくれるなんて、どれほど幸せなことなのだろうか。死にたくはないが、我妻の親友が少しどころではなく、羨ましい。
「……そういやお前、療養中なんだろ?こんなとこまで来てていいのか?」
「え?」
我妻の言葉に振り返ると、我妻は探るような目をしていた。ジロジロと上から下まで見られているが不快感はない。それは我妻から心配する匂いがしているからだ。
「ああ、実は体はもうすっかりいいんだ。機能回復訓練も順調だし……そろそろ任務復帰できると思う。刀を待ってるだけなんだ」
「へえ、そうか。そりゃ大変だな」
「大変?」
「また戦わなくちゃならないじゃないか」
嫌だ嫌だという思いを隠さない我妻に、竈門炭治郎は笑った。我妻善逸と話すのは楽しい。最初は話題をどうしようと思ったが、話が始めれば流れる水のようにとめどない。
「俺は早く鬼と戦いたいよ。家族の仇をとりたい。俺と同じ悲しみを持つ人を一人でも減らしたい。そうしないと落ち着かないんだ」
「……ふーん」
竈門炭治郎が笑ってそう言うと、我妻は急に冷めたようにそっぽを向いた。それにあれっと思うも、途切れた会話は戻らない。何かいけない事でも言っただろうかと焦りながらふいごを動かす。なにか話題を見つけなければ。
「……我妻君はその、大事な子と離れてていいのか?」
「え?」
「ここは俺がやっておくから、その……屋敷の中で寝かせているんだろ?一人にさせて、心配だったりしないか?ほら、起きて君がいないと探し回ってしまうかも。鬼は日に当たるとその……」
我妻が興味を持っているものがわからず、知っている情報を元に話を振ったが上手くできない。もごもごと誤魔化すようになってしまった言葉尻に失敗したと竈門炭治郎は焦った。風呂焚き口を閉め、どうしようとふいごを握り締め続ける。
「……起きたら分かるんだ。俺、耳がいいから。でも、じゃあ、お言葉に甘えて部屋に戻ろうかな。終わったら終わったって普通に呟いてくれれば聞こえるから」
我妻はすっかり表情をなくしたまま立ち上がった。耳がいいからという言葉に竈門炭治郎は驚くも、自分や伊之助と同じようなものかとすんなり納得できた。
「うん……」
「じゃあな」
我妻はそう言って勝手口から屋敷に上がってしまった。竈門炭治郎は我妻に何か申し訳ないことをした気持ちになり、肩を落とす。それなりに楽しそうにしてくれていたのに、突然、山の天気のように機嫌が変わってしまった。
(……鬼の子の話はもしかしてされたくないのか?急に警戒されたように感じたぞ)
もしかしなくても、我妻の中では鬼の子は慎重にならざるを得ないことなのかもしれない。親友の忘れ形見。我妻はそれを背負い、守りながら戦っているのだろう。鬼殺隊は鬼に恨みを持つ人間が多い。人を喰わない鬼だとしても、お館様に、柱に認められていても興味を持つ人間には警戒するのかもしれない。
(失敗した。次にいかそう)
「おい」
次の機会では鬼の子のことにはなるべく触れないようにと竈門炭治郎が反省し、改善点を考えていると、去ったはずの我妻がまたひょこりと顔を出した。
「え?」
屋敷に戻ったのではと目を瞬かせれば、我妻はお盆を持って近寄ってきた。そこには茶の入った湯呑みと饅頭が乗っている。
「これ、置いとくな」
我妻はそう言って平たい丸太の上にお盆を置いて、さっさと屋敷に戻って行ってしまう。竈門炭治郎はその後ろ姿を見送って、お礼を言い忘れてしまったなと恥ずかしさで頰を赤く染めたのだった。
****
「今朝は朝ご飯が鯵の開きだったんだ。大きさは俺のも伊之助のも殆ど同じだったけど……伊之助が俺の方のが大きいとか言い出して……」
「なに?取られたの?」
「取られたというか交換だな。俺のを伊之助にやって、伊之助のを貰ったんだが……そしたら、やっぱりそっちの方が大きい気がするとか言い出して」
「目に浮かぶようだわ」
「あはは。……我妻君は今朝は何食べたんだ?」
「んー……隠の人が用意してくれたしゃけ大根」
「へぇ。美味しそうだ」
「美味かったよ」
「隠の人、朝ご飯は作ってくれるのに風呂は沸かしてくれないのか?」
「……そういやそうだな。まあ、でも昼間は任務に行ってるみたいで隠の人もいないしな」
「そうかあ」
何気ない会話をしながら、困ったことになったと善逸は拳を握り、天を仰ぎ見た。晴れ渡る空の青は薄く、冬空である。空気も緩むこともなく冷たくて、春はまだ先。春がまだ先ということは、善逸が恐れている「記憶がない炭治郎に禰󠄀豆子を会わせる」という責務を果たすのが先ということだ。まだ時間に余裕はある。しかし実際の善逸には余裕はなかった。なぜなら、禰󠄀豆子と合わせたくない相手が足繁く冨岡の屋敷にやってくるからだ。
(こいつ……なに考えてんだ?)
善逸はそう思いながら、汗ばむ拳を開いた。目の前では今日も代わりに風呂焚きをしてくれている療養着姿の炭治郎がいる。炭治郎はだいたい朝食を食べ終わった頃にやって来て、昼前に帰ってくる冨岡の為に風呂焚きをする。元は善逸がやっていた仕事だが、どうやら二人は未だ会えていないらしく毎日のように炭治郎は屋敷にやってくるのだ。とはいえ、善逸も任務があるので毎日は家にはいないのだが。しかし翌日にやってきた炭治郎の弁で、毎日来ていることを知っている。
(今のところ、こいつが来るのは午前中で、禰󠄀豆子ちゃんが寝てる時間帯だからいいけど……でもいつか、鉢合わせしちゃうんじゃないか?)
善逸はダラリと汗を流しながら、目の前でしゃがんで火起こしをしている相手を睨んだ。ここから炭治郎は風呂が沸くまではこの場にいる。そこからもう少しいれば冨岡に会えると思うが、戻らねば昼餉がなくなるとのことで帰ってしまうのだ。
連日、来させるのをやめさせるには、引き止めて昼餉を食べさせて冨岡に引き合わせればいい。それを善逸とて分かっているが、禰󠄀豆子は昼餉あたりで目を覚ますことが多いのだ。もう陽の光を恐れなくていいので、禰󠄀豆子は目を覚ましたら飛び起きて屋敷の中を駆け回るだろう。
(午前のうちに帰ってもらわないと困る。禰󠄀豆子ちゃんにこいつを見せるわけにはいかない)
ここにはもう、来ないで欲しいと言うのは流石に横暴だ。なにせここの家主は冨岡で、炭治郎は冨岡の弟弟子なのだから。善逸はただの居候。しかも自分の我儘で禰󠄀豆子と炭治郎を引き離しているに過ぎない。それに冨岡は付き合ってくれているにすぎないのだ。
(……俺がこだわり過ぎなのかな?)
たまに、善逸は自信がなくなる。今やっていることは悪なのではと心が苦しくなる。仲の良い誰よりも優しい兄妹達を引き離す意地悪をしている。炭治郎の禰󠄀豆子は決して離れないことを誓っていた。どこまでも一緒に行くと。それなのに、それを知っているのに、善逸は禰󠄀豆子を攫ってきてしまった。
禰󠄀豆子が炭治郎に知らないと言われて傷つく音を聞きたくない故に。
炭治郎が禰󠄀豆子を前にして平坦な音を立てるのを聞きたくない故に。
(……でも、もしかしたら二人は特別な兄妹だからお互いを前にしたら炭治郎の記憶がすぐに戻ったりして……)
善逸は淡い期待をするも首を振った。それはあまりに希望的観測だし、もし失敗したら禰󠄀豆子が傷つくばかり。そして炭治郎もまた元に戻った時に悲しむだろう。忘れたこと自体はもうどうにもならない傷だが、禰󠄀豆子に傷をつけるのだけはなんとか防げるかもしれないのだ。善逸は禰󠄀豆子を傷つけることは断じて許せない。それが兄たる炭治郎でも鉄拳制裁だ。
(……ちくしょう。こんなに日に当たってるのになんで治んないだよぉ……。しのぶさんも血鬼止め飲ませてる筈なのに……)
善逸は目の前の炭治郎の音に耳を澄ませた。炭治郎からは明瞭で、健康で、やはり泣きたくなるような優しい音が聞こえてくる。しかしその音は今にも水に溶けて消えそうなくらい、薄い。切なさと寂しさを優しさと覚悟の薄膜で包んだような、そんな音だ。以前と比べると、大きく音が違う。禰󠄀豆子を忘れているからか、重厚感ある音が二音も三音も欠けている。
(やっぱり……覚悟の違いがあるのかも……)
しのぶか言うには炭治郎が鬼殺隊に入った理由は『妹を人に戻す為』ではなく、『親弟妹の仇打ち』にすり替わっているそうだ。確かに禰󠄀豆子の存在が炭治郎の中から消えれば、残るのは『親弟妹を殺され、一人だけ生き残ってしまった』という絶望だけだ。
実際には禰󠄀豆子がいて、炭治郎は禰󠄀豆子の為に生きることになったが、本当に一人残されていたらどうなっていたのか。記憶から禰󠄀豆子を奪われて炭治郎は一人生き残るという絶望を無理やりのように体感しているのかと思うと善逸は切なくなってくる。
善逸は目を細めると、炭治郎の背中をじっと見た。聞こえる血流の音から血管がある箇所を探ってしまう。炭治郎が生きている音。しかし善逸がよく知る炭治郎とは生き様の音が違う。
「……あの、我妻君。なんでそんなに見るんだ?」
「へ?」
掛けられた声にハッとして相手の顔を見れば、炭治郎はうっすらと頰を染めて振り返っていた。善逸はなぜ炭治郎が頰を赤らめているのかわからない。風呂焚きしていて暑いのだろうかと、炭治郎から聞こえる弾んだ音を聞こえないフリしてそっぽを向いた。
「あー……ごめん。俺、耳いいからさ。相手の体調どんなもんか分かるのよ。……すっかり健康みたいだね?」
音から判断するに、炭治郎はすっかり体調が戻っているようだった。どこかを庇うような動きもなく、以前の状態とほぼ同じであろう。善逸がそう言ってそっぽを向き続けていると、立ち上がった炭治郎はわざわざ視界に入り込んできた。
「そうなんだ!すっかり身体は良くなったんだ!」
嬉しそうな顔をして力瘤を作って見せる炭治郎にへぇーとか、ほーんとか善逸は相槌を返す。そんな雑な相槌にも炭治郎は嫌な顔はしない。しかしだらりと腕を下ろすと、難しそうな顔で「でも……」と言葉を漏らした。
「伊之助に全然敵わないんだ。前はほぼ互角だったのに、何回手合わせしても一本も取れない。前より弱くなってるかもしれないんだ」
その言葉に善逸はゾワっと背筋が震える。冷や汗が大量にでて、血の気が下がる音がした。善逸は耳から心臓がまろび出たのではないかと思うくらい、鼓動を高鳴らせ、言った。
「なら、俺とも手合わせしようぜ」
耳から心臓は出ていないが、口から言葉はまろび出た。善逸は己でも予想外な言葉に動揺するも炭治郎の『伊之助に勝てない』という情報の真偽について気になって仕方がない。嘘は言っていない。そんな音はしていない。ということはそれが真実であり、真偽を確かめる必要はないのだが、実際にこの目で確かめねば気が済まなと思ったのだ。
善逸は炭治郎の返事を待たずに風呂の隣にある道場に向かった。そして中に入ると壁にかけてある木刀を手に取る。
(炭治郎が、伊之助に勝てない。それも一回も勝てない)
そんな馬鹿なとしか思えない。自分達の手合わせでは、確かに伊之助の勝率はいい。勝ち星の数では伊之助、炭治郎、善逸の順で間違いはなかった。むしろ善逸こそ二人に勝てた回数が少ない。手合わせの数が少ないせいもあるだろうけど。
しかしその分、二人はお互いで手合わせをする回数が多い。つまりはお互いの手の内を知っているわけだ。勝ち星は伊之助の方が多かったとしても、炭治郎だって負けていない。なのに今、伊之助に勝てないということは……と、善逸は木刀を二本持って風呂焚き口のある場所まで戻った。
「え、あの……」
「ほら。軽くでもいいから」
「……いや、本気で頼む。正直に話すと、君と手合わせしてみたかったんだ」
炭治郎は木刀を受け取ると距離をとり、ワクワクした顔で振り返る。善逸は炭治郎が『君』とか『我妻君』とか呼ぶのに背筋が痒くなるし、寒い。ぐっと心臓が握りしめられたように痛んだが、無視して構えた。
「言っとくけど……俺は弱いぜ?」
善逸はそう言って炭治郎を待たずに踏み込んだ。まずは霹靂一閃と踏み込んで振り抜く。踏み込んで一拍もせず、炭治郎の目の前だ。炭治郎は驚いた顔で、しかしちゃんと一撃を防いだ。眼前に木刀を持ってくるのがあと一瞬遅かったら吹き飛んでいただろう。踏ん張りもなんとかできて、体勢も大きく崩れはしなかった。しかし勢いに押されているのか、炭治郎は防戦一方だ。斬り返してくることはなく、善逸は難なく後ろに戻り距離を取る。
(反応がすでに遅いな。いや、でも体温まってないし、俺を忘れてるなら速さに慣れてないのかも)
善逸は構え直すと霹靂一閃ではなく、そのまま打ち込みにいった。型は使えないが打ち合いくらいはできる。まずは準備運動とばかりに軽く打ち合い、音と、目で、炭治郎が打ち込む水の呼吸をかわす。
(……う、遅……い……)
善逸は炭治郎の型が目で追えたのにドッと汗が出た。普段ならば筋肉の音で技の予測を立てて避ける動作に入るが、今回は見てから避けられるくらいの勢いしかない。一般隊士としてはかなり強いが、これでは死ぬ。上弦にあたれば間違いなく死ぬ。あっという間だろう。
(よ、弱くなってる!!)
善逸はあまりにも軽い剣の威力に愕然としてしまいそうだ。鍛錬でさえ、あんなにも重い一撃だったのにと、打ち合う度に胸が張り裂けそうになる。これは確実にもう、炭治郎は弱くなったと言わざるをえない。炭治郎は禰󠄀豆子という存在を失い、その剣に乗せる重さがなくなってしまったのだ。だからこんなにも剣が軽い。
そもそも善逸が炭治郎と打ち合えている段階でお話にならない。打ち合えば不利になるから、善逸は炭治郎とも伊之助ともあまり打ち合いをしない。一撃必殺を狙っていくし、炭治郎や伊之助は一瞬の必殺に負けぬ為に善逸と鍛錬をしたがった。
(どうしよ……炭治郎、めちゃくちゃ弱くなってる……!)
善逸は炭治郎の技を難なくかわしつつ、距離を取っては型を打ち込んだ。炭治郎も少しずつ速さに慣れてきているのか、対応できているが善逸が打ち込んでいるのは霹靂一閃のみだ。六連も八連も使っていない。使えばあっという間に勝ててしまうのが分かるから使ってはいなかった。
(……ええい!!)
善逸はこれ以上は良くないと溜息を押し殺し、瞬きする間に距離を取ると、瞬きが開き切る前に踏み込み、炭治郎の持つ木刀を撃ち飛ばした。
「あっ……!」
木刀が折れ、宙に舞う。カランカランカランと二つの木片が地面に転がる音が響き、善逸は溜息ではなく深呼吸をした。耳をすませば、まだ禰󠄀豆子は眠っているようだ。霹靂一閃の音で起きて来なくて良かったと、思いの外、短慮なことをしてしまったことを善逸は反省する。鍛錬をすれば煩くなり、禰󠄀豆子を起こしてしまうかもしれないことを失念していた。
(危ない危ない。……もう炭治郎と鍛錬するのはやめておこ。とりあえず現状は分かったし。……それにしても、本当に弱くなってる……)
善逸は絶望的な気持ちになった。炭治郎は全集中・常中は使っているが、上弦の陸と戦った時よりも恐らく弱い。大事なものを失うと、こんなにも人は弱くなるのかと、善逸は恐ろしくなった。
(いや……そりゃそうか。禰󠄀豆子ちゃんは炭治郎の背骨みたいなもんだ)
禰󠄀豆子を人に戻す。その為には炭治郎は生き続けねばならない。死んでいる暇なんてないのだ。死なない為には強くなるしかない。鬼をなんとしても倒して、生き延びるほかない。だか今の炭治郎にはそこまでの覚悟がないのだろう。一体でも多くの鬼を倒す。けれど、生き延びる理由はない。
「……すごい……速い……!」
ドキドキと大きく鳴る鼓動の音に善逸は顔をあげた。すると炭治郎が頰を真っ赤に染めて、目をキラキラさせているが善逸は付き合いきれないなと頭を掻いた。
「そりゃどーも。……はあ、まあいいんじゃない?お前さん病み上がりだろ?今は伊之助に勝てなくても、鍛錬続けてれば元のようになるでしょ」
善逸はそう言ってひとまずこの場を収めることにした。嘘は言わない。今は確かに炭治郎は弱くなっているが、鍛錬次第ではまた強くなる筈だ。
しかし前よりは格段に腕が下がっているのは事実で、これはしのぶが言うようにやすやすと任務に出すのは危険かもしれない。炭治郎の中でどうなっているかは知らないが、本人の思う力と実際の力が乖離していて無茶をするかもしれない。禰󠄀豆子を失う前は無茶ではなくても、今は無茶になってしまう可能性が大きい。
「そうか……うん。鍛錬を続けるよ」
炭治郎はそう言って折れた木刀を拾い上げた。穏やかな表情にはあまりに『決意』が足りない。善逸はそれに目を細めると視線を逸らす。あまり炭治郎を見ていたくない。それは前との違いを探そうとしてしまうこともあったし、違いがない場所を見つけようともしてしまうから。
記憶があってもなくても、彼は『竈門炭治郎』だ。けれど善逸は禰󠄀豆子のことを忘れた『竈門炭治郎』は嫌だ。嫌いではない。でも嫌なのだ。
(……そういや、俺ばっかり炭治郎に会ってる)
禰󠄀豆子に炭治郎を会わせてやれないのに、自分は炭治郎と顔を合わせていることに善逸は罪悪感が募ってきた。禰󠄀豆子には我慢をさせて、自分は炭治郎の音を聞いているなんてと耳を掻きむしりたい。聞きたい音はこれではないのだが、それでもやはり優しい音なのだ。嫌いではない。
「……あの、我妻君」
耳を覆い隠して掻いていたら、炭治郎に呼びかけられて善逸は振り返る。炭治郎はどこか緊張したような表情をして善逸を見ていた。その目の色はいつものように赤銅色で変わらないのに、少し輝いて見えるのは何故だろうか。善逸が訝しむように目を細めると——。遠くで門扉が開く音がした。
「あっ。冨岡さん帰ってきた」
「本当だ。義勇さんの匂いだ」
二人は顔を見合わせると門扉の方へと向かう。冨岡は相変わらず汚れがない状態で、どこを見ているかわからない顔つきで庭の方へとやってきた。おそらく、風呂に入る為に勝手口から入ろうと思っているのだろう。帰ってきたら即風呂に入るのはここ最近の習慣だ。
「義勇さん、お帰りなさい!」
庭にやってきた冨岡と無事に鉢合わせ、炭治郎は出迎えの言葉を伝えた。冨岡は炭治郎がいることを不思議に思ってのか、首を傾げて善逸の方を見てくる。しかし善逸からすれば不思議がっている冨岡が不思議だ。ほぼ毎日、今日も炭治郎があなたを訪ねてきましたよと声を掛けているのに。しかし言っても無駄な相手なのは居候してよく分かったので、善逸は冨岡には何も言わなかった。その代わり、炭治郎に声をかける。
「良かったな炭治郎。冨岡さんだぞ」
「うん?」
「お前、会いたがってただろ?全く、用事なら鎹鴉に頼めばいいのに……」
柱は確かに多忙だが、冨岡と炭治郎は兄弟弟子だ。多少の我儘も通していいのではと、善逸は思う。兄弟弟子は少し、特別なものだろう。そう思って良かったなと炭治郎の肩を叩いてやると、炭治郎はキョトンと不思議そうな顔をした。
「うん?俺は別に義勇さんには用はないぞ?」
「「えっ」」
冨岡には用なし発言に、善逸は焦ってしまう。何しろ目の前にいる冨岡から傷ついた音がしたからだ。本人の前で用なし発言はまずいだろう。いや、それよりも冨岡に用がないとしたら、何故毎日のように冨岡の屋敷にやって来るのだ。
「いやいや!用がないって……えっ!?じゃあなんでここに来てたんだよっ!?毎日のようにお前くるじゃん!!」
「そ、それはその……」
炭治郎はポッと頰を赤らめると頭を掻いた。手に持っている木刀の破片の棘が刺さりやしないかと少し気になるが、それよりも気になるのは炭治郎が足繁くここに通う理由だ。冨岡が理由ではないとすると、もしや覚えてなくとも禰󠄀豆子になにか感じるものがと善逸は期待を募らせる。これは禰󠄀豆子を切っ掛けにすれば、記憶を取り戻すのではと胸を高鳴らせる。
「実は俺……」
「う、うん!」
「我妻君と仲良くなりたいんだっ!」
「はぁ?」
しかし当の炭治郎から転がり出た言葉は善逸の寄せる期待を裏切るものだった。善逸は一瞬で鼻白むと顔を歪めた。聞きたい言葉ではない。期待した言葉ではない。
「俺と仲良くなりたいぃ?」
「そうだ!」
「ケッ」
善逸は唾を吐き捨てると炭治郎の手から木刀を奪い取った。自分と仲良くなりたいなんて興醒めだ。全くもって迷惑だ。そんなことをしたら禰󠄀豆子に悪いではないか。禰󠄀豆子は我慢しているというのに、善逸だけが楽しい思いなんてしていい筈がない。
「お断りだよ。帰れ、もう来んな」
善逸はそう吐き捨てると、ふんっと鼻を鳴らして風呂焚き口の方に向かった。折れた木刀を焚き木にする為だ。善逸はムカムカする心にばかり気を向けていて、後ろから聞こえる炭治郎が傷つく音と、冨岡がオロオロしている様子の音にまるで気がつかなかった。
****
匂いは空気の流れにのる。相手の動きによって空気は揺れ動き、同時に匂いに濃淡がつく。右からの斬撃、左からの斬撃、回転しての蹴りに、その勢いを使っての踵落とし。そして——。
「がっ!」
竈門炭治郎は回し蹴りを下に避けた先の踵落としまでは避けられたが、その後の斬撃を見事に食らう。回し蹴りを下に向かって避けた時の体勢の崩れが尾を引いた形だ。
「俺様の勝ちだ」
「あいたたた……」
「ケッ。相変わらず弱いままだな。そんなんじゃ下弦の鬼にも勝てないぜっ!!」
竈門炭治郎は目の前に木刀を向けてくる伊之助を地面に手をつきながら見上げた。溜息と共に木刀の先端を横にずらし、自分の体たらくにもう一度溜息つく。
「だよなぁ。どうしてだろう……体が思うように動かない。まだ本調子じゃないのかなぁ」
炭治郎はそう言って身体を起こしてもう一度というように木刀を握った。しかしその合間にすかさず羽がやや貧相な鴉が蝶屋敷の塀に止まる。伊之助の鎹鴉である。
「……カァ!嘴平伊之助ェ!任務ゥ!!北北西ノ町ヘ……」
「よっしゃー!!北北西だなっ!!」
「アッ!待ッテッ!伊之助待ッテ!!合同任務ゥ!!水柱トノ合同……聞イテッ!?カァ!!」
伊之助は木刀を放り出し、縁側に立て掛けていた日輪刀を腰に下げると素早く庭を駆けていった。鎹鴉は置き去りだ。鎹鴉がまだ任務内容を伝えている最中なのに、伊之助はさっさと先に進んでしまう。鎹鴉も慌てて羽ばたき、伊之助から少し離れた頭上を飛んでいった。一人と一羽が蝶屋敷の正門の方へ向かう様子に、竈門炭治郎は「塀を乗り越えずにキチンと門扉に向かうところは立派になったな」なんて思いながら見送る。一人きりになった空間で木枯らしが吹き、カサカサと葉が地面を転がった。
「……伊之助。義勇さんと合同任務かぁ。強い鬼が相手なのかな……?あっ!しまった!!門まで見送りに行けば良かった……」
竈門炭治郎はそう呟き、木刀を握り、肩を落とした。伊之助のことだから強い鬼相手でもきっと無事に帰ってくる。何しろ彼は今の自分よりもずっと強いのだから……という半紙に墨汁を垂らしたような己の黒い感情に竈門炭治郎は頭を掻き回した。
「あーーー!!もうっ!!」
どうにも焦っている。竈門炭治郎は己の身体が思うように動かせないことに非常に焦っていた。休んでいる間に伊之助との実力の開きが出てしまっている。もちろん、己が休んでいる間に伊之助がキチンと鍛錬していた証拠かもしれないが……それにしても追い付けなさすぎだろうと、ここまで差があったかと焦れるのだ。
「俺、こんなに弱かったかなぁ」
上弦の陸も、上弦の肆も今の自分ではまるで歯が立たないだろう。刀鍛冶の里でカラクリ人形と鍛錬をした意味はと、人形師の少年にも申し訳ない気持ちになる。人形を半壊させた引き換えに鬼を倒す強さを得た筈なのにと竈門炭治郎は己の手を見つめた。
「何がいけないんだろう……」
結果が思うように出ないことに叫び出したい。この感覚は久しぶりだ。狭霧山で鱗滝から教えを乞えなくなり、一人で岩に立ち向かっていた頃に似ている。あの時は見かねた錆兎と真菰が力を貸してくれたが……今の自分の前には出てきはしないだろう。
「……焦ったらだめだ。鍛錬あるのに……。キチンとしていれば、いずれ結果はでる」
竈門炭治郎は己に言い聞かせるようにそう呟き、「本当に?」と心の中で問いかけた。浮かぶのは金色の髪を持った隊士の言葉だ。彼は今は病み上がりだから、鍛錬を続けていれば元に戻ると励ましてくれた。しかし——。
(あの時の我妻君、複雑な匂いをさせてた……。心配と、失望……?俺が思った以上に弱かったって思ったのかなぁ。伊之助と全然違うって、思われたのかなぁ)
人の強さについてどうこう考えることはあまりない。鬼には血鬼術や異形という問題があるので必ずしも隊士が複数いても共闘が叶うとは限らない。目の前にいる鬼を倒す為に、自分ができることをする以外の方法がないのだ。そして任務を共にする隊士を信じるほかない。
(でも……一緒に任務をするなら、自分くらい強い人の方がいいよなぁ)
実際問題、任務は階級が似ている者たちで纏められる。那田蜘蛛山の時は規模が大きすぎて階級が真ん中から下の範囲という感じであったが、階級が離れ過ぎていると足手纏いになるからいても意味がない。そう考えると任務を一緒にしたことがあるという我妻と伊之助は階級がほぼ変わらないのであろう。つまり、強さも同じくらいということだ。
(俺も我妻君と一緒の任務をしてみたいな)
自分は技が多いし、ひとつの型を応用して戦っている我妻の補助もしやすいのではと竈門炭治郎は考えたが、今の己は伊之助にまるで敵わない。追いついていないという事実に肩を落とす。共闘するならば、伊之助が選ばれるだろう。現に、今回も義勇の相手には伊之助が選ばれている。
「まあ、俺はまだ任務に出れないしな!」
竈門炭治郎は機能回復訓練中だからと頷いたが、すぐにじわっと心が震えた。おかしい。前はもっと早く任務に復帰できたのにと己の不甲斐なさを感じる。
「……よしっ。しのぶさんに相談しよう!」
しのぶからは任務復帰の話は出ていない。もしかせずとも以前の調子は出ていないことを把握されているのかもしれない。しかし上弦や下弦の鬼ほどの相手は無理でも、それ以下の強さの鬼なら倒せると炭治郎はしのぶの執務室に向かった。鬼殺隊は万年人手不足だ。強さが元に戻っていなくても出来ることはあるはず。
竈門炭治郎は庭から屋敷に上がると、しのぶがいるであろう執務室に向かう。蝶屋敷は常日頃、藤の花の匂いがする。もちろん、庭には藤の花の木が植えられているが、藤襲山とは違って一年中咲くなんてことはない。普通の藤だ。
(しのぶさんはこっちだな)
しかし屋敷には藤の花の匂いがする。それは屋敷の主人たる胡蝶しのぶから漂うものだ。出会った頃から藤の花の濃い匂いがしていたが、最近は彼女の感情の機微がまるでわからない程に藤の花の匂いが濃い。胡蝶しのぶは藤の花の毒を使う剣士だ。上弦の鬼を半分倒したいま、鬼殺隊はら鬼舞辻無惨との決戦を予感している。胡蝶しのぶもまた、より強い毒を調合しているのかもしれない。
「ん?あ、すみちゃん」
「あ!炭治郎さん!」
廊下を歩いていると随分と重そうな箱を持ったすみと鉢合わせた。竈門炭治郎はすみの身体半分はありそうな大きさの箱に、大変だと箱に手を伸ばした。
「俺が持つよ。こんな大きな荷物、運ぶの大変だ」
「え?いいんですか?」
「うん。どこに運ぶの?」
「これは納戸に。奥の棚にちょうど入る場所があるので……」
「納戸だね。分かったよ」
竈門炭治郎はそう言って箱に手をかけようとした。すみはホッと息を吐き、嬉しそうな匂いを醸し出して微笑みかけたが……すぐにハッと顔を硬直させると身を捻って箱を竈門炭治郎から遠ざけた。
「やっぱりいいです!大丈夫です!」
「え?でも……」
「重くないので!!炭治郎さんは手伝わなくていいんです!」
すみはそう言ってトタトタと走って行ってしまった。しかしその足取りは遅く、おぼつかない。竈門炭治郎はどうしようと迷ってすみの後を追いかけようとしたが、背後から濃い藤の花の匂いが漂ってきて立ち止まった。振り返れるといつものように微笑む胡蝶しのぶが立っている。
「しのぶさん」
「こんなところで立ち止まって、どうかされましたか?」
にこりと微笑むしのぶからはやはり感情の匂いはしてこない。いま、何を考えているのだろうかと思いながら、竈門炭治郎はしのぶに向き合う。そしてチラリと首だけで振り返ると、大きな箱を持ったすみが廊下曲がるところであった。
「いえ、大きな箱を納戸に運ぼうとしているすみちゃんと出くわして……手伝おうと声を掛けたんですが断られたところなんです」
「ああ。私が片付けるようお願いしたものですね。すみだけで十分運べるものですから、大丈夫ですよ。見た目に反して中身は軽いんです」
そう言ったしのぶからは嘘の匂いはしない。そもそも匂いがよく分からないからだ。炭治郎はなんだか怖いなも思いながら、せっかくしのぶに会えたのだからと当初の目的どおり、任務復帰について相談することにした。
「あの……しのぶさん。お願いがあります」
「はい?なんでしょうか?」
「俺、そろそろ任務に復帰したいです!」
「うーん……無理ですねぇ」
「でも!機能回復訓練は順調です!というか、機能回復訓練に関してはもう全部、こなせています!」
柔軟はもちろん、アオイとの訓練も、カナヲとの訓練も終えている.伊之助に勝てないまでも動きに違和感はない。ただ何故か弱くなっているが、身体に変な澱みや不調はないのだ。だから任務をこなしつつ、勘を取り戻していけばと竈門炭治郎はしのぶに言い募った。しかししのぶはあまりいい顔はせず、困ったように「うーん」と首を傾げた。本当に困っているかどうかは匂いが分からないので判別つかないが。
「しのぶさん!お願いします!」
「そうは言割れてもですね、炭治郎君。まだ刀がないんですよ」
「あっ」
竈門炭治郎は力を入れていた拳がふわっと緩んだ。肩からも力が抜け、ヘナヘナと角度が下がる。忘れていた。そうだ。刀がまだだったと肝心なことを忘れていた自分が恥ずかしくなる。
「鋼鐵塚さん、怒ってるんでしょうか」
「大丈夫です。まあ、ゆっくり待ちましょう。炭治郎君はたくさんの強い鬼を倒してますから、ここらで一度じっくり休むのもいいものですよ?」
しのぶはポンっと竈門炭治郎の肩を叩くと羽織を翻して去っていった。炭治郎はそれに少し違和感を持つ。しのぶは来た道を戻ったが、ここに何しに来たのだろうか。向こうに用があったのではないのだろうかと、目を細める。
「……鋼鐵塚さん。本当に刀を打ってくれてるのかな?」
彼は刀を折られるのが許せないタチだ。もう炭治郎は既に二回も折っている。二回目では刀を打つのを放棄されたのかと思うほど放っておかれたのに。実際には俺ない刀を打てるよう、鍛えていたらしいが……今回もそうなのだろうか。
「……はあ。部屋に戻ろう」
竈門炭治郎は考えても仕方がない。分からないなら鋼鐵塚に向けて手紙を書こうと間借りしている部屋に戻った。伊之助のいない部屋は静かなものだ。竈門炭治郎は重い足取りで文机に腰掛け、なんと書けば鋼鐵塚にいい返事を貰えるかと考えて頭を掻く。鋼鐵塚は気難しいのだ。
「えーっと、筆、筆……あっ。筆がへたっているな。替えはあっただろうか……」
竈門炭治郎は毛先が減り、なんとも貧相な筆の様子にこれでは書けないと立ち上がる。書けないこともないが手紙の宛先は鋼鐵塚だ。誠心誠意を見せても、許さないと怨嗟を撒き散らす人だ。筆の状態も気にしよう。
「ええと、筆はっと……」
竈門炭治郎は戸棚の引き出しを開けた。そこは竈門炭治郎専用の引き出しで、細々としたものを入れている。あまり荷物は持っていないので、筆や墨の替えやあとは人から貰った物や手紙など、大事なものしか入っていない。竈門炭治郎は久しぶりにその引き出しを開け、そして固まった。
ぞわりと足元から尻、そして背筋が震え、カチンっと前歯まで合わさって鳴いた。竈門炭治郎はドッドッと己の心臓が大きく跳ねているのを感じる。なぜなら、自分しか使わない引き出しの中から、あり得ない人の匂いが漂ってくるからだ。
「……我妻君の匂いがする」
竈門炭治郎はそう言って、桃色と黄色の折り鶴を手に取った。スンッと嗅げば間違いない。我妻善逸の強く、優しい匂いがする。なぜ、彼の匂いがするものがこの引き出しの中にあるのか。炭治郎は引き出しを引き抜き、畳の上に中身を広げた。そして細々としているものの中から、我妻善逸の匂いがするものを選び、他のものと避ける。
折り鶴、折り紙のやっこさん、血汚れのついた手拭い。他にも細々と色々あるが、共通して我妻善逸の匂いがするものは覚えがない。誰からも貰った記憶がないものであった。竈門炭治郎はじっとそれを見つめ、そして今度は知らぬ匂いにざわりと心を震わせた。
いや、知らない匂いではないのだ。間接的に知っている。これは人を喰わぬ鬼の少女の匂いだ。それは緑の折り鶴や、緑色をした折り紙のやっこさんから香っている。顔を合わせたこともない鬼の少女の匂いがどうしてこれについているのか。そしてその匂いがついたものも、竈門炭治郎はいつ手に入れたのかわからない。
「……………俺は本当に刀を折ったのか?」
竈門炭治郎は額に手の甲を当てて思い出す。鬼の攻撃をくらい、しかし刀を折るまいと受け身を取った。よほどのことがない限り、大怪我しても刀は庇う。刀が折れたら鬼を倒すのがより難しくなる。駆け出しの頃はまだしも、今の自分がそんなヘマをするだろうか。
「…………いや、ない。俺は刀を折ってない。もし折っていたら、鋼鐵塚さんが発狂して俺を殺しに来るはずだ」
新しい刀はカラクリ人形の中から出てきたもので、それを鋼鐵塚が命を懸けて研ぎ直したものだ。そんな代物をあっという間に折ったとあらば、鋼鐵塚は目も当てられないくらい怒り狂うだろう。もしそうなったら、鋼鐵塚は移設された刀鍛冶の里で延々と脇をくすぐられている。死ぬ。拷問だ。
「……俺が対峙した鬼の血鬼術は『大事なものを奪う』ものだった」
竈門炭治郎はその事を思い出し、そして目の前にある折り鶴を手に取った。緑色と黄色。すんっと匂いを嗅げばつい最近まで知らなかった存在達の匂いがする。しかし、竈門炭治郎が前にこの引き出しを開けたのは三ヶ月前だ。筆の替えを買って、しまった時。それ以降は開けていない。なのに、これは何故あるのか。どうして記憶がないのか。
「……奪われたのか……?俺は……大事なものを……鬼に奪われたのか?」
竈門炭治郎はわなわなと震えた。そして折り鶴を持ったまま立ち上がると駆け出した。屋敷の中を走るのは良くない事だが、今は大目にみてほしい。すぐに屋敷の外に出るし、そして何より心が苦しくて仕方がないのだ。
伊之助がいつもより何か不機嫌なのも、村田が頻繁に見舞いにくるのも、しのぶがまるで自分を監視するように立ち回るのも、全ては己がおかしくなっていたからだ。
生垣と塀に囲まれた道を抜け、人混みを縫って走り、畦道を駆ける。思い返せば色々な不自然さに行き当たった。どうして疑問に思わなかったのだと竈門炭治郎は奥歯を噛む。あの日、あの時、初めて我妻を見かけた時。彼の目は今にも泣きそうだったと竈門炭治郎は歯を食いしばって走った。
大事なものを忘れてしまった。なくしたくない、かけがえのないものを奪われてしまった。情けない。己の根幹たるものを失うなんて。これでは伊之助に勝てるはずがない。しのぶに認めてもらえる筈がない。
(けど俺は……!気がついたぞ……!!)
炭治郎は畦道を駆け抜けて、つい最近まで通っていた場所へとたどり着いた。塀の向こうから慌てたような匂いがしてくる。突然の来訪に警戒しているのだろう。それもその筈だ。彼は決して大切な子を傷つけたくないのだ。その子を傷つけるかもしれない、馬鹿な男を警戒しているのだろう。一つも嫌な思いをその子にさせたくないのだろう。自分がいくら傷つこうとも。
(好きだ!!好きだ!!好きだ善逸!!)
竈門炭治郎は確信した。記憶はないが、状況が全てを語っている。己と我妻善逸は通じ合っていた。お互いを信頼しあっていた。親友だったのだ。自分の大切なものを預けられるくらい、それを守るために自分の心が傷んでもいいくらい、お互いの中に情があった。
竈門炭治郎は我妻善逸を好きなのだ。きっと特別に。何よりも幸せにしたい、守りたい子と同じくらい、特別に好きだった。どちらも大切過ぎて、だから揃って失った。奪われたのだと竈門炭治郎は拳を握る。
ああ、ほら。愛しい人が見えてきた。驚いた顔で、門から出てきて……けど、門は閉める。もしかしたら今日は目を覚ましているのかもしれない。困惑したように、どうしようとオロオロしている様に、竈門炭治郎はじんわり胸が暖かくなり、そして痛くなる。愛しい人を自分が困らせ、傷つけているのだ。
「……善逸っ!!」
「炭治郎……?いや、ていうか何しに……」
竈門炭治郎は飛びかかるように我妻善逸を抱きしめた。その途端にじっくりときたような感覚に襲われる。その状態にやはり自分達はこうであったのだとお互いの関係性を確信した。善逸はびっくりした匂いをさせ、蜂蜜色の瞳を大きく丸くさせる。その様が可愛らしく、愛しく、堪らなくて……竈門炭治郎はちゅうとその唇を吸った。
「えっ」
「ごめん。善逸……俺はどうやら鬼の血鬼術にかかっているらしい」
「えっ……?また掛かったの?」
「善逸に関する記憶を……奪われた」
「あ、その話……?え、なんでいま口吸った……?」
「でも安心してくれ!!俺は必ず記憶を取り戻す!君達の存在を取り戻す!!だからそれまでこれを預かっていてほしい!!」
「は……?えぇ……?」
竈門炭治郎は善逸から一歩離れると持ってきた折り鶴を渡した。善逸は渡された折り鶴を見て、竈門炭治郎を見て、目を白黒させている。それはそうだろう。突然やって来てこんなことを言われたら混乱するはずだ。しかし今はそれでいいと竈門炭治郎は思っている。
これから例の鬼を倒し、自分は全てを取り戻す。善逸の元に来たのは決意表明のようなものだ。必ず大事なものを取り戻してくると愛しい人に宣言しただけだ。
「……二人とも、俺を待っていてくれ……!!」
「……う、うん……?」
パチパチと瞬く善逸があまりにも可愛らしくて、胸がいっぱいになり、竈門炭治郎はせめてもう一度と顔を素早くよせて唇を奪った。善逸は相変わらずポカンとしている。竈門炭治郎はそんな善逸に目を細めると堪らず言葉を零した。
「好きだよ善逸。だから……俺を信じて待っていてくれ!!」
竈門炭治郎は善逸の金糸を撫で、頰も撫でると名残惜しが一歩、二歩と離れる。そして何かを言われる前に踵を返して走り出した。背後から「炭治郎っ!!」と呼び止める声がしたが振り切った。
行かねばねならない。鬼を倒し、取り戻させねばならない。大事なものを失い、己の覚悟は弱くなったかもしれない。しかし彼らの存在が今の自分を強くすると竈門炭治郎は確信していた。
****
「帰れ」
「帰りません」
このやり取りを見せられて、何回目になっただろうか。最初はどきりとした伊之助であったが、実はもう、すでに飽きている。しかしここは鬼が潜んでいると言われている山の麓だ。気を抜いてはいけない。
「……早く終わんねぇかな……」
伊之助は飽きている身空で、しかし触覚だけは鋭敏にはせていた。なぜなら自分達はその鬼に見つかる前に探し出さねばならない。理由は簡単だ。自分たちが見つけるよりも早く、鬼に見つかってしまうと雲隠れというように逃げられるからだ。伊之助は何度もその煮湯を飲まされている。
「……帰れ」
「いえ!帰りません!!」
伊之助は睨み合う二人を横目に見た。半々羽織を着た無表情の冨岡義勇と、鬼気迫る勢いの竈門炭治郎。二人は先ほどからじっと睨み合い、「帰れ」「帰りません」という言い合いを続けている。それは合同任務の為に合流した伊之助と冨岡がさて、山に入るかとなった時に炭治郎が現れたからだ。彼は隊服に羽織を着て、腰には日輪刀という出立ちであった。多少の違和感は背中に箱がないからだろう。
けれど、それでも、気配は以前の彼に近かった。大事なものの為に戦う覚悟を持った人間。敵討ちなんて悲壮な意地の為に戦うものとは違う、生に溢れた気配であった。
恐らく、何かがあったのだろう。彼に変貌が。もしかしなくとも、奪われたことを自覚したのかもしれない。そうでなければ蝶屋敷の納戸に巧妙に隠されていた筈の日輪刀を持ってはいまい。そして彼の大事なものを奪った鬼の討伐にここのところ心血を注いでいる冨岡と伊之助の合同任務に無理やりついて来ようとはするまい。
そう。この山にいるとされているのは竈門炭治郎の記憶を奪い、彼の根幹を変えた『大事なものを奪う鬼』だ。伊之助は炭治郎がおかしくなってから、ずっとその鬼を探してきた。善逸と共に任務につければ、触覚と耳で追い詰めるのが可能だったかもしれないし、善逸もその鬼の討伐をしたがっていたが……善逸に関しては柱の意見により、秘密裏にその鬼から遠ざけられている。理由は簡単だ。もし、善逸までも鬼の血鬼術にかかってしまえば、誰が禰豆子の面倒をみるのかという話らしい。
その事をしのぶに説明された時、伊之助はなぜだと立ち上がった。なぜなら善逸は、炭治郎に忘れられてしまっているのだ。本人は時文が忘れられたことにはさほど衝撃はなかったようだが、炭治郎が禰󠄀豆子を忘れさせられた事には恐ろしい程の怒りを覚えていた。
伊之助はわざわざ、冨岡の屋敷まで二人に会いに行ったのだ。その時の禰󠄀豆子は眠っていたけれど、善逸は起きていた。鬼と戦う時の眠りに落ちた状態ではなく、目を開けて、ここにはいない、件の鬼をひたと見据えるかのように遠くを見ながら言ったのだ。
「……絶対に見つけ出して首を斬ろう」
その言葉は伊之助もそうしろ、そうするに決まっているだろうという投げかけでもあった。もちろん、伊之助もそうするつもりだった。竈門炭治郎から妹の存在を取り上げるなど、到底許せることではない。伊之助と善逸は同じ気持ちであった。しかし、ピッタリと重なるほどは同じではなかっただろう。何しろ伊之助は炭治郎に忘れられてはいなかったし、また、禰󠄀豆子に関する記憶を失ったと聞いた時にも禰󠄀豆子を炭治郎と会わせないようにしなければとは思いつきもしなかったからだ。
しかし目の前の男は迷わずその道を取ったらしい。禰󠄀豆子が兄に忘れられてしまったことに悲しまないようにと、しのぶから説明を受けてすぐに禰󠄀豆子を連れて蝶屋敷を飛び出したらしい。その時の善逸はどんな気持ちだったのだろうか。どんな覚悟だったのだろうか。
伊之助は知っている。炭治郎と禰󠄀豆子は決して離れ離れにはならないとお互いに決めていたし、それを一歩下がって嬉しそうに見ていた善逸を知っている。それなのに迷わず二人を引き離した善逸はどんな想いで駆け出したのだろうか。
(なんか……もやっとすんなぁ)
伊之助は沈みそうになった心に負けないと、ぐっと拳を握る。なんとなく、伊之助は蚊帳の外の気分なのだ。炭治郎が『大事なものを奪う』という血鬼術にかかり、禰󠄀豆子と善逸のことを忘れていて、自分に関しては覚えていたということは、自分と二人の間には差があるということではないか。
忘れられている二人の手前、ずるいなんて言えはしない。しかし『大事なもの』とそれ以外と線引きをされた気分だ。自分達は仲間なのに。他の鬼殺隊員も仲間に括られるのは分かっているが、それでもその中でも特別な仲間だと伊之助は思っていたのに、炭治郎は少し違ったらしい。
きっと本人に面と向かって言えば「そんなことはないよ。禰󠄀豆子も、善逸も、伊之助もすごく大事だ」と朗らかに言っただろうし、伊之助も疑わなかった。しかし現実は違う。鬼の血鬼術は全てを詳らかにした。
炭治郎は無意識のうちに禰󠄀豆子と善逸、そして伊之助の間に線引きをしていたらしい。伊之助はその事にショックを受けながらも、善逸が迷わず禰󠄀豆子を連れて蝶屋敷を飛び出したと聞いた時、納得してしまった。
善逸はいつだって禰󠄀豆子を守る為に走る。禰󠄀豆子を守ること、それはひいては竈門炭治郎を守ることに繋がる。禰󠄀豆子が幸せであることが、竈門炭治郎の生き甲斐であり、宿願だ。善逸はそれをずっとずっと手助けしてやっている。
伊之助は善逸に謝ったことはないし、自分が悪かったとも思っていないが、最初に炭治郎と善逸と禰󠄀豆子に会った時、禰󠄀豆子を殺そうとした事だけは浴衣の布地がひきつったような気持ち悪さを心の中に残していた。
鬼殺隊士としてそこに鬼の気配があるなら、殺すのが真っ当だ。しかしあの場に善逸がいなければ、伊之助は禰󠄀豆子と共に炭治郎の心も殺していた。そして自分は未来の特別な仲間を二人も殺したことなんて気が付きもせず、さっさとその場を後にして炭治郎とも顔を合わせなかっただろう。そして那田蜘蛛山で死ぬのだ。
鬼殺隊士の命はいつだって紙一重、巡り合わせの中にいる。運の要素も大きい。己の実力と機転だけではどうにもならない時は確かにあるのだ。伊之助はなんども窮地を仲間に助けられたし、そして伊之助も何度も仲間を救った。自分達は努力と気合と覚悟で、運を手繰り寄せている。伊之助は自分の人生を振り返ってみて思うのは、運が良かった時はいつだって誰かと関わった時だと知っている。
育ての親たる猪の母に拾われた時。
伊之助に人としての知識を多少なりとも教えてくれた爺さん。
鬼殺隊のことを教えてくれ、刀を手放してくれた鬼殺隊士。
そして——。
(炭治郎、善逸、禰󠄀豆子)
三人に出会えたからこそ、今の伊之助がある。伊之助は三人に対して照れ臭くて口に出せない感謝があった。本当なら、言葉にした方が喜ぶのだろうけど、うまく言葉にできないし、柄でもないと伊之助は思っている。そして言わなくても三人なら分かってくれているのも知っているのだ。
(……差があってもいいだろ。俺がこいつらを助けたいんだ)
明確に線が引かれたからと言ってなんなのだ。善逸は一度だって炭治郎の命より大切なものを否定したことはない。それがどれだけ、炭治郎の中で救いとなったか、三人を大事に思っている今の伊之助ならばよく理解できる。善逸と、自分では多少の立場が違うのだ。
伊之助は少し寒いなと思いながら鼻を啜った。猪頭があるから顔は暖かいが、上半身は裸なので冬の夜風は冷たい。天に昇った金の月に、遠ざけられているとも知らずに今も足掻いている親友を思い出して伊之助は息を吐いた。早く、早く取り戻してやらねばならない。勝手なことだが、それをかつての贖罪にさせてほしいと伊之助は胸を張った。しかし——。
「……帰れ」
「いやです!帰りませんっ!!」
目の前ではまだ冨岡と炭治郎の攻防が続いている。帰れ、帰りません。そればかりの言い合いに何の意味があるのかと、伊之助はげんなりした。ちなみに炭治郎に関しては「お願いします!」「俺も行かせてください!」「絶対についていきます!」と多少の違いはある。しかし冨岡に関しては「帰れ」の一言だけだ。説得したいならもう少し、違いを出してみればいいのにと伊之助でさえ思う。
実は冨岡は「(今のお前では実力が不足している)帰れ」であったり「(ここは俺と嘴平でなんとかする)帰れ」であったりと、心の中ではいろいろも話をしてはいた。しかし表出はしていないので、全く周りに伝わってはいなかったけれど。伊之助はぐだぐだしたくないと腕を組むと、炭治郎に問いかけた。
「おい。お前がここに来たこと、しのぶは知ってるのかよ」
伊之助の言葉に炭治郎と冨岡が顔だけで振り返った。炭治郎はぐっと眉毛を寄せると神妙に頷く。
「ああ。しのぶさんには許可を貰って来ている」
炭治郎の言葉に冨岡がハッとした顔をした。この冨岡が何を言いたいかは流石の伊之助でも分かった。「許可取ってあるなら最初に言え」である。しかし伊之助はそれは無視して、炭治郎をじっと見つめて言った。
「今のお前、前より弱いぞ。足手纏いになる」
「ならない」
間髪入れずに返ってきた言葉に、伊之助はおやっと思った。炭治郎は冨岡に向けていた身体を伊之助の方に向けると、ギリっと音がするほどに両の拳を握り締めた。
「確かに今の俺は弱くなったかもしれない。以前の俺とは何か覚悟が違うかもしれない。けど、気がついたんだ。大事なものを奪われたって。そうしたら、心の中にぽっかり穴があいているのにも気がついた。……俺は……これを埋めたい。大事なものを……二人の記憶を取り戻したい……っ!!」
「………っ!!」
伊之助はビリビリと伝わってきた気迫に、以前の炭治郎を垣間見た。やはり炭治郎は失った事実を知ったのだと伊之助は気がついた。そして、ここ最近の炭治郎が記憶をなくしているのに善逸に会いに行っていることを思い出して……なるほどと頷く。忘れても、特別になるのは変わりはないのだ。炭治郎は善逸に再び出会い、そして気がついたのだろう。善逸と禰󠄀豆子を失っていることに。
「……胡蝶が許可しているなら、俺は構わない」
「義勇さん……!!」
「お前は、探し出すのに全力を注げ。……鬼は俺が斬る」
冨岡はすんなりと炭治郎の任務同行を認め、さっさと山の方へと向かっていく。この場の責任者である冨岡が認めたなら、もうここに留まる必要は何もない。伊之助も炭治郎も冨岡の後に続くように歩き出した。
「……俺が斬る……か」
「俺とお前が見つけて、半々羽織が斬るのが一番確実だろ。この鬼を逃すんわけにはいかねぇんだ」
「……そうだよな」
炭治郎は悔しいというような顔で唇を噛んでいる。分からなくもない。大事な人の記憶を奪うなんて、人の心を土足で踏みにじるような行為だ。しかも奪うだけ奪って逃げて喰おうともしない。愉快犯など悪鬼にも程がある。けれどここはやはり、確実に鬼を倒したい。この鬼がのうのうと生き延び続けたのは、柱とは邂逅しなかったからだ。上位の階級である自分と炭治郎、そして柱の冨岡の三人であれば、鬼を逃す事なく確実に仕留められるだろう。伊之助はそう思って、善逸の悪夢の日々は今日で終わりだと炭治郎に発破かけた。
「テメェの手で首を斬りたいのは分かるが、善逸のことも考えてやれっ!今のお前にはそこまでの実感がないかもしれねぇけどな!あいつは本来泣き虫野郎なんだよ!それが泣もしねぇで踏ん張ってんのは、お前らを守るためだからな!!」
お前らと言って、炭治郎が自分と禰豆子のことだと思うかは分からなかったが、伊之助は善逸が何のために頑張っているかを正確に教えてやりたかったのだ。しかし禰󠄀豆子を忘れている炭治郎に、禰󠄀豆子の存在を直接伝えていいかが分からず、曖昧な言い回しになる。
「……うん。分かってるよ」
(……ん?)
伊之助は突如、ホワホワした空気が横から漂ってきたのにゾワリとして振り返った。すると炭治郎はほんのりと頰を染めて、今まで見たことない顔で歩いている。その横顔に、伊之助はなんと言えばいいのか分からない。これはどういう表情なのか。それなりに炭治郎の色んな表情を見てきたつもりであったが、知らないものであった。
「本当に不甲斐ない。大切な筈の妹と……恋人の記憶を失ってしまうなんて……。善逸には負担をかけてしまった」
「えっ」
伊之助はびっくりして固まった。禰󠄀豆子のことをちゃんと妹として認識していて良かったと思ったが、それよりもなによりも、今、善逸のことを何と表現しただろうか。
「妹は善逸が守ってくれているけど……善逸は泣かせてしまったかな」
ぐうっと苦しそうに胸を押さえる炭治郎のその横顔に、伊之助はなんとか声を絞り出して応える。
「ソンナコトナイトオモウヨ。ナイテナカッタヨ」
「……そうか」
炭治郎は切なげに微笑んだ。その笑みを受けて、伊之助は衝撃を覚える。炭治郎と善逸は、仲間というだけではなく、恋人という関係であったのかと衝撃を受けた。人間は雄同士では恋人にならないと思っていたが、やはり生き物。例外はあるのだろう。
「……知らなかった……」
「ん?」
「お前らそうだったのか……」
伊之助の呆然とした言葉に炭治郎はカアッと赤くなる。関係を隠されていたことに悔しさがでたが、雄同士という例外の関係だ。簡単には口にはできなかったのかもしれない。しかし、なるほど。
「線引きはそこか」
伊之助はまるで霧が晴れたような心地になった。禰󠄀豆子は妹、善逸は恋人。そりゃあ、忘れられても仕方がない。善逸は仲間という関係に加えて、もう一つの顔があったわけだ。伊之助は晴々とした気持ちで、猪頭に隠れて笑う。守ってやらねばならない。この大切な仲間であり、子分たちである三人を。また元の姿に戻してやらねば。
「よっしゃー!!親分である俺様に任せとけ!!」
「うわっ!いきなりどうしたんだ伊之助!」
「うるせぇ!行くぞ健太郎!!グワハハハハハ!!」
伊之助は日輪刀を両手に持つと、前を行く冨岡を追い越す為に走り出す。索敵は自分と炭治郎の役目だ。何が何でも鬼を見つけ出し、今夜で決着をつけてやると、不敵に笑った。
****
人間の一番大切な記憶を失うということは、その者の独自性の損失に繋がる。しのぶは血鬼術にかかり、『いちばん大切なもの』を奪われた過去の犠牲者の変容につい書かれた資料を読み、その恐ろしさに眉を顰めた。
しかし鬼殺隊士においては、どうにもできなかった己を縛る恨みから解き放たれたともとれる。強制的に奪われることで、腑が千切れて煮えそうな怒りと恨みから逃れることができる。刀を持ち、自分の身などどうでもいいから一匹でも鬼を倒すという気概のみで生きなくて済むのだ。そんなことをしのぶは一瞬だけ考えたことがある。
けれど鬼殺隊にいるものは大半が鬼に大切な人を殺された恨みを持つ者だ。大切な人の命まで奪い、大切な人の記憶まで奪うなど業腹だ。看過できない。人をどれだけ踏みにじればいいのかと怒りが沸く。
そうしてしのぶはこの鬼をなんとしても見つけて倒さねばならないと固く決意した。それは姉を喪った己が、姉の記憶さえも奪われたくはないと、姉を二度も死なせはしないと強く思ったからである。だからこそしのぶはずっとその鬼を探してきた。探して探して、ついにある場所にその鬼が潜んでいるのではと見当をつけた時、一人の少年隊士に任務を言い渡したのだ。
偶然ではなかった。意図的であった。彼は非常に鼻が利き、鬼の匂いを嗅ぎ分けられ、一度で匂いも覚えられる。鬼が逃げた際の追跡にはもってこいであった。そして彼は大変強い。もしかしなくとも、鬼の首が切れず、毒で殺す己よりも剣術は既に多いに勝っているかもしれないとしのぶは考えいた程だ。だから彼に任務を言い渡した。もちろん、相手の鬼の特性は事前に伝えていた。だが結局、戻ってきた彼は傷だらけ。目を覚ましてみれば、鬼の血鬼術で彼が一等大事にしていたものを失っていた。
柱に囲まれ、斬首せよとの声が上がる中、己の命がなくなることを一度も恐れることなく、ただただ、妹の安否だけを恐れる。鬼になっても兄を想い、決して人を傷つけない少女。その少女を何としても人に戻すと、恨みに支配されない刃を振るう少年の姿は、恨みばかりで姉の気持ちなぞ何も考えずに毒で体を満たすしのぶにはあまりに眩しいものだった。
この兄妹が、幸せになりますように。
しのぶはそう願っている。彼らの幸せを願い、そしてそれが叶えば、少しでも彼らに関わり力になれた筈の自分に上等さを感じられる気がしたのだ。恨みばかりで表面ばかりを取り繕う自分の人生に多少なりとも素晴らしいことをした彩りが添えられるとそう思っていたのだ。
なのに、少年は大切な妹の記憶を失ってしまった。それはあまりにも彼の根幹で、彼は何があっても妹を守ると誓っていたのにとしのぶの心は人知れず傷ついた。任務を言い渡したのは己で、しかし人選について判断を誤ったつもりはない。適任者は他にはいなかった。いや、己が行けばよかったのか。分からない。他の任務が己にも降っていた。
大事なものを失った隊士、竈門炭治郎はその有り様を大きく変えた。妹を人間にするまでは何が何でも勝ちに行く覚悟があったのに、境遇が『鬼に殺された家族の仇を取る』に変容してしまい、刃に重みがなくなった。判断も己で勝ちに行くものから、誰かに繋ぐ時間稼ぎのようなものに変わったのか動きに精彩はなかった。
しのぶは彼に目を掛けていたのでよく知っているのだ。今の竈門炭治郎は階級を二つや三つ落とした程に弱くなっている。これではダメだと顔には出さずとも恐ろしくなった。妹が兄に置いていかれてしまうと恐ろしくなり、しのぶは竈門炭治郎の刀を隠すことにした。
彼が何も気づかぬうちは、そっと任務から遠ざける。強い隊士を任務に出さないのは良くないが、彼はあまりに鬼舞辻無惨に目をつけられ過ぎている。いま強い鬼を差し向けられれば簡単に死んでしまうだろう。しかしどれだけ誤魔化せるかは分からない。
彼に記憶が奪われたことを伝えるのは……あまりにも不憫だった。任務にも出ることがないなら、知る必要はないのではないか。任務の免除は春までと決めている。それまでに鬼を倒せれば、彼は記憶を取り戻すかもしれない。そんな期待と、任務がこない違和感にいつ気づかれるかという思いのせめぎ合いをしのぶは抱えていた。そして——。
「しのぶさん、いまいいですか?」
入室の許可を取って部屋に入ってきた竈門炭治郎は、久しく見ていなかった隊服姿に羽織を着込み、腰には日輪刀を下げていた。それだけで分かる。自分の日輪刀は折れておらず、隠されていたのを知ったのだろう。顔つきは随分と勇ましく、以前の竈門炭治郎に近い。しかしどういった気持ちで今ここにいるのかは、本人に聞かねば反別はつかない。
「なんでしょう?」
日輪刀を隠していたことに関しては聞かれない限りは話すつもりはない。本人がまだ記憶を失っていることに気がついておらず、刀だけを見つけたならば誤魔化しようはある。しのぶは竈門炭治郎に目を掛けている。それと同じように彼の同期であり、親友の少年達にも目を掛けているのだ。
竈門炭治郎が血鬼術に掛かり、大事なものの記憶を失ったかもしれないと説明した時、彼の親友である金の髪の少年は迷わずに竈門炭治郎の妹を連れて出て行った。記憶を失った兄と、兄に忘れられた妹を対面させるわけにはいかないと、しのぶが考え付きもしなかったことを実行した。しのぶは忘れてしまった竈門炭治郎に、鬼の妹の存在をどう説明したら良いかばかりを考えていたのに。
しのぶが竈門炭治郎の任務を免除することにしたのは、彼の親友、我妻善逸の行動を見たからだ。自分もなにか、この兄妹にしてやりたくなった。だから竈門炭治郎が記憶を奪われたことを未だ気がついていないのならば、何としても騙しきるとしのぶは微笑む。ここで自分がバラしてしまえば、我妻善逸の努力は水の泡だ。
そう思ってしのぶがいつも通りの笑みで竈門炭治郎を見やれば、彼は開口一番に言った。
「俺、分かりました。善逸の背負っている箱……あそこに居るのは俺の妹ですね」
「…………」
参ったなとしのぶは思った。どうやら勘づかれたらしい。説明せよと求められると、傷つくものが出てしまう。しかし竈門炭治郎は説明を聞く権利がある。どう答えるべきかとしのぶが少し眉を動かせば、竈門炭治郎はビシッと手のひらを見せて返事を止めてきた。
「すみません。しのぶさんに確認したいわけじゃないんです。俺は確信してるので。……考えてみれば、変なところが多いんです。どう考えても俺一人では切り抜けられなかった場面があるのに、誰も死なせずに済んでいたり、記憶に違和感がある。……俺はあの日、血鬼術を受けたんですね」
悲しそうな顔をする竈門炭治郎に、しのぶはゆっくり頷いた。そこまではっきりと失ったと気がついているなら、血鬼術を受けたことを否定しても意味がない。しのぶは二ヶ月近く詰めていた何かを息とともに吐きだした。
「しのぶさん。俺、鬼を探してきます」
「……鬼をですか」
「はい。探して、倒して、大切な二人を取り戻します!!」
強い炎が宿った目だ。しかしそれは恨みが燃やすものではない。濁りのない瞳に、しのぶはやれやれといった心地になった。もう彼をどうやっても止められないだろう。竈門炭治郎が頑固で、こうと決めたら引かないことは散々見てきて知っているのだから。だからしのぶは口元をぐっと上に引き上げるとパンっと手のひらを叩いて笑った。
「それはちょうど良かったです!実は冨岡さんと伊之助くんが例の鬼が潜んでいるらしい場所に向かっている最中なんです!」
「それは本当ですか!?」
「はい。結構確かな情報ですよ。今からなら追いつけるかもしれません。場所は私の鎹鴉に伝えておきますので、ひとまず炭治郎君は伊之助君の後を追いかけてみてください」
竈門炭治郎が本気ならば、匂いを辿るくらい造作もないだろう。しのぶはそう思ってひらりと手を振った。その途端に竈門炭治郎は部屋を飛び出していく。実にしなやかな脚のバネで、しのぶは誰もいなくなった場所に、行ってらっしゃいと呟いたのであった。
「というわけで、炭治郎君は自分の記憶を奪った鬼を倒しに行きました!」
「いやいやいやっ!!もうちょっと止めてくださいよ!!」
「そんな、炭治郎君がやる気になったら止めても無駄じゃないですが。絶対に押し問答になるだけです。私、無駄なことはしない主義なんですよ」
そう言ってしのぶはにっこりと笑う。目の前にいる金の髪をした少年……我妻善逸は「でもぉ!」なんて言って半泣きだ。本人も止めても無駄なことは分かっているだろうにと、しのぶは椅子に座りながらニコニコと善逸を見上げた。
竈門炭治郎が出て行き、程なくしてからこの少年はやってきた。「しのぶさん居ますか!?」なんて執務室に駆け込んできて、しのぶが居ることを確認した途端に「ちょっと禰󠄀豆子ちゃんを預けてくるので、そのまま待っててくださいね!?お願いしますよ!?」と言って出て行った。それだけで分かる。禰󠄀豆子に聞かせたくない話、つまりは竈門炭治郎について何か話があるのだろうとしのぶは見当をつけたし、実際に戻ってきた善逸の話を聞いて、予想が当たっていたことを知る。どうやら竈門炭治郎はしのぶの所に来るより前に、善逸に会いに行ったらしい。
善逸が話すことによると、「炭治郎のやつ、突然に冨岡さんの屋敷に来て、鬼に記憶を奪われたーとか、必ず記憶を取り戻すーとか言って……どうして気がついたのかはいまいち分からないんですけど、あいつ今はすごく弱くなってるのに!自分を大怪我させた鬼に挑むとか無謀が過ぎます!!」なんて話すので、竈門炭治郎がしのぶに会いに来た辺りの話をかいつまんで説明してやった。
すると思った通りに善逸は発狂したように相貌を崩して頭を抱えている。しのぶは大慌てする善逸に「まあまあ、落ち着いてください」と声を掛けた。
「今回は炭治郎君だけではなく、伊之助君と冨岡さんも一緒です!そもそもお二人にお任せしていた所に炭治郎君が行くだけですから!大丈夫ですよ、今度こそ心配いりません!」
しのぶは善逸を励ますように握り拳を緩く作って見せた。善逸はべそべそと泣き顔を晒しながらも、しのぶの言葉にコクンと頷く。彼だって分かっているだろう。その布陣でダメならば、とんでもない相手だということに。しかしあの鬼は上弦には及ばない。下弦の鬼には匹敵するかもしれないが、冨岡と嘴平と竈門炭治郎がいれば大丈夫だ。一人が血鬼術にやられても、必ず残り二人が留めを刺す。
「まあまあ、大船に乗った気持ちで待ちましょう」
「……はい」
善逸はズズッと鼻を啜ると息を大きく吐いて背筋を伸ばした。そしてもじもじと手を揉み合せてしのぶを見てくる。
「あの……しのぶさん」
「はい?」
「……前に借りていた部屋、また戻ってもいいですか?」
善逸が言う借りていた部屋とは、竈門炭治郎と伊之助と共に使っていた部屋だろう。禰󠄀豆子を連れて逃げ出した時に竈門炭治郎に善逸の存在に気がつかれないように荷物を納戸に移動させ、いまは二人部屋となっている。そこにまた戻りたいも善逸は言っているのだ。
「ええ、もちろんいいですよ。善逸君の荷物は納戸に入れてあります」
「……ありがとうございます」
ペコリと頭を下げた善逸に、しのぶはそっと問いかけた。
「でも善逸君。鬼を倒してもすぐに記憶が戻るかは分かりませんよ?」
竈門炭治郎と禰󠄀豆子を引き合わせて良いのかと心配になって可能性を示唆すると、善逸はこてんと不思議そうに首を傾げた。
「そうかもしれませんけど……でも、炭治郎が二人で待っててくれって言ってたので」
善逸はそれだけ言って、頭を下げると執務室を出て行った。しのぶは善逸の猫背気味の背中見送り、ふむっと頷く。あれだけ二人を引き合わせないようにしていたのに、いったい何があったのか。
「……そういえば、善逸君も忘れられてるんですよねぇ。どうしてなんでしょうか?」
しのぶは分からないなと首を傾げたが、我妻善逸が竈門炭治郎にとってかえがたい存在であることには何も疑問には思わなかった。
****
じわっと香り立つ緑と、腐葉土の匂い。山の空気には人工物が混ざっておらず息がしやすい。鼻から大きく息を吸い、いつ何が起きてもいいように、全身に呼吸を巡らせる。血管の一つ一つ、手足の筋肉どころではなく、全ての筋肉の繊維まで意識し、月の光が朧げにしか届かない深い森の闇の中を駆けゆく。
(世界が違う)
竈門炭治郎はヒュゥゥゥゥと息を吐きながら己の視界から見えるものの精細さに驚嘆していた。昨日までとはまるで違う自分。呼吸の巡りも、手足を動かす速さも、滑らかさも違う。そして何よりも心の燃え上がりが違うのだ。
(煉獄さん……!)
鬼殺隊士としての使命、生き様、そして死に様すらを己に刻みつけていったあの夜明け。思い起こせばいつだって鮮やかに、あのどす黒い血を思い出す。しかし死ぬ間際ですら輝く瞳はいつだって刀握る時に蘇った。
(心を燃やせ。……そのことすら、俺は薄れていた….!!)
ゾッとすることだ。竈門炭治郎は多くのものを失い、その辛さに負けじと歩いてきた。自分の進んできた道を振り返れば忘れたくない人達が大勢いる。けれど、それは昨日まではうすらぼんやりとしていた。理由は簡単だ。竈門炭治郎が歩んできた鬼殺隊士としての道の傍には、いつだって大切な人がいたからだ。
(善逸は、もう、俺の人生になくてはならない人なんだ)
竈門炭治郎の中に我妻善逸の記憶はない。どう掘り返しても彼の存在はなく、いつかの散歩で町にて見かけたのが最初の記憶だ。けれどおかしい。考えれば考えるほど、誰かが抜け落ちたような感覚がある。無限列車で、煉獄一人が客車を守っていたか?いや、そんな筈はない。煉獄は五両だった。ではあと三両は誰が守っていたのだ。そもそも、煉獄と伊之助はどうやって目覚めた。
(大事な人を忘れたから、俺の全てが曖昧になっていく。ただしく覚えていたいものが、蹂躙されている……!)
鼓屋敷でもそうだ。あの時、竈門炭治郎は照子と一緒であったが、そうなれば正一はどうした。伊之助はあの時初めて会ったが、屋敷に踏み込んでからだった。あの時の伊之助は誰も連れていない。しかし竈門炭治郎は正一の安否をそこまで心配していなかった。必ず大丈夫だと、確信していたのだ。強い人が一緒にいるからと楽観的であった。
(……きっと、それが善逸だ)
強く意識して思い出せば、ぽっかり不自然と何かの存在が白く塗りつぶされたように見えてくる。伊之助と殴り合ったのはなぜだ。例え伊之助にかかって来られても、隊律違反になるから自分が積極的にやり合うだろうか。
「……っ!義勇さん!八時の方向から鬼の匂いがします!!」
竈門炭治郎はごく弱い風の中で、じわりと漂ってきた匂いに目を細める。知った鬼の匂いだ。鬼の知り合いなどほぼいない。生きていて、匂い
を知っている鬼なんて鬼舞辻無惨と上弦の参を除けば……件の鬼だけだ。
竈門炭治郎の言葉に冨岡が八時の方向へと向かう。そして右手を少し上げると指の形を一つ、二つと変えた。それを見て、竈門炭治郎と伊之助は別方向から回り込むように進路を変える。鬼を囲い込むという合図だ。
(……命より、大切なもの)
竈門炭治郎は鬼の匂いが近くなってくるのを感じながら、じっと考える。とても、とても大切なことを忘れている。無くしたことに気がつけば、心の真ん中にぽっかりと空いた空虚さがあるのだ。ここに居座っていたものはなんだろうか。鬼なんて生き物に恐れず立ち向かう為に、ここにあった筈なのにと竈門炭治郎は心臓の鼓動を聞く。
(俺は、命より大切なものがあるから……柱合会議に呼ばれたんだ)
あの時は散々であった。嫌というというほど、鬼殺隊士は鬼を憎み、殺さねばならないと思っていることを肌で理解した時だった。背中に食い込む伊黒の肘の鋭さや、不死川に打ちつけた頭突きの鈍い音。そして何よりも、鱗滝と冨岡に己は命を懸けさせた。だが、それら全てはなぜ起こったのか分からない。疑問にも思いもしなかったが、よくよく考えればおかしい。
(何をしたら自分は、煉獄さんや宇髄さんに斬首しようと言われるんだ!言う筈がないだろう!!あのお二人が!!)
自分の中の大切な人達の記憶が歪められている。鬼の血鬼術は『大事なものを奪う』だ。それは記憶を奪う形で叶えられ、奪われたことが分からぬように己の中で記憶のあちこちがぼんやりとしてしまう。竈門炭治郎は自分の記憶があまりにもあちこちが朧げであるのに、二人の存在がとても大切なんだと逆説的に感じ取った。
鬼殺隊になる前、もう物心ついた時からの記憶がおかしい。これは間違いなく、善逸が連れている人を喰わぬ鬼とやらが自分の妹であることの証拠だ。そしてそれだけでは埋まらない、陽が登った中の世界にある記憶の歪みは、我妻善逸を忘れてしまった故に引き起こされているのだろう。
(俺と善逸はずっと一緒だった)
名前すら分からない、実感のない妹もずっと一緒だった筈だ。離れたくないと隣にいてくれた人達が失われた。奪い取られた。許せない。必ず、必ず取り戻さねばならない。
(……俺は……二人の名前を呼びたい!)
竈門炭治郎は鬼狩りの気配を察知したのか、洞穴から飛び出してきた鬼の匂いを感じて、刀に手をかける。そして呼吸を強く巡らせると、足回りの筋肉を固めて、一気に駆け抜けた。
「ヒノカミカグラ!円舞一閃!!」
竈門炭治郎は鬼の首を斬ったと思った瞬間、不穏な匂いが揺めき、反射的に避けた。鬼の斬撃が地面を抉っており、炭治郎はチッと舌打ちをする。またこれだ。この鬼の厄介な点だ。
「伊之助ぇ!!この鬼は記憶を操る鬼だ!!見た記憶すら瞬間的に変化させて誤認させてくる!!首を斬ったと思っても油断するな!!幻覚の可能性があるっ!!」
竈門炭治郎はそう叫び声を上げた。冨岡の名前は呼ばない。近くには伊之助の気配があるが冨岡の気配はない。匂いだけは僅かに漂っているので、どこかに潜んでいるのだろう。自分と伊之助がこの鬼の注意を引いている間にできた隙をみて、血鬼術を喰らわずに鬼の首を斬るつもりだろう。
瞬間的に記憶を弄られ、首が斬れたか分からない状態の中での判断は嗅覚、触覚が優れている自分達の方が有利だ。竈門炭治郎は首を斬った後の独特な灰のような匂いを、伊之助は肉体が崩れる気配を感じ取ればいい。それがなければ、鬼は生きている。首を取れていない。
「ハッハー!俺様達が揃えば!なにも恐れるものはないぜ!!目にモノ見せてやるから覚悟しやがれこの野郎!!」
伊之助から漂う匂いは怒りを多分に含んでいた。しかし怒りで前が見えないなんてことにはなっていない。その一撃には鈍りがなく、的確に鬼を狙い、ずらさせた記憶に惑わされることなく鬼の攻撃を避ける。極度の集中。竈門炭治郎は伊之助が怒りを含んでいることに、嬉しさを感じた。彼もまた、間接的に大切な人達を奪われているのだ。自分達はきっと、四人で一つだったのだ。
竈門炭治郎は伊之助を相手取っている鬼の右側に滑り込んだ。そして首ではなく、攻撃手段を減らす為に右手を側を削り取ろうと下から刀を振り上げた。鬼はその攻撃を避ける為に下り、しかし伊之助の追撃を受けたのでさらに下がる。
(よしっ……!このまま冨岡さんの方に不自然にならないように誘導する!)
伊之助との目配せなどしない。伊之助の動きも敵を誘導するものだ。しかし首は狙っていく。あからさまに首を取る気がなければ怪しまれる。それに首が斬れればなんでもいいのだ。竈門炭治郎とて、こいつの首は自分で斬りたい欲がある。
(善逸……!善逸!!善逸!!善逸!!っ……!!)
炭治郎は善逸の名前を心の中で連呼し、そして歯を食いしばる。こんなにもこの名は自分の心を掻き乱すのに、思い出がない。あちこちと虫食いのように空いた記憶の穴に怒りが湧く。そして何よりも、辛いのはこれではないと我慢ならない竈門炭治郎は伊之助に注意を向ける鬼の隙を見てぐっと腹と刀を握る手のひらに力を入れて、叫んだ。
「あっーーー!!妹の名前が思い出せないっ!!知らないっ!!兄として!!あまりにも不甲斐ないっ!!」
炭治郎は灼骨炎陽にて前方を大きく抉った。鬼の半身が削り取られ、回復には大きく時間がかかるだろう。二撃目で首を落とすと思ったところで、鬼は叫ぶように口を大きく開けて咆哮を放った。もろにくらった竈門炭治郎はぐんにゃりと視界が揺らぎ、まるで走馬灯のようにさまざまな記憶が頭の中を巡った。
(あっ。善逸)
竈門炭治郎はぐちゃぐちゃと再生される記憶の中で、一際輝く金の髪を持った少年が頬っぺたを膨らませて幸せそうに焼き餅を食べている姿を見た気がした。善逸と町で買い食いをしたことなどない。
(いや、ある)
脳が動かなくて身体が制御できない。これはあの時と同じ展開だ。鬼を追い詰めたところで記憶をかき混ぜられるようにされ、体を動かせなくなった。しかし今は一人きりではない。辛うじて出来る呼吸の中、伊之助が動いている匂いがする。そして、鬼はやはり回復に時間がかかるのか、焦った匂いをさせていた。竈門炭治郎は殆ど意識の外でのことに僅かに安心すると、未だ脳を揺さぶる記憶に目を回す。
蝶屋敷での機能回復訓練の日々、無限列車での朝日に照らされながら泣いたこと、鱗滝の元での辛く苦しい不安な二年。そして——。
「……禰󠄀豆子……」
炭治郎はいつの間にか天を仰いでいた。背中に感じる柔らかい感触と強い土の匂いは枯葉と地面だろう。どうやら地べたに寝転がっているようで、森の木々の切れ目から月が覗いている。
「……大丈夫か?」
「あ……はい……」
視界が陰ったと思えば、冨岡が無表情ながらも心配そうな匂いをさせて覗き込んでいた。視界の中でゆっくり仕舞われる刀に、炭治郎はハッとして体を起こす。すると少し離れたところで鬼がボロボロと空気に溶けていくところであった。
「半々羽織が倒したぞ」
伊之助は消えゆく鬼を睨みつけながらそう言った。炭治郎は欠片ひとつも残さず消えていく鬼の侘しい匂いに、何故だろうと思う。なぜ、人の大事なものを奪い取るのか。大事なものを壊すではなく、記憶を奪うのか。
「……あ……」
すうっと溶けきった鬼に、炭治郎は何も言えなかったと息を吐いた。立ち上がり、泥を払い、落とした刀を拾う。頭が少しぐらぐらしている感覚があるが、次第にこの違和感も落ち着くだろうと緩慢な動きで刀を鞘におさめた。
「おい!鬼を倒したぞ!!記憶は!?記憶は戻ったのか!?」
「落ち着け。鬼を倒しても血鬼術はしばらく残る」
「あ、大丈夫です。戻りました」
炭治郎がそう言うと冨岡はびっくりした顔を見せた。分からなくはない。基本的に相手にかける血鬼術は、後々まで残るからだ。経験則でまだだろうと冨岡が思っても何も不思議なことはない。
「その、どうやら鬼の首を斬ろうとした時にかけられた術は、記憶を戻すものだったみたいです。あれを喰らうと頭の中が瞬間的にぐちゃぐちゃにかき混ぜられたみたいな感覚に陥って動けなくなるので……足止めの為にかけたんだと思います」
炭治郎はふわふわした感覚が残る頭を振って、息を一つ吐くと記憶の欠落がないか考える。生まれたての竹雄を可愛いとはしゃぐ禰󠄀豆子、ハイハイをする花子の隣で同じように這って遊ぶ禰󠄀豆子、茂のおしめを替えてあげる禰󠄀豆子、六太を背負って子守唄を歌う禰󠄀豆子。
「うん、大丈夫だ。ちゃんと取り戻した」
炭治郎はそう言って、ぐっと胸が震えた。去来したのは大きな感情だ。善逸が自分と禰󠄀豆子を絶対に会わせまいと引き離したその心。
(ああ……善逸っ……!)
炭治郎は込み上げてきた涙を隠すように手の甲を眉間に当てた。唇が震えて、呼吸が乱れる。胸が痛んで苦しい。炭治郎は冬の寒空の下、生ぬるい涙を流した。善逸にまた守られてしまったと申し訳なさが募るが、それを上塗るように喜びがくる。
(どうして善逸は……俺が喜ぶことばかりできるんだ……)
禰󠄀豆子と引き離してくれて良かった。お陰で禰󠄀豆子に『知らない』なんて『分からない』なんて言わずに済んだ。妹を無駄に傷つけずに済んだ。寂しがらせてはしまったかもしれないが、言葉で傷つけることにならずに済んだのだ。不幸中の幸いだ。けれどその幸いは、善逸が作り出してくれたものだ。
「……戻るぞ」
泣いている炭治郎に冨岡がそれだけ声をかけた。伊之助は何も言わずに歩き出す。炭治郎もなんとか涙を止めようと鼻を啜り、目元をぬぐった。少し先に行く二人を追うように歩きながら、じわじわと込み上げてくる何かに耐えきれなくて炭治郎は一気に走り出すと冨岡と伊之助を追い越した。
「すみませんっ!!先に行きます!!」
「あっ!待てよ健太郎!!」
炭治郎は伊之助の呼びかけに立ち止まることなく駆け続けた。早く、早く会いたいと涙を零し、鼻水を垂らしながら朝に向かう夜闇を駆ける。泣いていると流石に呼吸が乱れる。走り方も上手くない。後ろに伊之助がいるのに、追いつきも追い越しもしてこない。炭治郎は色々とぐちゃぐちゃになった自分に情けなさを感じた。
大切な二人を忘れてしまうなんてと、血鬼術だからしょうがないと思うことができない。けれどこの気持ちを忘れてしまっていた人に言えば、「はあー?血鬼術はしょうがないだろ?」と呆れた顔で言うに違いないし、言って欲しい。一回言われた程度じゃ納得できないし、心は軽くならない。どうか何回も言ってくれ。何回も言い聞かせて、最後には「なーんで忘れられた側の俺がお前を励まし続けなきゃならんのよ!もうそんなの拘ってないでさっさと罪を償え!!」とか何とか言って町にでも連れ出して欲しい。団子でも、焼き餅でもご馳走するから。鰻でもいい。
「……禰󠄀豆子……善逸ー!!」
炭治郎は蝶屋敷迄を延々と走り続けた。呼吸が乱れたからとても疲れた。汗だくで、ふらふらで、鬼殺隊士失格だと思いながら、朝日が昇る頃に蝶屋敷の門扉にたどり着く。ガクガクと笑う膝が辛い。自分を支えるように門扉に手をつけば、開けられないと勘違いしたのか伊之助が後ろから押してくれたお陰で、門扉に体重を掛けていた炭治郎は地面に倒れ込む。
「あ!おい!炭治郎!!」
焦った声の伊之助が、珍しく名前を間違えずに呼んだなと思いながら、炭治郎は起き上がらねばと腕に力を入れる。ぐらぐらする肘に回復の呼吸だと、なんとか座り込みながらヒーヒーと息を吸って吐いて、疲労を取る。早く、早く会いたいとそう思いながら動かぬ自分に悪態をつこうとしたその時、ふわりと花のような甘い匂いが香ってきて炭治郎は目を見開いた。
「お、おかえり、なさいっ……!」
朝日の中を飛ぶように駆けてくるのは、炭治郎の何よりも大切な宝だ。炭治郎はひさしぶりに見た禰󠄀豆子の姿によろりと立ち上がると迎えるために両手を広げた。
「禰󠄀豆子っ……!!」
「おにいちゃん!」
腕の中に飛び込んできた禰󠄀豆子はとても嬉しそうだった。その身体を抱きしめて、取り戻したと炭治郎は強く思った。この子を忘れていたなんて、本当に情けない。悔しい、不甲斐ないと炭治郎の中に罪が重なっていく。
「禰󠄀豆子、禰󠄀豆子……!」
「ん?」
「……兄ちゃん、兄ちゃんはっ……!ごめっ……」
「炭治郎、おかえり」
口をついて出そうだった謝罪を遮ったのは、炭治郎の心を丸ごと分かってくれるような人の声だった。炭治郎はその声につられて顔を上げ、唇を引き結ぶ。謝罪をしてはいけない。禰󠄀豆子には今回のことは何が何でも、徹底的に伏せるべきなのだ。ひと時でも、理由があったとしても、兄に忘れられてしまったなんて、禰󠄀豆子に知らせる必要はない。
「……ただいま、善逸」
炭治郎は自分を楽にする言葉を飲み込んで、そう言った。嬉しそうに微笑む善逸に、炭治郎も自然と笑みが浮かぶ。罪を許して欲しいと思っていた。何度でも謝って、そして許して欲しいと思っていた。しかし善逸はさせてはくれないらしい。きっと禰󠄀豆子の心を守る為だろう。
(ああ……好きだなぁ……)
炭治郎は朝日に照らされ、輝く善逸を見つめながらしみじみと思った。胸の中に満ちる気持ちはずっとずっと前から揺蕩っていたものだ。善逸を愛しいと、特別だと想う淡い恋心。男同士だからと、善逸は禰󠄀豆子が好きだからと、伝える気がなかった恋——。
(……口づけてしまったな……)
炭治郎は大切な二人に微笑まれながら、記憶がないうちにした己の失態にゾーッと背筋を震わせた。
****
吐く息が白く色づく。耳がじんっと痛んで震えるような空気の中、善逸は庭を楽しそうに駆ける炭治郎と禰󠄀豆子を眺めていた。二人穏やかに笑い、ひらひらと着ているものの裾を揺らしている。無邪気に遊ぶ二人の笑顔は溶けるように柔らかく、善逸はその笑顔をぼんやり縁側に座って見守っていた。
(春になる前に記憶が戻って良かった……)
善逸は再び体中の息をゆっくり吐き出しながら、最悪の事態にならなくて良かった、安心したと心の中で繰り返す。幾度も幾度も想像しては奥歯を噛み締めた事態はついに訪れなかった。その事が嬉しくて、安心して、こうして縁側に座って二人を眺める以外のことができないなと善逸は頷く。ちまたでは鬼の出現がやみ、最終決戦が近々起きるのではないかと専らの噂だ。柱稽古をする好機などと言われている。
「……そんなのもうちょっと後でいいのにー……」
善逸は鎹雀が伝えてきた柱稽古なる恐ろしい話を思い出して苦虫を潰したような顔になる。ようやくあの二人に平和が訪れたのに、どうしてそれを壊すようなことをするのか。柱稽古なんて始まったら、炭治郎は禰󠄀豆子そっちのけで鍛錬に勤しむに決まっている。
(禰󠄀豆子ちゃんはお前のこと、ずーっと良い子にして待ってたんだぞ!!)
善逸は記憶を失った炭治郎がいない間、じっと禰󠄀豆子と向き合ってきた。禰󠄀豆子は兄がいないことに寂しい様子は見せても、善逸に訴えることはなかった。むしろ善逸を励ますような微笑みを見せることもあり、その健気な姿に善逸は早く例の鬼を見つけなければと思ったほどだ。
(まあ、俺は何もできなかったんだけどね……)
善逸は炭治郎と禰󠄀豆子を助けなければと恐ろしいのを堪えて任務に幾度も向かったが、どれもこれも全くのハズレだった。結局、例の鬼は同じく探していた伊之助と冨岡、そして炭治郎が首を斬った。炭治郎は記憶がないことに気がつき、鬼を倒すために無理やり同行したそうだが……無事で良かったと善逸は何度も胸を撫で下ろしている。
何しろ炭治郎ときたら、記憶をなくす前と後では動きの精彩さがあまりにも違ったのだ。善逸は炭治郎の動きに恐ろしささえ感じていた。あんなにも強かった男が心ひとつ、記憶ひとつでこんなにも変わるのだ。しかし失ったものがあまりに大きい存在であるのは分かっていたので、弱くなったことに納得すらしてしまう。
(禰󠄀豆子ちゃんだもんなー。そりゃそうだよなー)
禰󠄀豆子は炭治郎の行動原理そのものだ。もちろん人を助ける、鬼を滅するという鬼殺隊士としての理念もあるだろうが、炭治郎が真に心の真ん中に置いているのは禰󠄀豆子の幸せだ。禰󠄀豆子を元に戻す。そして二人で家に帰る。それが暴れたとなれば、剣筋も身のこなしにも確実に影響がでるのは自明の理だ。
しかし実際に鬼を倒したときの炭治郎の動きは、伊之助いわく「そこまで悪くなかったぜ」とのことだった。鬼に記憶を奪われたことを自覚した故だろうか。途中、危ないところもあったようだが、任務にあたっていたのは三人であった為に大きな怪我をすることもなく無事に終わった。
善逸はふむっと頷きながら縁側にごろりと寝転がる。青い空にはうね雲が並んでおり、その一筋一筋を眺めながら、いつか炭治郎が話していた家の近くに作っていた畑の話を思い出す。大した広さはないけれどと前置きをしながら、小さな弟や妹たちが頑張ってタネを植えていたんだと懐かしいものを見つめるような眼差しをしていた。
まだ炭治郎は何かを懐かしむほどに歳を食っていないのに。善逸はこの世の無常に文句を言いたい。こんなにも優しい男から奪って何が楽しいのかと、世界のナニカに文句をつけたい。
(早く、本当に平和になればいいのに……)
妹と家に帰りたい。それだけの願いを叶えるのにどれだけの血を流し、命を懸けねばならないのか。どこかの大きな街で見かけた修道士が「これも神の試練です」などと話していたが、残念ながら善逸はひとつも理解ができなかったし、賛同もできなかった。修道士の話を聞いてきた人は教えに胸を震わせていたが、申し訳ないながら善逸にはちっとも分からない。
(試練で家族を殆ど殺されて、妹を鬼にされて、元に戻す為に人喰い鬼と戦い続けろってしんどすぎるだろ)
そもそも殺されたのが試練とかあり得ない。それとも鬼舞辻無惨と邂逅したことが死んだ家族の試練だったのか。どう足掻いても勝てやしないではないか。過剰すぎる試練を与えるなと善逸は心中で文句を言い、しかし試練であると何か拠り所がなければ立ち上がれない人も確かにいるのだと瞼を閉じる。
(俺も……炭治郎と禰󠄀豆子ちゃんを助けたいばっかりだもんな)
善逸は人の役に立ちたい、柱になりたいと思っている。もちろんその流れの中で自分と家族になってくれる人と出会い、幸せになりたいとも思う。しかし根っこの部分は良いことをして認められたいだ。善逸は鬼を倒せば感謝してもらえることを知っている。その為に日夜、訓練と鍛錬を重ねている。しかし目標に具体性のない鍛錬は辛い。だから善逸は口にはしないけれど、炭治郎と禰󠄀豆子がいつか家に帰れるように、二人を守るぞと決めて鍛錬をこなしている。
名前も顔も知らない誰かを助けたいからでは体が動かない。善逸はそこまでの聖人には到底なれない。だから身近にいて、幸せになって欲しい人達を想って鍛錬をし、戦うのだ。善逸にとって炭治郎と禰󠄀豆子の存在は怖くとも鬼と対峙する原動力。二人のためならこれが神の試練と言われても立ち向かえる。
「ぜんいつ?」
「……ん……?あ!禰󠄀豆子ちゃぁん♡ どうしたの〜♡」
善逸は肩を揺さぶられた感覚に目を開けた。すると視界に飛び込んできたのは己を覗き込む禰󠄀豆子で、その可愛らしさに善逸はパッと飛び起きた。禰󠄀豆子は縁側にちょこんと座りながらにこにこ笑っていたが、すぐにキッと眉根を寄せ、前に乗り出して言った。
「さむいよ!」
「えっ!?禰󠄀豆子ちゃん寒いの!?俺の羽織着る!?」
善逸は禰󠄀豆子の言葉に大変だと羽織を脱いだ。禰󠄀豆子は鬼であるから寒暖に影響を受けないと思っていたが、実は死なないだけで寒さ暑さを感じていたのだろうか。なんてことだ。気がつかなかったと半泣きで羽織を広げたところで、ざりっと地面の砂が擦れた音がする。
「……違うよ善逸。禰󠄀豆子は縁側で眠っていると寒くて風邪をひくと言いたいんだ」
そう言ったのは禰󠄀豆子のことをよく分かっている兄の炭治郎だ。炭治郎は縁側近くに寄りながらも、そっぽを向いてそう言った。善逸はその言葉を飲み込みながら、確かに寒いよなと炭治郎の赤くなった耳をじっと見る。しかし炭治郎はずっと違う方を見ていて、善逸を振り返りもしない。
「なるほど。禰󠄀豆子ちゃんなんて優しいんだ〜!」
善逸はそう言って「ありがと♡ お布団で寝るね♡」と言って立ち上がり、禰󠄀豆子に手を振ってから部屋の方に向かう為に縁側を歩く。すると去りゆく己の背中に、穴を開ける気かと言わんばかりの視線が刺さる。禰󠄀豆子はもう庭に駆け戻っているのか音が遠くなっていくが、重低音をかき鳴らすもう一つの音は変わらぬ位置にいるようなので視線は炭治郎のものだろう。
善逸は投げかけられる視線にうんざりして立ち止まり、バッと振り返った。するともう炭治郎は禰󠄀豆子の方を見ており、善逸は口の中で舌打ちをする。そして面倒だと思いながら溜息をついて部屋に戻ろうも再び歩き出すわけだが、そうするとまた背中に視線が刺さるのだ。
(まったく!なんなんだよいったい!!)
善逸は荒い足取りで部屋に戻ると、禰󠄀豆子に心配されたからといそいそ昼寝用に布団を取り出した。縁側で眠ると風邪をひくというなら、布団の中でしっかり昼寝しよう。昼寝の件に関しては炭治郎も何も言わなかったしと今までならば小言を言ってきただろう相手のことを想像して、善逸はまたぎりっと歯を噛んだ。
「炭治郎の奴、どうしちまったんだよ」
善逸はあまり声を荒げて言えない変化にうんざりしていた。炭治郎が記憶を取り戻してからはや三日。どうにも相手の態度がおかしい。以前と比較すると、明らかに炭治郎の態度がよそよそしいのだ。
もちろん変わらず寝食は共にしている。けれどそれ以外の時間は禰󠄀豆子とどこかに行ってしまい、善逸は取り残させる。音を頼りに後を追っても、追いやったりはしないものの先ほどのようにそっぽを向いている事が多く、視線はまるでかち合わない。
「……禰󠄀豆子ちゃんと引き離した事、怒ってんのかなぁ」
あの件について、特に炭治郎と話をしていない。話題に出せば禰󠄀豆子に聞かれるからだ。再会してからは基本的に禰󠄀豆子は炭治郎にべったりくっついている。離れていた反動だろう。禰󠄀豆子がいるところでは炭治郎が記憶を失い、禰󠄀豆子を分からなくなっていたなんて絶対に話に出すわけにはいかない。だから善逸は自分が取った行動について、炭治郎がどう思ったかの答え合わせはできていないのだ。
「帰ってきた時は、別に怒った音させてなかったんだけどな……」
禰󠄀豆子のことを思い出せた事実に感極まっていたからだろうか。時間をおいたら引き離したことについて怒りが湧いてきたのだろうか。
「でも俺は悪くない!!」
禰󠄀豆子を寂しがらせた事に善逸は罪を感じているが、禰󠄀豆子に嫌な記憶が残るくらいなら炭治郎は訳あって出掛けていることにした方が良かったと善逸は信じている。信じているが……炭治郎にそっぽを向かれると自信がなくなってくる。勝手なことをしたと呆れられているのかも、不快に思ったのかもと不安がふつふつと蘇ってくる。しかし善逸は何度同じ場面に出会しても、何回だって同じ道を選ぶ。炭治郎に禰󠄀豆子を知らないなんて、言わせることはできない。
「ちぇっ……炭治郎の馬鹿野朗……」
善逸はぐすんっと鼻を啜ると少しウキウキしながら布団を捲る。昼間から惰眠を貪れるなんて最高だ。炭治郎は部屋に寄り付かないから、怒られないぞと布団に入ったところで、こちらに向かってくる荒い足音が聞こえて善逸は頭から布団を被った。しかし障子が開く音がして、すぐさま温くなりかけた空気が霧散する。布団を剥ぎ取られたのだ。
「おい紋逸!なに昼間っから寝ようとしてんだっ!」
「もおおおお!!なんだよ伊之助!邪魔すんなよなぁ!!」
「寝てる暇があるなら鍛錬だ!もうすぐ柱稽古が始まるんだぞ!それに向けて猛特訓だ!!」
「柱稽古で鍛錬できるでしょ!?なんで稽古に向けて稽古すんのよ!?意味わかんない!!」
善逸は伊之助から布団を取り返すと再び布団に潜る。伊之助は深追いはしないのか、今度は布団を取り上げようとはしなかった。善逸はやれやれと思いながらも、柱稽古という単語に憂鬱になる。地獄の日々が着々と近づいてきている。強くなった方がいいのは分かっている。もし本当に最終決戦がくるというのなら、最後の方まで生き残らねば炭治郎と禰󠄀豆子を助けてやることもできないかもしれない。善逸は早々に死ぬわけにはいかないのだ。
(でも怖いんだよ柱ぁ!!あんっな化け物みたいな人たちから直々に稽古受けるとか怖すぎでしょ!?)
善逸は柱についてはよくは知らない。しかし柱になる人達なのだ。自分達が今やっている鍛錬よりももっと凄いことを日々してきたに違いない。世界が違う人間のやっている鍛錬など、炭治郎や伊之助くらいしか耐えられないのではとガタガタ震えた。早く布団よ温まってくれ。
「昼間から寝てると権八郎に怒られるぞ」
伊之助は布団は剥ぎ取らないが、寝ていることについては小言を伝えてくる。言い草がまるで「兄ちゃんに怒られるぞ」という弟丸出しで、善逸は笑ってしまいそうになった。しかし伊之助の言いたいこともわかる。特に任務もなかったのに昼寝なんて怠惰が過ぎると怒るだろう。以前の炭治郎ならば。
「……怒られないよ」
「なんでだ?」
「あいつ、俺のこと嫌いになって避けてるから」
そう言って善逸はちくんと胸が痛んだ。善逸は別に炭治郎と禰󠄀豆子の為と思って行動したわけではない。むしろ自分が気に入らないからと炭治郎の元から禰󠄀豆子を攫って逃げたのだ。けれど、それでも、少しは炭治郎の為になったらとも思っていた。だから炭治郎に避けられて、裏切られたような気持ちになるが……。
(炭治郎からしたら、俺が裏切ったみたいに見えるのかな)
炭治郎が禰󠄀豆子とずっと共にある覚悟を持っていることを善逸は知っていた。そして善逸が知っていることを炭治郎は知っていた。だから尚のこと、二人を引き離す行為をした自分を許せないのかもしれない。けれどはっきりと糾弾しないのは禰󠄀豆子に知られない為か、はたまた記憶がない時のことを詰るのは良くないと律しているからなのか。
(頭では良くないって思っても、心が嫌だっていうことあるもんな)
炭治郎は善逸を責めるべきじゃないと思いながらも、不満に思っているのかもしれない。だから側にはいるけど顔を見ないというようなチグハグさが出ているのかもと善逸は温くなってきた布団の中でうとうとと微睡む。しかしそれはまた布団が剥ぎ取られたことで遮られた。
「おい!あいつがお前を嫌ってるわけないだろ!!」
「急に寒っ!!何すんだよ伊之助ぇ!!」
「ハァァ!?お前がトンチキなこと言い出すからだろうが!!あいつがお前のことを嫌うわけがねぇ!どこに嫌われる点があるんだ!?分かった!弱味噌だからか!ならしょうがねぇ……」
「ちょっとぉぉ!!否定しておいて納得するなよっ!!違うよ!!えっ!?違うよね!?」
善逸は起き上がると目を剥き出しにして怒って泣いたが、伊之助は勢いに乗ってくることはなく、猪頭ごしにじっと善逸を見ている。
「知るかよ。弱味噌が理由じゃねぇなら、そもそもなんで嫌われてるとか思うんだよ。心当たりでもあんのか?」
純粋な疑問ですという澄んだ音に善逸の心はやられた。伊之助は一切茶化しておらず、素朴な疑問を投げかけているに過ぎない。善逸は正面からくる伊之助にぐっと喉を詰まらせたが、吐き出さねば死んでしまうと、どこにも吐き出せなくて苦しかった言葉をついにこぼした。
「いや……たぶん、禰󠄀豆子ちゃんと引き離したから……炭治郎は怒ってるんだわ」
「ナンデ?」
「なんでって……ほら、やっぱり了解も取らずに大事な妹を連れて行くのはさ……よくないだろ」
「だからなんでだよ。あいつその時、お前らのこと丸ごと忘れてたじゃねぇか。不満に思う方が酷くねぇか?お前ら、忘れられてたんだぞ?」
心底わかりませんという伊之助の言葉に、善逸はどう説明すれば伝わるのかと髪を掻き混ぜる。しかし炭治郎の為にも忘れたことをあまり重いことにはしたくないのだ。禰󠄀豆子を忘れたことは罪深いと思っているけれども、どうしようもないことでもあったのだ。
「でも……血鬼術のせいじゃん!炭治郎が忘れたのはさぁ!」
「じゃあ紋逸がねず公を連れて出て行ったのも血鬼術のせいだろ?権八郎の奴に忘れられたの知らせない為に出て行った。誰も悪くねぇ。なのになんで権八郎がお前を嫌うんだ!おかしいだろ!」
「そ、そうかもしれないけど……炭治郎にも思うところはあるんだろ。分かっていても納得できない……みたいなさぁ」
そう言って説明したが、伊之助はやはり分からないというように首を傾げている。その様子にまだこの話を続けなければならないのだろうかと、善逸は少しうんざりしてしまう。善逸とて炭治郎に避けられているのは辛いのだ。寂しいのだ。だからあまり考えたくないのにと、床に転がっている布団を引き寄せようとしたら、伊之助に踏まれて止まってしまう。
「おい、足……」
「炭治郎が言ったのか?」
「え?」
「お前のこと嫌いって。ねず公を連れて出て行ったの許せねぇって言ったのか?」
その神妙な声に、善逸は伊之助を見上げながらゴクンっと唾液を飲み込む。そして布団を掴んでいた手をぎゅうと握りしめると伊之助から視線を逸らした。
「いや、違うけど……」
「なんだよ。じゃあちゃんと理由を聞いてこいよ」
至極真っ当な指摘に善逸は固まる。それが出来たら苦労はしない。聞きに行って肯定されてしまったらどうするのか。決定的な決裂になってしまうかもしれない。
「いや……禰󠄀豆子ちゃんがいるのにその話題はさぁ……。折角隠し通せたんだから、バレるようなことは……」
「じゃあ俺が連れ出してやる。待ってろ」
「えっ!?あ!伊之助!!」
伊之助はバタバタと走り出した。その後を追おうとして立ち上がったが、布団が足に絡まってズルリと前に倒れ込む。危ないと手をついて受け身を取ると、何故かまた伊之助の足音が戻ってきた。なんだなんだと床に這いつくばりながら顔を上げると、開かれた障子から猪頭がひょこりと覗いた。
「お前ら二人は恋人ってやつなんだろ。だったらさっさと仲直りしやがれ」
「え」
伊之助はそれだけ言ってまた踵を返して走っていく。遠くから「走らないでくださいっ!!」とアオイの声が聞こえた。しかしその声では伊之助は止まらなかったらしく、あっという間に足音は遠くなる。
「……恋人?誰と誰が?」
善逸はそう呟いて会話の流れとしては自分と炭治郎の事だろうと口元に手を当てて驚愕する。しかしふにっと唇に指が当たった瞬間、ある感触を思い出した。
「あっ!!炭治郎のやつ!そういえば俺の口を吸ってきやがったんだった!!」
善逸は混乱の最中ですっかり忘れていたと、記憶がない頃の炭治郎が自分の口を突然吸って去っていった事実に驚愕する。あの後、禰󠄀豆子が起き出して善逸を探す声が聞こえたので炭治郎を追いかけたくてもできなかったのだ。ひたすら禰󠄀豆子を遊ばせ、元気いっぱい、鬼なので戦ってもいないならすぐには寝ないことを理解した善逸は二人で蝶屋敷に行くことにした。
その頃には炭治郎が禰󠄀豆子と自分の記憶がない事に気がついてしまった衝撃が強く、口を吸われたことなんてどうでも良くなっていた。しのぶにことの仔細を確認する為に蝶屋敷を訪れた際に、炭治郎と禰󠄀豆子が鉢合わせないかばかりを気にしていたせいもある。
「あいつなんで口なんか吸うんだよ〜!俺は初めてだったのに!!」
あの時、炭治郎は様子がおかしかった。しかし記憶を奪われている事に気がついたというなら、それは様子がおかしくなっても仕方がないだろう。もしかしなくとも、炭治郎も混乱していたに違いない。
「混乱してるからって口を吸うなよ」
善逸は炭治郎は混乱していたと決定づけはしたが、口づけに関してはおかしいと顔を顰める。しかし口づけの事実を思い出した善逸は、だんだんと炭治郎の態度がおかしいことに納得ができた。あの男はもしかしなくとも、あの口づけを覚えているのではないだろうか。
「……恥ずかしがってんのか?」
炭治郎は善逸を避けるようにするが、徹底的に避けてはいない。食事も寝る部屋も共にするし、しかし以前のようにはあまり積極的には話しかけてこないし、話がある時は先ほどのようにそっぽを向いていることがある。善逸は嫌われたかもとその態度で思ったが、音はどうだったか。炭治郎と目が合わないことばかり気になって、音にまで意識がいっていなかった。とりあえず自分が不安に思うような音は炭治郎からはしていなかった筈だと、善逸は少しだけ気分が上向く。
「……確認しよう」
そうだ。あの時の口づけはなんだったのか確認しよう。善逸はそう思って立ち上がると、足元にある布団を簡単にまとめて敷布団の上に乗せた。後でまた寝るから、押し入れに戻すのはしない。隊服と羽織に袖を通した善逸はよしっと頷いて気合を入れた善逸は縁側へと出ると音を頼りに炭治郎の居場所を探す。
伊之助は本当に禰󠄀豆子を連れ出したらしく、炭治郎は先程まで自分が寝転んでいた縁側辺りにいるようだ。善逸は炭治郎に何と話しかけるかを考えて、周りくどいと逃げられるかもしれないから「なんであの時、俺のに口づけしたの?」と聞こうと決める。
あの時の炭治郎は記憶がなかったのだ。何か変な理論で口づけをしてきていても何ら不思議はない。自分達の関係性を口づけしてもおかしくないものと判断したのかもしれない。
「……いや、いやいや。どんな関係なら口づけしていいっていうのよ」
善逸は自分の推論に恥ずかしくなって固まった。口づけをしていい関係なんて、夫婦か、恋人か、情がある者たちだけだろう。炭治郎が失ったのは禰󠄀豆子と自分の記憶だけで、常識や世俗について疎くなったわけではない。いや、元から少しおかしいところはあったが、誰彼構わずに口づけをしていいと思う男ではない。むしろその辺に関しては他の男よりも欲が薄いように見えた。
「……炭治郎の奴、俺との関係性を……こ、恋人だと勘違いしたのか?あっ!そうだ!伊之助もなんかそんなこと言ってたな!?」
去り際の伊之助がなにやら自分と炭治郎は恋人なんだろうと話していたと、善逸は青くなり、赤くなる。そんな恋人に見えるような何かが自分達にあっただろうか。普通の有人としての振る舞いしかしていない筈と思い起こすが……善逸はいままで友達がいなかったのでよく分からないのだ。
「うう……」
善逸は急に鼓動が大きくなった自分に戸惑う。もじもじと羽織の袖口を握り込み、ゆっくりと吸われた唇に指先を当てた。ここに炭治郎の口が当たったのだ。ほんの少しだけ吸われた感覚があった。
「た、炭治郎のやつ……俺のこと好きなの……?」
記憶のない炭治郎が自分達の関係を何故か知らないが恋人と誤解したとしよう。そこで「じゃあ口づけよう!」となるならば、炭治郎は自分に口づけてもいい気持ちがあったわけだ。善逸は自分が誰かに口づけてもいいと思ってもらえるなんてと心がきゅんと締め付けられた。
「あ……でも、あれか。炭治郎はあの時は記憶ないもんな。なんか、今も俺のこと見てこないし」
しかし嫌な音がしていないということは、恥ずかしがって見つめ合えないだけでは?もしかしなくても炭治郎は自分のことを元から好きなのでは?なんて善逸は尻をソワソワとさせた。なぜ尻がソワソワするのかは分からない。
「まいったな〜。俺にモテが来てしまった。でも俺が好きなのは女の子だし、禰󠄀豆子ちゃんだからな〜」
しかし誰かの好意は嬉しい。善逸は心が春の陽気のように暖かく感じるのににっこりと笑った。そしてそのまま歩いて行くと、少し先にぼんやりとした様子で縁側に座っている炭治郎が見えてくる。
(いや〜炭治郎に好きですって言われたらなんて断ろう。傷つけたくないしなぁ。あ、でも記憶がない頃の炭治郎の早とちりかもしれないし、今の炭治郎は何であんなことしたんだって恥ずかしがってるだけかもしれないし。それならあの時のことは水に流して忘れようって言ってやらないとなぁ。まあ、でも俺のこと本気で好きかもしれないですしぃ?ウィッヒヒ!)
善逸は「モテる男は辛いなぁ」なんて弾んだ気持ちで炭治郎の方へ近づいた。するとだんだんと炭治郎が苦悶の表情を浮かべているのがはっきり見えてきて、善逸はおやっと思う。しかしこんなに近づいても炭治郎は腰を上げないので、これ幸いとばかりに善逸は以前のように黙って横に並んで座った。
「……炭治郎?」
「…………」
炭治郎は善逸の呼びかけに目を瞑り、しばし沈黙すると、ゆっくり眼を開けた。その赤銅色の瞳は決意に満ちていて、善逸はドキンっと胸が高鳴る。
「善逸」
「は、はいっ!」
「……ここ最近、お前を避けるようなことばかりして悪かった。ごめん。謝るよ」
「あ、やっぱり避けてたのね……?」
「うん。でもそれは善逸が禰󠄀豆子を連れて義勇さんのところに行ったからとか、俺から禰󠄀豆子を引き離したからとかじゃない」
「とても具体的に言ってくるじゃん……」
「いや、さっき伊之助に聞いたんだ。善逸がその事で俺が怒ってるんじゃないか悩んでるって」
「あ、なるほど?」
どうやら頼もしい親分は炭治郎にも声を掛けていたらしい。禰󠄀豆子を連れ出す理由として話でもしたのだろう。だから炭治郎は逃げずにここにこうして座っているのだと、善逸は納得した。
「……俺が禰󠄀豆子ちゃん連れてったこと、怒ってないんだな」
「怒ってない!怒るわけがないだろう!むしろ俺は……善逸の優しさに感謝しかない!!」
前を向いていた炭治郎がそう言って善逸の方を振り向いた。心外だというように寄った形のいい眉は強い表情をさせているが、キラキラと輝く瞳は美しい。炭治郎が本当に怒っておらず、自分に感謝してくれているのだと音を聞かずとも善逸に伝わった。
「……そっか……良かった……」
善逸は炭治郎に感謝していると言われ、じわりと凍りついていた心の一部が溶け出すのを感じたい。これは恐れだ。炭治郎が怒っているかともと、余計なことをしたのかもと思っていた恐れが消えてなくなった。
「良かったよぉ〜!本当に俺、何を勝手なことしてるんだって炭治郎に思われてたら立ち直れなかった!!」
「そんなこと思わないよ。善逸が禰󠄀豆子から俺を引き離してくれたからこそ、禰󠄀豆子に悲しい思いをさせてなくて済んだんだ。……本当に、いつもいつも、俺は善逸に救われている。恩ばかりが募ってしまって、苦しいくらいだ」
善逸は炭治郎の言葉に買い被りすぎたなと思った。しかし鼻水が出てうまく喋れない。ずずっと吸い上げると、炭治郎は困ったような優しげな顔をして懐からチリ紙を出した。そしてそれを当たり前のように善逸の善逸の鼻先にあてる。
「ほら、善逸」
「ん……びぃぃぃぃ〜!……ありがと」
すっきり綺麗になったところで善逸は、「いや自分で鼻くらいかめるし」と子供扱いされたのを不満に思い、ムッと唇を突き出した。目だけで子供扱いをするなよなと訴えかければ、炭治郎は善逸の顔を見て、急に顔を赤らめた。その様子におやっと思っていると、視線がどうにも唇に注がれているような気がして、善逸は尖らせていた唇をギュッと噛み締める。
「……炭治郎のすけべ……」
「ええっ!?違う!!」
「いやでも、いま口見てただろ……」
「み、見てただけだろ!?」
「でもお前、勝手に俺に口づけしたじゃん。しかもちょっと吸ったよな?」
「あ……ぐっ……!」
炭治郎はカーッと顔を赤らめるとチリ紙を丁寧に畳んでポケットにしまった。そしてゆっくり前を向くと俯いて固く目を閉じる。顔の表皮は真っ赤で、耳までも赤い。心臓の音は和太鼓の如く大きく鳴っていて、善逸はつられて自分の心臓の音も大きくなるのを感じた。
「あの……なんか、伊之助が俺とお前は恋人だろ〜とか、言ってたんだけど……」
「……それは記憶のない頃の俺が、伊之助に行ってしまったんだ」
「んん?」
「俺が善逸との関係を……早とちりして、それでその、鬼を斬るために任務に同行したときにちょっと話になって……それで……」
「なるほど」
善逸は炭治郎の様子を眺めながら、これはどうにも雲行きが怪しいなと思った。赤かった炭治郎の顔はだんだんと青くなっていっている。その様子に善逸の心臓もだんだんと音が平常に戻ってきた。好きだと思われているかもなんて浮かれていたが、どうやら勘違いだったようだ。その証拠に炭治郎からは後悔するような音ばかりが立っている。
(なんだ。そっかぁ)
善逸はつまらない気持ちになりながら、縁側から放り出している足先で空を切った。本当は地面を擦りたかったが、草履を履いていない。
(あー……しょうがないなぁ。ここは俺が大人になって、水に流して忘れようって言うか)
善逸は炭治郎と仲良くしていたいのだ。変に気まずくなるのは辛い。だから記憶がない頃の話は回数に数えない、団子でも奢ってもらってそれでチャラにしようと提案するのだ。いや、禰󠄀豆子を守っていた礼を上乗せして鰻でも奢ってもらおう。そうしよう。
善逸はふうと息を吐くと肩をだらりとさせて炭治郎の方を振り返った。するといつの間にか炭治郎も振り向いており、ガチンと視線がかち合う。赤銅色の瞳は決意に満ちていて、善逸は再び胸が高鳴った。本日二度目だ。そう思ってその瞳を見つめてしまった善逸は、炭治郎に先手を取られる事になる。
「善逸!!こんなことを頼むのは申し訳ないが……あの時のことは水に流して忘れてくれないだろうか!」
「え」
「本当に、本当に申し訳ないが……あれはその、早とちりで……勝手に口づけてしまってごめん!どうか忘れて欲しい!!」
善逸はこの通りだと頭を下げる炭治郎にポカンと口を開けた。そして頭を下げ続ける炭治郎の脳天をしばし見つめ、いつまで頭を下げるのだろうと思ったところでフッと笑う。
「……善逸?」
炭治郎の不安そうな声があがる。善逸はやれやれと頭を振ると、炭治郎の肩をポンっと叩いた。
「顔を上げろよ炭治郎。俺は気にしてないからさ。お前の言うようにあの時のことはお互い水に流して忘れようぜ」
「善逸っ……!」
感極まったような声をあげて顔を上げた炭治郎に善逸はすかさず顔を寄せた。炭治郎のカガチの瞳が大きく見開く。善逸はそれを睨みつけながら、柔らかい唇に己のものを押し当て、あの時されたように僅かに吸った。
「ちゅっ」
「えっ」
炭治郎の間抜けな声をあげる。表情も間抜けだ。善逸はへっと鼻で笑うと立ち上がり、上から炭治郎を睨め付ける。
「返してもらったぜ。これでチャラな。あーもう、俺は忘れたから、お前も忘れろよ?」
善逸はそう言ってくるりと踵を返す。元から水に流してやろうと思っていたが、どうして自分からの提案ではなく、炭治郎から提案となると腹が立つのか。お前が言うのかと腹が立ってしまった。
(あームカつく!鰻奢らせられなかった!)
口づけを返してもらうことでチャラにした為、鰻を奢ってもらう提案はもうできない。だから腹が立っているのかもなと善逸は己を納得させながら、ドスドス足音を立てて部屋に向かった。こんな気持ちの時は不貞寝をするに限る。もうすぐ柱稽古も始まるのだ。ゆっくり惰眠を貪れるのもこれで最後かもしれない……なんて善逸が考えていたら、背後からドッと大きな音が鳴った。
その音は何もない空間に、突如として滝が生まれて激しい水流が地面にぶつかったのかと思えるくらいの凄まじい音で、善逸は慌てて振り返った。すると視界に、ゆらりと立ち上がりこちらに向かってくる炭治郎が映る。善逸は思わず足を止めてその姿に見入っていると、炭治郎は躊躇うことなく手を伸ばして、善逸の手首を掴んだ。
「好きだ。善逸」
赤銅色の瞳は決意に満ちている。この短時間で三回も見ることになろうとはと、善逸は三回目の胸の高鳴りの中、ぼんやり思った。