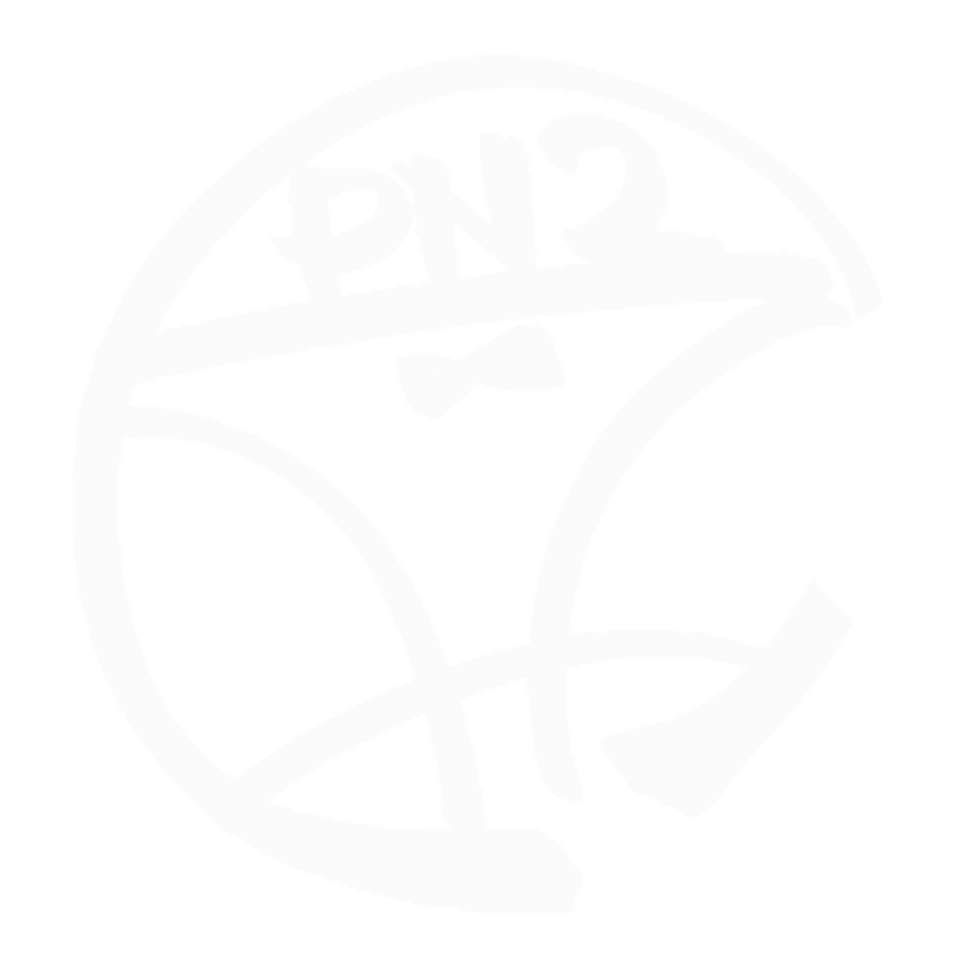大学生の善逸と高校生の炭治郎を見つめるお話です。ふんわり前世設定あり。前世の二人はブロマンスで終わってます。よって前世では双方ともに嫁がいました。二人には記憶がないのでほぼ関係ないです。
約19000字/現パロ
お天道様の下で見ればすくすくと花ひらいた蒲公英で、月の下で見れば雪の上で静かに座る福寿草。まあるい瞳はとろりと融けた蜂蜜で、その瞳の上にある眉毛は桜型。あまり大笑いはしないけど、控えめにこっそり笑うのが可愛いんだ。でもね、おとなしい子じゃない。泣き虫だけど好き嫌いははっきりしてて、誰も信じないことでも信じ抜ける強い心を持ってるんだ。
俺の好きな子。名前は我妻善逸。今度はずっと、ずっと、そばに居たいんだ。……内緒だよ?
****
絶対に声を掛ける。一目見た時から運命だと思った。蒲公英のような髪の毛も、蜂蜜色の瞳も、桜型の眉も夢想したままの姿だ。まさか大学でその姿を見かけるとは思いもしなかった。
初めての授業の日、広い講堂で姿を見つけた時、思わず叫んで駆け寄り、抱きしめたかった。けれどそんな事ができるわけもなく、どうやって近づくかを考える日々。考えすぎて何も前に進まないままゴールデンウイーク間近になってしまった。
このままでは大した接点が持てないまま、一年を過ごしてしまう。そうこうしている間に恋人でもできたら、俺は一生を後悔することになる。
怯むな。一歩を踏み出せ。何がなんでも仲良くなるんだ。諦めるな。俺が諦めたら、幸福な未来がない。辛いことがあった人生だった。決して全てが不幸だったとは思わない。けれど……心の底から欲しいと思った人と結ばれたいではないか。
俺は何度もシミュレーションし、練習した言葉を胸の中で繰り返しながら授業が終わったばかりでまだざわめいている教室を見渡す。蒲公英色の彼は俺の立っている場所から五つほど向こうのテーブルにいる。友人と楽しそうに喋っていて、まだ教室から出ては行かなそうだ。俺はその様子を伺いながら、頑張れ頑張れと己を鼓舞してとうとう声を上げた。
「……っ……我妻善逸君!」
「えっ、あっ……?はい……?」
俺が張り上げた声にびっくりしたのか、我妻君は俺を真っ直ぐ振り向いた。困惑した表情に気勢が削がれそうになるが負けるものかと眉間に力を入れる。すると彼はキョロキョロと辺りを見渡し、友達らしき子に背中を押されたのでその弾みのままこちらへとトコトコ歩いてくる。心配げな表情はハムスターやモルモットのようで……なるほどこれは可愛らしい。しかしそんな事を顔に出すわけにいかないので、俺は努めて冷静なふりを装いながら彼に言った。
「悪いが少し話がある。ついて来てくれ」
俺はドキンドキンと心臓を高鳴らしながら彼にそう言った。彼は涙目になりながら「え……お、俺……なにかしました……?」と訊いてくるがそれには答えられない。流石にこんなに人が多い場所では話はできない。俺は彼に荷物を持ってくるようにと言うと、教室のドアへと向かった。我妻君は慌てた様子でリュックを取りに行くと恐る恐るという様子で俺の元にくる。
「あ、あの……」
「こっちだ」
俺は三号館から出ると一号館の方へと向かった。彼は黙って俺についてくる。緊張で少し早足になってしまうな。俺は自分に落ち着け、落ち着けと言い聞かせながらエレベーターのボタンを押した。エレベーターは学生はあまり使わないので直ぐに来た。俺は中に入ると我妻君が乗ったのを確認してから閉めるボタンを押し、七階を押す。
「七階……?」
我妻君は不思議そうな声でそう言った。確かに入学したての彼ならばこんな所に来たことはないだろう。俺は七階に着くとエレベーターを降りて、誰も来ない場所へと歩いて行く。人があまりいない広い廊下でコツコツと足音が響き、目的地である部屋の鍵を開け、俺は彼を中に招いた。
「入って」
「……はい……」
我妻君はぎゅうっと上着の前を握りしめていた。緊張しているんだろう。分かる。俺もしている。今これから、彼に話すことはとんでもない事だと自覚があるからな。けれどこの話を俺はしないといけないし、彼を何としても口説き落とさねばならない。
俺は彼が部屋に入ったところで、扉に鍵を掛けた。がちゃんという音にハッとしたように我妻君が振り返る。その目には困惑が確かにある。分かる。けど俺も必死なんだ。絶対に逃したくない。どんな手を使っても、我妻善逸を逃したくない。
「……我妻君……」
「え、えと……な、なに……?」
俺は我妻君に一歩一歩と近づいた。彼は少し青い顔で後退るが、狭い部屋だ。すぐに机にぶつかる。俺はそれを好機と思い、手を伸ばし——彼の後ろにあった写真立てを手に取り彼に見せた。
「これ、今年高校三年生になる俺の息子なんだけど……」
「……は?」
「この子を見て、どう思う?」
俺は我妻君に自慢の息子の写真を押し付けた。我妻君は目に見えないが、クエスチョンマークを盛大に出しているだろう。しかし素直な性格なのか、マジマジと俺の息子の写真を見ている。ちなみにその写真は我妻君に見せる為にわざわざ撮った最新の息子の姿だ。
「……竈門教授によく似てらっしゃいますね?」
「他には?」
「えっ?……優しそうで……男前だと思います……?」
「本当に?ちなみに名前を当ててみて欲しいんだけど……」
「えっ!?」
「ヒント!ヒントをあげるから!俺の名前は炭十郎なんだけど、息子も俺の名前に似てるんだ!」
「……え、えーとぉ……?た、炭……?」
「炭!?」
「たーたー炭……じ?」
「炭治!?もう一声!!」
「……たんじーろー?」
「炭治郎!!そう!炭治郎なんだ!!すごいよ我妻君。よく分かったね!」
「……ははは……。……いや!めちゃくちゃ言わされたんですけど!?」
我妻君はそう言いながら俺に息子の写真を返して来た。うーんこの反応だと、我妻君は前世の記憶がないみたいだ。残念だ。記憶があったなら、あっという間に話が解決かと思ったんだが……仕方がない。
俺は息子の写真を撫でながら、次のフェーズに移ることを決める。我妻君は苦学生だ。それに住所を見たらアパートらしき名称だったから一人暮らしだろう。ならばつけ入る隙がある。
「時に我妻君。君をここに呼んだのは頼みごとがあるからなんだ」
「頼みごと?」
我妻君は来た時とは違ってリラックスした様子だった。随分と警戒心が薄い子だなと心配になる。大学の教授の中には少々、趣味がまずい人もいるからな。目を見張らせておこう。
「そうなんだ。実は……息子の炭治郎なんだが……進学をあまり考えていないみたいでね」
「はあ?就職希望ってことですか?」
「そうなんだ。けど、大学に興味がないわけじゃないんだ。実はうちは子沢山でね。下の子にお金をかけて欲しいと言って、進学しないと言い張っていて……」
「あらまあ、そうなんですか……。ええと、ひとまずは優しい心をお持ちの息子さんですね……」
我妻君は何と言うべきかと悩ましげな表情をしつつも、息子の考えをそれとなく受け止めるその姿勢に優しさを感じる。俺は彼の優しさに期待をかけながらもゆっくり頷いた。
「そうなんだ、優しい子なんだよ。けど俺は炭治郎にももっと自由な気持ちで学んで欲しいんだ。もちろん、やりたい仕事があるならそれでもいい。けれどそうでもないみたいでね。だったら、興味がある分野を学んでほしくて……こう思うのも私が大学で教鞭を取っているからかもしれないが」
「いや、いいと思います。竈門教授は息子さんの将来の道を増やしたいんですよね?」
「そうだね。うん。そうなんだ」
俺は溜息をつきながら顔を覆った。すると我妻君から明確に心配したような気配を感じる。うんうん。いい感じだ。前評判の通り、彼は大変に優しくて、お人好しのようだ。このまま……一気に仕留めよう。
「そこで我妻君。君にお願いがあるんだが……」
「俺に?」
「君は奨学金で大学に通っていたね?」
「何で知ってるんですか」
「その辺は気にしないでくれ。教授をしていると話が耳に入ってくるものなんだ」
「はあ……」
我妻君は胡乱げな視線を向けてきながらも、それ以上は突っ込まずに俺の話の続きを待っているようだ。なるほどお人好し。怖いな。やっぱりよくよく見ておかねばなるまい。再度そう思いながら、俺は我妻君に今日の本題を切り出すことにした。この交渉を必ずや成功させねばならない。これは、我が愛息の幸せな未来を左右する大きな一歩なのだから。
「我妻君。……俺の息子の……炭治郎の家庭教師を頼まれてくれないだろうか?」
心臓が飛び出るのではないかというほど緊張している。自分ごとならいいが、愛息の為の行動だ。緊張しないわけがない。手が震えるのではないかというのを呼吸で押さえ込みながら、俺は我妻君の反応を待った。
「……家庭教師?」
「息子が学ぶことに前向きになってくれる切っ掛けが欲しくてね。大学生と接する機会があれば息子も考え方に幅がでるかもしれないだろう?」
「……うーん……」
「まずは週二回でいい!二時間で五千円!!夕飯は我が家で食べていってくれ!」
「二時間で五千円!?さらに夕食付き!?」
「どうかな?交通費も出そう!」
「やります!!」
我妻君は目を輝かせると俺の手をガシッと掴んだ。その瞬間に、グーっとお腹の音が聞こえてくる。いつもお腹空かせてるのかな?いや、今は昼休みだから仕方がないだろう。とりあえず我が家でお腹いっぱいになって欲しい。
「いつなら都合がいいかな?」
「夜ならいつでも平気です!」
「じゃあ今夜から頼もう」
「えっ……早っ……」
我妻君はびっくりしていたが、こくんと頷いた。我妻君を早く炭治郎に会わせてあげたい。善は急げというからな。……駄洒落じゃないぞ?
****
「ただいま。こちらは我妻善逸君。今年、入学して来た子だよ」
「こ、こんばんは〜……」
「はあ……初めまして。いらっしゃいませ。どうぞ上がってください」
家族がポカンとする中、俺は強引に我妻君の背中を押して家に上がらせた。我妻君は間違いなく、いま引いている。困惑しきりという顔で、まあそれも仕方がないだろう。うちの長男の家庭教師にと望まれて家に来たはいいものの、出迎えた家の者たちが一様にポカーンとしているのだからな。我妻君は通されたリビングのソファに腰掛けながら、隣に座った俺を疑う目で見てきた。突き刺さるその視線は痛いが……甘んじて受けよう。
「あの、竈門教授?」
「なにかな?」
「ご家族の温度が……」
「うん。まあ、家庭教師を雇うとかなんの相談もしてないからな」
「ええ!?やっぱり!?」
我妻君は大きな声をあげたが、それをすぐに止めるように口を塞いだ。私の妻や子供達は不思議そうに我妻君を見ていて……特に長男の炭治郎と次男の竹雄は警戒しているようだった。それはそうだろう。俺が生徒を家に連れてきたことなんて一回もないし、それに長女の禰豆子は高校生だ。若い男をあまり近づけたくないのだろう。
「お茶です。ごめんなさい。急だったのでお煎餅くらいしかなくて……」
「いえいえ!おかまないなく!」
「あ、母さん。俺が持って行くよ」
キッチンから出てこようとした妻の葵枝を止めて、炭治郎がお盆を受け取った。そして我妻さんを不思議そうに見ながら、ソファの前にあるローテーブルにお茶を置く。
「どうぞ」
「えーと、ありがとうございます……」
我妻君はそわそわして炭治郎を見ている。その様子が気になったのか、炭治郎もまた我妻さんの顔を見返す。よしっ!いい感じ(?)に対面できたな!ここで説明しよう。
「炭治郎、実は我妻君を今日連れてきたのは、お前の家庭教師を頼んだからなんだ」
「え?家庭教師?」
「……そ、そーなんです……」
我妻君は手をもじもじさせながらそう言った。炭治郎は我妻君をジロジロと見て、そして困惑した表情で俺を振り返る。
「父さん、家庭教師ってどういうことだ?」
炭治郎の顔も声もやや険しい。周りにいる家族も長男の多少の怒りにオロオロとし始めた。妻の葵枝だけは成程というように頷きこちらを見つめているから、俺が現役大学生を家に連れてきた理由が分かったのだろう。流石だ。
「お前も高校三年生だろう?炭治郎は努力家だからクラス制の塾も向くと思うけど……容量はあまりいいタイプとは言えないからな。家庭教師の個別指導もいいと思ったんだ」
「いや、そうじゃなくて!!」
炭治郎は声を荒げたがその先は口を噤んだ。まだ弟や妹には大学進学しないことを公言していないからだろう。その点からも、まだ炭治郎が就職を絶対すると決めきれていないのが分かる。よしよし。これなら我妻君の家庭教師を任せる件は大丈夫そうだな。
「我妻君は受験終えたばかりの一年生で炭治郎と一つしか歳も変わらない。気軽に勉強のことが聞けるよ」
「いや、だから……」
「さあさあ。炭治郎、我妻君を自分の部屋に案内してあげなさい。ひとまず食事の用意ができるまでは世間話でも勉強の話でもさてみるといい。母さん、我妻君の分の食事も用意できるかな?できないなら何か出前でも取ろう」
俺はそう言って立ち上がった我妻君と戸惑う炭治郎の背中を押した。二人はお互いの顔をチラリと見合い……我妻君は困ったように笑い、炭治郎は溜息をつくと先導するように歩き出す。俺は耳を澄ませながら、二人が階段を上がって行く足音を聴き遂げると、ハアと肩から力を抜いて他の子供達を見渡す。
「炭治郎は大事な時期だから……邪魔しないようしなさい」
「はあい」
子供達は良い子の返事をするとあまり音を立てないようにすべきと判断したのか、そろそろと歩きだすとリビングのテレビをつけた。音量が控えめにされるのが可愛らしい。
俺は葵枝に出前とるかどうか確認しようとキッチンへと向かった。するとそこには既に追加の食事の支度を始めている妻と長女の姿がある。事前に我妻君を招くことを伝えておければ良かったのだが……声をかけた今日、そのままの勢いで連れてきたからな。でも日を改めて怖気付かれたら堪ったものじゃない。一刻も早く炭治郎に引き合わせたかったんだ。
「葵枝、禰󠄀豆子、急なことですまないな」
「いいのよ。あなたがそういう事するなんて初めてだもの。……今日じゃなければダメだったんでしょう?」
優しく微笑む葵枝に俺は頭が上がらないなと思いながら頷いた。ほんの少しのヒントだけで俺の心のうちを察してくれるのだから、本当に良くできた人だと思う。俺には勿体ないとよく思うが、他の誰に譲る気もないからなあ。
「……お兄ちゃん、大学行く気になりそう?」
こそりとそう言った禰󠄀豆子に、この子もまた聡いなと笑った。禰󠄀豆子は多分、炭治郎が考えていることを察しているのだろう。俺は禰󠄀豆子の頭を撫でると安心させるように言った。
「我妻君に任せておけばきっと大丈夫だよ」
「……良かった」
禰󠄀豆子はそう言って鼻歌を歌いながらゴボウと人参を冷蔵庫から取り出す。人数が増えたから、品数を増やすのだろう。さて、俺はどうしようかな、何か手伝おうかなと思いながらも上がっていった二人が気になって仕方がない。炭治郎は我妻君を少し警戒しているみたいだけど……ちゃんと上手くいっているだろうか?
今更ながら、数奇な事だと思う。俺、竈門炭十郎の人生は実に不思議な事で満ち溢れていた。何がかと言えば、俺には実は前世の記憶というものがある。
俺は前世で炭焼き小屋を営んでいて、先祖代々引き継いできたヒノカミカグラというものを習得していた。俺は少々、得意な体質で……強靭でありながらも病弱であった。熊を一撃で殺せるが、病んでいく体には勝つことができず、妻と六人の子供を残して若くして死んだ。そして……死後の世界からその後の家族の顛末を見守った。目を覆いたくなる悲惨なことも、慟哭したくなる辛いこともたくさんある顛末だった。
妻と多くの子が死に、生き残った長男と長女も苦難の道を歩き……しかし二人は全てにケリをつけて幸せを見つけた。長男は長生きをできなかったけれど、大切な人々に囲まれて看取られ、幸福そうにその生涯を閉じ、長女もまた、兄が信じた人に託されて幸せに生き、天命を全うしたのだ。
前世を覚えているなんて実に数奇だろう。しかし、不思議なことはそれだけではない。俺は事実とも夢とも判別つかない前世の記憶を、不思議なものだとあまり気にせず成長して、そして年頃になった時に衝撃を受けた。その理由は、前世の妻である葵枝と出会ったからだ。
そこから俺の人生はあれよあれよと変わっていく。葵枝と結婚をし、子供が産まれたと思えば間違いなく前世での長男……炭治郎であった。俺は産まれてきた我が子にもう一度炭治郎と名付けた。炭治郎が元気に走り回り、おしゃべりを楽しそうにするようになった頃、今度は前世の長女の禰󠄀豆子が産まれた。俺はまた、その子に同じ名前をつけて……「これは六人兄妹になるのでは?」と胸を躍らせる。
今世では鬼はもういない。俺も病弱ではない。今度こそ、家族で幸せになれるのではと期待に胸を膨らませていたが、それでも俺はまだ、前世の記憶を本物かどうか疑っていた。何しろ信じられる証拠がなく、全ては俺の胸ひとつだからだ。単に自分が実は空想好きだという可能性もあった。しかしそれは、長男の炭治郎が七歳の時に払拭された。炭治郎が密やかに、俺にだけ教えるから内緒だよと言いながら一つの話を披露してくれたからだ。
「俺ね。前にね、好きな子がいたんだ」
「好きな子?保育園で?」
「違うよ。俺が生まれてくるよりずっと前。俺は桃太郎みたいに鬼退治をしてたんだ。禰󠄀豆子を守るためにね」
炭治郎はそう言って悪戯っ子のように笑った。俺は炭治郎の生まれるよりも前の昔話とやらに心臓が痛くなる。もしや炭治郎にも前世の記憶がと思ったが、炭治郎は嬉しそうに楽しそうに好きな子とやらを教えてくれた。
「俺の好きな子はね、お天道様の下で見ればすくすくと花ひらいた蒲公英で、月の下で見れば雪の上で静かに座る福寿草。まあるい瞳はとろりと融けた蜂蜜で、その瞳の上にある眉毛は桜型。あまり大笑いはしないけど、控えめにこっそり笑うのが可愛いんだ。でもね、おとなしい子じゃない。泣き虫だけど好き嫌いははっきりしてて、誰も信じないことでも信じ抜ける強い心を持ってるんだ」
流暢に、好きな子を褒めちぎる炭治郎に俺は首を傾げた。俺の記憶が確かなら……その子は炭治郎の親友だった筈だ。炭治郎のことを誰よりも信じて、いつだって禰󠄀豆子の味方で守ってくれた子だ。俺も家族も彼が禰󠄀豆子を守る瞬間は手に汗握って応援をしたものだ。あの世で。
「えーと……男の子?」
「そうだよ。男の子。俺は好きだったけど……その子は女の子が好きだったから。だから禰󠄀豆子にあげちゃった」
あげちゃった、なんて炭治郎らしくない言い回しだ。しかし今の炭治郎は七歳だからな。俺は子供らしい物言いをするけれど、大人のように寂しそうに笑う炭治郎の姿に目眩がしそうだ。そうなのか炭治郎。お前、あの子のこと好きだったのか。
「俺の好きな子。名前は我妻善逸。今度はずっと、ずっと、そばに居たいんだ。……内緒だよ?」
炭治郎はそう言って人差し指を口元に立てた。そうして俺が何も言えないでいる間に、「遊びに行ってくる!」と言って駆けて行ってしまった。俺は突然にもたらされた新事実に、茫然としながら我妻善逸君の姿を思い返す。知らなかった。炭治郎はそうだったのか。
炭治郎が禰󠄀豆子の為に、仲間達の為に、己を殺して戦っていたのを俺は知っている。俺はそれを痛ましく思いながらも頑張れと応援していた。けれど我妻君は——。
「炭治郎の心をよく分かっていた子だなぁ」
我妻君は炭治郎に生きる事を、禰󠄀豆子と家族が待つ家に帰る事を諦めるなと叫んでいた。その事がどれだけ、炭治郎に響き、そして現世への縁を繋げただろうか。俺は生まれ変わった炭治郎もやはり我妻君に会いたいのだなと、何とかして会わせてあげたいなと思っていたが……。
「あがつまぜんいつくん?……そんな子は学校にいないよ?」
「えっ」
なんと炭治郎は八歳の誕生日を迎えたら何故か我妻君のことをすっかり忘れていたのだ。己が桃太郎のように鬼退治をしていたことも忘れ去っていた。それがなんなのか、考えても俺には分からない。とにかく炭治郎は我妻君のことを覚えていない。我妻君もずっと傍にいたいと言ったことも覚えていない。俺は……どうしたらいいのだろうか。
そう思って年月が経ち、今日という日を迎えた。我妻君を講堂の教壇の上から見つけた時は感動で震えたものだ。幸い、炭治郎は未だに彼女がいない。中学、高校とそれなりにモテて、告白された経験もあるようだが、決め手に欠けるというか気乗りがしないと誰とも付き合ったことはない。いやまあ、さりげなく「どうしたら良いかな?」と相談された時に「この人が運命だと思わない限り、付き合わない方が良いと思うぞ」と金髪の彼を思いながら助言したことがあるんだけどな。
さて、それにしても……二人の様子は結局はどうなんだ?ちゃんとお喋りしてるか?相互理解を深めているか?お互いの好きなものや趣味の話をしているか?勉強なんてどうでもいいから、お互いのことを深く知り合って仲良くして欲しい!!
「炭十郎さん。そんなに心配しなくても大丈夫ですよ」
「あ、ああ……そうだな」
俺はソワソワしながら廊下の方を見てしまう。でも葵枝のいうように俺がここでヤキモキしていてもな……。よし、少し落ち着こう。そうだお茶を部屋に持っていってあげよう。俺は様子を見る口実が出来たとお茶を淹れ直す為に茶筒を開けたところで上の階からドタバタと駆けてくる足音が聞こえ、「ぜーんーいーつ!こらーっ!!待てー!!」と炭治郎の荒げた声が追いかけて来る。そして「ごめんごめん!許して炭治郎〜!」という我妻君の声が玄関の方へと向い——ガチャンとドアが開いて閉まる音が二回響く。外を走る足音がだんだん遠ざかって行くな……?俺は茶筒を持ったまま玄関に行くと、炭治郎と我妻君の靴がないのを確認した。
「えっ。あの短い間にふざけ合って出てったのか?」
俺はポカンとして腕時計を見た。そして二階の方を仰ぎ見て、もう一度時計を確認する。いやいや、出会って三十分も経ってないぞ?二人ともお互いを呼び捨てにしてなかったか?
俺はお茶どうしようと思うが、二人ともいないのだからしょうがない。俺は茶筒を元の場所に戻しながらリビングに行った。葵枝も禰󠄀豆子も去っていった二人に合わせてか、夕飯の仕上げをやめてしまったしな。ああ、でも遅くならないように炭治郎にメッセージ入れておくべきか?
そんな風に思っていると十分くらい経ったところで二人が戻ってきた。楽しそうに笑い合いながら、コンビニ袋をそれぞれ持っている。炭治郎が「ただいまー。アイス買ってきたぞ」と箱アイスを出し、我妻君は「適当にジュース買ってきました」とテーブルに乗せる。
二人はそれだけ置くと手を洗いに行ったのだろうか、二人でニコニコ楽しそうに漫画の話をしながらリビングを出ていった。俺は信じられないくらいあっという間に縮まった距離感にオロオロしていたが、葵枝と禰󠄀豆子は気にならないのか、夕飯の仕上げを始める。……え?これ、俺がおかしいのか?若い子って馴染むのあんなに早いものなのか?
俺は結局、その辺りは分からないまま和やかな夕食の席を堪能した。流石に弟と妹がいるからか炭治郎も我妻君も先ほどより大人しかったが、食事が済んだらさっさと二人で食器を片付けて上に上がっていってしまった。食後のお喋りとか……リビングでしないのか?もう少し二人がどんな感じなのか観察したかったんだけどな。
「炭治郎、我妻君と仲良くなれたみたいで良かったわね」
「……うん。そうだな」
俺は妻の言葉に頷きながら見えない二階を仰ぎ見た。一体、炭治郎の部屋で何が起こったのだろう。いや、でも考えるだけ無駄か。何しろ彼は炭治郎の運命の人(予定)なのだから。
****
予定調和なんてものがどれほどあるのだろうか。どれだけ足掻いても、人の心なんてものは当人のもので、俺にできることは切っ掛けを与えることしかできない。それは重々承知であった。上手くいかなくてもそれはそれて仕方がないのだと。飲み込む覚悟はあった。けれど実際にその状況に陥ると、思ったより堪えるのだ。
「ひぁぁぁ〜♡ 禰󠄀豆子ちゃん今日も可愛いねぇ〜♡」
「もう、やだ。善逸さんったら!またそんなこと言って」
「いやいや、だって本当のことだもん!俺、禰󠄀豆子ちゃんに会う度に可愛さで目がやられそうだよ〜♡」
そう言ってクネクネと身を捩る善逸君を俺は微妙な顔で見た。禰󠄀豆子は確かに可愛い自慢の娘だが、男がそれを褒めちぎっているのは嬉しいが複雑な気持ちになる。男親としてのヤキモチだろうか?
「善逸、ここが分からないんだが……」
「んあ?ああ、はいはい。ここね。これはえーっと……公式がですね……」
我妻君は炭治郎のテキストを隣から覗き込んでいる。ついさっきまで禰󠄀豆子を褒めていた際の表情から打って変わって平坦だ。温度差が凄い。まあ、つねに溶けた餅のようにデロデロしているのはまずいだろうが。俺はリビングで炭治郎と善逸君が頬がくっつきそうな程に顔を寄せ合って勉強をしているのを少しホッとして見つめていたが……善逸君は教え終わるとすぐに目の前にいる禰󠄀豆子を眺め始めてしまう。それが……少しどころでなく不安だ。
「……失敗したかもしれない……」
「何がですか?」
「あ、いや。なんでもない。仕事のことだよ」
ダイニングテーブルに座っていた俺に、葵枝が朝食後の珈琲を淹れてくれた。それをありがたく受け取りながら、再びリビングで勉強会をしている三人を見やる。今日は休日だというのに、善逸君はわざわざ我が家に遊びに来て炭治郎と禰󠄀豆子に勉強を教えているらしい。善逸君は普段、平日の夜に炭治郎の家庭教師をしているが……時たまこうして昼間にうちに来ることもある。給料を支払うと言ったが、「遊びに来てるついでに教えてるだけなので」と断られてしまった。確かに長居をするから計算すると大変なことになってしまう。支払うことももちろん出来るが、善逸君が気軽に遊びに来れないのも困るので……お言葉に甘えさせてもらっている。
我妻君を我が家に連れてきて炭治郎に紹介してから二ヶ月以上が経った。毎回毎回、二人の状態を把握できているわけではないが……それなりに仲良くやっているようだ。あまり突き回すのも良くないかと、基本は放ってあるのだが、進学しないと言って塾代や家庭教師代は無駄だとばかりの頑なな炭治郎はというと、どういう心境の変化なのか何も言ってこずに勉強をしている。進学を決めたかどうかについては聞いてはいないが、善逸君が来ない日も受験生のようにしっかり机に向かって勉強をしているようなので、丸切り受験を見限ったこともなさそうだった。それにしても……。
「はぁ……可愛い……天使だ……♡」
問題はこれである。炭治郎と問題なく仲良くなり、友達になった善逸君であるが……本人はなんと禰󠄀豆子に熱をあげているのだ。これはよく考えれば意外なことではない。そもそも善逸君は前世の頃を鑑みても異性が恋愛対象だった。そして禰󠄀豆子は可愛い。花子も勿論可愛いが、善逸君が真っ当であるならば歳の近い禰󠄀豆子に惹かれるのは無理もないことだ。
「……いや、そもそも前提が違うのか……」
「?」
三人を眺めながらぶつぶつ言う俺を葵枝は放っておいてくれている。まだ俺の考えはまとまってないからありがたい。そもそも善逸君と禰󠄀豆子は前世で夫婦であった。時代として恋愛結婚が主流ではなく、縁があって年頃の男女であれば結婚の話が上がり、周囲に纏められてしまうことも普通にあった時代だ。同じ屋根の下で暮らしていた善逸君と禰󠄀豆子が結婚するのも不思議なことではない。加えて禰󠄀豆子の兄たる炭治郎は自らの寿命を悟っていた。となれば家長として禰󠄀豆子を一番信頼できる相手に託すこともなんらおかしくない。禰󠄀豆子がどうなろうと、必ず最後まで諦めずに守ってくれる者といえば、善逸君しかいないのは分かりきっていたことだ。
俺は冷静に分析しつつ、珈琲を口に含む。いつもより、香りよりも苦味が先立つのは俺の心が申し訳なさを抱えているからだろうか。俺は忘れていたのだ。炭治郎に善逸君を逃さぬように捕まえて欲しくて、すっかりと忘れていたが……善逸君は禰󠄀豆子の前世での夫であった。その二人が出会えば恋に発展する可能性がなきにしもあらずだったのだ。
「善逸、今度はここ教えてくれ」
「はいはい」
「あ……善逸さん。次は私の方の、ここの問題を……」
「えっ!分からないところあった!?どれどれ〜?」
「善逸、俺が先じゃないのか?」
「野郎は後回しだよ。今日の俺はボランティアで友達の勉強みてるだけだからね〜」
善逸君は基本的に炭治郎よりも禰󠄀豆子を優先している。勿論、家庭教師の時は話は別だが、炭治郎の友人として我が家を訪れている時はなによりも我が家の女性陣を優先している。それは別に構わないのだが……炭治郎は目の前で禰󠄀豆子を取るような態度の善逸君をどう思っているんだろうか。……うん。普通だな。一旦、休憩とばかりに伸びをしてニコニコと善逸君と禰󠄀豆子を見ているな。……これ、大丈夫なんだろうか。
俺は炭治郎が七歳の時に教えてくれた秘密を反芻し、頭を捻る。炭治郎は今度はずっと一緒にいたいと話していたが……そういえば恋仲になりたいとか、添い遂げたいとは言ってなかった気がする。もしかして長生きして友人としてでも側にいられたら本望なのだろうか。けれど禰󠄀豆子にあげちゃったと表現していたのだから、本音としてはあげたくなかったのだろう。それが炭治郎にとって一番心が穏やかになる選択であるのは間違いないが……どこかで我慢をした筈だ。その我慢をどうか今世では取り払って欲しい。俺はそう望むけれど……うん。炭治郎、普通だな。丸切り善逸君に恋愛感情とか持ってなさそうだな。
ああー……そうなのか。そういうものなのか。いやまあ、前世の話というのも分かるし、今世では確かに劇的で印象的な出来事も二人には起きていないのだろうけど……そうなのか。
俺は炭治郎と善逸君が真っ当な友情を育んでいるのにやや不満だ。前世で炭治郎が善逸君に想いを寄せていたことを知ってから思い返してみると二人はなかなかにいい関係であった気がするんだが。距離も近ければ、見たことはないが……念友であってもおかしくないほどの親密さだった。けど今回はそれはない。でも距離感はやはり似ているから、前世でも普通に友情だけだったのかもしれない。炭治郎、よく我慢したな。
「……ままならないな」
俺はそう言って溜息をつくと、そろそろ仕事をするかと立ち上がった。今日は休みだが、少し纏めたい資料があるんだ。俺は葵枝に淹れてもらった珈琲を片手に持つと善逸君に声を掛ける。
「それじゃあ善逸君。また」
「あ、はい。お疲れ様です」
「今日は炭治郎のこと頼んだよ」
「はーい。了解です」
「父さん、俺もう高校三年生なんだけど……」
炭治郎が不満そうに口を尖らせるのに幼さを感じる。さっきまで前世の、十三で大人にならざる得なかった炭治郎を思い出していたかもしれない。俺は十八になっても子供っぽさが抜けない炭治郎に嬉しくなって笑うとリビングまで行って頭を撫でた。
「善逸君の家ではしゃぎ過ぎないようにな」
「分かってるよ。大丈夫」
俺は炭治郎の返事に満足すると一階奥の書斎に向かう。炭治郎は今日、午後から善逸君と遊びに行って、その後は二人で善逸君の家に泊まるらしい。期末テストが終わったから、羽を伸ばすというのだ。炭治郎が弟妹から離れて友達の家にお泊まりだなんて、いい変化だと思う。炭治郎は昔から弟と妹ばかりを優先していたからな。
例え炭治郎と善逸君の間に恋が生まれなかったとしても、善逸君が禰󠄀豆子を選んだとしても、この出会いは二人にとって素晴らしいものだったに違いない。俺はそう納得すると、経過に一喜一憂するのはやめようと頷き、書斎の扉を潜った。
……これがだいたい、三十時間くらい前の出来事だ。日曜日の今日は善逸君がバイトだからと早朝に帰ってきた炭治郎は、顔を真っ赤にさせて俺の前に立っている。そしてどうしたと訊いた俺にしどろもどろに言ったのだ。
「……と、父さんは母さんを好きだなって、一番の人だなって思ったのはどんな時だった?」
えっ。なんでそんなことを今聞くんだ。炭治郎、お前……さっきまで善逸君の家に泊まって帰ってきたばっかりだろう?玄関開けて挨拶もそこそこ、一目散にここに来ただろう?なんだその表情は。初恋を知った小学生みたいじゃないか。
「……えーと、母さんを好きだと思った時か」
俺には前世の記憶があるからな。今世は葵枝を見た瞬間から好きだったな。えーと、前世前世は……。
「そうだなぁ。最初から素敵な人だと思っていたが……やっぱり触れたいと、どうしてもこの人に触れてみたいと強く思った時に気持ちを自覚したよ」
「………っ……!」
炭治郎は口を一文字にすると胸の辺りのシャツを鷲掴んだ。その表情はまさに恋をしていますというもので……えっ?それ相手って善逸君?昨日の今日で何があった?昨日の晩にどんなことが起きたんだ?
「炭治郎。……善逸君には聞いてみたか?」
「えっ!?善逸に!?」
善逸君の名前が出た瞬間に、炭治郎の顔色が一気に朱に染まった。間違いない。確定だ。炭治郎は善逸君の家で何かあって、そして恋を知ったのだろう。恋は突然とはいうが……本当に突然だな。どうしてそうなったのか凄く知りたい。だって昨日の朝は普通の友情だったじゃないか。
「……ぜ、善逸には聞けないよ……ありがとう、父さん」
炭治郎はそう言って口元を腕で隠しながら書斎から出て行った。炭治郎、なんということだ。これ、まずくないだろうか。善逸君は禰󠄀豆子に執心しているのに、炭治郎が恋に目覚めたぞ。失恋してしまうじゃないか。そう思って俺は頭が痛む。
……これが日曜日の話だ。そして本日、月曜日。講義室の中で物憂げに窓の外を見つめる善逸君の姿がある。いや、君……そういう顔もできるのか。教壇の上からたくさんの学生を見てきた俺には分かる。善逸君のその表情は恋に悩むものの顔だ。その顔をしていて授業を聞いてなくて後々泣く生徒がいるからよく知っている。恋煩いの顔だ。
ああ。予定調和とは。本当に神はこの世にいるのかもしれない。
****
人の恋路を邪魔するものは馬に蹴られて死んでしまえと言うが、人の恋路を応援するものはどうなのだろうか。人と人との関係性なんて多角的なものだから、炭治郎と善逸君の恋路を応援していたとしても、どこかの誰かからすれば恋路を邪魔されていると感じるのかもしれない。
俺はカフェテリアで女の子とお昼を食べている善逸君の姿を見かけて、声をかけるかどうか迷った。彼の近頃の憂い顔は間違いなく恋煩いだと思うのだが、それは俺の希望が多分に含まれているかもしれない。それに恋煩いだとしても相手が炭治郎とは限らない。炭治郎の方は確実に善逸君が相手だろうが。
経過で一喜一憂するのはやめようと思ったばかりなのに、どうにも実践ができない。何しろ我が子の恋の自覚を目の当たりにしてしまったのだ。その初々しくも一生懸命さを感じる恋が是非とも実ってくれればと願ってしまうのは親心だろう。そう思いながら今日も俺は善逸君をそれとなく観察してしまうのだ。
観察と言ってもストーカーのようにはしていない。移動先にいないかなとつい姿を探し、見かけたら少々様子を伺う程度だ。一人の生徒を追いかけ回しているなんて醜聞が出たら仕事を失うからな。本当に見かけたら程度なわけなんだが……そう思ってカフェテリアで珈琲を買い、テーブルを借りて愛妻弁当を広げていると善逸君がパッとこちら見た。それに合わせて女の子も振り返る。派手な格好をしているが、随分と美人な子だ。でも大学では見かけないような……人の顔を覚えるのは職業柄得意な筈なんだが。
そんなことを思いながら笑って手をあげると、善逸君は女の子に二、三言なにかを告げて立ち上がる。そしてこっちに向かってくるので俺はついつい居住まいを正した。弁当の蓋を閉めたほうがいいだろうかと迷ってるうちに善逸君が俺の目の前にくる。
「おはようございます、竈門教授」
「おはよう、我妻君」
「……あの、少し話いいですか?」
「構わないよ」
俺は深刻そうな表情をしている善逸君に嫌な予感を感じたが、平静を装って前の席を勧めた。やはり教師が座っているからか、周囲のテーブルは少し空いている。二つ離れたテーブルでは生徒達がにこやかに談笑しているが……このテーブルの空気は少し重いな。俺は弁当の蓋をやはり閉めるかと思って持ち上げたが、善逸君は「召し上がってください」と言ってくれたのでありがたく食事をさせてもらうことにした。
「話とはなにかな?」
「……あの、炭治郎君の家庭教師の件なんですけど……」
「うん」
「……今週いっぱいで辞めさせてもらえないでしょうか」
「うん!?」
「急なお話なのは分かってます。でも炭治郎君も勉強に対して前向きだし……進学のことも本気で考えてるみたいなので、刺激を与えるっていう俺の役目はもう終わってかなって思っていて……」
落ち着け。落ち着くんだ炭十郎。取り乱すな。まずはさりげなく引き止めるんだ。
「ええと、炭治郎が勉強に前向きになったとは俺も感じているよ。その点は本当に我妻君に感謝している。我妻君に炭治郎を任せて本当に正解だったと思っているんだ」
「……」
「それで、ええと。炭治郎も我妻君と相性が良いようだし、俺としては刺激を与える役目を終えたとしても引き続き家庭教師をして欲しいと思っているんだが……」
「すみません」
まさかの『すみません』か。迷わず被せてきたな。そうだ。思い出してきたぞ。確か善逸君は前世でも判断が迅速な子だったな?迷っているような表情をみせているけど完全に彼の中では答えが出てないか?
「ちなみに、どうして家庭教師を続けられないのだろうか?理由を聞かせてもらえないだろうか?」
もう少し引き止める取っ掛かりが欲しいと尋ねれば、善逸君は眉毛を八の字にしながらも俺を真っ直ぐに見つめた。その瞳には迷いがなくて、俺は冷や汗がでる。
「家庭教師として俺に限界を感じました。俺には炭治郎を正しく導く自信がないんです」
本当にこの前の土曜日何があったんだ?ちなみに今は火曜日です。まだ土曜日から三日しか経っていないんだが……。
「正しいとか正しくないとか、そういうものはすぐに結果が分からないものだが、炭治郎はこの前の期末テストは今までで一番良くできたと喜んで話していた。炭治郎が前向きに自信を持ってテストに望めたのは我妻君の指導が正しかったからだろう?」
「炭治郎は元から出来るやつですよ……。本気になれば、何だって出来る。俺なんて居なくても大丈夫です。受験も問題ない。絶対にどこだって合格します。あいつは凄い奴だから」
前半は語調が弱いのに、後半ははっきり強く言うな。そんなに炭治郎を信頼してくれているのか。いやでも善逸君。炭治郎が頑張ったのは君がそうして全幅の信頼をしてくれるからこそで、あの子はそれに応えたかったんだと思うけれど……。
「あの、我妻君。君の気持ちは分かったよ。自分の指導に自信がないってことだね?」
「……はい」
「なるほど。そうか。俺も教師の端くれだ。生徒をどうしたら正しく導けるかについては幾度も考えた事がある。君の悩みは至極真っ当だ。けどもし、君が炭治郎を少しでも想ってくれるならこのまま家庭教師を続けてもらえないだろうか?もうすぐ夏休みに入る。受験生にとったら大事な時期だ。塾に通うよりも炭治郎はやはり家庭教師の方がいいと思うし、俺もすぐに信頼できる新たな家庭教師を探すのは難しいところがある」
ドキドキしながら延長を願い出てみるが、善逸君は戸惑う様子もなく真っ直ぐ俺を見ている。若者にこんなに緊張させられるのは久しぶりだ。やはりこれは息子の恋人候補という点が大きいんだろう。俺の失敗で折角繋がった縁が切れるなんて耐えられない。
「はい。俺も炭治郎は家庭教師の方が向くと思ってます。なので、一応次の家庭教師を引き受けてくれる人を探してあるんですけど……二年生の村田って名前で、俺の高校時代の先輩です。教えるの上手いですし、人当たりも良くて優しいので炭治郎とも相性いいと思います」
「仕事が早い……」
俺は善逸君の手際の良さに項垂れたい。なぜだ。なぜそんなに炭治郎の家庭教師を辞めたいんだ。いい感じじゃなかったのか?もしかしてあの憂鬱そうな表情は恋煩いではなく、炭治郎からの好意に戸惑っているのか?迷惑なのか?
「……我妻君は……もしかして炭治郎が嫌いだったりしたのかな?」
少し泣きそうになりつつ、恨みがましくそう言えば善逸君はびっくりした顔を見せた。そしてぶんぶんと勢いよく頭を振ると「まさか!!」と否定する。その心底あり得ないという表情に俺はホッとする。炭治郎を嫌いなわけではないんだな。良かった。
「炭治郎は優しいし、気が合うし!一緒にいると楽しいですよ!俺、こんなに誰かと過ごして落ち着くなんてこと……今まであんまりなかったから驚いたくらいで……」
「……うん?」
「俺、炭治郎のこと好きです。……だからこそ、もっと成績を伸ばして欲しいし、いい人生を歩んで欲しいんです」
「うん」
「でもそれをするには俺は炭治郎の足を引っ張っちまう。……俺、炭治郎の邪魔したくないんです。俺、炭治郎のいい友達でいたいから」
理論がよく分からないな?炭治郎を大切に想ってくれているのは分かった。その気持ちがどんな感情からなのかは分からないが、一般的な友情よりも重いような……?どうなんだ?親友なら普通だろうか。
「なるほど。炭治郎を大事に思ってくれるのは分かったよ」
「はい」
「……えーと……」
「明日、村田さんをご紹介します」
「……うん……ありがとう」
「いえ。お時間取らせてすみません。失礼します……」
善逸君はそう言って頭を下げるとカフェテリアの出口へと向かっていく。俺の目の前にある弁当は手付かずのままだが、今はちょっと食べる気になれないと蓋を閉めた。次の講義が終わってから食べよう。
俺はしまったなと思いながら、テーブルの上を片付けて立ち上がった。完全に善逸君が家庭教師を辞めることで話が終わってしまったぞ。家庭教師を辞めてしまったら、炭治郎との接点がなくなってしまう。
「ねぇ、昨日のドラマ見た?」
「どれよ?」
「あれあれ!家庭教師と男子高校生のやつ!」
「あーあれ?見た見た!とうとう両片思いになったのに、家庭教師の女が怖気づいて辞めるとか言い出したよねー。意気地なしって笑った」
「えー!?家庭教師としての葛藤じゃん!教え子を誘惑した結果になったって悩んでるのがいいんじゃん!」
元気にお喋りしながら通り過ぎた女子生徒達の会話に、俺はなるほどと頷く。そうか。今のままだともし炭治郎と上手くいった場合、善逸君は教え子を誘惑したことになるのか……?俺としてはそれを狙ったわけなんだがな。
「……」
俺はちょっと迷ってから炭治郎宛にメッセージを送った。内容は簡潔に『善逸君が家庭教師をするのは諸事情で今週中までになった。たぶん、来週からは他の人を呼ぶことになる』というものだ。炭治郎は当事者なんだから知る権利はあるだろう。善逸君がうちに家庭教師に来るのは今日と、金曜日の予定だ。その二回でどうにか炭治郎には足掻いて欲しい。
そう思って俺は大きく溜息をつく。親として情けないが出来ることはこれくらいしかない。出来れば善逸君を引き止めたかったが……彼の意思は固そうだった。あれをもし変えられるとしたら、きっとそれは炭治郎だけなんだろう。
****
「あ、竈門教授。大学に息子さん来てましたけど、お会いになりました?」
「は?」
講義が終わり、さて弁当を食べようと教授室に戻ろうとしていたら事務員さんに声を掛けられてびっくりした。どういうことだと聞けば、何やら炭治郎が大学内に来ていたらしい。金髪の生徒の腕を引きずって歩いていたとの事だが……俺はその話にズボンの中に入れていたスマートフォンを引っ張り出す。サイレントにしていたから気が付かなかったが、炭治郎から着信が凄いな。メッセージを見ると『それ本当?』と短い言葉が入っている。
「……炭治郎。学校はどうしたんだ……」
俺はそう思いながらも炭治郎に折り返して電話するのは辞めた。衝動的に学校を早退するのもまた貴重な人生経験だ。青春ってものだろう。そこをとやかく言うのは無粋というものか。
俺はやれやれと思いながら教授室に戻ると冷蔵庫から弁当を取り出し、蓋を外し、レンヂにかける。くるくる回る愛妻弁当を見つめながら、俺はふと思った。
「……明日、村田君って子は紹介されるのだろうか」
多分、されないな。本気になった炭治郎が凄いことは善逸君もよく知っているだろう。なぜなら本人がそう評していたんだから。やれやれ。これで俺がやきもきするのも終わるのだろうか。
ピロリロと音が鳴ったレンヂの扉を開ける。温まった愛妻弁当は美味しそうだ。今なら間違いなく、美味しく楽しく頂ける。
「頂きます」
俺はそう言って手を合わせると箸を取った。妻の手料理は今日も美味い。愛する人の作ってくれた料理は格別で、炭治郎がそれを知る日は近いのだろうか。善逸君が料理をするかどうかは知らないからなぁ。
……そんな事を思いながら俺がのんびり構えていたのは半日以上前だ。俺は炭治郎がまだ帰ってこないと心配する妻に「多分、善逸君の家にいるんだろう」と宥めつつ、電話をするかしないかで悩んでいた。
炭治郎とはずーっと連絡が取れてないらしい。それが妻や家族の心配を助長しているようだが、たぶん、間違いなく炭治郎は善逸君の家にいる。そして家族に連絡することも、家族からの連絡に気づかないほど、何かに夢中になっているのだ。
「まあ、男の子だし、高校生だし。大丈夫だろう」
俺はそう言って炭治郎の朝帰りの手助けをした。炭治郎と善逸君の恋路を応援したい。そう思い、結局俺は炭治郎の電話にコールをするのをやめた。明日の朝は二人揃って家にくるだろうか。我が子は一皮も二皮も剥け、男として成長をしているのだろうか。
どちらにせよ、二人の運命の歯車はもう廻りだしたのだから、止まることはないのだろう。