現パロ炭善。受の女体化。
男だと思ったら女の子だったという話。
生理描写あります。
約60000字/女体化/現パロ
「大変!!申し訳ありませんでしたぁぁぁ!!」
「ひえっ!!いきなり飛び込んできてなにぃぃぃぃ!?」
俺、竈門炭治郎は床を割るつもりの勢いで土下座を決めた。目の前は混乱と罪悪感で歪んでいて、『どうしよう、責任を取らねば』という文字ばかりだ。なんの説明もせずに頭を下げているから、相手も状況が分からないだろうに。困惑しているらしく、頭上から「か、竈門君?」とオロオロした声が聞こえて、俺はそれに釣られて少し顔を上げてしまった。
「!?」
その途端に視界に飛び込んできたのは、土下座をする俺を近くで覗き込むために膝をついている相手の姿だ。金の髪がさらりと流れる音がした。我妻先輩は薄っぺらいタオル一枚を胸のところで縦に押さえて、たったそれだけで身体を隠している。胸も、腹も、股もそれだけで隠している。そのタオル一枚剥ぎ取られれば、その先は裸だ。そんな頼りない姿を俺に当たり前のように晒しているのは……俺がそれがここでのマナーと言わんばかりに教えてしまったからだ。
「うああああっ!ごめんなさいっ!!」
「だから!どうしたのよっ!?」
「違うんです!ごめんなさいっ!俺っ!俺っ!!我妻先輩が女性だって知らなかったんです!!」
「えっ?」
「さっき禰󠄀豆子に言われて初めて知ったんです!俺、今までずっと、先輩は俺と同じ男だと思ってたんです!!」
「え、ええええー!?さんっざん俺の裸見たのにぃぃぃ!?」
「すみませーーん!!」
俺はそう叫んでゴッと額を床に打ちつけた。凄い音がしたから、タイルが割れたかもしれない。しかし俺の罪悪感はその程度じゃ消えない。女性の先輩を男と間違えて、あんなことや、こんなことをしてしまった俺は……何がなんでも、『責任』をとらねばならない。
ことの始まりはどこだろうか。俺がキメツ学院に入学したことだろうか。それとも形見であるピアスが先輩との接点なのだから、父さんが死んだ時からだろうか。
俺、竈門炭治郎はこの街の代々続く銭湯の息子だ。六人兄弟の長男で、下には妹二人、弟三人がいる。皆んな良い子で、俺の自慢だ。父さんと母さんも仲が良くて、おしどり夫婦だって町内では評判だったけど……俺が十三の時に父さんは病気で死んでしまった。元から、身体は丈夫ではない人だった。
父さんが死んでからは、女手ひとつで六人もの子供を養わなければならなかった母さんはとても大変な日々を過ごしている。幸いだったのは、夫婦で銭湯を営んでいて、地元密着型で沢山のお客さんがうちをご贔屓にしてくれていたから、父さんがいなくても収入には問題がなかったことだろう。父さんが外勤めだったら大変だったけど、俺と長女である禰󠄀豆子がそれまで以上に頑張れば銭湯はなんとか回った。目まぐるしい日々だったけど、下の妹と弟も育ってきてどんどん手が掛からなくなる。家のために周りよりも少し大人になるのが早いのは……申し訳ないし、寂しいけど、我が家は皆んなで力をあわせて幸せに暮らしてきた。
さてここまでで我妻先輩がまだ出てきていないが、登場はここからだ。先輩との出会いは俺が高校生として、禰󠄀豆子が中学の頃から通っていたキメツ学院に入学した時のことである。キメツ学院は家から通える一番近い学校で、私立でも学費はかなり安く一年間で六十万いかない程度。勉強の指導も分かりやすいし、部活は帰宅部でもOKという楽な学校だった。塾に行く暇もない我が家のことだ。塾代が削れるし、定期代もかからないのだから、公立より多少高い程度なら近いところがいい。
というわけで俺はキメツ学院という学校に通っているのだが……流石に学費が安くて色々と融通が効くとしても、服装には厳しい。まあ、ピアスの着用を許可する学校がどれほどあるか知らないけど。俺は死んだ父さんから譲り受けた形見のピアスをつけている。このピアスは竈門家の長男に代々受け継がれているもので、歴史があるものなんだ。外してはならないと遺言にもあったし、俺はピアスを肌身離さず着けている。
というわけで、ピアスを禁止されているキメツ学院にも当然、着用したまま登校している。勿論、最初は注意された。その注意をしてきた相手が、キメツ学院二年の我妻善逸先輩だった。我妻先輩は風紀委員で、毎朝校門の前に立って生徒の服装チェックをしているんだ。
俺は我妻先輩にピアスを注意されて、申し訳ないが形見なので外せないことを誠心誠意込めて説明した。我妻先輩は頭を下げ続ける俺にあたふたしていたみたいだが、キチンと話を最後まで聞いてくれて「も、もういいよぉ〜そんなこと聞いたら取り上げられないよぉ〜」と俺を見逃してくれた。優しい。
しかも先輩は一回見逃してくれただけではなく、毎日毎日、他の風紀委員の人が俺を見つけるよりも早く俺に声をかけて、そして見逃してくれる。毎日毎日、こんなに見逃して怒られないのだろうかと不安になっていたけど、ある日担任の先生に言われたのだ。
「竈門。ピアス着用の許可証が発行されたぞ。これは生徒手帳に入れておくようにな」
俺は先生のこの言葉に凄くびっくりした。俺は申請すれば許可を貰えるなんて知らなかったからだ。そして許可証に押されているハンコが風紀委員会のものと、学院長のもので俺は閃いた。間違いない。我妻先輩が発行してくれたのだと確信した。俺の話を聞いてくれた我妻先輩が許可証が取れるように掛け合ってくれたのだ。
俺はその事実に嬉しくなって、先輩を二年の校舎で探したけど……見つからなかった。仕方なく翌日を待って、朝にお礼を伝えに行ったけど、先輩は風紀委員の仕事で忙しいから長々とお礼は伝えられない。俺は伝えたい気持ちの三分の一も伝えられないまま、「この度はありがとうございました!!」「はいはい。じゃあもう通って良いよ」という簡単なもので終わってしまった。納得がいかない。
俺の身の内にある感謝は言葉一つで昇華できるものじゃない。もっともっと、我妻先輩に報いたい。そう思っても先輩の好きなものも、欲しいものも分からない。何しろ俺と先輩の間には大した接点はないのだ。親切にしてもらった、親切にしたという関係しかない。俺は先輩に何とかお礼をと考える日々を暫く過ごして……そして訪れたのだ。絶好の好機が!!
それは夏が始まったばかりの暑い日。夕食時で常連客もまばらになった頃合いだった。なんと我妻先輩が我が銭湯、竈門極楽湯にやって来たのだ。俺はそれに驚いたし、我妻先輩はフロントに俺が座っていたのに驚いていたようだった。
「我妻先輩!」
「あ、竈門君。そっか、ここって竈門君の家だよね……」
「そうです!今日はどうかされたんですか?えっと、先輩、うちに来るの初めてですよね?」
俺はドキドキそわそわしながら先輩にそう言った。先輩は白いTシャツにハーフパンツという夏の少年らしい格好で、子供の頃に使っていたプールバッグだろうか。水色のクリアバッグを片手にしていた。描かれているキャラクターは可愛いらしい狸で、俺も見たことあるキャラクターだった。
「それがさぁ〜聞いてくれよ!なんとアパートの給湯器が壊れちゃったの!古いアパートだからしょうがないけどさぁ〜。大家のお婆ちゃんが言うには直すのに時間かかるらしくて……」
「えっ!?それは……大変ですね」
「そうなんだよ。流石にこの季節でもずーっと真水でシャワーは辛いよ!そしたら大家のお婆ちゃんが銭湯行けばいいからってここを紹介してくれてさ」
「そ、そうだったんですね!それは良かった!」
「いや、良くないよ。広いお風呂は楽しみだけど」
先輩は溜息をつきつつ、入湯料をトレーに置いた。俺はお金なんていらないと頭の中を過ったけど、もう一つポッと考えが浮いてきたのだ。
(そうだ!!先輩に垢擦りのサービスやろう!)
垢擦りのサービスとは父さんが居た頃は年中やっていたサービスで、追加料金を貰ってお客様の垢を落とすというものだ。父さんが死んでからは時間の都合上、俺が長期休みの時しかできない期間限定サービスだ。ちょうど夏休みだし、先輩にもうちを贔屓してほしいしと俺は名案とばかりに先輩に言った。
「我妻先輩!垢擦り受けてみませんか?お代は要らないので!」
「え?垢擦り?」
「これが回数券です!我妻先輩にはお世話になったので……他のお客様には内緒でこっそりサービスします!」
俺は簡素な回数券を先輩に手渡した。それは本当に簡素なもので、うちのハンコが押してあって『垢擦り回数券』と書かれているだけのカードだ。五回分の回数券だから、チェック欄が五分割されている。それだけのもの。
「垢擦りって……何するの?」
「垢擦りは皮膚に付着した垢をこすり落とすものです。ボディーソープや石鹸では落とせない頑固な垢を落とすんですよ!体臭予防や、美肌効果もあります!」
「へぇ〜?いいねぇ」
「やりますか!?」
「うん。折角だし……無料サービスは魅力的だもん」
えへへと笑う我妻先輩に俺もニッコリ笑う。我妻先輩に喜んでもらえて良かった。後悔させないようにしっかり垢擦りしないとな!
「それじゃあ、先にお湯に浸かって身体を温めてください。身体を洗う際は石鹸は使わないでくださいね。垢が出にくくなるので」
「えっ、そうなの?」
「はい。局部は石鹸で洗っても大丈夫なので」
「え、う、うん……」
仄かに赤くなった我妻先輩にどうしたのかなと俺は不思議に思ったけど、説明の続きがあったので特に気にしなかった。先輩に風呂から上がったら脱衣所にある『垢擦りルーム』という札が出ている扉を開けて廊下を進むように伝える。
「廊下の先にまた部屋があるので、入ってください。そこで垢擦りするので。タオル一枚で来て大丈夫です。予約時間はえーと、八時で大丈夫ですか?」
「うん。平気」
「それじゃあ、予約取っておきます」
俺はそう言って先輩を見送った。我が家の銭湯は、脱衣所の扉はフロントから左に曲がった一箇所のところにまとまっている。だからお客様の姿がフロントからは見えなくなる。昔は番台が男湯と女湯の間にあったけど、マッサージチェアを置いたり、憩いのスペースを作るために父さんが跡を継いだ時に改装したらしい。
昔と違って各家庭に風呂があるのは当然に近い。銭湯は毎日通う風呂というものではなくなり、少し形を変えないとお客が寄りつかなくなっていく。そう思った父さんが昔の雰囲気を残しつつ、居心地がいいように銭湯を変えていった。俺は今の姿しか知らないけど、俺もいつまでも銭湯が続けられるように、時代に合わせて柔軟に変化させていかなきゃって思う。
「さて、時間が来るな。垢擦りの準備をしよう」
俺は春休み以来の垢擦りだと張り切った。次男の竹雄にフロントを交代してくれと頼んで、俺は準備のために垢擦り用の小部屋に入る。そしてマッサージ台に枕を置いて、垢擦り用のミトンを用意する。と、ここでガチャリと扉が開いた。俺は我妻先輩だと振り向けば、我妻先輩は真っ赤な顔でタオルを身体に巻いて立っていた。うん、良くお風呂に浸かってくれたみたいだ!うちの湯は少し熱かったのかな?
「先輩、湯加減はどうでした?」
「え、あ、気持ち良かったけど……えっ!?待って!?なんで竈門君がここにいるの!?」
「え?垢擦りは俺がやってる仕事なので……?」
「ええっ!?」
「それじゃあ始めましょう!」
「えっ!?えっ!?ま、待ってぇ!?」
先輩は後輩に裸を見られるのが恥ずかしいのだろうか?それとも技術を心配しているのか?けど俺もプロとしてやっているから、先輩の身体を見てもどう思うこともないし、腕前にも自信があるっ!
「安心してください!俺は中学の時から垢擦りの仕事してます!プロです!大丈夫です!」
「ひ、ひぇ……」
「はい、ここにうつ伏せになって寝てください」
「ひゃ、ひゃああああ……」
俺は我妻先輩の腕を引いてマッサージ台に寝かせると全身磨きあげるぞと、垢擦り用のミトンをつけた。そして我妻先輩の足、手、背中、お尻を順番に擦って磨いていく。
「う、う……」
「先輩、痛くないですか?」
「だ、大丈夫……」
「じゃあ、今度は仰向けになってください」
「えっ!?仰向け!?」
「はい」
垢擦りは一般的ではないから、不思議に思うことも多いだろうなと思いつつ、俺は先輩の聞き返しに頷いて返した。先輩はしばらく沈黙していたが、ゆっくりと身体を起こしてひっくり返る。その時の顔が本当に真っ赤で、湯に浸かりすぎて上気せてないかと心配になってきてしまう。
「先輩、具合悪いですか?」
「えっ!?そんなこと……ないよ……色々、びっくりして……」
「そうですか?じゃあ、続けますね?」
「う、ん……ってひぇっ!!あ、たお、タオル!!」
「お腹を擦る時に邪魔なので」
俺は先輩が胸と腹にかけて乗せていたタオルを腰付近まで引き下ろした。背中を見て思ったけど……我妻先輩は少し痩せすぎている。肋が浮いているし、胸筋も薄くて心配になる。病気で痩せてしまった父さんを思い起こす。
「あ、う、う……」
「?」
先輩は真っ赤な顔で目を瞑って垢擦りを受けていた。この貧相な身体だと、確かに後輩に見られるのはちょっと恥ずかしいのかもしれない。俺はなるべく見ないようにしながら垢を落とすと、ミトンを外した。
「も、もう終わり……?」
「まだです。石鹸で洗って、垢を流します」
「えっ、ああ〜!」
「ほら先輩、肌がツルツルになってる感じしませんか?」
「ん、んん……♡」
「胸と腹も洗いますね」
「あ……あぅ……♡」
「タオルで拭き取ります!」
「んやぁ……♡」
「最後に……じゃーん!!保湿オイルです!身体に塗り込んでいきますね♡」
「あ……あ……んやぁぁぁんっ♡」
というわけで俺は我妻先輩に無事に垢擦りのサービスを提供した。恩があるからと、いつも以上に気合をいれてサービスした。丹念に股間を除く隅々まで垢擦りし、洗い上げ、オイルを塗った。
「じゃあ回数券にチェック入れますね。あと四回ありますけど……次の予約とっておきますか?垢擦りは予約必須なので……次来た時に空いてるとも限らないですし……」
「……うん」
「頻度としては一週間に一回がいいかなと思うので、えーと……同じ時間帯で大丈夫ですか?」
「……うん」
「はい!じゃあ予約取っておきました!この日に待ってますね!」
「……うん」
我妻先輩はコクンと頷いて帰って行った。初めての垢擦りに気疲れしてしまったのだろうか。俺はそう思いながらも、明日も風呂に入りに来てくれるかなと上機嫌だ。何しろ我妻先輩に恩返しを始められたのだ。浮かれるのも仕方がないだろう。ずーっとずーっと、何かで報いたいと思っていたのだから。
それから我妻先輩は毎日うちの風呂に来てくれた。給湯器が直ってからも、三日に一回くらいは「広いお風呂って気持ちいいから」とはにかんでうちに通ってくれた。そして——。
「あっ♡ あっ♡ だ、だめ…擽ったいっ……♡」
「我妻先輩って胸触られるの弱いんですね?」
俺は俺で、恩返しを続けていた。二回、三回、四回と我妻先輩に垢擦りをした。我妻先輩は毎回真っ赤になって、身体をタオルで隠しながら部屋に入ってくる。その姿に慣れないんだなぁなんて呑気に思いながら、俺はとうとう、夏休み後半、そして人生におけるXデーを迎えてしまったんだ。
「禰󠄀豆子、兄ちゃん垢擦りしにいくからフロント頼む」
「うん、分かった」
この日、いつもフロントの交代を頼んでいた竹雄は友達の家に泊まりに行っていた日だった。夏休みの宿題を集まって仕上げると出ていった弟の代わりに、長女の禰󠄀豆子にフロントを頼んだのだ。
「よし、じゃあ準備に行くな」
「うん。行ってらっしゃー……いっ!?待って!?待ってお兄ちゃん!!」
「ん?どうした禰󠄀豆子。そんなに大きな声を出して」
垢擦りルームに向かおうとした俺を禰󠄀豆子が慌てた声で引き止めてきた。客商売だから大きな声は良くないのに、そんなの良く知っている筈なのにどうしたのかと不思議に思って禰󠄀豆子に近づくと、禰󠄀豆子は垢擦りの回数券を見て驚いていたようだった。その回数券には名前が書かれていて、我妻善逸と記入されている。先ほど風呂にきた我妻先輩が置いていったものだ。垢擦りをしたらチェックを入れる必要があるから、受け取ったものだ。
「これっ!これっ!!我妻善逸って書いてあるんだけど!?」
「そりゃそうだ。我妻先輩のだからな」
「なんでっ!?」
「何でって……ほら兄ちゃん、我妻先輩にはお世話になっただろう?少しでも恩返ししたくて垢擦りの回数券を無料であげたんだ!」
「お母さん知ってるの!?」
「母さんにも説明したぞ?お世話になった先輩に無料サービスしたいって……」
「えっ!?えっ!?」
禰󠄀豆子は真っ青になって、真っ赤になって頭を抱えた。様子のおかしい禰󠄀豆子に、どうしたのだと俺が思っていると、禰󠄀豆子はそろりと顔を上げた。顔色は赤から青になっている。
「お兄ちゃん……もしかして……我妻先輩のこと勘違いしてる……?」
「勘違い?」
「だって、だって……うちの垢擦りは男性専用のメニューでしょ?」
「うん、そうだな?男の俺が女性の垢擦りをするわけにはいかないからな?」
そうなのだ。竈門極楽湯の垢擦りは『男性専用』なのだ。垢擦りの勉強を父さんから習ったのは俺だけで、まだ他の弟妹には時間がなくて伝授できていないからな。垢擦り用の部屋も少ないし。だから男性専用のサービスだが……それが我妻先輩と何が関係あるのだろうか。
「お兄ちゃん!!我妻先輩は女の人よ!?」
「え?」
禰󠄀豆子の言葉が一瞬、分からなかった。何を言っているのか、変な冗談をと思うけれどこんな真っ青な顔でそんな冗談を禰󠄀豆子が言うわけがない。面白くもない冗談だし。だから俺は、禰󠄀豆子の言った『我妻先輩は女の人』という事実にガーンっと頭をぶん殴られた。
「えっ!?嘘だろ」
「嘘でしょ!?気がついてなかったの!?垢擦りしてて!?」
「き、気がつかなかった……!胸も男みたいにまるでないし、チンコがついているかなんて下を見てないから分からないし……!」
「最低!!やめてよ!!それよりももう四回も垢擦りしてるじゃない!!気がつかなかったじゃ済まされないわよ!どうするのよ!!」
禰󠄀豆子にそう言われて俺は確かにと思った。俺は女性である我妻先輩の裸を四回も念入りに触れ回っているのだ。股間以外は触れてないところはないと言うくらいに、手も足も、背中も腹も、胸もお尻も撫で回している。先輩が毎度毎度、顔が真っ赤だったのは……当たり前だ。後輩の男に裸を見られて撫で回されるなんて、そりゃ真っ赤になるだろう。
「や、やってしまった……!」
「我妻先輩に男専用のサービスって説明しなかったの?」
「し、してない。我妻先輩を男だと思ってたから……」
「最初の時にお兄ちゃんいて驚いてなかったの!?」
「驚いてたけど……気にせず施術を進めてしまった」
「もーー!!」
バンバンとフロントカウンターを叩く禰󠄀豆子は相当に混乱しているようだった。それは俺もで、今までの先輩の姿を思い起こしてしまう。
『あっあっ♡ やだっ♡ やだっ♡』
『んっ…んんっ……♡』
『ひぅ……♡ かまど…くぅん……♡』
「わーーーーー!!」
「お兄ちゃん!?」
俺は頭が沸騰した勢いで駆け出した。スタッフオンリーの扉を開き、いつも通り垢擦りルームに突入する。予約時間は既に超えていて、我妻先輩はいつものように白い肌を薄いタオル一枚で隠していて、タオルが薄すぎて薄ら肌の色が透けている……気がする。我妻先輩はびっくりした顔をしていて、俺はというと先輩の戸惑いよりもその裸に近い姿に意識がいって——罪悪感で土下座を決めた。そして、冒頭に戻る。
「大変!!申し訳ありませんでしたぁぁぁ!!」
「ひえっ!!いきなり飛び込んできてなにぃぃぃぃ!?」
俺、竈門炭治郎は床を割るつもりの勢いで土下座を決めた。目の前は混乱と罪悪感で歪んでいて、『どうしよう、責任を取らねば』という文字ばかりだ。なんの説明もせずに頭を下げているから、相手も状況が分からないだろうに。困惑しているらしく、頭上から「か、竈門君?」とオロオロした声が聞こえて、俺はそれに釣られて少し顔を上げてしまった。
「!?」
その途端に視界に飛び込んできたのは、土下座をする俺を近くで覗き込むために膝をついている相手の姿だ。我妻先輩は薄っぺらいタオル一枚を胸のところで縦に押さえて、たったそれだけで身体を隠している。胸も、腹も、股もそれだけで隠している。そのタオル一枚剥ぎ取られれば、その先は裸だ。そんな頼りない姿を俺に当たり前のように晒しているのは……俺がそれがここでのマナーと言わんばかりに教えてしまったからだ。
「うああああっ!ごめんなさいっ!!」
「だから!どうしたのよっ!?」
「違うんです!ごめんなさいっ!俺っ!俺っ!!我妻先輩が女性だって知らなかったんです!!」
「えっ?」
「さっき禰󠄀豆子に言われて初めて知ったんです!俺、今までずっと、先輩は俺と同じ男だと思ってたんです!!」
「え、ええええー!?さんっざん俺の裸見たのにぃぃぃ!?」
「すみませーーん!!」
俺はそう叫んでゴッと額を床に打ちつけた。凄い音がしたから、タイルが割れたかもしれない。しかし俺の罪悪感はその程度じゃ消えない。女性の先輩を男と間違えて、あんなことや、こんなことをしてしまった俺は……何がなんでも、『責任』をとらねばならない。
「責任をとります!!どんなことでもします!!だから!弟たちの為に、竈門湯を訴えるのだけは許してください!!」
家には俺を除いても子供が五人もいるんだ。俺はどうなってもいいが、弟妹は見逃してほしい!!その一心で土下座をしていると我妻先輩はゴソゴソと何かをし始めて、俺はその音が気になって顔を上げた。すると我妻先輩が真っ赤な顔で、部屋に置いてあった大判のタオルを身体に巻き付けて、棚の隅で小さくなっていた。
我妻先輩は恥ずかしそうに、悔しそうに顔を歪めていて、俺は「あっ」と思う。弟妹の保身に走りすぎた。今は我妻先輩の傷ついた気持ちに寄り添わねばならなかったのに、先輩にあった振り上げる拳を先に止めてしまうようなことを言ってしまった。優しい先輩のことだ。弟と妹のことを口にすれば、自分が理不尽な目にあったのに飲み込んでしまうかもしれない。
「せ、先輩!すみません!!」
「……安心しろよ。訴えたりしないから。竈門君、気づいてなかったんだろ?俺が女だって。ははっ。まあ、そうだよなぁ。こんなガリガリで貧相な身体なんだもん。気がつかないよなぁ」
俺は先輩に何と言えばいいのか分からず、ぐるぐる視線を巡らせる。何を言っても傷つけそうで、言葉が出ない。どうしたらいいんだと荒い呼吸をしていると、スタッフ用の扉がギィと開いた。
「あの、我妻様……大変申し訳ありませんでした」
「……母ちゃん……!」
「おはよー!」
「あっついねー」
「今日、夏休みの宿題提出だよなー?」
「はぁー、まだまだ休みてぇー」
ざわざわと楽しそうな生徒達の声が聞こえる通学路を俺は重い足取りで歩いていた。気分はもはや、断頭台に向かう罪人だ。断頭台はどこだって?それは勿論、俺が会いたくて会いたくて、でも会いたくない相手が学校がある日は毎日のように立っている……校門だ。
「お、おはようございます……」
「……はい、おはよう。通っていいよ」
「…………」
俺は視線をすっと外してきた我妻先輩の態度に悲しい気持ちになるが、どうしようもない。俺がしてしまったことはあまりにも罪深いものだから。俺は校門を過ぎてから、予鈴がなるまで短い間を木陰で過ごした。何故かといえば、我妻先輩が校舎に入るのを見たかったからだ。予鈴が鳴る頃になると、風紀委員の先生が来て服装チェックを交代するのだ。それを待っていると、風紀委員の人たちがバラバラと校舎に向かって歩き始めた。男女で何となく進む方向が左右に別れていき、我妻は右側に進んでいく。俺はちなみに男だから左側の校舎の木陰に立っている。
「……やっぱり、我妻先輩は女の子なんだ……」
俺は改めて自覚して、溜息をついた。俺が通っているキメツ学院は珍しいことに男女別学である。同じ校門を使い、行事や一部の授業は男女で行うが、基本的には校舎が別になっている。
「……制服がスラックスだったから、勘違いしてしまった……」
そう、我妻先輩は制服がズボンなのだ。それがまた俺の勘違いを……というよりも男だという思い込みを加速させた要因である。
キメツ学院は男女共に制服は規定のものを着ていれば自由だ。スカートとスラックス、男女ともにどちらを着用してもいいということになっている。男女別学なのに風変わりなと思うかもしれないが、この男女の校舎も性自認する方に入学が可能であるので、相当変則的で実験的な学校なのだ。
「そういう学校なのは分かっていたんだから、服装に惑わされてたらダメだろ……はぁ……」
俺は女子校舎に入っていった我妻先輩の姿にしくしく胸を痛めた。女性であったのだから、そりゃ男子校舎を探してもいない筈だ。俺は女性である先輩を辱めてしまったと後悔をたっぷりしながら、下駄箱へと向かった。
あの日、先輩の性別を正しく認識した日、戸惑う俺と泣く我妻先輩の元に来たのは俺の母さんだった。母さんは竈門極楽湯の責任者として我妻先輩に謝罪し、賠償をすると頭を下げた。禰󠄀豆子にことの次第を聞いたんだろう。俺は頭を下げて小さくなった母さんの背中を見ながら、泣きたくなった。けど俺が泣くべきところじゃない。泣きたいのは、泣いていいのは我妻先輩だけだと堪えていると——。
「お金とか要りません。……こんな身体の俺が悪いんだ」
我妻先輩はそう言って、うちからのお金はいらないと断ってきた。それにそんなわけにはいかないと母さんが言ったけど、我妻先輩は「お金を払うというなら訴えます」と言ってきて、黙るしかない。訴えられるのは困る。しかしお金を払いたいと言うと訴えるとは何なのか。お金を払わないなら訴えないなんて逆じゃないのか。
「……じゃあ、ここの年間パスポートください。もうそれでいいです」
全然良くない。結局、年間と言わず、一生分のパスポートと書き直したものを我妻先輩に渡した。我妻先輩はそれだけ受け取って、逃げるように竈門極楽湯を去っていった。母さんと俺はその後ろ姿を頭を深く下げて見送って……それでおしまいだ。
俺は母さんには叱られなかった。母さんもなんと叱ればいいのか分からなかったんだろう。身体を見ても気がつかないなんてと叱ったとしよう。それだと我妻先輩の身体が性別を気がつかれない程のものだと言うような
ものではないか。だから母さんは我妻先輩を侮辱するような事は口にするまいと俺に何も言わなかったのだろう。
さて、そんなわけで竈門極楽湯としては我妻先輩についての問題は一生分のパスポートを渡したことで、大変遺憾であるが解決している。なぜ遺憾であるかは簡単なことだ。我妻先輩はあの日から竈門極楽湯に通わなくなってしまったからだ。
今までは三日に一回と通っていたのに、夏休み後半から一切来なくなった。我妻先輩の家は家から歩いて五分と聞いている。そんな距離で、年間パスポートがあって来ないということは……もう、うちの湯には入りたくもないということだろう。それはそうだ。自分を辱めた相手がいる銭湯に当たり前のように通うなんて出来るわけがない。つまり竈門極楽湯がした先輩への償いはほぼ、何の意味も成していない。
「うう……。先輩への恩返しのつもりが……恩を仇で返してしまった……」
責任、責任をとりたい。我妻先輩への責任をとりたい。とにかく何でもいいから、責任を取れと俺に命令して何か償いをさせてくれと俺はずーっと思っている。それこそ、考えない日はないくらいに先輩のことを考えている。
「ハァー……ん?」
俺は下駄箱を開けて目に飛び込んできた封筒に、おやっと思った。誰からだろうと表と裏を見るが、『竈門君へ』としか書かれていない。中を開けて開くと、『昼休みに3号館の裏手に来てください。 我妻善逸』と書かれていて、びっくりした。
「へっ!?あ、我妻先輩!?」
俺はまさかの呼び出しにカッと身体に熱が入る。学校が始まってから、校門で会っても素っ気ない態度を取られてる日々が続いて凹んでいたが、まさか呼び出しをしてくれるなんて。たとえ罵るために呼ばれたのだとしても嬉しい。まだ俺を視界に入れてくれるのが嬉しい。俺は丁寧に手紙を鞄にしまうと、スキップしたいほどの軽い足取りで校舎に入っていった。昼休みがとても楽しみだ!
「というわけで我妻先輩!!責任を取らせてください!!」
「なんの用件もまだ言ってないんだけど……」
待ちに待った昼休み。我妻先輩はお弁当の袋を片手に現れた。俺はというと我妻先輩との約束に本気で臨むために三限後の休み時間に早弁をしてしまったから弁当はない。
「竈門君、お昼は?食べた?」
「早弁しました!」
「ええ……?お腹空かないの?」
我妻先輩はそう言いながら、日陰のベンチに座る。この三号館の裏はベンチがあるけど人はあまり来ない。それは今が夏休み明けで暑いからもあるし、男子校舎からも女子校舎からも遠いこともある。
俺は我妻先輩の手の中にある小さなお弁当箱を見ながら、じっと先輩の言葉を待った。ところで量があまりに少ないのだが……それで足りるのだろうか?花子の弁当箱より小さいぞ?
「あのさぁ、竈門君」
「はい!」
「あの……ちょっと頼みがあるんだけどさぁ……」
「……頼み……ですか?」
我妻先輩の言葉に俺は首を傾げた。俺にするような頼み事って何だろうか。何であろうと先輩からの頼みなら全力で取り組むと決めているけど。
「嫌だったら断ってくれていいんだけどね?」
「いえ、絶対に断りません」
「いやいや!中身は吟味しよ!?」
「大丈夫です!何なりと申しつけてください!!」
「どういうテンションなの……?まあ、出会い頭に責任取るとか言ってるわけだから、竈門君の罪悪感が凄いのはわかったよ」
「うっ……」
やはり前のめりに責任を取らせろと言われるのは先輩にとっても負担だよな。先輩は一切悪くないのに俺に対して憤ることもできなくしてしまうかもしれない。でも俺は罪を償いたい。許してくれなくてもいいから、先輩に何か償いをしたくして仕方がない。
「……正直に言って欲しいんだけど、竈門君は俺の身体見てどう思った?」
「えっ」
それはどういう意味だろうか。何を言っても失礼にならないか?先輩を余計に傷つけないか?そう思ってしまって俺は中々言葉が出てこない。
「ごめん。答えづらいよな。じゃあ、俺の質問に頷いてくれるだけでいいや。……竈門君は俺の身体、胸ないなって……思った?」
「……」
俺はその質問にダラリと汗を流す。しかし先輩は『正直に』と言った。そして言葉が出ない俺を気遣って、頷くだけでいいとしてくれたんだ。相当に譲らせているのだから、これ以上の黙秘はダメだ。俺は夏が理由だからではない、尋常ではない汗を流しながら歯を食いしばって頷いた。
「……俺の身体、男みたいだった?一回も女だって思いもしなかった?」
「…………」
油の切れたブリキ人形のようにゆっくりと、軋むように俺は首を縦に振った。一回の頷きでどっと疲れる。我妻先輩は「そっかぁ」と言うと、ちびちびとお弁当を摘み出した。俺が先輩をチラリと見やれば、悲しそうな横顔をしていて……心臓がすり鉢で擦られているのかと思うくらいに痛くなる。
「……竈門君にだから言うけど、俺さぁ。こんな男みたいな格好してるけど、本当はスカート履きたいんだよね」
「え」
「意外だって思うかもしれないけど、まあ、俺見かけがマジで男みたいだから……スカートの制服を着る勇気なくて。似合わないって笑われたらヤダなって、スラックス履いてるの」
我妻先輩は恥ずかしそうにして、ローファーのつま先を擦り合わせた。よくよく見れば俺と足の大きさが随分違う。禰󠄀豆子より少し大きいかなってくらいで、俺と並べたら一回り以上違うんだ。その小さな足に、心臓がまた痛くなる。でもすり鉢で擦られるような痛さじゃなくて、締め付けられる感じの痛みだ。
「……俺、もう少し女の子らしくなりたい。胸も巨乳とは言わないけど……もう少し大きくさぁ」
そう言って自分の胸をベストの上から押さえた我妻先輩に俺はいても立っても居られず立ち上がった。先輩が望むなら、俺はそれを叶えるべきだ!!
「先輩の頼みはわかりました!引き受けます!」
「えっ?何を?」
「俺に任せてください!必ず先輩の力になります!」
「だから何を!?」
「そうと決まればまずは健康的に肉をつけましょう!俺、一走り購買に行ってきますね!」
「えっ!?えっ!?竈門くぅぅぅん!?」
俺は我妻先輩の静止を振り切って購買に走った。胸が大きくなりたいと言うなら、もっとカロリーを摂るところから始めなければ。我妻先輩はガリガリすぎる。もっともっと食べて脂肪を蓄えないと、胸が大きくなるはずがない。
「よしっ……!頑張るぞ!俺は必ず、我妻先輩の胸を大きく成長させてみせる!」
俺は先輩への償いを見つけて、意気揚々と購買部がある校舎に駆け込んだ。今の時間だと甘い系ばかり残っていそうだが……太るには甘いものがいいよな!
****
ブーっと鳴ったチャイムに、俺は参ったなと思いながらアパートの玄関を開けた。そこにはキラキラお目目の後輩君が立っていて、手にはエコバッグがある。
「こんばんは!」
「……こんばんは。また来たの?」
「毎日来ます!」
「ああ……そう……?」
この後輩を止めても無駄である。人の話を聞いているようで聞いていないし、我を押し通すところは押し通してくる。それを俺は身に染みて分かっているから抗うなんてことはせずに道を開けた。すると後輩君は当たり前の顔で「お邪魔します」と言って、丁寧に靴を脱いだ。一つ一つの所作から滲み出る育ちの良さに俺は溜息が出てしまいそうで、それを何とか堪える。
「台所を借りますね」
「俺も手伝うよ」
「ありがとうございます」
にっこり笑う後輩君は今日も顔がいい。流石、女子校舎で美人と評判の竈門禰󠄀豆子ちゃんのお兄ちゃんだぜ。男女別学であまり男子と接点はないけど、カッコいいとよく名前があがるのもよく分かる。
「竈門君のお家のご飯は今日も凄いなぁ」
「食べ盛りが多いので。妹達が頑張ってくれてます」
竈門君が持ってきたエコバッグから、料理が詰められたタッパーが次々と取り出されるのに感心した俺に、ちゃんと妹を褒めて見せるのだから偉いお兄ちゃんだ。俺もこんなお兄ちゃん欲しかったな、なんて血の繋がりのない年長者達を思い出す。
「味噌汁、温めるよ」
「お願いします」
俺は竈門君から容器を受け取って、小鍋に入れた。俺の家にある調理鍋はこれだけだ。あとは小さいフライパン。それがなんだか恥ずかしくてしょうがないけど、ないものはないのだ。買う余裕も今月はない。
俺は味噌汁をじっと見つめて、沸騰したけど煮たたない程度とやらで火から下ろした。隣の竈門君はそれをどう思ってるか、聞く勇気は俺にはない。上手に出来たでしょうと胸を張るには随分と簡単すぎることだ。
「先輩、火の見極めが上手くなりましたね」
「へっ!?」
「食べましょう」
竈門君は持参した二つの茶碗にご飯をよそい、持参した一つの椀に味噌汁を入れて、もう一つは俺の家の棚から取った。俺の家にはお椀は一つあるけど茶碗はない。ご飯を炊いてわざわざ茶碗になんてのせないから。でもお茶碗の中によそわれているご飯はとても輝いて見える。あるべきところにあるのだと、誇らしく粒が立っているような気がする。
「いただきます」
「いただきます……」
俺は誰かの『いただきます』が自分の部屋から聞こえるのに未だ慣れない。竈門君が俺の家で持参したご飯を食べるなんて、もう二週間も続いているのに……全然、慣れないんだ。
(なんでこんな事に……)
俺はそう思いながら、竈門君の家の本日の夕飯を御相伴に預かっている。肉じゃが美味しい。凄い。どうやってこんなの作るんだろう。そんな風に思いながら箸を動かしていると視線を感じて正面を見た。竈門君は嬉しそうに、ニコニコしながら俺が食べるのを見ている。人が飯を食べているだけの姿の何がそんなに面白いのか。俺のちっぽけな城である、六畳一間の安アパートに君がいる方がよほど面白いことだぞと言ってやりたい。
なぜ竈門炭治郎という後輩が、毎日毎日、俺の家に食事を運んで来るかを説明するにはどこから始めればいいのだろうか。俺も正直、始まりが分からない。
竈門炭治郎は俺の通うキメツ学院の一年生で、入学初日から校則違反である耳飾りをつけてくるという猛者である。それを注意したのが風紀委員である俺で、竈門君は「死んだ父親の形見であるから外すことはできません!」と重苦しい理由を述べてきた。そしてその耳飾りが代々家に受け継がれている大切なものでと由来まで説明してくるのだ。勘弁して欲しい。そこまでの理由があるなら、ここで見逃しても、後ほど風紀委員会に所持の理由を提出して着用許可を求めてくるだろうと、俺は「もういいよ。後で許可とってね」と言ってその場を行かせた。
そして竈門君はその後も立派に耳飾りを着けて学校を過ごしているわけだが、何故か知らないが許可の申請が風紀委員会にやって来ない。俺は彼は何してんだろうかと思いながら、毎日毎日、彼を見逃すようにしていた。そしてとうとう、風紀委員会の担当教師に俺は聞かれたわけだ。「竈門炭治郎のピアス着用の申請書はいつになったらできるんだ?」とね。
えっ?それって俺が作るの?竈門君が自分で作るものじゃないの?俺はそう言いたかったけど、俺は女子校舎で、竈門君は男子校舎だ。探しに行くのは手間だしと……俺は全くもって不可解だが竈門君の家庭の事情を勝手に記入して申請書を作り、そして許可証を発行してもらった。今になっても何故俺がやらねばならなかったのか分からない。毎日毎日、俺が竈門君を率先して見逃してたから?
というわけで、何やらその辺りが竈門君が俺に恩を感じた要因らしい。俺は別にやりたくてやったわけじゃないし、完全に成り行きだった。だけど竈門君は俺に恩を感じて、それに報いたいと思っていて……そしてその結果、『我妻先輩、実は女の子だっんですか』事件が起きたわけだ。
何それって思うかもしれないけど、漫画みたいなことが起きたんだよ。竈門君の家が営む銭湯に行ってみたら、あれよあれよという間にエッチなマッサージされちまったんだ!!裸にされて、胸も腹もお尻も触られた!!しかも男の後輩に!!俺はいつ犯されちゃうのかとドキドキしてたけど……なんのことはない。マジで普通に、なんもない通常のマッサージだった。
いや、マッサージじゃなくて垢擦り?とかいうやつらしくて、肌が確かにピカピカになった。後輩である竈門君は「どうでした?」なんて爽やかな笑顔で言っていて、「プロってすげぇ」と恥ずかしくなったね。エッチなことされてるって思ってしまった自分が恥ずかしかったね。竈門君はこんな、女性の裸を前にしても平然とマッサージできるのかって……すげぇよ。現役イケメン男子高校生が垢擦りしてくれるってどこかの層にウケそうだななんて茹だった頭で俺は帰ったし、なんか竈門君が次回の予約まで取ってくれたから……まあ、その後も三回同じ施術を受けたわけですけどね。
いやーしかし、やられたわ。女性の裸をものともせずに、男がマッサージするってどんな鋼の精神なんだ、本当に高校生男子かと思っていたけどさぁ。まさか垢擦りマッサージは男性限定サービスだなんてな!おいこら、俺は女なんですけど!?
思い返すほど腹が立つ。ほぼ丸ごと裸を見られているのに気がついてもらえないなんてな?確かに股間は見られてませんよ?そんなに俺の身体、女の子から駆け離れてるの?うん、駆け離れてますね。よーく知ってるよ。竈門君は髪の毛一本の太さも、俺の性別を疑ったことないんだよね。男じゃなくて女だったなんて、きっと天地がひっくり返るくらいの出来事だったんだろうねー?喧しいわ。こちとらめちゃくちゃ気にしてんだよぉぉぉ!!
俺の性別を妹から聞いて知った竈門君は、もう凄い勢いで土下座してきたけど……もうこれは交通事故みたいなものだ。しかもどっちも不注意というか、何というか。もう霧がかかる山道のカーブでぶつかってしまったようなものじゃない?竈門君的には交通事故というか、隕石が勝手に降ってきた感じかもしれないけどさぁ。
というわけで、竈門君は俺に対して恩と罪を抱えているという可哀想な事になったわけだ。お詫びとしてフリーパスを貰ったのに、流石に気まずくて銭湯に行けないまま新学期を迎えたら、今にも死にそうな竈門君が現れてびっくりしたよね。めちゃくちゃ気にしてるのがもろばれだよね。俺のこと幽鬼みたいな顔で見てくるし。ちゃんと寝てるのかって聞きたくなる顔色だった。
俺はその顔が毎日毎日、こっちを見てくるのに耐えられなくてとうとう竈門君を昼休みに呼び出した。罪の概念が解けないっていうなら、ちょっとは何が酷い目に遭わしてやろうと思ったんだよ。俺にはたぶん、その権利があると思うし、竈門君もたぶん、俺に多少理不尽なことをされれば罪の意識も落ち着くかなと思って、俺は竈門君と並んでベンチに座ったわけですよ。
そして俺は、ずーっとずーっとひとりで抱えていた本音を竈門君に伝えた。入学した時からスラックスを履いていた、見かけも仕草も男みたいな俺が、実はスカート履いて可愛くなりたい、胸もおっきくしたいなんて本音を持ってるなんて恥ずかしいじゃないの。好き好んでこの格好してますって顔して過ごしてんのに、本当は可愛くてふわふわした女の子になりたいとか、俺に似合ってなくてしんどい。でも可愛くなりたい。おっぱいもおっきくなって欲しい。そんな愚痴を竈門君に聞いて欲しくて、そしてこれからもたまにで良いから吐き出させて欲しくて、俺は彼を呼びだしたわけですよ。
でもなぜか、そこからまた展開が斜め上に進んだ。竈門君は「先輩の頼みはわかりました!引き受けます!」なんて言って、俺にやたらに食事を運ぶようになった。昼休みは勿論、夕飯も今のように家にやって来て食べさせてくるのだ。
「……我妻先輩、少し丸くなりましたね」
「……むぐっ。そ、そりゃあ……こんなに餌付けされたら多少は太るよ!」
「ふふふ。いい感じです。もっと太りましょう」
現役女子高生に対して『もっと太れ』ということに罪は感じないのだろうか。なんて俺は思うけれど、確かに最近は体調が良くなったこともあって、自分の痩せすぎについては改善していくべき問題だと認識した。人には少しは肉がついている必要がある。身体の軽さが違うぞ。
(竈門君は……何を考えてるんだろうねぇ)
俺は味噌汁を飲んで一息を吐きながらそう思う。いや、理由は知っている。呼び出した際に連絡先をもぎ取られ、そしてその晩に家はどこだと聞かれて教えたら押しかけてきた。その不可解な展開に一体どうしたと聞けば、竈門君は「先輩を健康的に太らせて、胸を大きくします」なんて宣った。それからはずーっとずーっと竈門君はせっせと俺を太らせようとしている。何が楽しいのか。
(竈門君は責任感強すぎだろ)
お陰で俺は温かいご飯にありつけているわけですけど。俺は学費と進学費で生活費を削らないとならない苦学生なので、正直なところめちゃくちゃ助かってる。人の弱味につけこんで得ているタダ飯という点は気になるけどね。
「ご馳走様でした」
「お粗末様です」
竈門君は嬉しそうに笑うと立ち上がって俺の隣に座った。そしてスッと手を伸ばすと当たり前の顔で俺の手首や、腕を触っていく。これにむず痒い気持ちになるけど、竈門君はやましい気持ちは一切ないのだ。ただ単に、俺の身体の肉付きを確認しているだけ。
「昨日からそんなすぐに変わらないよ」
「それはそうですけど」
ふふふと子供のように笑う竈門君には翳った様子はもうない。きっと俺にせっせと食事を運ぶのが罪の気持ちを軽くしているのだろう。手間じゃないのかと俺は心配になるんだけどね。だって毎日だよ?お家の仕事もあるだろうに。何やら家族でやりくりして、竈門君は俺の家に通う時間を捻出しているらしい。
(なんか申し訳ないな……)
竈門君がいつ、食事を運ぶのに飽きるか知らないが、俺は早急に太るべきなのかもしれない。何しろ俺は運ばれてくる食事の費用を出してない。出すと言っても断られたし、受け取ってもらえないのだ。つまり、竈門家としてはひとり分の食費が増えたようなものだぞ。大変じゃないか。
(早く肉がついて、竈門君が満足しないかな)
俺はそう思いながら、自分の脇腹に触れた。最近は少し摘める気がするんだよな。この調子で上手いこと竈門君が納得する体型にならないかなと思っていたら、ぐいっと背中を押されて俺はびっくりした。
「わっ!」
突然、背中が伸びた。ぐっと視線が上にあがり、ない胸が張られる。それを俺にさせたのは竈門君だけど、いきなり何をするのだろうか。
「え?なに?」
「……前から思ってましたけど、先輩って猫背ですね」
「猫背?ああ、そうかも……?」
「健康に悪いです。バストアップには猫背の矯正も効果があるそうです。今日から猫背を直しましょう!」
「は、はい……」
キラキラした竈門君の目に押されて、俺はコクンと頷いた。しかし猫背の矯正でバストアップなんて……もしかしなくても、竈門君はマジでおれの胸を大きくするつもりなのか?この何もない断崖絶壁に丘を作ろうというのか?
「バストアップするストレッチも勉強したので、今日から始めましょう!」
「おお……?」
竈門君はそう言って折り畳みテーブルの上にあった食器を台所に運んでいく。そしてテーブルを付近で拭くと、折りたたんで壁に立てかけて俺を振り返る。先ほどまであったテーブルがなくなったので見事にストレッチをする空間が出来てしまった。
「じゃあ先輩、やりましょう」
「……はい」
この後輩を止めても無駄である。人の話を聞いているようで聞いていないし、我を押し通すところは押し通してくる。それを俺は身に染みて分かっているから抗うなんてことはせずに……のそのそと這いながら、開けた空間に移動した。
****
竈門極楽湯が一番混み合うのは、夕飯前の十七時、十八時だ。うちの常連は夕飯の前に風呂に入りに来る人が多い。多いのはやっぱり男性だけど、女性もそこそこ来る。夫婦で仲良さげにやって来るのだ。
「はぁー……炭治郎、今日もいい湯だったぞ。また来る」
「ありがとう、三郎爺さん。気をつけてくれ」
「分かってるよ」
近所に住む三郎爺さんを見送って、俺は時計をチラリと見た。三郎爺さんは十七時きっかりにやってきて、風呂に入り、談話室でのんびりして十八時半に帰る人だ。俺は三郎爺さんが帰るのを見て、時計を確認してやっぱり十八時半だと頷く。
俺は別に三郎爺さんが十八時半に帰るかどうかの確認を毎度しているわけじゃない。ただその辺りの時間になると俺の交代時間になるから、ついつい三郎爺さんを確認してしまうだけなんだ。
「……交代だよ」
「ありがとう竹雄」
家の勝手口から出てきた竹雄が、フロントにいる俺に声を掛けてくれる。俺はいそいそとフロントから抜け出ると、竹雄に手を振ってみるが、竹雄はふいっと顔を逸らしてしまった。
(ああ、今日もか。最近の竹雄はぶっきらぼうだな。……反抗期が来たんだろうか)
俺は竹雄の様子にううんと頭を捻った。竹雄ももう中学生だ。反抗期が来るのは成長の証なわけだけど、それを手放しで喜ぶには少し寂しい。ほんの少し前、秋の初めまでは兄ちゃん、兄ちゃんと俺を慕ってくれていたのに。
「ただいまー」
俺は勝手口を開けて家の中に入った。ここはもう、我が家の廊下だ。俺は家の奥に向かって声を上げると、六太がドタドタと走って来る。
「おかえりお兄ちゃん!」
「ただいま。夕飯食べたか?」
「全部食べたよ!おかわりもした!」
「そうか、凄いぞ!」
俺は六太の頭を撫でて、ダイニングに入る。ガラス戸の向こう側は居間になっていて、弟妹達がテレビを見ているようだった。竹雄が好きな番組をやっていて、見れなくなるのが不機嫌の理由かなと思ったけど、フロントにも小さいけどテレビはある。暇つぶしに向こうで見てるだろう。
「お兄ちゃん、今日も出かけるの?」
「うん。そんなに長居はしないけど行ってくるよ」
「……お兄ちゃん、最近、おうちでご飯食べてくれないね……」
「うっ……ごめん、六太……」
しょんぼりとする六太に俺は申し訳ない気持ちになる。確かに俺はここのところ我妻先輩の家に食事を運んでそこで食べるから、家で皆んなが居る中で食べるということはしていない。それがどうやら六太に寂しい思いをさせているのかも。でも俺が我妻先輩の家に行くのは責任を取るためだ。食事だけ置いて行くのも……なんかアレじゃないか?
「炭治郎、戻ったの?ちょっとこっちいらっしゃい」
「あ、うん」
母さんがひょこりと廊下の向こうから顔を出した。俺は六太の背中をトンと軽く撫でると、母さんの方に歩き出す。母さんは廊下の向こうに消えると、二階へと上がっていった。この時間ならだいたい一階にいるのに、どうしたんだろうと思いつつ後を追うと、母さんは箪笥がある和室の中へと入って行った。
「母さん?」
「炭治郎、これを持って行ってちょうだい」
「うん?」
俺は、追いかけて行った先の母さんが差し出してきた袋を手に取った。それはピンク色の分厚い手提げのビニールで、どこかのショップ名が書いてある。中身は何だろうかと覗いてみるが……なんだろう。服っぽいように見えるけど……。
「これ、なに?」
「育乳ブラよ。夜、寝る時に着けるブラジャーで、バストアップの効果があるの」
「バスト……えっ!?これ……ブラジャー!?」
俺はカッと赤くなり、取り出していたパッケージを袋にしまう。中身はピンクと白と水色のブラジャーだった。これが、これが例の育乳ブラ!?バストアップについて調べた時に検索上位に出てきた育乳ブラ!?
「え、な、なんで……」
「我妻さんに渡して頂戴。……二人で体型を変えようと頑張っているんでしょう?」
「う、うん……そうだけど……」
なんで母さんはそれを知っているんだ。俺は確かに我妻先輩の胸を大きくしようとしてるけど!流石に毎日出掛けるには理由を伝えなければと思ったから、母さんにはちゃんと「我妻先輩が痩せすぎてて心配だから、夕飯を持っていきたい!」と伝えてはあるけど!!
「あと生の林檎もバストアップにいい食べ物なの。台所にあるからそれも一緒に持って行って」
「え、いや、待ってくれ!なんで母さんは俺が我妻先輩の胸を大きくする手伝いをしているの知ってるんだ!?」
俺は大きく出てしまった声に慌てて口を閉じた。しまった。下に聞こえなかっただろうか。流石に我妻先輩のアレコレを吹聴するわけにはいかない。母さんは勘づいていたみたいだから見逃して欲しいけど。
「……それは、店のパソコンで検索履歴に残っていたから……」
「あ……」
「隠し事があるなら、ちゃんと隠しなさい」
「……はい」
そういえば店の帳簿をつけてるパソコンでふとバストアップの方法は何があるのかと思って調べたんだった。自分のスマートフォンでやれば良かった。いや、俺のスマホは六太がゲームしたりするから、それもマズイな。
「台所にタッパーに入れたお夕飯あるから。我妻さんに宜しくね」
母さんはそれだけ言って、俺を部屋に残して行ってしまった。店の片付けの準備を始めるんだろう。俺は手の中にあるブラジャーに困惑しながら立ち尽くす。
「……どう切り出せばこれを渡せるんだ?」
男が「ブラジャー用意しました!バストアップ効果あるらしいですよ!」なんて差し出してきたら怖くないか?いやでも、そもそも男がバストアップの手伝いしてること自体がおかしいのか?
俺はぐるぐる考えて、頭が痛くなりそうだ。ぼーっとしてしまうし、いっそ何も考えず手渡してしまうべきかとも思うけど、引かれたらと思うとそれも難しくて……。
「竈門君、もしかして具合悪い?」
「え?」
「いや……なんか、箸の進みが遅いし、今日はなんか生返事が多いし」
俺はハッと気がついた。いつの間にか我妻先輩の家にお邪魔している。ヤバい。あんまりこれまでの記憶がないぞ。でも目の前には食べ進めている食事の皿が広がっているから、俺は母さんと別れた後にちゃんと台所の料理をエコバッグに入れて、我妻先輩の家に来たみたいだ。
「いや、大丈夫です……」
「本当?無理しないでいいよ?明日の約束も……やめとこっか?」
「いえ!大丈夫です!元気いっぱいです!」
明日の約束を取りやめるなんてとんでもない!明日は日曜日で午前はまるっと暇がある。我妻先輩がせっかく誘ってくれたんだから、行かないなんて選択肢はない!
「平気だよ?ホームセンターに食器とか調理器具買いに行くだけだし」
「食器は重たいですよ。荷物持ちします」
「そーお?ありがとね?」
へへへと笑う我妻先輩に、俺はホッとする。今のところ我妻先輩の胸を大きくできた実感がないから、こうして物理的に役に立てる機会は嬉しい。けど俺が先輩に頼まれたことは『胸を大きくすること』だ。そこを叶えられなければ俺の償いはいつまで経っても本懐を迎えない。うん、そうだよな。どうやって手渡そうとか悩んでいる場合じゃなくないか?さらっと手渡してしまうべきじゃないか?そして一分一秒でも早く胸を大きくする為に、我妻先輩には今夜からでも育乳ブラを着けてもらうべきじゃないか?それが我妻先輩の為じゃないか?恥を捨てろ竈門炭治郎!!
「あの!我妻先輩!」
「ん?なに?」
「俺、ちょっと渡したいものがあるんです!」
俺はそう言ってペラペラになった状態のエコバッグを引き寄せた。このエコバッグは俺が我妻先輩の家に来る時にいつも使ってるもので、料理の入ったタッパーとか食器とか入れているんだが……ペラペラだな?中には何も入ってないと外から見て分かるくらいペラペラだ。
「……すみません。持ってくるの忘れました」
「あ、うん。だろうね。何も入ってなさそうだもん」
「明日、渡します……」
「ふ、ふふっ……うん。……あははっ…!」
我妻先輩はふすんと鼻息を出して肩を震わせている。渡したいものがあると勢い込んだのに持ってきてないのが可笑しかったんだろう。まさか俺も忘れてくるなんて思ってなかった。いや、母さんから手渡された衝撃で記憶が色々と飛んでいるから、普通に家に置いてきたんだろうけど。……台所に置いてきてないよな?
「……笑わないでください」
「ウィッヒヒ、ごめんごめん!」
ごめんと言いながらまだ笑っている我妻先輩に俺はムスッと眉間に力を入れたけど、すぐに力が抜ける。我妻先輩がこんなにおかしそうに笑っているの、初めて見たんじゃないか?先輩の笑顔はどことなく控えめで、人の様子を伺ったような遠慮したものが多い。少なくとも俺は先輩が肩を震わせてケタケタ笑うのは初めて見た。
「……はぁ」
なんだか力が抜けてしまった。笑いのツボにハマったのか、未だしつこく笑っている先輩につられて、俺もふふっと笑ってしまう。我妻先輩が楽しそうに笑ってくれるなら、忘れた甲斐があるんじゃないだろうか?
「なんて思ったけど、緊張する回数が増えただけだった……」
「ん?竈門君、何か言った?緊張する回数?」
「いえ、なんでもないです。フライパンなら安くて簡単に使えるテフロンの方がいいですよ」
俺は先輩が両手でそれぞれに掲げているテフロン加工のフライパンと、ステンレス製のフライパンの方から前者を推奨した。我妻先輩は料理は初心者みたいだから、使える期間が短くて買い替えが必要でも簡単に扱える方がいい。俺はリュックの中にある育乳ブラの存在を一回頭の中から追い出し、我妻先輩の買い出しの手伝いに注力することにする。
「そっか。竈門君がそう言うなら、こっちにする」
「はい」
我妻先輩はなんの疑問も持たず、ステンレスのフライパンを元の場所に戻した。まあ、そもそも性能云々を置いておいてもステンレスのフライパンは我妻先輩の予算オーバーだっただろうけど。
俺と我妻先輩は今、隣町に近いところにあるホームセンターに二人で来ていた。ここはうちも結構使うんだ。隣に農協のマーケットもあるから車で来て、洗剤やら掃除道具やら食材を一気に買い混んで帰る。車は母さんしか運転できないから、俺たちは今日は徒歩で来た。
「ホームセンターって色んなものあるね」
「そうですね。食器はこっちですよ」
「うん」
キョロキョロと辺りを見渡す我妻先輩が楽しそうなことについて来て良かったと俺は思った。最初、俺が誘われた時は「ホームセンター行ったことないから怖いんだよぉ!」と狼狽えていたからな。俺が一緒じゃなかったら、何がどこにあるとか分からず、何を買っていいか分からず、不安になって先輩は何も買わずに帰ってしまったかもしれない。
「おお、すごい。沢山あるなぁ」
「先輩、どんな食器欲しいんですか?」
「……どんな……?」
我妻先輩はピタッと止まると困った顔をした。この反応はさっきもしたな。フライパンや鍋のエリアで種類の多さに戸惑っていたのを俺は思い起こす。我妻先輩には調理器具がどれだけの種類があるかも、食器の形が何に適しているかも、たぶん、きっと曖昧なんだ。見る機会も、触れる機会も、教えられる機会もなかったから。
「……分かんない。何が必要なのかな……」
「とりあえず、少し深さのある大きめの皿なら何にでも使えますよ。カレーとかも入れられるし、肉料理とか、魚も入りますし」
「うん」
俺に言われるまま、我妻先輩は一人用の中皿を吟味し始めた。中皿といっても値段もデザインも色々ある。我妻先輩はしゃがんで「うーん」と唸っていて、俺はそんな先輩の薄い肩をじっと眺める。先輩は軽そうなダウンに長袖のカットソー、そしてジーパンというラフな格好だ。俺と同じような服装で、側から見たら男の子みたいな格好だが……その華奢さや薄さを考えれば女の子だ。俺は本当に、どうして先輩を男だと思っていたんだろうか。
我妻先輩の手や足を見れば、女の子であるのは一目瞭然だろうに。喉仏だってなくて、声は少しハスキーだけど俺を呼ぶときの声には不思議に甘さがある。たぶん、女の子だから……いや、性別は関係ないか?イントネーションの問題か?
「竈門君、ねぇねぇ、これとかどうかな?」
「えっ、わっ!」
「ん?」
しゃがんでいた先輩が俺を振り返って見上げてくる。その大きな瞳が俺をじっと見やるのに小動物らしい可愛さがあって、ドキッとしてしまい、慌てて視線を外してハッと気がついた。
「つけてないっ!?」
「んん?つけてない?」
俺は目に飛び込んできた光景に絶句した。我妻先輩は使い倒したカットソーを着ているのか、襟ぐりが随分と緩くなっている。あと多分、サイズが合ってない。だから我妻先輩が前屈みになるとガバリと開いてしまい、さらに上からその姿を見ている俺には中が丸見えだ。お臍の辺りまで丸っと見えてしまっている。
「先輩!!ちょっとこっちに!!」
「え、え、お皿は?」
俺は我妻先輩からカゴを取り上げて、ホームセンターの階段わきへと向かった。エスカレーターとエレベーターが完備されているから、あまり階段を使う人はいない。人目をしのぶにはいい場所なんだ。俺は我妻先輩を階段わきに連れてくると、カゴを一回床に置いて、背中からリュックを下ろし、中からピンクのビニール袋を取り出した。そしてそれを我妻先輩にずいっと押し付ける。
「先輩!今すぐつけてください!!」
「え?な、なにこれ?」
「…………ブラジャーです……」
「ブラジャー!?」
「ちょっ!声が大きいぞ!!」
「ごめんっ!!」
二人してワタワタして、辺りを見渡す。誰も気に留めていないようだ。俺たちはホッと息を吐くと改めてピンク色のビニール袋を見下ろした。俺はそれを我妻先輩に再度差し出す。
「夜、寝るときに着けるようの育乳ブラですけど……普段使いも出来ます。トイレで着けてきてください」
「えっ!なんで!?なんでそんなの竈門君が持ってるの!?あとなんでこ、ここで着けるの……?」
我妻先輩は困惑した顔で顔を赤らめ、襟元をぺたんと両手で押さえている。その反応を見るに……中を覗かれたのに気がついたんだな。俺は申し訳ないと思いながらも早めに気がついてよかったと思う。なぜなら、我妻先輩の胸は……たぶん、前よりちょっとだけ大きくなっている気がするんだ。前は本当に真っ平らだったのに、今はほんの少しふっくらとしている気がする。じっくり見ていないから分からないけど。そんな可愛らしい育ち始めの胸を他の人間に気がつかれたら可哀想だ。
「……これは、その、俺の母さんが先輩にって買ってきたものです」
「ま、待って!?竈門君、お母さんに俺の胸のこと話してるの!?」
「話してません!!断じて!断じて話してません!でも何かを察したらしい母さんがいきなり渡してきたんです!とりあえず貰ってください!」
我妻先輩は真っ赤になって言葉も出ないようだったけど、ビニール袋を受け取ると女子トイレに向かって走って行ってしまった。俺はそれにホッとしたけど、先輩は女子トイレに入る手前で止まり、少しウロウロして優先トイレのボタンを押した。
「ええ……?」
もしかして女子トイレに入って男と間違われるのを心配したのか?そこまでする必要はないんじゃないだろうか。けど裸を何回も見ても男だと思っていた俺が言えることではない。俺はしょぼんとしながら優先トイレに入っていく我妻先輩の背中を見ながら、早くもっと女の子らしい体つきにしてあげなければと心から思う。外出時に入るトイレに迷うなんて可哀想だ。大手を振って、自信を持って女子トイレに入れるようになってほしい。
「……頑張れ竈門炭治郎。責任を持って我妻先輩の胸を大きくするんだ」
先ほどチラッと見えた限りでは、見間違いでなければ、効果は出てきている。浮いていた肋も薄くなってきたし、小学四年生あたりの時の禰󠄀豆子くらいの胸の大きさはあった気がする。その年齢あたりで一緒に風呂に入らなくなったから記憶が曖昧だけど。
「……食事改善の効果、あったみたいで良かった」
俺は思わずぽつりと呟いてしまった。独り言はやめようと口元を抑えるが、じんわりと嬉しくなってきて口角が上がってしまう。我妻先輩にせっせと食事を運び続けて約二ヶ月。とうとう効果が出始めたのだ。
我妻先輩は、とにかく栄養状態が悪かったと思う。初めて食べているお弁当を見た時も思ったけど、明らかに弁当は小さいし、中身も偏っていた。米ばっかりで肉も野菜も少ない。それが心配になって、もっとバランス良く食事を取りましょうと購買のパンを食べさせながら提案したら、我妻先輩は困った顔で言ったんだ。
「俺、一人暮らしだから金ないの。学費とか家賃とか、そういうので手一杯なんだよ〜」
先輩は俺が重く受け止めないようにか、軽く笑ってそう言った。けど俺はどうして一人暮らしなのか、仕送りはないのかとか、先輩がこんなに栄養状態が悪いのに、家族は何も思わないのかと不安になって次々聞いてしまって……もしかしたら、我妻先輩を傷つけてしまったかもしれない。
「俺、生まれたときに親に捨てられてさぁ、施設育ちなんだよ」
先輩は種明かしのようにそう話してくれたけど、実際には大変な話だった。施設は十八歳までしか居られないこと、けど先輩は少し自分が神経質なところや、施設の中でどうにも相性の悪い相手がいて、陰で殴られたりする事があり、双方の精神に良くないので勉強して、キメツ学院の特待生の枠を勝ち取ったらしい。そして一部免除される以外の学費や生活費は自分でなんとかするという約束で施設から一人暮らしを認められて、今を過ごしている……という話だった。
「というわけで、進学費も稼ぎたいからバイトしなきゃだし、でも特待生から外れるとお金足りなくなるから勉強もしなきゃだし、そうなるとカツカツの生活になるんだよね。食費は削んなきゃいけなくてさぁ」
我妻先輩は俺が渡した菓子パンを綺麗に食べ終えた。二つ買ってきたそれは我妻先輩のお腹の中に収まってしまっていて、間違いなく、我妻先輩はお腹が空いているのだ。それに俺はどうしても悲しくなってしまう。
考えてもみて欲しい。子供がお腹を空かせてるんだぞ?我妻先輩はまだ高校生で、なのに自分一人で生きようと頑張って……結果お腹が空いているんだぞ!?
俺は先輩の境遇を聞いて、同情かどうかは分からないけど……とにかく先輩にお腹いっぱいになって欲しくなった。幸い、うちは食には困ってない。父さんに知り合いが多くて、あちこちから米とか贈られたりするし、大家族だから業務用系の食材を買うから安上がりになるんだ。だから俺は先輩の胸を大きくすると誓ったあの日から、せっせと我妻先輩に食べさせている。その結果、先輩は少しずつふっくらしていき……そしてとうとう、胸も僅かにふっくらしてきたというわけだ。
「か、竈門君……着けてきたけど……変じゃない?」
聞こえたか細い声に俺は過去に想いを馳せていた意識を今に戻した。振り返れば我妻先輩が恥ずかしそうに立っている。禰󠄀豆子や花子が初めてブラジャーをつけたときもこんな風にソワソワ恥じらっていたなぁ。
「変じゃないですよ!大丈夫です!でも前は閉めましょうか!今日は寒いですから!」
俺はそう言って先輩のコートのファスナーを上まであげた。先輩のカットソー生地が伸びているからか、薄らピンク色が透けてしまっている。今度は肌着もプレゼントしよう。
「じゃあ、買い物に戻りましょうか」
「うん。えーと、あとなに買おうかなぁ」
えへへと笑って弾む足取りで我妻先輩は売り場へと出て行く。俺はカゴを持ち上げるとその後を追おうとした。カゴの中には新しいフライパンや、鍋が入っていて少し重さがある。でもこの重さは先輩が料理に興味が出てきた証拠だから、嬉しい重さだ。お金がないから食事を疎かにしていた我妻先輩だけど、作ってきて貰うばかりは美味しいけど、悪いからと言って自炊を少しずつ始めるつもりのようだった。
施設では給食室のようなものがあって、子供は調理に参加しないから一人暮らしをしても料理をどうしたらいいのか分からなくて手が出せなかったようだ。だから弁当の中身が米ばかりだったらしい。
「皿はさっきこれと、えーと……あと、茶碗?」
「茶碗は家にありましたよね。新しくするんですか?」
先輩と二人で食器売り場に戻ってきて、選び途中だった皿をカゴに入れた。すると先輩は平皿の横にあった茶碗にも手を伸ばして俺を振り返る。先輩の手の中にあるのは緑色の綺麗な茶碗だ。意外だな。先輩は持ち物、黄色が多いのに。
「いや、竈門君のぶん。毎度、自分の食器をうちに持ってくるじゃん。割れると危ないし、いっそのこと俺の家に買っておいたら便利かなって思って……あ、お椀も買おう」
我妻先輩はそう言って大きめのお茶碗とお椀、そして箸とマグカップをカゴに入れていく。俺はそれにちょっと呆然として、そして……なんだか喜んでしまったけど、ダメだダメだ!それはダメだ!先輩が頑張ってバイトして稼いだお金を俺なんかに使うべきじゃない!
「いや!大丈夫です!俺、自分で買います!」
「ええ?いやでも……」
「ダメです!先輩のお金は自分の為に使ってください!」
俺はそう言って頑なに首を振った。我妻先輩は俺を上目遣いで見上げながら、不満そうに首を傾げている。そんな可愛らしい表情してもダメなものはダメだ。そもそも我妻先輩の家で食事をしているのも、俺の償いの一環なんだから。食器も持参が当たり前じゃないか?俺のものを置いたら、先輩の家の収納スペースを減らしてしまう。
「でも、竈門君にブラジャー買ってもらったから。そのお礼も兼ねてさ。ね?」
「っ……!!」
いつの間に距離を詰められたのか、我妻先輩は俺の耳にそう吹き込んだ。潜められた声と漏れ出た吐息に俺はぶわっと肌が粟立つ。なんだか突然、恥ずかしくなって固まってしまう。
「じゃあ買ってくるな〜」
「あっ!」
我妻先輩は俺の硬直に気がついているのかいないのか。カゴを奪い取るとレジに小走りで向かって行ってしまった。俺はドクドクと速まる心臓に息を一つついてから、急いで我妻先輩の後を追った。ブラジャー、俺が買ったんじゃないんですってば!!
****
生まれた時から施設育ち。俺には普通だけど、これが普通だと思えない人は世の中にたくさんいるんだろう。けど俺に親がいないのは当たり前で、俺のことを特別に抱きしめてくれる腕がないのも当然で、そうなると人の熱すら貴重だった。
人との触れ合いすら不足している俺だ。それはもう、色んなものが足りない。教科書や図書室のテキストが教えてくれる公式や文法は理解できるんだ。勿論、理解させる為に書いてあるからな。でも他のことは分からないものが多い。
例えば洗濯の仕方とか、掃除の仕方とか、料理の仕方とか。道具もどれを使えばいいとか、そういうことは学校でもちょっぴりしか教えてくれなくて、あとは家で教えてもらってねって感じ。
でも施設じゃそんなの教わらない。教えてくれるところもあるのかもしれないけど、俺のところじゃ教えてもらえなかった。物の買い方も、下着の選び方も全部全部、分からない。体験した事ない。習った事がない。だから今の俺の状況も、よく分からないんだよな。
「……ひ、ひぎゃああああ!! えっ!? なにこれ!? なにこれ!? 何これぇぇぇ!?」
俺は目が覚めて、ヒヤッとした感覚を不思議に思って布団を捲ったら中は血の池地獄だった。シーツが真っ赤に染まってる。あと、俺のパジャマのズボンも赤い。ヤバいくらい赤い。
「えっ、あっ、えっ……!?」
俺はなんの病気だとパニックになってスマホを手に取った。病院、救急車に連絡かと思って緊急電話のボタンを押しそうになったが……迷う。救急車を呼んだら、施設に連絡が行くんじゃないか? もし病気で、一人暮らしはダメって言われたら、施設に戻らなきゃいけなくならない?
「っ……!」
俺は緊急電話ではなく、メッセージアプリを立ち上げると上の方にある『竈門くん』のアイコンをタップする。どうしたらいいのか分からない。病院に行くべきなのか、救急車を呼ぶべきなのかを自分で決められなくて、俺はいま、唯一頼れる相手である竈門君に相談することにした。きっと竈門君なら、たくさん兄弟と家族がいるまともな竈門君なら、俺が今どうすべきなのか教えてくれる筈だ。
アプリの電話機能を使ってコールをするが、三回、四回と鳴っても繋がらない。朝の時間だから忙しいのかな。スマホに気がついてくれないかな。竈門君に見捨てられたら、俺、俺、どうしたらいいんだよぉ!!
『はい、もしもし?』
なんて思って震えていたら電話が繋がった。俺はそれに安心して目からビャッと水が出たけど、同時に股のあたりからゴボッとなにか出た気がする。
「ひぎゃあああああ!!」
『えっ!? どうしたんですか我妻先輩!? 』
俺はギュッと膝を抱えて鼻を啜った。じわじわと湿ってるのって血が出てるの? なに? なんで? どっか怪我した? お腹痛い。
「うっうっ……竈門君……今までありがと……」
『えっ? 』
「俺、俺、今日、出血で死ぬかも……」
『えっ!? 怪我したんですか!? 』
頼るつもりで電話を掛けたのに、死に際の言葉を残すみたいになってしまった。でも布団が真っ赤になる程の出血ってこれもうダメだろ。死ぬだろ。俺は竈門君に心の中でごめんよぉと謝りながら、俺の最期の言葉を聞かせる。
「俺、俺、竈門君に……ううん。炭治郎に会えて良かったよ。裸見られたの恥ずかしかったけど、炭治郎と仲良くなれたし……悪くない人生だったよ……」
『いやいや! 待ってください! 何があったんですか!? 』
ドタンバタンと電話の向こうから大きな音が聞こえる。俺は何してるのかなと思いながら、炭治郎にお礼を伝えた。言えるときに言うべきだ。あとどれだけ、俺は生きてられるか分からない。今もまだ、血が出てるみたいだし……止め方分かんないし。
「一緒にご飯食べてくれてありがとね。いつも本当に楽しくて、嬉しかったんだ。買ったばっかりのお茶碗、あんまり使えなかったのと、料理練習して、上手になったら炭治郎に何かご馳走してあげたかったけどできそうにないのは心残りだけど……」
炭治郎は俺にたくさん温かい思い出をくれたから、少しでも何かを返したかった。炭治郎は俺を男と思って裸を見るだけでなく撫で回したのを気にしてるみたいだけど、生まれた時から施設育ちで人の熱が貴重だった俺には、炭治郎の伸ばしてくる手は得難いものだったんだ。それが恥ずかしいところを撫で回されるものだとしても、肌に触れられることに嬉しさを感じてしまったんだ。
炭治郎には恥ずかしくて言えなかったけど、俺、触られるの気持ちよくて通ってたんだ。恥ずかしくて嫌だったら、行かなきゃいいだけだもん。でも俺は予約を取ってくれたからって言い訳して、炭治郎の手のひらの熱を貰いにいってたんだ。
「たんじろぉ〜俺が死んでも、俺のこと忘れないでくれよな〜。一生覚えてろとかは言わないから、三年くらいは忘れないでくれよぉぉぉぉ。頼むよぉぉぉぉ」
そう言ってべそべそと泣いていたら、ドンっと大きくドアが叩かれた。それにびっくりして肩が跳ねる。その途端にまたドバァと何かが股から流れて俺は悲鳴のような泣き声をあげた。
「ひぇぇぇぇぇん! 死にたくないよぉぉぉぉ!」
「『我妻先輩!! 』」
ドカンという音がして、続けざまにスマートフォンのスピーカーからも、玄関の方からも炭治郎の声が聞こえた。俺はびっくりして玄関の方に顔を向ければ、狭い部屋だから炭治郎の姿がすぐに見えた。あれ? 俺、玄関に鍵かけてたよね? もしかしてドア壊した?
「か、竈門君!?」
「我妻先輩! 何があったんですか!? どこを怪我したんですか!?」
「わ、わ、分かんない……お、お腹……?」
「お腹!?」
竈門君は勢いよく、ズカズカと部屋に上がってくると俺の布団を捲り上げた。その瞬間に、覗き込んだだけで怖くて蓋をしていた真実が詳らかにされる。俺は怖くて怖くて目を閉じて手のひらを顔に当てた。横からは竈門君が息を呑む音がして……そしてバサリと布団が床に落ちる音がした。
「…………あ、これ、生理か……?」
「え……?」
「いや、たぶん……我妻先輩、生理の日じゃないですか? これ……たぶん……」
竈門君の言葉に俺は手を下ろして目を開けた。生理、生理、生理? 生理ってなんだって? あ、あれか。股から血が出てくるやつ?
「これが生理なの? なった事ないから分からない……」
「え」
竈門君は膝を抱えて小さくなる俺をしげしげ見て、そして耳まで真っ赤にするとバタバタと玄関の方に向かって行ってしまった。俺はそれに置いていかれたのかと慌てて振り返るが、竈門君はどこかに電話をしているだけのようだった。
「もしもし、母さん? あの、我妻先輩が……は、初めて生理がきたみたいで……ちょっと来てほしいんだ。俺だとどうにもできない。うん、うん。分かった。とりあえず、風呂を用意すればいいんだな? うん、待ってるから」
竈門君は電話を切ると、また俺の方に戻ってきた。そして俺の膝に布団をかけ直す。今気がついたけど、掛け布団も血で汚れてるな。布団、もうダメかも。どうしよう。
「先輩、今から俺の母が来るので……」
「うん……」
「お風呂を用意しておけと言われたので、お風呂にお湯を張りますね」
「うん……」
「……じゃ、じゃあ!」
竈門君は真っ赤な顔でそう言うと、俺の狭い家の風呂場のドアをピタリと当てて中に入って行った。ジャーっと勢いよく水が出る音がする。俺はその音を聞きながら、じわじわと今の状況を理解していった。そうか。生理、生理ですか。ほーん? なるほどなるほど?
「恥ずかしっ……!」
俺は布団の掛かった膝の上に顔を埋めた。十七にもなって生理も分からないとか呆れられたかもしれない。朝から大騒ぎして、ものすごく恥ずかしい。
え? これ、竈門君に対するセクハラじゃない? うわー。やってしまったわ。本当に申し訳ない……! というか今まで生理なんて一回も来た事ないじゃん! なんで今日来た!? 来るならくるよーって事前に教えてくれ!! ナプキンとかうちにないから!!
「我妻先輩。母さんがこの近くまで来たみたいなので迎えに行ってきます」
「あ、うん……」
竈門君は玄関の方に行くと靴を履いて、ガタガタととドアを動かしている。俺は布団の位置からその姿をじっと見て……なんかドアが一枚の板みたいになってない? え? もしかして壊れてない? その扉、大丈夫?
「……我妻先輩」
「……うん……」
「すみません。開けたときに、ドアを壊してしまったみたいです」
竈門君は青い顔してそう言った。うん、なんとなく、そうなんじゃないかなって分かってたよ……。
****
「まだご飯おかわりあるー?」
「あ、それ私が食べようとしてたのに!」
「早い者勝ちだろー?」
「わぁ……」
俺は目の前できゃいきゃい繰り広げられている光景に感嘆の声が漏れてしまう。こんなに和気藹々と楽しそうな食事風景のご家庭って本当にあるんだな。
「我妻先輩、大丈夫ですか?」
「えっ!? 大丈夫だよ!?」
こそりと隣から聞こえた声に、俺は取り皿の上にある料理をちまちまと食べた。最初に竈門君が装ってくれたから十分な量がある。
俺は大家族の食事風景に感動しつつ、葵枝さんと禰豆子ちゃんが作ってくれたご飯を食べた。二人は今は銭湯の仕事をしてるらしく不在だが後で美味しかったと伝えなければ。いつも家で頂くのも美味しいけど、出来立てってすごく美味しいんだなぁ。竈門君、俺の家に来てないで出来立てを食べればいいのに。
「あ、兄ちゃん達いちゃいちゃしてる〜!」
「こら! そういうこと言わないの!」
三男の茂君のからかいを次女の花子ちゃんが諌めた。でも花子ちゃんも俺と竈門君の方をチラチラ見てくるから、興味はあるんだろう。まあ、お兄ちゃんの学校の先輩がいきなり家にやって来て「今日は泊まります」なんてことになったら驚くよね。
俺は朝目覚めて、生理なんてもんが来たおかげで今日は竈門家にお世話になることになってしまった。なぜかというと、俺の家の玄関が壊れたからだよ。俺がパニックになって竈門君に変な電話を掛けてしまった結果、電話を受けてやっぱり慌てた竈門君が鍵の掛かった玄関を蹴飛ばして入ってきてしまったのだ。古い木造アパートだ。男子高校生のマジ蹴りに耐えられなかったらしく、ドア枠ごと外れていた。
結果として修理しないとダメということになってしまい、竈門家が費用を払って直してくれるらしい。大家のおばあちゃんは「古いからねぇ」と笑っていたけど、笑い事じゃないだろ。
というか、俺って物凄く竈門家に迷惑掛けてない? お金使わせすぎてない? 毎日毎日さぁ、食費だって馬鹿にならないだろ。こんなに子供がいて、こんなに沢山料理があるのにどんどんなくなっていくんだぞ? 俺に食費を割いてる場合じゃなくない? それなのに壊れたドアの費用や、ナプキンとかも沢山くれて……こうして家にも泊めてくれて……ヤバい。そろそろいい加減にしてくれと言われてもおかしくないのでは!? やだやだ!! 俺、友達少ないんだよ! 炭治郎が構ってくれなきゃ明らかに会話量が減るぞ!? 学校でも友達多いわけじゃないんだからな!?
「うぐぅ……」
「どうしました? もしかして、具合悪いですか?」
「いや、大丈夫……」
確かに生理痛やらで腹は痛いけど呻いたのはそれが理由じゃない。ちょっと罪悪感が出てきてしまっただけだ。竈門君はあまり気にした様子ないし、せっせと俺に良くしてくれるけど……竈門君の弟や妹達は俺のことどう思ってんだろ。竈門君のお母さんも生理で狼狽えてた俺を優しく介抱してくれたけど……本当は呆れてない? 困ってない? 竈門君なんて自慢の息子だろ? それがこんな妙ちきりんな女に振り回されてるの嫌な気持ちにならない? 大丈夫? 心配になってきた……!!
「……なんか、意外だなぁ」
「ん? 竹雄兄ちゃん、何が?」
斜め向かいに座ってる次男の竹雄君がご飯を口に入れながら呟いた。それを隣にいる茂君が唐揚げを取りながら聞きかえしている。
「いや、兄ちゃんは女子アナっぽい人が好きなんだと思ってたから。我妻さん、めちゃくちゃボーイッシュじゃん。だから意外だと思っ…イテッ!?」
シーンっとその場が静まり返った。なぜなら、竈門君が立ち上がって竹雄君の頭をガツンと殴ったからだ。突如起きた暴力事件に俺はびっくりしてしまう。
殴ったと言っても、勢いよくではなく、グーで脳天をごつんとした感じだけど。でも周りの子達も固まってるのを見るところ、お兄ちゃんの突然の行動にびっくりしたんだろう。竹雄君もびっくりした顔でしてるし。当の竈門君は……強い表情で悲しそうな顔をしていた。
「……人の見掛けを比較するような事を言うな。……いきなり殴ってごめん」
「…………」
変わらずシーンとする食卓。完全にお通夜だ。お通夜になんて出た事ないけど、これくらい静かなんじゃない? え、嘘でしょ? 居た堪れないんですけど……? こ、この空気どうすんの!?
「竹雄ー。そろそろ交代できるー?」
固まった空気を動かしたのはダイニングに入ってきた禰󠄀豆子ちゃんだった。たぶん、交代の時間だったんだろう。じんわりと固まった場の空気が緩む。い、息が詰まるかと思ったわ……!
「禰󠄀豆子、俺が交代するよ」
「え? お兄ちゃんが?」
「うん。我妻先輩を頼むな」
竈門君はそう言って食器をキッチンに運んで、ダイニングを出て行ってしまう。いや、竈門君だけこの空間から脱出するんかい!! 俺は引き続き、竹雄君と微妙な空気を味わう羽目になってるんですけど!?
「……何かあったの?」
禰󠄀豆子ちゃんも部屋の空気がおかしいのを察したんだろう。竹雄君がバツの悪そうな顔をしたが、いち早く回復したらしい花子ちゃんが「聞いてお姉ちゃん!」と眉根を寄せた。
「竹雄お兄ちゃんが善逸さんのこと悪く言ったのよ! それでお兄ちゃんが怒ったの!」
「え?」
「悪くなんて言ってない!! ただ、その、兄ちゃんはお淑やかそうな人が好きなんだと思ってたから、我妻さん連れてきて意外だなーと思って……」
「あっ! またそんなこと言って! 失礼でしょ!!」
「今のは説明だろ!!」
ギャアギャアと言い合う花子ちゃんと竹雄君に、禰󠄀豆子ちゃんは「静かにしなさい!」と叱った。腰に手を当てて少し前傾姿勢になった姿はまさに『お姉ちゃん』だ。俺は禰󠄀豆子ちゃんのお姉ちゃんという姿にちょっと感動する。
だって、こんなにも可愛い子がお姉ちゃんしてるってもう凄い可愛いじゃん。何を隠そう、俺は禰豆子ちゃんの外見も内面もドストライクに好きなんだよ。
「ごめんなさい善逸さん。弟が失礼なこと言って……」
「え、いやいや! 俺が女らしくないのは事実だし……」
何しろ口調がそもそも女らしさのかけらもないからな。竹雄君のは俺を見て思った素直な感想なんだろうし。
「……あの、ごめんなさい。我妻さんを悪く思ったわけじゃなくて……」
「いいからいいから! 大丈夫!」
竹雄君は少ししょぼんとしたようにしていて、俺は気にしなくていいのだと手を振った。そんなに申し訳なさそうにされる方が困る。でも竹雄君はギュッと眉根を寄せると心底後悔したような溜息を吐いて箸を置いた。
「いや……ううん、本当にごめんなさい。兄ちゃんが怒るのも当然だよ。自分の彼女に対して、好みのタイプと違うんじゃないかとか……本当にごめんなさい」
「え、いや、うーん……えっ? 彼女?」
真面目に謝罪してくれてる竹雄君には申し訳ないけど、今なんて言った? 彼女って誰が? 誰の?
「え? 誰が誰の彼女?」
「「「「「え?」」」」」
****
「かーまーどーくーん!!」
「あ。我妻先輩、どうしました?」
竈門家の自宅と竈門極楽湯を繋ぐ扉を潜って少し歩けば、すぐにフロントで、竈門君は常連さんらしいおじさんにお釣りを渡そうとしているところのようだった。
「ごめん、後でいいから……」
「あーいいよいいよ! 続けて続けて! なんだ炭治郎、お前とうとう彼女出来たのか? これなら竈門極楽湯も安泰だ! 葵枝さんも一安心だな!」
「ちょ、ちょっと! 違いますよ! この人は俺の学校でお世話になってる先輩です!」
竈門君はワタワタと言い訳をし始めて、俺はスンッと熱が引く。なんだろうか。俺は竈門君に「弟と妹に俺のことなんて説明してんだよ!!」と詰め寄りに来たわけなんだけど……詰め寄る前に回答を聞いたような気分になったわ。これはアレだな。俺の家に毎晩通う理由は弟と妹に何も話してないってパターンだな? 把握したわ。
竈門君を揶揄ったおじさんは更衣室の方へと行ってしまった。竈門君は恥ずかしそうにしながら、おじさんを見送って俺の方を振り返る。
「えーと、すみません。なんですか?」
「いや……えーと、さっきのことだけど……」
「はい?」
「竹雄君、謝ってくれたから……その、もう竈門君も怒んなくていいからね」
「あ……」
竈門君はパチンと瞬いて、そして困ったように笑って頷く。俺は竈門君がもう怒ってなさそうなのに安心した。俺のせいで兄弟仲が悪くなるのとか勘弁してほしい。そんな事になったらとんでもない業を背負って生きる事になってしまう。
「竹雄が言ったこと、本当にすみません。なんで竹雄があんなこと言い出したのか、分からないくらいで……」
「いやまあ、お兄ちゃんが彼女を連れてきたと思ったら男みたいな女だったからびっくりしたんだろ?」
「え?」
俺の言葉に竈門君は不思議そうな顔をした。それにやっぱりなと思う。竈門君がなんの説明もしないで俺のところに毎晩通っているから……竈門家の良い子たちはお兄ちゃんに彼女ができたと思っていたのだ。
「彼女?」
「うん。俺が竈門君の彼女じゃないって知って、皆んな驚いてたよ」
「えっ!? 彼女!? 我妻先輩が!? 俺の彼女!?」
「おいやめろ! 心外です、みたいな反応やめろ!! 傷つくだろ!?」
竈門君が信じられないみたいな顔をしたのに、胸の真ん中辺りがぐわんと揺れた。そして次第にズキズキ痛むのに、俺は唇を突き出して不満そうな顔を隠さずに見せる。こちとらお年頃なんだ。やっぱりその、男の子に『彼女なんてあり得ない』みたいな態度を取られると腹立つんだよ。まあ、確かに俺が竈門君の彼女とか……あり得んけどさぁ。だってほら、俺って竈門君の弱み握ったみたいな感じだし……。
「え、いや別に……心外なわけでは……。むしろ俺が我妻先輩の彼氏という方が問題かと思って……俺はその、罪人ですし……!」
「罪人!?」
「先輩を辱めてしまったので……!!」
そこまで思い詰める必要はあるのだろうか。俺はこの話はもうやめようと、竈門君の横にある椅子に座る。ふうん? フロントから見る景色ってこんな感じなのか。ロビーで楽しそうにしているおじさん達が見えるな。
「……」
「……」
「……」
「……」
気まずっ……! なんでここに座ったんだよ俺は! さっさと戻ればよかったのに! でもあの会話の流れで「それじゃあね」なんて去るわけにもいかねぇし! なんか、なんか気の利いた会話ないか!?
俺はうーんと唸りながら目線を動かしていると、二十代前半らしきお姉さんがこちらに向かって手を振っていた。それに頭を下げる竈門君を見て、俺もフロントに座っているのだからと頭を下げる。お姉さんは綺麗なウェーブが掛かった髪を靡かせながら十二月の寒空の下へと出て行った。
「……そういや、竈門君は女子アナみたいな人がタイプなの?」
「えっ!?」
「いや、女子アナが嫌いって男はそもそも少ないか」
女子アナってもうジャンルの一つだろ。清潔感あって、印象がいいし、タイプじゃなくても悪い気はしないよな。
「別にその、特別女子アナがタイプというわけでは……」
「いいなぁ。俺も今のお姉さんみたいに髪の毛伸ばしてみようかなあ」
そう言って髪の毛先を摘んでみる。そういえば生まれてこの方、髪を伸ばしたことがないな。金髪だと派手だから、あまり面積を広げるのが躊躇われたし、シャンプーやリンスとか手入れも大変になる。やっぱり時間も手間もお金も掛かるしな。今みたいに自分で適当に切るのもできなくなるかもしれない。やめとこ。
「伸ばすんですか? 先輩の髪、綺麗な色しているから絶対に素敵ですよ」
「そーお? ふへへっ♡ じゃあ伸ばそっかなー♡」
持ち上げられたら俺は盛大に調子乗るぜ? 竈門君の絶対に素敵という言葉に気分が良くなって髪を伸ばす事を決めた。
そうだよ。髪を伸ばしたらちょっと身体が貧相でも女の子っぽく見えるんじゃない? ボーイッシュな印象は払拭されるんじゃない? 胸を大きくするよりお手軽で確実じゃん!
「俺の髪が伸びたら、竹雄君も見違えるんじゃない? 流石にボーイッシュとか言われないよね? ねぇ、竈門君もそう思うでしょ?」
「…………」
横を振り返ってみれば、竈門君はぷくっと頬を膨らましているじゃないか。何その顔と思ってびっくりしていると、竈門君はつまらなそうに言った。
「竹雄のことは名前で呼ぶのに、俺は竈門君なんですね」
「ん?」
「俺の方が我妻先輩と付き合いが長いのに」
竈門君はぶずっとした声でそう言って、そしてじわじわと赤くなっていく。竈門君はとうとう大きな手のひらで自分の顔を隠してしまった。でも赤く染まった耳は全然隠れてない。俯いた時にカラリと耳飾りが鳴る。
「……し、下の名前で呼ぼうか?」
「……はい」
ポツリと聞こえた竈門君の声を打ち消すように、「あっちいなぁ〜!」とダミ声のおじさんの声がフロアに大きく響いた。竈門極楽湯のお風呂から出ると、体の芯までポカポカになるもんね。と、俺は入ってもいないのにポカポカと体を手を煽いだ。
****
「おはよー今日って英語、小テストあるよな?」
「やべ、体操着忘れたー!」
「ねぇ、放課後遊びに行かなーい?」
いつも通りざわついた通学路をのんびり歩く。四月に入ってきた新入生達もそろそろ制服が小慣れた頃か。ゴールデンウイークも明けて、また授業が始まり、中間テストまでの束の間の日常だ。テスト期間になれば、この登校風景もほんの少し雰囲気が変わる。
去年のことを思い出しながら、俺は校門に差し掛かった。今日もいつも通り、風紀委員の人達が服装チェックをしている。テスト期間中は委員会もなくなるので、来週には彼らが校門に立っている姿もしばし見られなくなるんだけど、それを少しだけ寂しく思うのは俺だけだろうか? 俺は通学路の真ん中を歩いていたのを、少しずつ右側に進路をとった。
キメツ学院は女子校舎が右側にあるので、女子の風紀委員も右側に集まっていることが多い。特に男子が左側通行、女子が右側通行と決まっているわけではないから、なんとなく左側の方が空いてしまう傾向があった。
それはやっぱり男子生徒達に、女子生徒との青春を楽しみたいという願望があるからだろうか。二年に上がって余裕が出てきたのか、クラスでも「彼女が欲しい」という言葉をよく耳にするようになった。
チラホラとクラスメイトや見知った顔の男子生徒が女子の風紀委員の方へと吸い寄せられていくのに、俺は「うわぁ」とちょっとだけ思う。まあ、俺も右側に向かっているんだけどな。だけど俺はちゃんと用があるし、女子の風紀委員に用があるんじゃない。誰でもいいわけじゃない。
「善逸、おはよう」
「炭治郎! おはよ〜」
怠そうな顔で仕事をしていた善逸が、俺を見つけて笑ってくれた。その変わりようについつい、俺も嬉しくなってしまう。だから二人で向かい合い、ふふふと笑いあうが、風紀委員である善逸はいま忙しい時間だ。善逸は細めていた瞳をパッと丸く戻すと、肘に掛けていた保冷バッグを差し出してくれた。
「はい、今日のやつ」
「ありがとう」
お礼を言って受け取れば、善逸は「どういたしまして」と軽く手を振ってくれる。それでもう、この場はお終いだ。もっと話をしたいと思うけど、今はできない。あとは放課後のお楽しみだ。二人で「じゃあ」と言って手を振り合い、俺は校門の中に入り、善逸は風紀委員の役目に戻っていく。
名残惜しいけど、邪魔しちゃいけないと保冷バッグを揺らさないように気をつけながら校舎に向かっていると、ばしんと背中を叩かれた。振り向けばクラスメイトがいて、ニヤニヤとした顔で俺を見ている。それに「またか」と思いつつ、気にせず昇降口へと歩き続けた。
「おはよう」
「おーっす。お前、見たぞ〜! 我妻先輩にまーた弁当貰ってただろ!」
「……まあな」
「なんだよその『タメ』は!! 勝者の余裕か!?」
「いてててててて」
ぐいぐいと脇腹を肘で押してくるクラスメイトに「そんなんじゃないよ」と白旗を上げつつ上履きを自分の下駄箱から取り上げた。クラスメイトは納得いかない顔しながらも「俺も我妻先輩みたいに優しい彼女ほしー」と二個離れた下駄箱の前でボヤいている。
「そんなんじゃないよ」
「ん? なんか言ったか?」
俺の小さすぎる呟きはクラスメイトに届かなかったらしい。俺はクラスメイトの誤解を完全に解くことを早々に諦めて、靴を履き替えた。
「なんでもない」
俺と善逸が名前で呼び合う仲になって、四ヶ月経った。名前を呼び合う辺りから伸ばし始めた善逸の髪は今はもう、肩先に触れるくらいだ。顎下から長さが数センチ伸びただけで、こんなにも人からの評価が変わるのだと俺は驚いている。
「なんだよ竈門ー。まーた彼女見てるのか?」
「うーん」
相槌とも肯定とも取れる曖昧な返事を返しながら、俺は教室の窓から風紀委員の職務を全うする善逸の姿を眺めていた。朝の太陽に照らされる善逸の髪はキラキラ輝いていて綺麗だ。僅かな光の反射を見ているだけでも、どこか楽しい気持ちになる。
「彼女もちは羨ましいぜ」
「俺も勝ち組になりてぇ〜」
「…………」
俺は春になってからクラスメイトが俺を揶揄うのに、人の見た目はこんなにも反応を変えるのだと少し驚いている。善逸が髪を伸ばし始めた頃は何も反応をしなかったのに、春になり、髪の長さが、あまり男子生徒には見られないものになった頃、そして暖かくなってコートを脱いだからだろう。周りは善逸を『女の子』と見るようになった。
冬はコートを着て外に立っていたから体型が分からなかったのだろう。去年の春から秋は善逸の体はガリガリで制服がダボついていたので体つきはまるで分からなかった。しかし栄養状態が良くなって、定期的にきちんと生理がくるまでになった善逸は、すっかりとフォルムが柔らかくなった。明け透けに言ってしまえば、胸部と臀部に丸みがつき、でも腰はくっと細く肩も薄い。男とはまるで違う体型に、きっと誰もが見た目で性別をはっきりと認識できるようになったのだ。
その結果、いつの間にか俺は他の男子生徒に羨ましがられるようになった。男女で別学になっているうちの学校は、女子と触れ合う機会は少ない。高校生ともなれば、女子との触れ合いが気恥ずかしいよりも、積極的にしていきたいと思考する男は多い。俺は別に女子と積極的にどうこうなりたいとは……思ってないけど。
俺は予鈴が鳴るから仕事を切り上げて校舎に戻ろうとしている善逸をじっと見つめる。すると善逸は間違えずに俺の教室の方を見て、そして嬉しそうに笑って手を振った。俺はそれに口元を緩めて手を振り返す。
「いちゃいちゃすんなよ、この! 早く退け!」
「あいてっ!」
クラスメイトが俺のふくらはぎを蹴った。いちゃいちゃしているつもりはないんだけどな。でも俺はそれを口にすることもなく、予鈴が鳴ったので窓から離れる。なにしろ俺の席は入り口側だからな。退かないと、俺のふくらはぎを蹴った生徒が席につけない。
俺は黒板の上に設置された時計を見て、ひーふーみーと時間を数える。あと四時間もしないうちに善逸の作ってくれたお弁当を食べて、それから三時間ちょっとしたら下校時間だ。俺は今日も頑張るぞと気合を入れ、中間テストで補習になんてなりたくないと教科書を取り出した。
「あれ? 今日は長男と次男坊? 善ちゃんいないの?」
「いますよ。家で禰󠄀豆子と夕飯作ってます」
「なんだ花嫁修行中か。竈門家はしっかりしてんなぁ」
「違いますよ。そんなんじゃないです」
「はい、マサさんお釣り」
竹雄の差し出すお釣りを受け取ると、常連客のマサさんは「善ちゃんに宜しくね〜」と言って更衣室に行く。俺はそれにうーんと心の中でモヤモヤした感覚を抱えながら見送った。
「知ってたけどさあ。やっぱり善逸さん、常連のおっさん達に人気だね」
「うっ」
横からきた竹雄の包み隠さない言葉に俺は身体が僅かに固まった。俺が思っていたモヤモヤを的確に突いてくる竹雄は冷静で観察眼がある。
「善逸さんの代わりに俺がここに座ってるだけで、一体何人のおっさん達が声掛けてくるんだよ」
「えーと、今日は五人かな?」
「多いよ。はー……すっかり善逸さん、竈門極楽湯のおっさんのアイドルじゃん」
「……うん」
竹雄が呆れたように言うのに、俺も同意する。いま、ここ竈門極楽湯では空前の善逸ブームなのだ。どういうことか説明すると、俺と善逸が名前で呼び合うようになった頃から、善逸は俺の家で過ごす時間が増えたのだ。今までは俺が善逸の家に通っていたけど、善逸に初潮がきた時のゴタゴタで俺以外の家族とも縁ができた。
母さんもそれはまでは少し遠慮気味だったけれど、接点が増えたからか露骨に善逸を心配するようになったし、弟や妹も善逸になつき始め、そうなれば押しに弱いところがある善逸は誘われるがままに我が家に遊びに来ては夕飯を共にしたり、禰󠄀豆子や花子の部屋に泊まったりするようになった。
すると優しい善逸は「銭湯の仕事、簡単なものなら手伝うよ」と言ってくれて俺とフロント作業したり、フロア掃除したりするようになり、あれよあれよと言う間に常連客の人達に顔が知れ、顔が覚えられ、すっかりおじさん達に気に入られてしまったのだ。
「まあ、姉ちゃんや花子は常連のおっさん達からすれば娘みたいなもんだもんな」
「そうだなぁ。古い常連さんからすれば、禰󠄀豆子達は赤ちゃんの頃から知ってるからな」
父さんや爺ちゃんの代から通ってくれてる人達からすれば、禰󠄀豆子と花子は『若い女の子』という枠には入らないのだろう。玉のように見守る対象で……その結果、善逸は見事に竈門極楽湯の『若い女の子』枠にハマってしまった。俺は常連客とはいえ、あまり善逸に色めき立つのはやめてほしいと思っているのだが、制御はなかなか難しい。セクハラなんてことが起こり得るのではと心配だ。
「うーん。やっぱり、兄ちゃんが言うように常連さんの時間は善逸さんは外した方がいいかもね」
「だよなぁ」
「善逸さんも料理上手になってきたし、兄ちゃんと姉ちゃんと俺がフロント回せばよくない?」
ケロリとそう言う竹雄に俺は素直に頷けない。皆んな、当たり前のように善逸が我が家と銭湯にいると思っているが、善逸はうちのバイトでもなんでもない、俺の……俺の? 俺の先輩という関係? なのか……? 考えても正確な答えがでない。俺と善逸は一体全体、どんな関係なんだ?
「お疲れー。おっ? 竈門兄弟が並んでるな? 善ちゃんどうした? 風邪か?」
「お疲れ様でーす。入湯料四六〇円でーす」
竹雄は六人目の『善ちゃんどうした?』の質問に辟易したように入湯料を提示した。俺はそれに常連さんだぞと思いながら「善逸は家の方で夕飯の支度してます」と答える。すると「なんだよ、嫁さん隠してんのか」と揶揄うように言われたので、俺は何にも言えずに曖昧に笑った。
学校にいても、学校から帰ってきても、俺は善逸とのことについて揶揄われる毎日だ。学校で揶揄われるのは四月に入ってからだけど、銭湯では正月くらいからだったか。学校での善逸は俺の彼女扱いで、銭湯では嫁扱いだ。それに俺は少しだけ困ってしまう。善逸は嫌がってないかと不安に思うけど、善逸は特に何も言わずに常連さん達にニコニコしてる。
「はっきり、違うって言うべきなんだろうけど……」
俺はガシガシとタイルを磨きながら、溜息をついた。営業時間が終わったので風呂場を磨いている。時間は二十二時。うちは子供が多いから、他のところより少し早めに閉まる。それでも常連さん達は通ってくれてるんだから、ありがたいことだよな。
「よいっしょ。よし、こんなもんかな」
俺は風呂場の掃除を終えると脱衣所に出た。脱衣所では竹雄と花子が忙しなく働いてる。俺は二人に手を軽く手を振ると、掃除道具を片付けて銭湯から家の方へと戻った。古い我が家はもう殆ど電気が落ちていて、俺はそっと二階へと向かう。なるべく静かに歩いてもギシギシ鳴る階段に、六太を起こしませんようにと思いながら登り切る。
「……善逸?」
そう言ってそっと部屋を覗き込むと、二組ある布団の一つで六太が寝息を立てていて、そして部屋の隅にある折り畳みテーブルに突っ伏している善逸がいた。教科書を下敷きにしているところを見ると、勉強していたがうたた寝してしまったというところか。俺はそーっと善逸の横に膝を下ろすと顔を覗き込んだ。
すやすやと気持ち良さそうにしている善逸の寝顔をじっと見つめる。本当ならすぐにでも起こして、家に送っていくべきなのは分かっているが、俺が心のままに善逸を眺めていられるのはこういう時しかない。
「……可愛いらしいなぁ」
俺は思わず漏れた言葉に慌てて口を噤んだ。善逸を起こすほどの声量ではなかったけど、改めて音にすると衝撃が強い。俺はドキドキする心臓に一つ息を吸うと、再び善逸を見た。
うん、可愛い。たぶん、きっと、俺の人生で一番可愛いと思ってる。禰󠄀豆子と花子も可愛いけど、二人は妹だから善逸を可愛らしいと思う気持ちとはまるで違う。善逸に抱く可愛いは……自分の手の中だけで可愛がりたいという強い欲だ。
「……はぁ」
俺は大きな溜息をついた。そして善逸の肩に触れようと手を伸ばして、ついっと視線を下にずらす。ハーフパンツから覗いた柔らかそうな足を撫でたい。けどそんなこと出来るわけも、していいわけもない。だって俺と善逸の間には何もないから。俺と善逸の関係性はいまもずっと先輩と後輩でしかない。もしくは被害者と加害者かもしれない。
「善逸、善逸。起きろ善逸」
「んう……?」
「起きたか? 六太についていてくれてありがとう」
「んーん……平気……」
銭湯の後片付けはそれこそ母さんから茂までと大人数でやる。そうすると夜遅いのに六太が家に一人になってしまうのだ。けど善逸が我が家に良く来るようになってからは、善逸が六太のそばにいてくれる。六太が布団に入って眠るのを見守りながら、善逸は勉強をするのだ。それまでは六太を談話室のソファで寝かせていたから……善逸のおかげでちゃんと布団に寝かせられるようになって助かっている。
「もうすぐ茂が戻ってくるから。家に帰ろう」
「うーん」
善逸はふらふら立ち上がると、眠気まなこを擦りながら俺の腕にしがみついてくる。ぎゅうと抱きつかれるようにされるのに、全くもって、凄く困る。善逸の身体が、すっかり柔らかくて困るのだ。
「……じゃあ、行こうか」
「うん……」
俺はやや寝ぼけている善逸が転ばないようにとその細腰に腕を回した。去年の夏に触れた時とは雲泥の差で柔らかい肉がついている。俺はそれにホトホト、困っている。
善逸がすっかり女の子になってしまった!!
どうしよう!!
芋虫が蛹になり蝶へと羽化するように可愛らしくなってしまった善逸に俺は焦るばかりだ。最初は男と思うほど貧相だった善逸だったが、きちんと食事を食べさえすれば他に特に何をすることもなく、立派な身体つきになってしまった。
本人はまだ、多少胸が小さいのを気にしているようだが、もうどこをどう見ても立派な女の子だ。過去の俺も、今の状態の善逸であれば「我妻先輩! 垢擦りしませんか!」なんて言うはずがない。とんでもないことだ。そんな事をするわけがない。だってそんなの、嫌われてしまう!! 俺は善逸に嫌われたくない!! だって好きだから!! そう! 俺は善逸が好きなんだ!
いつからかは分からない。もしかしたら最初からかもしれない。俺は善逸を男と思っている時からずーっと何かしたいと思っていた。俺に優しくしてくれた善逸の為に、恩を返せる機会を虎視眈々と狙っていた。だからきっと、俺は善逸を好きになってしまう才能が元からあったのかもしれないし、善逸にも俺に好かれる才能があったのだろう!
「あ〜もうすぐ中間テストだな〜」
「うん……」
「テスト期間になちゃうけど、俺、竈門極楽湯遊びに行ってもいい? 一人は寂しいからさぁ」
「うん、いいぞ」
俺も善逸に会えないと寂しい……とは言えない。俺にそれを言っていい権利があるか分からないし、言えば俺が善逸に向けている気持ちが筒抜けてしまうかもしれない。
「やった! 成績落ちないように頑張らないとな! 葵枝さんに心配掛けちゃ悪いからな〜」
嬉しそうに笑う善逸は、母さんにすっかり懐いている。母親を知らないという善逸は、もしかしたら母親像というものを俺の母さんに見出しているのかも知れない。俺はそれに悪い気なんてしない。でも善逸がただ母さんの娘になるのは嫌だなとは思う。
俺たちは夜だからと少々、声を密やかにしながら善逸のアパートへと向かった。と言っても歩いて五分だ。でも街灯も少ない夜道だから、オレは毎回毎回、善逸を家に送る。今日も無事に善逸をアパートに送り届けられてホッとした。最初の頃は送りなんていらないと言われたからな。無理やりついて行っていたけど。
「炭治郎、今日も送ってくれてありがとな」
「いいんだよ。たいした事じゃないし」
毎度お礼を言ってくれる善逸に、心からそう言う。俺からすれば本当に善逸を家に送ることは大したことじゃない。善逸の安全が少しでも保証されるんだ。それは何がなんでも優先すべきことだ。だって、善逸は可愛らしい女の子だから。
善逸はすっかり可愛らしくなってしまった。学校でも、竈門極楽湯でも、善逸を男だなんて思う奴はいない。色んな人間が善逸を可愛いと思って見てる。
幸い、俺を善逸の彼氏と勘違いしてる人達が多いから未だ善逸は誰かにちょっかいを出されたことはないけど……それも時間の問題だ。善逸は今年三年生。来年の四月には進学か、就職か……今と環境が違う世界にいく。そうなったら、今の善逸だと男達がふらふら寄ってくるだろう。花の匂いに吸い寄せられる虫のように。
嫌だな、と思う。声を大にして嫌だと言いたい。俺がせっせと育てた女の子が、どこぞの男の手を取る日が、どこぞの男に花が散らされる日が来るのかと思うと怖気が走る。
どうか、どこにも行かないで俺のそばに居てくれと叫びたいけど……その権利が俺にはない。俺が善逸を女の子にするためにせっせとした努力は徹頭徹尾、償いの為だ。善逸を傷つけた責任を取る為であって、俺が甘い蜜を吸う為じゃない。善逸が素敵な花になる為だけに注いだことだ。咲いた後、摘み取る資格も権利も、俺にはない。
「じゃあ、おやすみ善逸。戸締まりしっかりするんだぞ」
「分かってるって、子供じゃないよ!」
子供じゃないって分かっているからこそ心配しているんだよ……なんて思っても言うことはできない。俺はそれじゃあと手を振ると、今日も羊でいられた自分を褒めて帰途に着いた。
****
可愛いリボン、たっぷりのフリル、キラキラ輝くビジュー。どれもこれも可愛くて、可愛くない俺には似合わないもの。好きなものを好きなだけ身につければ良いじゃんと言われれば、俺とて同意はするけれど、でも現実を知ってるんだよ。可愛いものを身につけて満足できる人もいるかもしれないけど、可愛いものをつけた自分を可愛いと思えないのが嫌って人もいるんだ。俺はちなみに後者な。リボンもフリルもどれもこれも似合わなくて、好きでも、気になっても、避けて通ってた奴もいるんだよ。
俺はそう思いながら鏡の前でムニッと胸を寄せた。そしてくるりと回ってみて、胸と尻を包む布ににんまり笑う。
「う、ウヒヒッ♡ 可愛い♡」
俺は一昨日、葵枝さんと禰豆子ちゃんに連れられて買いに行ったブラジャーとショーツに身をくねりとさせる。すると前はなかった胸がぽよんと揺れた。感動だ。俺に揺れるだけの胸がある!!
「はぁー♡ 凄いっ! ブラジャー凄い! 寄せてあげる機能とか最高!!」
俺は禰󠄀豆子ちゃんが見繕ってくれた白地に黄色の刺繍が入っているデザインの下着に溜息が出てしまう。その下着は流れた脂肪を集めて固定してくれるもので、サイズが少し大きくなる効果がついている。俺はそのブラジャーの効果を目で感じてうんうんと頷いた。
「……凄い。絶壁だった俺が……まさかBカップまで来れるなんて……!」
特に何か頑張ったということもない。毎日毎日、せっせと竈門家に餌付けされてふくふく太り、バストアップのストレッチというよりも普通にストレッチをして健康維持に努めていただけだ。そしたら気がついたらこんなに胸がありましたとさ!
「うふふ♡ これ、結構俺、可愛いんじゃない? イケてるんじゃない?」
俺はくるりくるりと鏡の前で回ってみる。真ん中にリボンがついたブラジャー可愛い! ツルツルした手触りのパンツ……じゃない、ショーツ可愛い! ちょっと弛んで見える尻の肉が気になるけど……胸ができたからよしっ!
「……可愛い……凄い、俺かわいい〜♡」
なんてヘラヘラしながら押し入れの中の衣装ケースを開けてテンションが下がる。先程の陽気はどこいったのかと思うくらい、テンションは駄々下がりだ。でもそれも無理もない。俺の衣装ケースを開けてみてみれば、悲しい現実が横たわっているんだから。
「……可愛い服がない」
俺はそう言って溜息をついた。前々から分かっていたことだし、あえてそうしてきたのは自分だけど、見事に可愛い服を持っていない。俺はうーんと唸りながら衣装ケースの中を漁るが、禰󠄀豆子ちゃんが選んでくれた下着に見合う服がない。葵枝さんが「いつもお手伝いしてくれて助かってるから」と買ってくれた下着に相応しい服がない。
「……どうするかな……」
俺はそう言いながらも、炭治郎とした約束の時間が迫っているので数少ない手持ちの中から、よく分かんないブランドのロゴが入った黒Tシャツとストレートのジーパンを取り出す。スキニージーンズとか持ってたら、体のラインがでて少しは可愛いかもしれないけど、ガリガリで貧相な身体を出す自信なんて以前の俺にはなかったわけで。
「うーん、ものすごく中学生」
鏡の前にいる自分は見事に可愛らしさのないダボついた服を着ている冴えない中学生だ。胸の大きさも尻の丸みも綺麗に服が隠してしまっている。俺はその出来栄えにくしゃっと顔を顰めるが、すぐに気を取り直して禰豆子ちゃんに借りた雑誌のヘアスタイル特集を開いた。そしてそれを見ながら、ちっちゃい容器に入った一番値段が安かったワックスをそっと指で掬う。
これは特別な日に使うものだ。毎日毎日髪につけるとワックスはすぐなくなってしまう。大きいの買うと高いし……髪に気を使う前に服にお金かけたいし。
そう思いながら俺はちょびちょびと髪に揉み込んで、百均で買った髪に絡まないゴムを取り出して口に咥える。そして慣れない手つきで何回かやり直しながらも、肩まで伸びた髪を編み込みの三つ編みにした。なんとか左右で均等に見えるようできてホッと息を吐く。
「うん……可愛いくできたかも?」
俺は編み込みで作った二本の三つ編みに、ダボっとしたTシャツとジーパンという出立ちにうーんと首を捻る。髪型は上手くできたけど、やっぱり全体を見ると……あんまり可愛くない。それにしょんぼりしながら、Tシャツを捲りあげれば、うん、可愛い。ブラジャーが出ると途端に可愛いな。
「……どんな服買えばいいんだろ」
俺はもっと禰󠄀豆子ちゃんに聞いておけば良かったと思いながら、でも禰󠄀豆子ちゃんが着ているような可愛いらしすぎる服はまだ俺には早いやと首を振った。禰豆子ちゃんみたいに華麗にスカートを履きこなしてみたいけど、そこまで到達するには俺にはステップが幾つもある。そもそもスカート履いた時の歩き方すら分からないわ。今のように大股歩きダメだよな?
「無難に……ズボン。女の子っぽいズボン。あ、ショートパンツ?」
そうだよ。太もも出せばいいんだ。これから夏だしいいんじゃないかな? Tシャツもダボついたのじゃなくて、ピッタリした方が可愛いよね? 俺はうんっと頷くと今日のターゲットを決めた。ショートパンツとタイトなタイプのTシャツを買おう。着替えも欲しいから、三枚くらい上はいるかな…? あ、でも予算足りないかも。俺はうーんと唸りながらお財布と睨めっこしていたら、トントンと玄関のドアを叩かれた。それにハッとする。炭治郎が迎えに来てくれた!
「はいはーい♡」
俺はリュックを引っ掴んで玄関に向かうと木枠だけ新しいドアを開けた。木枠だけ新しい理由は炭治郎が前に壊したからだ。新しいドアに丸ごと変えようとしたけど、アパートが古いせいで同じドアが作られてなく、今風のを取り付けると違和感すごいから木枠と金具を変えてドアは以前からのものを流用したんだ。
「炭治郎! おはよう!」
「善逸! こら! またすぐに開けたな!」
「あっ」
ドアを開けてすぐに炭治郎からのお叱りが飛んできて、俺はしまったと思った。けどすでに開けてしまったものはどうしようもない。俺は耳がタコになるほど言われていることを、また実践しなかったのにオロオロとする。
「ごめん……習慣がないからすぐ忘れちゃうんだよ」
「ダメだ!! 相手を確認しないでドアを開けるのは防犯上よくないぞ!」
「でもドアスコープもないし、インターフォンもないんだよ? どこから見るんだよ〜!」
俺の住んでるアパート、本当古いの。築何十年? 五十年とか経ってんじゃないのかってくらい古いのよ。だから相手の顔を確認する為のドアスコープもないし、呼び鈴は付いてるけど配線が壊れてて鳴らないし。とにかく不便。地震とか台風来るたびに壊れるんじゃないかなって心配になるくらいだよ。それで壊れたことはないけど。
「はぁ。ほら、ここの窓から見るんだ」
「ここ錆び付いてて開きにくいんだけど」
「ダメだ」
「はぁい」
俺はもう良い子の返事をひとまずしておこうと言い訳するのをやめた。靴を履いて外に出て、炭治郎が蹴飛ばすだけで壊れちゃうボロい玄関扉の鍵をかける。まあ、前はドア枠とドアの間に隙間あったし、金具も錆びてたからな。今はどっちも新しいから、蹴っても壊れないだろうけど。
「おしっ。おっけー! 行こうぜ炭治郎!」
「うん」
俺が歩き出してアパートの敷地から路地に出ると、炭治郎が隣に並んだ。当たり前な顔で俺を車道の内側に追いやるのにグッと胸が苦しくなる。道が狭いからピッタリと並んでいて、炭治郎の体温が肌で感じられるようだ。たまーにコツンと腕が当たるけど……それだけ。手を繋ぐとかはない。
それはしょうがないよな。俺たち別に彼氏彼女でもないし。『炭治郎』、『善逸』って名前で呼び合っててもただの友達だし。仕方ない、仕方ない。
(いやそんなわけなくない!? どこが仕方ないんだよ!? なんだよ俺たちのこの関係は!?)
危ない危ない。危うく声を出して叫ぶところだった。口の中だけで叫べて良かった。俺はふーっと息を吐くと隣を歩く炭治郎をチラッと見上げる。
炭治郎は真っ直ぐ前を見ているけど、前よりもなんとなく距離がある。それは身長が伸びてるからだろうな。炭治郎は出会った頃よりも、ずっとぐっと大きくなった。体つきも元からしっかりしてたのが逞しくなって、少年から青年に着々と成長している。そのお陰で、女子校舎では炭治郎の評判は上々だ。五月にあった体育祭の応援団でも活躍してたもんな。学ラン姿の炭治郎、カッコ良かったな〜!
「善逸!」
「わっ!」
俺はぐいっと腕を引かれたのにびっくりした。引かれた勢いのまま、体勢が崩れて炭治郎にしがみつく。おおっと。これはしっかりした筋肉ですね!?
「余所見をしていたら危ないぞ。電柱にぶつかるところだった」
「あ、ごめん」
俺はいつの間にか目の前に電柱があってびっくりする。脳内で学ランの炭治郎を愛でていたから現実が見えてなかったわ。俺は硬くて大きい電柱にぶつからなくて助かったと思いながら、しがみついていた炭治郎の肩に頭を寄せる。すると炭治郎はさっきは引っ張った俺の腕をぐいっと押しやって、二人の間に空間を作った。
「気をつけるんだぞ」
「……うん」
俺はちぇーっと思いながら、炭治郎から離れる。もう少し近くに居たかったのになぁなんて、正直な言葉を言うこともできず、俺たちは目的地である駅前のショッピングモールに向かった。そこは最近出来たショッピングモールでセールをやってるんだよね!
セールは俺に取ったら必要なものを買うチャンスだ! 何しろカツカツな貧乏苦学生だからな。必要なものすら買うのを渋るくらいだ。だって学費は一部免除されてるといえど、支払うものはそれなりにあるし、生活費も家賃もあるんだぜ? 進学用の学費も……うん、多少は貯めておかないとダメだし。
正直、アパートの家賃が超絶格安じゃなかったら俺は施設を出れてない。施設でない方が金の心配はなかったけどさ、どうにも相性の悪い奴がいてダメだったんだよね。火と油? みたいなさ。くっそ、あの野郎。俺を前世からの敵みたいな目で見やがって。俺がお前に何したっていうんだよ。
「……善逸、それを着るのか?」
「ん? これ? とりあえず試着はしようかと思ってたけど……」
俺は手の中にあるショートパンツを見て、そして試着室の列を見る。うーん。あそこに並ぶのは確かに気合がいるな。やっぱりセールだからか、人が多い。あそこに並ぶと炭治郎をどれだけ待たせることになるんだろうか。炭治郎とデートっぽいことがしたくて誘ったんだけど、時間が掛かり過ぎたらうんざりさせてしまうじゃないか。
「うーん。並びたくないな……。どう、変じゃない?」
俺はやや短めのパンツを自分に当ててみて、炭治郎に聞いてみる。すると炭治郎は微妙な顔で首を傾げた。俺はあんまり良くない反応に、炭治郎はショートパンツ好きじゃないのかなと焦る。やっぱり、スカートの方が女の子っぽくていいのかな?
「ごめん。履いてる想像があまりつかなくて……」
「あ、そう……?」
まあ、そりゃそうか。俺、いま長いズボン履いてるからな。当ててみても下にズボン見えてて想像しにくいよな。俺はどうしよう、試着しようかなと思いながら服が掛かったハンガーをガチャガチャみていく。と言ってもどんな服がいいかなと考えながら探しているわけじゃなく、炭治郎はどんな服が好きなのかという思考が頭の中いっぱいに広がっている。
だって、俺が欲しいのはただの可愛い服じゃないんだよ。ただの女の子っぽく見える服じゃないんだよ。炭治郎がいいなって、可愛いなって思ってくれる服が欲しいんだ。
「……じゃあ、こっちのキュロットは?」
「う、うーん……?」
炭治郎は困ったような顔をして首を傾げている。俺は炭治郎からいい反応がないのに参ったなと持っていた服を全部、元に戻した。炭治郎に良いって思ってもらえないなら、完全に無駄金だ。正直言って、セールになっていても予算オーバーしてるんだよな。
「善逸……」
「あれ、竈門だ!」
「あ、本当だー! 久しぶりー!」
「え? あ、おはよう」
突然に掛けられた声に、俺はびっくりして距離を取る。すすすと移動しながら炭治郎に声を掛けてきた子達を見れば、これまた可愛らしい女の子達だった。今時の、お洒落で可愛い格好をした子達。自分が一番可愛く見える服を自信満々に着ている。一人の子は嬉しそうに炭治郎に話しかけていて、もう一人の子は少しずつ離れていく俺をチラリとだけみて、そして興味なさげに視線を戻した。もう、炭治郎しか見えてないっぽい。
「おわっ……」
俺は登場した女の子達を前にして、急に恥ずかしくなってしまった。何しろ、唐突に気がついてしまったからだ。俺はまだ、この店にくる資格がない。あまりにもこの店に入るには、今の服装は浮いてしまっている。場違いだ。
「ねぇ、竈門も遊びに行かなーい? これから他の奴も来るんだけどー」
「え、俺は……」
「ひえっ!」
俺は居ても立っても居られず、その場からスタコラサッサと逃げ出した。完全に炭治郎を置き去りにしてしまったが、どういう関係か知らんけど知り合いっぽい子達だから平気だろう。むしろ久しぶりとか言ってたから、俺の方が邪魔になるわ。
「……はぁ、はぁ……」
俺は気がつけば商店街まで戻ってきていた。そしてトボトボ歩きながら、いつも御用達の激安洋品店に入る。ここはTシャツとかめちゃくち安いんだぜ。ペラッペラで変な英字入ってたりするけど、一枚五〇〇円とかなの。俺は無感動に白Tシャツだけ二枚買った。もうこれでいいや。ズボンはジーパンとかジャージあるし。別にいいか。どこに出かけるでもないし、誰かに見せるために着るでもないし。
俺は水玉柄のうっすいビニール袋を揺らしながら、家に向かった。じめっとした空気が梅雨を感じさせる。梅雨が明けたら期末テストだ。俺は学費一部免除の特待生で居続けるためにいい点取らなきゃいけないからな! お洒落とかしてる暇あるか! 勉強だ勉強! 絶対に施設に逆戻りとかヤダっ!! 俺は一人で自由に生きてくんだ!!
「善逸」
呼ばれた声に俯いていた顔を上げれば、アパートの玄関の前に炭治郎が立っていた。俺はあれっと思うけど、炭治郎がぐっと眉根を顰めて睨んでくるのに息が止まる。
「勝手にどこかに行くな! すごい探したんだぞ!」
「ごめん、友達と遊びに行くかと思って……」
「俺は今日は善逸と約束してたんだ! 行くわけがないだろう!」
「あ、うん。そりゃそうか……」
俺がゴメンともう一度言えば、炭治郎はまだ何か言いたそうだったけど黙ってしまった。そしてゆっくり玄関の前を開けるから、俺はそこまで歩いて行って鍵を開ける。
「入って」
「うん」
物凄く気まずいが、炭治郎を追い返すわけにもいかない。とりあえずお茶を出そうと中古の小さい冷蔵庫を開けた。そこから百均で買ったプラスチックの麦茶ポットを取り出して、これまた百均で買ったグラスに注ぐ。
「はい」
「ありがとう」
炭治郎はすごい探したと言った通り、汗をかいているようだった。それなら喉も乾いていたのだろう。ごくごくと麦茶を飲み干し、喉仏が上下している。
「まだ飲む?」
「うん、欲しいな」
そう言って差し出されたグラスに俺は麦茶を注いだ。トクトクと注がれる麦茶を見つめながら、この瞬間に世界が終わればいいのに、なんて思ってしまう。だってそれなら、炭治郎の役に立ってる時に死ねるんだぜ? 炭治郎だって俺の存在を最後に認識するんだ。最高じゃん。まあ、たわいもない妄想だけどな。
「……服、商店街で買ったのか?」
「ん? ああ、うん。よく考えたらセールでも予算オーバーだったから。試着するにも人が多いし……やっぱり俺にはまだああいうのは早いわ。大人になってからにする」
「……そうか」
炭治郎は少し寂しそうな声で相槌を打ったけど、現実は無情なんだよな。実際に俺には先立つものが少なすぎる。自分でも言った通り、予算オーバーなんだ。
冷静に考えて服を買って着飾る余裕が俺の財布にはない。ただでさえ、生理がきてナプキン代という固定費が月々発生しているのだ。食事は竈門家にお世話になっているから浮いてるけど、今年の俺は高三だ。一応、できれば進学を検討してるから模試を受けるお金とかもあるし……まあ、就職が濃厚だけどな。学びたい分野もないし。
「可愛いには先立つものが必要なんだなー。みんな、金かけて可愛くなってんの理解したわ」
「お金を掛けてなくても可愛いものは可愛いだろ?」
炭治郎が不思議そうな顔をするのに、俺はへっと鼻で笑ってしまう。男なんてこんなものか。俺もよく知らなかったけど、禰󠄀豆子ちゃんに借りた雑誌を見れば分かる。
あそこには可愛くなる為にできる努力のやり方がたっくさん書いてあったんだ。服も、化粧も、ダイエットの方法も。そのどれも、俺が知らなかったものばかりだった。
「そりゃ元から顔の作りが可愛い子はいるよ? でもみんながみんなそうじゃないし……元が良い子も女の子は可愛く素敵になる為に隠れた努力をしてたりするし、お金もそれなりに掛かってんのよ。その辺分かってないとダメだぞ炭治郎」
「そうなのか」
「そうなんだよ。だって見てみろ。このブラジャーだって一枚三千円もするんだぞ? 三枚買ったら一万いく……」
俺はガバリとTシャツを持ち上げて見せたら、炭治郎に腕を掴まれて引き下ろされた。その勢いが凄すぎて、俺は心臓が止まるかと思ったし、声も止まってしまった。え、何、とばかりに炭治郎の顔を見れば物凄く怒った表情をしていて、心臓が止まった。止まってないけど。
「はしたないことをするなっ!!」
「ひえっ!」
「善逸は女の子なんだぞ! いつまでも無頓着でいるんじゃない! いい加減にしろっ!!」
炭治郎に怒鳴られて、俺はぶるぶると震えた。こんなに怒ってる炭治郎初めてかも。でも炭治郎はいつも優しいから、すぐに「怒鳴ってごめん」って言ってくれる筈。
そう期待して俯いていたら、炭治郎は「今日はもう帰る」と言って、俺の部屋から出て行ってしまった。ガチャンと台所のシンクにコップが置かれ、バタンと古い家の扉が鳴る。それらの音すら怒っている気配を感じて、俺は立ち尽くした。
「……怒らせちまった」
炭治郎ってこんな風に怒ってどっか行っちゃうことあるのか。俺は呆然としながら、のろのろと麦茶のポットを冷蔵庫にしまった。古い冷蔵庫のブーンという音がやけに耳につく。
「謝らなきゃ」
たぶん、きっと、間違いなく、俺が悪い。炭治郎が正しいに決まってる。親も、金も、服も足りない俺より、全部持ってる炭治郎の方がきっと普通の世界の中では正しいんだ。
俺は追いかけて謝らなきゃと思うけど、足は動かない。早く追いかけなきゃ家に着いちゃうぞと自分を叱咤していたら、コンコンと玄関を叩く音がして顔を上げた。
「炭治郎?」
俺は期待しながら玄関に飛びついて扉を開けた。するとそこにいたのは炭治郎ではなく、困ったような、申し訳なさそうな顔をした大家のおばあちゃんだった。
****
「ん〜? 今日も長男だけか〜」
「善逸なら、しばらく竈門極楽湯には来ないよ」
「誰も善ちゃんのことは聞いてないだろ? 不貞腐れやがって。振られたのか?」
ケラケラと笑う常連さんにしまったと思ったがもう遅い。俺は「さっき善逸のことを聞かれたんだ! あと! 善逸が来ないのはテスト期間だからだ!!」と言いながらお釣りを返す。
「おお、怖い。炭治郎が不機嫌なんて壁に穴が開く!」
「そこかしこに頭突きなんてしないぞ!」
俺はカウンターから身を乗り出してそう言った。常連さんは笑いながら、軽い足取りで更衣室に逃げて行く。子供の頃からの知り合いは心強い時も沢山あるけど、揶揄ってくるのは困りものだ。俺はカウンターの椅子に座り直すと、大きく溜息をついた。
「俺は真剣に悩んでいるのに……」
今の俺の頭の中は善逸のことでいっぱいだ。自分でテスト期間だから善逸は来ないって言ったけど、それは嘘だ。テスト期間より前から、善逸は竈門極楽湯に来てない。『しばらく行けない』と母さんに電話があって、夕飯も食べに来なくなってしまって、料理の練習と笑って俺に渡してくれていたお弁当もついでのようになくなってしまった。その結果、最近、クラスメイトが「元気出せよ」と昼休みに慰めてくるのが鬱陶しい。
「……善逸は特待生だし、三年生なんだ。本当はあまり遊べないんだよ」
別にうちに来て善逸は遊んでいたわけではない。教科書を開いていることも多かった。でも一番多かったのは善逸が「何か手伝うよ」と言って竈門極楽湯の仕事をしてしまうことだ。うちの仕事をすると、善逸の勉強する時間が減ってしまう。だから期末テストが近づいてきた今、善逸は泣く泣くうちに来ていないんだ。家で勉強する為に。
「……はぁ」
なんて納得できるよう、自分に言い聞かせているが全然ダメだ。不安で仕方がない。けど俺はいま、善逸に避けられている為、その不安は日々増えていっている。
「善逸、どうしたんだろ……」
もし俺が避けられているのだとするなら、たぶん、最後に会った日の別れ際の件が問題だったんだろう。善逸に誘われて服を買いに行った日、中学の同級生に会って話しかけられて……気がついたら善逸はいつの間にかその場にいなかった。ショッピングモールを探して、スマホを鳴らしてみてもダメで、商店街を駆け抜けて、家に帰ったのかと思ってアパートまで確認しに行ったら、善逸がゆっくり歩いて帰ってきたんだ。
「ぐう……」
あの時の俺は色々腹が立っていたんだ。折角、善逸と出かけることになったのに、目を離した隙に善逸はいないし、散々探したのに本人は商店街の服屋で服を買って帰ってきてるし。可愛い服が欲しいからと買いに出かけたのに、いつも通りの服を諦めた顔で買ったその姿が寂しくて、なんだか苛立って……だから善逸がふいに捲りあげて見せてきたものに動揺して怒鳴ってしまった。
「いやでも、下着は……ああ、もう……」
あんな可愛らしいブラジャーを善逸がつけているなんて不意打ち過ぎた。少しずつふっくらして、胸も出来てきているだろうと予想していたけど、見せつけられるなんて思ってなかった。
最初に見た男と間違えるほどの体とは違う。青白さはなくなって、ふっくらとした胸と身体は抱きしめればとても気持ちよさそうだった。なのに善逸はその変化に頓着してないらしく、簡単に俺に見せてしまう。まさか他の奴にもするんじゃないか、なんて心配になって、はしたないと叱ってしまった。
「いや、あれは……正しいだろ。あんなことを軽々しくしてたら、危ないじゃないか」
善逸はだいたい、危機意識が足りないのだ。玄関を開けるのも誰が来たのか確認せず開けるし、帰り道だって「一人で帰れるよ」と言う。俺からすれば善逸の住んでいる場所は結構あぶない。善逸の家は通りに対して一番奥だし、一階だし。物陰に誰かが隠れていて、玄関を開けた時に押し入られたらどうするんだといつも不安だ。善逸は「うちに来るの炭治郎だけだから」とよく言うけど、善逸に用があって訪ねてくるのは俺だけだとしても、不届き者が家にやって来る可能性だってあるだろう!
「炭治郎、お疲れ様。フロント交代するから、これ持って行ってくれる?」
「あ、うん」
俺は保冷バッグを片手にやってきた母さんに立ち上がって頷いた。保冷バッグの中身は間違いない。今日の夕飯だ。持って行く先は善逸の家に決まっていて、俺はいそいそとそのバッグを受け取るとサンダルを引っ掛けて外に出る。時刻は八時だから流石にもう辺りは暗い。
「……善逸、いるかな?」
俺はドキドキしながらアパートへと向かう。最近はノックしても反応がなくて、でも部屋の明かりはついている。家に来るのは俺だけと思っているから、玄関を開けてくれないのだろうか。いやでも、夕飯は食べてくれてるみたいだし。
「……今日も返事なし……か」
俺は大きな声で呼ぶ勇気も出なくて、軽いノックの後にいつものように保冷バッグをドアノブに引っ掛けた。玄関側の窓は磨りガラスなので中は見えない。灯りはついているけど、音はしないな。
「もしかしていないのか?」
よく考えてみたら善逸の家にはクーラーがないな。暑いから図書館にでも行って勉強をしているのかもしれない。俺は明かりがついた善逸の部屋をじっと見て、そして溜息をつくと歩き出す。これでお弁当の空箱は、明日の放課後までに俺の下駄箱に入ってるだろう。いつもそうだからな。朝に渡してくれてもいいのにと思うけど、テスト期間だから服装チェックがないからな。
そう思いながら家に向かう為に道路を渡ると、反対側、さっきまで俺がいた道を善逸が歩いているのが見えた。
「あっ……」
善逸はトボトボと制服姿で歩いていて、俯いているようでもしかしたら泣いているのかもしれない。けど俺は動くこともできず、向かい側を通り過ぎていくのを見送ってしまった。信号が赤になったということもあるけど、それ以外に気になることがあるからだ。
「……悲鳴嶼先生?」
善逸が悲鳴嶼先生と歩いていた。俺はそれに首を傾げてしまう。間違いない。三年生の学年主任をしている悲鳴嶼先生だ。体の大きさで分かる。悲鳴嶼先生は隣を歩く善逸をなにやら気遣っているのか、声は届かないけど口が動いているのが見える。
「なんで悲鳴嶼先生と善逸が?」
俺はブーンっと飛ばして行くバイクの音に背を押されて、青になった信号を渡った。そして来た道を戻って行くと、善逸のアパートから悲鳴嶼先生が出てくる。善逸は家に帰ったらしい。
男の先生が女子生徒を家まで送るというのは聞きようによっては危ないが、相手は悲鳴嶼先生だ。信頼できる先生だから変なことではない。むしろ、なんで送る事態になったのかが気になる。だって……テスト期間中、悲鳴嶼先生は生徒が繁華街で遊んでいないか見回りしてるって噂を聞いたことがあるから。
「……そこにいるのは竈門か?」
「あ……悲鳴嶼先生、こんばんは」
完全に死角にいたと思ったのに、ピタリと当てられてしまった。俺はひょこりと電柱の裏から姿を表すと、悲鳴嶼先生の前に行って頭を下げる。悲鳴嶼先生は少し前屈みになりながら、俺の様子を伺っているようだ。
「我妻に夕飯を届けに来たのか?」
「え? なんで分かるんですか?」
「先ほど、我妻の家の玄関のドアノブに保冷バッグがぶら下がっていた。それを何かと聞けば、竈門が持ってきてくれる夕飯だと話していたんだ」
「なるほど」
善逸が話したのか。……善逸、どんな顔で受け取ってくれたんだろう。気になるけど、先生に聞いて教えてくれるかな。なんで聞くんだって不思議がられるかな。
「……竈門と我妻は仲がいいんだったな」
「え」
「我妻に昼のお弁当を作ってもらっているんだろう? 職員室でも話題になっていた。……交際をしているのか?」
悲鳴嶼先生の言葉に、俺はなんて答えればいいのか分からない。確かに前まではお弁当を作ってもらっていたけど今は違うし。そして俺たちは別に交際もしていない。よくて、ただの友達だ。でも避けられている今、その友情もあるのか分からない。果たして運んでいる夕飯は喜ばれているのかも分からない。
「……交際は、してません」
「……そうなのか」
俺が頷くと、悲鳴嶼先生の大きな手が俺の頭を撫でてくれた。大きな男の人の手に頭を撫でられるなんて久しぶりだ。父さんが死んでからはなかったから。俺はその手の大きさに安心を感じたけど、同時に嫉妬もある。俺の手のひらがもっと大きかったら、俺がもっと大人だったら、善逸と上手くやれるのだろうか。
「悲鳴嶼先生」
「うん?」
「交際はしてないですけど、俺は善逸のことが好きです」
初めて誰かに善逸へと向けている気持ちを言ってしまった。少しドキドキしてしまうが、今の今まで、気持ちを口にする資格もないと思って黙っていたから……すごくスッキリした。うん。俺は善逸が好きだ。この気持ちをもっと、声に出していきたい。
「……そうか!」
悲鳴嶼先生はどこか嬉しそうな顔で頷いてくれた。そして頭を再び撫でようとしたのか、手を伸ばしたけど、すぐにそれを俺の肩に照準を変える。ぽんぽんっと肩を大きな手で叩かれた。
「……好きならば、支えてあげなさい」
「……はいっ!」
悲鳴嶼先生は大きく頷くと「じゃあ、今度は竈門を送ろう」と言って、俺を家まで送ってくれた。大丈夫だと言っても首を横に振られてしまい、素直に送られる方が先生の時間を無駄にしないなと思って家に向かって先生と歩き出す。
さっき見た善逸の足取りは随分とゆっくりだったけど、男二人の足ならあっという間だ。俺は竈門極楽湯の明かりが見えたところで先生に頭を下げた。悲鳴嶼先生はお決まりの両手を合わせたポーズで会釈すると踵を返して去って行った。
「……明日でテストは終わりか。……善逸と話をしよう」
話をして、仲直りをしよう。そもそも喧嘩しているのかも分からないし、善逸は怒っているとかではなく、本当にテスト勉強に勤しんでいたのかもしれない。さっき、悲鳴嶼先生に送ってもらっていた時には泣いていたように見えたけど……暗かったし、遠かったし。図書館からの帰りに出会って送ってもらった可能性だってある。善逸は俺のこと別になんとも思ってないかもしれない。
「でも……寂しいよ、善逸」
結局はそれなんだ。俺がただ、寂しいだけなんだ。善逸に会いたいし、炭治郎って呼んで欲しい。忙しいなら忙しいでもいいんだ。でもたまには顔を見せて欲しい。忙しくて会いにくるのが難しいなら、俺が会いに行くから。
****
「たーんじろっ! 今日は一緒に帰ろうぜ!」
「あ、え、善逸……?」
「いやーテストも終わって爽快感があるなー! ほら、早く早く!」
「あ……待ってくれ! 善逸!」
最終日のテストも終わって、午前中に下校。二年生の男子校舎の下駄箱前にいた善逸は踊るように、歌うようにご機嫌な様子で俺の前を歩いている。その姿にホッとするよりも、何故かソワソワする。なんでだろうか。こんなに浮かれたご機嫌な善逸が珍しいからだろうか。ふわふわとしていて、地に足がついていないという感じがする。
「……その紙袋、大きいな?」
「うん? これ? へっへー良いもんが入ってるんだよ!」
「そうなのか?」
「俺の家で見せてやるよ! だからちょっとうちに寄っていって!」
善逸は輝くような笑顔でそう言った。その笑顔が可愛らしくて、じわっと汗が出る。顔も赤いかもしれないけど、七月に入ってもう中旬になる。暑いからと言い訳できる筈だ。
「そういえばもうすぐ炭治郎の誕生日だなー」
「あ、そうだな」
「何か欲しいものとかある?」
「いや……」
「高いものでもいいよ」
そう言って笑う善逸に俺は首を軽く振った。欲しいものなんて、一つしかない。けどそれには値段なんてつけられない。ついたとしてもとんでもなく高いものだ。でも売りものじゃないし、売って欲しいわけでもない。
「なんか考えておいてよ。七月中までに教えてな」
善逸は到着したアパートの玄関扉に鍵を差し込みながら、そう言った。誕生日までに教えてくれじゃないんだな、なんて思いながら開けられた玄関を潜って、俺はギョッとした。
「ごめん。散らかってんだわ」
「えっ!?」
散らかってるも何も、善逸の部屋は荒れていた。服はあちこち転がっていて、布団も投げつけられたようにキッチンに転がっているし、キチンと小さな本棚に収まっていた教科書やテキストはビリビリになって転がっている。
「善逸!? な、なんだこの状況は!?」
「なあなあ、これ見て! じゃーん!」
「善逸!!」
「キメツ学院の制服!!」
「……は?」
善逸が紙袋から出したのはキメツ学院の制服だ。それも、スカートの方。新品らしく袋に入っているそれを、善逸は床に転がっていたキッチンバサミを拾い上げて風を開けた。そして取り出してタグも切り落とすと、風呂場へと向かう。
「待ってろ! 今着替えてみせるから!」
「……うん」
善逸は嬉しそうに風呂場に入るとドアを閉めた。俺はあの扉の向こうで着替えているのかとドキドキして目を逸らしたが、その途端に部屋の惨状が視界に飛び込んできて頭を抱える。この部屋の状態はどうしたんだ? なぜ、教科書とかが破られているのか。空き巣……という線はなさそうだ。善逸があまりに落ち着いている。ということは、これは善逸がやったのだろうか?
「お待たせ♡ じゃーん! どうどう? 似合ってる〜?」
「……わぁ……」
風呂場からテンション高く飛び出してきた善逸は、膝上のスカートを見事に履きこなしていた。男女共通のシャツとタイはさっきと同じままだが、スラックスをスカートに変えただけでこんなにも印象が違うのか。善逸のすらりとした足は日焼けを一切していなくて、白く輝いている。小ぶりの膝小僧が見えるのが新鮮で、俺はギュッと心臓が痛くなった。
「なんか言ってくれよ」
「……可愛い。すごい……可愛いぞ、善逸」
恥ずかしながらも思ったままのことを伝えれば、善逸はパッと顔を輝かせて、猫のように目を細めて笑った。滅多に見れない、善逸の穏やかな微笑みに俺はますます胸が苦しくなる。スカートの制服を用意したということは、これからは学校ではこの格好で過ごすのだろうか。それは……少し嫌だな。善逸が可愛らしいことが、もっともっと知れ渡ってしまうぞ。
「……皆んな、きっと善逸がもっと可愛くなったことに驚くな」
「んー? まさかぁ。そんなことないって」
「そんなことあるよ。……すごく、すごく可愛いから。絶対だ」
だからどうか、スカートなんて履かないでくれ。俺は善逸にスカートもだし、短いズボンも履いて欲しくない。前に服を一緒に見に行った時も、短いズボンを買おうとする善逸が嫌だった。周りの人に足を晒すのを嫌に思っていたんだ。
けどこんな気持ちは伝えられない。俺は善逸の彼氏でもなんでもない。彼氏だってこんな事をいうのはアウトだろう。善逸は自由に着たい服を選べる筈なんだ。ようやくスカートを履く自信がついたんだ。それを邪魔しちゃいけない。だから俺はぐっと堪えて黙ったわけだが……善逸はやっぱり「そんなことないんだって」と笑った。
「だって、俺この制服着る時ないし」
「ん? あ、それ冬用か? 二学期の衣替えが来ないと着れないのか」
「いやいや、そうじゃないよ。まあこれは確かに冬スカートだから今は着れないけどね。そうじゃなくて。俺、今学期で退学するの」
「え?」
「七月中にこのアパートも退去しちゃうし。学校も辞めるんだ」
「……えっ!?」
ふふふんと笑いながら善逸はその場で回転している。スカートがくるりくるりと舞い上がってパンツが見えそうだ。いや、そこを気にしてる場合じゃない。学校を退学? アパートから退去? なんでだ!?
「待て!? どうしてだ!? 卒業しないのか!?」
「んー?」
「善逸! ふざけてる場合じゃないだろ!! なんで退学なんだ!?」
「ふざけてないよ。……単純にお金なくなっただけわ」
善逸はスカートの裾を摘みながら、悲壮感もなくそう言った。明るい言い方ではない。ただ、諦めた声だった。
「お金……? 卒業できる算段だったんじゃないのか?」
「うん、そうだったんだけどさ。いやぁ、計算が狂ったんだよ」
「計算……?」
「……ここのアパートが取り壊されることになっちゃったんだよね。老朽化してて、危ないってのもあるし……大家さんの息子夫婦が跡地に二世帯住宅建てたいって言ってるのもあるらしくてさぁ」
善逸は困った顔をしながらそう言った。俺はその表情にゾッとしてしまう。善逸はここらで一番安いアパートに暮らしてる。そうじゃなきゃ、生活費や学費が休日の僅かなバイトで賄えないからだ。なのに、その住処がなくなるのか。その為に善逸は学校を退学しなくちゃいけないのか?
「退去費用は?」
「……ん? 退去費用?」
「急に決まったんだろう? それなら、退去費用が出る筈だ。大家側の都合なら、まとまった退去費用を請求できる。それを使って、他のアパートに住めば退学しなくてもよくないか? 食事はうちで全部食べればいいし……」
そうだ。ここより少し高くなってもまだ手はある筈だ。せっかく、せっかく善逸は頑張ってきたんだ。高校もあと半年くらいだぞ。ここまできたら卒業した方が絶対にいい。
「うーん……。無理かな」
「なんでだ!?」
「いや、実は……大家のおばあちゃんの厚意で、元から家賃を下げてもらってんの。お金ないから大変でしょって。だから、退去費用をくれとか……流石に言えんのよ」
「いや、でも……!! それだと善逸はどうするんだ!? 高校を卒業できないと中卒扱いだぞ!? 中卒で、親という存在もなく、どうやって就職するんだ!? 就職できる幅が狭まるだろう!」
俺の言葉に善逸はやっぱり困ったように笑った。何がおかしいのか分からない。けど、この部屋の惨状の理由はわかったぞ。善逸はもう、散々に感情を発露した後だったんだろう。悔しくて、悲しくて、暴れた跡なんだ。
「まあ、しょうがない。人生なんてこんなもんだ」
「そんな……!」
「それにお金貰ってどっかアパートに住んでもダメなんだ。実はさぁ、手っ取り早くお金欲しくて、短期バイト入れてみたけど……そのせいで全然勉強できなくて……テスト散々だったんだわ」
「…………」
「絶対に特待生の成績、維持できてないし……年齢嘘ついて働いてたの、悲鳴嶼先生に見つかっちゃった」
「……それ、どこで働いてたんだ……」
「……お酒出すお店……あ、でも、何にもなかったよ?」
俺は片手で顔を覆った。言いたいことはたくさんある。けど、どれも気安く言葉にはできない。善逸は俺の妹じゃない。善逸には善逸の境遇があって、それを何とかする為に必死になってやった筈なんだ。善逸だって高校を卒業したいに決まってる。退学したいわけがあるか!!
「……泣くなよ炭治郎ぉ〜!」
「……泣いてない……」
「泣いてるって! あーもう……泣かしたくて連れてきたわけじゃないんだよ!! ほら、タオル使えよ。あ、これは床に落ちてないやつだから」
「……そんな心配してない……」
俺は善逸からタオルを受け取ると目元を拭いた。そしてそのタオルを丁寧に折り畳んで善逸に返そうと思ったら、銘が竈門極楽湯であることに気がつく。これ、竈門極楽湯で売ってるタオルだ。そういえば善逸に一つあげたことあったな。
「……そうだ善逸!! うちで暮らせばいい!」
「ん?」
「だから、俺の家で暮らせばいいんだ! そうしたら家賃も光熱費もゼロだし、食費もゼロだ! それなら学費だけで済むから、何とかなる!」
キメツ学院の学費は安いから、家賃と生活費がなくなれば特待生じゃなくとも、週末のバイトだけでも学費は払えると思う。足りないなら、うちが善逸に貸せばいいし……名案だ! これなら善逸は卒業できる!
「た、炭治郎……それは流石に……」
「どうしてだ? 絶対に母さんだって賛成する! 弟や妹達も善逸がいなくなったら寂しがる! それに善逸も高校卒業した方が絶対にいい筈だ!」
「……いや……」
俺は善逸の両手を取ると縋るように見つめた。どうか、どこにも行かないで欲しい。俺の家に住んでほしい。せめて、せめて高校卒業まででいいんだ。どうか、突然に居なくなるのだけはやめてくれ。そう思ってこの気持ちが伝われと見つめ続けたけど、善逸の表情はずっと困ったままだった。それにゾワゾワと背筋が寒くなっていく。今日は雨も降ってないのに。
「ごめん、炭治郎。それはできない」
「なんでだ? 名案じゃないか! うちは気にしない! 大丈夫だ!!」
「うーん……いや、やっぱりダメ」
「善逸!!」
「ダメよ。ダメダメ。……だって俺、女の子だから」
善逸のその言葉に俺は息が止まる。
「女の子になったの、俺。親戚でもない、同じ学校に通う年頃の男の子と一つ屋根の下で暮らすのは……はしたないでしょ」
「あ……そんなこと……」
善逸は手を掴んでいた俺の手を外すと、一歩後ろに下がった。そして俺に披露するようにスカートの裾をそっと摘む。
「炭治郎のお陰でさぁ、俺、女の子っぽくなったよ。ありがとな」
「……善逸は最初から女の子だろ……」
「ははっ。最初は男と思ってたのによく言うわ」
「面目ない……」
「あははっ……は、ははっ……」
善逸の笑い声が途切れ、二人で沈黙する。俺と善逸の間にある数十センチの距離がもどかしい。この距離だけで嫌なのに、これから善逸はもっと遠くに行くと言うのだ。
「……炭治郎、俺はお前に感謝してるよ。お前に出会えてよかった。楽しかった。この楽しさがあったならさ、裸見られて触られたくらいは安いもんだよ。高校中退でも……うん、お釣りがくる」
「そんなわけない……」
「あるんだって。俺はお前を責めないよ。お前は罪悪感とか、償いとか色々俺に対して思うところあるんだろうけど……俺は楽しかった。幸せだった。キメツ学院に通えてよかったよ。だから、いいんだ」
「…………」
「今生の別れでもないだろ? そんな顔するなって! 俺は施設に戻るだけだし」
「……施設……」
「こっから遠いけどさ。いつか大人になってお金ができたら会いにくるよ。だから……な? 手ぇ、離してよ」
善逸にそう言われて気がついた。いつの間にか距離を詰めて、俺は善逸の手を再び握っていたらしい。善逸は俺が掴んでいる手を緩く振りながら、「離して?」ともう一度言う。それを聞きながら、先ほどまでの善逸の感謝の言葉を思い出し、俺はポッと疑問に思う。なんで善逸の手を離さなきゃいけないんだ。
「……嫌だ。離さない」
「は?」
「善逸が施設に戻るのは嫌だ」
「いやいや、嫌だと言われても……」
「そこには……善逸からすれば家族かもしれないけど、年頃の男もいるんだろ?」
「……お、おう……? まあね……?」
「……じゃあ、やっぱり嫌だ。俺は善逸が好きだから、俺以外の男と暮らして欲しくない」
「えっ!? 好きっ!?」
今の善逸はとっても可愛く見えるようになってしまった。もしかしたら施設に戻ったら、善逸の変化に色めき立つ奴がいるかもしれない。これは完全に俺の妄想だし我儘だ。でもやっぱり嫌だ。俺の知らないところで、俺の知らない奴が善逸に近づいてくるかもしれないっていうのが嫌だ。俺以外の奴が善逸の特別になろうとするのが嫌だ。
「た、たたた炭治郎さんっ!? 好きって、え!? す、好きって俺を!?」
「うん、好きだよ善逸。……だから傍にいてくれないと寂しいし、辛いし、苦しい。……俺が高校を卒業したら結婚して欲しい。どうか俺と婚約して、俺の家に住んでくれ。それなら、はしたなくないだろう?」
「……ひぇっ……」
力が抜けたのか、善逸はガクンと膝から崩れた。俺は繋いでいた手を慌てて引いて、反対側の手で腰を支える。そしてゆっくり床に座らせたので、随分と善逸との距離が縮まってしまった。顔が真っ赤になって、涙目になっている善逸に、俺はゴクンっと唾液を飲み込む。
「……我妻善逸さん。俺の、お嫁さんになってください。お願いします」
「……はっ……はっ……ひゃいぃ……」
「善逸っ!?」
プシュンという音が聞こえた気がした。善逸は気を失ったように身体がぐにゃぐにゃになって、床に倒れていく。腰を支えていたけど、俺も腰を下ろしていたから体勢的に維持するのが難しい。善逸が頭を打たないようにと床になんとかそっと寝かせながら、俺は意識がなくなったのだろうかと慌てて善逸の顔を覗き込んだ。すると善逸は、床に寝そべってから一拍おいて、両手で顔を覆った。
「……嬉しい……俺も炭治郎好き……」
「えっ!」
「……炭治郎のお嫁さんになる……なりたいよぉ……」
「……うん……」
俺と善逸は、片方はキッチンの板間に腰を下ろして、片方は寝そべって、二人して沈黙する。ジーワジーワと蝉の声がどこかから聞こえてきている。まだ梅雨は開けきらないがもうすぐ夏がやって来るのだ。
俺たち二人の、長い人生における二回目の夏が……もうすぐ。
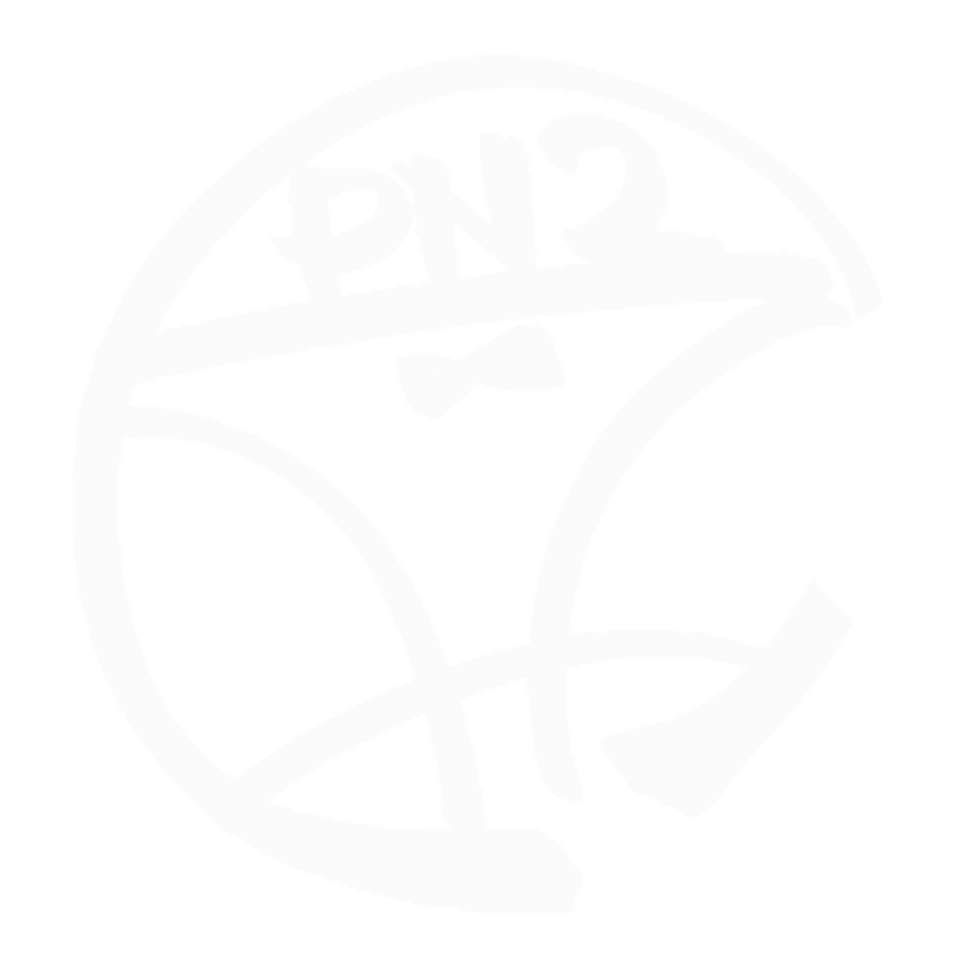



コメント