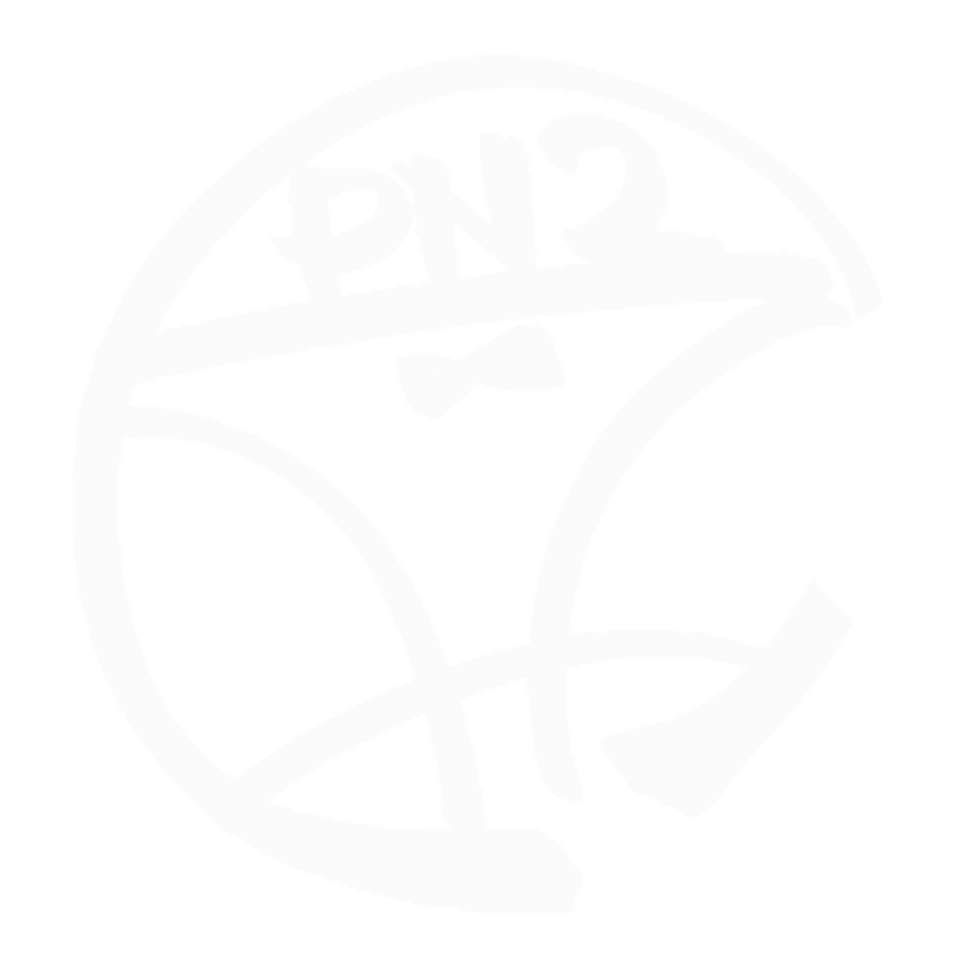現パロの炭善のちょっと不思議物語です。
虫苦手ならやめておいても良いと思います。
約20000字/現パロファンタジー?
気がついたら独りぼっちで寂しくて、しくしくしくしく泣いていた。なんとか明るいところに行かねばと這い出して、誰か俺と結婚してくださいと広いところで叫んだが、だーれも見向きもしてくれず、地べたに這いつくばるばかりだ。
高みを見上げれば、女の子達は這いつくばる俺なんて見向きもせず他の野郎たちのもとへと一目散。しょうがないよね。俺、女の子に上手く声をかけるのも下手だし、そもそも底辺をウロウロする奴だ。こんな奴に女の子が見向きするわけがない。
悲しい、悲しい、寂しい。誰でもいいから俺の愛を受け取ってよ! 同じ量なんて返してくれなくてもいいからさ!! なんて叫んでいたら、そっと頭を撫でられた。
「なんて場所でないてるんだ。踏まれてしまうぞ?」
その声は優しくて、俺を撫で触る手も優しくて、俺は思わず「みぃん!」と泣いた。いったい誰だと相手を見れば、これはまた顔のいい奴で。けれどそいつから聞こえてくる音は泣きたくなるくらい優しい音で。俺はさらに「みぃん!!」と縋るように泣いた。
「しっかりしろ。素敵なお嫁さんを見つけるんだろ?」
そう言って俺を叱咤し持ち上げてくれるそいつの笑顔は眩しくて、俺はそいつが子供なんて産めないのを承知で好きになった。俺の命を、存在を賭けてもいいって思うくらい、そいつを好きになってしまったんだ。
****
八月も下旬に入り、学校が主催する夏期講習がやってきた。炭治郎は残暑が厳しい中、堅苦しい襟付きシャツを着込み、夏仕様といってもさほど涼しくもないスラックスを履いて、革鞄を片手に歩いていた。最短距離を歩けば学校から家までは二十分だ。しかしその道はあまりに日陰がなく、仕方なしに少し遠まりして帰宅する。歩く時間が八分増えるだけで日陰ばかりの道を歩いて帰れるのだ。体感温度がまるで違った。
夏しか歩かないその道は細い川に沿うようになっていて、見事な街路樹が植わっているのだ。あまり車も通らない道なので排気ガスも少なく、より涼しく感じる。水場が近いおかげで蚊が多いのだけは難点だが、虫除けスプレーに頼れば大丈夫だ。あと学校を出る際に足裏をウエットシートで拭くだけでも蚊が寄ってくる確率が違う。
「暑いな……」
ミーンミンミンミン……とあっちこっちで蝉が鳴いている。もうすぐ夏も終わりになる頃だ。あとひと月もしたら完全にこの声を聞くことがなくなるんだろうなと炭治郎は四季の移り変わりを意識する。次女は蝉なんてうるさいし、怖いと騒ぐけれど、炭治郎は別に蝉が嫌いではない。普通に触れるし、幼い頃は網を片手に蝉を追いかけ回したものだ。
「……あの時は悪いことをしたなあ」
炭治郎は蝉が鳴いているのはお嫁さんを探しているからだと分かっていなかった。知っては居たが、自分が捕まえてしまうとその蝉はお嫁さんを見つけられず、一人で死んでいくというというのを理解していなかった。捕まえて七日後、虫かごの中でひっくり返って足を閉じている姿を見つけた時は涙が出た。こんなに早く死んでしまうなんてと泣いて、図鑑を読み返してまた泣いた。
蝉は何年も土の中で一人きりで過ごすのだ。そうしてようやく大人になって外に出て必死に鳴く。子孫を残すために、短い一生に意味を持たせるために命懸けで鳴くのだ。それを自分が邪魔をしてしまったと気がついた炭治郎は、次の夏から虫取り網を持つことはなかった。
夏がくるたび思い出す。ひっくり返って動かなくなった蝉。炭治郎は頭上のミンミン鳴く声に顔を上げ、そして今度は足元を見た。もうどこかに蝉の死体が転がっていてもおかしくない頃だ。炭治郎は苦い思い出があるにも関わらず、つい蝉の亡骸を探してしまう。
人がやって来ないのをいいことに、キョロキョロと地面を見渡しながら歩いていると、木と木の間にスニーカーが見えた。それにぎくりとして、なるべく不自然にならないよう炭治郎は身体を起こす。すると突如目の前に影が現れ、先程の人が自分の前に立ちはだかったのだと気がつく。
「えっ」
驚いた炭治郎が顔を上げると、そこに居たのは見事なまでの黄色い髪色をした少年だった。Tシャツにハーフパンツ姿の彼は今にも泣きだしそうな顔をしていて、炭治郎は息を呑む。随分と、切羽詰まった表情の人物に立ちはだかられたら、そりゃ驚いて息も呑むだろう。しかしそれにしても見事な金髪だと炭治郎が驚きつつも感心していると、少年はぐっと拳を握り、息を吸って、叫んだ。
「あ、の!! お、俺……お前のこと好きなんだ!! 結婚してくださいっ!!」
「……は?」
叫ばれた内容に、炭治郎はパチリと目を瞬き、後ろを振り返る。誰もいない。その事を確認してから少年に向き直ると、少年は真っ赤な顔で俯き、もじもじしていた。
炭治郎は少年の様子を観察して、先程の言葉を反芻して、なる程と頷く。とりあえず、告白されたらしい。ならば返事をしなければならない。炭治郎は息を吸うと先程の少年の声音に負けぬ程の声を出した。
「すまない!! 気持ちはありがたいが、知らない人に告白されてプロポーズされても応えられない!! 俺のことは諦めてほしい!」
自分達はどう見ても男同士だが、彼の恋愛対策が男であるなら男同士だから結婚できないと振るのは誠実ではない。炭治郎は男をいいなと思ったことはないが、それよりもまず、相手をまるで知らない方が問題だ。名前どころか顔すら見かけたことがない。こんな見事な金髪をした相手、すれ違うだけでも忘れないだろうに。
そう思って炭治郎がお応えできませんと断れば、少年はショックを受けた顔をして、蜂蜜色をした瞳にうるうると涙を溜めていく。そして炭治郎が、あっと思うよりも早く泣き出してしまった。
「なぁぁぁぁんだよ!! それぇぇぇ!! 期待させて落とすんじゃないよぉぉぉ!! お前! お前! 俺に優しくしたくせに俺のこと好きじゃないのかよぉぉぉ!!」
「うわっ!」
泣かせてしまったと罪悪感を抱く隙がないほと煩い。炭治郎は蝉の鳴き声かと思うくらい煩く泣く少年にびっくりして耳を塞いだ。今いるところは川沿いで家が並んでいるところから少し距離はあるが、それでも煩い。これは近所迷惑だと炭治郎は泣き喚く少年の手を引くと近くにあるベンチに連れて行く。
「あんまりだよぉぉぉ! お前なら俺を受け入れてくれるかと思ったからこうして勇気だしたのにぃぃぃ!!」
「落ち着け! ちょっと煩すぎるぞ! 泣くのをやめてくれ! 近所迷惑だ!」
「これが泣かずにいられるか!! こちとら一世一代の大博打に負けたんだぞ!? なんだよ知らないから諦めてくれって! そんな簡単に諦められないから頑張って勇気だしたのに!! 酷すぎるだろ!!」
「ああ……」
わんわんと泣く少年に、しまったと炭治郎は頭を掻く。炭治郎は経験がないが、告白は相当勇気がいるはずだ。さらにこの少年と自分は顔見知りですらない。向こうはこちらを知っているようだが、炭治郎はまるで知らないので……要するに知り合いではない。なのに告白してきたのは、確かに一世一代の大博打だろう。
ならまず、知り合いになって仲良くなってから告白すべきではと炭治郎は思ったが、学校でまるで知らない女子に告白された経験もあるため、いきなり告白するのもありなのだろう。
それに少年は自分と同じ学校でもない。こんな金髪なんて見かけたこともない。となると知り合いになることすら、難易度が高いから、彼がいきなり自分に告白してきたのはそこまで変なことではないのかもしれない。自分という存在を認識させるには確かに有効な手だ。
「やだよぉぉぉぉ! 俺と結婚してくれよぉぉぉ!! お前の前に立つために俺がとんだけ勇気出したと思ってんだ!! 責任取れっ!! 俺のこと知らないからダメって言うならもうちょっと知ってくれよ!! ちょっとの間でいいから俺に時間くれよ!! 俺が死ぬまででいいからぁ!!」
「もの凄く要求してくる……」
少年は空気を激しく震わせるような泣き声をあげていた。目から涙が溢れ、わんわんと泣くのは幼児のようだ。周りに響いていた蝉の声もかき消すほどのその声に、炭治郎は早く泣くのを止めねばと焦ってしまう。近所迷惑だからとベンチに連れてきたが、たぶん、何も変わっていない。
「分かった!! 分かったから!! 友達から始めよう!」
「……へっ?」
地べたに膝をつき、こちらの腰に縋り付いて泣く少年を引き剥がしながら、炭治郎はそう言った。少年は涙と一緒に鼻水が出ていて、炭治郎は溜息を吐くとちり紙を取り出し鼻を拭いてやる。ぶびんっと素直に鼻を拭かれる少年に末の弟のようだなと、つい笑ってしまう。
「知り合いでもないのに告白してくる君の勇気は凄い。尊敬するよ。確かに知らないから応えられないは君の勇気に見合ってないな」
炭治郎は今まで知らないからで断ってきた相手に申し訳なくなる。しかしそれは今更すぎるので、とりあえず今は自分の落ち度に気がつかせてくれた目の前の彼に誠意を見せる事を考えよう。
「……友達……」
「君の人となりを知ってから、返事をするよ。それじゃ駄目か?」
「……ううん。いいよ」
少年はずびっと鼻を啜ると立ち上がった。膝小僧が土に汚れているのを払いもしないのが気になり、炭治郎はパンパンと少年の膝の土汚れを払ってやる。少年は何も言わず、じっと炭治郎を見ていた。その目の熱量は恋なのかと思うと、炭治郎は途端に恥ずかしくなる。透き通るようにじーっと見つめられるのが照れる。こんな事をしてくる人は、今まで告白してきた中にいなかったのでどう対処すればいいのか分からない。
「……お前、やっぱり優しいのな」
そう言ってへへっと笑う少年に炭治郎は返事はできなかった。だから苦し紛れに己の名前を言う。
「……俺の名前は竈門炭治郎だ」
「ん? うん。たんじろう」
少し舌足らずに復唱した少年は無邪気に笑っていた。しかしニコニコと「たんじろう、たんじろう」と言うばかりで一向に名前を教えてくれない。その事にあれっと思いながら、炭治郎は頰を掻き、少し抜けているところがあるんだなと少年についての情報を増やした。
「あの、君の名前は……?」
「へっ? あ! あー………えーっと……ぜ、善逸?」
「善逸。苗字は?」
「ええと……我妻……」
善逸は一度、後方を振り返ってからそう言った。炭治郎は何を見ていたのかと思い、善逸が振り返った方を見ると、道路を挟んだ向こう側に『我妻』という表札が掲げられた家があった。そこの家の子だろうかと思い、善逸を見ると、善逸は炭治郎の手をぐいぐいと引いてくる。
「なあなあ、炭治郎。炭治郎はどこに住んでるの? 家に住んでるんだろ?」
「うん? 俺の家はこの道をずーっと歩くと見えてくる、商店街の中にあるぞ。家はパン屋をやっているんだ」
「ぱんや……」
どこかボンヤリとした話し方をする善逸に炭治郎は変わってる子だなと思った。もしかしたら同じ歳に見えるが、少し歳下なのかもしれない。綺麗な金髪な事だし、外国の血でも入っているのかと思ったところで、ブーっとスマートフォンが鳴った。画面を見ると、妹の名前が出ている。
「あ! しまった……早く帰るって言ってたんだった」
「なになに? 何が鳴ってるの?」
「ごめん善逸、今日はもう帰らなきゃ。俺の家族が待ってるんだ」
炭治郎がそう言うと、善逸はあっさりと手を離した。そして告白を断った時とは打って変わって聞き分けよく、手を振ってくる。
「あ、そうなの? じゃあまた明日な。俺、またここにいるからさ」
「うん、ごめん」
炭治郎は善逸を置いて歩き出し、通話ボタンを押す。すると妹の声がスピーカー越しに聞こえてくる。今どこにいるのかという問いかけに答えながら炭治郎が曲がり角辺りで振り返ると、金色の姿はもうどこにもなかった。
****
「あ、炭治郎! おはよー♡」
「……おはよう、善逸」
ジーワジーワと蝉が鳴く川辺の道に善逸はいた。今は登校時間だ。昨日、連絡先も交換しないまま別れたので、また出会えるのかという不安を炭治郎は少し抱えていたのだが、それは杞憂だったようだ。
炭治郎は、朝の登校時には最短距離の道を使っているけれど、今日はいつもより少し早く出て、帰る時に使う遠回りの道を選んだ。それは連絡先を交換しなかったのでもう善逸に会えないかもという不安からだったけれど、まさかこんな簡単に会えるとはと笑ってしまう。
「善逸、朝からここにいたのか?」
「うん? 俺はずっとここにいるよ?」
「暑いだろう……ちゃんと水分取ってるか?」
「大丈夫だけど? それより炭治郎、ちゃんと来てくれたんだな! 来てくれるって信じてたけど……来てくれなかったらどうしようとも思ってたからさ〜」
ニコニコ嬉しそうに話す善逸は昨日と変わらない出立ちだった。炭治郎は腕時計を確認すると、十分くらいは一緒にいられそうだと思い、善逸との立ち話に花を咲かせることにした。とはいえ、昨日の今日、出会った相手と何を話せばいいのか。どうしたものかと迷っていると、善逸が炭治郎に言った。
「なあなあ。炭治郎の家族について教えておくれよ!」
「……いいぞ!」
家族の話題なら炭治郎は大得意だ。炭治郎は自慢の家族の話を善逸に聞かせる事にした。炭治郎は家族自慢が好きだが、周りにいる友人はあんまり他所の家に興味がないらしくテキトーな返事しかない。しかし善逸は嬉しそうに、興味深そうに聞いてくれるので、話す炭治郎にも熱が入り、ついついたっぷりと語ってしまった。
「へえ〜炭治郎の家は皆んな、仲がいいんだなぁ」
「そうなんだ! うちは家族仲がって……はっ! いま何時だ!? ……もうこんな時間!?」
「え?」
炭治郎は腕時計を確認して、時間が随分と経っていることに驚いてしまった。どう考えても遅刻だ。炭治郎はあわあわとしながら善逸に「ごめん! もう行くな!!」と言って駆け出した。後ろから「たんじろお〜!?」と善逸の声が聞こえたが、振り返っている暇はない。いまさら走っても遅刻だが、炭治郎の性格上、走らないわけにもいかない。
その日結局、炭治郎は見事に遅刻をした。理由は新しくできた友達とお喋りしすぎたからという、反省文にも書きにくい理由でだ。
しかし炭治郎が学校に行っているのは授業ではなく、参加自由形の夏期講習だ。だから遅刻をしても叱られることはない。ただ、講習が受けられなくて勿体無いというだけ。
炭治郎は朝最初の英語を見事に逃し、二つ目の数学から教室に入った。朝から全力疾走したせいで汗だくになってしまった。パタパタとシャツを動かせば汗の匂いがする。放課後までに汗の匂いがなくならないだろうか、なんて考えながら制汗スプレーの購入を検討するのだった。
****
「あっ!! 炭治郎!! なんで朝にいなくなったんだよお前! 会えたと思ったらあっという間に行っちまうとか酷いだろ!? なんで俺をひとりにしたの!? 寂しかったよぉ!」
夏期講習が終わり、友達と別れて帰ってきた途中の道で、炭治郎は前方で声を上げている人物に気が付いた。いつ学校が終わるなんて話を炭治郎はしなかったのだが、もしや彼はずっとここに居たのだろうかと、どっと汗が出る。なにしろ木陰の向こうに見える太陽は今日もジリジリと照っているのだ。こんな中で、いくら多少は涼しい場所だとしても長時間いるのは良くない。あれからここにずっといたのだとしたら、四時間くらいは過ごしたことになる。
炭治郎は慌てて善逸に駆け寄り、そしてぎゃあぎゃあ文句を言っている善逸をベンチに座らせた。善逸は汗は出ておらず、逆に大丈夫か不安になる。ぴとりと頰に触れてみれば……意外にひんやりしていた。
「えっ。た、炭治郎どうしたの?」
「……熱中症ではなさそうだな。でもちょっと待っててくれ」
炭治郎はそう言って善逸の横に鞄を置くと、木陰から外に出て信号のない横断歩道を渡る。殆ど車が通らない場所だが、左右をしっかり見てから渡り、そこからすぐ先にある自販機の前に立った。
ズボンのポケットに入れている二つ折りの財布を取り出すと、千円札を入れてボタンを押す。そして出てきた小銭を拾い上げ、もう一度お金を入れると同じボタンを押した。
「……暑いな……」
自販機の周りは日陰がないからとても暑い。炭治郎は吹き出してくる汗を感じながら、ペットボトルを両手にそれぞれ持って走り出した。もちろん、横断歩道を渡るときは左右確認を忘れない。炭治郎は手の中にある冷えた存在に、ゴクンっと喉が鳴った。今すぐ飲みたい衝動が込み上げてくるが、視線の先にはこちらをじっと見返している瞳がある。
(座らせたのにまた立ってる)
善逸は眉毛を八の字にし、両手を前で握って体を小さくしている。まるで癇癪を起こした後にやり過ぎたことを後悔する子供のようだった。そんな姿は弟妹達でたくさん見慣れている炭治郎はふふっと笑いが込み上げてきてしまう。
「善逸、ほら」
炭治郎は暑い日照りの世界から、多少は涼しい木陰の世界に踏み込んだ。そして走ってきた勢いのまま、善逸にペットボトルを差し出す。
「えっ。なにこれ?」
「なにって……飲み物だ。暑いからな。俺の奢りだよ」
炭治郎が善逸に手渡したのは何の変哲もないスポーツ飲料だ。青色のラベルが貼られたそれは見慣れたもので、善逸も見たことくらいあるだろう。朝は慌てていて、何も言わずに善逸を置いていったような形になったのでお詫びの気持ちも込めて買ったのだ。けれど実際、木陰とはいえ暑いものは暑い。善逸がどれくらいここにいたのか分からないし、そしてこれから二人で話しをするとなると時間はあっという間に過ぎてしまう気がしたので、熱中症対策の意味も含めて買ったのだ。
「飲み物……へぇ! ありがとう!」
善逸は両手でペットボトルを持ち、冷たさを確認しているようだった。炭治郎は喉が渇いていたこともあり、自分の分を先に開く。ペットボトルを片手で持って、反対の手で蓋を回せばカチリと鳴った。
善逸は炭治郎が開けたのを見て、それから自分もと蓋を回していたが、一回目では開かなかった。力が足りなかったらしい。けれど二回目は肩肘を張るくらい力を入れたおかげか、簡単に開く。
「できた! ……うん、美味しい……ありがとう炭治郎」
心底嬉しそうに、ふんにゃりと笑う善逸に飲み物くらいで大袈裟だと炭治郎は思った。しかし何となく、頰が熱い。蕩けそうな善逸の笑顔を見たせいだ。こんな表情を家族以外から向けられたことがない。
(そうだ……善逸は俺が好きなんだった)
炭治郎は急にドキドキとしてきてしまった。善逸はどう見ても男であったが、同じ男である自分のことを好きらしい。結婚してくれとまで言っていた。炭治郎は今までの人生で、道端での出会い頭求婚をする人間を見たことがない。他人にしていたらドン引きどころではないし、場合によっては求婚されている側の救助に向かうところだが、自分がされてみると、そう悪い気もしなかった。
(いや……そんなことないか。最初は俺も困惑したし。罪悪感で友達から始めてみて……思ったより善逸が良い奴だったのが分かったから好印象になってきただけだ)
炭治郎はスポーツドリンクを三分の一ほど飲んで横を見た。善逸はちびちびとペットボトルを舐めていて、普通の男よりもピンクみが強い唇が湿っている。
男に好意を持たれることは初めてであったが、炭治郎とて性にそれなりに興味がある年頃だ。なんとなく唇に注目してしまう。好きだと、結婚してくれと言うくらいなのだから、善逸は自分に対して性的な欲求を持っているのかと考えてしまう。
(俺とキスしたいとか、セックスしたいとか、そう思う人って本当にいるのかな……?)
炭治郎とて親から生まれているのだ。人の営みの中で性の交わりが確かにあるのは知っている。精通も済ませているし、自分の手で慰めることもある。いつか誰かと結婚して、交わりを持ち、子供を作るのではと漠然と考えたこともある。しかし実際に自分に性的関心があるかもしれない相手が目の前にいる事実に、炭治郎は緊張していた。
小学校や中学校で、女子に告白されたことが片手で数える程度にはある。しかしそのどれにも性を感じた事はない。相手が少女であり、炭治郎もまた性についてはまだまだ先と無意識に思っていたからかもしれない。けれどいま隣にいる善逸は男だ。炭治郎と同じ年頃であれば、精通も済んでいるし、自慰もしたことがあるだろう。となればいままで炭治郎に告白してきた少女達よりも、善逸は性に関して近いところにいる。
炭治郎はごくんっと唾液を飲み込むと、考え込んでしまった。隣にいる相手は自分のことを性的に見ているかもしれない。炭治郎は好きな人がいないので、誰かを具体的に想像して自慰をしたことはないが、善逸はもしかしたら自分を想って慰めたことがあるのかもしれない。
(……思ったより、嫌悪感はないな)
誰か知らない相手に夢想されて自慰に使われるなんて身の毛がよだつが、善逸だと思うと嫌悪はなかった。むしろ、自分をオカズにした事があるのか確認したい気持ちの方が強い。
しかし確認して「あるよ」と言われてもその後どうすればいいか分からないし、「ない」と言われたら言われたで何となく傷つく。好きじゃないのかと言いたくなる気がして、炭治郎は聞けなかった。そもそも自慰の話をするにはまだ関係が浅すぎる。
「炭治郎、どうしたんだ?」
「わっ!」
炭治郎は顔を覗き込んでくる善逸にびっくりして仰け反った。何しろ距離がとても近かったからだ。鼻先が触れそうなほど覗き込まれれば、誰だってびっくりするだろう。炭治郎は善逸から香る甘酸っぱい匂いに真っ赤になって鼻と口を覆った。炭治郎は、人よりも鼻がいいのだ。善逸からはくらりと酩酊しそうな甘酸っぱい匂いがする。昔、キャンプに行った森で嗅いだクヌギを思い出すような匂いだ。雨上がりの森の、緑と樹液の匂い。
「……炭治郎の目は少し赤いんだなぁ! カブトムシの甲殻みたいだ!」
善逸はそう言って瞳を輝かせて、乗り出すようにして炭治郎の瞳を覗き込んでくる。炭治郎は善逸がなんの恥じらいもなく、自分の胸に手を置いて乗り出してくるのに困惑した。好きと言う相手に躊躇いもなく身を寄せてくる無邪気さに驚いてしまう。
(ち、近いっ!!)
炭治郎はジロジロと見てくる善逸の瞳の透明さに、なんだか恥ずかしくなってしまった。この反応は、もしかしたら善逸は自分に性的なことを感じたことはないのかもしれないと思った。善逸の『好き』は高校生男子の大半が抱える粘ついた性欲求とはかけ離れた清いものなのかもしれないと、ちょっとばかりガッカリする。
「…………へへへっ。炭治郎の目、凄い綺麗だなぁ。……ちょっと酸漿にも似てるね」
「かがち……?」
「鬼灯のことだよ」
そう言って善逸は微笑んだ。その微笑みはうっとりとしており、視線は炭治郎から外れない。炭治郎はその視線に身体中が熱くなった。善逸はやはり本当に自分のことを好きなのだと理解した。いままでの恋に恋するような、夢みがちな少女たちの眼差しとは違うナニカが善逸の瞳にはある。そしてそれは線香花火のように一瞬で燃え盛り、消え落ちるような儚さを炭治郎は何故か感じた。
「ぜ、善逸……ちょ、ちょっと近い……」
「え? ああ、ごめんよ。炭治郎の目が凄く綺麗だったからさあ」
炭治郎が距離の近さを指摘すると、善逸はあっさりと離れた。口説かれているのかと思ったが、このあっけらかんとした物言いから意図的な接近ではないことを炭治郎は知る。天然で距離を詰めてきたのかと思うと少し怖い。
炭治郎は赤くなったであろう頰の熱をとりたくて、スポーツドリンクをごくごくと飲んだ。あっという間に一本を飲みきり、パタパタと襟元を掴んで扇ぐ。川辺の木陰はいつも他より涼しいと思っていたのに、今日はとても熱い。風も吹いているのにおかしいなと炭治郎はハンカチを出して額の汗を拭った。
「炭治郎、これも飲む?」
「えっ、いや……それは善逸のだろう?」
「俺は暑いの結構得意だし、汗もかかないし平気だぜ?」
善逸はそう言ってホラと炭治郎にペットボトルを差し出してくる。しかし炭治郎はブンブンと首を振った。善逸に渡したそれはもう、善逸のものだし、先ほど口をつけてしまっている。いつもならば回し飲みなど躊躇いもしないが、善逸は炭治郎のことを好きだと言った。善逸との間接キスに嫌悪はない。ただ、なんとなく恥ずかしいのだ。
「いや、いい。もう一本買ってくるから! それは善逸が飲むんだ!」
炭治郎はそう言って日向に出ようとした。するとするりと手を掴まれて肩が跳ねる。振り向けば善逸が伺うように炭治郎を見ていた。
「俺も炭治郎と一緒に行きたい」
一緒に行くも何も、炭治郎が向かうのは目と鼻の先ほどの自販機だ。僅かな距離過ぎて一緒に行く意味はあるのかと思ってしまう。しかし繋がった手のひらに、僅かに力を込められるのに、善逸の願いに切実さが感じられて炭治郎はコクンと頷いた。
「いいよ」
炭治郎が善逸の願いを聞き届けると、善逸はそれは嬉しそうに顔を輝かせた。何がそんなに嬉しいのだろうか。炭治郎は善逸の喜びの中心に、自分への恋心があるのかと思うと、背筋がゾワゾワする。しかしそれは嫌悪ではなかった。
****
「あれ? 善逸?」
炭治郎は学校の帰り、いつものようにペットボトルを二本持って川辺の街路を訪れた。善逸がいつもいるケヤキの木の下に人影はなく、炭治郎はおやっと首を傾げた。炭治郎は善逸がスマートフォンを持っていないというので連絡をつける手段がない。しかしいつもここに居ると言っていたので、登校時間と下校時間に寄るようにしているのだが、今日は朝も今もその姿がないのだ。
「……家にいるのかな?」
炭治郎は道路を挟んだ向こうにある、『我妻』の表札を出している家を見た。大きな家だが、複雑な家庭環境がありそうだと炭治郎は勝手に思っている。何しろ善逸は学校に通っていないらしい。なぜかの理由は聞いてはいない。何かがあって不登校かもしれないと思ったからだ。そして善逸が夏の暑い最中に外にいることを考えると、家の中にも居場所がないのではないかと考えてしまう。
「……善逸……」
炭治郎は善逸の姿がないことに、寂しさと不安を覚えた。この感覚は物凄く久しぶりのものだ。炭治郎は小学生の時、友達と約束の仕方を失敗して出会えなかったことを思い出す。友達はキッズケータイを持っていたが、炭治郎は持っていなかった。待ち合わせはうまく行かず、その日は友達に出会うのに一時間掛かってしまったのだ。何度家に戻って友人の家に電話をしたことか。
しかし炭治郎は大きくなり、スマートフォンという力を手に入れた。友達との待ち合わせに失敗することはない。出会えなくても電話をかければすぐに会えるからだ。しかし善逸はそれができない。何しろ電話をかけることができないからだ。家の番号すら教えてもらえていない。
(……急に会えなくなるとか、あるのかな)
炭治郎はこの四日、善逸と日々を過ごしている。登校時の僅かな時間と下校してから一時間程度というくらいだが、炭治郎は刺激的な日々だと感じていた。善逸に向ける感情が恋とは思わないが、親しい友人だとは思っている。善逸は知りたがりで、自分のことより炭治郎の日々の話を聞きたがったが、会話の応酬は心地よく、沈黙が訪れても不快感がなかった。ただ、善逸が向けてくる視線の熱さにだけは緊張する。けれどその緊張感もまた、心地よいのだ。
(……善逸に会えなくなるのは嫌だな……)
友達から始めようと言ったが、本当に友達になって終わりはまずい。善逸は炭治郎のことを好きで結婚してくれと言ったのだ。炭治郎は善逸に対して答えを返さねばならない。けれど善逸の『好き』に応えられなければ、友達という関係すら失う。ならば応えねばいい……というわけにはいかない。善逸は炭治郎と友達になりたかったわけではないのだから。善逸が望んでいるのは、炭治郎ともっと踏み込んだ関係になることだ。
(そもそも善逸は俺のどこが良かったんだろう……)
善逸は「優しくしたくせに」と話していたが、炭治郎にその記憶はない。誰か他の人と勘違いしているのではと思ったが、疑って問いかけるのは、あの真剣な眼差しを向けてくれる善逸に失礼な気がしてできていない。だが本当に記憶がないのだ。炭治郎はもし本当に自分ではなく、別の相手と取り間違えていたらと思うと残念で仕方がない。善逸は勘違いに気がついたら、自分ではなく、その優しくしてくれたという相手を好きになるのかなと寂しくなってしまう。
(そんなことより、今は善逸に会えるかどうかだろう)
炭治郎はよしっと顔を上げると、善逸がいつもいる木のところに立つ。いつもは善逸が待ってくれているのだから、今日は自分が待つ番だと気合いを入れた。
ジーワジーワと蝉が鳴いている。こめかみから伝う汗がくすぐったく、ぐいっと手の甲で拭ったところで、ガサリと植え込みが揺れる音がして炭治郎は振り返った。
「ひぃぃぃぃん! たんじろぉぉぉ!」
音が聞こえた方向を振り返った瞬間、善逸が飛びついてきた。それにホッとしながらも、炭治郎はペットボトルで塞がった手では宥められないので肩にかけていた鞄になんとかペットボトルをねじ込んだ。
「どうしたんだ善逸? 随分とみっともない顔で泣いているな?」
「いや酷っ! もうちょっと言い方ってもんがあるんじゃない!?」
「毎回毎回、何かにつけて善逸は泣いてるじゃないか……。今回は何があったんだ?」
善逸が泣き喚いているのは、もう炭治郎の中でさほど珍しいことではなかったので、涙を指先で拭い、頭を撫でてやりながら起きた出来事について聞いてやる。すると善逸はぐしゃっと顔を情けなく歪めながら、自分の身に降りかかった不幸について教えてくれた。
「それがさあ! 俺、住処を追われちまったんだよぉ!」
「えっ!?」
善逸の言葉に炭治郎はギョッとした。そしてバッと振り向き、道路の向こうにある白い壁の『我妻』の表札が掛かった家を見る。いったい何をしたら家から追い出されるのか。あんな裕福そうな家なのに、随分と前時代的な叱り方をするのだろうか。
そんな事をぐるぐる考えながら、炭治郎は今度は空を見上げた。木々の合間から見える空は今日も快晴だ。ジーワジーワと蝉もうるさく鳴いていて、どうやら程近くにいるのだろう。何にしても暑い。こんな日照りの中に追い出されたなんて、叱るにしてもやり過ぎではないだろうか?
「いったい何があってそうなったんだ?」
「いったい何がもないよ! 寝てたら朝方になってぶん殴られて追い出されたの!」
「えっ!?」
「気に入ってた寝床なのに!!」
「え?」
「生まれてこの方、ずっとそこに住んでたのに!!」
「……?」
炭治郎は善逸の言い回しが変であることに頭を捻る。確かにあの家で生まれ育ったならばその通りであろうが、まるで住み着いていたというようかニュアンスだ。
「誰に殴られたんだ?」
親か、兄弟か、それとも……まさか親戚か。実は不幸なわけでもあって、親戚の家にでも預けられていて厄介者として扱われているのか。
そんな悲しく恐ろしい想像をした炭治郎であったが、善逸は泣きながら怒りの表情を見せ、ずびしっと指先を木の幹に向けた。そこには保護色で見えにくいが大きな蝉がとまっていて、ジジジジと鳴いている。
「……え?」
この台詞を僅かな間に何回口にしたであろうか。炭治郎は目を瞬き、蝉を睨みつけるように目を細めた。そして沈黙をし、善逸の頭を撫でる。もしや熱すぎて妄言を吐いているのだろうかと背筋が震えてしまう。善逸の頭が心配だ。
「あいつ! あいつ! あの蝉!! この辺で一番のモテ男!! もう三回も交尾してやがんのにまだ生きて鳴いてるの!! あいつのせいで一回も女の子と交尾できない奴がこの周りにはいるんだぜ!? 俺あいつ嫌い!! 今の俺には炭治郎がいるから、女の子達とられるのはいいんだけど……でも嫌い!! 昨日まではもっと遠くで鳴いてたのに、あいつ俺の住処の木にやって来やがったんだ!! それで俺に出て行けって……えぇーん! たんじろぉ! 俺、今日から別の木で眠らなきゃならないんだよぉ! この木は他の昆虫とかあんまり来ないから気に入ってたのにぃ!!」
「大変だ善逸。お前、熱中症になったのかもしれない」
炭治郎はゾッとして善逸の両頬に手のひらを当てる。すると善逸の顔色はみるみるうちに赤くなった。炭治郎はやはり熱中症だろうかと焦り、つい、善逸の顔をもっと近くで覗き込んでしまった。その次の瞬間——。
「んっ!」
「んぐっ!?」
ガチンッという音はしなかったが、唇同士が強くぶつかり、歯に押されて痛い。炭治郎は何が起きたと思うと、潤んで煌めく蜂蜜色の瞳と目が合う。そして口の中で僅かに鉄臭い匂いを感じて、唇同士が当たった勢いで歯がぶつかり、口内を切った事を理解する。つまりは、炭治郎と善逸はキスをしてしまったということだ。
「あ……わあ!!」
炭治郎は善逸をドンッと突き飛ばした。すると善逸は勢いのまま尻餅をつく。炭治郎が口元を押さえながら善逸を見れば、善逸は呆然としていた。しかし二回ほど瞬きをすると、眉毛を下げて、泣きそうな顔をし、俯く。
「……ごめんよぉ。人間は顔寄せたら唇を合わせる生き物だって思ってたから……」
独特な言い回しに炭治郎は困惑した。善逸はもしかしなくても頭がおかしいのかとほんの少し怖くなる。しかし善逸から香る匂いは甘くて、不快ではない。炭治郎は善逸がぐすんっと鼻を啜って「ごめんよぅ」と言うのに胸がなぜか苦しくなった。
「いや、その……驚いただけなんだ。怒ってないよ」
炭治郎は善逸を泣き止ませたくてそう言った。ファーストキスを勝手に奪われたことへの悲しみもショックも確かにない。怒りももちろんなかった。急だったことへの驚きと、そして善逸の突拍子もない行動への理解ができない恐怖はあるが。
「ほんとうに? ほんとうに怒ってない?」
「だ、大丈夫だ」
「…………」
善逸は尻餅をついた状態から、ゆっくりと立ち上がった。そして土汚れを払うこともなく、自分の手のひらを眺めた。炭治郎は善逸が手のひらを見ているのに、もしや倒れた時に擦ってしまったのかと心配になる。けれどさっきの今で近づくのは緊張する。分かっていたはずなのに分かっていなかった。善逸は自分が好きなのだと炭治郎は急に恥ずかしくなる。
(き、すをされた……)
炭治郎は初めてのキスが勝手に奪われたことはどうでもいい。そんな事よりも善逸はやはり自分にキスとかそういうことをしたいのだという確信を得てしまったほうが問題だった。ドキドキと心臓が鳴り、これからどうしたらいいのか分からなくなる。善逸と友達になったのに、キスをしてしまった。勿論、元から善逸から好意があるのは知っていた。しかし自分にキスをしてしまうくらいの想いがあるのは知らなかった。
(か、考えなきゃ……善逸への返事を……。キスしたら、友達じゃない……友達のままはおかしい……)
炭治郎はダラダラと汗をかく。善逸とまだ一緒にいたい。しかし友達のままでは駄目だ。それは自分に恋心を持つ善逸を苦しめるだけ。一緒にいるなら善逸の気持ちに応えなければならない。それが自分に本当にできるのだろうか。
「……あーあ……」
炭治郎は善逸の声にびくんと肩を震わせた。そして善逸を見ると、善逸は悲しそうに、しかしへらりと笑って両方の手のひらを振る。善逸の向こう側、木陰が終わった日照りの道路では空気が揺らめいていた。
「俺からしても駄目みたい。ちゃんと両想いじゃないと、お天道様は願いごと叶えてくれないんだね」
「……願いごと?」
炭治郎が聞き返すと、善逸はこくんと頷いた。そしてまるで諦めたような眼差しで炭治郎を見つめてくる。その表情の意味することは何なのかと炭治郎は今までで一番、ゾッとした。
「両想いでキスできたら、仮初じゃなくて、本物の人間にしてくれるってお天道様が約束してくれたんだ。でも、俺と炭治郎はやっぱり両想いじゃないんだね」
善逸がお天道様との約束なるものについて話してくれたら、大きく風が吹いた。木立が揺れて、もちろん葉も揺れて、隙間からお天道様の光が漏れる。その眩しさに炭治郎が目を細めた瞬間、「あーあ」と善逸の声がまたして、消えた。
声も姿もないことに驚いて目を見開いた炭治郎の視界の端には「ミィン」と鳴いて飛び立つ蝉がいた気がした。
****
「ただいまー……」
「おかえりお兄ちゃん。今日も遅かったね」
「うん……」
炭治郎が大量の汗を掻きながら家に帰り着いたのは十七時の頃だ。まだ外は明るいけれど、太陽の位置はだいぶ低くなっているし、空の青さも薄らいでいた。ここのところ、炭治郎は学校からの帰りが遅い。本来なら十四時には帰ってこれるのだが、色々あって十七時になってしまうのだ。
しかし、色々あってと表現したが、炭治郎の十四時から十七時の間に何かがあったわけではない。もっと広い括りで何かが既に起きたため、炭治郎は毎日、三時間ほどを川辺の道にある木陰で佇んでいるのだ。そこで炭治郎が出来ることは、待つこと以外は何もなかった。
(今日も善逸に会えなかった……)
炭治郎が善逸に会えなくなって、三日が経っていた。最初に出会った場所で毎日、登校時と下校時に善逸の姿を探し、待っているが、ジーワジーワと蝉の声ばかりするだけで、善逸の泣き声は聞こえてこない。炭治郎は姿形が見えなくなった善逸にゾッとした。本当に、会えなくなってしまったのかもしれない。
炭治郎は汗だくになった身体をシャワーで流すと、疲れた溜息を吐いた。毎日、暑い中、何時間も外にいるのだから疲れてしまう。けれどそれで善逸に会えるならば炭治郎は何時間だって待てる。出来るならば今だって外で、あの場所で善逸を待っていたい。けれど弟達の夏休みの宿題を見てやらねばならないので帰ってきているのだ。
「茂ー。算数のドリルで分からないところ……」
「あ! お兄ちゃん! これ、これ読んでみて!」
脱衣所から廊下を通り、リビングに入ろうとした炭治郎を出迎えたのは次女の花子であった。花子は『特別号』と書かれた分厚い少女漫画の雑誌を開いて押し付けてくる。炭治郎は何事かと思いながら受け取って、花子が見せてくるページを捲った。
「え? これがどうしたんだ? 景品でも当たったのか?」
「違うよ〜! この読切のお話が素敵だったの! 最後が悲しかったけど!!」
「悲しい話なのか……兄ちゃん、ハッピーエンドが好きなんだけどな……」
しかし家族の半笑いな様子を見るに、皆んな読ませられたらしい。いいと思ったものを共有した気持ちは分かる。炭治郎は受け取った『悲しい結末』の漫画を読んだ。最初は立って読んでいた炭治郎であったが、主人公らしき女の子が登場したところで、ダイニングチェアに移動して座る。
「…………」
「どうどう? 面白いでしょ? 主人公の女の子は、お日様の力を借りて人間になってる朝顔なんだよ?」
「……花子、ちょっと静かに読ませてくれ」
「はぁい」
自分を笑って撫でてくれた男の子に恋をした朝顔。太陽の力を借りて、ほんの数日を人間として生きる。恋が実れば本当の人間になれる『変化の魔法』を持つが、実らなければ女の子は『変化の魔法』で朝顔に戻るか、期限切れで消滅をするか……といったお話だ。炭治郎は人間になった朝顔に、つれない態度をとる男の子にハラハラしながら先を読み進めた。なぜなら花子のネタバレで『悲しい結末』らしいので。ようするに人魚姫をモチーフにした漫画らしい。
「………はぁ……」
「どうどう? 素敵なお話だったでしょ? 悲しいけど……胸がぎゅーってしたの!」
「……全然、素敵じゃない」
炭治郎は妹の同意を求める言葉を蹴ってしまった。花子は素敵な話を共有したかったのだろうが、炭治郎にはこの話は刺激が強すぎた。あまりにも身に覚えがありすぎて、ちょっと他人事とは思えなかったのだ。
そう、炭治郎にとっては他人事ではない。まさにいま、自分に降りかかっているかもしれないことだ。この漫画の少年のように、気がついたら失ってしまうかもしれない。しかしこの少年と違うところは、最後の最後で相手の正体に気がついたわけではないことだ。そして、炭治郎はもう一つ大事な情報を知っている。『両想いになれば人間になれる』ということを知っているのだ。
(……善逸っ……!!)
炭治郎は立ち上がると漫画雑誌を花子に返した。そしてキッチンで夕飯の支度をしている母に声を掛ける。
「母さん! 俺出かけてくる! 遅くなるかもしれないから、夕飯先に食べてて!!」
「炭治郎? どこに行くの?」
炭治郎はその問いには答えずに家を出た。急いでいたので虫除けスプレーも掛けていない。炭治郎はサンダルを履くと、鍵とスマホと財布だけを持って玄関扉を開ける。するとちょうど、父親が夕飯時で店から戻ってきた所であったようだ。鉢合わせたのに、炭治郎は急いでいるのにとたたらを踏む。
「炭治郎、こんな時間に出かけるのか?」
「う、ん。……行ってくる。好きな人に会ってくる!」
炭治郎はえいやという勢いでそう言い放ち、父親の横を通り過ぎた。早くしなければならない。善逸と会えなくなってもう三日が経っている。もしかして善逸の魔法はもう、なくなってしまったんだろうか。
(……もう一度、もう一度キスできたら、善逸は人間になれる……!)
炭治郎は自然とそう思い、自分が善逸に向ける気持ちに納得した。
善逸が好きだ。
最初に告白された時はびっくりして困ったけれど、いまは違う。善逸がいないと嫌なのだ。善逸とこのままもう会えないなんて考えたくもない。そして何より、善逸が元から人間でないとしても、会いたい、一緒にいたい、という炭治郎の気持ちが変わらないのが何よりもの証拠だった。炭治郎は善逸を好きになったのだ。
「はぁ……はぁ……」
それでも炭治郎は念のためと『我妻』と名札のかかったお宅のインターフォンを押した。ブーっと音がして、暫くすると音声が繋がる。スピーカーから聞こえてきたのは少し老齢な女性の声で、炭治郎は自分の名前と、そして『善逸』に会いにきたことを女性に伝えた。
結果としては炭治郎の想像通りであった。落胆もない。むしろまた一つ、善逸の言っていたことが真実である証明のように思えた。炭治郎は女性に「お宅を間違えたみたいです」と伝えてその場を去った。向かうのは道路を挟んだ先の川辺だ。もう日がだいぶ低くなり、夕陽が外を赤くしている。
「善逸! 善逸ー!!」
炭治郎はいつも二人で会っていた木の前に立ち、名前を呼んだ。しかし返事はない。ジーワジーワと蝉の鳴き声だけがしていて、振り返ってみれば大きな蝉が木の上の方に止まっていた。しかもその近くにもう一匹がいて……これは雌かもしれない。
「他の蝉に木から追い出されたって言っていたな……」
いつの間にか始まった蝉の交尾に、炭治郎は「これは善逸じゃない」とその場を離れる。なぜなら善逸は自分のことを好きだからだ。他の雌蝉に現を抜かすわけがない……筈だ。
炭治郎はキョロキョロと辺りを見渡し、川の向こうを見た。川向こうにも木がたくさん生えている。もしかしたらあちら側にいるのだろうかと、炭治郎はフェンス越えて川の方へ降りていった。川は浅いが、フェンスで区切られているところを越えるなんてとても悪いことをしている。しかし善逸がいる気がして、炭治郎は躊躇わずに進んだ。
「善逸ー! 善逸ー! どこにいるんだ! 頼むから出てきてくれ!」
炭治郎は足を濡らしながら川を上の方に進み、声を張り上げた。周りからは逃げたペットでも探しているように見えるだろうか。しかし探しているのはペットではない。好きな人だ。いや、好きな蝉だ。
「……善逸……」
炭治郎はだんだんと空が群青になるのに焦ってくる。このままでは視界が悪くて善逸を見つけられない。善逸が人として出てきてくれればいいが、もし今は蝉の姿であるというなら見つけるのは大変だ。蝉の姿は保護色気味で見えにくいから。
「……もう、変化の魔法を使って完全な蝉になったのだろうか……」
変化の魔法なんて漫画で読んだ設定だったが、炭治郎の中にじわじわと不安が這い上がってくる。漫画の少年のように、自分は大切な人を気づかぬまま失ったのか。炭治郎はぎゅうと拳を握る。爪が手のひらに食い込み、痛い。血が出たらパン作りの時に不衛生だと力を抜いた。もちろん、グローブつけてパンを捏ねてはいるが、衛生面には気をつけねば。
「善逸に、俺の作ったパンを食べて欲しかったのに……」
そう呟いて俯いた時、川辺にある少し大きめな石の上にひっくり返る蝉がいるのに炭治郎は気がついた。ふんわりと香ってくる、雨上がりの森の、緑と樹液の匂い。炭治郎はそれにハッとすると、這いつくばるようにして蝉に顔を近づけた。間違いなく、善逸の匂いだ。
「善逸っ……! そんな……! 嘘だろ!?」
善逸は石の上でひっくり返っていた。くたりと開かれた足は生命力を感じさせない。ミィンと鳴くことのないその姿は、あまりにも侘しい。炭治郎は濡れるのも気にせず、川の中に膝をついた。善逸が死んでしまっている。
「善逸……。俺は……間に合わなかったのか……?」
炭治郎は呆然としながら善逸に手を伸ばした。しかし触れたら壊れそうで、寸前で止めて、拳を握り込む。今度は爪で皮膚を傷めるなんてことは思い付かず、ぎゅうっときつく握りしめた。
「……好きだよ、善逸。善逸にもう二度と会えなくなるのかと思うと、胸が痛くて仕方がないんだ」
炭治郎は誰に言い聞かせるでもなく、そう呟いた。本当なら善逸に聞かせたかった。しかし自分の判断は遅く、間に合わなかったのでこの気持ちはもうどこにもいけない。炭治郎の中で沈んで、墓にまで持っていくものになってしまった。
「……俺は馬鹿だな……」
最初から善逸は好きだと伝えてくれていたのにと、炭治郎は己を笑った。炭治郎の中はもう、善逸でいっぱいだ。きっとこれから経験していく全てのことは『善逸と一緒に体験したかった』と思うことだろう。いつだって善逸を思い出す筈だ。
「善逸。馬鹿な俺を許して欲しい」
炭治郎はホロリと涙を流す。次々と溢れてくるものを手の甲で拭い、息を吐くとそっと善逸に手を伸ばした。本当なら、木々が生えている土に還してやった方がいいのだろう。しかし炭治郎は善逸を連れていくことに決めた。亡骸だけでも欲しかったのだ。
善逸の亡骸を土に還せば、他の虫に食べられる可能性がある。それなら自分の手で持ち帰り、鉢植えにでも入れてずっと人生の傍におこう。そして自分が死んだ時、その土を一緒に墓に入れるのだ。
炭治郎はずびっと鼻を啜ると両手でそっと、善逸を掬い上げた。その瞬間!!
「ジジジジジジジジジジッ!!」
「うわっ!」
急に動き出した蝉……ではなく善逸に炭治郎はびっくりして仰け反った。びっくりして放り投げた蝉……ではなく善逸は宙に舞い、炭治郎の眼前に落ちてくる。ビダンっと顔に当たった感触に、炭治郎は思わず目を閉じた。そしてそのままのし掛かってくる重さに耐えられず、炭治郎はひっくり返って、バジャーンと大きな水音を立てた。
「わあ! 炭治郎ー! 大丈夫かー!?」
聞こえてきた声に炭治郎はもがくように手を伸ばす。すると自分の手を握り、起こしてくれる体温があった。炭治郎は水を払う為に頭を振る。そして水を切って開いた視界に飛び込んできたのはこの三日、そしてこの先の人生でずっと見たい黄金色だ。
炭治郎はふふっと笑うと腕を伸ばして好きな蝉……ではなく、好きな人を抱きしめた。自分とほぼ同じ質量、そして沢山の力を入れても壊れない強さに炭治郎はふははと笑いが止まらない。
「せ、蝉ファイナル……」
「えっ? なに? せみふぁいなる?」
「なんでもない! 良かった善逸! 間に合って……本当に良かった!!」
「ん? う、うん……?」
「好きだぞ! 善逸!」
「う、うん! 俺も炭治郎が好きっ!」
炭治郎と善逸はお互いをぎゅうぎゅうと抱きしめあった。お天道様はもう帰るところで、辺りはほとんど暗がりだ。遠くの方で赤く光る程度。それでも、祝福は届いたのだ。お天道様との約束は守られた。炭治郎は絶対に離すまいとばかりに善逸の手を握り、考える。
(……蝉だと戸籍ないな……)
炭治郎は急に現実が見えてきてどうしようと思う。しかし目の前で嬉しそうに、ニコニコとしている善逸を前にしてしまえば、この先に待ち構えているだろう現実的な手続きの大変さなんて些末ごとだ。
(いや、俺は未成年だから手続きできないな……? わー!! 父さん、母さん、皆んな……ごめんっ!!)
炭治郎は絶対に巻き込まれる両親や弟妹に心の底から謝った。しかし善逸を手放すつもりは微塵もない。炭治郎は嬉しそうに抱きついてくる善逸を万感の思いで抱きしめ続けたのだった。